人事制度とは、人材を管理・マネジメントするための企業になくてはならない仕組みのひとつ。人事制度を整えれば、企業の成長・発展へつながるでしょう。人事制度とは改めて何か、そして人事制度の目的や種類、設計方法やポイントなどを詳しく解説します。
目次
1.人事制度とは?
人事制度とは、人材を管理・マネジメントするための仕組みのこと。人事異動や福利厚生、労務や人材育成などが含まれる点で、広義では「働き方に関する仕組み」ともいえるのです。
近年は「従業員の処遇を決定する仕組み」を人事制度と意味する場合が増えています。
2.人事制度を整える目的
人事制度を整える目的は、人的資源を最大限生かし、経営戦略を実現して企業の成長・発展を目指すためです。
人事制度の存在によって、報酬や昇進など、仕事での頑張りや結果が評価されます。そして従業員のモチベーションを維持する仕組みが構築されるのです。
また、人事制度は仕組み化されているため、組織の公平性を保つため機能します。よって人事制度が整備されておらず、公平性が保たれてないと従業員が不信感を抱き、思うようなパフォーマンスが発揮されなくなってしまうのです。
経営戦略を実現するためにも、従業員が最大限パフォーマンスを発揮できるようにしましょう。人事制度によって適切な人材マネジメントが行われると従業員のモチベーションも向上し、経営戦略の実現から企業の成長・発展まで期待できます。
3.人事制度の種類
人事制度は、「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の3本から構成されています。ここでは、人事制度の種類を詳しく解説します。
等級制度
「能力」「職務内容」「役職」によって定められた等級にもとづいて、社内での位置づけや報酬を決定する制度です。従業員の序列化ともいえ、下記のような区分で従業員を等級わけします。
- 1等級:取締役
- 2等級:部長
- 3等級:課長
- 4等級:社員(マネージャー)
- 5等級:社員(一般)
等級制度は、人事制度の中心となる制度です。等級を決める基準は企業の価値観や人材観が反映されるため、企業風土を形成する要素ともなります。代表的な等級制度として挙げられるのは「職能資格制度」「職務等級制度」「役割等級制度」などです。

等級制度とは?【3つの制度】メリデメ、作り方をわかりやすく
等級制度とは、従業員を能力や職務、役割によってランクわけする制度のこと。人事評価制度を構成する柱のひとつで、ベースとなるものでもあります。
等級制度について、その目的や各等級制度のメリット・デメリット...
職能資格制度
業務を遂行するにあたって必要となる能力(職務遂行能力)をベースに等級を決定する制度です。職務遂行能力にもとづいて、昇進・昇格・昇給・能力開発などを決定します。

職能資格制度とは? 職務等級制度との違い、メリットデメリット
職能資格制度など人事制度の導入や見直しには人事担当の余裕が必要不可欠!
カオナビで人事業務の負担を減らし、業務の余裕をつくりませんか?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアク...
職務等級制度
「職務記述書」を作成し、基準に対する結果を点数化して等級を決定する制度です。スペシャリストの育成に有効な制度であり、点数化するための明確な基準があるため明快な評価が行え、職務の変更で等級の昇格・降格が発生します。

職務等級制度とは?【職能資格制度・役割等級制度との違い】
組織の状態の見える化で、職務等級制度の構築・見直しをラクに。
人事評価システム「カオナビ」なら、時間がかかる人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてP...
役割等級制度
経営方針・戦略などと連動した「仕事の基本的役割」を調査し、「役割価値」を明確にしたうえで、従業員が目標とする「役割」と個人の「チャレンジ目標」を評価基準とします。近年導入が進んでいる制度です。

役割等級制度とは? 職能資格制度・職務等級制度との違い
組織の状態の見える化で、役割等級制度の構築・見直しをラクに。
人事評価システム「カオナビ」なら、時間がかかる人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてP...
評価制度
従業員を評価するための制度で、評価結果は役職や報酬に反映されます。また、評価結果をもとに人材育成の方向性を決めるのも可能です。
評価制度で明確にすべき点は、「何をどのように評価するか」「いつ評価するか」「誰が評価するか」の3点。どのような評価制度を導入するかは企業によってさまざまで、代表的な評価制度には「能力評価」「職務評価」「役割評価」「成果評価」があります。

人事評価制度とは? 目的や仕組み、種類や手法、導入手順を解説
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...
能力評価
職務遂行能力を評価します。評価基準には「能力」「成績」「情意」の3つがあり、うち能力に重点が置かれるのです。年齢や経験年数によって評価が上がりやすいため、年功序列運用になりがちな評価制度といえます。

能力評価とは? 項目と評価基準、目標・評価シートの書き方を解説
能力評価は人事評価項目の一つであり、職務遂行に必要なスキルや能力を評価する評価方法です。能力評価は定性的な評価項目であるため、導入する際はその性質や目的を理解し、適切な評価基準を設定して運用していくこ...
職務評価
「職務記述書」をベースに、従業員に与えられている職務内容や責任などに応じて相対的な価値を評価します。能力があっても、一定の職務についていないと等級や報酬に反映されません。

職務評価とは?【わかりやすく解説】手法、項目、職務等級制度
職務評価制度の構築や評価運用をラクにしませんか?
人事評価システム「カオナビ」で、時間がかかる人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウ...
役割評価
従業員の役割をもとに評価を行うもの。何を役割とするかは企業によってさまざまあり、一般的には役職ごとに求められる成果責任を役割とします。なかには、業績にどれくらい貢献したかを基準とする場合もあるのです。

役割評価とは?【わかりやすく解説】役割等級制度
役割評価とは社内の職務内容をベースにして、給料などの処遇を決定する人事評価制度です。社内における役割が大きくなればなるほど、給料も比例して高く設定されます。
1.役割評価とは?
役割評価とは社内の...
成果評価
成果主義にもとづく評価制度です。どの評価制度にも成果責任を問う基準はあり、これはなかでも成果の評価度合いが大きいです。
目標管理制度(MBO)にもとづいた目標管理シートを利用して成果評価を行い、その結果が昇給額や賞与額など報酬制度に反映します。
報酬制度
等級制度や評価制度にもとづいて給与や賞与を決定する制度のこと。一般的には等級ごとに報酬テーブルが設定されており、評価結果をふまえて等級ごとに決められた報酬の幅から具体的な給与や賞与が決まるのです。退職金や福利厚生も報酬制度の一部といえます。
下記は、報酬制度を構成する代表的な要素です。

報酬制度とは?【制度設計の進め方】事例、目的、種類
報酬制度とは、企業が従業員に支払う報酬のルール・仕組みです。報酬制度は単に従業員の働きに対する対価を支払うだけでなく、従業員のモチベーションアップや人材定着、人件費の最適化などさまざまな目的を持ちます...
基本給
ベースとなる基本の給料で残業代や賞与、退職金の計算ベースになります。年齢や勤続年数、能力や業績などによって基本給が決定するものの、昇給のルールは企業によってさまざまです。

基本給とは? 手取りとの違い、平均、ボーナスや残業代との関係
毎月の給与明細の印刷・封入作業をペーパーレス化でなくしませんか?
「ロウムメイト」で時間が掛かっていた給与明細発行業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスして...
賞与
毎月の給料とは別で支払われ、基本給や成績、企業の業績や個人の評価によって決まる報酬です。日本では一般的に夏と冬の年2回に支払われ、必須の報酬制度ではありません。しかし賞与によって従業員のモチベーションがアップしやすくなるのも事実です。

賞与(ボーナス)とは? 支給時期や平均、手取りの計算方法を解説
賞与(ボーナス)とは、毎月の給与とは別に、企業が従業員に対して支給する特別な報酬のこと。支給額や回数、支給時期などは企業の判断に委ねられているため、各社で賞与の条件が異なる場合があります。
この記事で...
手当
給料とは別に支払われる交通費や住宅手当、家族手当など。残業代や休日手当、退職金のように支払い義務がある手当から、福利厚生の一環として支払われる手当もあります。

手当とは? 主な種類一覧、課税・非課税対象をわかりやすく
初期費用無料! めんどうな紙の給与明細の発行がWEBでカンタンに。
「ロウムメイト」で時間が掛かっていた給与明細発行業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
退職金
退職によって支給される報酬です。退職金制度があるかは企業によって異なり、なくても違法にはなりません。近年、人材の流動化も進んでいる背景から、退職金制度を廃止する企業も増えています。

退職金とは? 高卒・大卒の相場、計算方法、税金
退職金は、従業員が企業を退職した際に支給される金銭で、退職後の生活基盤を支える原資として、労働者にとっては重要な意味を持ちます。近年、この退職金制度に改革の波が押し寄せているのです。
退職金とは何か...
4.人事制度の設計・構築方法
人事制度の設計・構築のステップについて見ていきましょう。各ステップから人事制度の設計・構築方法を詳しく解説します。
人事制度を設計・構築するうえでのベースとなる考え方となり、各仕組みとの整合性を測るための基準としても役立ちます。
アンケートによる従業員満足度調査や各部門へのヒアリング、他社の人事制度との比較から現状を分析します。この結果から、設計・構築する人事制度の方向性を決定していきます。
等級制度のポイントは、現状の人事制度に見られる課題の解消をメインに、経営理念や人事理念にもとづいて設計すること。たとえば、従業員がモチベーションを維持できていない課題が見られる場合、成長実感が得られるスキルに応じた等級制度へ変更します。
次に、設計した等級制度に対応する形で評価制度を設計する段階です。スキルに応じた等級制度を導入する場合は、能力評価を設定しましょう。そして、評価制度を適正に反映するための報酬制度を設定します。
等級ごとの報酬テーブルを設定し、等級内での上限・下限を決めます。あわせて、従業員が無理なく生活していける報酬が得られるかといった報酬の適正もチェックしましょう。
運用開始後も引き続きモニタリングし、従業員の反応や課題をチェックしてください。課題があれば改善を図りながら、制度の浸透に努めましょう。
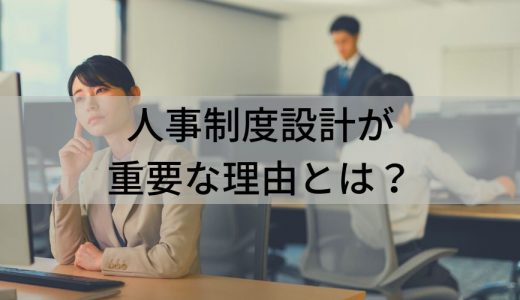
人事制度設計のやり方とは?【手順をわかりやすく解説】
人事制度は企業の成長を左右する重要な要素のひとつです。人事制度設計の重要性、人事制度設計を進める際の手順やポイント、オススメの参考書などを解説します。
1.人事制度設計が重要な理由
人事制度設計が重...
5.人事制度設計・構築のポイント
人事制度設計・構築のポイントを解説します。
- 独自性を失わない
- 従業員から理解と協力を得る
- 社会情勢も加味する
①独自性を失わない
人事制度は企業理念や経営方針を元に設計・構築すべきもの。他社のよい人事制度をそのまま導入しても成功しにくいです。自社の経営理念や課題をふまえて独自性のある人事制度を生み出しましょう。
②従業員から理解と協力を得る
人事制度を変更して大きく影響を受けるのは従業員であり、人事制度を狙いどおりに機能させるには従業員に制度を浸透させる必要があります。そのためにも、人事制度変更に至った背景や変更による影響をしっかりと説明しましょう。
また、人事制度の変更によって給与などに大きく影響が出る従業員がいる場合、猶予期間を設けて対処しましょう。従業員の不安を解消し、新たな人事制度に理解と協力が得られるよう体制を整えることが大切です。
③社会情勢も加味する
人事制度は経営理念にもとづいて設計・構築することが基本です。しかし社会情勢に合っているかも加味するとよいでしょう。たとえば、人材の流動化が進み、終身雇用制度が実質的に崩壊しているなか、年功序列型の人事制度は適しません。
また、そもそも経営理念や経営方針が時代に合っていない場合もあります。人事制度の変更を機に、経営理念や経営方針を見直すのもひとつの手です。
6.人事制度運用の課題と解決策
人事制度は時代の変化にも影響されやすく、運用するなかで企業ごとに課題も出てくるものです。ここでは、定量的に見られやすい人事制度運用の課題とその解決策を解説します。
- 多様化した働き方への対応
- 業務の個別化による評価難易度の上昇
- 成果主義型における人事制度の成熟
①多様化した働き方への対応
時代や社会環境の変化にともない、リモートワークやフレックスタイム、時短勤務やワーケーション、副業やダブルワークなど、働き方の多様化が進んでいます。
就業場所や就業スタイルが多様化してくると、人事制度の運用も複雑化するため、等級制度・評価制度・報酬制度も多様化する必要があります。
主な解決策は、多様な働き方に対応できていない現状の人事制度のポイントを洗い出し、見直し・改定を行うこと。多様な働き方の導入を進めていくと同時に、人事制度も並行して必要な見直しを図りましょう。
②業務の個別化による評価難易度の上昇
ジョブ型雇用が進み、従業員の業務と能力の個別化が進んでいます。そのため、誰がどの指標で評価すればよいかが不明瞭になりやすく、一律の評価基準では適切な評価が行えない状況になりつつあります。
主な解決策は、人事制度自体を個別化すること。業務や能力の個別化が進むと、評価者や指標によっては評価の公平性が失われかねません。個別化の度合いをふまえて人事制度も対応させていく必要があります。
③成果主義型における人事制度の成熟
成果主義型の人事制度を導入している企業も多くあるものの、徐々に成熟している状況にあります。その結果、成果主義型の問題点が顕著になり、個性が発揮されにくい、個人主義が強くなる、チームワークが低下するといった課題を抱える企業も少なくありません。
主な解決策は、成果主義型以外の人事制度を整えること。成果主義型の人事制度を導入している企業は、アンケートなどを活用して現状の課題を従業員からヒアリングしてみましょう。
成果主義型がモチベーションや生産性低下の原因になっている場合は、自社に合った新たな人事制度を設計・構築してみてください。
7.注目・トレンドの人事制度
働き方の多様化が人事制度の新たな課題として登場したように、人事制度は社会環境の変化に応じてトレンドも変わるものです。
ここでは、今押さえておくべき注目・トレンドの人事制度を紹介します。
1on1
部下の育成やモチベーション管理を目的に上司と部下が行う1対1の面談のこと。評価に関係する人事面談のような堅い形式の面談ではなく、相互理解を深めるカジュアルな面談です。上司と部下の信頼関係構築に貢献し、定着率アップや離職率の軽減に役立ちます。

1on1ミーティングとは? 目的や効果、やり方、話すことを簡単に
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入する...
OKR
「Objectives and Key Results(目標と主要な結果)」の略で、目標設定・管理方法のひとつです。従来の目標設定・管理手法に比べて、高い頻度で設定・追跡・再評価が行えるため、評価制度の効率化に有効です。
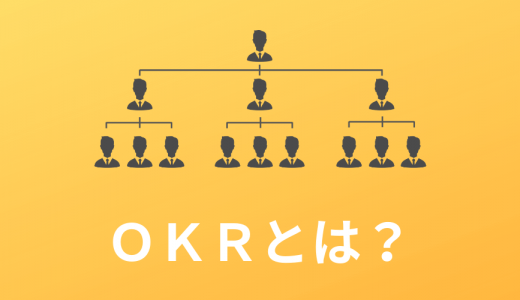
OKRとは? 【Googleが使う目標管理ツール】KPI・MBOとの違い
Excel、紙の目標設定・評価シートを豊富なテンプレートでクラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で、時間が掛かっていたOKR・MBOの問題を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonav...
360度評価
上司だけでなく、同僚や部下など複数の評価者から評価する方法です。多面的に評価することから360度評価といいます。
上司だけでは、評価対象である部下の行動をすべて把握できず、そのままの状態で評価すると評価の質が低下する恐れもあります。多面的な評価なら評価の客観性と納得感が向上し、より適切な評価が行えるでしょう。

360度評価とは? 目的やメリット・デメリットをわかりやすく
360度評価テンプレートで、Excelや紙の評価シートを楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp に...
コンピテンシー評価
コンピテンシーとは、ハイパフォーマーに共通して見られる行動特性のこと。これを評価基準にする評価方法が、コンピテンシー評価です。
評価の公平性や効率的な人材育成に有効であり、ハイパフォーマーの行動特性を浸透させると、期待する行動を促せる効果が期待できます。評価基準も明確になり、納得感が得られやすい点もメリットです。
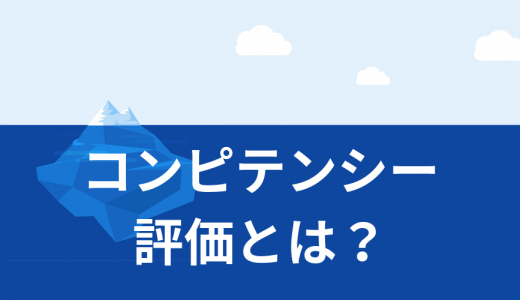
コンピテンシー評価とは? 項目例、メリット、導入手順を簡単に
コンピテンシー評価には、ハイパフォーマーの共通点の見える化が必須。
人事評価システム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...
ジョブ型雇用
職務内容を明確にしたうえで、職務を遂行するに適したスキルや経験を持つ人材を採用する手法です。近年、大手企業でもジョブ型雇用が進んでいます。人事制度に含まれる職務等級制度や職能評価は、ジョブ型雇用に準拠している制度です。
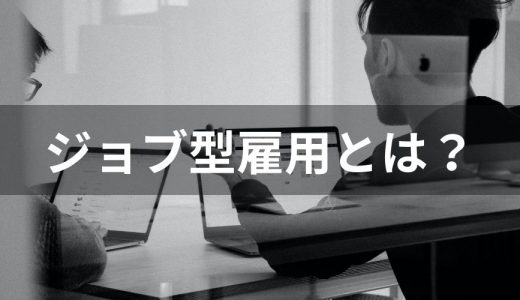
ジョブ型雇用とは?【メンバーシップ型との違い】メリデメ
ジョブ型雇用とは、従事する職務を限定し、成果によって報酬を決める雇用制度。
スペシャリストを確保したい企業を中心に導入が進められています。
1.ジョブ型雇用とは?
ジョブ型雇用とは、職務内容を明文化し...
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる


