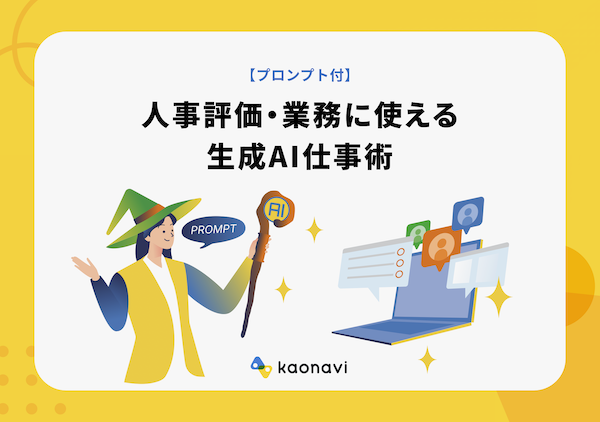部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
360度フィードバックとは、対象者の行動が「周囲にどのように伝わっているのか」を整理し、フィードバックする仕組みのこと。ここでは360度フィードバックの特徴や注目される背景について説明します。
目次
悩む時間を減らす実務プロンプト集
1.360度フィードバックとは?
360度フィードバックとは、対象者の行動が「周囲にどのように伝わっているのか」「周囲はどのように受け取っているのか」を整理し、フィードバックする仕組みのことです。社員の納得感を高められるため、採用して独自評価制度を展開する企業が増加しています。

360度評価とは? 目的や導入効果、メリット、運用方法をわかりやすく解説
タレントマネジメントシステムなら評価業務を効率化!
導入効果や、具体的な導入手順、システムの選び方を解説
⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
360度評価の工程を半...
本人へのフィードバックが大きな目的
ここで留意したいのは、360度フィードバックは本人へのフィードバックが大きな目的であり、社員のスキルやパフォーマンスを評価し、給与や昇格に反映させるものではないという点です。

フィードバックとは? 意味・使い方・効果と具体的なやり方をわかりやすく解説
部下のモチベーションを上げ、目標を達成させるための「フィードバック」とは?
スキルや個人の特徴を踏まえながら管理できる「カオナビ」がおすすめ!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp...
360度フィードバックで行う内容
360度フィードバックでは、優れたパフォーマンスを出している社員の行動特性をもとに診断を実施します。まず上司や同僚に対してアンケート調査を行い、対象社員のパフォーマンスの強みや弱み、改善点などを診断。
ここではポジションに相応しい行動を実践できているかなどの具体的な観点から、チェックします。最後にそれらの調査をもとにした面談を行うのです。
1対多の評価である
360度フィードバックは上司と対象社員という「1対1」の関係ではなく、「1対多」の関係のなかで評価を行います。これには上司のみならず、部下や同僚、ほかチームメンバーなども含まれているのです。
こうした多彩な立場からの社員が評価するため、「1対1」よりも多種多様な観点からの評価となり、それがフィードバックにもつながるのです。
1対1の評価で懸念されるデメリット
「1対1」の評価では上司のスキルによって部下の評価が左右される可能性もあるため、公平性が保たれにくいという一面があるのです。また「1対1」ではお互いの信頼性や関係性がカギになります。
つまり対象社員と相性の良くない上司がフォローしても、対象社員の行動が改善される見込みは薄く、やる気の低下を招いてしまう可能性も高いのです。
リモートワークと相性が良い
従来の日本企業では、上司に指示された仕事を部下数人が行うというケースも多かったため、上司自身は依頼した仕事をどの社員が手がけたか認識できない、という状況が目立ちました。
しかしリモートワークでは、上司が部下一人ひとりへ明確に指示できるため、社員の能力を把握しやすくなります。そのため「360度フィードバック」はリモートワークと相性が良いと考えられているのです。
多くの国内外企業で導入済み
日本では大企業を中心に360度フィードバックが導入されており、ここ数年では横ばい傾向にあります。
一方、米国では、日本企業よりもはるかに「360度フィードバック」の採用が進んでいるのです。アメリカのビジネス誌の発表によると、売上規模全米上位1000社における導入率は9割を超えるとされています。
課長や部長を対象にしている企業も多い
日本では、360度フィードバックを課長や部長を対象に実施している企業が多いといわれているのです。
ポジションの高い管理職などは、周囲の社員から正直な評価やフィードバックがされにくい傾向にあります。しかし360度フィードバックを採用すると、多面的なフィードバックを得られ、行動改善を狙えるのです。

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.360度フィードバックの導入目的とは?
人材育成を目的に360度フィードバックを導入する企業も増加しています。経営層や管理職は部下すべての仕事ぶりを細かく把握するのは難しいもの。
そこで第三者からの意見を汲み取ると、上司には見えていなかった部下の行動が明瞭化され、社員のスキルアップを目指せるのです。
公平な評価の実施
上司のみが部下を評価する場合では、部下との相性といった主観的な部分が影響しやすくなります。その結果、部下が上司に好かれようとして意見を言えなくなり、その風潮が浸透して、閉塞感のある職場になる可能性も高いです。
360度フィードバックでは上司だけでなくさまざまな立場の社員が評価します。そのためより公平な評価が可能になると考えられるのです。
社員のモチベーションアップ
これまで日本企業で行われてきた従来の人事評価では、公平性に欠けているという一面がありました。しかし360度フィードバックを導入すると、人事評価の公平性が保たれやすく、社員にとっても納得されやすいというメリットが生まれます。
人事評価の信頼性が高まるため、社員のモチベーションがアップし、離職防止にもつながるのです。

3.360度フィードバックの導入背景とは?
360度フィードバックの導入背景には「コスト削減のため管理職人員を整理」「社内コミュニケーションのクラウド化」などがあります。
さらに上司と部下といった「縦のつながり」や、同僚や部下、ほかチームとの「横のつながり」を深めるという目的もあるのです。
働き方や人材育成の変化
360度フィードバックを、人手不足解消に向けたひとつの手段として導入する企業が増えたといえます。
どの企業でも、人材育成に費やせるリソースは限られているもの。社員は自分自身を見返してスキルや問題を把握し、レベルアップしていくことが求められるときに、社員間で評価が行える360度フィードバックはとても効果的なのです。

4.360度フィードバックのメリットとは?
360度フィードバックのメリットとは何でしょうか。下記3点から解説します。
- 評価の客観性が高まる
- 評価結果に納得しやすい
- 改善につなげやすい
①評価の客観性が高まる
従来の人事評価制度では、「評価者と被評価者の関係性やコミュニケーションの度合い」が、評価に深く影響するという一面がありました。
しかし360度フィードバックでは、上司だけでなく同僚や部下などからフィードバックを得られるので、さまざまな視点から評価できます。それにより客観性や妥当性が向上するのです。
②評価結果に納得しやすい
組織の規模や形態にかかわらず、人事評価には公平さが求められるもの。しかし評価する上司と評価される部下の関係性などが、多かれ少なかれ評価に影響を及ぼすと考えられます。
360度評価フィードバックでは直属の上司だけでなく、同僚や部下も評価を行うため、客観的や妥当性が向上し、人事評価への納得感も高まるのです。
③改善につなげやすい
社員のモチベーションややる気には、上司や同僚、部下からの評価やフィードバックが大きくかかわるといえます。
360度フィードバックでは一方向からだけの評価ではなく、さまざまな立場の社員から評価されるのです。それにより対象社員は自分自身を客観視するとともに、新たな気付きを得られます。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
5.360度フィードバックのデメリットとは?
一方で、360度フィードバックにはデメリットもあると考えられます。ここでは代表的である下記2点について解説しましょう。
- 主観や馴れ合いが入る場合も
- 運用までにかかる時間と手間が多い
①主観や馴れ合いが入る場合も
360度フィードバックの基準は、そのほとんどが主観によるものといっても過言ではありません。相性が悪い社員同士ですと、本来のスキルやパフォーマンスに関係なく評価を落とす可能性もありますし、またその逆もありえます。
つまり評価者の視点がバラバラになると整合性が取りづらく、正しい人事評価ができなくなる可能性も高いのです。「評価者と被評価者の関係性が影響しない体制づくり」も重要でしょう。
②運用までにかかる時間と手間が多い
360度フィードバックは複数の評価者が行うため、「設問項目の準備」「回答結果の分析」「本人へのフィードバック」など多くの工程や作業が必要となります。
なかでも「対象社員をどの社員が評価するのか」というプロセスに多くの時間と手間が費やされるでしょう。それゆえ社員数が多い大手企業では、より多くのコストが発生するといえます。

360度評価の失敗理由とは? 失敗例と原因、防ぎ方を簡単に
社員の納得度を高める評価手法の一つとして注目を集める360度評価。多くの社員を巻き込むからこそ、失敗したくありませんよね。本記事では360度評価の失敗例とそこから学べる「成功のポイント」をご紹介します...

6.360度フィードバックを実施するときの注意点とは?
360度フィードバックを実施する際、何に注意したらよいのでしょうか。それぞれの注意点に留意して取り組むと、評価の客観性や公平性も向上します。ここでは注意すべき4点について説明します。
- 評価の対象範囲は全社員とする
- 評価内容は、主に執務態度
- 評価得点は平均と分散状況を参考にする
- 必ずフィードバックする
①評価の対象範囲は全社員とする
評価の公平性という視点から、360度フィードバックは可能な限り社員全員に実施しましょう。特定の社員のみに対して360度フィードバックを実施すると、不公平感が生じやすいです。
また一般社員だけでなく管理職や経営層などを含む社内全員がかかわると、それぞれのモチベーションが高まり、企業改革も期待できます。
②評価内容は、主に執務態度
360度フィードバックにおける質問項目は大きく分類すると「成果」「発揮能力」「執務態度」です。評価内容は、このうち「執務態度」を中心に構成するとよいでしょう。
一般社員であれば主体性や業務遂行力、周囲との協調性などが、マネジメント層であればリーダーシップや組織構成力、メンバー育成力などが当てはまります。
③評価得点は平均と分散状況を参考にする
360度評価の評価得点を計算する際は評価の合計を集計し、その平均値を評価対象者の評価得点にしましょう。さまざまなポジションの社員から集めた評価得点を見ると、人によってかなり差が出てくるためです。
公平な評価ができるように、最高値や最低値ではなく平均化した数値を評価点にするとよいでしょう。
④必ずフィードバックする
360度フィードバックで最も重要となのが対象社員へのフィードバック。「評価だけでフィードバックはしない」これでは評価者が「無駄に時間と手間がかかった」と思ってしまいます。
またフィードバックの際は主観を組み込まず、事実のみを報告しましょう。その際、課題を解決する方法などアドバイスもともに示します。

7.360度フィードバックの運用方法と項目とは?
360度フィードバックを実施する際は、運用方法や評価項目についても注意が必要です。多くの社員に納得してもらうためにも、事前の制度設計と正しい運用に注意しましょう。
運用方法
まず導入の目的を設計し、活用用途をイメージしながら評価基準やフィードバックの内容、運用フローを組み立てていきます。次に導入目的をもとに評価基準を設計し、評価項目の選定を行うのです。
活用目的によっては、360度フィードバックの実施時期や実施方法、回答期間など運用プロセスを細かく設計する必要も生じます。
マネージャーや管理職の評価項目
ポジションや職位によって求められる役割が異なるため、360度フィードバックの実施においては、一般社員とマネージャー職それぞれに異なる設問項目を設定します。
マネージャーや管理職は、「リーダーシップ」「組織構成力」「部下育成力」などのマネジメントスキルを判断する評価項目にするとよいでしょう。
一般的な社員の評価項目
一般社員の評価項目では、執務態度や業務に求められるスキルが中心になります。「主体性」「コミュニケーション力」「判断力」「課題解決力」「業務遂行力」「周囲との協調性」などです。
業務の結果やその効果が評価の対象ではあるものの、結果だけでなくプロセスについても重視しましょう。

8.360度フィードバックで評価基準を設定する際のポイントとは?
360度フィードバックの評価基準の設計を誤ってしまうと、せっかくの評価が成り立たなくなる可能性もあり得ます。ここで挙げるポイントを押さえて、有効性の高い評価制度を導入しましょう。
目的に応じてカテゴリーやウェイトを決める
評価基準を設定する際は、活用目的をもとに評価項目のカテゴリーを構成し、設問数の配分を決めていきます。社員の業務成果のみを重視するのではなく、結果までのプロセスも組み込んで設定するとよいでしょう。
成果ばかりに比重を置き、プロセスを評価しなければ社員のモチベーションの低下を招く可能性が高いからです。

9.360度フィードバックの導入事例
最後に360度フィードバックを導入し、人事評価業務の効率化を実現した「愛知日産自動車」と「バンドー化学」の事例を紹介します。導入を検討する際、参考にしてみてはいかがでしょう。
愛知日産自動車
愛知日産自動車は社員の成長やキャリア形成を目的に「カオナビ」を導入。従来では1週間費やしていた評価の収集や資料作成の業務が3日に短縮できたそうです。
ITに不慣れな社員でも、かんたんに使いこなせるインターフェースが魅力的と担当者は話します。さらに「カオナビ」の導入により、現場でのマネジメントのあり方を見直すきっかけにもなったようです。
バンドー化学
産業用ベルト製造を展開するバンドー化学はそれまで、紙とエクセルで評価をしていたため、工数の多さが課題になっていました。
しかし「カオナビ」の導入によって評価業務の工数は大幅に削減。何と年間100時間以上の業務量を削減できたのです。「SMART REVIEW」の活用によって、一次評価、二次評価で評価者が記載したコメントなどがすべて可視化された点も好評となっています。

【事例5選】360度評価(多面評価)導入企業の成功・失敗例
360度評価の導入を考えているけれど、どのような運用をしていいか分からないなどお困りではありませんか? このページでは360度評価をうまく活用できている企業の事例を集めて紹介していきます。
日本を代表...

評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など