「カオナビ」なら人事評価に必要な機能が揃っています。
人的資本の情報開示やリスキリングの効率化にも対応!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
製造業における人事評価制度の構築は、現場の特性を理解した評価基準設計と適切なシステムの導入により実現できます。
この記事では、製造現場に適した人事評価制度の重要性やメリット、人事評価の種類と人事評価システムの導入事例まで具体的に解説します。
実践することで、従業員一人ひとりが正当な評価を実感し、モチベーション向上と人材定着を実現できるでしょう。
目次
製造業における人事評価の重要性と期待できるメリット

まずは、製造業において人事評価がいかに重要であり、どのような良い変化が期待できるのかについて、わかりやすく解説します。
人事評価は、従業員のやる気を引き出し、企業の成長を支える大切な仕組みです。
適切に運用することで、以下のような多くのメリットが生まれます。
- 従業員の意欲向上
- 人材の定着と育成
- 生産性の向上
- QCD改善
それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
従業員の意欲向上
製造業における人事評価制度は、従業員一人ひとりの働く意欲を高めるうえで重要な役割を果たします。
評価基準が明確かつ公正に運用されることで、従業員は自分自身の頑張りがきちんと認められ、報われると感じられます。
たとえば、日々の業務改善や目標達成への貢献が、以下のように具体的な形で評価として現れると、従業員の満足度は大きく向上するでしょう。
- 昇給
- 賞与
- 昇進
納得感のある人事評価は、従業員の内発的な動機付けを促し、職場全体の活力を高める効果が期待できます。
人材の定着と育成
適切に設計された人事評価制度は、製造業における貴重な人材の定着を促し、従業員の能力を計画的に育成するための基盤となります。
評価を通じて、各従業員の持つ、以下の点が具体的に明らかになるため、企業は一人ひとりに合った育成計画を立てやすくなります。
- スキル
- 知識
- 今後の成長課題
特定の技能を持つ従業員に対しては、より高度な専門性を磨くための研修機会を提供したり、多能工を目指す従業員には、複数の工程を経験できるようなローテーションを計画したりできるでしょう。
人事評価を育成と結びつけることで、従業員は自らの成長を実感し、企業への貢献意欲も自然と高まります。
生産性の向上
製造業において人事評価制度を戦略的に活用することは、工場全体の生産性を高めるうえで大きな効果を発揮します。
評価項目に生産性に関連する具体的な目標を組み込むことで、従業員は日々の業務においてこれらの数値を意識するようになります。
目標が明確になることで、作業の効率化や無駄の削減に向けた自発的な工夫や改善提案も生まれやすくなるでしょう。
適切な評価は、従業員のスキルアップを促し、結果として組織全体の生産性底上げに貢献します。
QCD改善
製造業の競争力を支えるうえで重要な要素のひとつがQCDです。QCDとは、日本語で以下を意味します。
- 品質(Quality)
- コスト(Cost)
- 納期(Delivery)
人事評価制度をこのQCD改善と結びつけることで、組織全体のパフォーマンス向上を効果的に推進できます。

QCDとは?【優先順位・改善方法をわかりやすく】生産管理
QCDとは、「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「納期(Delivery)」の頭文字を取った言葉です。優先順位の決め方、改善方法などについて解説します。
1.QCDとは?
QCDとは、品...
たとえば、評価項目の中に以下のような具体的な指標を設けます。
- 製品の品質基準達成度
- 不良品削減への貢献度
- 製造コスト削減目標への達成度
- 納期遵守率
これにより、従業員は日々の業務において、単に製品を作るだけではなく、良い品質を低コストで、納期を守ってお客様に届けることの重要性を常に意識するようになるでしょう。
以下の記事では、中小企業の人事評価について解説していますので、ぜひチェックしてください。

中小企業が人事評価システム導入すべき理由とメリットとは?
中小企業にも人事評価システムを導入すべきなのでしょうか。人事評価システムの特徴や導入の注意点とともに、見ていきましょう。
1.中小企業が人事評価システムを導入すべき理由
中小企業における人事評価シス...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
●1on1の進め方がわかる
●部下と何を話せばいいのかわかる
●質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見られる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
製造業の人事評価が難しい3つの背景

製造業において人事評価制度の構築や運用がなぜ難しいといわれる主な背景について紹介します。
製造業特有の課題を理解することは、効果的な人事評価制度を設計するための第一歩です。
主に以下の3つの背景が挙げられます。
- 現場作業の貢献度が見えにくい
- 評価基準設定が難しい
- 評価への納得感を得にくい
それぞれの背景についてまとめていきますので、ぜひ参考にしてください。
現場作業の貢献度が見えにくい
製造業における人事評価の難しさのひとつに、日々の現場作業における個々の従業員の貢献度が、目に見える形や数値で捉えにくいという点があります。
製造ラインではチーム一丸となって製品を完成させるため、一人ひとりの働きぶりを明確に切り分けるのは容易ではありません。
機械の操作や部品の組み立てといったルーティン業務の中にも、以下のような行動が含まれています。
- 担当者による細やかな改善活動
- 複数の工程をこなせる多能工としての高いスキル
- 周囲のメンバーへの的確なサポート
しかし、これらの貢献は、日報の数字だけではなかなか表面化しづらいのが実情です。
「見えにくい貢献」をいかに公平に評価し、従業員のモチベーションにつなげていくかが、製造業の人事評価における重要な課題となっています。
評価基準設定が難しい
製造業の人事評価において、すべての従業員にとって公平で納得感のある評価基準の設定は難しい課題です。
製造現場には多種多様な職種があり、それぞれに求められるスキルや成果の尺度が大きく異なるためです。
具体的には、以下の点で評価すべきポイントが変わってきます。
- 精密な機械加工を担当する技術者
- 製品の品質を最終チェックする検査員
- 生産ライン全体の効率を管理する監督者
生産量や不良率といった定量的な目標は設定しやすいものの、定性的な側面を適切に評価できません。
さらに、企業によってそれぞれの現場の実情に合わせた評価基準の設計が求められるため、一律の基準を適用することが難しいという側面もあります。
こうした複雑さが、製造業における評価基準設定の難易度を高めているのです。

製造業(工場、生産管理など)のKPI例【設定方法】
業種や職種ごとに効果的なKPIは異なります。製造業で業務の効率化や改善を図り、目標達成を目指すには、どのような指標が適切なのでしょうか。製造業におけるKPIの意味や必要性、製造業でよく使われるKPIの...
評価への納得感を得にくい
製造業の人事評価制度が従業員のモチベーション向上や人材定着につながるためには、評価結果に対する納得感が不可欠です。
評価基準が曖昧であったり、評価プロセスが不透明であったりすると、従業員は「なぜ自分がこのような評価を受けたのか」と疑問を抱きやすく、不公平感を覚えてしまうことがあります。
たとえば、悪い評価を受けてしまった場合、評価者である上司の主観や印象によって評価が左右されているのではないかと考えてしまうこともあるでしょう。
こうした背景から、評価への納得感が醸成されにくく、結果として従業員の不満やエンゲージメントの低下を招いてしまうケースが見られます。
以下の記事では、人事評価に納得できない理由を解説していますので、ぜひご覧ください。
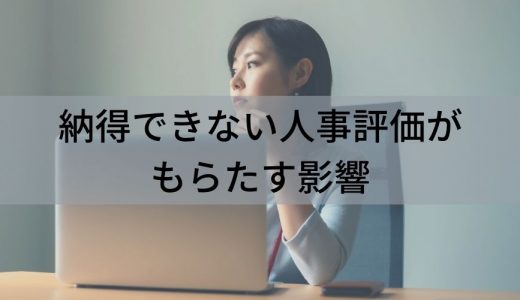
人事評価が納得できない理由と対策【わかりやすく解説】
納得できない人事評価は、従業員のモチベーション低下や離職率の増加などさまざまなリスクをもたらします。納得できない人事評価の要素や、納得感を高めるポイントについて解説しましょう。
1.人事評価に納得で...
人事評価は人事、上司、部下すべての関係者にとって負担がかかります。
「カオナビ」でシステム化し、煩雑な紙やExcelでの運用から脱却しませんか?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
製造業で使える人事評価制度の種類

製造業の現場で実際に活用できる代表的な人事評価制度の種類について紹介します。
人事評価制度には主に以下のものがあります。
- 目標管理制度(MBO)
- 能力評価
- 360度評価
それぞれの人事評価制度について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
目標管理制度(MBO)
目標管理制度(MBO)とは、従業員一人ひとりが所属する組織の方針に基づいて個別の目標を設定し、その達成度合いを評価する仕組みです。
製造業では、従業員が自ら目標設定に関わることで、主体的に業務に取り組む意欲が引き出されます。
たとえば、「不良品率を1年以内に2%以下に抑える」といった具体的な目標は、達成度が客観的に判断しやすく、評価への納得感も高まります。
上司は、部下が挑戦的かつ達成可能な目標を設定できるよう支援し、定期的な進捗確認や丁寧なフィードバックを通じて、目標達成を後押しする役割を担います。
以下の記事では、目標管理制度について詳しく解説していますので、目標管理制度の導入を考えている方は、ぜひご覧ください。

目標管理制度(MBO)とは? 意味や目的、メリット・デメリット、導入方法を簡単に解説
面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決
クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
能力評価
能力評価とは、従業員が持っているスキルや知識、業務を遂行する上での行動特性を評価する制度です。
製造業においては、製品の品質や生産効率を左右する専門技術や、多岐にわたる工程に対応できる多能工の育成が重要となります。
たとえば、特定の製造機械の操作スキルレベルや品質改善提案能力といった項目を設定し、その習熟度を評価します。
この評価結果を昇進や昇給だけでなく、個別の教育研修プランやキャリア開発支援に結びつけることで、従業員は自身の成長を実感しやすくなり、モチベーション向上にもつながるでしょう。
公平な評価のためには、評価基準を明確にし、評価者による判断のばらつきを抑えるための研修も大切です。
以下の記事では、能力評価について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

能力評価とは? 項目と評価基準、目標・評価シートの書き方を解説
能力評価は人事評価項目の一つであり、職務遂行に必要なスキルや能力を評価する評価方法です。能力評価は定性的な評価項目であるため、導入する際はその性質や目的を理解し、適切な評価基準を設定して運用していくこ...
360度評価
360度評価は、従来の上司による評価だけでなく、同僚や部下、場合によっては他部署の関連スタッフなど、複数の立場の人から評価を受ける手法です。
製造業の現場では、チームワークや部門間の連携が生産性や品質に大きく影響するため、上司だけでは見えにくい、以下の側面を多角的に把握するのに有効です。
- 協調性
- コミュニケーション能力
- リーダーシップ
360度評価を通じて、本人が自身の強みや改善点に気づき、自己成長につなげることが期待されます。
たとえば、管理職が部下から「指示が明確で頼りになる」という評価もあれば、「時には意見を聞いてほしい」といったフィードバックを受けることで、自身のマネジメントスタイルを見直すきっかけになります。
ただし、導入の目的を明確にし、評価結果をどのように活用するかを事前にしっかりと周知することが重要です。
とくに、人事評価に直接反映させる場合は、評価者への研修や匿名性の確保など、慎重な運用が求められます。
以下の記事では、360度評価について詳しく解説しています。360度評価について理解を深めたい方は、ぜひご覧ください。

360度評価とは? 目的や導入効果、メリット、運用方法をわかりやすく解説
タレントマネジメントシステムなら評価業務を効率化!
導入効果や、具体的な導入手順、システムの選び方を解説
⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
360度評価の工程を半...
人事評価の業務に時間がかかっていませんか?
タレントマネジメントシステムを活用すれば、大幅に効率化できます!
⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
製造業の人事評価を成功させる4つのコツ
製造業において人事評価制度を成功に導き、従業員の成長と企業の発展を両立させるための具体的な4つの秘訣について紹介します。
人事評価の成功には、主に以下の取り組みが重要となります。
- 評価制度の目的を明確にする
- 評価者への教育を徹底する
- 社員への丁寧な周知と説明をおこなう
- 定期的な制度の見直しと改善をおこなう
それぞれ解説していきますので、参考にしてください。
評価制度の目的を明確にする
製造業で人事評価制度を効果的に運用するには、制度が「何のために存在するのか」という目的を明確に定めることです。
目的が曖昧なままでは、一貫した評価制度が難しくなります。
たとえば、単に「社員の頑張りを評価するため」といった抽象的な目的では、評価基準も具体性を欠き、社員の納得を得にくくなるでしょう。
製造現場の実情を踏まえ、以下のような自社が抱える課題や目指す姿を具体的に反映した目的を設定することが求められます。
- 技術力の向上
- 生産性の改善
- 品質意識の徹底
- 若手人材の育成と定着
明確化された目的は、評価制度の設計思想となり、評価基準や評価方法を選ぶ際の軸となります。
評価者への教育を徹底する
人事評価制度の公平性と納得性を担保し、本来の目的を達成するためには、評価者に対する教育の徹底が不可欠です。
評価者が制度の趣旨や評価基準を十分に理解し、適切な評価スキルを習得していなければ、どんな制度も正しく機能しません。
とくに、製造業においては、専門的な技術や多様な職務内容が存在するため、評価者による評価のばらつきや主観、偏見が入り込むリスクがあります。
評価者自身が自信を持って評価に臨めるよう、企業として十分な教育機会を提供し続ける姿勢が、制度への信頼感を高め、従業員の成長支援という本来の目的達成につながります。
社員への丁寧な周知と説明をおこなう
新しい人事評価制度を導入したり、既存の制度を改定したりする際には、内容や変更点について、全社員に対して丁寧な周知と説明を尽くすことが極めて重要です。
社員が制度の目的や評価基準を正しく理解していなければ、新制度に対する不安や不信感を抱きやすくなります。
とくに製造業の現場では、日々の業務に追われる中で新しい情報が浸透しにくいケースも考えられるため、一方的な通知だけでなく、双方向のコミュニケーションを意識した説明機会を設けましょう。
社員一人ひとりが「自分は公正に評価される」「この制度は自分の成長につながる」と実感できるよう、理解と納得を促す努力が求められます。
定期的な制度の見直しと改善をおこなう
製造業の人事評価を成功させるには、定期的な制度の見直しと改善が必須です。
人事評価制度は、一度導入すれば完成というものではありません。
以下のようなさまざまな状況にともない、最適な評価のあり方も変わってきます。
- 企業の成長段階
- 事業戦略の変化
- 市場環境の変動
- 従業員の意識や構成の変化
制度の形骸化を防ぎ、常に実効性の高いものとして機能させるためには、導入後も定期的にその内容を見直し、継続的に改善していく取り組みが不可欠です。
具体的には、社員や評価者を対象としたアンケート調査やヒアリングを定期的に実施し、現行制度に対する満足度、課題と感じる点、改善要望などを収集します。
調査によってわかった生の声を真摯に受け止め、分析し、制度改定の具体的な案へとつなげていきましょう。
人事評価のデータを踏まえて、タレントマネジメントできていますか?
タレントマネジメントの基礎的な知識や、やり方を解説!
⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
製造業の人事評価は人事評価システムの利用がおすすめ

製造業特有の課題に対応し、従業員の成長と企業の発展を両立させるためには、適切な評価の仕組みが不可欠です。
人事評価システムは、制度の構築と運用をサポートします。
- Excel管理の限界とシステム化による評価業務の劇的な効率化
- DX連携とデータ活用で実現する客観的で公平な評価基準
- 多能工化や現場の声を反映した人材育成とモチベーション向上
上記について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
Excel管理の限界とシステム化による評価業務の劇的な効率化
製造業の多くで人事評価に利用されてきたExcelですが、従業員数が増えるにつれて管理が複雑になるという課題があります。
具体的には、以下の一連の業務に多くの時間と手間がかかります。
- 評価シートの配布や回収
- 評価結果の集計
- フィードバック資料の作成
手作業によるデータ入力は、入力ミスや計算間違い、ファイルの破損や紛失といったリスクもともないやすいです。
上記の作業は、人事担当者や管理職の大きな負担となり、本来注力すべき業務にかける時間を圧迫してしまうこともあるでしょう。
人事評価システムを導入することで、これらの定型的な評価業務を自動化し、大幅に効率化できます。
DX連携とデータ活用で実現する客観的で公平な評価基準
製造業における人事評価では、現場の成果をいかに客観的かつ公平に評価するかが重要な課題となります。
以下のような製造現場特有の指標は、従業員の努力や貢献を測る上で欠かせません。
- 生産量
- 不良率や手直し率などの品質データ
- 設備の稼働率
しかし、これらのデータを手作業で収集し、評価に正確に反映させるのは容易ではありませんでした。
リアルタイムのデータを人事評価システムに自動で連携させることで、具体的な数値に基づいた客観的な評価が可能になります。
評価基準の曖昧さが排除され、従業員は自身の頑張りが公正に評価されていると納得感を得やすくなります。
多能工化や現場の声を反映した人材育成とモチベーション向上
製造現場で必要な、ひとりの従業員が複数の異なる工程や機械操作に対応できる多能工の育成にも人事評価システムは有効です。
システム内のスキルマップ機能を活用し、各従業員が保有するスキルや習熟度、資格情報などを一元的に可視化します。
企業は計画的なスキルアップ研修を実施しやすくなり、従業員自身も次に目指すべきスキルが明確になります。
新たなスキルを習得したり、対応可能な業務範囲を拡大したりしたことを評価項目に設定し、昇給や昇格に反映させることで、従業員の学習意欲とモチベーションを高められるでしょう。
評価システム「カオナビ」を使って評価工数を削減しましょう。
カオナビの導入効果や機能一覧について、以下の資料で解説しています。
⇒ カオナビの資料を見てみたい
製造業で人事評価システムを導入する3つのメリット
現代の製造現場では、適切な人事評価が従業員のモチベーション維持や生産性向上に不可欠です。
人事評価システムは、これらの課題解決を支援する有効な手段となります。
具体的には、主に以下のメリットが期待できます。
- 評価業務を効率化できる
- 公平性と透明性の向上が狙える
- データ活用で最適な人材配置をおこなえる
それぞれ解説していきますので、導入時の参考にしてください。
また、以下では、人事評価システムについて紹介していますので、ぜひチェックしてください。

人事評価システム13選! 機能とメリット、比較ポイントを解説
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...
評価業務を効率化できる
製造業において人事評価システムを導入する大きなメリットのひとつは、評価にかかる業務を大幅に効率化できる点です。
従来、多くの企業では評価シートの作成から集計までの作業に、多くの時間と手間を要していました。
人事評価システムを導入すると、それぞれのプロセスが自動化され、一元的に管理できるようになります。
評価シートの電子化により、配布や回収がオンラインで完結し、入力されたデータは自動で集計されるため、手作業によるミスを防ぎ、作業時間を大幅に短縮できます。
公平性と透明性の向上が狙える
人事評価システムの導入は、製造業における評価の公平性と透明性を高めるうえで有効な取り組みです。
製造現場では、評価基準が曖昧であったり、評価者の主観が入りやすかったりすることで、従業員が不公平感を抱き、従業員のモチベーション低下や離職につながる可能性があります。
人事評価システムを活用することで、企業は全社共通の明確な評価基準や評価項目をシステム上に設定し、すべての評価者と被評価者に共有できます。
評価プロセスもシステム上で記録・管理されるため、評価の経緯が可視化され、評価の客観性を高めることが期待できます。
結果として、企業と従業員との信頼関係が醸成され、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。
データ活用で最適な人材配置をおこなえる
人事評価システムを導入する3つ目の大きなメリットは、収集・蓄積された従業員データを活用して、より客観的で戦略的な人材配置や育成を実現できる点です。
人事評価システムは、以下のような人材データを一元的に管理するデータベースとしての役割を果たします。
- 個々の従業員のスキル情報
- 保有資格
- 研修履歴
- 過去の評価結果
- キャリア志向
データを分析することで、「特定のスキルを持つ人材がどの部署に何人いるのか」「将来的に不足しそうなスキルは何か」「誰をどのポジションに配置すれば能力を最大限に発揮できるか」といった戦略的な検討が可能になります。
個々の従業員に適した育成計画を立案したり、プロジェクトの要求スキルに合致したメンバーを迅速に選抜したりと、データに基づいた最適な人材活用が期待できるのです。
MBO、OKR、コンピテンシー評価、360度評価のすべてに対応。
人事評価を効率化するなら、人事評価システム「カオナビ」です!
資料の無料ダウンロードは⇒ こちらから
製造業にあう人事評価システムの選び方

システム選定は、企業の成長を左右する大切なプロセスです。
人事評価システムの選定には主に以下の5つの確認事項があります。
- 自社の目的に合っているか
- 使いやすいか
- コストパフォーマンスは良いか
- セキュリティ対策はされているか
- サポートはあるか
自社の目的に合っているか
自社の目的達成に貢献する機能を備えたシステムを選びましょう。
目的が曖昧なままシステムを導入してしまうと、多額の投資をしたにも関わらず、現場のニーズと合わなかったり、一部の機能しか活用されなかったりする事態に陥りかねません。
結果として、期待した効果が得られず、従業員の不満が増加し、評価制度自体が機能しなくなる恐れもあります。
システム導入を成功させるためには、経営・人事・現場の代表者が集まり、何を実現したいのかを徹底的に話し合い、具体的な目標と必要な機能要件を明確に定義することが不可欠です。
目的を確認することで、システム選定の軸が定まり、自社に本当に合ったツールを見つけ出せます。
使いやすいか
人事評価システムは、人事担当者や一部の管理職だけでなく、工場で働くすべての従業員が日常的に利用するため、ITスキルに自信がない方でも直感的に操作できることが重要となります。
操作が複雑であったり、画面が見づらかったりするシステムは、従業員の利用意欲を削ぎ、入力ミスを誘発したり、問い合わせが増加したりする原因となります。
とくに、日々の業務に追われる製造現場においては、システムの使いにくさが評価業務の負担をさらに増大させ、制度の形骸化を招くことにもつながりかねません。
導入前には必ず無料トライアルやデモンストレーションを利用し、自社の運用に合っているかを確認することが、失敗しないシステム選びの鍵となります。
コストパフォーマンスは良いか
人事評価システムの導入には、初期費用や月額利用料といった直接的なコストが発生しますが、費用だけではなく、導入によって得られる効果を総合的に考慮し、コストパフォーマンスを判断することが重要です。
たとえば、以下のような観点からコストと効果を比較検討できます。
| コストの側面 | 考慮すべき点 |
|---|---|
| 初期導入費用 |
|
| 月額・年額利用料 |
|
| オプション費用 |
|
| 運用・保守費用 |
|
安価なシステムでも、必要な機能が足りなければ目的を達成できず、逆に高機能でも使いこなせない機能が多ければ無駄な投資となってしまいます。
自社の従業員規模や予算、そしてシステム導入によって得たい具体的な成果を明確にし、長期的な視点で費用対効果を見極めることが、賢明なシステム選定につながります。
セキュリティ対策はされているか
人事評価システムで取り扱う情報機密性の高い個人情報を含むため、システムを選定する際には、漏洩や不正アクセスから守るためセキュリティ対策が講じられているかどうかの確認が必須です。
万が一、情報漏洩が発生してしまえば、従業員からの信頼を著しく損なうだけでなく、企業の社会的信用の失墜やブランドイメージの低下、法的責任を問われる事態にも発展しかねません。
クラウド型システムの場合は、データセンターの物理的セキュリティや運用体制も重要な確認項目です。
サポートはあるか
人事評価システムの導入と運用をスムーズに進め、その効果を最大限に引き出すためには、提供ベンダーによる質の高いサポート体制が不可欠です。
システム導入時には、初期設定の支援や既存データの移行サポート、操作方法に関する研修などが提供されるかを確認しましょう。
また、運用開始後には、日常的な操作に関する疑問やトラブルが発生した際に、迅速かつ的確に対応してくれる窓口があるか、その対応時間や手段も重要です。
契約前には、サポートの具体的な範囲や内容を確認し、自社の運用体制やITスキルレベルに合ったサポート体制が整っているシステムを選びましょう。
以下の記事では、人事評価システムの選び方について解説しています。人事評価システムの導入を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
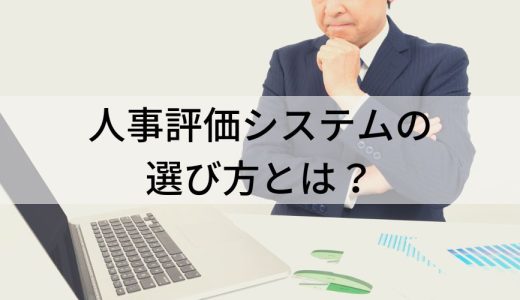
人事評価システムの選び方と10の選定ポイント
人事評価システムを選ぶ際は、自社の課題や導入の目的を明確にする必要があります。ここではシステム選びの重要性や事前準備、具体的な選び方などについて解説します。
1.なぜ人事評価システムの選び方が重要な...
人事評価を踏まえてタレントマネジメントできていますか?
タレントマネジメントの基礎知識や、具体的なやり方を解説!
⇒タレントマネジメント解説資料【3セット】を無料ダウンロードする
製造業の人事評価システム導入事例
製造業でカオナビを導入し、業務効率化をおこなった事例をご紹介します。
- 四国化成工業株式会社
- 株式会社湖池屋
- エスエスケイフーズ株式会社
それぞれ解説いたしますので、ぜひ参考にしてください。
四国化成工業株式会社
香川県の老舗化学メーカー四国化成工業が、紙ベースの人事管理から脱却するためにカオナビを導入し、業務効率化と戦略的人事を実現した成功事例を紹介します。
同社がカオナビ導入に至った背景には、深刻な業務効率の問題がありました。社員の緊急連絡先が紙の原簿に保管されており、緊急時にすぐ確認できない状況でした。
また、A3紙の手書き評価シートを全国拠点に郵送する非効率な評価運用が続いており、社員データの更新も5〜10年間隔と非常に遅いペースでした。
導入後の活用では、まず、評価運用において紙の評価シートをそのまま再現することで、スムーズなデジタル化を実現しました。
人材データベース機能では、全社員情報を一元化した「母艦」として活用し、配置検討や現状把握に役立てています。
また、アンケート機能はお弁当注文から新規事業企画まで幅広く活用されており、組織図機能では人事異動のシミュレーションを効率化しています。
カオナビの導入により、同社では作業的業務から解放され、企画・戦略業務に集中できるようになりました。
経営層も自分でシステムを確認するようになり問い合わせが削減され、全社でのアンケート活用により情報収集・意見集約が効率化されています。
出典:四国化成工業株式会社|導入事例|カオナビ【シェアNo.1】社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステム
株式会社湖池屋
総合スナックメーカーの湖池屋が、紙ベースの人事評価運用からの脱却を目指してカオナビを導入し、評価フローの可視化と組織文化の改革を実現した成功事例です。
同社がカオナビ導入に至った背景には、長年続いていた非効率な人事評価運用がありました。紙ベースの運用では各部門で評価フローが異なり、進行状況の把握ができない状況でした。
工場部門では従来Excelで管理していたスキルマップをカオナビに移管し、多能工化の推進や育成計画に活用しています。
さらに、コロナ禍で希薄になった社内コミュニケーションの改善策として、若手社員と先輩社員による1on1面談をカオナビで管理し、形骸化することなく継続的な実施を実現しました。
アンケート機能や組織図機能、性格診断なども幅広く活用し、評価運用を超えた組織活性化ツールとして定着しています。
上記の取り組みにより、目標設定から振り返りまでの文化が全社に定着し、定性的な目標も含めて意識するようになったことで組織が活発化しました。
また、評価データの一括ダウンロードによる大幅な効率化や、セキュリティ管理の改善なども実現しています。
出典:フローの可視化で人事評価も1on1も“実のある”ものに。湖池屋の人事制度改革
エスエスケイフーズ株式会社
最後に、静岡県の食品メーカーエスエスケイフーズが、カオナビを導入し、人事業務の劇的な効率化と新制度の浸透を実現した成功事例をご紹介します。
従来の評価制度は導入時から大きく変わらないまま会社が成長を続けてきたため、抜本的な見直しが必要となっていました。全国10拠点での紙・Excel運用による管理の煩雑さや、自社独自での情報集約システムへのニーズも顕在化していました。
導入後の活用では、基本的な人事情報から雇用契約書、面談記録まで、登録可能なデータを可能な限り一元管理することで、社内外からの問い合わせ対応業務の大幅な効率化を実現しました。
帳票機能を活用した保存義務帳簿の作成や、社員からの情報収集プロセスの簡素化も図られています。
評価運用においては、スマートレビュー機能により面談シートの作成から配布、回収、蓄積まで一元管理を実現し、効率化だけでなく、新評価制度の浸透促進という副次的効果も生まれています。
特に、人事のみ閲覧可能な質問項目を設置することで、社員からの率直な意見収集や深刻な悩み事の早期発見にも活用されています。
出典:評価制度改定を機にカオナビを導入。効率化に加え、新制度の浸透にも効果が
評価システム「カオナビ」を使って評価工数を削減しましょう。
カオナビの導入効果や機能一覧について、以下の資料で解説しています。
⇒ カオナビの資料を見てみたい
製造業の人事評価システムにはカオナビがおすすめ

カオナビは顔写真を軸とした人材情報一元管理システムで、紙・Excelベースの人事評価運用からの脱却を支援し、評価業務の大幅な効率化と透明性向上を実現するタレントマネジメントシステムです。
評価シートの配布から回収までワークフロー化し、データを自動集計します。評価の進捗が明確に把握でき、誰がどこまで進んでいるか一目で確認できるため、運用管理が大幅に改善されます。
また、面談でのフィードバック履歴が残ることで、どんな相談にどんな回答をしたかが分かり、面談の満足度が向上します。評価結果を相対的にチェックできるため、評価者による評価のばらつきや基準との乖離が分かり、評価の透明性向上に貢献するのも特徴です。
さらに、紙やExcel、基幹システムに散在していたデータを集約し、自社に合わせた方法で人材情報を一元管理できます。
社員の評価履歴や異動履歴、スキル情報を簡単に検索でき、リアルな情報を把握することで適切なマネジメントに活用可能です。
直感的な操作性と高いカスタマイズ性により、企業規模や業種を問わず導入しやすく、評価の質と透明性を両立しながら、従業員エンゲージメントの向上と戦略的人事の実現を支援しています。
以下から、カオナビを無料でお試しいただけます。ご興味のある方はぜひお試しください。
⇒ カオナビを無料で試してみる
まとめ|製造業の人事評価で従業員を育てましょう
製造業の人事評価制度は、従業員の意欲向上や生産性向上、QCD改善など、多くのメリットがあります。しかし、現場作業の貢献度が見えにくく、評価基準設定が困難で、納得感を得るのが難しいという課題も同時に存在しています。
これらの課題解決には人事評価システムの導入が有効です。
システム化により評価業務の効率化や客観的で公平な評価基準の実現、データ活用による最適な人材配置が可能になります。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見られる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

