Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人事考課制度とは、従業員のモチベーションにも影響を及ぼす重要な制度。人事考課をスムーズに行うためにも、人事考課制度の設計に際しては制度の目的や役割を正しく理解して、効果的な制度設計をすることが求められます。
- 人事考課制度の意味や目的
- 役割やその効果
- 制度設計
について解説しましょう。
目次
時間が掛かる評価業務を効率化!
人事評価システムの選び方がわかる解説資料をプレゼント
資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから
1.人事考課制度とは?
人事考課制度とは上司が部下の業務に関する成績や能力、意欲などを多角的、総合的に評価するための制度です。
人事考課制度では、人事考課基準や考課方法から、報酬にどう連動させるかまで、人事考課に関わる全社的なしくみを取り決めていくことになります。
制度設計に当たっては公平性や透明度の高い設計が求められます。
人事考課は従業員一人ひとりの評価に直結するもの。従業員のやりがいや報酬にも影響を及ぼすため、適切な設計・運用を心がけましょう。
人事評価制度との違い
人事考課制度と人事評価制度には、ほとんど違いがないと考えて差し支えありません。
どちらも従業員の業務・成果・スキルなどを総合的に判断し、処遇について検討するフローです。
ただし、厳密には人事考課と人事評価には次のような目的の違いがあります。
- 人事評価(制度):従業員の業務や業績について判断する(ための制度)
- 人事考課(制度):従業員の処遇を目的に能力などを査定する(ための制度)

人事評価と人事考課の違いとは?【わかりやすく解説】
人事評価とは一体何でしょう。また人事考課との違いはどこにあるのでしょうか。目的や知っておきたいそれぞれの制度、システムについて深く掘り下げます。
1.人事評価と人事考課の違いとは?
人事評価は、会社...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.人事考課制度の4つの目的
人事考課制度には、4つの目的があります。
- 賃金制度の昇給や賞与の個人配分の資料
- 役職制度、職能資格制度の昇進、昇格の資料
- 異動制度の配置・異動資料
- 能力開発制度の教育訓練や指導の資料
これら4つの目的はすべて、客観的な資料を必要とする特徴があります。
また、従業員のモチベーションや能力開発など、経営資源「ヒト、モノ、カネ、情報」の一つである「ヒト」を活用して企業価値を高めるための重要な部分に関わる項目でもあるのです。
①賃金制度の昇給や賞与の個人配分の資料として提供する
賃金制度においては、人件費の総額を従業員にいかに適正に分配するのかが問われます。昇給や賞与といった個人の業績によって変動する賃金の適正な分配は、何らかの客観的資料に基づいて行う必要があるでしょう。
実際の給与額に影響を及ぼしますので、従業員も納得できる根拠が必要となります。人事考課制度は昇給や賞与の個人配分を決める資料を提供できるのです。
②役職制度、職能資格制度の昇進、昇格の資料として提供する
役職や職能資格などの制度を設けている企業は多くあります。これらの昇進、昇格、あるいは降格といったものを決定するにも、客観的資料は不可欠です。
これら制度は、従業員のモチベーションに直接関係してくる制度でもあります。人事考課制度を用いれば昇進や昇格などを公正かつ客観的に行えるでしょう。
③異動制度の配置・異動資料として提供する
従業員の異動を検討する際にも、人事考課制度は活用されます。人事考課制度は、個人の業務に関する成績や能力、意欲などを客観的、多角的、総合的に評価するもの。
従業員一人ひとりがどの持ち場でなら能力をフルに発揮できるのか、といった異動制度に基づく配置や配置先での職務検討などに活用できます。
④能力開発制度の教育訓練や指導の資料として提供する
人事考課制度は、従業員一人ひとりの能力を客観的に見つめ直すきっかけをつくってくれるほか、現時点での従業員のスキルや能力を客観的に評価する指針にもなります。
今、足りないスキルや能力、今後身に付けると良いスキルや能力を浮き彫りにできるため、日常の業務に関する指導だけでなく、能力開発や教育訓練を計画する際の基本的な資料として大いに役立つのです。
人事考課制度は構築・導入で終わらず、その後の運用も大切です。少しでも運用の負担が大きいと感じたら人事評価システムの導入を検討しましょう。人事評価システム「カオナビ」の資料を ⇒ とりあえず見てみる
3.人事考課制度の役割と機能
人事考課制度は従業員格付制度と個別管理をつなぐ役割を持っており、導き出された結果は、
- 従業員一人ひとりの賃金
- 昇進や昇格
- 配置や異動
- 能力開発
などさまざまな従業員格付制度につながっています。そして、各従業員を格付制度のどこに配置していけば良いかを客観的に判断する材料となるのです。
人事考課制度の結果が適切に提供されなければ、従業員の個別管理は成り立ちません。人事考課制度がない企業では、「一生懸命やっても、やらなくても、結果は同じ」という空気が蔓延し、個人のモチベーションはおろか組織の活力も低下するでしょう。

昇給とは? 平均金額と時期、決め方や計算方法をわかりやすく解説
昇給とは、企業が定める基準を満たした場合に従業員の基本給が上がる仕組みです。昇給制度は従業員や企業にとってさまざまなメリットがあるものの、うまく仕組みを構築して運用できないとメリットが発揮できなくなっ...
評価業務の時間が1/10以下になった実績多数! 人事評価システム「カオナビ」の資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから
4.人事考課制度のメリット・デメリット
人事考課制度では、上司が部下の業務に対する姿勢や成果などを考課表にまとめます。この考課表をもとにさまざまな人事処遇を決定するのですから、人事考課制度の効果は非常に大きいといえるでしょう。当然メリットが大きいと言えます。
一方で、誤った運用をしてしまうとデメリットも生じます。
人事考課制度のメリット・デメリットを見てみましょう。
人事考課制度のメリット
具体的な人事考課制度のメリットとして、
- 評価者の人を見る目が養われる
- 評価者が被評価者間の個人差を認識できる
- 被評価者の勤労意欲を向上させる
- 被評価者の人材育成ニーズの把握
- 教育効果のチェック
- 評価者と被評価者とのコミュニケーションの促進
などがあり多方面にさまざまな効果をもたらすのです。評価作業には、十分な時間をかけるとともに、評価者は面接やヒアリングなどを活用して丁寧な考察を行う必要があるでしょう。
人事考課制度のデメリット
では人事考課制度のデメリットは何でしょうか。
前提として、正しく人事考課制度を設計・運用すればデメリットはありません。ですから、ここで紹介するのは「人事考課制度を誤った方法で運用した場合のデメリット」です。
- 名ばかりの制度ではかえって被評価者のモチベーションを下げてしまう。
- 人事考課制度が形骸化すると、人手と時間ばかり奪われる。
- 適切な目標設定がされていないと被評価者の成長が見込めない。
- その時その時に適した制度に刷新していかないと機能しなくなる。
これらは人事考課制度を正しく使えていない場合のデメリットです。
繰り返しになりますが、評価作業に十分な時間をかけたり、被評価者に対するヒアリングを丁寧に行ったりするようにしましょう。
また非効率な人事考課制度の運用は、人事の負担を増やし、組織全体の評価の質を下げる可能性があることにも注意しましょう。評価制度や基準の改善、評価者育成の実行は、人事に余裕があってこそです。
評価業務の効率化で、人事の負担を減らし、評価の質を高める。人事評価システム「カオナビ」の紹介資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから
5.人事考課制度のつくり方とポイント
人事考課制度の設計には、5つのポイントがあります。それぞれについて、具体的に解説していきましょう。
- What:評価の対象(評価項目の定義とウェイト)
- How:評価点の定め方や集計方法(評定尺度、評語)
- Who:評価を行う人物(評定者の多層化と役割)
- When:評価期間
- Why:評価結果の活用対象(評価結果の目的)
①What:評価の対象(評価項目の定義とウェイト)
まず、人事考課制度を設計するに当たって、
- 何を考課対象にするのか
- 考課項目の定義とウェイトはどうするか
決めなければなりません。そもそも以前の日本では、年功序列制度が一般的であり、個人の能力の評価よりも勤続年数が優先されていました。

年功序列とは? メリット・デメリット、廃止の理由を簡単に
日本特有の雇用制度といわれる年功序列。成果主義が台頭しつつある現代でも、年功序列を導入している企業はまだ多くあるようです。
年功序列とはどんな制度なのか
意味や特徴
成果主義との違い
年功序列のメリ...
1969年に『能力主義管理―その理論と実践(日経連出版部)』が出版されて以降、個人の職務遂行能力を処遇に生かすため、職能資格制度に基づく人事考課制度が広がっていきます。現在、人事考課項目でよく用いられるのは、
- 能力評価
- 情意(態度)評価
- 成績評価
の3種類。このうち、能力、情意は潜在能力として、成績は顕在能力として評価されています。これら3つの人事考課項目について考察してみましょう。
能力評価
能力評価で観察される能力には、
- 職能資格要件に定めてある知識
- 統率力や指導力、判断力などの人間対応能力
- 理解力、企画力といった業務処理能力
3つがあります。最近では、1~3の枠を超えて、
- 人材開発能力
- 問題解決能力
- 数値管理能力
- 課題対応能力
など目的に応じて個別能力の名称を用いて従業員の能力を測るケースも増えているようです。評価対象となる能力は、業種や職務によって異なります。それぞれに合った能力の評価項目を設定しましょう。

能力評価とは? 項目と評価基準、目標・評価シートの書き方を解説
能力評価は人事評価項目の一つであり、職務遂行に必要なスキルや能力を評価する評価方法です。能力評価は定性的な評価項目であるため、導入する際はその性質や目的を理解し、適切な評価基準を設定して運用していくこ...
情意(態度)評価
情意評価は、性格的な面や仕事に対する意欲といったものを評価基準とします。具体的な評価項目として使われるのは、
- 責任感
- 協調性
- 勤勉性
- 積極性
など。一定の評価期間内で組織に対しどのように貢献したかを、態度や姿勢、行動といった側面から評価します。
情意的側面は、組織に与える影響が思いのほか大きい場合もあるのです。そのため情意評価の結果は、昇給や昇進だけでなく、配置転換や異動など幅広く活用されています。

情意評価とは?【わかりやすく解説】項目例、評価基準
情意評価の成功に欠かせない面談管理と評価業務をまとめて効率化。
人事評価システム「カオナビ」で、評価の質を上げ、従業員エンゲージメント向上!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp ...
成績評価
能力評価と情意評価が潜在能力であるのに対し、成績評価は顕在能力を評価するもの。成績では、
- 一定の評価期間における仕事の量や質に関する遂行度合い
- 上司からの指示や命令に対する職務遂行度合い
が評価要素になります。
成績評価は、これら評価要素に対してどの程度の成果を上げることができたかを評価します。評価結果は、主に賞与額に反映されることが多いようです。
②How:評価点の定め方や集計方法(評定尺度、評語)
人事考課制度を設計する際に、評価点をどのように定めるか、評価点の集計方法をどうするか、について考える必要があります。よく、
- 極めて優れている
- やや優れている
- 普通
- やや劣っている
- 劣っている
といった評語を使用した評価点を目にしますが、評価度合いを曖昧な言葉にすると評価者の主観が混ざってしまうこともあるのです。評価を表す言葉は、
- 当初期待したレベルをはるかに超えた仕事ぶり
- 期待水準を下回る出来で終わった
など具体的な言葉とし、それらを5点から1点で数値化した5段階評価で行うとよいでしょう。
③Who:評価を行う人物(評定者の多層化と役割)
人事考課制度では、誰が評価を行うのかを明確に設定する必要があります。人事考課は上司が部下の仕事ぶりを評価するものですが、上司は一人である必要はありません。
近年では、「評価の多面化」「評価者の多層化」といった言葉にも象徴されるように直属の上司のみならず、何段階かにわたる複数の上司によって「2次評価」「3次評価」といった評価システムを採用する企業も多いです。
④When:評価期間
人事考課制度では、必ず評価期間を設定します。情意評価と成績評価は変動しやすいので半年に1回程度、変動が少ない能力評価は年1回行うといった期間設定が一般的です。
人事考課は、評価期間の従業員の働き方を評価するもの。よって、前評価期間で高評価であった者が、今期の評価期間でも必ず高評価になるとは限りません。
反対に、前評価期間で評価が今一つだった者でも、頑張り次第でいくらでも高評価を目指すことができます。従業員が常に新たな気持ちで評価期間に全力を尽くせるよう、サポート体制を整えることも重要でしょう。
⑤Why 評価結果の活用対象(評価結果の目的)
人事考課制度で下された評価結果は、評価項目に応じてさまざまな目的のもと使用されます。能力評価の活用目的に多く見られるのは、
- 昇給・昇格
- 賞与
- 配置・異動
- 能力開発
など。情意評価は、
- 昇給・昇格
- 賞与
などに用います。また、成績評価は、主に賞与に用います。
人事評価は部署や業種によって変わったり、ビジネス環境の変化に合わせて変えていく必要があります。そのためシステムを導入する際には、あらゆる人事評価に対応できる柔軟性をもったシステムを選ぶことが大切です。
カオナビなら時代や組織の状態に合わせて評価項目や評価シートを自在にカスタマイズ可能。長い目で見て実用的なシステムです。資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから
6.人事考課制度の運用に役立つ3つの評価手法
ここからは人事考課制度をうまく運用するための3つの人事評価方法を紹介します。業界や職種、役職ごとで適切な方法を選択し活用しましょう。
MBO
MBOとはManagement by Objectives(目標による管理)の略です。「目標管理」や「目標管理制度」と呼ばれることもあります。
個人や部署ごとで目標を決めて、それに対する達成の程度を評価する手法のことです。1954年、ドラッカーが提唱した組織マネジメントの概念です。

目標管理制度とは? 意味や目的、メリット・デメリットを簡単に
マネジメントで有名な経営思想家ピーター・ドラッカーが提唱した、組織における目標管理制度(MBO)。この目標管理制度は、組織貢献と自己成長の両方が達成できる個人目標を設定させ、その達成度で評価を行う人事...
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは職務ごとに定義された行動特性(コンピテンシーモデル)をもとに行う人事評価のことです。
高い業績を上げる社員には共通する行動特性があります。「なぜ高い業績を達成できるのか」という理由を体系化したものがコンピテンシーです。
コンピテンシーを明確化するためには、能力だけではなく「どのように行動したのか」という行動特性を把握する必要があります。
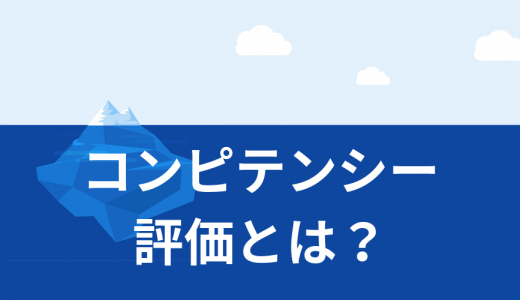
コンピテンシー評価とは? 項目例、メリット、導入手順を簡単に
コンピテンシー評価には、ハイパフォーマーの共通点の見える化が必須。
人事評価システム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...
360度評価
360度評価とは、被評価者の上司や同僚、部下などさまざまな立場の人物が多面的に評価する手法です。
上司の判断に依存しすぎることなく、公平で客観的な評価を得やすいというメリットがあります。
評価対象者が納得しやすい評価制度です。

360度評価とは? 目的やメリット・デメリットをわかりやすく
360度評価テンプレートで、Excelや紙の評価シートを楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp に...
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる
カオナビで人事評価を【システム化】することで、評価の“質”や“納得度”を上げるような時間の使い方ができます
⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)
