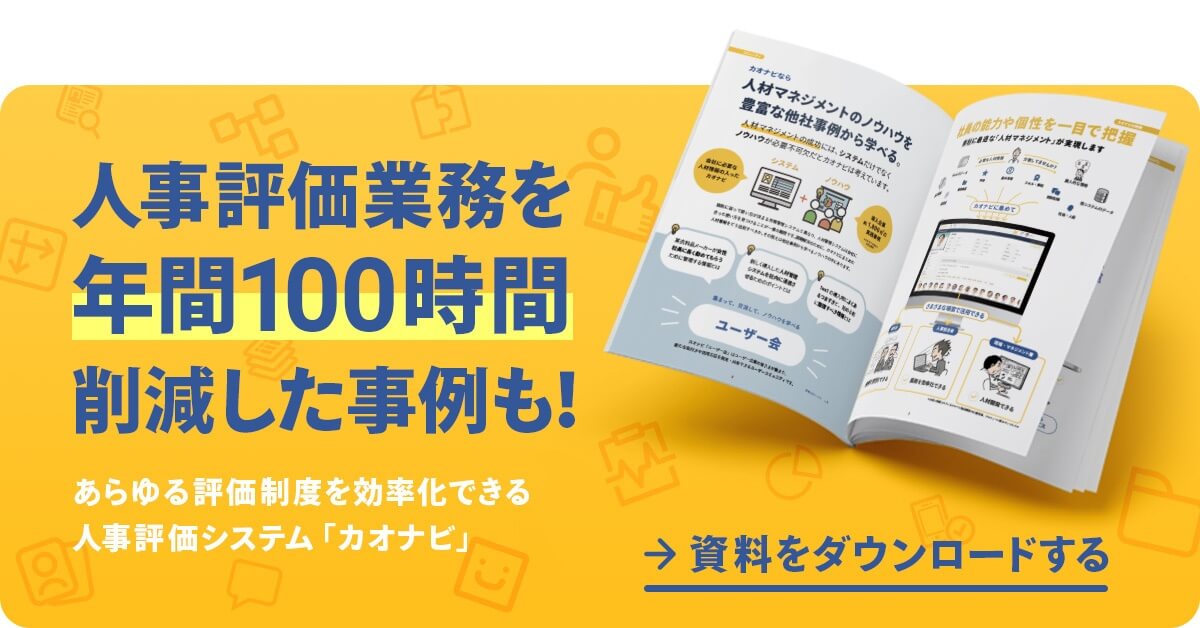情意評価の成功に欠かせない面談管理と評価業務をまとめて効率化。
人事評価システム「カオナビ」で、評価の質を上げ、従業員エンゲージメント向上!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
評価手法の1つである情意評価。数値化できないものを評価する評価において、具体的に何を評価し、どのようなポイントを押さえればいいのでしょうか。情意評価の概要とともに確認していきましょう。
1.情意評価とは?

情意評価とは、従業員の仕事に対する意欲や姿勢を評価する手法です。業績評価のように成果が明確な数字で表すことできないため、評価者の主観に左右されやすい特性があり、そのため評価項目を具体的に定め運用する必要があります。外的要因等で数値目標達成が難しい従業員のフォローを目的に利用されることもあります。

人事評価制度とは? 目的や仕組み、種類や手法、導入手順を解説
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.情意評価の具体的な項目とは?

情意評価は主に4つの項目に分けて考査されます。まずは規律性です。会社が組織として活動する際、一定のルールがあります。このルールにのっとった行動ができているかどうかを査定します。さらに視点を広げて社会的な規範を守れる人物かどうかも考慮します。
2つ目の項目は積極性です。上司からの指示を待つだけでなく、必要なことを積極的・能動的に行動に移せるかどうかです。時には、上司が忙しくて指示を出す余裕のないこともあります。その時自分で仕事を見つけて動ける人材は、会社にとっても好ましいでしょう。
3つ目は責任性です。ポジションによって大小はあるものの、新卒の社員でも仕事や職務に対して何らかの責任を持ちます。自分の責任を認識して、その役割を全うしようとする姿勢・意志を持っているかどうか評価します。
最後が協調性です。チームや部署の同僚をうまく付き合っていけるか、職場に溶け込もうと努力しているかどうかを評価します。この4つの項目をベースにして、情意評価を決めましょう。
記憶便りに情意評価を行ってしまうと、実態とは異なる不適切な評価となり、部下の不満やエンゲージメント低下につながるリスクがあります。
質の高い情意評価の実施には、部下の日々の行動や面談の記録を残しておく仕組みづくりが重要です。これは紙やExcelでも可能ですが、運用の負担を考えると、人事評価システムの利用が効果的です。
カオナビなら、情意評価の効率化に対応。クラウド型なのでリーズナブルに導入可能です。人事評価システム「カオナビ」の資料は⇒ こちらから
3.情意評価の書き方のポイントとは?

情意評価を行うにあたって注意しなければならないのは、誤った判断を下さないことです。情意評価は評価する人の主観が入りやすいです。特に注意するポイントとして、ハロー効果があります。ハローとは太陽や月の周囲などに現れる光の輪のことです。思い込みの一種で、ある評価項目の評価が悪いとほかのものもすべて悪く思ってしまうことです。逆もあって、一つがいいとほかもいいように錯覚する可能性もあります。
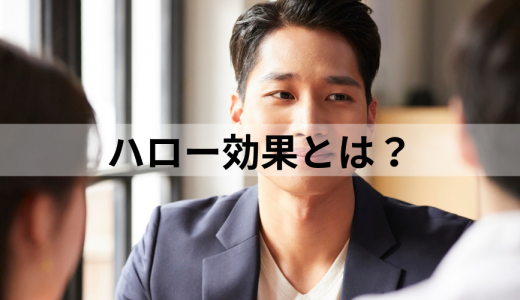
ハロー効果とは?【意味を図解でわかりやすく】具体例と対策
人事評価の実施において気になるのは、評価者による評価エラーでしょう。こうした評価エラーの中に、ハロー効果と呼ばれるものがあるのですが、一体どのようなものなのでしょう。
ハロー効果の種類や実例
ハロー...
そのほかにも寛大化傾向も情意評価の書き方で注意すべきことです。寛大化傾向は普段かわいがっている部下に対して甘い評価をしてしまうことです。また極端な評価を出すと後々角が立つので、無難な評価をする中心化傾向も正しく評価する足かせになりかねません。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる
カオナビで人事評価を【システム化】することで、評価の“質”や“納得度”を上げるような時間の使い方ができます
⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)