人事評価を行うには、タレントマネジメントが重要です。
タレントマネジメントの基礎知識や、システムの選び方を解説!
⇒「タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
公平で納得感のある人事評価の基準は、明確な評価項目と客観的な判断指標を設定することで実現できます。
この記事では、国家公務員の評価制度も参考にした基準表の作成方法、5段階評価の点数配分、基準日の設定から基準公開までの具体的なプロセスを解説します。
評価の根拠が上司と部下間でしっかり共有され、従業員が目標達成に向けて主体的に行動し、組織全体の業績向上と継続的な成長サイクルが根付く職場環境を実現したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
人事評価の基準とは

まずは、人事評価における基準について、以下のポイントについて詳しく解説していきます。
- 人事評価の基準を設ける目的
- 人事評価の基準がない場合の問題点
人事評価の基準を設ける目的
人事評価の基準を設ける目的は、以下の3点です。
- 評価の公平性確保
- 従業員の成長促進
- 組織目標と個人行動の連動
明確な基準を設けることにより、評価が主観に左右されず、従業員が「何をどのように取り組めば評価されるのか」を具体的に理解できます。
たとえば、顧客満足度向上を基準に組み込むことで個人の行動が会社のビジョン達成に直結し、段階的な基準設定により評価者の客観的判断と従業員の具体的目標設定が可能になります。
適切な評価基準は従業員と組織の成長を結びつけ、持続的発展を促す好循環を生み出します。
以下の記事では、人事評価制度の目的について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

人事評価制度の3つの目的【わかりやすく解説】種類、導入手順
人事評価制度とは、企業が目的達成のために、社員の業務を合理的手段によって評価する制度のこと。ここでは、導入の流れや導入事例について解説します。
1.人事評価制度導入の目的とは?
人事評価制度導入の目...
人事評価の基準がない場合の問題点
人事評価の基準がない場合の問題は、不公平な評価により従業員のモチベーションが低下することです。
基準が曖昧だと評価が上司の個人的な感情や印象に依存し、従業員は「頑張っても正当に評価されない」と感じて仕事への意欲や会社への信頼を失います。
たとえば、リモートワーク環境では、オンライン会議で目立つ従業員だけが評価され、チャットでの知見共有や地道な課題解決に取り組む従業員があまり評価されないケースが起きるかもしれません。
不公平な評価で社員のモチベーションを低下させないためにも、明確な評価基準を決めておくとよいでしょう。
以下の記事では、従業員が人事評価に納得できない理由を解説しております。公正な人事評価についてお考えの方はぜひ参考にしてください。
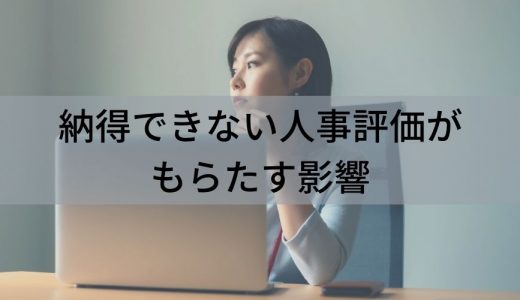
人事評価が納得できない理由と対策【わかりやすく解説】
納得できない人事評価は、従業員のモチベーション低下や離職率の増加などさまざまなリスクをもたらします。納得できない人事評価の要素や、納得感を高めるポイントについて解説しましょう。
1.人事評価に納得で...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
●1on1の進め方がわかる
●部下と何を話せばいいのかわかる
●質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見られる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
人事評価の基準を定めるメリット

客観的で透明性の高い評価基準は、従業員と企業の双方にとってメリットをもたらします。
人事評価の基準を定めることで得られる具体的なメリットは、以下のとおりです。
- 公平・公正な評価ができる
- 従業員のモチベーションアップにつながる
- 社員の育成ができる
公平・公正な評価ができる
人事評価の基準を設けるメリットは、評価者の主観や印象に左右されない公平な評価を実現できる点にあります。
人は無意識のうちに好き嫌いで判断したり、ひとつの印象に全体が引っ張られる「ハロー効果」といった認知の偏りを持っていたりします。
たとえば、評価基準がない場合、「Aさんはいつも元気で印象が良いから高評価」といった曖昧な判断がされがちですが、「業務知識レベル3:マニュアルを見れば独力で業務を遂行できる」という具体的な行動基準があれば、評価者も被評価者も客観的な事実にもとづいて判断できます。
公平な評価は従業員との信頼関係の土台となり、組織の健全な成長を促します。
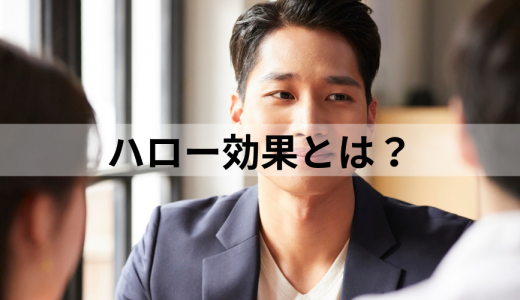
ハロー効果とは?【意味を図解でわかりやすく】具体例と対策
人事評価の実施において気になるのは、評価者による評価エラーでしょう。こうした評価エラーの中に、ハロー効果と呼ばれるものがあるのですが、一体どのようなものなのでしょう。
ハロー効果の種類や実例
ハロー...
従業員のモチベーションアップにつながる
明確な評価基準は、従業員の努力の方向性を具体的に示し、モチベーションを引き出す効果があります。
従業員は、「何を達成すれば評価されるのか」「どうすれば昇進や昇給につながるのか」というキャリアの見通しが立つことで、日々の業務に目的意識を持って取り組めるようになります。
たとえば、個人の成果だけでなく、チームワークへの貢献といった行動も評価項目に加えることで、チーム全体で目標を達成しようという協力的な文化が育まれ、組織全体の士気も向上します。
従業員のモチベーションは、企業の成長につながるため、明確な評価基準を定めましょう。
社員の育成ができる
人事評価の基準は、単なる査定のためのルールではありません。
従業員一人ひとりの強みや課題を可視化し、効果的な人材育成を実現する上で、重要な役割を担います。
たとえば、評価結果から「Aさんは顧客への提案力は非常に高いが、データ分析のスキルに課題がある」という事実が明確になった場合、上司は具体的な研修をすすめたり、OJTで関連業務を任せたりする、といった的確な育成アクションを取れます。
評価面談も、単なる結果の通知の場から、「この課題を克服するために、来期は一緒にこう取り組んでいこう」という未来を見据えた対話の場へと変えられるでしょう。

中小企業が人事評価システム導入すべき理由とメリットとは?
中小企業にも人事評価システムを導入すべきなのでしょうか。人事評価システムの特徴や導入の注意点とともに、見ていきましょう。
1.中小企業が人事評価システムを導入すべき理由
中小企業における人事評価シス...
カオナビには、人事評価に必要な機能が揃っています。
従業員のデータを一元管理できます。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人事評価の基準となる3つの主要な基準

人事評価の基準となる3つの主要な基準について紹介します。
人事評価の主要な基準には、以下があります。
- 成果についての評価
- 能力についての評価
- 勤務態度についての評価
これらの基準は、職位や職級に応じた等級制度であるグレード制度や総合職・専門職などのキャリアコース別の制度であるコース制度と連動して設計することで、より効果的な人事評価システムを構築できます。
成果についての評価
成果についての評価は、従業員が一定期間内に達成した具体的な業績や目標達成度を数値で測定する人事評価の基準です。
この評価方法は、売上高や生産量、プロジェクトの完遂率など、客観的に判断できる指標を用いるため、評価の透明性と公平性を確保しやすい特徴があります。
たとえば、以下のように職種とグレードレベルに応じた具体的なKPIを設定することが重要です。
| 職種 | KPI例 |
| 営業職 | ・売上目標達成率120% ・新規顧客獲得数50件 |
| 製造業 | ・生産効率向上率15% ・品質不良率0.5%以下 |
ただし、成果のみに偏重すると短期的な結果を追求する傾向が強まり、チームワークの阻害や長期的な成長の妨げになる可能性があるため、他の評価基準とのバランスが必要です。
能力についての評価
能力についての評価は、従業員が業務を遂行する過程で発揮する知識やスキル、専門性などの職務遂行能力を測定する人事評価の基準です。
この評価では、以下のような成果を生み出すプロセスで必要となる能力を評価対象とします。
- 企画力
- 問題解決能力
- コミュニケーション能力
- リーダーシップ など
たとえば、コンピテンシー評価では「チームメンバーの意見を積極的に聞き、合意形成を図る」などの具体的な行動指標で評価し、総合職コースでは管理能力、専門職コースでは技術的専門性を重視するなど、コース制度に応じた能力評価の重点を変えることが効果的です。
能力評価は人材育成の方向性を示す重要な指標となるため、評価結果をグレード昇格の判断材料や研修計画、キャリア開発に活用することが効果的です。
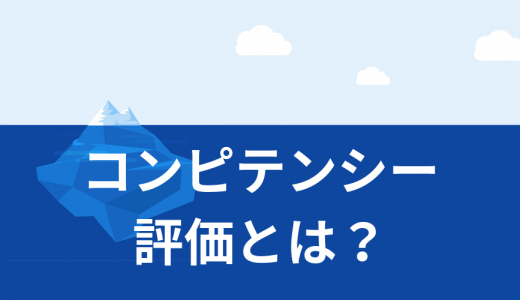
コンピテンシー評価とは? 項目例、メリット、導入手順、注意点を簡単に解説
コンピテンシー評価には、ハイパフォーマーの共通点の見える化が必須。
人事評価システム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...

能力評価とは? 項目と評価基準、目標・評価シートの書き方を解説
能力評価は人事評価項目の一つであり、職務遂行に必要なスキルや能力を評価する評価方法です。能力評価は定性的な評価項目であるため、導入する際はその性質や目的を理解し、適切な評価基準を設定して運用していくこ...
勤務態度についての評価
勤務態度についての評価は、以下のような仕事に向き合う姿勢や行動特性を評価する人事評価基準です。
- 従業員の規律性
- 協調性
- 積極性
- 責任感など
この評価は、企業の理念や価値観への貢献度を測定し、組織文化の維持・向上に重要な役割を果たします。
具体的には、以下のように基準を定めます。
| 評価するポイント | 基準 |
| 規律性 | ・遅刻・欠勤の頻度 ・報告・連絡・相談の徹底度 |
| 協調性 | ・チーム内での情報共有頻度 ・他部署との連携積極性 |
| 積極性 | ・改善提案の回数 ・自己啓発への取り組み度 |
ただし、勤務態度の評価は主観的な判断になりやすいため、「協調性がある」という抽象的な表現ではなく、「部署間の調整会議で積極的に発言し、合意形成に貢献した」など、具体的な行動事実に基づいて評価することが公平性確保の鍵となります。
カオナビには、人事評価に必要な機能が揃っています。
導入効果や機能一覧をわかりやすく解説しています。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人事評価の基準の具体的な作り方

具体的な人事評価の基準の作成は、以下の点に注意しておこないましょう。
- 具体的な評価項目を決める
- 評価基準の点数化をおこなう
- 評価担当者を決める
- 評価をおこなう期間を設定する
- 評価結果を今後に活かす
具体的な評価項目を決める
人事評価基準の作成において最初におこなうのが、具体的な評価項目の設定です。
評価項目は、企業の戦略目標と職種の特性を考慮し、成果・能力・勤務態度の3つの軸から体系的に設計する必要があります。
評価制度の導入時には従業員説明会や個別面談を実施し、各項目の意味と測定方法を詳しく説明することで、制度への理解と納得感を高められます。
評価基準の点数化をおこなう
評価項目を決定した後は、客観的で公平な判断を可能にする点数化システムの構築が必要です。
一般的には5段階評価(S・A・B・C・D)が採用され、各段階に具体的な行動基準を設定します。
たとえば「リーダーシップ」という項目では、以下のように各レベルを具体的な行動で定義します。
| 5段階評価 | 評価基準 |
| S | チーム全体を牽引し困難な状況でも明確な方向性を示す |
| A | 通常業務では適切な指示・支援ができる |
| B | 基本的なリーダーの役割は果たせる |
| C | 指示を受ければ行動できる |
| D | 指示待ちの傾向が強い |
5段階基準の設定においては、評価者間の判断のばらつきを防ぐため、評価者研修での目線合わせを徹底し、評価基準表を全社で共有することが重要です。
評価担当者を決める
公正で信頼性の高い人事評価制度を構築するには、適切な評価担当者の選定と役割分担の明確化が不可欠です。
基本的な評価体制は、直属の上司が一次評価者、その上位管理職が最終評価者となる複数段階評価システムが推奨されます。
たとえば、360度評価を導入する場合は、上司・同僚・部下からの多面的なフィードバックを活用することで、より客観的な評価を実現できます。
評価者には、評価エラーを避けるための専門研修を実施し、評価スキルの向上を図ることで、より精度の高い評価ができるようになるでしょう。
評価をおこなう期間を設定する
人事評価の実効性を高めるには、適切な評価期間の設定が重要です。
評価期間が短すぎると十分な成果測定ができず、長すぎると目標と現実のギャップが生じやすくなるためです。
具体的なスケジュールは、以下のような流れが一般的です。
- 4月に目標設定
- 9月に中間レビュー
- 10月に評価とフィードバック
- 翌年3月に最終評価
近年は変化の激しいビジネス環境に対応するため、四半期ごとの短期サイクル評価を導入する企業も増えています。
評価期間の設定では、業界特性や繁忙期を考慮し、従業員が十分なパフォーマンスを発揮できる期間を確保することが肝心です。
評価結果を今後に活かす
人事評価の真価は、評価結果をいかに組織の成長と従業員の発展に活用するかで決まります。
評価データは給与や賞与の決定だけでなく、人材育成やキャリア開発、適材適所の配置に戦略的に活用すべきです。
たとえば、バリュー評価では企業理念や行動指針への貢献度を以下の指標で測定します。
- 理念に基づいた提案回数
- メンタリング活動への参加度
- 社内イベントへの貢献 など
評価結果から明らかになった課題に対しては、個別の育成計画を策定し、定期的な1on1面談でフォローアップを実施します。
全社的な傾向分析により、階層別研修プログラムの企画や後継者育成計画に活用し、組織全体の能力向上を図ることが重要です。

バリュー評価とは? 特徴やメリット、書き方と具体例を解説
近年、多くの企業が導入を進めている「バリュー評価」は、従業員の行動を企業の価値観やミッションに照らし合わせて評価する人事評価制度です。企業の一体感や従業員のモチベーション向上に寄与するため、注目されて...
1on1で話す内容について困っていませんか?
部下と話すべき内容や、質の高い質問項目を解説しています。
⇒ 「1on1ミーティングガイド」を無料ダウンロードする
人事評価の基準を決める際のポイント
人事評価の基準を実際に定め、運用していくうえでは、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
具体的には、以下の6つのポイントが重要です。
- 評価基準や項目は複数人で決める
- 評価基準を明確にする
- 評価基準を従業員に伝える
- 相対評価と絶対評価を使いわける
- 評価担当者への研修をおこなう
- 評価に対してのフィードバックをおこなう
評価基準や項目は複数人で決める
人事評価の基準や項目は、経営層や人事担当者だけで決定するのではなく、現場の管理職や従業員代表など、複数の関係者を巻き込んで多角的な視点から決めることが成功の鍵です。
現場の実態から乖離した評価基準は、従業員の不満や制度の形骸化を招く大きな原因となります。実際に業務をおこなう従業員や、部下のマネジメントを担う管理職の意見を取り入れることで、より現実的で意味のある基準を作成できます。
たとえば、各部門から代表者を集めて評価基準に関するワークショップを開催したり、人事部門が作成した草案に対して、全社的に意見を公募する期間を設けたりすることが有効です。
策定プロセスに従業員が関与することで、自分たちも参加して作った制度という当事者意識が芽生え、導入後の納得感を高める効果も期待できます。
評価基準を明確にする
設定した評価基準は、誰が読んでも同じ解釈ができるレベルまで、具体的かつ明確な言葉で定義する必要があります。
評価におけるトラブルの多くは、基準の曖昧さが原因で起こり、「リーダーシップを発揮した」「業務に貢献した」といった抽象的な表現は、評価者によって解釈が大きく異なり、評価のブレや不公平感を生む温床となります。
明確な基準は、評価の客観性を担保するだけでなく、従業員が目標を設定する際の具体的な行動指針ともなります。
評価基準を従業員に伝える
どれほど優れた評価制度を構築しても、その内容が従業員に伝わっていなければ意味がありません。
完成した評価基準は、全従業員に対してその目的や内容を丁寧に伝え、周知徹底することが不可欠です。情報の透明性を確保することが、制度への信頼と納得感につながります。
たとえば、全社または部門ごとに説明会を開催し、質疑応答の時間を十分に設けたり、評価基準表をまとめた詳細なガイドブックを作成し、社内で誰もがいつでも閲覧できる状態にしておくことが有効です。
評価基準の伝達は一方的な通知ではなく、従業員との対話と捉え、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
相対評価と絶対評価を使いわける
評価方法には、集団内での位置づけで評価する相対評価と、個人の目標達成度で評価する絶対評価の2種類があります。
相対評価は、S評価〇%、A評価〇%といったように評価の分布を事前に決めるため、人件費のコントロールがしやすいメリットがあります。一方で、必ず低評価者が生まれるため、従業員の過度な競争や不公平感につながる可能性もあるでしょう。
絶対評価は、個人の頑張りや成長をそのまま評価できるため、モチベーション向上につながりやすいですが、評価が全体的に甘くなる傾向があり、部門間の評価レベルの調整が難しいという課題があります。
それぞれのメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット | |
| 相対評価 | 人件費の管理が容易である ・従業員間の競争を促進しやすい |
・必ず低評価者が発生する ・チームワークを阻害する可能性 |
| 絶対評価 | ・個人の成長を正当に評価できる ・納得感を得やすい |
・評価が甘くなる傾向にある ・評価者によるレベルのばらつき |
近年では、個人の成長を促すために絶対評価を基本としながら、最終的な処遇決定の段階で部門間のバランス調整をおこなうハイブリッド型の手法を取り入れる企業が増えています。

相対評価と絶対評価の違いとは?【比較表でわかりやすく解説】
【AI活用でスムーズに】目標設定、評価シート入力をAIがアシスト!
生成AIに「たたき台」を作らせて、目標・評価シート作成の悩む時間を解決しませんか?
⇒【コピペで使える】プロンプト付き「生成AI仕事...
評価担当者への研修をおこなう
人事評価制度の公平性と実効性は、評価者となる管理職のスキルに大きく依存するため、評価担当者への研修をおこないましょう。
評価は、人が人を評価する行為であるため、評価者が訓練を受けていない場合、ミスが多くなる場合があります。
評価者研修では、以下を学びます。
- 自社の評価制度の目的と基準の理解
- 陥りやすい評価エラーの種類と防止策
- 客観的な事実に基づき評価するための記録方法
- 部下の成長を促す効果的なフィードバック面談の進め方 など
評価者研修は、公正な評価制度を維持するためのコストではなく、組織のマネジメント能力を向上させるための戦略的な投資と捉え、継続的に実施しましょう。

評価者研修とは?【必要な理由】目的、具体例、実施ポイント
評価者研修とは、管理職や人事部の担当者など、人事評価の評価者を対象とした研修です。人事評価の仕組みや評価方法、評価に必要な知識・スキルを体系的かつ実践的に学べます。
評価は人材戦略の重要な要素であり、...
評価に対してのフィードバックをおこなう
評価は、結果を通知して終わりではなく、評価面談を通じて具体的なフィードバックをおこない、従業員の次の成長につなげることが重要です。
建設的なフィードバックは、評価結果に対する従業員の納得感を高めてモチベーションを向上させ、上司と部下の対話を通じて信頼関係を深める効果もあります。
効果的なフィードバックのポイントは、以下の3点で、よかった点(承認)と改善が期待される点(期待)の両方を伝え、次はどうすればもっとよくなるかを共に考える未来志向の対話を心がけることが重要です。
- 具体的であること
- タイムリーであること
- 双方向の対話であること
質の高いフィードバック文化を組織に根付かせることが、従業員と組織が共に成長していくための鍵となります。
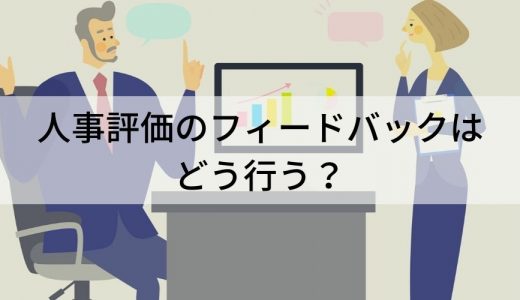
人事評価のフィードバックとは? 適切な方法を解説
人事評価のフィードバックとは、人材育成の役割を担う重要な業務です。ここでは人事評価におけるフィードバックのメリットや実施のポイント、目的や生かせるスキルなどについて解説します。
1.人事評価における...
「カオナビ」なら人事評価にかかる工数を大幅削減!
導入効果や、機能一覧についてわかりやすく解説しています。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人事評価の基準に関するよくある質問
ここからは、人事評価の基準に関するよくある質問について解説していきます。
具体的なよくある質問は、以下のとおりです。
- 人事評価の基準は何段階でおこなうべき?
- 人事評価の基準でよく聞くノーレイティングとは?
- 人事評価エラーとは?
- 数値化しにくい人事評価の基準の決め方とは?
人事評価の基準は何段階でおこなうべき?
評価段階の数に絶対的な正解はありませんが、一般的には5段階評価が多くの企業で採用されています。
段階数が少なすぎると、従業員のパフォーマンスの微妙な差を表現しきれず、評価が中央に集中しやすくなります。反対に多すぎると、各段階の定義が複雑になり、評価者の判断が煩雑になります。
近年では、あえて普通という選択肢を設けない4段階評価も注目されており、中間の選択肢がないため、評価者がより慎重によい点・悪い点を吟味して判断する必要があり、評価にメリハリがつきやすいというメリットがあります。
まずは一般的な5段階評価を基本に検討し、自社の文化や評価者に求める判断のレベルに合わせて最適な段階数を決定しましょう。
人事評価の基準でよく聞くノーレイティングとは?
ノーレイティングとは、S・A・Bといった年次のランク付けを廃止し、上司と部下による継続的な1on1ミーティングや、リアルタイムのフィードバックを重視する人事評価の考え方や仕組みのことです。
従来の年次評価が持つ、変化の速いビジネス環境に対応しきれない、過去の業績評価に偏りがちで未来の成長につながりにくい、といった課題を克服するために生まれました。
目標の柔軟な見直しやタイムリーな軌道修正が可能になり、従業員は自身の成長を実感しやすくなりますが、ランク付けがなくなる分、給与や賞与といった処遇を別途明確に設計する必要があります。
単にランク付けを廃止する制度ではなく、本質である「継続的な対話と成長支援」の文化を組織に根付かせられるか、慎重に検討しましょう。
人事評価エラーとは?
人事評価エラーとは、評価者が無意識のうちに持つ心理的な偏りによって、客観的であるべき評価が歪められてしまう現象のことです。
評価は人が人を評価する行為であるため、評価者の心理状態や先入観などの影響を完全に排除することは困難です。エラーの存在を理解せず放置すると、評価の公平性・信頼性が大きく損なわれ、従業員の不満の大きな原因となります。
代表的な評価エラーには、以下のような種類があります。
| エラー名 | 内容 |
| ハロー効果 | 学歴や第一印象など、ひとつの目立つ特徴に評価全体が引っ張られてしまう。 |
| 中心化傾向 | 部下からの反発などを恐れ、評価が「普通」の段階に集中してしまう。 |
| 寛大化/厳格化傾向 | 全体的に評価が甘すぎたり、逆に必要以上に厳しくなったりする。 |
| 期末効果(直近効果) | 評価期間全体のパフォーマンスではなく、評価直前の出来事の印象に左右される。 |
| 論理誤差 | 「〇〇が得意だから△△もできるはず」と、事実に基づかず推論で評価してしまう。 |
評価エラーは誰にでも起こりうるという前提に立ち、評価者研修などを通じてエラーの種類と対策を学ぶことが、エラーの発生を最小限に抑える上で重要です。
以下の記事では、人事評価のエラーについて解説しています。種類や対策についても解説していますので、人事評価エラーにお悩みの方はぜひ参考にしてください。

人事評価エラー(バイアス)とは? 種類と対策をわかりやすく
人事評価エラー(バイアス)とは、偏った思考により不公平な人事評価を行ってしまうこと。人事評価エラーは企業全体に悪影響を及ぼすため、早期の是正が必要です。
1.人事評価エラーとは?
人事評価エラーとは...
カオナビなら、人事評価にかかる工数を大幅削減!
従業員データをデータベースで一元管理できます。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人事評価の基準の作成にはカオナビがおすすめ

人事評価の基準作成と運用には、カオナビのタレントマネジメントシステムが効果的です。
カオナビでは、従業員の成果・能力・勤務態度を一元管理し、5段階評価の設定から360度評価の実施、評価結果の分析まで包括的にサポートします。
評価基準の可視化機能により、評価者と被評価者が共通認識を持てるほか、評価エラーを防ぐためのアラート機能や、人材育成に活用できる詳細な分析レポートも提供されます。
また、1on1面談の記録管理やフィードバック履歴の蓄積により、継続的な人材開発を実現し、組織全体の構築に役立つでしょう。
公平で透明性の高い評価制度の導入を検討されている企業は、ぜひカオナビの活用をご検討ください。
以下からカオナビの特徴がわかる資料をダウンロードいただけますので、ご興味のある方はぜひ確認してみてください。
⇒カオナビの資料ダウンロードはこちら
まとめ
人事評価の基準は、評価の公平性確保や従業員の成長促進、組織目標と個人行動の連動を目的として設定されます。
基準がないと評価が主観に左右され、従業員のモチベーション低下や人材流出を招く重大なリスクとなります。
効果的な評価基準を作成するには、成果・能力・勤務態度の3つの軸から具体的な評価項目を設定し、5段階評価などで点数化をおこない、複数の関係者を巻き込んで現場の実態に即した基準を策定することが重要です。
また、評価者研修の実施、従業員への丁寧な説明、継続的なフィードバックを通じて、組織全体の成長と持続的発展を促す評価制度を構築することが成功の鍵となります。
まずは各部門の代表者を集めた評価基準検討会議の開催から始め、段階的により良い評価制度を構築していきましょう。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見られる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

