部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人材育成とは、企業が業績を上げて経営目的を達成するために従業員を育成する取り組みをいいます。従業員を役職や職種、入社年数などで分けてグループごとにスキル習得を促します。
従来、人材育成は人事部や人材育成部などが行うイメージが強かったですが、現在ではその時々において必要になるスキルや能力を習得できるよう現場も含めて取り組む必要性が出てきました。
手法は、OJTやOff-JT、自己啓発など様々です。メンター制度やジョブローテーションなども人材育成において重要で、多方向から従業員の育成を促す必要があります。
この記事では、人材育成の目的や人材開発・組織開発との違い、必要な理由などを解説します。人材育成の進め方、具体的な取り組み方法など悩んでいる方は参考にしてみてください。
1.人材育成とは?
人材育成とは、企業が従業員に対して必要なスキルや知識を習得させ、組織全体の成長や目標達成に貢献できる人材へと成長させる取り組みです。
自社で価値を発揮し、成果を上げられる人材を育てることが重要です。そのため、人材育成計画は、自社の理念や戦略、現在の課題を踏まえた上で、自社に最適な形で策定する必要があります。
人材育成の手法はOJT、Off-JT、自己啓発などがあります。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.人材育成の目的
人材育成の目的としては、以下が挙げられます。
- 経営目標を達成させるため
- 競争力を強化するため
- 生産性を向上させるため
経営目標を達成させるため
企業が持続的に成長し、事業戦略を実現するためには、従業員のスキル向上が不可欠です。人材育成を通じて、従業員一人ひとりが経営目標を理解し、それに向けた行動がとれるようになると企業全体のパフォーマンスが向上します。
また、従業員が自身の役割や企業の方針を理解することで、業務の効率化や意思決定の迅速化にもつながります。
競争力を強化するため
人材育成は、短期的な成果だけではなく、中長期的な組織力強化にも役立ちます。特に、昨今では生成AIの登場など急激なビジネス環境の変化に柔軟に対応できる人材が必要です。
強い組織力を持つ企業は、変化に迅速に対応し、持続可能な成果を出せます。
若手社員が10年後、20年後には企業の中心的存在として、スキルや能力を発揮する必要があるため、中長期的な視点で競争力を強化しなくてはいけません。
生産性を向上させるため
従業員がスキルや知識を身につけることで、仕事の進め方が効率的になり、その結果、生産性の向上が期待できます。
特に、日本では少子高齢化による人手不足が深刻化しており、一人ひとりのパフォーマンスを高めることで人材不足をカバーする必要があります。
新しい従業員を採用および育成するには多くのコストがかかりますが、既存従業員だけで十分な生産性を上げられるのであれば、その分のコスト削減にも有効です。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.人材育成と人材開発、組織開発との違い
人材育成・人材開発・組織開発は、いずれも組織の成長や発展に関する言葉です。しかし、対象者や目的、手法に違いがあります。
| 人材育成 | 人材開発 | 組織開発 | |
| 対象者 | 特定の階層や役職 | 全従業員 | 組織全体 |
| 目的 | 個々の能力向上 | スキル向上による組織力の強化 | 組織全体のパフォーマンス向上 |
| 手法 | メンター制度やOJTなど | OJT、集合研修、自己啓発支援など | ワールドカフェ、AI、組織診断など |
人材育成と人材開発との違い
人材育成は、業務上必要なスキルを習得させ、組織の目標達成に向けて活用することが目的です。例えば、新入社員研修や管理職研修など、特定の階層や役職に応じ、一律の教育プログラムを実施するのが一般的です。
一方で、人材開発は全従業員を対象に、個人の潜在能力を開花させ、組織全体の競争力を高めることが目的です。例えば、OJTや集合研修、自己啓発支援などが該当します。

人材開発とは? 具体的な仕事内容や進め方、人材育成との違いを解説
企業成長につながる人材開発を効率的に実施できる!
人材情報を一元化してスキル管理をスムーズにするタレントマネジメントシステム「カオナビ」
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアク...
人材育成と組織開発との違い
人材育成が各従業員の能力向上に焦点を当てるのに対し、組織開発は組織全体のパフォーマンス向上が目的です。
例えば、人材育成では新入社員への研修プログラムを通じて個々のスキル向上を図りますが、組織開発ではチーム間のコミュニケーション改善やリーダーシップ強化など、組織全体の働き方改革を進めるのが特徴です。
組織開発では、「個人」ではなく「関係性」や「相互作用」に注目し、組織内の風土や構造を見直すことで成果向上を目指します。

組織開発とは? 人材開発との違い、手法と手順、事例を簡単に
人材育成がなかなか組織の活性化につながらないとお悩みではありませんか?
カオナビなら組織全体を見ながら、個々の適切な人材の育成が可能です。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp に...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.人材育成が必要な理由
人材育成が必要な理由は以下2つです。
- テクノロジーの進歩による市場の均質化
- 人材不足への対応
これらは人材育成の重要性を認識する上で、重要なポイントです。それぞれを詳しく解説します。
テクノロジーの進歩による市場の均質化
近年、テクノロジーの急速な進化により、企業間の製品やサービスの差別化が難しくなっています。
このような状況下で他社と差別化を図るためには、従業員一人ひとりのスキルや知識、創造性が重要となり、これが企業の競争力を左右すると言っても過言ではありません。
人材不足への対応
日本では少子高齢化の進行に伴い、労働力人口の減少が深刻な課題です。
新たな人材の確保が難しくなる中、既にいる従業員のスキルや能力をいかに発揮してもらうかが企業の成長や存続に直結します。
そのため、従業員一人ひとりの力を最大限に引き出すための人材育成が、以前にも増して重要になるでしょう。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
5.人材育成の問題と課題
多くの企業が人材育成に取り組む中で、以下のような課題に直面しています。
- 人材育成の優先度が低くなる
- 自律型の人材が育たない
- 指導できる人材が足りない
- 人材を育成しても辞めてしまう
人材育成の優先度が低くなる
日常業務の忙しさから人材育成が後回しにされている現場も少なくありません。
とりわけ短期的な業績向上が求められる現場では、教育や研修を行う時間の確保が難しく、結果として人材育成の優先度が下がる傾向があります。
また、コロナ禍以降のテレワークの普及により、対面でのコミュニケーションが減少し、若手社員の新たなスキル習得や能力向上のための指導の機会が減っている問題もあります。
自律型の人材が育たない
人材育成の課題のひとつが自律型の人材が思うように育たないという点です。
育成担当者や人事部が熱心に取り組んでも、従業員自身に学ぶ意欲がなければ、十分な成果は得られません。つまり、従業員が自ら考え、行動する自律性を養う必要があります。
自律型人材の育成には、責任ある仕事を任せたり自発的な学びを支援したりすることが重要です。また、自律型人材を育成する上で、上司や先輩のアドバイスは欠かせません。
部下や後輩が伸び悩んでいた場合、適切にフォローします。そのために、上司や先輩の立場にある人もコーチングスキルを磨くなど、指導方法を工夫しましょう。

コーチングとは? 意味、ビジネスでの効果、やり方を簡単に
コーチングは、運動や勉強、技術の指導において、学習や成長を促進するアプローチです。この方法は、クライアントの潜在能力に働きかけ、最大限に力を引き出すことを目的としています。単なる指導にとどまらず、相...
指導できる人材が足りない
人材育成を効果的に進めるためには、経験や知識を持った指導者の存在が必要不可欠です。
しかし、指導者となるべき管理職、または先輩社員に育成スキルや意識が不足していることもあり、管理職研修やマネジメント研修などが必要な企業も少なくありません。
また、現場が人材育成の重要性を認識していないケースも見られます。このような状況では、効果的な人材育成が難しくなるため、現場が人材育成に理解を示していない場合は、その重要性を認識してもらうところから始めないといけません。
人材を育成しても辞めてしまう
人材が定着せず、育成してもすぐに退職してしまう課題もあります。時間とコストをかけて育成した人材がスキルや経験を積んだ後に退職してしまうことは、企業にとって大きな損失です。
特に、育成した人材が競合他社に転職すると、投資したリソースが無駄になるだけでなく、競争力の低下にもつながります。
このような問題を防ぐためには、従業員のモチベーションを高め、組織への貢献を意識できるような取り組みを行い、帰属性を高めなければいけません。

モチベーションアップの方法は? 要素、理論、名言などを紹介
従業員のモチベーションを可視化し、不満や離職の原因を明らかに。
人材管理システム「カオナビ」で、従業員のエンゲージメントを向上!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.人材育成で大切なこと
効果的な人材育成を実現するためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 企業理念・経営戦略/経営層との連携を行う
- 目的を明確にして社内理解を得る
- 育成対象者の自主性を引き出す
- 長期的な育成計画を策定する
- 指導者側のスキル向上も並行して進める
- 従業員のモチベーション管理を行う
- 人材育成に関する制度を整備する
- 実践的な機会を提供する
- 人材データを活用し、従業員ごとに最適な支援を行う
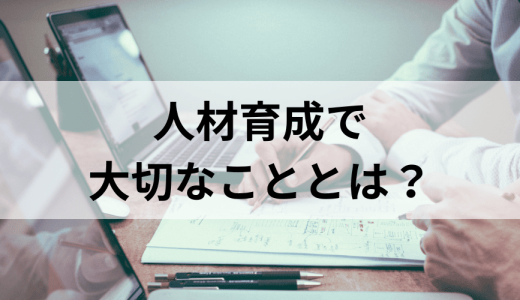
人材育成で大切なこととは? 手法やフレームワーク、スキルを解説
人材育成は企業の成長を促すために欠かせない取り組みです。
しかし、人材育成は簡単な取り組みではないため、さまざまな育成をおこなっているもののうまくいかないと悩む企業も少なくないでしょう。人材育成がうま...
企業理念・経営戦略/経営層との連携を行う
人材育成の視点は、従業員個人のスキル向上と成長だけではありません。
なぜなら、人材育成の本質は、企業理念・経営戦略の実現にあり、企業の理念や長期的な目標達成に貢献するかが重要です。
そのためには、経営層も連携して全社的に人材育成に取り組む必要があります。企業理念や経営戦略に精通しているのは経営層です。経営層と人材育成の方向がずれないよう、人材育成についての共通認識を築くことが大切です。
また、すべての部門が共通の意識を持って人材育成に取り組めるよう、部門間の連携を強化することも求められます。
目的を明確にして社内理解を得る
人材育成の目的を明確に定義して、それを組織全体で共有することが重要です。自社の課題や中長期計画を示しながら、育成のゴールを具体的に設定しましょう。
これにより、従業員のスキルアップ意欲を高め、組織全体で人材育成の重要性を認識できます。なお、目的を明確にする上で重要なポイントは以下の通りです。
- 定量的に評価できるようにする
- 期日を明確にする
- 企業の方針に基づいたものにする
従業員自身も納得できるような目的を設定する必要があります。
育成対象者の自主性を引き出す
従業員が主体的に学び、成長する姿勢を持つことは、人材育成の効果を高める上で欠かせません。
そのような自主性や自発性を養うためには、従業員が自ら目標を設定し、その達成に向けて行動できる環境を整えることが必要です。
さらに、従業員に自己啓発の機会を提供したり、チャレンジングなプロジェクトへの参加を促したりすることで、従業員の主体性を引き出せます。
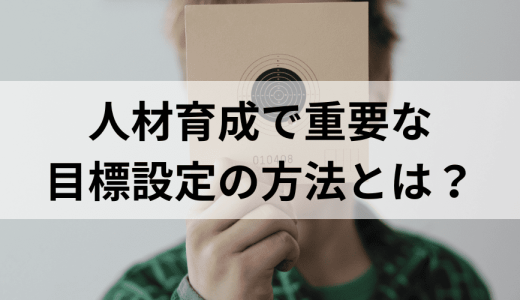
人材育成で重要な目標設定の方法とは? 手順やコツ、具体例を解説
企業の成長と従業員のスキル向上を実現するためには、適切な目標設定が欠かせません。目標を定めることで、企業の方向性が示され、従業員も自身の成長に向けた道筋を理解しやすくなります。
さらに、目標が明確であ...
長期的な育成計画を策定する
人材育成は短期的な視点だけでなく、中長期的な展望を持って計画を立てる必要があります。
企業の将来像や市場の変化を見据え、5年後、10年後に主力となる人材像を明確にし、それに向けた育成計画を策定しましょう。人材育成はすぐに実現できるものばかりではありません。

人材育成計画とは? 立て方、計画書の作り方とテンプレート
人材育成計画とは、将来的に活躍してくれる優秀人材を育成するための計画です。育成方針や求める人材像などをプランニングし、中長期的に取り組む人材育成の指針として活用されます。
今回は人材育成計画について、...
指導者側のスキル向上も並行して進める
人材育成を効果的に実践するためには、育成対象者だけではなく、指導者のスキル向上も平行して進めなければいけません。
育成担当者や管理職などの指導者が、適切な指導力やマネジメントスキルを持つことで、部下や後輩の成長をより効果的に支援できます。
そのため、指導者向けの研修やトレーニングを実施し、指導力の強化を図ることが求められます。具体的には、自分のペースで学習を進められる「eラーニング」の活用が有効です。
従業員のモチベーション管理を行う
自主性・自発性を養うことにも関連するのが、従業員のモチベーション管理です。モチベーションが低いと、従業員自身が人材育成に取り組む意欲が失われてしまいます。
モチベーション管理は、育成担当者の役目でもあります。人によってモチベーションを高める要素は異なるため、コミュニケーションを取りながらフォローしていくことが大切です。なお、モチベーションには「内発的」「外発的」の2種類あり、両方にアプローチする指導や施策を組み合わせることがポイントです。
| 内発的モチベーション | 外発的モチベーション | |
| 特徴 | 興味や好奇心、達成感など行動そのものから得られる満足感 | 行動の結果得られる外部からの刺激によって得られる満足感 |
| モチベーションが高まる例 | ・理想のキャリアの実現 ・やりたい仕事へのアサイン |
・給与アップ ・昇進、昇格 ・インセンティブ |
| メリット・デメリット | ・モチベーションの持続性が高い ・効果が出るまでに時間がかかり、モチベーションが上がっているかが見えにくい |
・短期的なモチベーションアップの効果が高い ・持続性が低い、自分でコントロールしにくい |

モチベーション管理とは? メリットや効果、高めるポイントを解説
モチベーション管理とは、社員のモチベーションを高めて生産性やパフォーマンスを向上させるための施策やプロセスのこと。メリットや社員のモチベーションを高めるポイントなどを解説します。
1.モチベーション...
人材育成に関する制度を整備する
安定した人材育成を行うには、それに関する制度の整備も大切です。従業員が成長しやすい環境を整えることは、自社の成長に直結します。
人材育成に関する制度の例
- 人事評価制度
- 研修制度
- OJT制度
- メンター制度
- ジョブローテーション制度
制度が整っていないと、従業員に「成長できる環境がない」「自分の会社は人材育成に消極的」といったネガティブな感情を持たれてしまうおそれがあります。最悪のケースでは離職に発展するため、要注意です。
実践的な機会を提供する
人材育成の効果を高めるには、学んだことをアウトプットできる実践的な機会を提供することも大切です。人材育成で行ってきたことを実際に業務に活かして成果を出せないと、意味がなくなってしまいます。
実践していく中で上司や先輩からアドバイスやフィードバックを得られれば、さらなる成長が促進されるでしょう。また、育成の効果検証にもなり、課題が見えれば次のアクションにもつなげられ、効率的な人材育成が可能となります。

人材育成とは? 目的や手法、大切なこと、取り組み方、成功事例を解説
人材育成とは、企業が業績を上げて経営目的を達成するために従業員を育成する取り組みをいいます。従業員を役職や職種、入社年数などで分けてグループごとにスキル習得を促します。
従来、人材育成は人事部や人材育...
人材データを活用し、従業員ごとに最適な支援を行う
人材育成の効果を最大化するためには、個々の社員の特性や成長段階に応じた最適な支援を行うことが大切です。人材データの活用で、各従業員の強みや弱みを明確にし、個別のニーズに応じた育成プランを策定しましょう。
ただし、本人の意見を取り入れ、柔軟に育成プログラムを調整できる環境を整える必要があります。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード7.【階層別】人材育成のポイント
人材育成で大切なこととして「階層別の育成」も挙げられます。従業員は階層によって求められるスキルや役割、スキルのレベルも異なるため、画一的な育成はできません。
ここでは「新入社員・若手社員」「中堅社員」「管理職」の3つの階層別に人材育成のポイントをご紹介します。
新入社員・若手社員
新入社員・若手社員の人材育成のポイントは、土台作りです。とくに、新入社員はビジネスパーソンとしての知識やスキルをこれから身につけていく段階にあります。
ビジネスパーソンとしての基本を育成しつつ、企業文化の理解やキャリア意識の醸成が人材育成の軸となります。
新入社員・若手社員の人材育成のポイント
- ビジネスマナーの習得
- 業界や自社の構造の理解
- 業務に必要な知識・スキルの習得・向上
- 経営理念の理解
- 従業員それぞれの役割の理解
- キャリアプランの作成
中堅社員
中堅社員に明確な定義はありませんが、一般的には入社4〜10年目の社員が該当します。組織や業務に慣れて役職を持ったり、管理職候補に抜擢され始めたりする段階です。
育成担当者として、新入社員や若手社員の育成に携わる段階でもあるでしょう。中堅社員は企業の将来を担う重要な存在です。以下のようなポイントから人材育成に取り組むことが大切になります。
中堅社員の人材育成のポイント
- 組織の中枢、企業の将来を担っていることの自覚
- 育成担当者に必要なスキルの向上
- マネジメントスキルの習得
管理職
管理職は、部下を指揮・管理し、組織の運営にあたるポジションです。リーダーとして組織を引っ張っていく立場であり、経営層と現場をつなぐ役割も持ちます。
管理職は求められるスキルが高度であるため、経営層が育成担当となる、あるいは外部の研修を受講する方法が一般的となります。育成されるよりも、実際のマネジメントや自己啓発を通じて自ら学んでいくことも多くなるため、自己啓発を支援する環境を整えることもポイントです。
管理職は評価者の立場になるため、評価スキルの育成も必要となります。
管理職の人材育成のポイント
- 経営視点の育成
- 組織マネジメント能力の向上
- 評価スキル、マネジメントスキルの向上
- ハラスメントへの理解
8.人材育成の手法
効果的な人材育成を実現するためには、様々な手法を理解し、適切に組み合わせて活用します。そこで、代表的な人材育成の手法が以下の通りです。それぞれを紹介します。
- OJT(On-the-Job Training)
- Off-JT(Off-the-Job Training)
- 自己啓発
- eラーニング
- メンター制度
- ジョブローテーション
- 目標管理制度(MBO)
- 1on1ミーティング
OJT(On-the-Job Training)
OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務を通じて従業員に必要なスキルや知識を習得させる育成方法です。主に新入社員に対して、同じ部署の上司や先輩がマンツーマンで指導するのが一般的です。
実務を通じて学ぶことで、業務に直結するスキルや知識が習得でき、即戦力の育成が期待できます。個々の能力や進捗に応じた指導が可能であり、それぞれに合わせた能力向上に向いています。

OJTとは? 意味や目的、メリット、進め方、OFF-JTとの違いを簡単に
OJT(On the Job Training)は、実際の業務を通じて従業員を育成する方法として、多くの企業で採用されています。
座学では学びきれない実践的なスキルを習得できるのが特徴で、新入社員や異...
Off-JT(Off-the-Job Training)
Off-JT(Off-the-Job Training)は、職場を離れて行う研修やセミナーのことです。具体例は、外部の専門家や講師による講義やワークショップ、オンライン研修などです。
これは、体系的な知識の習得や、業務では得られない新しい視点の獲得に最適です。複数の従業員が同時に受講できるため、共通の理解を得られます。また、普段はあまり関わりのない同僚と交流を図れる機会にもなります。

OFF‐JTとは|OJTとの違い、メリットや具体例などを紹介
人材情報から戦略的育成を!
カオナビならOFFJTなどの研修履歴がわかるから、計画的な人材育成ができます。
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロー...
自己啓発
自己啓発は、従業員自身が主体的に学習やスキルアップを行う方法です。書籍、通信教育、資格取得、セミナー参加など、多様な方法があります。
企業は、自己啓発を支援するために、学習費用の補助や情報提供を行うことが効果的です。それにより、従業員の自主性やモチベーションの向上、キャリア形成の促進につながります。
特に、資格取得は、資格によって手当をつけて給与をアップさせることで積極的な姿勢を促せるでしょう。ただし、相応のコストがかかるため、予算や人材育成目標に確実につながるかを勘案して導入を検討する必要があります。
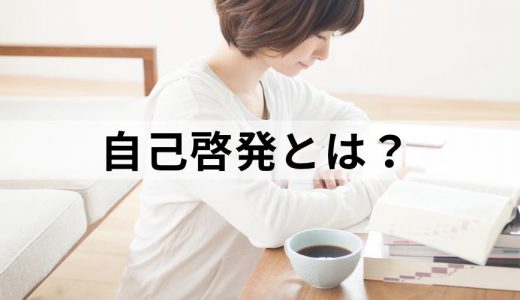
自己啓発とは? 意味や仕事での効果、やり方や具体例を簡単に
自己啓発とは、自分に本来備わっている能力を伸ばすために行う行為のこと。
自己啓発では、精神的な成長を促して、
より高い能力
より大きい成功
より充実した生き方
より優れた人格
などを目指していきま...
eラーニング
eラーニングは、インターネットを活用したオンライン学習方法です。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから受講でき、時間や場所にとらわれず自分のペースで学習できるため、忙しい従業員にも適しています。
共通の教材を使うことで、教育の質を均一化できます。また、複数人が同時に受講する場合、1人あたりのコスト削減が可能です。ただし、自己管理が求められ、学習意欲の維持が課題となる場合もあります。

eラーニングとは|システム、導入事例、導入時のポイントなど
eラーニングとは、インターネットを通して学習や研修を行う方法のこと。インターネットの普及とともに、企業の教育施策に取り入れられるようになりきました。
eラーニングとは何か
eラーニングの種類
eラー...
メンター制度
メンター制度は、新入社員や若手社員に対して先輩社員が指導役となり、仕事上だけでなく精神面でもサポートする取り組みです。新人のスキル定着やキャリア形成を促進するだけではなく、新人とメンター双方の成長につながる点が魅力です。
ただし、指導する先輩社員のスキルによって成長度に差が出ることや、相性の問題が生じる可能性があります。

メンター制度とは? メリット・デメリット、成功事例を簡単に
メンター制度を運用するための、従業員情報を管理できていますか?
タレントマネジメントを行うことで、人員管理を効率化できます!
⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
...
ジョブローテーション
ジョブローテーションは単なる人事異動ではなく、計画的な人材育成の一環として実施される配置転換です。
従業員を計画的に異なる部署や職務に異動させ、幅広い経験やスキルを習得させます。その結果、従業員は多角的な視野を持ち、組織全体の理解を深められます。
さらに、社内の異なる部署間でのネットワークを形成でき、協働性を高めることが期待できます。

ジョブローテーションとは?【意味を解説】メリット、何年
期末の度に人材の配置にお悩みではありませんか?
人件費やスキル値を確認しながらローテーション計画が立てられます
⇒人材配置計画が得意な「カオナビ」の資料を見てみる
ジョブローテーションとは、職場や職種...
目標管理制度(MBO)
目標管理制度は、従業員一人ひとりが目標を設定し、その達成度を評価する手法です。企業が一方的に評価するのではなく、個人が自ら設定した目標を上司とすり合わせるところがポイントです。
従業員は自らの目標に向けて主体的に行動し、達成状況に応じて評価や報酬が決定されます。その結果、従業員の自主性や責任感を高め、組織全体の目標達成に貢献する意識の芽生えが期待できます。

目標管理制度(MBO)とは? 意味や目的、メリット・デメリット、導入方法を簡単に解説
面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決
クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に行う1対1の面談です。部下の成長促進や上司との信頼関係構築が主な目的です。
単なる業務報告の場にするのではなく、部下の自主性を育み、能力やモチベーションの向上を図るように取り組む必要があります。
例えば、上司は部下の業務上の課題やキャリアに関する悩みを聞き、それに対する適切なフィードバックを行うことで、部下の成長をサポートします。
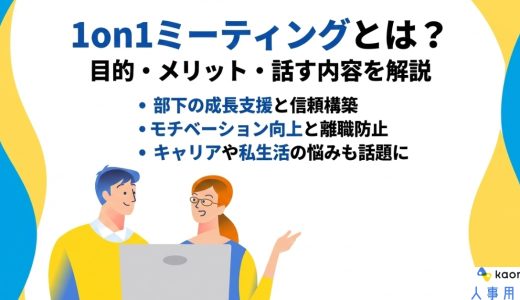
1on1とは? 目的とやり方、メリットや話すことがなくても失敗しない方法を解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
現在では多くの企業が導入する1on1とは、上司と部下が定期的...
9.人材育成で役立つフレームワーク
人材育成を効果的に進めるためには、適切なフレームワークの活用が欠かせません。代表的なフレームワークは以下の通りです。
- カッツモデル
- ギャップ分析
- 7:2:1モデル
- コルブの経験学習モデル
- HPI(ヒューマンパフォーマンスインプルーブメント)
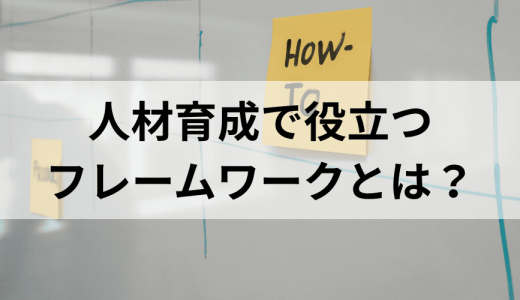
人材育成で役立つフレームワークとは? 活用の手順やポイントも解説
企業の成長と競争力強化には、人材育成が欠かせません。しかし、効果的な育成を実現するには、体系的なアプローチが必要です。そこで役立つのが「フレームワーク」です。
フレームワークの活用によって、育成の方向...
カッツモデル
カッツモデルは、組織内の各階層に求められるスキルを示したフレームワークです。アメリカの経済学者ロバート・カッツ氏によって提唱されました。
このモデルでは、テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルの3つのスキルに焦点を当てています。
- テクニカルスキル:専門的な知識や技術で主に現場で重視される
- ヒューマンスキル:対人関係能力やコミュニケーション能力で中間管理職に求められる
- コンセプチュアルスキル:全体を俯瞰して戦略的に考える能力で上級管理職に求められる
カッツモデルの活用によって、各従業員の現在の役職や将来のキャリアパスに応じた、上記3つのスキルをバランスよく育成できます。
役職に連動して身につけたい能力がわかるため、トップダウン型組織で教育効果が出やすいとされています。

カッツモデルとは? 3つのスキルや人材育成への活用方法を解説
カッツモデルとは、ビジネスパーソンに必要とされる能力を階層別やスキル別に分類したフレームワークのことです。メリット、構成、活用方法などを解説します。
1.カッツモデルとは?
カッツモデルとは、階層別...
ギャップ分析
ギャップ分析は、現状と理想とのギャップを明確にし、そのギャップを埋めるための方策を考える手法です。現状の原因ではなく、理想との間にある「課題」に焦点を当てるところが特徴です。
例えば、「リーダーシップが不足している」という分析結果が出た場合、プロジェクトリーダーなどを経験させながら、裁量と責任を持たせるといった改善策が講じられます。
7:2:1モデル
7:2:1モデルは、人材が成長するために必要な要素の割合を示したフレームワークです。その割合は以下の通りです。
- 7割:実際の業務や経験からの学習
- 2割:他者からのフィードバックや指導
- 1割:研修やセミナーなどの形式的な学習
座学も人材育成には欠かせません。しかし、このモデルでは実践的な経験が成長のために最も必要な要素であると示しています。経験の積み重ねと適切なフィードバックを行いつつ、学習のバランスを取ることが大切です。
コルブの経験学習モデル
コルブの経験学習モデルは、アメリカの組織行動学者デービッド・コルブ氏が提唱した、経験を通じて学習するプロセスを説明するフレームワークです。
以下の通り4つの段階からなるサイクルで構成されており、これらを繰り返すことで効果的に学習ができます。
- 具体的経験:実際に経験を積む段階
- 内省的観察:経験を振り返り、観察する段階
- 抽象的概念化:経験から得た気づきを一般化する段階
- 能動的実験:学んだことを新たな状況に適用する段階
このモデルは、単に経験を積むだけではありません。経験した後にその経験を深く振り返り、そこから得た学びを概念化し、新たな状況で応用させます。このように継続的な成長を促進するところが特徴です。

経験学習とは? コルブの経験学習モデル、サイクル、具体例
経験学習とは、経験から学ぶ学習プロセスです。ここでは、経験学習についてさまざまなポイントから解説します。
1.経験学習とは?
経験学習とは、経験の中から学んだ内容を次に活かしていく学習のプロセスです...
HPI(ヒューマンパフォーマンスインプルーブメント)
HPI(ヒューマンパフォーマンスインプルーブメント)は、組織や人材の現状と課題を明確にし、人事施策のPDCAサイクルを継続的に実行するためのフレームワークです。以下のステップで構成されています。
- パフォーマンスの現状分析:現在のパフォーマンスを評価する
- 理想的なパフォーマンスとのギャップ特定:現状と理想の差を明確にする
- ギャップの原因分析:ギャップの原因を探る
- 改善策の策定:原因に対処するための施策を計画する
- 施策の実行と評価:計画した施策を実行し、その効果を評価する
このアプローチの特徴は、単なるスキルトレーニングにとどまらず、組織の構造や文化、経営計画など、パフォーマンスに影響を与えるあらゆる要因を考慮するところです。
これにより、組織の真の課題を特定し、最適な解決策を見出せます。

HPIとは? 【意味をわかりやすく】ODとの違い
HPI(ヒューマンパフォーマンスインプルーブメント)とは、Human Performance Improvementの略で、人材の現状から組織の課題を見出し、改善に向かって進める方法のことです。
ここ...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
10.人材育成で必要なスキル
人材育成では、人に教えるスキルだけでなく、以下のように幅広いスキルが必要です。
- コミュニケーションスキル
- リーダーシップ
- 論理的思考力
- 目標設定・管理スキル
人材育成で必要なスキルをおさえ、担当者の選定や育成に活用しましょう。
コミュニケーションスキル
コミュニケーションスキルは、人材育成に必須のスキルです。人材育成の効果と効率を高めるには、円滑なコミュニケーションが鍵となります。
ここでいうコミュニケーションスキルには、以下のようにさまざまなスキルが含まれます。
| 傾聴力 | 相手の話を注意深く聞いて理解したり、相手の気持ちに寄り添い、共感したりする力 |
| 伝達力 | 自分の考えや意図、必要な情報をわかりやすく伝える力 |
| 質問力 | 相手に考えさせるような質問を投げかけ、主体的な行動を促す力 |
| フィードバック力 | 相手の行動や成果に対して、具体的な評価や改善点を伝える力 |
| ティーチングスキル | 知識や経験が浅い人にわかりやすく教える力 |
| コーチングスキル | 相手の能力ややる気を引き出す力 |
リーダーシップ
リーダーシップは、目標達成に向けて部下を引っ張っていくスキルです。状況に応じて部下を励ましたり、厳しく指導したりして部下をリードすることは、育成において大切です。
リーダーシップにも、以下のようにさまざまな種類があります。
| 指示型 | 具体的な指示を示すタイプのリーダーシップ |
| 支援型 | 部下の状態に気遣い、配慮するタイプのリーダーシップ |
| 参加型 | 部下に意見を求める協働タイプのリーダーシップ |
| 達成志向型 | 高い目標を提示し、部下に努力を求めるタイプのリーダーシップ |
| 奉仕型 | 部下が求めるものを与えるタイプのリーダーシップ |
企業文化や状況に合わせて、適切なリーダーシップを取れるかが大切です。その人の性格や適性によってもリーダーシップは変わってくるため、自社が求めるリーダーシップを定義し、習得してもらうことが必要な場合もあります。

リーダーシップとは? 種類や理論、ある人の特徴、高め方を簡単に解説
従業員のリーダーシップを育成できていますか?
カオナビならスキルを可視化し、戦略的な育成プランが立案できます!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウ...
論理的思考力
人材育成には課題と結果、その原因が存在します。問題の本質を見抜き、根本的に解決してこそ目標達成と育成につながります。課題に基づく目標設定、目標達成のための育成手法を検討する際に論理的思考力が必要です。人材育成の一連のプロセスを論理的に考えられることで、人材育成の効果に期待できます。
目標設定・管理スキル
適切な目標を設定し、達成に向けてしっかり管理することもスキルの一つです。
目標設定は、人材育成の方向がぶれないため、そして従業員が主体的に取り組むために大切です。部下のレベルやキャリア志向などさまざまな要素をふまえ、適切な目標を設定することが求められます。また、設定した目標を達成に導くことも重要です。
達成進捗の確認やスケジュールの調整、必要に応じたフォローなどにより目標達成に向けて管理していく必要があります。目標を管理して適切なフォローを提供することは、部下のモチベーションを維持するためにも大切です。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード11.人材育成の取り組み方・計画の立て方
自社に適した人材を効果的に育成するためには、次のステップに沿って進めましょう。
- 自社の課題を把握する
- 従業員のスキルや能力を把握する
- 自社の戦略や目指す方向性を確認する
- 課題に適した解決方法を検討する
- 運用方法や仕組みを整える
①自社の課題を把握する
人材育成計画を立てる際は、まず自社が抱える課題を明確にすることが重要です。そのために、現場の声を聞き、従業員が直面している問題やスキル不足を洗い出しましょう。
例えば、ヒアリングやアンケート調査、スキルマップの作成などを活用して、現状のスキルセットと目標とのギャップを特定します。
課題を「人事部門だけ」の視点に限定せず、経営層や現場の従業員と連携して幅広い情報の収集を意識してください。
これらにより、従業員のスキルや知識、業務プロセス、組織文化などを評価し、自社の強みと弱みを特定します。
②従業員のスキルや能力を把握する
次に、各従業員の現在のスキルや能力を評価しましょう。
職業能力評価シートやスキルマップを活用し、個々の強みと課題を視覚的に整理します。それを使うことで従業員一人ひとりを評価できるだけではなく、組織全体の強みや弱みを客観視できます。

スキルマップとは? 目的や導入メリット、作り方や項目例を解説
社員のスキルを集約・見える化し、スキルマップ作成を簡単に。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、スキル管理の問題を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
③自社の戦略や目指す方向性を確認する
自社の課題を見つけた後は、それが本当に解決すべき重要なものかを見極めましょう。今後の戦略や事業の方向性にとって優先度の高いものかを評価し、必要であれば重点的に取り組みます。
④課題に適した解決方法を検討する
課題と目指す方向性が明確になったら、それに適した解決方法を検討します。具体的には、OJT、Off-JT、eラーニング、メンター制度など、多様な育成手法から最適なものを選びます。
例えば、新入社員向けにはOJTで実務スキルを習得させます。
一方、中堅社員にはリーダーシップ研修やジョブローテーションを活用して多角的な経験を積ませます。このような形で、階層ごとに異なるアプローチを取ることも検討するとよいでしょう。
ただし、解決方法を決める際は、現場の負担やコストパフォーマンスの十分な検討が求められます。
⑤運用方法や仕組みを整える
最終的には、人材育成計画を実行するための運用方法と仕組みを整えます。また、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を導入し、継続的な改善プロセスを組み込むことも重要です。
12.人材育成に成功している企業事例
人材育成に成功している企業事例を3つ挙げます。
- コスモシステム株式会社
- 大王電機株式会社
- サイバーエージェント
自社にも活かせる内容があるかもしれないため、ぜひ参考にしてください。
コスモシステム株式会社
コスモシステム株式会社は、全国各地で移動体通信基地局の建設工事をはじめ、自社製造品の開発・製造、設置工事まで幅広く手がけている企業です。
コスモシステム株式会社では、若手社員を長期的に育成するため、10年の期間を見据えた「人財育成プログラム」を導入しました。
ジョブローテーションを通じて多様な業務経験を積ませることで、技術的知識やコミュニケーション能力のバランスが取れた育成を目的としています。
「人財育成管理票」を作成し、各社員の異動履歴や取得資格、受講した研修内容などを詳細に記録し、どのようなスキルを持った人材か一目でわかるように管理しています。
さらに、従業員の目標達成度や取得資格のランクを評価基準とした「チャレンジプラン」という評価制度を運用しました。
これらの取り組みを効果的に運用するために、人材情報の一元管理が可能なツール「カオナビ」を導入しています。これにより、情報共有の効率化と柔軟な対応を実現し、長期的な視点での人材育成が可能になりました。
参照:「人材情報は「カオナビ」に集約。「導入ディレクション」の効果もあり、新入社員を長期スパンで育成するプロジェクトが進む」
大王電機株式会社
大王電機株式会社は、生産設備や検査装置の開発を行う企業です。技術者の世代交代と新事業展開に向けた人材育成に取り組んでおり、人材の採用・育成を中核に据え、経営理念、ビジョン、スローガンを体系的に整理しています。
具体的には、職務等級を設定し、等級ごとの役割を明確に定義しています。それを使って、若手技術者の育成とスキルの可視化を推進し、中堅社員向けの社内研修を強化しました。
また、社長自らが会社について語る場を設けることで、従業員が自社の理念や方針をより深く理解できる機会を提供しています。
これらにより、中期計画に沿って、人材の採用と育成を計画的に進められるようになりました。
さらに、ベテラン社員から若手社員への技術継承も、優先順位を考慮しながら体系的に実施しています。
参照:中小企業庁「中小企業・小規模事業者の人材活用事例集」
サイバーエージェント
サイバーエージェントは、インターネット広告代理店やメディア事業、ゲーム事業などを手がける日本のIT企業です。
サイバーエージェントでは、「決断経験が成長を促す」という考えのもと、主体的に判断し、自立して行動できる人材の育成を重視しています。
その一環として、現部署で1年以上勤務した社員が希望する部署への異動に挑戦できる「キャリチャレ」や、社内版転職サイト「キャリバー」など、独自の施策を実施しました。
また、内定者を含む全社員を対象に、新規事業案を募集する制度は、2004年から継続して運用されています。
将来の経営幹部候補となる人材の育成にも力を入れており、次世代リーダー育成プログラム「BREAK8」では、選抜された若手社員を対象に役員陣が特別講義を実施しました。
チャレンジする機会を積極的に与えることで、社員が主体性を持ちやすい環境を整えており、継続的な事業拡大の原動力となっています。
参照:サイバーエージェント「人材育成」
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

