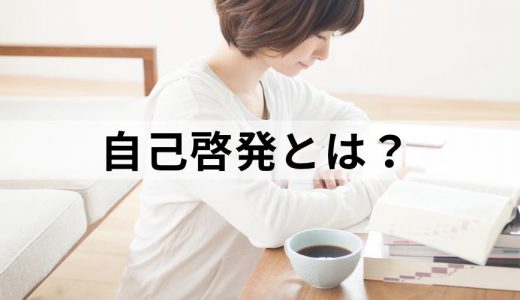企業成長につながる人材開発を効率的に実施できる!
人材情報を一元化してスキル管理をスムーズにするタレントマネジメントシステム「カオナビ」
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人材開発とは、社員一人ひとりのスキルや能力を高めて、最大のパフォーマンスを発揮させる取り組みのことです。
例えば、新人社員研修やメンター制度、リスキリングなどが挙げられます。短期的な視点だけではなく、中長期的なキャリア形成を見据えて行うことが重要です。
さらに、人材開発によって、企業理念やビジョンなどの価値観が共有でき、従業員のエンゲージメント向上にも期待ができます。
本記事では、人材開発と人材育成の違いや目的、人材開発が重要な理由などを解説します。人材開発の基本を確認し、効率的に業務を進めたい方、具体的な進め方を知りたい方はぜひお読みください。
目次
戦略的な人材開発をサポートする「カオナビ」の資料を見てみる⇒こちらから
1.人材開発とは?
人材開発とは、企業が従業員のスキルや能力を向上させ、組織全体のパフォーマンスを高めるための取り組みのことです。組織全体の生産性向上を目的としているため、一部の従業員だけではなく、全従業員を対象に実施します。
これらを効率的に行うことで、モチベーションの向上や組織への帰属意識の強化にもつながります。
2.人材開発と人材育成の違い
人材開発と人材育成には、従業員のスキル向上を図り、組織の成長を促進するという共通点がありますが、目的や実施のタイミング、対象、期間などに違いがあります。
人材開発は、組織の目標達成を支援するために、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出すことを目的としており、すべての従業員を対象とし、実践的なプログラムを実施するところが特徴です。
一方、人材育成は、業務遂行に必要なスキルや知識を習得させるために、企業が主体となって従業員に学習を促す取り組みをいいます。職種や役職、キャリアステージに応じて施策が分けられることが多いです。
それぞれの特徴を表にまとめると、以下の通りです。
| 人材開発 | 人材育成 | |
| 対象者 | 全従業員 | 特定の階層や役職 |
| 目的 | 組織の目標達成に向けた個々の能力向上 | 業務に求められるスキルや知識の取得 |
| 期間 | 比較的、短期 | 長期 |

人材育成とは? 基本の考え方や育成方法、具体例をわかりやすく
従業員個々のパフォーマンスを最大化し、経営目標の達成から企業の成長・発展へと導くには、人材育成が欠かせません。しかし人材育成にはさまざまな手法があるため、どのように自社で実践していけばよいか迷ってしま...
人材開発するにあたって、従業員のスキルを把握・管理する必要があります。クラウド型のデータベースを導入すると、スキルをはじめとした人材情報の一元化&見える化が可能に。戦略的な人材開発ができるだけでなく、適材適所な人材配置にも活用できます。
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
3.人材開発の目的
人材開発の目的は以下の通りです。
- 新入社員の早期戦力化
- 組織が求める人材の育成
- 経営戦略の実現
これらは組織力を高めるために重要なポイントです。それぞれを詳しく解説します。
新入社員の早期戦力化
人材開発の目的のひとつが新入社員の早期戦力化です。新入社員を迅速に組織の戦力として活用することは、企業の競争力維持・向上において非常に重要となります。
これを実現するためには、効果的なオンボーディングプログラムの実施が不可欠です。具体的には、メンター制度や1on1によるフィードバックを活用し、継続的かつ実践的なOJTを行うことが挙げられます。
OJTでは、実務を通じて必要な知識やスキルを身につけられるため、早期に即戦力としての活躍が期待できます。
組織が求める人材の育成
人材開発は、組織が求める人材の育成を目的として行われます。企業のビジョンや戦略を実現するためには、リーダーシップや専門的なスキルを持つ人材の育成が必要です。
そのためには、業界や職種に応じた専門知識やスキルを習得するためのOJTを活用したり、将来の管理職や経営層を育成するためのプログラムの実施などを行います。
適性のある人材を選択し、マネジメントスキルを早期習得させることは計画的な次世代リーダーの育成につながります。

経営戦略の実現
人材開発には、企業の経営戦略を実現するという目的もあります。経営戦略の実現には、一律の教育施策ではなく、個々の従業員に最適化された育成プログラムを導入することが必要です。
これらを通して、個人の能力を最大限に引き出し、主体的な学びを促進するアプローチを取ります。
その結果、従業員は企業から一方的に指示されるのではなく、自発的に成長できるようになり、モチベーションを高めながら経営目標の達成を目指すようになります。
タレントマネジメントシステムを導入すると、一元化した人材情報を人事・経営・現場でスムーズに共有可能に。組織の潜在能力の最大化に貢献する、タレントマネジメントシステム「カオナビ」のPDF資料を無料ダウンロード ⇒こちらから
4.人材開発が重要な理由
人材開発が重要視される理由は、以下などが挙げられます。
- 社会環境の変化に適応
- DXを推進できる組織の確立
- 価値観の多様化への対応
社会環境の変化に適応
現代社会は、技術革新やグローバル化の進展により急速な変化を遂げており、企業を取り巻く市場環境も絶えず変動しています。
これらに適応するためには、従業員が意欲を持って新しい知識やスキルを継続的に学ぶことが求められます。人材開発を通じて多様なスキルを備えた人材を育成し、変化に柔軟に対応できる組織を構築することが大切です。
DXを推進できる組織の確立
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業の競争力強化に不可欠です。DXを成功させるためには、従業員一人ひとりのデジタルリテラシーの向上や推進できる人材の育成が欠かせません。
人材開発を通じて、デジタルスキルを持つ人材を育成することで、DXを推進できる組織体制を構築します。
価値観の多様化への対応
従業員の価値観やキャリア観は多様化しており、ワークライフバランスを重視したい人や将来は起業したい人など様々で、一律の教育や研修では対応しきれない状況になりつつあります。
人材開発は、個々の従業員のニーズや目標に応じた柔軟な学習機会を提供することで、モチベーション向上や離職防止の役割を担っています。人材開発では個人支援が原則です。つまり、従業員一人ひとりの価値観や目標とするキャリアに応じて、成長の機会の提供が必要とされます。
タレントマネジメントシステムを導入すると、人材情報の見える化だけでなく評価運用や人材育成にも大いに活用できます。誰でもカンタンな操作感が人気のタレントマネジメントシステム「カオナビ」のPDF資料を無料ダウンロード ⇒こちらから
5.人材開発の仕事内容
人材開発の部署では、具体的にどのような業務を行うか気になる方もいるかもしれません。主な業務は以下の通りです。
- 教育・研修制度の企画・設計
- 研修の実施・運営
- 自己啓発の支援
- 育成担当者へのサポート
教育・研修制度の企画・設計
人材開発担当者は、組織の目標や戦略に沿って、従業員のスキルや知識を向上させるための教育・研修制度を企画および設計します。具体的には、研修の目的設定、カリキュラムの構築、教材の選定などです。
集合研修やオンライン学習、OJTなど、様々な手法を組み合わせて効果的な学習環境を提供します。
研修の実施・運営
企画および設計された研修を実際に実施・運営することも、人材開発の業務のひとつです。研修のスケジュール調整や講師の手配、参加者の管理、研修効果の評価など、多岐にわたるタスクを遂行します。
研修が円滑に進行し、従業員の成長につながるようサポートすることが重要です。
自己啓発の支援
人材開発担当者は、従業員が自主的に学習やスキルアップに取り組むために自己啓発を支援しなければいけません。具体的には、資格取得支援制度の導入や、学習意欲を高めるための環境整備などが挙げられます。
これにより、従業員のモチベーション向上だけではなく、組織全体の学習文化の醸成が期待できます。
育成担当者へのサポート
現場で従業員の指導および育成を担当するマネージャーやリーダーに、効果的な指導方法やコーチング技術、評価の仕方など習得してもらうためのサポートも重要です。
具体的には、マネージャーやリーダー自身の指導力を高めるための研修や、育成計画作成の支援などが挙げられます。
6.人材開発で効果的な手法
人材開発は、効果的な手法を適切に選択し、バランスよく組み合わせることが重要です。代表的な6つの手法について詳しく説明します。
- OJT(On-the-Job Training)
- Off-JT(Off-the-Job Training)
- 自己啓発支援
- 1on1ミーティング
- eラーニング
- タフアサインメント
OJT(On-the-Job Training)
OJT(On-the-Job Training)とは、実際の業務を通じて従業員の能力を高める教育方法のことです。
上司や先輩社員が指導者となり、日常業務の中で具体的なスキルや知識を習得してもらいます。実践的な能力が身につきやすく、業務への適応もスムーズに進むのが特徴です。
ただし、新入社員や若手社員向けのOJTは体系的に整備されている企業が多い一方で、中途採用者向けのプログラムが未整備の企業も少なくありません。さらに、指導者のスキルや指導方法によって効果が左右されるため、指導者自身の育成も求められます。
Off-JT(Off-the-Job Training)
Off-JT(Off-the-Job Training)とは、日常業務以外で行う研修やセミナーのことです。集合研修やセミナー、ワークショップなどの形式で実施されることが多く、新入社員向け研修や管理職研修などが代表的な例です。
体系的な知識や理論を学ぶのに適しており、人材育成の場面で頻繁に活用されます。
外部講師を招くことで、自社にはないノウハウや業界の最新トレンド、専門知識を学べる機会になります。
自己啓発支援
自己啓発支援とは、従業員の自主的な学習意欲を促進し、サポートする取り組みのことです。企業には、業務関連の資格取得や通信講座の受講料補助、学習のための時間確保など、従業員の自己啓発を促進する環境作りが求められます。
ただし、本人任せにしてはいけません。定期的な1on1ミーティングを実施し、適切なフォローアップを行うことが大切です。
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に一対一で行うミーティングのことです。業務の進捗確認や課題の共有、キャリア相談などを通じて、従業員の成長をサポートします。
定期的なコミュニケーションにより、信頼を深めて相談しやすい関係性を築く効果も期待できます。
1on1ミーティングでは、テーマを明確にし、双方が考えを整理してから臨むことで、より密度の濃い対話が可能です。
eラーニング
eラーニングとは、インターネットを活用した学習方法のことで、時間や場所を問わず学習できる柔軟性が特徴です。ビジネスマナーや語学など、多様なコンテンツが充実しており、従業員は自分のペースで学習を進められます。
紙の教材とは異なり、画像や音声なども活用して学習を進められるのが魅力のひとつです。さらに、進捗状況の管理や効果測定も容易で、効率的な人材育成が可能です。
タフアサインメント
タフアサインメントとは、従業員にとって挑戦的な業務やプロジェクトを任せて、能力開発を促進する手法のことです。高い目標や困難な課題に取り組むことで、問題解決能力やリーダーシップなどが鍛えられ、さらなる成長意欲につながります。
例えば、マネージャーやプロジェクトリーダーなど、他の従業員を支援する役割を与えることで、学びの機会を提供するケースもあります。
ただし、過度な負担はストレスによる休職や退職につながるリスクもあるため、日常的なコミュニケーションを密に取りながら、状況を丁寧に見守ることが重要です。
7.人材開発の進め方
人材開発を進める時は、まず組織が抱える課題やニーズを明確にし、求める人材像を具体的に定めます。その上で、OJT、Off-JT、自己啓発などの育成手法を効果的に組み合わせ、体系的な人材育成プログラムを構築する必要があります。
具体的な手順は以下の通りです。
- 現状を把握する
- 課題の抽出をする
- 求める人物像を確立する
- 必要なスキルを洗い出す
- 人材開発計画を立てる
- 実践・フィードバックを繰り返す
①現状を把握する
まず、組織内の人材に関する現状を正確に理解します。従業員の業績評価、スキル評価、従業員満足度調査などを活用し、組織全体の強みや弱みを明らかにしましょう。
例えば、タレントマネジメントシステムを導入することで、従業員の基本情報やスキルデータの収集・分析を一元管理し、効率的に運用します。これらの情報を総合的に分析することで、組織の人材に関する現状が把握できるでしょう。
②課題の抽出をする
現状把握ができたら、次は組織の課題を抽出します。課題抽出の視点は多岐にわたります。
例えば、以下のようなものです。
- 新入社員のビジネスマナー不足
- 中堅社員のマネジメントスキル不足
- 特定部署のパフォーマンス低下
- 従業員自身が感じている不満
- 外部環境の変化への対応力不足
課題抽出の際は、現場の声を丁寧に拾い上げることが重要です。ヒアリングを通じて、現場が直面している問題や改善したい点を洗い出しましょう。
ただし、すべての課題が人材開発で解決できるわけではありません。その他の方法で解決する方が適しているのではないかという視点も持ちつつ、見極める必要があります。
③求める人物像を確立する
課題が明確になったら、組織が目指すべき人材像を定義しましょう。求める人物像は、企業のビジョンや中長期的な経営戦略と結びつけて考えるのが適しています。
明確な基準を設定することで、育成の方向性が定まり、従業員も自身の課題や目標を理解しやすくなります。
④必要なスキルを選定する
次は、求める人物像に必要なスキルや知識を具体的にリストアップします。これにより、現状の従業員の能力と比較し、ギャップを特定することで、どの分野の育成が必要かを判断できるようになります。
リストアップした能力は、技術的スキル・ビジネススキル・ヒューマンスキルなど、カテゴリー別に整理してください。各スキルの重要度や優先順位をつけておくと、今後の人材開発を計画する上で役立ちます。
⑤人材開発計画を立てる
人材開発計画を立てて、特定したギャップを埋めるための具体的な育成計画を策定しましょう。
計画する際は、以下の点を明確にするのが重要です。
- 実施の対象
- 目標
- 研修プログラムの内容
- 実施方法
- スケジュール
- 予算配分
- 責任者
各従業員の現在のスキルレベルやキャリア志向も考慮に入れ、個別の育成計画を併せて作成することも効果的です。
⑥実践・フィードバックを繰り返す
次は、実践およびフィードバックを繰り返しましょう。人材開発の実施後は、アンケートや面談、理解力テストを実施して、その効果を評価し、必要に応じて改善を行います。
このサイクルを繰り返すことで、組織全体の人材開発の質を高められます。フィードバックを受けて気づいた課題を分析して、別のアプローチ方法がないか検討することも重要なプロセスです。
8.人材開発のポイント
人材開発を効果的に進めるためのポイントは以下の通りです。
- 実際の経営課題と結びつける
- 組織の理想像を明確に伝える
- 従業員のスキルレベルを把握する
- 内発的動機付けを引き出す
- 専門部署を設置する
- 人材開発担当者の専門性を高める
実際の経営課題と結びつける
人材開発の取り組みは、自社の経営課題や事業戦略と連動させる必要があります。そうすことで、従業員は学んだスキルや知識を実際の業務で活用でき、組織全体のパフォーマンス向上につながるのです。
これを実現するためには、人材開発担当者が経営層との綿密なコミュニケーションを図り、育成計画を策定することが求められます。
組織の理想像を明確に伝える
組織が大切にする理念や目指すビジョン、求める人材像を従業員に明確に伝えることは、育成の方向性を定める上で不可欠です。
組織の求める姿が現場に十分に浸透していなければ、従業員の自主的な学習意欲が高まりにくいでしょう。
そのために、組織が目指す方向性を明確に伝えた上で、従業員自身がそれに沿った目標を設定しながら学習を進められるように促しましょう。
従業員のスキルレベルを把握する
従業員のスキルを正確に把握しないまま、人材開発の目標や計画を策定すると、既に習得済みのスキルを再度研修で学ばせるなど、重複する可能性があります。これでは、効果的な人材開発が難しく、効率的ではありません。
その点、タレントマネジメントシステムなどを活用すれば、従業員が持つ能力や技術を事前に把握することが可能です。さらに、人材開発によるスキル向上の進捗も適切に管理できて、継続的な改善につなげられます。
内発的動機付けを引き出す
人材開発は、従業員が自ら成長したいと感じる内発的な動機を促すことが重要です。
しかし、企業や上司などからの一方的な支援にならないように注意が必要です。一方的に学習を強要されていると感じると、従業員のモチベーションが低下し、人材開発の効果が発揮されにくくなります。
個々の関心や成長意欲を考慮した研修プログラムの提供や、裁量権の付与などにより、従業員の自律性や意欲を高める環境を整えてください。従業員にどのような能力を高めたいか、丁寧にヒアリングすることも重要です。
専門部署を設置する
人材開発を組織的かつ継続的に推進するためには、専門部署の設置が効果的です。これにより、育成プログラムの企画および運営が円滑に進み、組織全体で一貫性のある育成が可能になります。
専門部署の担当者は、人材開発の業務に集中して取り組めるため、途中でトラブルが発生しても、素早く対応でき、迅速な改善が期待できます。
人材開発担当者の専門性を高める
人材開発を担当する人事やマネージャー自身のスキル向上も欠かせません。最新の育成手法や知識を習得し、効果的な指導やサポートを行えるよう、人材開発担当者自身にも研修や学習の機会を提供する必要があります。
学習を深めることにより、人材開発の研修プログラムや進め方がブラッシュアップされ、より効果的になります。
9.人材開発担当に必要なスキル
人材開発担当者には、組織の成長と競争力強化を支える重要な役割があります。その役割を果たすために、以下のようなスキルが必要です。
- 現状把握力
- 問題発見力・問題解決力
- 目標設定力
- 企画力
- 運営調整力
- ファシリテーションスキル
- コミュニケーション力
- リーダーシップスキル
- ロジカルシンキング
現状把握力
組織や従業員の現在の状況や能力を正確に理解する現状把握力は、適切な開発計画を立てるために欠かせません。
現場のニーズに合わない研修を実施すると、不要なコストが発生するだけでなく、従業員の研修に対する印象が悪化する恐れもあります。
現状把握力が高い人材開発担当者は、各部門の課題やニーズを的確に把握し、それに合った教育機会を提供できます。これにより、研修の効果が高まり、従業員の協力も得やすくなるでしょう。
問題発見力・問題解決力
問題発見力と問題解決力は、人材開発を効果的に進める上で不可欠です。
問題発見力があれば、表面的な課題だけでなく、根本的な原因の特定ができます。また、問題解決力があれば、様々な選択肢の中から最適な解決策を選び、実行に移せます。
これらのスキルを磨くには、日頃から批判的思考を心がけ、様々な角度から物事を見る習慣をつけることが重要です。
目標設定力
目標設定力は、人材開発の方向性を定め、適切に効果を測定する上で重要なことです。組織の長期的なビジョンと現状のギャップを分析し、具体的かつ達成可能な目標を設定する能力が求められます。
適切な目標設定は、従業員の成長意欲を高め、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
目標設定の際は、SMARTの原則を意識し、明確で測定可能な目標を立てることが効果的です。
なお、SMARTの原則とは、以下の頭文字を取ったものです。
- Specific(具体的な)
- Measurable(測定可能な)
- Achievable(達成可能な)
- Relevant(関連性のある)
- Time-bound(期限が明確な)
具体的に目標を設定することで、フィードバックや改善がしやすくなります。
企画力
目標達成に向けて、効果的な研修プログラムや育成施策を企画および立案する企画力も人材開発施策を具体化する上で不可欠です。
高い企画力があれば、組織のニーズに合った独自の人材開発プログラムを作り出せます。企画力を高めるには、常に新しい情報や事例に触れ、柔軟な発想を持つことが大切です。
また、他部門や外部の専門家との協働を通じて、多様な視点を取り入れることも効果があります。
運営調整力
運営調整力は、人材開発施策を円滑に実施するために必要なスキルです。研修やプログラムの実施にあたっては、様々な関係者との調整や、予期せぬ事態への柔軟な対応力が必要な場面もあります。
高い運営調整力があれば、研修の実施に伴う調整業務を円滑に進められ、無駄な労力やコストを省けます。運営調整力を磨くには、細部まで配慮しつつ全体を俯瞰する視点を持ち、臨機応変に対応する柔軟性を鍛えましょう。
ファシリテーションスキル
ファシリテーションとは、グループの相互作用を促進し、効果的な議論や意思決定を支援する能力のことです。研修を運営する際に、参加者が安心して意見を述べられる環境を作ります。
さらに、参加者の意見を引き出し、それらを整理および構造化する能力も不可欠です。参加者が自ら気づきを得られるよう支援し、研修後のフォローアップでも、学びの定着や実践につなげるためのファシリテーションが求められます。
コミュニケーション力
コミュニケーション力は、人材開発のあらゆる場面で必要とされます。従業員や経営層、外部講師など、様々な立場の人と効果的にコミュニケーションを取る能力が求められるためです。
高いコミュニケーション力があれば、研修の内容を分かりやすく伝えたり、部門間の協力を円滑に促せます。従業員の声に耳を傾け、ニーズを的確に把握する上でもコミュニケーション力は欠かせません。
リーダーシップスキル
リーダーシップスキルは、組織やチームを率いる上で重要です。チームメンバーの能力を最大限に引き出し、共通の目標に向かって導く能力が求められます。
人材開発においては、リーダーシップを発揮することで、従業員の潜在能力を引き出し、自主的な挑戦や自己啓発を促せます。
ロジカルシンキング
ロジカルシンキングは、物事を論理的に考え、整理および分析する能力のことです。人材開発の戦略立案や効果測定において、論理的に思考し、データに基づいた意思決定を行う際に重要になります。
さらに、人材開発の企画を伝える際にも、ロジカルシンキングは必要です。施策の目的やメリットを論理的に整理して説明できれば、社内の理解や賛同を得やすくなります。
10.人材開発の企業事例
人材開発に力を入れている企業の事例を紹介します。本記事で紹介する企業は以下の通りです。
- 株式会社イトーキ
- ソフトバンク株式会社
- 株式会社ニトリホールディングス
株式会社イトーキ
株式会社イトーキは、オフィス家具メーカーとして知られていますが、近年はワークスタイル・空間デザイン・製品・ソリューションのトータル提案を行う企業へと進化しています。
事業モデルの変化に伴い、2023年にタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入し、人材開発と人事業務の効率化を図りました。
導入の背景には、「強みを活かした育成の組織浸透」「社内コミュニケーション」などの課題があります。
カオナビを単なる人事システムではなく、社員のエンゲージメント向上のためのツールとして位置づけています。
面談や研修時のアイスブレイクとしてカオナビの情報を参照したり、自己PRのツールとして活用したりと、その使い方は様々です。
また、1on1面談のページを作成し、備忘録や異動時の引き継ぎ、業務分担の参考資料として活用するなど、育成の観点でも役立てる取り組みを進めています。
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社は、事業の多角化と急速な成長を背景に、人材開発に積極的に取り組んでいる企業です。
企業主導の画一的なキャリア開発や研修制度ではなく、従業員が自身のキャリア目標に応じて主体的に選択できる、「ソフトバンクユニバーシティ」という制度を整えています。
さらに、集合研修に加え、パソコン・スマートフォン・タブレットなどのマルチデバイスで受講可能なeラーニング、オンラインでの双方向型リアルタイム研修、アーカイブ動画配信など、ICTを活用したソフトバンク独自の学習スタイルが特徴です。
AIを活用できる人材の育成を目的に、AI関連の学習コンテンツを体系化した「AI Campus from SBU Tech」を2021年から展開しています。
2023年度には、計77コースの研修や学習機会を提供し、全従業員の29%にあたる6,156名が受講しており、自律型のキャリア開発を進めています。
参照:ソフトバンク株式会社「キャリア開発・能力発揮」
株式会社ニトリホールディングス
株式会社ニトリホールディングスは、企業の発展には従業員の成長が不可欠であると考え、意欲のあるすべての従業員に学習の機会を提供できるよう、従業員教育に力を入れている企業です。
「ニトリ大学」と呼ばれるニトリ独自の研修制度を設けています。配属前の全体研修をはじめ、1年目の新人研修、2年目・3年目の若手研修といった年次別のプログラムに加え、部署別・職位別研修まで、キャリアの各段階に応じた学習機会を提供しています。
「大学」と名付けられているのは、多彩なカリキュラムが用意され、受講を重ねることで段階的に成長できる仕組みになっているためです。
例えば、カリキュラムの1つである「未来会議」は、既成概念にとらわれない自由な発想で、新たな事業アイデアを経営陣へ提案できます。
提案内容は、「ニトリ研究所の設立による素材開発」「リペア事業への参入」「新規ブランドの展開」など、多岐にわたっており、その中から実現の可能性が高く優先度の高いものを選定し、検証を進めながら事業化を目指しているのです。
さらに、自主的にスキルアップに取り組み、成果を上げた従業員に対して教育マイレージを付与する「教育マイレージ制度」という制度を導入しています。
マイレージを貯めることで、アメリカでのセミナー参加や、検定・資格試験の受験料補助など、さらなる成長の機会として追加の支援を受けられる魅力的な内容です。
この研修制度を通じて、従業員は着実にスキルを磨き、専門性を高めながらキャリアを積み上げています。
参照:株式会社ニトリホールディングス「ニトリ独自のカリキュラム『ニトリ大学』」
人材開発にこんなお悩みをお持ちではないですか?
・従業員のスキル情報や研修履歴が管理できていない
・組織に不足している人材がわからない
・人材開発の方向性がわからない
・人材開発の成果が出ているのかわからない
\カオナビなら/
人材情報を一元化できるから、従業員の能力やスキル情報が一目瞭然!社内で不足している人材も見える化!一人ひとりに最適な人材開発プランの立案に活用可能!