労働基準法とは、労働条件について最低基準を定めた法律のこと。本記事では、労働基準法の概要や目的、対象とならないケースなどについて解説します。
目次
1.労働基準法とは?
労働基準法とは、1947年に制定された、労働条件に関する最低基準を定めた法律のこと。労働基準法をもとに内閣の政令「時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」や厚生労働省令「労働基準法施行規則」などが制定されています。
労働基準法の強行法規性(労基法第13条)とは?
労働基準法13条とは、労働基準法の基準に達しない労働契約は無効となる条件を定めている条文のこと。強行的直律的効力といわれるものであり、たとえ労働者が同意したうえでその労働条件を受け入れたとしても無効になります。
無効となる例
実際に労働基準法により、労働条件が無効になる例を紹介します。労働基準法では、1日の法定労働時間を8時間と定めており、8時間を超える労働に対しては時間外労働として割増賃金を支払わなければいけません。
たとえ1日の所定労働時間を10時間として労働契約を締結したとしても、8時間を超える労働は無効とみなされます。そのため、1日の労働時間は8時間(法定労働時間)+2時間(時間外労働)に修正されることになります。
2.労働基準法の目的
労働基準法の主な目的は、労働条件に最低基準を設定して労働者を保護すること。民法91条では「契約自由の原則」が適用されており、当事者は対等な立場であり、合意があれば自由に契約を締結できることが前提となっています。
しかし、実際のところ、労働契約では雇用する側である雇用者が有利になることが多いため、労働基準法を制定して労働者の保護を行っています。
3.労働基準法の対象になる労働者
労働基準法の対象は、他人を雇う事業者および雇われている人です。ただし、一部の労働者は対象外となっています。
適用されないケース
労働基準法が適用されないケースは以下のとおりです。
- 一部の船員
- 家族経営の事業で働く親族
- 家事使用人
- 一部の公務員
それぞれについて詳しく解説します。
一部の船員
一部の船員は、労働基準法の対象外です。
原則、労働基準法の規定は船員にも適用されます。しかし一部の条件(5トン未満の船舶や、漁業に使われる船舶など)に該当する船舶の船員に対しては、労働契約や労働時間などの重要な規定を除外しているのです。
ただし、除外された船員の労働条件には船員法を適用させて、労働者の保護を行っています。
家族経営の事業で働く親族
労働者が同居親族のみの場合は、労働基準法が適用されません。ただし同居親族ではない他の労働者を雇用する場合は労働基準法が適用されます。
「同居」とは、住居と生計が同一の状態のことで、「親族」とは、民法上の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)を指します。
家事使用人
家事使用人も労働基準法の対象外です。家事使用人とは、いわゆるお手伝いさんのように家庭内で家事全般に従事する人のこと。
雇用主が一般の個人の場合、家事使用人は労働基準法の適用外となり、適用外は社会保険などの保障が受けられません。しかし、家事サービス代行会社などで雇われる場合は労働基準法が適用されます。
一部の公務員
国家公務員は、原則として、労働基準法や労働契約法などの対象外です。ただし、一般職の国家公務員には労働基準法が適用されます。知事や市町村長、議員など特別職に該当する地方公務員は、地方公務員法第58条に該当しません。そのため、労働基準法が適用されます。
4.労働基準法の主な内容一覧
労働基準法では、労働契約において生じる労働者の権利と雇用者の義務を全13章でまとめています。主な内容は以下のとおりです。
- 労働条件の明示(労基法第15条)
- 解雇の予告(労基法20条)
- 賃金支払いの4原則(労基法24条)
- 労働時間の原則(労基法32条)
- 休憩(労基法34条)
- 休日(労基法35条)
- 時間外および休日の労働(労基法36条)
- 時間外、休日および深夜労働の割増賃金(労基法37条)
- 年次有給休暇(労基法39条)
- 就業規則(労基法89条)
- 制裁規定の制限(労基法91条)
- 周知義務(労基法106条)
- 労働者名簿の作成(労基法107条)
- 賃金台帳の作成(労基法108条)
- 労働関係に関する重要な記録の保存(労基法109条)
①労働条件の明示(労基法15条)
第15条では、使用者は労働者と労働契約を締結するにあたり、当該労働者に対して、賃金や労働時間、その他厚生労働省令で定める労働条件について、明示しなければならないとされています。
目的は、雇用契約締結後の労使トラブルを防止し、労働者を保護すること。労働条件の明示を怠った雇用主に対しては、30万円以下の罰金刑が科されることもあります。
労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約の解除が可能です。
必ず明示しなければならない項目
必ず労働条件を明示しなければならない項目は14あります。
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰および制裁に関する事項
- 休職に関する事項
上記のうち、①~⑥は書面での交付が必須です。ただし、⑦以降は社内に関連する定めがない場合は明示する必要がありません。
明示事項の追加(2024年4月から)
2023年3月30日に改正省令が告示され、2024年4月1日以降の労働契約に関しては、明示しなければならない項目が増えます。その内容は以下のとおりです。
- 全労働者に対して、就業場所・業務内容における雇用後の変更の範囲を明示する
- 有期契約労働者に対して、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件を明示する
まず、全労働者に対して、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務内容の範囲も明示する必要があります。
また、有期契約労働者に対して、更新上限の有無と内容の明示が必要です。有期契約労働者の契約期間が長期間になることを避けるために、雇用者が有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限を設定することがあります。
それ自体は違法となるものではないと解釈されているものの、更新回数の上限に関する認識のずれからトラブルに発展する恐れがあるため、あらかじめ明示しておく、という考えになりました。
あわせて雇用者は、無期転換申込機会(期間の定めがない労働条件に転換する機会)や無期転換後の労働条件についても説明する必要性があります。
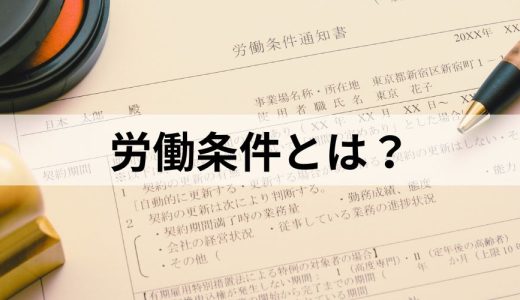
労働条件とは? 明示義務、明示事項一覧、変更について簡単に
労働条件とは、賃金や就業時間、就業場所などの働く上でのあらゆる取り決めのことです。労働条件は雇用する労働者に対して明示義務があり、明示する内容には定めがあります。違反した場合には罰金が科されるものもあ...
②解雇の予告(労基法20条)
使用者は労働者を解雇しようとする場合、
- 少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならない
- 30日前に解雇の予告をしない場合には、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならない
のです。
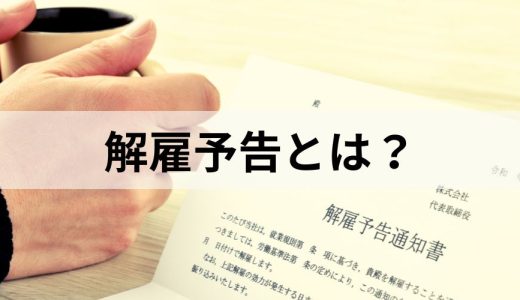
解雇予告とは? 手続きや注意点、手当の計算法をわかりやすく
解雇予告とは、従業員を即時解雇せず、あらかじめ解雇日を伝える手続きのこと。本記事では、解雇予告と即時解雇との違いや解雇予告が必要ないケース、解雇予告手当などについて解説します。
1.解雇予告とは?
...
解雇予告に関する注意点
労働基準法第20条は解雇のための手続きを定めたものですが、それに従い解雇予告をしても解雇事由が、客観的、合理的な理由を欠いている場合、当該解雇は無効になります。
ただし、
- 天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能
- 労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇
の場合、労働基準法第20条の限りではないとされています。
解雇制限
次のケースの場合は解雇制限があり、一定の期間は解雇できません。
- 業務上のケガや病気が原因で休業する期間とその後30日間
- 産前産後の女性が休業する期間とその後30日間

解雇制限とは?【解雇できる?できない?条件まとめ】
致し方ない事情があって労働者を解雇したい、そう思っても急に解雇することはできません。なぜなら、突然解雇されては労働者の生活に支障が出るからです。また、すぐに勤め先を探せない場合もあります。解雇制限は労...
③賃金支払いの4原則(労基法24条)
賃金支払い4原則とは、下記のようなものです。
- 賃金を通貨で支払う、通貨支払の原則
- 賃金は直接労働者に支払う、直接払いの原則
- 賃金はその全額を支払う、全額払いの原則
- 賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払う、毎月1回以上一定期日払の原則
ただし、法令や労働協約に別段の定めがある場合など一定の条件が整った場合には、
- 通貨以外のもので支払う
- 賃金の一部を控除して支払う
などの取り扱いが可能となります。
賃金全額払原則に関する注意点
賃金全額払原則の注意点は、使用者が労働者に賃金を支払う際、賃金と当該労働者に対する債務を相殺すること。労働基準法では賃金と債務の相殺は、賃金全額払原則に違反する行為となっています。
④労働時間の原則(労基法32条)
労働時間の原則とは、下記のようなものです。
- 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない
- 使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない
働き方改革の影響もあり、さまざまな働き方を導入する企業が増えてきました。このような背景もあって、労働基準法第32条、労働時間の原則には例外があります。たとえば下記のようなものです。
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- みなし労働時間制
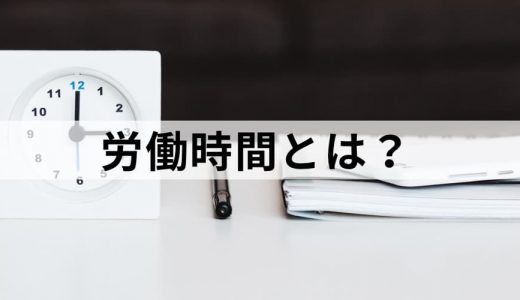
労働時間とは? 労働基準法の定義、上限、計算方法を解説
就職や転職を考える際、気になることのひとつが「労働時間」です。働き方スタイルが見直される昨今、労働時間は重要なキーワードになっていますが、実際どういったものなのでしょうか?
ここでは
労働基準法にお...
変形労働時間制
変形労働時間制とは、労働基準法32条にもとづいていて定められた制度のこと。
月や年単位で労働時間を調整し、繁忙期に時間外労働扱いを回避するためのもの。法定労働時間を超えた場合は残業代を支払う必要があり、教職員など長期休暇のある職種でも適用が検討されています。

変形労働時間制とは? メリット、導入方法、残業代は?
一般的に企業では就業時間が固定されています。それに対して労働時間を繁忙期や閑散期に合わせて調整できる勤務体系を「変形労働時間制」と呼ぶのです。
ここでは、労働者と企業、共にメリットがある制度として注目...
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、期間内に総労働時間を達成すれば、労働者が日々の勤務時間と始業・終業時刻を自由に選択できる制度のこと。こちらも、労働基準法32条にもとづいて定められました。

フレックスタイム制とは?【どんな制度?】ずるい?
フレックスタイム制とは、従業員が始業・終業時刻などの労働時間を自ら決められる勤務体系のことです。
目的、導入率、メリット・デメリット、働き方改革関連法による新フレックスタイム制、導入方法などについて紹...
みなし労働時間制
みなし労働制度とは、実際の労働時間とは関係なく、事前に決められた労働時間を働いたとみなす制度のこと。
労働時間の管理が難しい場合や高いパフォーマンスが期待される場合において適用されるため、営業職の方や高度な専門性が求められる方が当てはまります。労働基準法38条にもとづいて定められました。
裁量労働制はみなし労働時間制のひとつです。

みなし労働時間制とは?【わかりやすく解説】残業、違法
みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず一定時間労働したとみなす制度です。
ここでは、みなし労働時間制について解説します。
1.みなし労働時間制とは?
みなし労働時間制とは、実際働いた時間の長...
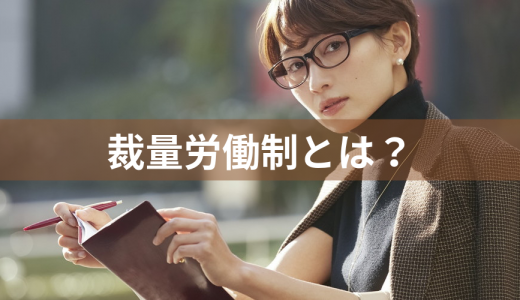
裁量労働制とは?【専門・企画業務型】残業代をわかりやすく
昨今話題になっている裁量労働制。会社員の働き方に関する非常に重要なキーワードですが、実際どういったものなのでしょうか?
ここでは、
裁量労働制の意味
裁量労働制と他の制度との違い
裁量労働制の制度詳...
⑤休憩(労基法34条)
使用者は、労働時間が、
- 6時間を超える場合においては少なくとも45分
- 8時間を超える場合においては少なくとも1時間
の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない、と定められています。休憩時間は労働者にとって、心身の休息を図る大事な時間です。
- 休憩時間は、一斉に与えなければならない
- 使用者は、労働者に休憩時間を自由に利用させなければならない
なども定められています。
休憩に関する注意点
労働基準法第34条に定めのある休憩とは、労働から解放されている時間のこと。たとえば、作業と作業の間に手が空いた時間などは使用者の指示があればすぐに業務に従事する時間と考えられます。
そのため、労働者が労働から解放されていない時間については労働時間の一部であると見なされてしまうのです。つまり、このような手が空いた時間は、労働基準法第34条の中にある休憩時間には含まれません。

休憩時間は何分?【労働時間6時間・8時間の場合】労働基準法
1.労働基準法が定める休憩時間は何分?
休憩時間は、労働者の肉体的・精神的な疲れを癒すための時間のこと。労働基準法第34条では、以下のように定められています。
使用者は、労働時間が六時間を超える場...
⑥休日(労基法35条)
使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。また、4週間を通じ4日以上の休日を与えることも可能です。
過労死などを防ぐためにも、休日の適切な管理は非常に重要でしょう。そこで労働基準法では、労働者が休日を取得できるよう、具体的な日数管理の方法を明記しているのです。
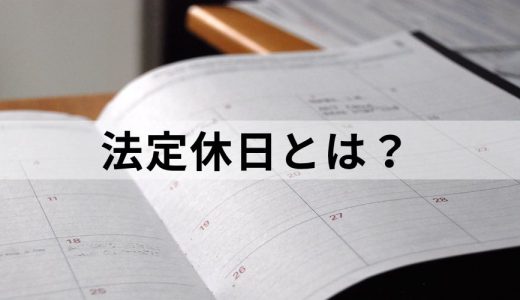
法定休日とは?【法定外休日との違い】出勤・残業の割増賃金率
「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」はどちらも使用者が労働者に与える休日であるものの、法律での要件や運用方法は大きく異なります。
これら休日は従業員の権利と福祉に直結し、また企業の法的責任にもかか...
⑦時間外および休日の労働(労基法36条)
使用者は、
- いわゆる36協定と呼ばれている労使協定を締結する
- 労使協定を労働基準監督署に届け出る
2つの条件を満たした場合、当該労使協定で定める範囲内で、労働時間の延長や休日労働が可能となります。逆説的に言えば、時間外労働や休日労働をさせる予定のある使用者は、事前に36協定を締結し行政官庁に届け出ておかなければならないのです。
36協定(サブロク協定)とは?
36協定とは、労働基準法第36条に明記されている労働協定のことで、正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定届」です。
使用者は、36協定の締結および労働基準監督署への届け出なしに、労働者に対して法定時間外労働や休日労働を命じることはできません。労働基準法は休日労働を除いた時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間と定めています。
臨時的な特別の事情がない限り、この上限を超えて労働させることはできません。また仮に、臨時的な特別の事情があっても、
- 時間外労働は、年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計時間は、月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内
としなければなりません。なお、中小企業についての時間外労働の上限適用は、2020年4月からとなっています。
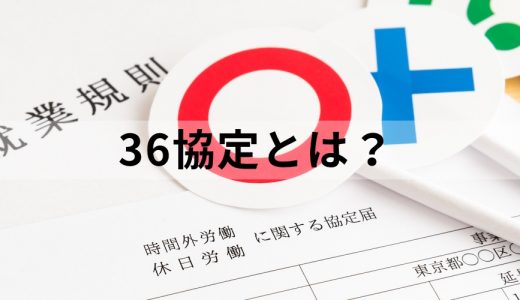
36協定とは? 残業時間の上限、特別条項などわかりやすく解説
36協定とは、従業員に時間外労働・休日労働をさせる際に締結しなければならない取り決めのこと。締結したからと無制限に時間外労働・休日労働させていいわけではなく、残業時間の上限や違反した際の罰則など、押さ...
⑧時間外、休日および深夜労働の割増賃金(労基法37条)
使用者が労働者に対して、法定時間外労働・休日労働・深夜労働を命じた場合、割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金の割合は、時間外労働や休日、深夜などの場合で異なります。
どの割増率で賃金を支払えばいいのかを正しく理解してきましょう。具体的な割増賃金の計算は、以下の通りです。
- 法定時間外労働は、1時間当たりの賃金×1.25
- 休日労働は、1時間当たりの賃金×1.35
- 深夜労働は、1時間当たりの賃金×1.25%
- 法定時間外かつ深夜労働は、1時間当たりの賃金×1.50
- 休日かつ深夜労働は、1時間当たりの賃金×1.60%
残業代の計算方法に関する注意点
残業代を計算する際の注意点は、1カ月の法定時間外労働が60時間を超えるようなケースにおいて、60時間を超える部分についての時間外労働の割増賃金は、25%増しではなく50%増しで支払う義務があること。

残業代とは? 種類と仕組み、割増率、計算方法をわかりやすく
8時間以上の仕事をすると残業代が支払われると思っていませんか。残業の種類、計算方法、トラブルなど残業代について詳しく説明します。
1.残業代とは?
残業代とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超...
⑨年次有給休暇(労基法39条)
使用者は、
- 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務
- 全労働日の8割以上出勤
の条件を満たした労働者に対し、継続または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。年次有給休暇の付与日数は、勤続年数が増加するに従って最大20労働日まで増加します。
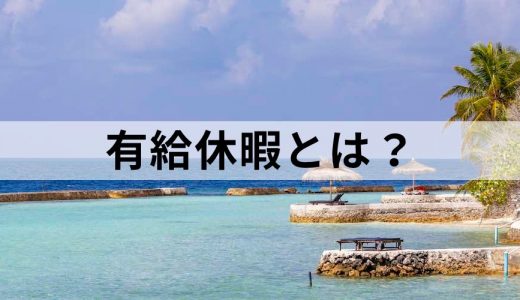
有給休暇とは? 付与日数や計算方法、繰越の上限をわかりやすく
有給休暇(年休)とは、従業員が心身の疲労回復やゆとりある生活を送ることを目的に取得できる休暇で、休暇でも賃金が発生します。従業員は有給休暇を取得する義務があり、企業は有給休暇を付与・取得を承認する義務...
パートタイム労働者の有休について
年次有給休暇は正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトといった週の所定労働時間が短い労働者に対しても
- 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務
- 全労働日の8割以上出勤
という条件を満たした場合に付与されます。付与される年次有給休暇の日数は、週所定労働日数によって異なります。
⑩就業規則(労基法89条)
就業規則については、
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する
- 作成した就業規則は行政官庁である労働基準監督署に届け出なければならない
と明記されています。常時10人以上の労働者は、雇用形態や勤務時間などを問いません。
必ず記載しなければならない項目
就業規則に記載する項目は、以下の3つです。
- 絶対的必要記載事項:必ず記載しなければならない
- 相対的必要記載事項:定める場合は必ず記載しなければならない
- 任意記載事項:雇用主が任意に記載できる
「絶対的必要記載事項」は、さらに以下の3つにわけられます。
- 労働時間に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職に関する事項
就業規則の効力
就業規則が合理的かつ労働者へ周知されている場合、「就業規則=労働条件」とします。ただし、労働契約法で定めている労働条件を下回る就業規則は無効です。
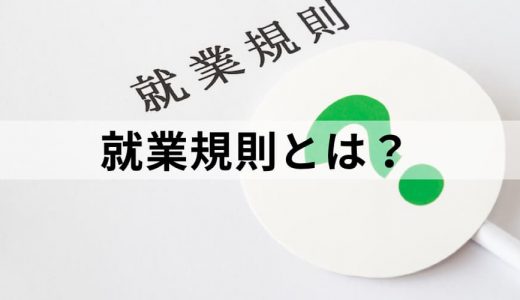
就業規則とは?【要点を簡単に】作成・届出の方法と流れ
就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する使用者が作成しなければならない規定です。職場のルールや労働条件に関わる内容が記載されているため、従業員もその内容を把握しておく必要があります。
ここでは、
...
⑪制裁規定の制限(労基法91条)
就業規則の中で減給の制裁規定を設ける場合、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という規定を遵守する必要があります。
制裁については減給のほか、出勤停止や譴責、懲戒解雇などがありますが、減給以外の制裁内容について労働基準法による制限は規定されていません。
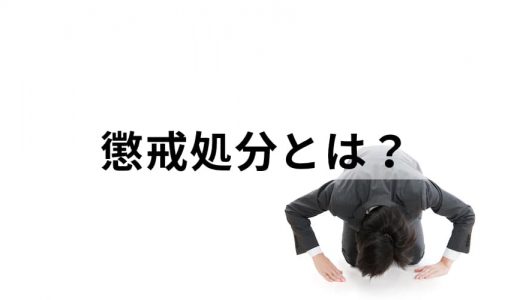
懲戒処分とは? 種類、判断基準の具体例、進め方をわかりやすく
企業は、秩序を乱した従業員に対して、問題行為に応じた懲戒処分を実施できます。万が一、従業員が懲戒処分に該当するような問題行為を行ったときに困らないためにも、
懲戒処分とは何か
懲戒処分の種類
懲戒処...
⑫周知義務(労基法106条)
使用者が労働者に対して周知しなければならないものは、労働基準法や就業規則などです。
使用者は、労働者に対して労働基準法や就業規則などを、
- 常時、各作業場の見やすい場所へ提示する、又は備え付ける
- 書面を公布する
- その他、厚生労働省令で定める方法、磁気テープや磁気ディスクによって周知する
などで伝えなくてはなりません。
⑬労働者名簿の作成(労基法107条)
労働者に関する情報をまとめた名簿のこと。日雇い労働者を除く労働者について、事業場ごとに調製・保存が義務づけられています。労働者の死亡や退職または解雇の日から3年間保存する義務があります。
なお、労働者名簿の書き方と記入例、必須項目や保存期間は、こちらの記事で詳しく紹介しています。あわせて参考にしてみてください。

労働者名簿の記載事項と作成方法│保管期間やデジタル化のメリットも
労働者名簿を作成するには、法的要件や必要な記載事項の把握が欠かせません。しかし、その詳細を完全に理解することは簡単ではないはずです。保存期間や管理方法に関する法律も、しっかりと考慮する必要があります。...
⑭賃金台帳の作成(労基法108条)
氏名や性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、早出労働時間数、深夜労働時間数、基本給・手当、控除項目・額を記載したもの。
事業場ごとに賃金台帳を調製したうえで、賃金を支払うたびに遅滞なく記入し、最後の記入日から3年間保存することが義務づけられています。

賃金台帳とは? 作成方法、記載事項の書き方、保管期間を簡単に
賃金台帳とは、給与の支払い状況を記載する書類です。法定三帳簿の一つであり、事業場ごとに作成と保管が義務づけられています。今回は賃金台帳の記載事項や書き方、保管期間や保管方法などについて詳しく解説します...
⑮労働関係に関する重要な記録の保存(労基法109条)
出勤簿は、労働者の出勤状況を記載した帳簿のこと。
法律上の明文はないものの、労働基準法における労働時間・休憩・休日に関する規定の趣旨に照らし、会社は従業員の出勤情報を記録し、適正に管理する必要があるとされています。保存義務期間は3年間です。

出勤簿とは? 項目や書き方、保存期間をわかりやすく解説
出勤簿とは、労働者の出勤日や労働日数、労働時間などを記載する書類です。作成・保管が義務付けられている書類であり、企業は事業場ごとに作成する必要があります。
今回は出勤簿について、詳しい記載事項や書き方...
5.労働基準法違反となるケース
以下に該当する場合は労働基準法違反となります。
- 国籍や性別で差別
- 労働の強制
- 賠償予定を含む労働契約
国籍や性別で差別
国籍などによる差別は労働基準法3条、性別による差別は4条に違反します。たとえば、女性であることを理由にして男性よりも低賃金とするといったことは許されません。
労働の強制
労働基準法5条では強制労働を禁止しています。長期労働契約や身体の拘束による労働の強制はもとより、前借金などで退職できない状況へ追い込むなどといった行為も違反となります。
賠償予定を含む労働契約
労働基準法16条では、労働者が自由に退職できなくなる恐れがあるため、賠償予定(違約した場合の罰金や損害賠償額)を含む労働契約を禁止しています。
6.労働基準法違反を犯した場合のリスクと罰則
労働基準法に違反した場合は、罰則を受けます。最悪の場合、雇用主が逮捕される場合もあるのです。
もっとも重い罰則は「強制労働の禁止」に違反するときで、1年以上10年以下の懲役または20万以上300万円以下の罰金が科されます。
そのほか、労働条件の明示違反や休業手当の不支給などでは、30万円以下の罰金が科せられます。
7.労働基準法の注意点
労働基準法は、労働に関する最低限のルールを定めたものです。
実際に人を雇う際は、さらに労働契約法や最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法などの関連法令も違反しないように注意しなければなりません。
また、法律は改正されることもあるため、つねに動向をチェックする必要があります。
8.労働基準法の主な改正内容
2018年に「働き方改革関連法」が公布され、順次施行されています。そのタイミングで労働基準法の一部が改正されました。最後に、改正された一部の内容を解説します。
年次有給休暇取得の義務化
2019年4月から、10日以上の有給休暇が付与される全労働者に対して、5日間の有給休暇を取得させる義務が生じました。正規・非正規、無期雇用・有期雇用の全労働者が対象です。
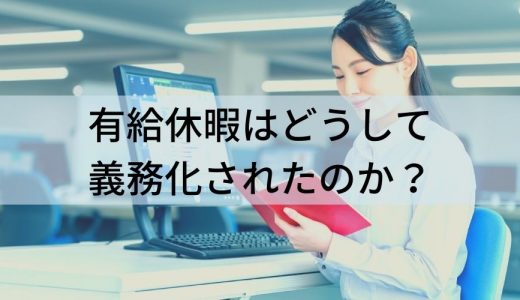
有給休暇の年5日取得義務化とは? 罰則や対策について解説
2019年4月から、すべての使用者に対して「労働者の年間5日の年次有給休暇取得」が義務付けられました。ここでは、対象者や義務化の内容や企業における対応方法などをご紹介します。
1.有給休暇はどうして義...
時間外労働の法定割増賃金率を引き上げ
同じく2019年4月から、月60時間以内の時間外労働については25%以上、月60時間を超える時間外労働について50%以上を割増賃金率とすることが定められました。
大企業・中小企業のいずれも対象で、所定休日(法定休日以外の休日)に勤務した場合も時間外労働に含まれます。深夜の時間外労働の場合は、さらに割増賃金25%を加算します。
建設業における時間外労働の上限規制
建設業における時間外労働の上限が定められました。
建設業では長時間労働が常態化していることが問題視され原則として労働時間は月45時間以内・年360時間以内と定め、特別な事情がなければ遵守する必要があるとされています。
大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用済みです。長時間労働の浸透と深刻な人材不足という状況を考慮して、5年間の猶予を認めていました。しかしこの猶予が2024年6月1日から撤廃されます。

