フレックスタイム制とは、従業員が始業・終業時刻などの労働時間を自ら決められる勤務体系のことです。
目的、導入率、メリット・デメリット、働き方改革関連法による新フレックスタイム制、導入方法などについて紹介します。
目次
1.フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。
フレックスタイム制では、
- 時間帯の中であれば自由に出社・退社しても良い「フレキシブルタイム」
- 時間帯には必ず就業しなくてはならない「コアタイム」
とを設定するのが一般的です。
フレックスタイム制を導入するためには、事前に労使間で36協定を締結する必要があります。

コアタイムとは?【意味・目的を簡単に】フレックスタイム制度
フレックスタイム制を導入する企業が増え、多様な働き方ができる制度として注目を集めています。
ここでは、フレックスタイム制における「コアタイムとか何か」を軸に、制度の仕組み、フレックスタイム制とコアタ...
裁量労働制との違い
裁量労働制は、労働時間が労働者の裁量にゆだねられている労働契約のことです。
フレックスタイム制は会社が決めた所定労働時間は働かなければならないため、みなし労働時間のある裁量労働制とは時間の自由度が異なります。
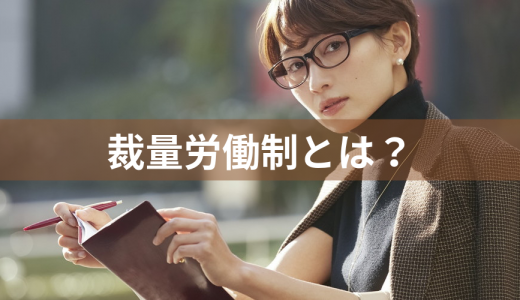
裁量労働制とは?【専門・企画業務型】残業代をわかりやすく
昨今話題になっている裁量労働制。会社員の働き方に関する非常に重要なキーワードですが、実際どういったものなのでしょうか?
ここでは、
裁量労働制の意味
裁量労働制と他の制度との違い
裁量労働制の制度詳...
時短勤務との違い
時短勤務とは、1日の勤務時間を通常よりも短縮した働き方で、就業時間が固定されています。
一方で、フレックスタイム制は始業・終業時刻、労働時間を自分の裁量で決めることができるので、時間の自由がききます。

時短勤務(短時間勤務制度)とは? 内容と期間をわかりやすく
時短勤務とは、フルタイムよりも勤務時間を短くする「短時間勤務制度」のことです。近年、働き方の多様化によって注目を集めています。時短勤務は、どのような特徴などを持つのでしょうか。
1.時短勤務とは?
...
2.フレックスタイム制の目的
フレックスタイム制は労働者自身が勤務時間帯を自由に決めることができるため、柔軟な働き方の選択が可能になります。
- ワークライフバランスの推進
- 生産性と業務効率の向上
といった点を目的としています。
以下で詳しく見ていきましょう。
ワークライフバランスの推進
多くの企業にとって、ワークライフバランス実現は課題になっており、フレックスタイム制はその方策のひとつでもあります。
労働者自らが出社や退社時刻を決めることができるので、
- 介護や子供の病気など緊急時には出社時間を遅らせる
- 妊娠中の社員などが通勤ラッシュを避ける
といった場合にも、遅刻や早退などをせずに柔軟に働くことが可能になります。
生産性と業務効率の向上
生産性と業務効率の向上を目的に導入する企業が多くなっています。
フレックスタイム制を導入することで、
- 業務が立て込んでいる時期は長く
- 落ち着いている時期は短く
と、業務量に応じて勤務時間を柔軟に調整できます。
また従業員個人の仕事への取り組み姿勢が変わることで、
- 業務効率化
- 生産性の向上
も期待できます。
3.フレックスタイム制の導入率
厚生労働省が発表した「平成29年就労条件総合調査結果の概況」で、フレックスタイム制の導入率は全体の7.9%となっています。
業種別に上位3種は、
- 情報通信業:23.6%
- 学術研究、専門・技術サービス業:20.3%
- 電気・ガス・熱供給・水道業:20.0%
です。
下位3種は、
- 医療、福祉:0.4%
- 生活関連サービス業、娯楽業:0.8%
- 教育、学習支援業:1.1%
でした。
フレックスタイム制が普及しない理由
フレックスタイム制が普及しない理由にはさまざまな課題があります。とくに次の3点が考えられます。
- 労働時間管理が難しい
- 一部の社員に導入すると不満が出る
- 出社の時間が遅くなる懸念
それぞれ詳しく解説していきましょう。
労働時間管理が難しい
社員によって出勤、退勤時間が異なるので通常のワーキングスタイルよりも複雑になりがちです。
通常の労働時間制であれば、タイムレコーダーをもとにエクセルなどで簡単に残業代の計算もできましたが、フレックスタイム制の時間外労働は清算期内の総労働時間で見極めます。
その日のみの勤務時間では、残業時間を把握することができません。
一部の社員に導入すると不満が出る
すべての業務にフレックスタイム制が適していないため、全員にフレックスタイム制を導入することは困難です。
しかし一部の社員にだけフレックスタイム制を導入すると、他の社員から不満の声が上がるケースもあるでしょう。
フレックスタイム制を導入した社員だけが、特別扱いしたように受け取られてしまう可能性もあり、社内不和の原因になります。
出社の時間が遅くなる懸念
フレックス制で出社が遅くなることが危惧されています。
- ほとんどの社員が夜に出社する
- 深夜に仕事をして朝出社する社員がいなくなる
など朝夜が逆の働き方になってしまうケースです。
またフレックスタイム制を導入しても、深夜時間帯の勤務の増加とともに、割増賃金の支払いが増えれば、会社の経営状況を圧迫しかねません。
4.フレックスタイム制の仕組み
柔軟な働き方の選択が可能となるフレックスタイム制について、人事がしっかりとその仕組みを理解し、全従業員に伝える必要があります。
新しい労働体系が浸透しなければさまざまなトラブルが生じる可能性もあります。
コアタイム
コアタイムとは必ず勤務しなくてはいけない時間帯のことです。
必ずしもコアタイムの設定が義務付けられているわけではありませんが、社員が比較的集まりやすい時間帯をコアタイムとして設定している企業が多いようです。
コアタイムの設定の仕方について労使協定の中で合意済みであれば、自由に決めることが可能となります。
フレキシブルタイム
フレキシブルタイムとは、従業員が出勤時間と退勤時間を自ら自由に選択できる時間帯で、いつ出勤しても、退勤してもよい時間帯ということです。
つまり、始業と終業の時間を、労働者本人の選択に委ねるものです。
フレキシブルタイムを定める場合は、その正確な時間帯を、労働組合との労使協定によって決定する必要があります。
精算期間
フレックスタイム制を導入した会社では、労働組合との労使協定によって「清算期間」が決められています。
そのため、法定労働時間を超えただけでは時間外労働とはみなされず、「清算期間内における総労働時間よりも実際に働いた時間が長い場合」が時間外労働となります。
残業代が支払われるのも、この条件に該当する場合となります。
総労働時間
清算期間における「総労働時間」として定められた時間は、労働契約上、労働者が労働すべき時間を定めるものであり、所定労働時間のことです。
総労働時間は一般的に「標準となる1日の労働時間×その月の所定労働日数」として定めます。
その場合、清算期間を平均して、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えないことが要件となります。
5.働き方改革関連法による新フレックスタイム制について
働き方改革関連法により、フレックスタイム制に関する変更が加えられ、2019年4月に施行されました。
労働時間時間の調整が行える時間が1カ月から3カ月へと延長されました。
しかし、新フレックス制導入により、さまざまな課題点が発生しました。

働き方改革関連法とは? 2023年の施行内容、罰則、テーマ
働き方改革関連法とは、労働に関する既存の法律に加わった改正の総称。働き方改革関連法の主な施行内容や罰則、企業が変革すべき項目について解説します。
1.働き方改革関連法とは?
働き方改革関連法とは、改正...
清算期間の上限が2か月に延長
フレックスタイム制の清算期間の上限が1カ月以内から3カ月以内に延長されました。
清算期間の延長により、3カ月の平均で法定労働時間以内で働いた場合には割増賃金の支払いが不要になりました。
そのため所定労働時間と実労働時間の過不足時間を管理する必要があります。
従来では超過した時間に対して割増賃金の支払いが必要でした。
完全週休二日制の特例
完全週休2日制のフレックスタイム制で、1日平均8時間労働であったとしても、曜日のめぐりによって、所定休日が少なく労働日数が多い月には、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまうことがありました。
改正後は労使協定で「所定労働日数に8時間を乗じた時間数」を法定労働時間の総枠とすることを定めることが可能になりました。
労使協定
フレックスタイム制の改正後、清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制の労使協定は、制度の適正な実施を担保する観点から労働基準監督署に届出が必要になりました。
- 就業規則への規程
- 労使協定で所定の事項を定めること
- 労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る
といったことがポイントです。これに違反すると罰則が科せられることもあります。
賃金の清算
清算期間が1カ月を超える場合に、実際に労働した期間が清算期間よりも短い労働者については、その期間に関して清算を行います。
実際に労働した期間を平均して、週40時間を超えて労働していた場合には、その超えた時間分の割増賃金を支払います。
清算期間が月単位ではなく最後に1カ月に満たない期間が生じた場合には、その期間について週平均50時間を超えないようにします。
割増賃金の計算方法
割増賃金の計算方法は次の通りです。
残業代=残業時間×1時間当たりの基礎賃金×割増率
割増率は、労働基準法にそれぞれ規定があります。
- 時間外労働(法定外残業)は25%
- 休日労働は35%
- 深夜労働(22時~5時までの労働)は25%
と定められています。
大企業は、1カ月あたりの法定労働時間を60時間以上超える部分の残業については、割増率が50%になります。
6.フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制は社員にとっても会社にとっても多くのメリットをもたらします。
テレワークの導入が難しい業種においては、出勤ピークタイムを避けられるメリットを活用して、フレックスタイム制導入する企業も増えています。
企業のメリット
優秀な人材の獲得や従業員のモチベーションアップ、残業時間の削減、従業員の労働負担の軽減のなどメリットはたくさんあります。
フレックスタイム制は従業員自身が勤務時間帯を自由に決めることができる柔軟な働き方である一方、自己管理が求められます。
それをうまく活用できる自立した人材を多く採用できれば、企業の生産性にもつながります。
従業員のメリット
- 通勤ラッシュを避けられる
- 自由な時間を確保しやすくなる
などのメリットがあります。
フレックスタイム制の導入によってプライベートの時間が充実し、ストレスを軽減できるなど従業員のワークライフバランスの向上につながります。
新しい趣味を始めた、決まった曜日に習い事を入れられるなど従業員がリフレッシュして仕事に取り組むことができます。
7.フレックスタイム制のデメリット
企業によってはフレックスタイム制が合わない場合もあります。
しっかり検討せず安易に導入すると、業務効率の低下やトラブル発生などを招く恐れもあります。
会社によって向き、不向きがあるため慎重に考えた上で導入すべきでしょう。
企業のデメリット
時間帯によっては従業員がほとんど出社しておらず、担当者が不在で取引先対応がおろそかになり、業務が滞ったりトラブルが起こったりすることがあります。
また従業員の出勤、退勤時間が毎日一定ではないため、勤怠管理が難しくなります。
これまではエクセルなどで管理していたのが、勤怠管理システムを導入するなどコスト面でもデメリットがあります。
勤怠についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
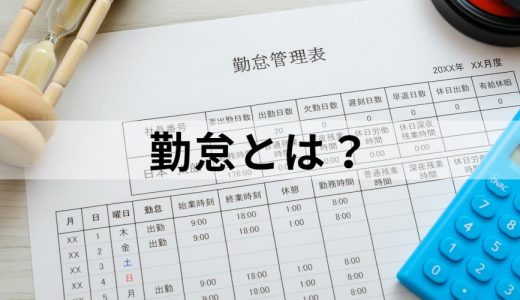
勤怠とは? 意味・読み方・使い方、管理の目的と項目を簡単に
勤怠とは出勤や退勤をはじめとした従業員の出勤状況を表す言葉です。出社や退社、休暇や休憩などが含まれます。勤怠について、詳しく見ていきましょう。
1.勤怠とは?
勤怠(きんたい)とは、従業員の出退勤や...
従業員のデメリット
出勤時間、退勤時間がそれぞれ異なるため、従業員間のコミュニケーション不足や業務がルーズになりがちになるなどのデメリットがあります。
- 顔を合わせてあいさつができない
- 打ち合わせや報告もメールだけになった
など、社員間にすれ違いが生じてしまい、仕事上での重大なミスへとつながりかねません。
円滑なコミュニケーションの仕組みが必須です。
8.フレックスタイム制を導入するには?
フレックスタイム制の導入に当たってはいくつか確認することがあります。
- 厚生労働省による解説を読む
- 就業規則を規定する
- 労使協定を締結する
- 残業と休憩時間の扱いをおさえておく
それぞれ詳しく解説しましょう。
厚生労働省による解説を読む
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署が発行するパンフレット「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」ではフレックスタイム制導入に当たっての注意事項を解説しています。
フレックスタイム制の法令解説編から、就業規則などに規定し労使協定を締結する事項や方法など実務対応編まで詳しく解説しています。
就業規則を規定する
始業、終業の時刻の決定を労働者にゆだねる内容を就業規則に定める必要があります。
同時に勤務しなければならないコアタイム、従業員の決定にゆだねる始業、終業の時間帯フレキシブルタイムについても就業規則に定めなくてはなりません。
就業規則の作成義務のない場合には、労働者に周知される文書で知らせる必要があります。
労使協定を締結する
フレックスタイム制を導入するためには、事業場の過半数労働組合、それがない場合には過半数代表者と労使協定を締結する必要があります。
労使協定で定める項目は次の通りです。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム
- フレキシブルタイム
- 起算日
- 有効期限と労働基準監督署への提出
残業と休憩時間の扱いを押さえておく
時間外労働は割増賃金を支払う必要があります。
月あたりの合計が60時間を超えるときは、5割以上の割増率により計算された割増賃金の支払いが必要です。
休憩時間は、
- 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分
- 8時間を超える場合は少なくとも1時間
の休憩を労働の途中に与え、自由に利用させるといったことが必要です。

