労働者名簿を作成するには、法的要件や必要な記載事項の把握が欠かせません。しかし、その詳細を完全に理解することは簡単ではないはずです。保存期間や管理方法に関する法律も、しっかりと考慮する必要があります。
デジタル化による効率化が進む中で、そのメリットを労働者名簿でも享受できるのかと悩んでいる人事労務担当者も多いでしょう。労働者名簿を法的要件を満たしながら安全に管理し、より効果的に業務を進めるためのポイントを解説します。
目次
労働者名簿の基本と法的な要件

労働者名簿は、労務管理の基礎となる重要な帳簿です。法令に基づいて適切に作成・管理しなければなりません。そのためには労働者名簿が何のためのもので、法的に誰が対象となっているのか、法令に違反した場合はどのようなペナルティがあるのかを知っておく必要があります。
労働者名簿とは?定義や法律の定め
労働者名簿は、企業が雇用する従業員の情報をまとめたものを指します。労働基準法の第107条で作成と保存が義務付けられている、「法定三帳簿」のひとつです。
労働者名簿を作成することで、企業は効率的な従業員の労務管理が可能になります。対象は日雇い労働者を除くすべての労働者です。正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトも含まれます。
労働者名簿は、個人情報や雇用履歴が記載された労務管理の基盤ともいえる帳簿です。労働基準監督署などの調査時にも使われます。作成時には、法令で定められた記載事項を守らなければなりません。法令を順守した作成や管理を怠ると、ペナルティを科される可能性が出てきます。
労働者名簿の対象とならない人物
労働者名簿の対象は原則としてすべての従業員ですが、中には対象とならない人物もいます。対象外となる人は以下のとおりです。
- 日雇い労働者:継続的な雇用関係が前提でないため
- 派遣社員(派遣元の雇用):雇用契約が派遣元との間にあるため
- 出向社員(移籍出向の場合):移籍先との雇用契約があるため
- 役員:労働者に該当しないため
ただし、同じく「法定三帳簿」のひとつとされる「賃金台帳」には日雇いの労働者についても作成が必要です。この点を混同しないように注意しましょう。
参考:『労働基準法 第108条|e-Gov 法令検索』
参考:『労働基準法施行規則 第53条|e-Gov 法令検索』
法令を守らなかった場合の罰則とリスク
労働者名簿を法令にのっとって作成・管理しないと、企業は罰則を受けたり、信頼低下のリスクに直面したりするる可能性があります。労働者名簿は作成・保存が義務付けられているだけでなく、記載事項に変更があった場合には迅速な修正が必要です。
これを怠った場合、労働基準監督署からの是正勧告を受けるだけでなく、悪質と判断されれば30万円以下の罰金が科されます。法律違反が発覚すると企業名が公表されることもあり、企業の評判を大きく落としてしまう事態になりかねません。
参考:『労働基準法 第120条第1号|e-Gov 法令検索』
労働者名簿をどう作成・保管すべき?
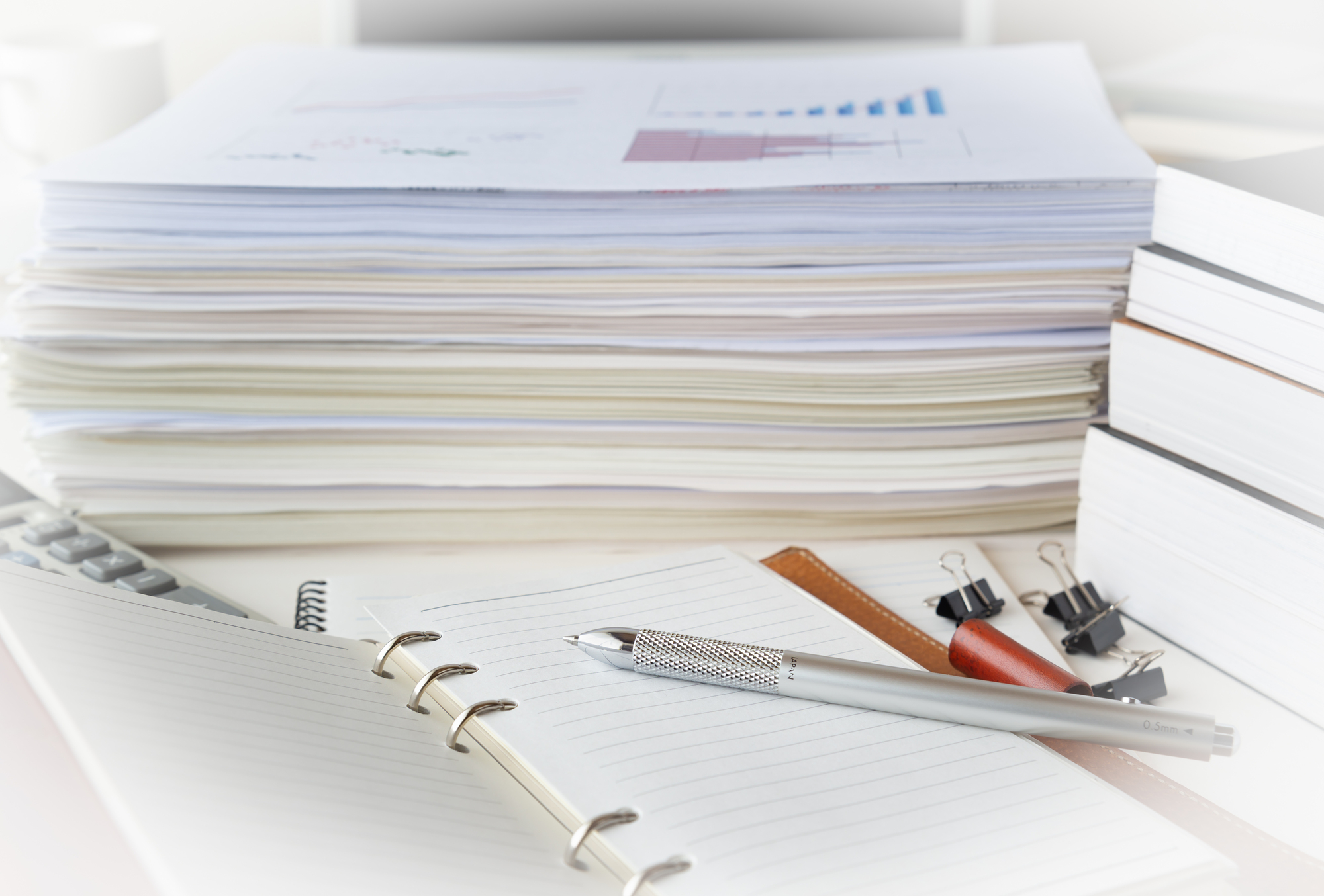
労働者名簿を作成・保管する際には、法令に従った正確な記載事項や保管期間の把握が不可欠です。必須項目を漏れなくチェックして法的要件を満たすことが、後々のトラブル防止につながります。
どうすれば法的な要件を満たしつつ効率的・安全に労働者名簿を作成・保管できるのか、具体的に見ていきましょう。
必須項目の一覧をチェックする
労働者名簿を作成するに当たって、まずは記載すべき項目を把握しなければなりません。法令で定められている必須項目は、以下のとおりです。
<労働基準法で定められた項目>
- 氏名
- 生年月日
- 履歴(一般には異動・昇進など社内での履歴。法令では明確に示されていない)
<労働基準法施行規則で定められた項目>
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類(常時雇用している従業員が30人未満の場合は記載不要)
- 雇入の年月日
- 退職の年月日とその理由(解雇による退職の場合は解雇の理由)
- 死亡の年月日とその原因
氏名には読み仮名の記載も推奨されます。住所は最新のものが求められるため、変更時にはできるだけ早めに更新しなければなりません。
職種や業務も詳細に記載し、異動履歴も分かるようにしておきましょう。退職日やその理由も具体的に記録します。特に会社都合の場合は、正当性が認められる理由の記載が必要です。
参考:『労働基準法 第120条第1号|e-Gov 法令検索』
参考:『労働基準法施行規則 第53条|e-Gov 法令検索』
労働者名簿のテンプレートを選ぶ
労働者名簿を作成にはテンプレートの活用が効率的です。テンプレートは法令の要件を考慮して作られているため、法的リスクの軽減にも役立ちます。テンプレートは、業務のニーズに合わせて選びましょう。特定の業種に特化したテンプレートは、業務に最適化されています。たとえば、特定の職種に応じた記載欄があることで情報管理がより効率化されるはずです。
また、カスタマイズ可能なテンプレートを利用すれば、自社の状況に応じて必要な情報の追加もできますす。
クラウドサービスの従業員管理機能に備わったテンプレートを使うのも、ひとつの方法です。カスタマイズ可能であれば、自社のニーズに合わせた労働者名簿が簡単に作成できます。
労働者名簿を法令に従って保存・管理する
労働者名簿は、企業が労働者を雇う際に必ず作成するのはもちろん、一定期間の保管も義務付けられている重要な帳簿です。労働基準法の第109条では、労働者の退職・解雇・または死亡の日から5年間保管しなければならないとされています。
また、労働者名簿には従業員の個人情報や詳細な雇用履歴が記載されているため、安全に管理しなければなりません。名簿を閲覧できる人物や部署の制限、保管場所に出入りした従業員のチェックなど、厳重なセキュリティ体制を用意する必要があります。
労働者名簿はデジタル化で法令対応と効率化を

労働者名簿のデジタル化は、業務効率を向上させのに役立ちます。実際にデジタル化することの具体的な利点は何でしょうか。
労務管理クラウド「ロウムメイト」を使った労働者名簿作成や管理のメリット、デジタル化に向けたステップも解説します。
労働者名簿のデジタル化による具体的なメリット
労働者名簿のデジタル化には、多くの利点があります。特にクラウドシステムを利用すれば、各事業所で常に最新の情報を迅速に確認でき、業務の効率化が図れます。結果として、急な労働基準監督署の調査にも対応しやすくなるでしょう。
デジタル管理によるペーパーレス化で紙の紛失による情報漏えいリスクが軽減する上、保管スペースも不要になるのは大きな魅力です。ただし、常に最新情報の正確な収集と管理は必要です。システムを導入しても、古い情報のまま放置しないよう注意しましょう。
「ロウムメイト」で労働者名簿の作成・管理が楽に
カオナビが提供する労務管理クラウド「ロウムメイト」は、労働者名簿の作成・管理を効率化する優れたツールです。ロウムメイトの従業員管理機能を利用すれば、人事労務業務の手間を大幅に削減できます。
労働者名簿のテンプレートを用意しており、自社向けにカスタマイズも可能です。正社員・パート・アルバイトといった雇用形態別のテンプレートもあるため簡単に作成できます。
直感的に操作できるUI、1社につき1人の専任サポートで、システム導入後の運用までしっかりフォローします。
ロウムメイトには従業員管理のほかにも機能があります。ただ欲しい機能だけを選んで導入できるため、不必要な機能にコストがかかる心配はありません。
労働者名簿をデジタル化するときのステップ
労働者名簿のデジタル化を進めるには、まず準備が必要です。事前に既存の紙ベースの名簿を整理することで、スムーズに電子化できます。
次に入力すべき項目を確認し、必要に応じて調整しましょう。準備が整ったら自社のニーズに合わせて、法令対応にも十分な信頼性の高いシステムを選びますう。な移行が可能です。ロウムメイトのCSVアップロード機能を使えば、既存システムとの連携もスムーズに進むでしょう。
まとめ

労働者名簿に必要な記載事項には、氏名や生年月日・性別・退職日やその理由などが法令で定められています。これらを漏れなく記載し、法的要件を満たしましょう。
さらに、名簿の保存期間(5年間)や個人情報の安全な管理方法も、適切な運用のために重要です。
クラウドサービスを活用した電子化により、効率化を図りつつ、法令要件を満たした名簿の作成・保管が可能になります。
法的要件を満たしたシステム、カスタマイズ可能なテンプレートのある「ロウムメイト」をぜひご検討ください。
