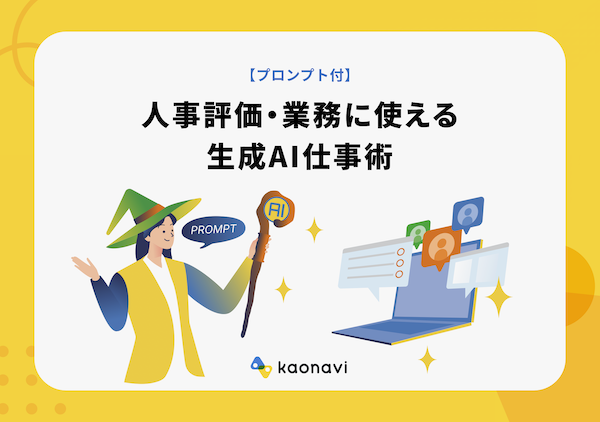目標管理(MBO・OKR)を効率化し、従業員エンゲージメント向上。
人事評価システム「カオナビ」で、部下の目標達成を充実サポート!
⇒
【公式】https://www.kanavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人事評価・考課における目標設定は、従業員の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上につながる重要なプロセスです。
しかし、「どのように目標を設定すればよいのか」「評価の公平性を保つにはどうすればよいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では人事評価・考課における目標設定の基本から、具体的なメリットや注意点、効果的なフレームワークまで詳しく解説します。
また、職種ごとの目標設定例の紹介や実践的な活用方法も紹介します。適切な目標設定を行い、従業員のモチベーション向上と企業の成長につなげましょう。
目次
悩む時間を減らす実務プロンプト集
1.人事評価・考課で目標設定が重要な理由
人事評価・考課は、企業が従業員の業績や能力、勤務態度などを評価し、昇進や昇給、配置転換などの人事決定に活用する制度です。
従業員の貢献度を適切に把握し、組織の成長につなげるために実施されます。この評価を適切に行うには、事前の目標設定が重要です。目標の達成度や業務に取り組む姿勢は、従業員一人ひとりの評価材料として活用できます。
特に、目標の達成状況は数値で示せるため、評価基準が明確になり、公平な評価につなげられます。また、企業の経営目標を部門や個人の目標に落とし込むことで、組織全体が同じ方向を向いて進められます。
適切な目標設定は、従業員の納得感を高めるとともに、組織全体の成長促進につながるでしょう。
【従業員の目標達成をサポートする機能が揃っています!】
人事担当者からマネージャー、従業員まですべての目標管理・評価業務を効率化するなら、人事評価システム「カオナビ」です!
●フィードバックに役立つ人材情報を把握できる
●目標進捗を一覧で確認できる
●1on1などの面談管理が簡単にできる
●従業員エンゲージメントを見える化できる
●MBOやOKRシートのテンプレートが利用できる
2.人事評価・考課における目標設定のメリット
人事評価に目標設定を取り入れることで、企業と従業員の双方に多くのメリットが生まれます。
ここでは、特に重要な4つのメリットを紹介します。
- 従業員のモチベーションが上がる
- 従業員のスキルアップにつながる
- 生産性が向上する
- 企業と従業員の相互理解が深まる
従業員のモチベーションが上がる
明確な目標の設定により、従業員は自分が何を達成すべきかを具体的に理解できます。目標がはっきりしていると、日々の業務に対する意識が高まり、積極的に取り組む姿勢が生まれます。
特に、自ら設定した目標が評価や報酬に直結する場合、達成した際の喜びや達成感は大きくなるでしょう。これにより、自己効力感が向上し、さらに意欲的に業務へ取り組むことが期待できます。
従業員のスキルアップにつながる
目標設定は、従業員の能力開発を促進する役割も果たします。
具体的な目標設定により、達成に必要なスキルや知識を習得しようとする意識が高まり、計画的に学習やトレーニングに取り組めます。
また、目標には期限が設定される場合が多く、限られた期間内で成果を出さなくてはいけません。そのため、従業員は自主的に業務へ取り組む姿勢が身につき、継続的な成長が可能です。
生産性が向上する
目標を設定すると、業務の優先順位や進め方が明確になります。従業員は限られた時間内で効率的に業務を遂行しようとするため、不要な作業が減り、生産性が向上します。
さらに、目標達成のための具体的な行動計画を立てることで、業務プロセスの見直しや改善が進みます。個々の業務効率が向上するだけでなく、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与するでしょう。
企業と従業員の相互理解が深まる
目標設定の過程では、上司と部下が対話を重ね、企業のビジョンや方針、従業員のキャリア志向を共有する機会が生まれます。
このコミュニケーションを通じて、相互理解が深まり、信頼関係の構築につながることもメリットのひとつです。
また、定期的なフィードバックや面談により、従業員は自身の役割や期待される成果を再確認できます。企業側も従業員の状況や意見を把握しやすくなり、より適切なサポートができるでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.人事評価・考課で適切な目標設定ができないデメリット
適切な目標設定が行われないと、評価の公平性が損なわれたり、従業員の意欲が低下したりする可能性があります。
ここでは、具体的な問題点を3つ解説します。
- 公平性の欠如によりモチベーションが低下する
- 人材が流出する
- 組織目標との乖離により業績が悪化する
公平性の欠如によりモチベーションが低下する
明確な目標が設定されていないと、評価基準が曖昧になります。その結果、評価者の主観や先入観が入り込み、公平な評価が難しくなるおそれがあります。
このような状況では、たとえ同じ業績を上げても評価が異なる可能性があり、従業員の間で不公平感が広がるでしょう。
公平性を欠いた評価は従業員のモチベーションを下げ、業務の生産性の低下につながります。さらに、不満が蓄積すると、離職率の増加にも影響するため、企業にとっても大きな課題です。
人材が流出する
目標が明確でないと、従業員は自分の役割や期待される成果を十分に理解できません。業務の方向性が見えないと、働く意欲を失い、成長の実感が得られにくいでしょう。
さらに、成果が正しく評価されなければ、会社への不満が募ります。自分の業務が認められないと、やりがいを見いだせず、最終的には転職する場合もあります。
その結果、離職率が上昇し、特に優秀な人材が流出するリスクが高まります。
組織目標との乖離により業績が悪化する
適切な目標設定がなければ、個々の従業員の目標と組織全体の目標が一致しません。
各従業員がバラバラの方向を向いて業務を進めると、組織全体の戦略にズレが生じ、連携を取るのも困難です。このような状態が続くと、効率的な業務運営が難しくなるでしょう。
結果として、組織の業績が低下し、市場での競争力も弱まる可能性があります。企業の成長を支えるためにも、適切な目標設定の運用が大切です。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード4.人事評価・考課で用いられる主な評価手法
人事評価は企業にとって重要な取り組みであり、適切な評価手法の選定が成功の鍵となります。
ここでは、代表的な評価手法とその特徴について解説します。
- 目標管理制度(MBO)
- 360度評価
- コンピテンシー評価
- プロブスト法
- 段階択一方式
- ポイント制
目標管理制度(MBO)
目標管理制度(MBO:Management By Objectives)は、従業員が自ら目標を設定し、その達成度を評価する手法です。
自身で目標を決めるため、主体的に業務へ取り組む意識が高まる点がメリットです。また、目標が明確になることで、従業員の成長を促進し、成果に対する納得感も得やすくなります。
ただし、個人の能力や環境によって目標の難易度が異なる場合、公平な評価が難しくなる点に注意しましょう。
360度評価
360度評価は、上司だけでなく、同僚や部下、取引先など、業務上関わりのある複数の人物から評価を受ける手法です。
多方面からのフィードバックにより、評価の公平性や客観性を高められます。この手法は、従業員が自分の強みや改善点を理解できる点が特徴です。
ただし、従業員1人に対する評価者が多い分、集計などに手間がかかるため、注意しましょう。
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価は、優秀な従業員に共通する行動特性や能力を基準に、ほかの従業員を評価する手法です。
具体的な行動やスキルが評価項目となるため、基準が明確で、公平に評価できます。また、求められる行動や能力が示されることで、従業員自身が成長目標を明確にできる点もメリットです。
ただし、企業の業種や職種によって適用が難しい場合もあるため、基準の設定には工夫が求められます。
プロブスト法
プロブスト法は、評価項目をチェックリスト形式でまとめ、各項目について該当するかを確認しながら評価する手法です。
評価者の主観や先入観の影響を最小限に抑え、客観的に評価できます。ただし、チェックリストの項目設定が適切でないと、評価の精度が低下する可能性があります。
そのため、評価対象の業務内容や職種に合った項目を慎重に設定することが重要です。
段階択一方式
段階択一方式は、評価項目ごとに複数の評価段階を設定し、最も適した段階を選んで評価を行う手法です。評価基準が明確で、評価者によるばらつきを抑えられる点が特長です。
例えば、「積極性」の評価では、以下のような段階を設定します。
- A:自主的に知識を習得し、目標達成のために積極的に行動している
- B:上司のアドバイスを求め、実践している
- C:上司の指示に従うが、自主的な行動は少ない
- D:知識習得の意欲が低く、アドバイスを受けても行動に移さない
このように、具体的な基準を設けることで、評価の公平性を高められます。
ポイント制
ポイント制は、各評価項目に点数を割り当て、合計点で従業員を評価する手法です。業績や能力、勤務態度などの各項目ごとに配点を設定し、評価者が採点します。
この方法は、評価の数値化により客観的に比較しやすい点がメリットです。ただし、点数の基準や配点のバランスが不適切だと、実際の成果や能力と評価結果が乖離する可能性があるため、慎重な運用が求められます。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
5.人事評価・考課の目標設定フレームワーク:SMARTの法則
SMARTの法則は、効果的な目標設定のためのフレームワークとして広く活用されています。
SMARTの法則とは、目標を設定する際に必要な5つの要素の頭文字を取ったものです。ここから、それぞれの要素について詳しく解説します。
①S:Specific(具体的)
目標は具体的かつ明確であることが重要です。曖昧な表現では、従業員が何を達成すべきかを理解しづらく、行動に移すのが困難です。
例えば、「業績を向上させる」といった漠然とした目標ではなく、「四半期の売上を前年比10%増加させる」や「次の四半期で新規顧客を10社獲得する」といった具体的な目標を設定します。
これにより、達成すべき基準が明確になります。
②M:Measurable(測定可能)
目標には、進捗や成果を測定できる指標を使います。測定可能な目標の設定により、定期的に進捗状況が確認でき、必要に応じて計画の修正が可能です。
例えば、以下のように数値を明確にすることで、達成度が測定できます。
- 新規顧客を100件営業して5件獲得する
- アフターサポートを100%実施し、顧客満足度を80%以上にする
- SaaSサービスの改善要望を10件抽出し、新機能を3つ追加する
- シーズン向けの記事を5本追加し、Webサイトへの流入数を前年比10%増加させる
このように、数値化できる目標の設定により、達成状況を明確に評価できます。
③A:Achievable(達成可能)
目標は、挑戦的かつ現実的に達成可能な範囲で設定します。目標が高すぎると達成が困難になり、従業員のモチベーションを低下させるおそれがあるためです。
逆に、簡単すぎる目標では成長の機会を失い、組織の発展にもつながりません。従業員が継続的に成長できるバランスの取れた目標設定が大切です。
④R:Related(関連性)
目標は、組織のビジョンやミッション、上位目標と関連している必要があります。
個人の目標が組織全体の方向性と一致していれば、従業員は自分の業務が会社の成長に貢献していることを実感できます。例えば、企業の目標が「新規顧客の獲得」だとします。
この場合、営業部門の個人目標として「半年間で新規顧客を20社獲得する」と設定し、企業目標と個人目標を連携させましょう。
⑤T:Time-bound(明確な期限)
目標には明確な期限の設定が重要です。期限がない目標では、達成に向けた計画が立てづらく、モチベーションの維持も難しいでしょう。
期限を設けることで、従業員は計画的に行動でき、進捗を管理しやすくなります。具体的には、以下のような期限を設定すると効果的です。
- 今年度末までに
- 上半期の終わりまでに
- 半年以内に
- 年間を通じて
このように、明確な期限を設けることで、目標達成に向けた具体的な行動計画が立てられます。
SMARTの法則をより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.人事評価・考課における目標設定のポイント
目標設定を行う際は、SMARTの法則以外にも活用できるフレームワークがあります。
ここでは、より挑戦的な目標や組織全体の方向性を意識した目標を設定するためのポイントを解説します。
FASTの法則:難易度が高い目標設定に
FASTの法則は、難易度が高い目標を設定し、それを効果的に管理するためのフレームワークです。
以下の4つの要素で構成されています。
-
F(Frequently discussed):頻繁に議論される
目標の進捗や課題を定期的にチーム内で話し合い、共有することで達成確率を高めます。 -
A(Ambitious):野心的
現状を超える成果を目指し、成長を促すような意欲的な目標を設定します。 -
S(Specific):具体的
誰が見ても理解できるように、明確な目標を立てます。 -
T(Transparent):透明性
目標と進捗を組織全体で共有し、達成状況を可視化することが重要です。
SMARTの法則と同様に、具体的な目標設定が求められますが、FASTの法則は特に高い目標を設定する際に適しています。
よりハードルの高い目標を達成したい場合に活用すると効果的です。
OKR:組織全体の方向性を明確にする
OKR(Objectives and Key Results)は、組織全体の目標(Objectives)と主要な成果指標(Key Results)を設定し、それを各部門や個人の目標と連動させる手法です。
まず、企業全体の大きな目標(Objectives)を設定し、それを達成するための具体的な指標(Key Results)を部署、チーム、個人レベルに落とし込みます。
OKRでは、組織の戦略と個々の業務を結びつけられるため、従業員は自分の目標達成が企業の成長に貢献していることを実感できます。
例えば、「新規市場でのシェア拡大」を企業のObjectiveとした場合、Key Resultsとして「半年で新規顧客100社を獲得する」などの具体的な数値目標を設定します。
従業員の目標と組織の方向性を一致させることで、目標達成の効果を最大化できます。
KPI:最終目標から逆算する
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、最終目標(KGI)を実現するために、途中で達成すべき数値目標を設定する評価手法です。
KPIを適切に設定すれば、目標達成までのプロセスが明確になり、進捗も効率的に管理できます。KPIの設定には、SMARTの法則を意識することが重要です。
例えば、営業職で「半年で売上を20%増加させる」というKGIを設定した場合、以下のようなKPIが考えられます。
- KPI1. 半年間の商談数を30件から50件に増やす
- KPI2. 半年間の受注率を1.2倍にする
このように、最終目標から逆算した具体的な指標の設定によって、目標に向けた行動をより計画的に進められます。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
7.人事評価・考課における目標設定の進め方
効果的な目標設定を行うためには、適切な進め方の理解が必要です。
ここでは、目標を適切に管理し、達成を促進するための3つのステップについて解説します。
①期初に上司と部下が納得いく目標を設定する
期初面談は、上司と部下が互いに納得できる目標を設定するための重要な機会です。この面談では、組織の方針や部門の目標を共有し、それに基づいて個人の目標を策定します。
目標を決める際には、具体的で明確な基準を設けることが重要です。達成基準が曖昧だと、評価時に不公平感が生じる可能性があります。組織の方向性と個人の成長を両立させるためにも、適切な目標設定が求められます。
期初面談のポイント
期初面談では、組織の目標と個人の目標をすり合わせ、明確な評価基準の設定が重要です。
期初面談の具体的なポイントは以下のとおりです。
- 組織の目標と個人の目標を連携させる
- SMARTの法則に基づいた具体的で測定可能な目標を設定する
- 目標の難易度や達成可能性について上司と部下で十分に話し合う
- 目標達成に必要なリソースやサポート体制を確認する
- 評価基準を明確にし、双方が納得できる形で合意する
これらのポイントを押さえることで、従業員のモチベーションを維持し、目標達成に向けた意識を高められます。
②中間面談で進捗を確認し、状況に応じて目標を見直す
設定した目標に対する進捗状況は、定期的に確認し、必要に応じて調整します。そのために、四半期ごとの中間面談がおすすめです。
中間面談により、目標達成に向けた課題を早期に把握でき、適切な対応を取れます。また、環境の変化や新たな業務の発生にともない、目標の内容や達成基準を見直すことも大切です。
柔軟な調整によって、従業員のモチベーション維持と業務効率の向上が図れるでしょう。
中間面談のポイント
中間面談では、進捗状況を正確に把握し、必要に応じて目標の見直しやサポートを行うことが重要です。
具体的な中間面談のポイントは以下のとおりです。
- 進捗状況の共有:部下が現状の進捗や課題を報告し、上司がフィードバックを行う
- 目標の再評価:業務環境の変化や新たな課題に応じて、目標の内容や達成基準を柔軟に見直す
- サポートの提供:目標達成に必要なリソースや支援を確認し、上司が適切なアドバイスを行う
定期的な進捗確認を行い、必要に応じた目標の調整によって、目標達成の確率を高められるでしょう。
③期末評価で成果を振り返り、次期の目標設定に活かす
期末評価は、設定した目標に対する成果を総括し、次期の目標設定に反映させる重要なプロセスです。
この評価を適切に行うことで、従業員の成長を促進し、組織全体の生産性向上につながります。評価の際は、達成状況だけでなく、取り組みのプロセスや努力の度合いも考慮する必要があります。
単なる結果評価にとどまらず、次の目標につなげるためのフィードバックを行うこともポイントといえるでしょう。
期末評価のポイント
期末評価では、達成度の確認だけでなく、成功要因や改善点を明確にし、次の目標につなげることが重要です。
具体的なポイントは、以下のとおりです。
- 成果の振り返り:達成度合いや取り組み内容を具体的に評価し、成功要因や改善点を明確にする
- フィードバックの提供:上司が部下に対して、具体的なフィードバックを通じて成長を促進する
- 次期目標への反映:今回の評価結果をもとに、次期の目標設定に活かし、継続的な成長を促進する
適切な期末評価によって、従業員の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上につなげましょう。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
8.人事評価・考課における目標設定の注意点
目標を設定する際は、どのような点を意識すべきか悩む人も多いのではないでしょうか。ここでは、効果的な目標設定のために注意すべきポイントを解説します。
企業全体の目標を共有する
まず、企業のビジョンや戦略を全従業員と共有することが不可欠です。
組織全体の目標が明確であれば、各部門や個人の目標が企業の方向性と一致し、一体感を持って業務に取り組めます。
また、従業員も自身の役割をよく理解できるため、個人目標の設定も容易でしょう。経営陣からのメッセージを適切に伝え、全員が共通認識を持てる体制作りが重要です。
部門ごとの目標を設定する
企業全体の目標を踏まえ、各部門は自部門の役割や業務内容に応じた数値などの具体的な目標を設定します。
部門ごとの目標が明確になれば、チームとしての方向性が統一され、業務の効率化につながります。
ただし、すべての部門が数値化した目標を設定できるわけではありません。その場合、業務プロセスや行動に焦点を当てた指標を設定します。
例えば、人事部門では「従業員エンゲージメントの向上」を目的とし、「従業員満足度調査のポジティブ回答率を80%以上にする」といった目標を立てます。
目標は上司とすりあわせる
目標設定の際は、1on1ミーティングなどを活用し、上司と従業員が十分に話し合って目標の内容や達成基準を擦り合わせることが重要です。
双方の認識にズレがあると、評価に対する納得感が得られず、不満につながる可能性があります。また、押し付け型の目標設定は従業員のモチベーション低下を招くため、避けましょう。
従業員が納得し、自ら取り組める目標を設定することで、主体的な行動が促され、成果につながるでしょう。
従業員主導で目標を立てる
目標設定の段階では、従業員が主体的に関わることが重要です。自ら目標を設定できれば、業務への責任感が生まれ、目標達成への意欲が高まります。
ただし、完全に従業員の判断に任せるのではなく、上司とすり合わせながら、組織の目標と整合性を取ることが大切です。
組織の方向性と個人の成長を両立させることで、従業員のモチベーション向上と企業の業績向上の両方を実現できるでしょう。
従業員の目標設定をサポートする
目標設定に慣れていない従業員や、適切な目標を考えるのが難しい従業員に対しては、上司がサポートを行うことが重要です。
目標が不明確なままでは、達成に向けた行動がとりづらくなり、評価時の納得感も得られません。上司は、従業員が努力次第で達成可能なやや高めの目標を設定できるように導く必要があります。
目標達成により、従業員の自信が高まり、モチベーション向上につながるため、適切な支援を行うことが大切です。
PDCAサイクルを回す
目標達成に向けて、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)のPDCAサイクルを回すことも効果的です。定期的に進捗を確認し、必要に応じて目標やアプローチを見直すことで、柔軟かつ継続的な成長が期待できます。
また、上司が評価を行う際は、目標の精度を高めるために有益で具体的なフィードバックを提供しましょう。適切なフィードバックを繰り返し行い、従業員の成長を支援し、組織のパフォーマンス向上につなげます。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
9.人事評価・考課における目標設定例・例文
人事評価の目標は、職種ごとに適した内容を設定する必要があります。ここでは、各職種に応じた具体的な目標設定例を紹介します。
営業職
営業職の目標設定では、売上や新規顧客獲得など、数値ベースの目標が重視されることが一般的です。しかし、目先の数値だけを追い求めると、顧客との信頼関係が損なわれたり、将来的な事業成長が停滞したりするおそれがあります。
そのため、数値目標と顧客満足度の両立が大切です。さらに重要なのが、売上や利益の向上につながる具体的な行動を示した目標設定です。
例えば、以下のとおりです。
- 新規顧客獲得数の増加:四半期ごとに新規顧客を10社獲得し、売上を20%向上させる
- 既存顧客のリピート率向上:定期的なフォローアップを実施し、既存顧客のリピート率を15%向上させる
- 情報共有の強化:1週間に一度、ヒアリングで得た情報を関係者間で共有する
事務職
事務職はルーティン業務が中心であるため、数値を用いた目標設定が難しい傾向があります。そのため、業務の効率化や正確性の向上に焦点を当てることが効果的です。
例えば、以下のとおりです。
- 業務プロセスの効率化:書類管理システムを見直し、デジタル化の推進により、書類検索時間を30%短縮する
- コスト削減:ペーパーレス化を推進し、コピー用紙の使用量を前年より20%削減する
- スキルアップ:業務に関連する資格(例:MOS、簿記2級)を取得し、業務の幅を広げる
人事・労務
人事・労務部門では、採用や人材育成、労働環境の改善に関する目標の設定が一般的です。
例えば、以下のとおりです。
- 採用プロセスの改善:新卒採用の応募者数を前年より20%増加させ、内定承諾率を10%向上させる
- 研修の実施:今期中にハラスメント研修を実施し、従業員からの相談件数を年間3件以内に抑える
- 労務管理の強化:勤怠管理システムを導入し、残業時間を月平均10時間削減する
販売・接客
販売・接客業では、顧客対応の質や具体的な販売数、売上額などを目標として設定できます。
例えば、以下のとおりです。
- 顧客満足度の向上:月間の顧客アンケートで満足度90%以上を達成する
- サービスの質向上:クレーム件数を月5件以内に抑える
- 販売スキルの向上:新商品の提案力を高め、関連商品の売上を15%増加させる
企画・マーケティング
企画・マーケティング部門の目標設定では、数値で評価できる指標に加え、新たなアイデアや施策の提案も重視されます。
例えば、以下のとおりです。
- 新規プロジェクトの立ち上げ:市場調査を基に、新商品の企画を半年以内に3件提案し、そのうち1件を商品化する
- アクセス数の改善:Webサイトの月間アクセス数を前年同月比で20%向上させる
- デジタルマーケティングの強化:SNSを活用したキャンペーンを実施し、フォロワー数を20%増加させる
エンジニア・技術職
エンジニア・技術職の目標設定では、個人のスキルアップとプロジェクトの遂行に関する目標を両立させることが重要です。
例えば、以下のとおりです。
- 新技術の習得:最新のプログラミング言語を学び、今期中に社内ツールを1つ開発する
- 業務の効率化:開発工程を効率化し、プロジェクトの所要時間を15%短縮する
- 新技術の導入:四半期に1回以上、新技術のプレゼンテーションを実施する
- システムの安定稼働:サーバーの稼働率を99.9%以上に維持し、障害発生時の対応時間を平均30分以内に抑える
管理職
管理職の目標設定では、部下の育成やチームの生産性向上に関する目標が中心となります。
例えば、以下のとおりです。
- チームの生産性向上:業務プロセスを見直し、チーム全体の生産性を半年で15%向上させる
- 部門間の連携:部門間の連携を強化し、クロスファンクショナルなプロジェクトを年2件以上立ち上げる
- 部下の育成:部下一人ひとりに対して月1回の1on1ミーティングを実施し、チームの目標達成率を90%以上に引き上げる
- 労働時間の適正化:部署全体の平均残業時間を月20時間以内に抑える
医療・福祉職
医療・福祉職の目標設定では、患者や利用者の満足度向上や自己のスキルアップなどの要素を考慮することがポイントです。
例えば、以下のとおりです。
- 満足度の向上:患者アンケートの総合満足度を5段階中4.5以上に引き上げる
- 専門資格の取得:6ヶ月以内に認定看護師の資格を取得し、取得後は学んだ知識を現場で活用する
- 専門的なスキルアップ:最新の医療技術に関するセミナーへ四半期に1回以上参加し、知識をアップデートする
- チームワークの強化:月に一度、他職種との連携会議を開催し、情報共有を促進する
公務員
公務員の目標設定では、行政サービスの質向上や業務効率化に関する目標が中心となるでしょう。
例えば、以下のとおりです。
- 市民サービスの向上:窓口対応の平均待ち時間を20分から15分に短縮する
- 業務の効率化:行政手続きのオンライン化を推進し、電子申請システムの利用率を30%から50%に向上させる
- 政策提案の実施:地域活性化を目的とした新しい政策を3件提案し、そのうち1件を年度内に実施する
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など