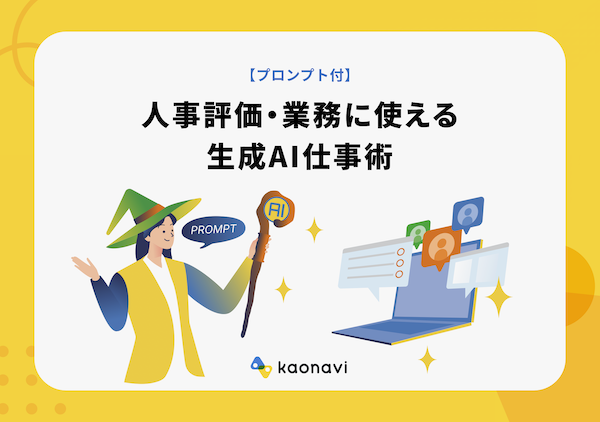社内の職位や職責をわかりやすく可視化しませんか?
タレントマネジメントシステムで、時間がかかる組織の見える化を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
日本の一般企業では職位、職責、役職、階級などという言葉が頻繁に使われています。しかし正確にその違いを説明できるでしょうか。「職位と役職って同じじゃないの?」と混同している人もいるでしょう。
- 職位とは?
- 職責とは?
- 職位の具体例
- 職階、役職、階級、等級など職位の類語とその違い
上記について、本記事で詳しく解説します。
目次
【コピペで完結】
目標管理、評価シートの「下書き」はAIにお任せ。 悩む時間を減らす実務プロンプト集
1.職位とは?
職位とは、組織内における特定の「役割」と「責任の範囲」を定義した、仕事上の地位のことです。単なる呼称ではなく、そのポジションに求められる任務、権限、貢献レベルを明確にするための、組織設計の根幹をなす概念です。
多くの企業で「役職」や「肩書き」と混同されがちですが、厳密には異なります。たとえば、「営業部長」という職位には、「営業部門全体の目標達成責任を負い、予算策定やメンバーの育成を行う」といった具体的な役割と責任が紐づいているのです。
職位を明確にすることで、責任の範囲や仕事内容がはっきりするため、マネジメントやコミュニケーションが円滑になるメリットがあります。
一般的な企業に存在する職位は、下記の通りです。
- 主任
- 監督者
- 係長
- 課長補佐
- 課長代理
- 課長
- 次長
- 部長
- 監査役
- 常務
- 専務
- 副社長
- 社長
- 会長
英語では
職位を英語表記にすると、「duty position」「employment position of rank」などと表現します。
職責とは?
職責とは、特定の職位に伴って発生する「果たすべき具体的な義務や責任」を指します。職位が「ポジションそのもの」を指すのに対し、職責はそのポジションが「何をすべきか、何に対して責任を負うか」という中身を説明する言葉です。
たとえば、「プロジェクトマネージャー」という職位には、以下が含まれます。
- 「プロジェクトの納期と品質を担保する」という職責
- 「予算内でプロジェクトを完遂させる」という職責
- 「チームメンバーのタスク進捗を管理し、課題解決を支援する」という職責 など
職務記述書(ジョブディスクリプション)は、まさにこの職責を言語化したものと言えます。人事制度のしっかりした企業では、部長や課長など役職ごとに職責を一覧にまとめているケースもあります。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
1on1の基本的なやり方や、質問方法について解説!
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
- 評価シートが自在につくれる
- 相手によって見えてはいけないところは隠せる
- 誰がどこまで進んだか一覧で見られる
- 一度流れをつくれば半自動で運用できる
- 全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.職位の類語とその違い
職階との違い
職階とは、仕事の内容や責任の軽重、種類などによって分類して定めた階級のことで、職務上の階級ともいいます。たとえば、国家公務員や地方公務員には「職階制」があります。
同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職位または職について、同一の資格要件を必要とするとともに、かつ、当該職位に就いている者に対して、同一の幅の俸給が支給されるように定められた制度です。
役職との違い
役職とは、組織の階層構造における特定の「ポスト(地位)」を示す呼称です。一般的に「部長」「課長」「係長」といった、指揮命令系統上のポジションを指します。
職位と役職の最も重要な違いは、その焦点にあります。職位が「そのポジションが果たすべき機能や責任(What)」を定義するのに対し、役職は「組織図上の呼称や序列(Name/Rank)」を示すものです。
たとえば、ある企業に「東日本営業部長」と「西日本営業部長」という2つの職位が存在する場合、両者は担当エリアという点で異なる「機能・責任」を持ちます。しかし、役職はどちらも「部長」です。このように、職位は役職よりも具体的で、業務内容に密着した概念であると理解するとよいでしょう。

役職とは?【一覧でわかりやすく】会社の役職名と肩書きを解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてサービス概要を見る
...
階級との違い
階級とは、軍隊などに見られる地位といった上下に分かれる「位」や階層のこと。日本では自衛隊や警察で階級が使用されており、組織における上下関係や指揮系統をはっきりと区別しています。
階級にもそれぞれの任務が課せられており、職位との違いを見た場合、同じような意味として捉えることもできるでしょう。
等級との違い
等級とは、従業員の能力、貢献度、経験などを評価し、処遇(給与や賞与など)を決定するために設定される「序列・ランク」のことです。「G1」「M3」のように記号で示されることが多く、人事評価制度の根幹をなします。
職位が「組織上の役割」を示すのに対し、等級は「個人の能力や貢献レベル」を示すものです。そのため、同じ職位であっても等級が異なるケースは珍しくありません。
【具体例】
- 「課長になったばかりで、まだ定型業務のマネジメントが中心」のAさん(例:M1等級)
- 「課長として複数年の経験があり、部門横断的な課題解決も担う」Bさん(例:M2等級)
このように、等級は職位をさらに細分化し、個人の成長や貢献度をより精緻に処遇へ反映させるための仕組みです。

職能資格制度とは? 職務等級制度との違い、メリットデメリット
職能資格制度など人事制度の導入や見直しには人事担当の余裕が必要不可欠!
カオナビで人事業務の負担を減らし、業務の余裕をつくりませんか?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアク...
社内の職位や職責をわかりやすく可視化しませんか?
タレントマネジメントシステムで、時間がかかる組織の見える化を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
3.職位の具体例
社員、主任、課長、部長など、職位をポジションと捉えた場合の具体例を紹介します。
一般社員
社員とは、特定の役職に就いていない一般的な社員のことで、平社員や一般社員とも呼ばれます。また通常、社員は正規に雇用されている労働者のことを指し、アルバイトや派遣社員、契約社員など非正規社員は含まれません。
主任
主任とは、企業やグループなど組織をまとめるリーダー的存在のこと。新しいプロジェクトを立ち上げた際など、係長以下の職位が必要になったときに主任を置くことがあります。強い上下関係はなく、わかりやすくいうとグループリーダーというイメージです。
係長
業務を行う最小単位を係といいますが、そのトップが係長です。一般的に係は課の下に属しているので、係長は課長の下で主任や社員をまとめる管理的立場となります。主任とも近いですが、肩書きが付くため地位は上がります。
課長
課長とは、部の中に設置された「課」という単位の業務執行責任者であり、多くの企業で「中間管理職」の中核を担う職位です。
主な役割は、部長が策定した部門方針に基づき、課の具体的な目標を設定し、メンバー(係長、主任、一般社員)の業務進捗を管理しながら目標達成に導くことです。単なるプレイングマネージャーではなく、部下の育成、業務プロセスの改善、他部署との調整など、戦術レベルでのマネジメント全般を担います。
経営層の視点と現場の視点の双方を理解し、両者の橋渡し役となることが期待されます。

課長とは?【簡単に】役割、年収、部長との違い、代理、補佐
課長とは、ひとつの課の事務を統括管理する役職です。ここでは、課長について、いくつかのポイントから解説します。
1.課長とは?
課長とは、官庁や会社など組織にある課の業務を、総括・管理・統制・監督する...
次長
次長とは、部門管理者の次に当たる存在です。企業など組織では、部長を補佐する役職が多く、課長よりも上という立場です。一般的に「営業部次長」などと部署名を付けることが多いでしょう。
業務内容は、部署内の運営事務の統括や、部長代理といったものになります。
部長
部長とは、営業部や開発部といった「部」単位の最高責任者です。課長が戦術レベルのマネジメントを担うのに対し、部長は担当部門全体の戦略立案、予算策定・管理、最終的な意思決定など、より経営に近い視点での事業運営を担います。
多くの場合、取締役会などで決定された全社戦略を、自身の担当部門の具体的な事業計画に落とし込む役割を持ちます。部門全体の業績責任を負うと同時に、将来の事業を担う人材(次期課長など)の育成や、組織文化の醸成といった長期的な視点での貢献も求められる、極めて重要な職位です。
事業部長、本部長
企業では部長が複数存在する場合がありますが、その際、その中の代表となる人を本部長、または事業部長と呼ぶのです。または、数ある事業部の本部における最高責任者を指すことも。部長は役員との立場を兼務していることが多いです。
監査役
監査役とは、取締役および会計参与の職務執行を監査し、健全かつ適正な企業経営を実現する役割を担う役員のこと。取締役と同じく、3人以上の監査役がいれば監査役会という機関を設置できます。
専務
専務とは、一般的に社長の補佐をするポジションにある場合が多く、会社の管理や監督業務に携わり、取締役会にも参加して会社の意思決定を行うのです。社長不在のときは社長代理として、業務を代行することもあります。
代表取締役、社長
代表取締役と社長を別個にしている企業もありますが、代表取締役社長と兼務する場合も非常に多いといえます。
代表取締役社長は社の顔といえる存在です。中には代表取締役社長の上に会長が置かれていることもありますが、退任した社長の席という認識がほとんど。そのため実質のトップは代表取締役社長となります。

代表取締役とは? 社長・取締役との違い、代表権について
代表取締役とは会社法の規定にある呼称です。代表取締役はどんな人が就くのでしょうか。権限や任期、また取締役社長との違いなど、代表取締役について詳しく解説します。
1.代表取締役とは?
代表取締役とは、...
会長
会長とは、社の代表ではありますが、退任した社長や会社の創業者などが名誉職としてポストに就くケースが多いです。会長が社長の上に置かれていても、実務を行っているのは社長なので実務上では社長が最も権限を持っていることになります。
社員の情報を一元管理して、データドリブンな人材配置を行うには?
職位・職責を上手く配置するポイントを解説!
⇒資料を無料ダウンロードする
4.自社の職位制度のチェックリスト
まずは、自社の職位制度がどこまで機能しているのかを把握することから始めましょう。以下の「セルフ診断チェックリスト」を活用すれば、次に取るべき具体的なアクションが見えてきます。
◆ 原則1:経営戦略とのつながり
- 職位制度は、企業理念や事業戦略と明確に結びついているか?
- 各職位の役割は、組織目標の実現に貢献するよう設計されているか?
◆ 原則2:公平さと透明性の確保
- 職務記述書などを通じて、各職位の役割・責任が明文化されているか?
- 昇進・昇格の基準が明確で、社内に公開されているか?
- 評価結果と報酬(給与・賞与)の関係が納得できる形で説明されているか?
◆ 原則3:柔軟な運用体制
- 組織や事業の変化に合わせて、職位の定義を定期的に見直しているか?
- 管理職以外にも、専門職など多様なキャリアパスが用意されているか?
- 職位制度に対する意見や改善提案を現場から吸い上げる仕組みがあるか?
◆ 現場での活用度
- 従業員は、「誰に何を相談・報告すればよいか」を迷わず行動できているか?
- 管理職は、職位に応じた目標設定と部下育成を適切に実践できているか?
診断結果の目安
チェックが8個以上
素晴らしい状態です。制度が実際に機能しており、運用面でも高い完成度がうかがえます。今後も継続的な改善を意識しましょう。
チェックが4〜7個
基盤はできているものの、見直しの余地があります。チェックがつかなかった項目を中心に、優先順位をつけて改善に取り組んでみてください。
チェックが3個以下
制度が形だけのものになっている可能性があります。この記事の内容を参考に、制度の再構築に本格的に取り組むことをおすすめします。
社内の職位や職責がすぐにわからず困っていませんか?
タレントマネジメントシステムで、時間がかかる組織の見える化を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
5.職位に関するよくある質問(Q&A)
1. 中小企業でも職位制度は必要でしょうか?
はい、必要です。
むしろ、会社が小さいうちから職位の仕組みを取り入れておくことで、将来的な成長の土台になります。最初から複雑な制度を作る必要はありません。
たとえば「メンバー」「リーダー」「マネージャー」など、シンプルな3段階でOKです。各ポジションの役割と責任を明確にするだけで、組織運営がスムーズになります。
会社の成長にあわせて、制度を少しずつブラッシュアップしていくと良いでしょう。
2. 役職がない「平社員」はどう扱えばよいですか?
「一般職」や「メンバー」として職位に位置づけるのが一般的です。
役職がないように見えても、「責任を持って担当業務をこなす」という役割を持つ職位です。役割がはっきりすれば、本人の意識や周囲の評価も安定します。
さらに「メンバーレベル1」「レベル2」のようにスキルや経験で段階をつければ、役職がなくても成長を実感でき、やる気の維持にもつながります。
3. 降格を行う場合、どんなことに注意すればよいですか?
降格は社員に大きな影響を与えるため、慎重に対応する必要があります。以下の3つがポイントです。
| ポイント | 詳細 |
| 就業規則の確認 | 降格のルールが、就業規則に明記されているかをチェックしましょう。 |
| 客観的で納得できる理由 | 能力不足や勤務態度の問題など、誰が見ても納得できる明確な根拠が必要です。 |
| 丁寧なコミュニケーション | 一方的に通告するのではなく、本人としっかり面談し、理由や今後への期待を伝えることが大切です。 |
4. 「フラットな組織」では職位は不要ですか?
完全に職位が不要というわけではありません。
フラットな組織は、決定のスピードが速くなったり、風通しが良くなったりするなどの利点があります。
ただし、「プロジェクトリーダー」や「技術スペシャリスト」など、役割を明確にするための「職位のような呼び方」は必要です。これにより、誰が何を担当し、責任を持っているのかが明確になります。
ポイントは、上下関係ではなく「機能と役割」に基づく柔軟な体制を作ることです。
【人事業務を大幅に効率化できます!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
- 評価シートが自在につくれる
- 相手によって見えてはいけないところは隠せる
- 誰がどこまで進んだか一覧で見られる
- 一度流れをつくれば半自動で運用できる
- 全体のバランスを見て甘辛調整も可能