従業員個々のパフォーマンスを最大化し、経営目標の達成から企業の成長・発展へと導くには、人材育成が欠かせません。しかし人材育成にはさまざまな手法があるため、どのように自社で実践していけばよいか迷ってしまう方も多いでしょう。
今回は人材育成について、目標や課題、解決策となる具体的な手法・施策、人材育成計画の立て方などを詳しく解説します。
目次
1.人材育成とは?
人材育成とは、企業の成長や発展、経営目標の達成に貢献できる人材を育成することです。単に人材の能力を高めるだけでなく、その能力で経営目標の達成や成長・発展などの成果につなげることが重要です。
そのためにも、人材育成は「自社の目標」とリンクさせる必要があります。企業によって必要な人材は異なるため、計画的かつ戦略的な育成ができるかが重要です。
人材育成と人材開発の違い
人材開発とは、従業員のもとある能力・スキルを向上し、成長を促進させること。従業員が個々にゴールを設定して、必要な手段で能力向上を目指します。
人材育成は経営目標とリンクし、自社の成長や目標達成を目的として育成が行われるものの、人材開発は個人が自ら望んで学びます。
つまり人材育成は企業の目標とマッチしますが、人材開発は必ずしもそうとはかぎりません。一方、人材開発が企業の成果と両立する場合もあります。

人材開発とは? 具体的な仕事内容や進め方、人材育成との違いを解説
企業成長につながる人材開発を効率的に実施できる!
人材情報を一元化してスキル管理をスムーズにするタレントマネジメントシステム「カオナビ」
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアク...
人材育成と能力開発の違い
能力開発とは、個人がスキルや能力を向上させること。能力開発は、特定のスキルを向上させるために用いられる表現で、人材育成のひとつです。
人材育成は業務全般における能力向上である一方、能力開発はスキル・能力単位での育成を指します。つまり、人材育成と能力開発では、育成の粒度に違いがあるのです。
2.人材育成の目標
人材育成の最大の目標は、組織全体の成果や競争力を高めること。ここでは、その具体的な目標を詳しくご紹介します。
- スキルや知識の向上
- 生産性の向上
- 人材の流出防止
- リーダーシップの育成
- 従業員のキャリア開発・自己実現
①スキルや知識の向上
業務に必要なスキルや知識を向上させると業務の質も向上し、業績アップに貢献します。専門性が高まるため、成果も生み出しやすくなるのです。
②生産性の向上
少子高齢化による労働人口の減少により、多くの企業で人材確保が困難な状況にあります。限りあるリソースのなかで最大限成果を上げるには、生産性向上が重要です。
人材育成により従業員の能力が向上すれば、生産性の向上につながるでしょう。一人が三人分の働きをすれば、人手が足りなくても生産性や業務の質も低下せず、むしろよい成果を生み出せます。
③人材の流出防止
優秀人材やコストをかけて採用した人材の流出は、企業にとって大きな損失です。とくに、優秀人材の離職は競争力の低下にもつながります。今いる人材も育成によっていずれ大きな戦力、ひいては将来のリーダー候補になる可能性もあるでしょう。
人的資本経営が重要視されているように、企業に価値を生み出すのは人材です。流出自体が企業の成果や競争力に影響をおよぼしてしまうため、人材育成で流出を防止しつつ、従業員の戦力化を図ることが求められます。
④リーダーシップの育成
企業にとって、後継者の育成も重要な課題です。長期的な目線で人材育成に取り組むと、将来のリーダー育成につながります。人材の流出防止とあわせれば、企業への理解が深く、かつ能力の高い人材をリーダーとして輩出できるでしょう。
企業が発展するためには、優れたリーダーが欠かせません。その点で、長期的に計画的かつ戦略的な人材育成が重要です。

リーダーシップとは? 種類や理論、ある人の特徴、高め方を解説
リーダーシップは、組織やチームを成功へ導くために必要不可欠な能力です。現代のビジネスやコミュニティでは、その重要性がますます高まり、リーダーシップのスタイルも多様化しています。
この記事では、リーダー...
⑤従業員のキャリア開発・自己実現
目まぐるしく変化するなか企業が発展するには従業員の発展が欠かせません。中長期的な視野での成長が求められます。
キャリア開発や自己実現にもとづく人材育成は、従業員のモチベーション向上につながり、結果戦力となる人材が生まれ、企業の成果に貢献します。

キャリア開発とは? メリット、具体的な手法、企業事例を解説
現代のビジネス環境では、終身雇用や年功序列といった従来の雇用形態が崩れつつあり、企業と従業員の双方に新たなキャリア戦略が求められています。
また、デジタル技術の急速な進化に伴い、適応力のある人材育成が...
3.人材育成が重要な理由
人材育成が重要な理由は、企業に利益や価値をもたらすのは「人材」であるからです。従業員の能力は商品やサービスの質、企業の利益に直結します。
価値や利益を創造する当人の能力が十分でないと企業の発展は見込めないため、人的資本経営が重要視されているのです。
市場変化も激しく競争が激化しているなか、企業が優位性を確保するにはイノベーションが必要であり、それを生み出すのも人材といえます。また、少子高齢化によって労働人口が減少するなか今いる従業員を育成し、企業に貢献してもらう必要があるのです。
人材育成に力を入れている企業は従業員の価値が高まるだけでなく、採用力の強化にもつながります。くわえて技術革新はどんどん進んでいるため、対応できる人材を生み出すためにも育成が必要です。
時代の流れに遅れず企業をつねに発展へと導くには、人材育成による人材のアップデートが欠かせません。
4.人材育成の具体的な手法と施策
企業によってマッチする人材育成の手法・施策はさまざまです。自社の課題や育成したい人材像に合わせて、最適な手法・施策を取り入れるとよいでしょう。ここでは人材育成の具体的な手法と施策をみていきます。
- OJT
- OFF-JT
- eラーニング
- 自己啓発
- メンター制度
- 目標管理制度(MBO)
- タレントマネジメント
①OJT
先輩社員によるマンツーマンの指導のもと経験を積んでいきます。実際の現場・業務に触れながら仕事を覚えていけるため、新人の早期戦力化に有効です。代表的な人材育成の手法であり、主に新人育成に用いられます。
メリットは、進捗を確認しながら育成スピードや内容を調整できること。一方、OJTする側の能力によって育成の度合いにばらつきが出る、OJTする側の業務負担が増えるといったデメリットもあります。
OJTに依存しすぎず、主体性や自律性を促すような育成や自律的に学べる環境も用意することがポイントです。

OJTとは? 意味、教育や研修の方法、OFF-JTとの違いを簡単に
OJTとは、実務を通してマンツーマン指導により知識・スキルを身につける育成手法です。実務を通した研修となるためスキル・知識の定着化が早く、新人や未経験者の早期戦力化に期待できます。
OJTとは何かをふ...
②OFF-JT
職場以外で行う研修のことで、ビジネスマナーやマネジメント研修といった集合研修やセミナーなどが、OFF-JTに該当します。
OFF-JTは、現場から離れるためじっくり学べる点が特徴です。役職や業務別に従業員が身につけるべき能力や伸ばしてほしい能力にフォーカスし、細分化して取り入れると効果的でしょう。
専門家から学べるため、個々が学べるスキルにばらつきが生じないメリットがある一方、研修参加費や交通費などのコストがかかる、業務が忙しいと時間が確保できないなどのデメリットもあります。

OFF‐JTとは|OJTとの違い、メリットや具体例などを紹介
人材情報から戦略的育成を!
カオナビならOFFJTなどの研修履歴がわかるから、計画的な人材育成ができます。
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロー...
③eラーニング
ネット上で研修を受けられるeラーニングは、時間や場所にとらわれず人材育成ができ、移動コストがかからない点がメリット。Off-JTのデメリット解消にも有効な手法です。
eラーニングには、オンデマンド配信だけでなく、Web会議ツールを用いてリアルタイムに研修が受けられるものも。体系的にスキルや知識を身につけるのに適しており、全国に拠点がある企業でも従業員が一律で同じ研修を受けられます。

eラーニングとは|システム、導入事例、導入時のポイントなど
eラーニングとは、インターネットを通して学習や研修を行う方法のこと。インターネットの普及とともに、企業の教育施策に取り入れられるようになりきました。
eラーニングとは何か
eラーニングの種類
eラー...
④自己啓発
従業員が自発的に書籍や勉強会などでスキルや知識を取り入れていくこと。福利厚生によくみられる資格取得支援制度や書籍購入費補助などは、自己啓発のために設けられています。
自己啓発は従業員が自らのキャリア開発や職務に必要なスキル習得を目指して、自発的に取り組むことがポイントです。企業によっては、従業員がキャリアや習得したいスキルを選択しやすいようプログラムを用意するケースもあります。
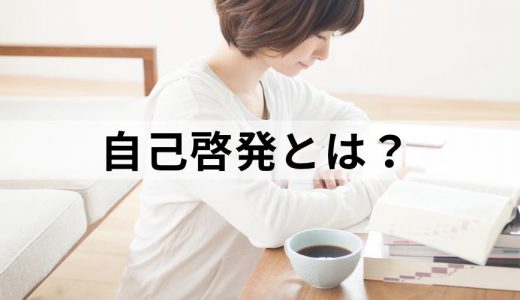
自己啓発とは? 意味や仕事での効果、やり方や具体例を簡単に
自己啓発とは、自分に本来備わっている能力を伸ばすために行う行為のこと。
自己啓発では、精神的な成長を促して、
より高い能力
より大きい成功
より充実した生き方
より優れた人格
などを目指していきま...
⑤メンター制度
近い立場の先輩社員が後輩社員をサポートする手法です。OJTは実務的なスキルを身につけることを目的としている一方、メンターは精神的なサポートが主な目的です。
信頼関係を構築し、相談しやすい環境をつくるため、心理的安全性の確保や早期離職の防止、定着率の向上にもつながります。精神面のケアも両立するため、安心できる環境で人材育成に取り組めるようになるでしょう。

メンター制度とは? メリット・デメリット、成功事例を簡単に
1.メンター制度とは?
メンター制度とは、年の近い先輩社員が新入社員や若手社員をサポート・育成する制度のこと。業務に関する支援だけでなく、人間関係やキャリアなど、幅広くサポートする点が特徴。不安や...
⑥目標管理制度(MBO)
目標を立てて、進捗や度合いを評価する手法です。一方的な評価ではなく、個人で設定した目標を共有し、定期的に自己評価を行います。自己評価によって内省機会が得られ、目標達成に向けて自ら工夫・改善に取り組めるようになり、自律的な育成に役立つのです。
人材育成に活用する際は、個人で設定する目標と経営目標がリンクしているかどうか、をチェックしておきましょう。

目標管理制度とは? 意味や目的、メリット・デメリットを簡単に
マネジメントで有名な経営思想家ピーター・ドラッカーが提唱した、組織における目標管理制度(MBO)。この目標管理制度は、組織貢献と自己成長の両方が達成できる個人目標を設定させ、その達成度で評価を行う人事...
⑦タレントマネジメント
タレントマネジメントは、個々の適性や潜在能力を引き出すマネジメント手法です。適材適所な人材配置や戦略的な育成、個を尊重した育成を可能とします。
従業員の強みを引き出し、不足部分は研修で補いながら、自身の能力が最大限発揮できるように育成するものです。
タレントマネジメントを人材配置に生かせば、適材適所な配置で個々のパフォーマンスも最大化し、モチベーション向上にもつながります。

タレントマネジメントとは? 意味や目的、導入の進め方を簡単に
タレントマネジメントに必要な機能が揃っています!
タレントマネジメント特化のシステム「カオナビ」で、時間がかかる人事課題を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
5.人材育成で大切なこと
人材育成を成功させるためには、以下のポイントが大切です。ここでは、人材育成において大切なことをお伝えします。
- 人材育成の目的を明確にする
- 経営陣・部門責任者・人事が連携して取り組む
- 階層別に適した人材育成を行う
- 実践機会とサポート体制を整える
- 指導側の育成にも力を入れる
- 人材育成の進捗・成果を見える化する
①人材育成の目的を明確にする
人材育成は組織を成長・発展に導く人材を生み出すこと。よって経営目標とリンクし、目的を明確にしたうえでの育成が重要です。闇雲な人材育成では、本当の意味での人材育成は達成されません。
また目的が明確なら、人材育成が効率的に進みます。まずは自社の課題や経営目標を明確にしたうえで、達成・解決のために必要な人材を定義し、人材育成の目的としましょう。
②経営陣・部門責任者・人事が連携して取り組む
人材育成と経営目標とリンクさせるのはつまり、人材育成に企業全体で一体的に取り組むと同じこと。よって人事や各部門が独立した状態で人材育成に取り組まないよう、注意しましょう。
人材育成の重要性や位置づけ、ミッションやビジョンの達成に必要な人材の定義などについては、全体で共通認識をもつことが大切です。
③階層別に適した人材育成を行う
新入社員・中堅社員・管理職と階層別に適した人材育成を行いましょう。下記は、階層別に求められる人材育成のポイントです。
- 新入社員:自社の経営理念やビジョンを理解する・ビジネスマナーなどの基礎を身につける・業務に必要なスキルや知識を身につける・メンタル面に注視した育成:早期離職の防止
- 中堅社員:組織の中枢となる重要なポジションとの意識づけ・育成者としてのスキルを向上させる・管理職を見据えたマネジメントスキルの習得
- 管理職:経営的視点の養成・評価スキルを身につける
企業によって、各階層に求める姿やスキルレベルは異なるもの。育成の指針となるよう、各階層に求める姿をしっかり定義するとよいでしょう。

階層別研修とは? 目的と内容例、メリット、体系図の作り方
階層別研修とは、社員を階層ごとに分けて異なる内容の研修を受講させること。ここでは階層別研修の目的や種類、実施のポイントなどについて解説します。
1.階層別研修とは?
階層別研修とは、社員を階層ごとに...
④実践機会とサポート体制を整える
体系的に学んでいるだけでは、スキルや知識が自分のものとして定着しません。そのためインプットだけでなく、実践機会を設けてアウトプットし、知識・スキルが自分のものとして身につくよう育成することが大切です。
本人に任せるだけでなく、学んだことが生かせる業務やプロジェクトに企業側で配置したり、そのためのサポート体制を整えたりするのも求められます。
⑤指導側の育成にも力を入れる
指導側の育成も大切です。育成側のスキルや知識が十分でなかったり、指導方法がなっていなかったりすると、効果的な人材育成は望めません。管理職やOJTを行う従業員の研修参加や指導経験を積む機会が後回しにならないようにしましょう。
そうした環境を実現するためにも、既存業務の負担を軽減できるよう調整する、人材育成の意義を理解してもらうなどして経営陣や人事側からアプローチすることが大切です。
⑥人材育成の進捗・成果を見える化する
目標を達成するための進捗、その成果が見える化していると、人材育成のPDCAを効率的に回せます。目標管理制度や1on1などで進捗を確認しながら、必要に応じて目標の追加・変更、必要な施策を実行していくことが大切です。
従業員の目標達成度やスキルレベルを客観的・定量的に把握するためには、タレントマネジメントシステムといったツールの導入も視野に入れましょう。進捗や成果が見える化するために人材育成も管理でき、効率的かつ効果的な人材育成に取り組めます。

1on1ミーティングとは? 目的や効果、やり方、話すことを簡単に
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入する...
6.人材育成の課題と解決策
厚生労働省が発表した『平成30年版 労働経済の分析』による、人材育成における課題のトップ5は以下のとおりです。
従業員の業務が多忙で、人材育成に充てる時間を確保できない
- 上長等の育成能力や指導意識が不足している
- 従業員が能力開発に取り組むため不在にしても、その間、ほかの人が業務を代替できる体制が構築できていない
- 人材育成を受ける従業員側の意欲が低い
- 社内で人材育成を積極的に行う雰囲気がない
ここでは、上記5つの課題とその解決策をみていきます。
①人材育成の時間が確保できない
人材育成は通常業務と並行して行うため、人手不足の企業にとってはリソース面での課題が大きいでしょう。しかし中長期的な視点から人手不足を解消するためにも、人材育成は欠かせません。
人材育成が後回しにされないためにも、育成担当者の業務量を調整したり、チームで協力して育成に取り組んだりするなど、人材育成へのサポート体制を整える必要があります。
②指導側の育成スキル・指導意識が不足している
指導側の育成スキルや指導意識が不足していると、人材育成の質も低下してしまいます。まずは指導側の意識改革や育成に必要なスキルが身につけられる業務・研修など学べる機会を提供することが重要です。
③社内のリソースが十分でない
OFF-JTで現場を離れた時のポジションが埋められない、育成担当者の業務を分担できないなど、社内リソースが十分でない環境下では、満足に人材育成に取り組めないでしょう。
人材育成を行う際は周囲に協力を呼びかけるだけでなく、現場の状況を把握したうえで無理のない育成を進めていくとよいでしょう。
④育成される側の意識が低い
指導側に問題がなくとも、育成される側が受け身であったり、意欲的でなかったりする人材育成の効果を発揮できません。育成される側の意識を改革するには、育成の目的や重要性を理解してもらう、明確な目標を提示することがポイントです。
評価項目に育成に関連する基準を取り入れると、意欲的に取り組めるようになるでしょう。
⑤社内で人材育成を行う雰囲気がない
年功序列の評価制度が確立している、こなすだけの業務が多く自発的に成長しようと思えない環境では、人材育成を行う雰囲気も生まれません。社内で人材育成に取り組む風土を醸成するためにも、人材育成の重要性について共通認識を持つことが重要です。
そのうえで、個々の頑張りが評価される仕組みの構築や従業員が自発的に学べる仕組みを整えることが求められます。
7.人材育成計画の立て方
人材育成計画は、以下のステップで進めていきます。
- 現状を把握する
- 人材育成の目標を設定
- 段階的な目標を設定
- 必要な施策・リソースの明確化
- 実行・評価・改善
①現状を把握する
まずは現状の把握から課題を抽出し、必要な人材を定義します。誰がどのような能力を持っているか、どのような業務を担当しているか、どのポジションに配置されているかを確認しましょう。
人材管理システムがあれば、効率的に現状が把握でき、的確に課題も抽出できます。情報収集・測定環境を整えておくこともポイントです。
②人材育成の目標を設定
目指す姿と現状のギャップから、企業における人材育成の目標を設定します。理想と現実のギャップを埋めるための人材像をイメージし、リーダー候補となる人材を3年で10人育成するのように、目標を数値化するのもポイントです。
③段階的な目標を設定
従業員のキャリアや役職に応じて、段階的な目標を設定します。このとき、いつまでにどれくらいのスキルを身につけていればよいか、可視化されるスキルマップの活用がオススメです。
いきなり高度な目標を掲げても、現状のスキルとの差が大きいと達成に時間がかかり、従業員のモチベーションも低下してしまいます。段階的な目標設定により成長が実感できるよう目標を設定するとよいでしょう。
④必要な施策・リソースの明確化
目標達成のために必要な育成に関する施策やリソースを明確にします。目標達成のために何が必要かを自発的に考え、取り組める環境を整えることがポイントです。
育成側も育成される側も本業務と並行して行うため、業務の支障にならないよう計画的に進めていきましょう。
⑤実行・評価・改善
目標を設定し、達成のための行動計画が明確になったら、実行・評価・改善のPDCAを回していきます。目標達成のためには、評価・改善のステップが欠かせません。最短ルートで目標を達成し、目指す姿に到達するためにも、効率的にPDCAを回していきましょう。

人材育成計画とは? 立て方、計画書の作り方とテンプレート
人材育成計画とは、将来的に活躍してくれる優秀人材を育成するための計画です。育成方針や求める人材像などをプランニングし、中長期的に取り組む人材育成の指針として活用されます。
今回は人材育成計画について、...
8.人材育成の具体例
企業によって求める人材像は異なるため、企業風土や経営目標に合った人材育成を行うことが重要です。ここでは人材育成の参考として、2社から具体例をご紹介します。
スターバックスコーヒージャパン
スターバックスコーヒージャパンでは、正社員やアルバイトの区別なく全員が同じ教育プログラムを受講できる環境を整えたうえで、従業員の成長ステップに合わせて4段階のOJTを実施しています。
研修だけでOJTが7つのモジュール、OFF-JTを4クラスの計11プログラムを展開。育成側も教えることで、教えたことを身につけられています。
また、スターバックスのマニュアルレスの現場を支える育成制度の根幹には、自ら学ばせる「ラーナードブリン」の発想があります。なぜそうするのかを考え、納得できるようコーチングを行っているのです。
トヨタ自動車
トヨタ自動車では、ここ数年で人の移動の全般について支援する「モビリティカンパニー」への変革を、評価制度や採用、人材育成などさまざまな面から行っているのです。
人材育成面では、「トヨタらしさ」(豊田綱領・TPS)を兼ね備え、変革を実現できる人材の育成を目指しています。
その一環として、社員に目指すべき姿を浸透させるために社員手帳を作成。社員手帳にはトヨタフィロソフィーや豊田綱領、トヨタウェイ2020などが掲載されています。
トヨタフィロソフィーとは、モビリティカンパニーへ変わろうとしている同社が未来へ歩んでいくための道標であり、豊田綱領を原理原則に置き、ミッション・ビジョン・バリューを再定義したものです。
また、本部長やプレジデントが次世代候補の育成にかかわっている点も大きな特徴。基幹職に昇格した30代後半の若手には、トヨタを外からみて学ぶため外部の企業で働く経験をさせています。
9.人材育成に使える補助金・助成金
人材育成は育成側のリソースだけでなく、コストも発生するものです。ここでは、人材育成に使える補助金や助成金をご紹介します。
- 人材開発支援助成金
- キャリアアップ助成金
- 企業内人材育成推進助成金
①人材開発支援助成金
雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練を計画に沿って事業主が実施した際、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。2023年6月時点では、以下7つのコースがあります。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
たとえば、人材育成支援コースでは、一人1職業訓練実施計画届あたりのOFF-JTにかかる経費が実施時間に応じて助成されます。助成限度額は、中小企業の場合で15〜50万円、中小企業以外では10〜30万円です
参考 人材開発助成金厚生労働省②キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。現時点では、下記5コースを用意しています。
- 正社員化支援
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
たとえば、正社員化支援コースでは有期雇用労働者を正社員化した場合、中小企業で57万円、大企業で42万7,500円が1人あたりに助成されます。キャリアアップ助成金を活用することで、正社員化を目指して適切な人材育成が図れるようになるでしょう。
参考 キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)厚生労働省評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

