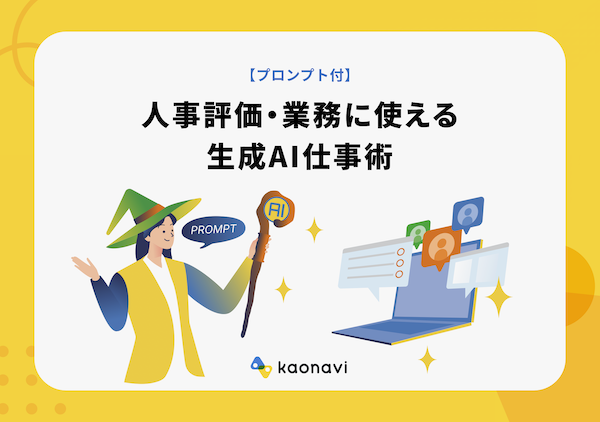煩雑になりやすい目標設定、評価シート入力をAIがアシスト!
生成AIに「たたき台」を作らせて、目標・評価シート作成の悩む時間を解決しませんか?
⇒ 【コピペで使える】プロンプト付き「生成AI仕事術」を無料ダウンロード
人事評価というと給料などの待遇を決めるためのツールと思っていませんか?
確かにそのような側面はあります。しかしそのほかにも、
- それぞれの従業員に強みと課題を認識させる
- 人材の育成につなげる
- モチベーションの向上を図る
など会社の活性化のためにも欠かせない手法でもあります。
人事評価で部下が納得できるような評価をするためには、直接面談をするのがおすすめです。
面談を通じてコミュニケーションを図ることで、
- 部下が何を考えているのか
- 将来会社で何をしたいのか
といった希望を知ることができます。
目次
【コピペで完結】
目標管理、評価シートの「下書き」はAIにお任せ。 悩む時間を減らす実務プロンプト集
1.人事評価面談とは

人事評価面談とは、四半期や半期、または一年に一度など一定のサイクルで実施する上司・部下間の面談のことです。実施するタイミングは会社ごとで異なります。評価者の上司と被評価者の部下が1対1で話し合うのが基本ですが、場合によっては評価者が複数人いたり、人事担当者が同席することもあります。
人事評価面談中は、上司が部下に仕事の成果を聞き、フィードバックをしながら対象期間の評価を行います。
人事評価面談の内容はそのまま人事評価に反映される企業は多く、重要性は高いです。人事評価面談のやり方を工夫して、人材育成や社員のモチベーション向上につなげる企業もあります。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
●1on1の進め方がわかる
●部下と何を話せばいいのかわかる
●質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【目標管理・評価シートの作成、コメント記入は「AIアシスト」で時短する】
悩む時間が長引く目標管理・評価業務を専用の「プロンプト」で効率化!!
●カオナビのAIアシストで目標、評価管理をスムーズにできる
●資料は安全に使うための「5つのルール」付き
●事実を入れるだけの「SBI型コメント」生成
●穴埋め形式だから初心者でもすぐ使える
⇒ そのまま使える「人事評価プロンプト集」をダウンロードする
2.人事評価面談の目的
人事評価面談を行うことは、企業と社員どちらにとっても大切なことです。
人事評価面談の目的は主に3つあります。
人事考課
人事評価面談の1つ目の目的は人事考課です。
人事考課とは、従業員の給与や賞与、昇進・昇格といった処遇を公正に決定するため、一定期間の業務成果や能力、勤務態度を評価することです。
評価面談は、評価結果とその根拠を本人に直接伝えることで、評価の透明性と納得性を担保する重要な役割を担います。評価の客観的な根拠を示すことで、従業員は自身の待遇について理解しやすくなります。
人材育成
人事評価面談の2つ目の目的は人材育成です。
評価面談における「人材育成」とは、上司が一方的に指導する場ではなく、部下自身が自己の成長課題に気づき、主体的に行動変容を起こすための「きっかけ」を提供することです。
【きっかけの具体例】
「今回のプロジェクトでのAさんのデータ分析力は素晴らしかった。特にあのレポートは、次の意思決定の大きな助けになったよ(具体的な行動の承認)。
もし次に、その分析結果から導き出されるアクションプランまで提案できれば、さらに大きなインパクトを与えられると思うんだけど、どうかな?(未来に向けた成長の示唆)」
上記のように具体的な成功体験を承認した上で、次のステップを問いかけるアプローチが有効です。これにより、部下は自身の強みに自信を持ち、改善点も前向きな課題として捉えることができます。
モチベーション向上
部下のモチベーションを管理・向上させることも、人事評価面談の目的です。この役割は「動機形成」とも呼ばれます。
目先の業務や成果に意識が向きすぎると、やりがいや目的意識を失ってしまうこともあるでしょう。評価面談ではそういった部下のモチベーション低下を防ぐために、仕事に前向きに取り組むための動機付けをする必要があります。
取り組んでいる業務の大義を伝える、長期的な育成プランを一緒に考える、部下の考えを引き出し言語化するなど、その時々にあったやり方が求められます。
部下に「自分のことをよく理解してくれている」と感じてもらえなければ、面談でのエンゲージメント向上は望めません。部下の理解にはまず、人材情報の見える化するところからはじめましょう。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」なら、人材情報を見える化!
さらに見える化した情報を活用して、一人ひとりに最適な配置や育成が可能になります。
無料の資料のダウンロードは ⇒ こちらから
3.人事評価面談(フィードバック面談)の進め方

人事評価のフィードバックは人材育成の観点からも大変重要なプロセスといえます。
中小企業ではあまり行われていないようですが、大企業では人事評価を行っている会社の中で8割以上がフィードバックを実施しているといわれています。
社員の能力を見極めて適材適所で働かせることで、従業員の能力を引き出す、ひいては会社により大きく貢献してもらって企業の充実を図ります。

フィードバックとは? 意味・使い方・効果と具体的なやり方をわかりやすく解説
部下のモチベーションを上げ、目標を達成させるための「フィードバック」とは?
スキルや個人の特徴を踏まえながら管理できる「カオナビ」がおすすめ!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp...
テーマはあらかじめ整理
フィードバック面談では時間に限りがあるのでテーマをあらかじめ整理しておきましょう。1人当たり30分~1時間でまとまるように準備することが大事です。
この時間でしっかりした話し合いをするためにはテーマは1つに絞る、せいぜい2つくらいまでにしておくべきです。
落ち着いて話せる場所で
個室で周りに内容を聞かれないように配慮することも大事です。フィードバック面談では部下にいかに納得してもらうかに注意を払うべきです。
そのためには結果を無責任に伝えない、不誠実な態度で臨まないのが基本です。何気ない一言、事実誤認で上司に対する信頼を失ってしまいかねないからです。
部下の自己評価を聞く
必ず、上司からの評価を伝える「前」に、部下本人による自己評価を話してもらいます。これは重要なポイントです。
もし先に上司の評価を伝えてしまうと、部下はそれに迎合したり、反発したりして、率直な自己評価を話しづらくなります。
ここでは、部下が話している間は決して遮らず、最後まで傾聴する姿勢が求められます。「そう感じた背景には、どんな出来事があった?」「特に手応えを感じたのはどの部分?」といった深掘りの質問(オープンクエスチョン)を投げかけ、部下自身に内省を促しましょう。
このプロセスを通じて、上司は部下の認識や価値観を正確に把握することができます。
評価結果を踏まえて今後について話し合う
よかったところとダメだったところをひと通り説明したら、今後のことについて話します。マイナスの部分をどう改善していくか、プラスの部分をより伸ばすための方策、今後のキャリアのことを考えると何が必要なのかなどのやり取りをします。
丁寧に話し合いをすることで、従業員の課題・目標を共有できますし、上司・部下間の信頼関係もどんどん構築できるでしょう。
タレントマネジメントシステムなら、社員の情報を一元管理!
基礎的な知識から、具体的なやり方までわかりやすく解説。
⇒ タレントマネジメントシステム解説資料【3点セット】を無料ダウンロード
4.人事評価における面談での質問事項

人事評価における面談は、通常社員の自己評価に始まって、上司の評価に関する説明を行います。最後に今後の課題をどうするか話し合って、その問題点を共有します。このような流れになりますが、スムーズにいかないときもあるでしょう。
社員の自己評価の際に言葉に詰まってしまう、考えがまとまっていなくて話が進まなくなることは十分考えられます。そのようなときに、上司のほうから質問をすることもあるでしょう。この質問で注意しなければならないのは、誘導尋問にならないようにすることです。
2種類の質問の仕方
こちらの意図する方向に話を持って行くような質問をしてしまうと、部下の客観的な評価の妨げになりますし、「上司の思い通りに話を進められた」という部下の不信感を招きかねないからです。
うまく部下からの発言を引き出すために2種類の質問のスタイルを身につけましょう。
拡大質問をする

まずは拡大質問(オープンクエスチョン)をすることです。
質問をする際に「イエス」「ノー」としか答えられないものは極力避けるべきです。もちろん質問するにあたって状況によっては、このような2択のことを尋ねないといけないことも出てくるでしょう。
しかしこのような2者択一方式の質問ばかりしていると、話がなかなか膨らみません。しかも質問される部下の身になると、尋問を受けているような印象を持ちかねません。
たとえば社員の自己評価の中でダメだったところ・いけなかったところについての言及があったとします。「今度同じ状況になったときにどこをどう変えればいいかな?」といった感じで、話を広げるような問いを提示するのが拡大質問です。
このような質問を振ってあげることで、問題の原因や今後の課題・対策などを相手に話してもらうことができます。また部下にとっても、「なぜダメだったのか?」などより深く掘り下げて考える場にもなるのです。
肯定質問を使う

もう一つは肯定質問をしましょう。
たとえば社員で期日を守れない人間がいたとします。この時「どうして期日を守れないのか?」と聞くと、相手は非難されているような印象を受けます。そうではなく「どうすれば期日を守れるようになるかな?」と尋ねましょう。全く同じ内容の質問でも後者のほうが、相手を非難する要素がなくなります。
非難されるような質問だと聞かれたほうは気分も沈んでしまって、あまり話をしたくなくなるでしょう。しかし肯定質問をすれば、建設的な話し合いもしやすくなります。
効果的な質問やフィードバックは、部下への理解から生まれます。部下の人材情報を見える化して、人事評価面談を有意義なものにしましょう。
人材情報の一元化と見える化なら人事評価システム「カオナビ」
機能一覧や、導入効果をわかりやすく資料にまとめています。
⇒ とりあえず資料を見てみる
5.人事評価の面談を成功させるポイント
面談の方法ですが、最初にいきなり部下と話をしても内容のある話し合いはできないでしょう。そこでおすすめなのが事前に自己評価の書類を作成してもらうことです。
- 目標の内容
- 達成度
- よかった点
- 改善の必要のある点
を書類にしてもらいます。
そのうえで面談の最初に自己評価の説明をさせます。すると漏れなく説明してもらえ、その自己評価に対するこちらの答えを提示できます。こちらが評価する際には、ただ単に「よかった・だめだった」だけでなく、評価の理由を説明します。そのほうが部下も評価に対して納得しやすくなります。
納得感のある面談にするために

人事評価の面談の際に気を付けないといけないのは「いかに部下に納得してもらうか?」です。そのためには、面談を率直に意見の言い合える話やすい環境にすることがポイントです。
もし上司が一方的に部下に評価を告げる形の面談であれば、「評価を押し付けられた感じ」「こちらの言い分が聞き入れられていない」というネガティブな印象を持たれかねません。
部下の中には、なかなか思うような結果が出なかった人もいるでしょう。その場合、ダメなところだけを伝えるだけでは相手のモチベーション低下を起こしかねません。そこで変化や成長している部分はないか探して、その部分を認めることも重要です。
その上で課題を提示すれば、部下も受け入れやすくなります。「この人は自分のことをきちんと見てくれているから」ということでモチベーションの向上に持っていくことも可能です。部下の強み・改善すべき点を明確にすれば、彼らも今後どのように仕事をすればいいかが見えてきます。
このように面談はやり方ひとつで、人材育成の大きな効果も期待できるわけです。
業績評価・能力評価・情意評価を使い分ける
人事評価面談をより納得感のあるものにするために、適切な評価要素を用いることも有効です。具体的には、以下の3つの要素を使い分けます。
- 業績評価
- 能力評価
- 情意評価
業績評価
業績評価とは、営業成績などの業績に対する評価のことです。成果評価ともいいます。
定量的で分かりやすい点が特徴です。
能力評価
能力評価とは、社員が持っている知識やスキルに対する評価のことです。これだけで待遇が左右されることは少なく、育成や成長のために使われるケースが多いです。
役職や職種によって必要とされる能力は異なるので、さまざまな項目で能力評価は行われます。
情意評価
情意評価とは、主に勤務態度に対する評価のことです。どれくらい熱意を持って業務に取り組んでいるか、会社のミッション・ビジョン・バリューに沿った働き方ができているかなどの観点で評価を行います。定量的に測りづらい部分を評価できるのがメリットで、社員のモチベーションと直結する内容でもあります。
タレントマネジメントシステムなら、人事評価の情報を一元管理!
基礎的な知識から、具体的なやり方までわかりやすく解説。
⇒ タレントマネジメントシステム解説資料【3点セット】を無料ダウンロード
6.リモートワーク勤務における評価面談のポイント
リモートワークやハイブリッド勤務が普及した現代において、評価面談のあり方も変化が求められています。オフィスでの勤務と異なり、日々の業務プロセスや「頑張り」が見えにくい環境では、従来通りの評価面談では認識のズレが生じやすくなるでしょう。ここでは、リモート環境下で公平性と納得感を担保するための、評価者・被評価者双方のポイントを解説します。
- 評価の軸を「成果」と「プロセス」の可視化に置く
- コミュニケーション機会を意図的に増やす
- オンラインでの面談環境を整備する
評価の軸を「成果」と「プロセス」の可視化に置く
リモートワークでは「勤務時間の長さ」や「熱心に仕事に取り組む姿」といった情意的な評価が困難になります。そのため、評価の軸を「期間内にどのような成果を出したか(成果評価)」に明確にシフトさせることが重要です。
期初に、達成すべき目標(KPI)を具体的かつ測定可能な形で合意しておくことが、公平な評価の土台となります。同時に、成果に至るまでのプロセスを可視化する工夫も必要です。
週次での進捗報告や、プロジェクト管理ツール上での活動記録などを評価の参考情報とすることで、「成果は出なかったが、プロセスには評価すべき点があった」といった多角的な評価が可能になります。
コミュニケーション機会を意図的に増やす
オフィスでの雑談や気軽な相談がなくなる分、意図的にコミュニケーションの機会を創出する必要があります。
評価面談という年に数回の場だけでなく、週に1回30分程度の1on1ミーティングを定例化し、業務の進捗確認、課題の相談、キャリアに関する対話を継続的に行いましょう。
この定期的な対話の積み重ねが、評価面談での大きな認識ズレを防ぎ、信頼関係を維持する生命線となります。
オンラインでの面談環境を整備する
オンラインでの評価面談は、対面以上に環境と進行への配慮が求められます。カメラは必ずオンにし、お互いの表情が見える状態で対話しましょう。
画面共有機能を活用し、評価シートや関連資料を一緒に見ながら話を進めることで、認識の齟齬を防ぎます。
また、対面よりも反応が伝わりにくいため、意識的に相槌を大きくしたり、「ここまでで何か質問はある?」とこまめに確認を挟んだりする工夫が、部下の安心感に繋がります。
人事評価システム「カオナビ」なら、評価内容を一元管理!
機能一覧や、導入効果をわかりやすく資料にまとめています。
⇒ とりあえず資料を見てみる
7.人事評価面談を成功させるための準備チェックリスト
人事評価面談は、社員のモチベーションを高め、成長を後押しする大切なコミュニケーションの場です。面談をただの評価通知で終わらせず、部下との信頼関係を築く場として活用するには、入念な事前準備が不可欠です。
以下のチェックリストを活用し、「評価面談を通じて部下の成長を支援する」という本来の目的をしっかり果たしましょう。
①面談環境とスケジュールの整備
まずは、面談を行う環境とタイミングの見直しから始めましょう。評価面談は心理的な安全性が問われる場でもあります。
- 部下が安心して話せる静かな個室を確保しているか(最低でも60分は確保)
- 面談の時間帯は、双方にとって余裕のあるタイミングに設定されているか
- 通知音や着信などの妨げがないように、PCやスマートフォンは事前にオフにしておく
- オンライン実施の場合は、通信環境・マイク・カメラの動作確認を行う
こうした配慮が、部下の本音を引き出す土台になります。
②評価に必要な情報の整理と事前分析
評価の質は、準備された情報の質で決まります。評価面談の場で慌てないためにも、以下の確認を忘れず行いましょう。
- 評価シートおよび部下の自己評価をあらかじめ確認済みか
- 評価期間中の行動や成果を記録した1on1メモや、週報を見返しているか
- 承認すべき点(良かった点)について、具体的に3つ以上挙げられるか
- 改善を期待する点も、根拠あるフィードバックを準備できているか
- 自己評価と上司評価のギャップが大きい項目がないか、その差異を説明する準備があるか
- 「なぜこの評価なのか?」という質問に論理的に答えられるだけの材料があるか
「曖昧な記憶」で評価していると思われないよう、事実に基づく準備が鍵になります。
③評価者としてのマインドセットの確認
人事評価面談で重要なのは、評価を伝えることではなく、「部下の納得感」と「次の成長につなげること」です。そのためには、評価者自身のスタンスが問われます。
- 面談のゴールが「通知」ではなく「対話」であることを意識しているか
- 会話の主導権は部下に渡し、自分は7割「聞く」姿勢が取れているか
- ハロー効果や中心化傾向などの評価バイアスが入っていないか、内省できているか
- どんな意見が出ても、まずは受け止める傾聴の姿勢を持てているか
こうしたマインドを持つことで、評価面談が単なる儀式ではなく、部下の成長を促す機会となります。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる
カオナビで人事評価を【システム化】することで、評価の“質”や“納得度”を上げるような時間の使い方ができます