面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決
クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
組織マネジメントの一つに、目標管理があります。目標管理という言葉を知っていても、その意味やメリットなどを正確に理解している人は多くないようです。
企業にとって目標管理とは、社員の自主的な業務への取り組みを促すための仕組みのこと。目標管理の意味やメリット、起こりがちな失敗などを含めて説明します。
目次
目標管理(MBO・OKR)や評価業務を効率化した実績多数! 人事評価システムの導入相談なら「カオナビ」にお任せください。貴社の状況に合った活用方法や導入効果をわかりやすくお伝えします⇒ 無料オンライン相談はこちらから
1.目標管理とは?

目標管理は、企業で広く用いられる組織マネジメント手法の一つです。
具体的には、
- 個々の業務を担当する社員に、自らの業務目標を設定・申告させる
- 申告した業務目標の進捗や結果を社員自らが管理する
という方法で社員自らが組織を動かしていくマネジメント方法と考えるとよいでしょう。
業務を行う社員が自ら目標設定に関わり、その進捗や成果物の管理を行うことで、社員の主体性や積極性を育むことが可能です。活力ある組織づくりには欠かせない方法でしょう。
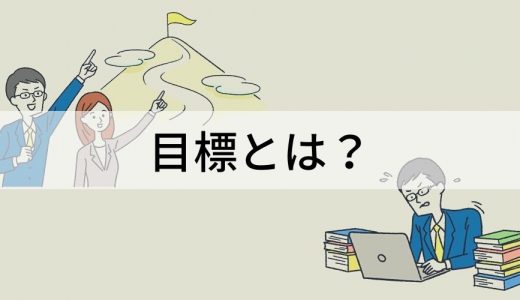
目標とは? 意味、目的やゴールとの違い、設定のコツを簡単に
面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決
クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【MBO・OKRの「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って、評価業務の時間を10分の1にした実績多数!
●MBO・OKRに対応した目標シートを自在につくれる
●部下の進捗を一覧で確認できる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●1on1面談の記録を簡単に蓄積・参照できる
●クラウド型だから費用を抑えられる
2.目標管理制度とはどのような組織マネジメント?

目標管理制度とは、目標管理に存在する仕組みの規模を大きくして企業内の制度に応用したもののこと。
目標管理制度の仕組みは、下記のようになっています。
- 個別、またはグループごとに目標を設定
- 目標に対する達成度で評価を決定
また、個人と組織の目指すベクトルを合わせ、最終的に社員一人ひとりの目標と組織の目標をリンクといったことを実現することで、
- 「やらされている感」が生じにくくなる
- 「目標達成に貢献する」といった社員の参画意識を育成
などのメリットも得られます。目標管理制度は、社員一人ひとりが意欲的に業務に取り組むための土台づくりに大きく貢献するのです。
目標管理制度のポイント
目標管理制度のポイントは、
- 誰にとっても分かりやすい具体的な目標
- 目標のレベルは高すぎず低すぎない
- 目標達成までの期間を設定
- 目標に合わせて具体的な取り組み方が明記されている
- 企業戦略と一人ひとりの社員の役割とが関連性を持つ
これら項目がすべて網羅されることで、目標管理制度の効果を最大限発揮できると考えられています。
目標管理制度の運用方法
目標管理制度を運用する際、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
- 運用に向けて適切な目標を設定
- 設定した目標から実際の行動を逆算して計画、実行
- 日報や定期的な面談などによって進捗を確認
- すべての工程において客観的な評価を心掛け、評価後には適切なフォローを実行
どんな制度でも運用方法を間違えれば、効果は期待できません。
目標管理制度(MBO・OKR)の運用は、従業員にも負担がかかります。シートやファイルのやり取りが発生する紙やExcelの利用した制度運用の負担は大きく、目標設定や自己評価に取り組む従業員のモチベーションを下げる恐れがあります。
目標管理を成功させるには、その負担を取り除くことも重要なのです。カオナビなら誰でも使いやすい操作性で、目標管理・人事評価のスムーズな運用が可能です。
導入効果が分かる資料の無料ダウンロードは⇒こちらから
3.目標管理の導入による効果、メリット

目標管理の導入には、3つのメリットがあると考えられています。
- 社員のモチベーションアップ
- 社員のスキルアップ
- 評価しやすい
①社員のモチベーションアップ

1つ目のメリットは、意欲的・積極的に取り組む社員を育成できる点。
目標管理とは、業務を担当する社員自らが、業務目標を設定・申告したり、申告した業務目標の進捗や結果を主体的に管理したりすることで、社員自らが組織を動かしていくマネジメント方法のこと。目標管理の導入により業務に対する社員の自主性が高まります。
自主性が高まることで、
- 社員のモチベーションの向上
- 自ら考え、自ら働く人材の育成
の実現につながるでしょう。
- 上司に言われたからやる
- すでに決まっていることだから取り組む
といった受身的・消極的姿勢ではなく、意欲的・積極的に取り組む社員を育成できるのは、企業にとっても大きな魅力でしょう。
②社員のスキルアップ
2つ目のメリットは、社員のスキルアップを促せる点。
- 自らの意思で自分の目標を設定
- 設定した目標を実現するために進む
というプロセスを経ることで、社員一人ひとりのスキルが磨かれます。
個々の社員が能力を高めれば、チームのレベルも底上げされるでしょう。チームのレベルが高くなれば、当然、企業としての力もレベルアップします。企業を構成する社員一人ひとりの能力向上は、企業そのものの価値を高めることにつながるのです。
③評価しやすい
3つ目のメリットは、各工程を評価しやすくなる点。
- 目標に対してのプロセス
- 目標に対しての進捗
- 目標に対しての成果
のそれぞれを評価しやすくなるのです。目標管理は、なるべく具体的な目標を設定します。
それにより、
- 目標達成に向けてどのような方法でアプローチを行っているのか
- 目標達成に対してどこまで進んでいるのか
- 目標達成に対してどのような成果を出せているのか
といったさまざまな観点からの評価が容易になるのです。また、公平な評価制度としても活用できるでしょう。
目標管理制度(MBO・OKR)のメリットを最大化するには、上司による部下の理解の深さや的確なフィードバックが必要です。
この実現には、部下の目標に対する進捗や面談履歴を把握できる人材データベースの構築が効果的です。
カオナビならあらゆる人材情報をデータベースに集約。部下の現状把握やフィードバックに必要な人材情報にスムーズにアクセス可能です。
資料の無料ダウンロードは⇒こちらから
4.目標管理の運用で起こりがちな失敗

目標管理を運用する際、失敗することもあります。失敗の多くは、目標管理そのものが悪いというよりは、目標管理の運用に問題がある場合が多いようです。ここでは、目標管理の運用で起こりがちな3つの失敗について説明します。
- 目標至上主義
- 手段の目的化
- 社員のモチベーション低下
①目標至上主義
1つ目は目標至上主義によるもの。目標そのものに重きを置くあまり、目標に対する成果のみを評価してしまうケースです。
- 売り上げ200万円の目標に対する結果は190万円、目標は達成できておらず低評価
- 新規顧客10件獲得の目標に対する結果は9件、目標に足りていないため低評価
など目標をノルマ管理の一つとしてしか活用できていないケースです。このような目標至上主義では、本来の目標管理が目指す、
- 社員のモチベーションの向上
- スキルアップ
といったメリットを享受しにくくなります。
②手段の目的化

2つ目は目標管理の手段が目的化されてしまうこと。
目標管理を行う際、社員自らが立てた目標に対する進捗や結果を検証するため、上司との間で目標管理面談を行います。
目標管理面談は、
- 評価者である上司の負担が大きい
- 組織内をあらゆる観点で評価するため、ミドルマネジメントのマネジメント力が求められる
という特徴を持つもの。
もし、目標管理面談の実施が目的となったら、業務よりも評価を優先するようになるでしょう。
つまり手段の目的化となり、結果「評価しやすい」という目標管理のメリットが損なわれ、評価そのものが大きな負担になってしまうのです。

目標管理制度(MBO)において面談の適切なタイミングは?
期初や期末などある程度決められた期間に面談を行います。人事評価のタイミングに合わせて行う場合も多いでしょう。
しかし中には目標の達成度合いを気にしすぎて、上司が部下に詰問してしまう場合も。大手企業の組...
③社員のモチベーション低下

3つ目は社員のモチベーション低下。
目標管理の運用に失敗すると、目標管理は単なるノルマ管理になり、毎日の業務が会社や上司からの押し付けになります。それによって社員のモチベーションは低下し、そして生産性も低下してしまうのです。
企業目標を達成するために行った目標管理によって、企業の弱体化を招いてしまっては本末転倒といえます。目標管理を運用する際は、目標管理の意味をよく考え、導入メリットを最大限享受できるような方法を構築しましょう。

【Q&A】目標管理制度に失敗してしまうことはありますか?
失敗例はあります。失敗を避けるには、人事評価に連動しすぎない適切な利用が必要です。
目標管理制度とは社員個人の目標を上司がともに管理・サポートして、目標達成を目指す制度のこと。人事管理制度でも重要な観...
【従業員の目標達成をサポートする機能が揃っています!】
人事担当者からマネージャー、従業員まですべての目標管理・評価業務を効率化するなら、人事評価システム「カオナビ」です。
●フィードバックに役立つ人材情報を把握できる
●目標進捗を一覧で確認できる
●1on1などの面談管理が簡単にできる
●従業員エンゲージメントを見える化できる
●MBOやOKRシートのテンプレートが利用できる

