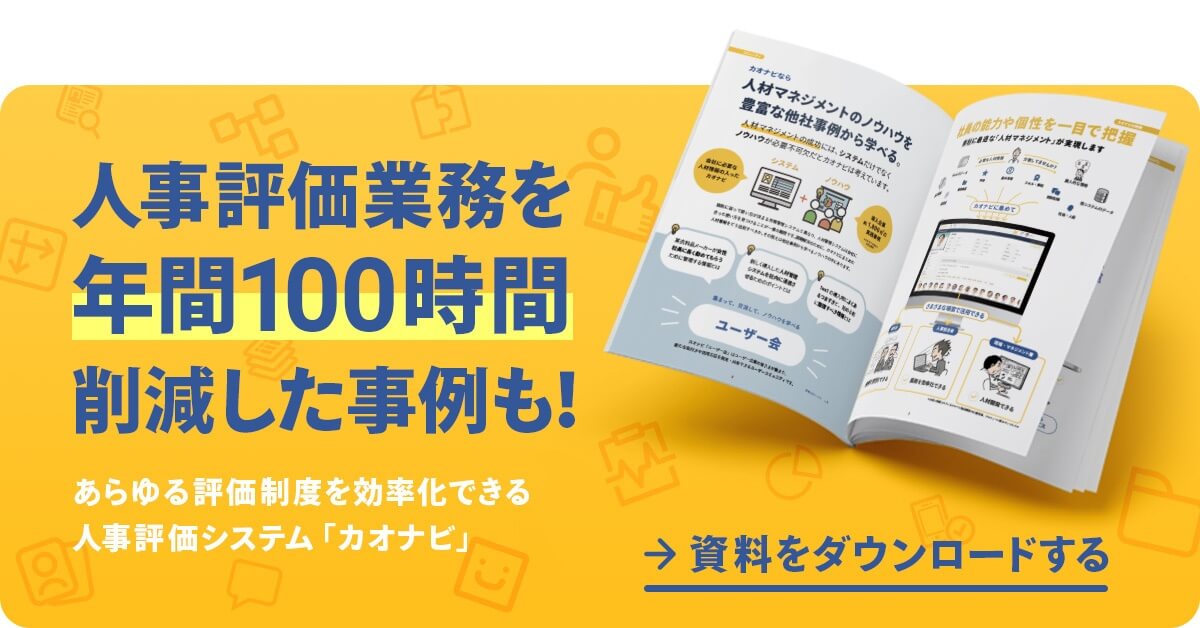行動評価に欠かせないコンピテンシーの分析、モデルの開発を効率化。
人事評価システム「カオナビ」で、時間がかかる人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
行動評価項目とは、1990年代頃から日本の企業でも導入が始まった人事評価システムのこと。ここでは行動評価項目のメリットや効果について解説します。
目次
行動評価(コンピテンシー評価)の導入・見直し以前に、評価業務効率化の方が重要課題になっていませんか? 人事評価システム「カオナビ」なら、評価業務の時間を10分の1にした実績多数! 導入効果が分かるPDFの無料ダウンロードは⇒ こちらから
1.行動評価項目とは?
行動評価項目とは、もともとアメリカを中心に導入されていた人事評価システムで、「コンピテンシー評価」とも称されているものです。日本では1990年代頃からさまざまな企業で導入が始まりました。
成果を出す社員の行動特性を元に策定されるもので、現在では多くの企業で重視されている人事評価システムです。

行動評価とは? 項目例、能力評価との違い、メリットを簡単に
行動評価とは、成果を出している従業員の行動を評価基準とした評価手法です。結果や能力だけを基準とした評価システムは、従業員の努力や取り組みが正しく評価されない恐れがあります。明確な評価基準のもと、公平な...
コンピテンシー(行動特性)とは?
コンピテンシーとは、優れた成果を出す人材の行動特性のこと。ハイパフォーマンスを生み出す社員には特定の行動特性があり、その特性を策定して人材育成や人事評価に活用しようという試みです。
コンピテンシーでは優れた成果を出した社員が持つスキルではなく、パフォーマンスを発揮した結果や、具体的な行動を重視しています。

コンピテンシーとは? 意味や人事評価、面接での使い方を解説
コンピテンシーの活用には、優秀人材の共通点の分析が必須
タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...
コンピテンシー(行動特性)で評価すること
コンピテンシー評価とは、職務ごとに定められた行動特性をベースにした人事評価のこと。社員のスキルや適性を公正に評価できる制度として近年注目されています。
対人交渉能力や重要事項の意思決定能力、タイムマネジメントなどの評価項目によって構成されるのが一般的です。社員の業務を進める工程やプロセスが明確になるため、不足しているスキルの把握も可能になります。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【行動評価(コンピテンシー評価)の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●社内の優秀人材を簡単にピックアップできる
●優秀人材のコンピテンシーを分析できる
●行動評価に対応した評価シートをつくれる
●誰がどこまで評価が進んだのか一覧で見られる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
2.従来の能力評価項目と行動評価項目の違いについて
かつて多くの日本企業では「能力=職務遂行能力(職能)」と捉えられてきました。しかし
行動評価では、それと異なる視点から評価できます。従来の能力評価項目と行動評価項目の相違点について、解説しましょう。
成果と直接結び付いた能力を評価している
行動評価では、成果と直接結び付いたスキルを評価します。つまり「企画力」「理解力」「表現力」などのスキル要素を「足す」のではなく、成果と結び付いた要素を検証して全体的に判断するのです。
従来の能力評価では成果が生み出されるスキルを「足し算」で考えていたため、この行動評価とは大きく異なります。
人事評価における能力評価項目とは?
人事評価とは、社員が業務で身に付けたスキル・能力を評価すること。
評価項目は、「理解力」「提案力」「指導力」「発想力」「人材育成力」「調整力」「構想力」「企画力」「実行力」「改善力」「問題発見力」「課題解決力」「分析力」「判断力」「積極性」「責任性」「規律性」「チームワーク」「顧客志向」などです。
能力評価のメリットとは?
能力評価を行うと、企業が求める人材と社員の持つスキルのマッチングがよりかんたんにできます。社員自身が「会社が自分にどのようなスキルを求めているのか?」などを理解できるため、必要なキャリア形成に積極的に取り組めるのです。
また自己表現にも活用できるでしょう。
能力評価のデメリットとは?
能力評価は業務の成果や職務内容ではなく、年齢や勤続年数、経験や学歴などをベースに等級や評価を決めるため、優れた成果を生み出している若手社員が不満に感じやすいのです。
また行動評価には、優秀人材のコンピテンシー分析やコンピテンシーモデルの開発が必要になるなどの違いがあります。
これらの実施には、そもそも従業員の能力やスキルに関する情報のデータベース化が必要です。データベースがない場合は、アンケート等を利用し、人材情報を集めるところから始めなければなりません。
カオナビなら、行動評価に必要なデータベース機能や分析機能が揃っています。またアンケート機能を利用すれば、アンケートで収集したスキル情報をそのままデータベースに反映。紙やExcelのやり取りや転記の煩わしさがありません。導入効果が分かる資料の無料ダウンロードは⇒ こちらから
3.行動評価項目で評価するメリットや効果について
行動評価項目で評価すると、企業の方向性や理念が幅広く浸透するため、社員の意識向上を図れるのです。ここでは行動評価項目での評価によるメリットや効果について、見ていきましょう。
- 公平かつ納得につながる評価が可能
- 成果や業績につながる
- 人材育成が効率的
- 離職防止の一助になっている
- 評価者によるブレが少ない
①公平かつ納得につながる評価が可能
行動評価は業務の成果だけでなく、そこに至るまでのプロセスを評価するため、公平性が高くなります。一般的に成果は個人のものとして評価されがちですが、ほか社員のサポートが影響しているケースも少なくありません。
さらに担当している市場による場合もあるので、不確定な要素が多いともいえます。そのため行動評価では「プロセス」も重視しているのです。
②成果や業績につながる
行動評価項目は、優れた成果を生み出す社員の行動特性を基準として策定するため、それらの成功法則を社内や組織で共有できます。
つまり優れた成果やハイパフォーマンスを出す社員のコンピテンシーを、ほかの社員が取り入れるようになるため、組織全体の業績や成果、生産性向上が期待できるのです。
③人材育成が効率的
評価基準には、仕事で成果を出している社員の行動が設定されています。そのため評価される点が具体的になり、社員の行動目標も決めやすくなり、モチベーションの向上にもつながるのです。
また目標が明確になると、スキル開発や教育指針への活用も可能に。効率的な人材育成を展開できるでしょう。
④離職防止の一助になっている
これまでの日本では、職務遂行能力を評価基準としてきました。その結果、企業と応募者とのミスマッチが発生しやすくなり、離職率の増加などが問題視されるようになり、行動評価が取り入れられたのです。
企業が求める人材の行動特性を明確化するため、採用活動の評価項目にも活用できます。採用の選考段階で企業が必要とする人材が分かりやすいため、採用のミスマッチが生じにくくなり、離職率の低下にもつながると考えられているのです。
⑤評価者によるブレが少ない
行動評価を用いた人事評価では、結果へのプロセスではなく、「プロセスをこなすことで特定の状況を生み出せたか」という点に注目できます。
さらに行動評価は客観的な評価ができるので、「評価が不明瞭」「上司との相性や関係性による」「上司の考え方が評価のベースとなってしまう」という社員の不満も解消できるのです。
一方で行動評価には、その準備や運用に手間がかかるというデメリットがあります。
- 優秀人材の特定
- コンピテンシーの分析
- コンピテンシーモデルの開発
- 評価制度への組み込み
- 従業員への周知
など、対応すべきことは山積みです。
現状の評価業務で大きな負担を感じている場合、行動評価を導入しても、失敗に終わってしまう可能性があります。そのため評価業務の効率化が急務になります。
カオナビなら、行動評価を含む人事評価を効率化。クラウド型なので、費用を抑えて導入が可能です。カオナビが詳しくわかる無料PDFのダウンロードは⇒ こちらから
4.コンピテンシー(行動特性)の行動評価項目を決めるポイントとは?
行動評価項目を決める際、コンピテンシーディクショナリーをもとに項目を作成する方法があります。下記6つに分類して解説しましょう。
- 達成やアクション
- 支援と人的サービス
- インパクトと影響力
- マネジメントコンピテンシー
- 認知コンピテンシー
- 個人の効果性
①達成やアクション
行動評価項目を決めるポイントでは、「達成重視」「秩序や正確性」「イニシアティブ」「情報探求」の4カテゴリーがベースとなるのです。
生産性を高めるためには達成コンピテンシー群が高く評価される傾向にあります。「情報探求」と「イニシアティブ」 は、コンピテンシーの支援に活用できるのです。「達成重視」コンピテンシー群は、ほかとの併用が重要になります。
項目例
項目の一例は、下記のとおりです。
- 業績や成果を測定した結果はどうか
- 指示される前から課題に取り組んでいるか
- 多くの異なる情報源に積極的にアクセスしているか
さらに組織環境をふまえて、「社員の行動やアイディアがどれだけ新しいか」「ほかの社員と異なっているのか」という項目を入れてもよいでしょう。
②支援と人的サービス
支援と人的サービスは、「対人関係理解」と「顧客サービス重視」で構成されています。
- 対人関係理解:顧客との接点が多い営業職や部下とかかわる場合の多い管理職などに必要とされるスキル。他人を理解したいという気持ちから、表面化されにくい考え方や感性、懸念を正しく聴き取り、理解する能力を指す
- 顧客サービス重視:他人の求めるものに応えて支援し、サービスを提供したいという気持ち。クライアントの求めに注目したり、エンドユーザーを重視したりするのはそのひとつとされている
項目例
項目の一例は、下記のとおりです。
- 相手の立場になって考えられるか
- 目の前にある課題や問題だけに飛びつくのではなく、物事の本質をとらえられるか
- 自分の感情と事象に線を引き、根拠のある行動が取れるか
行動基準として適用すると、成果が期待できます。
③インパクトと影響力
インパクトと影響力とは、自分の考え方や行動がほかの社員から支持されるなど、特定のインパクトや効果を与えている状況のこと。
また自身が所属する組織などから理解を得る「組織の理解」、さらには多くの人とのコミュニケーションを図って友好的なネットワークを築く「関係の構築」も重要な項目だと考えられています。
項目例
項目の一例は、下記のとおりです。
- 読解力
- 傾聴力
- 議論力
- 記述力
- 提案力
④マネジメントコンピテンシー
マネジメントコンピテンシーは、ほかの社員を牽引し、チームワークや協調を促すマネジメントが行えるかどうかといったものです。
項目例
「部下への配慮と責任」「現在と将来の仕事を適切に管理する」「チームメンバーへの積極的な関わり」「困難な状況における合理的な考えと対処」4つの領域があり、それぞれに紐付くA〜Cの項目があります。
たとえば「部下への配慮と責任」の領域であれば、
- A:誠実さ
- B:感情コントロール
- C:配慮ができる
「チームメンバーへの積極的な関わり」の領域であれば、
- A:身近な存在である
- B:社交的である
- C:共感を持って接する
となっているのです。
⑤認知コンピテンシー
認知コンピテンシーには、「分析的思考」「概念化思考」「マネジメント専門能力」の3つがあります。「企画・管理」や「ITエンジニア」「モノづくり系エンジニア」「金融専門職」などの職種で重視される傾向にあるものです。
これらはイニシアティブの知的能力発揮というように、問題や知識の理解に結び付くと考えられます。
項目例
項目として挙げられるのは、下記の3つです。
- 分析的思考能力…物事をさらに詳しく掘り上げて状況を比較、検討、分析。そこから効果的な対応や計画を立てていく力
- 専門性…職務に関する専門的かつ技術的知識を高めてそれらを活用していく力
- 概念化…出来事の関係性や表面化していないパターンを見抜いて、 状況を統合的に理解していく力
⑥個人の効果性
個人と他者との比較などにて、成熟度の一部を反映します。さらには個人がプレッシャーや困難に直面したときの出来不出来をコントロールするのです。その環境に関係しているコンピテンシーの効果性にも影響を及ぼすとされています。
項目例
項目の例は、下記のとおりです。
- 自己確信…気力を奪うような挑戦や懐疑、無関心と出会っても成果を生み出せる
- セルフコントロール…敵対的なストレスの高い環境などでも成果を生み出せる力
- 柔軟性…さまざまな人、グループや組織に効果的に対応するための行動特性
- 組織へのコミットメント…組織の行動と目的に個人の行動と意識を合わせる

人事評価システム「カオナビ」なら、あらゆる人材情報をデータベースに集約。行動評価に必要な職種や等級ごとの項目や評価シートの作成が可能です⇒ カオナビの資料を見てみる
5.行動評価項目の基準を決めるには
行動評価項目の基準を決める際、「共通基準」「業務や役割に応じて活用する個別基準」の2つを作成するとよいでしょう。評価基準には達成できたか、あるいはできなかったかを設定し、今後につなげていくという目的があるからです。
共通して使う基準
共通基準とは、企業や組織全体、すべての社員に共通する基準のこと。組織にはさまざまな業務があり、担う役割も違えば求められるスキルも当然異なります。
自ずと個別評価は必要になりますが、個別評価の前に、社員に共通する評価尺度がなければ、組織全体がバラバラになってしまうでしょう。まず組織全体の共通基準を定めると、公正な評価を実現できるのです。
個別基準
個別設定基準は、目標管理の工程で設定される「目標達成度」を評価する際に活用されるもので、能力評価などでも作成できます。コンピテンシーディクショナリーは人事評価尺度基準のひとつですが、抽象的な側面もあるもの。
しかし個別設定基準の考え方を習得できれば、人事評価結果をフィードバックする際に評価理由をきちんと提示できるため、有効だと考えられているのです。
基準を決めるためにはコンピテンシーモデルを作ろう
基準を決めるためにはコンピテンシーモデルを作るとよいでしょう。一般的な方法は、優れた成果を生み出す社員のスキルと行動を十分に分析し、基準に落とし込むというもの。
このケースでは、対象社員の上司やプロジェクトメンバーから日頃の行動などについてヒアリングや取材を行って進めます。
理想型モデル
会社が求める人物像にもとづいて、評価モデルを設計します。理想とするモデルを想定したうえで、具体的な評価項目を設定。組織にモデルとするべき優れた社員がいない場合に、有効でしょう。
しかし理想を追求し過ぎると、現実とかけ離れた評価モデルや項目を設計してしまう可能性もあるため、注意したいところです。
実在型モデル
実際に在籍している、能力の高い社員を参考にコンピテンシーモデルを設計します。手本となる社員が身近にいるため、理想型モデルよりコンピテンシーの設計がかんたんです。
しかし手本となる社員の行動特性は、「後天的に身に付いたものではない」可能性も。どのような行動特性を採用するのか、しっかり検討する必要があるでしょう。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる
カオナビで人事評価を【システム化】することで、評価の“質”や“納得度”を上げるような時間の使い方ができます
⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)