もっと効率的に、成果を出すためのマネジメントを行いませんか?
カオナビなら、人材のスキルや目標に対しての進捗度を一元化し人材育成をサポートします。
⇒
【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
テレワークの普及により、働き方が柔軟になる一方で、マネジメントのあり方も大きく変わりつつあります。
これまでオフィスで自然に行われていたコミュニケーションや進捗管理が難しくなり、生産性とチームワークに課題を抱える企業も少なくありません。
この記事では、テレワークにおけるマネジメントの重要性や直面しやすい課題、その解決策を解説します。あわせて、実際に取り組みを進めて成果を上げた企業事例もご紹介します。
1.テレワークでマネジメントが重要な理由
テレワークの拡大に伴い、従来とは異なるマネジメントの課題が浮き彫りになっています。とくに、対面でのやりとりが減ったことで、情報共有や意思疎通が難しくなり、業務の進捗と成果の把握をしづらくなるケースが増えているようです。
このような環境下では、チームの生産性やモチベーションの低下を招きかねません。
だからこそ、テレワーク時代に適応したマネジメント手法がこれまで以上に重要となっています。具体的には、コミュニケーションツールの適切な活用や、業務の進捗状況を可視化する仕組みの導入などが求められるでしょう。
【マネジメントの「むずかしい」「時間がかかる」を一気に解決】
人材管理システム「カオナビ」を使ってマネジメントの生産性を大幅改善!
●時間のかかる1on1や360度評価をシステムで効率化できる
●面談記録を簡単に残し、必要な時にすぐ確認できる
●部下の進捗やスキルを一覧で確認できる
●部下のエンゲージメントを見える化できる
2.テレワークとオフィスワークのマネジメントの違い
テレワークとオフィスワークでは、マネジメントのアプローチにいくつかの違いがあります。オフィスワークでは、上司・同僚と日常的に顔をあわせるため、仕事の進み具合やメンバーの様子が自然と把握できます。
また、何かあればすぐに声をかけて対応できるのも大きなメリットです。
一方、テレワークでは相手の状況が見えにくく、同じような対応が難しくなります。そこで重要になるのが、オンライン会議やチャットなどを使ったこまめなコミュニケーションです。
また、タスク管理ツールを活用し、進捗や成果を明確に共有する仕組みも欠かせません。
さらに、各自の自己管理能力がより問われるため、上司は目標設定やフィードバックを強化し、従業員のモチベーション維持と成果向上をサポートする必要があります。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.テレワークのマネジメントの6つの問題点
テレワークにおけるマネジメントでは、どのような点が問題になりやすいのでしょうか。ここでは、とくに注意すべき6つの課題について整理してみましょう。
- 経営方針が浸透しづらい
- 緊張感が無くなり、生産性が低下する
- 過剰労働のリスクがある
- コミュニケーションが不足する
- 適切な評価が難しい
- モチベーションや健康状態を把握しにくい
① 経営方針が浸透しづらい
テレワークでは、経営者の想いや方針が現場の従業員に伝わりにくくなります。オフィス勤務であれば朝礼や期初会などを通じて、企業文化やビジョンを共有できますが、リモート環境ではそのような機会が減るからです。
さらに、情報共有の手段がメールやチャット、オンライン会議に限られるため、相手の表情や声のトーンといった非言語情報を捉えにくくなります。
その結果、微妙なニュアンスが正確に伝わらず、業務における重要な意図および背景がうまく共有されないおそれも出てくるでしょう。

経営方針とは?【考え方をわかりやすく】中小企業、経営理念
経営方針とは、経営理念を実現するために取るべき行動や方向性を具体的に示したもの。企業の存在意義は経営理念に示されているものの、それを実現するには従業員に具体的な行動に落とし込んでもらう必要があります。...
②緊張感が無くなり、生産性が低下する
テレワークでは自宅などプライベートな空間で働くことが多く、どうしても気が緩みやすくなります。周囲の目がないことで、仕事のペースが遅くなったり、集中力が続かなかったりという声も少なくありません。
自己管理能力の低い従業員は、生産性が下がることもあるでしょう。これを改善するには、日々のスケジュールを明確に設定したり、朝会などの定例ミーティングを取り入れたり、適度な緊張感を持たせることが有効です。
③過重労働のリスクがある
テレワークでは通勤時間がない一方で、勤務開始・終了の区切りが曖昧になりやすく、結果として長時間労働になるケースが増えています。
業務の合間に家事を挟むなど柔軟な働き方ができる反面、就業時間外にもメール対応や資料作成をしてしまう人も多く、知らぬ間に過重労働に陥るリスクがあるでしょう。
これを改善するには、労働時間の記録を徹底する勤怠管理ツールの導入が効果的です。また、上司がメンバーの業務状況を定期的に確認し、業務量の調整を行うなど、働きすぎを防ぐ意識づけが欠かせません。

過重労働とは? 定義、意味、基準をわかりやすく解説
長時間労働やブラック企業という言葉が社会に定着してきている一方で、過重労働対策に取り組む企業も増えてきています。今回は人事面での知識として覚えておきたい、過重労働対策についての厚生労働省や大手企業の取...
④コミュニケーションが不足する
テレワークでは、対面でのちょっとした雑談や気軽な相談が減り、コミュニケーション不足が大きな課題となります。
会議では業務の話だけで終わりがちで、メンバー同士の関係性が築きにくいものです。その結果、孤立感や不安を抱える従業員も少なくありません。
また、細かいニュアンスが伝わりづらくなるため、ミスや誤解の原因になることもあります。これを防ぐには、1on1ミーティングや雑談タイムを意識的に設けるなど、メンバー同士の心理的な距離を縮める取り組みが必要です。
⑤適切な評価が難しい
テレワークでは従業員の勤務態度や業務プロセスを直接観察できないため、業務の過程や努力が見えにくくなります。成果だけを評価しようとすると、チームワークやプロセスを軽視してしまい、不公平感が生まれるおそれもあるのです。
また、評価の透明性が低いと、従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼすでしょう。成果だけでなく、業務プロセスやチーム貢献も含めた多面的な評価制度の導入が求められます。
定期的な目標設定と進捗確認、振り返りを取り入れることで、納得感のある評価が可能です。
⑥モチベーションや健康状態を把握しにくい
テレワークではメンバーの表情や雰囲気が分かりづらく、モチベーションの変化に気づきにくくなります。
ストレスや悩みを抱えている場合でも、周囲に気づかれないまま放置されてしまうかもしれません。モチベーションが下がると、業務への集中力や生産性にも影響を与えるでしょう。
そのため、日常的な声かけや簡単なアンケートを活用し、従業員の状態を見える化する工夫が欠かせません。上司は業務だけでなく健康状態にも関心を持ち、気軽に相談できる関係を築くことが求められます。

モチベーションとは? 意味や下がる原因、上げる方法を簡単に
従業員のモチベーションの可視化と分析ができる「カオナビ」
⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから
従業員のモチベーションが上がらずにお悩みではありませんか? カオナビなら、従業員のモチベ...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.テレワークにおけるマネジメントの方法
テレワーク環境でマネジメントを成功させるためには、従業員の心理状態や健康状態を把握すること、そして適切な評価制度を整備することが必要です。ここでは、具体的な取り組みについて紹介します。
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で行う対話の場で、業務の進捗確認だけでなく、従業員の心身の健康やモチベーションの維持・向上を目的としています。
テレワークでは孤独感やコミュニケーション不足が問題となるケースが多いです。こうした個別面談は従業員のメンタルケアにも役立ちます。
定期的な面談により、従業員の心理的安全性を高めながら信頼関係を築けるでしょう。また、早期に問題を発見し、適切なサポートを提供することで、離職防止や生産性向上にもつながります。
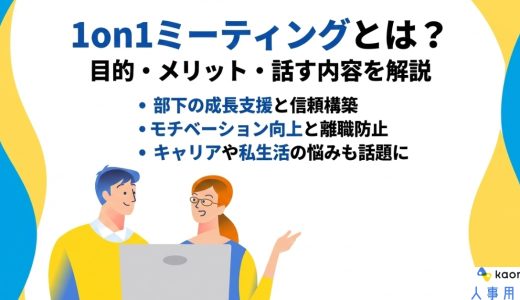
1on1とは? 目的や導入効果、面談との違いとやり方を簡単に解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入す...
テレワークに合った評価制度の導入
テレワークでは、従業員の働きぶりを直接観察することが難しく、従来の評価制度では対応しきれないケースも出てきます。
そこで、あらかじめテレワークに適した評価基準を整備しておくと、より公正で納得感のある人事評価が可能になるでしょう。
さらに、目標管理制度(MBO)を取り入れるのも効果的です。これは、従業員自身が業務目標を設定し、その達成状況をもとに評価する仕組みで、上司と目標を共有することで透明性も高まります。
また、企業の価値観や行動指針にもとづいて評価する「バリュー評価」もおすすめです。これにより、個人の行動が組織の方向性と一致しやすくなり、チームとしての一体感やモチベーションの向上にもつながります。

目標管理制度(MBO)とは? 意味や目的、メリット・デメリット、導入方法を簡単に解説
面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決
クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...

バリュー評価とは? 特徴やメリット、書き方と具体例を解説
近年、多くの企業が導入を進めている「バリュー評価」は、従業員の行動を企業の価値観やミッションに照らし合わせて評価する人事評価制度です。企業の一体感や従業員のモチベーション向上に寄与するため、注目されて...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
5.テレワークマネジメント成功ポイント
テレワーク環境下でも成果を出すためには、ツール活用と人的サポートの両面から工夫を凝らすことが不可欠です。ここでは、テレワークでのマネジメントを成功させるポイントを5つ紹介します。
- 業務を見える化する
- 業務アサインを適切に行う
- 報連相のルールを徹底する
- セルフマネジメントを促進する
- ミドルマネージャーを育成する
①業務を見える化する
テレワークでは従業員の作業状況を直接確認できないため、業務プロセスの「見える化」が欠かせません。
具体的には、タスク管理ツールで進捗状況を共有したり、スケジュールアプリで作業時間を可視化したりすると、誰がどの仕事をしているのかが一目で分かります。
これによって、チーム全体の状況を把握しやすくなり、必要なサポートや人員の調整もしやすくなるでしょう。
また、周囲から見られている意識が働くことで、仕事への緊張感が生まれ、手を抜きにくい環境が整います。さらに、働きぶりの見える化により評価の公平さが増し、従業員も納得しやすい人事評価が実現できます。
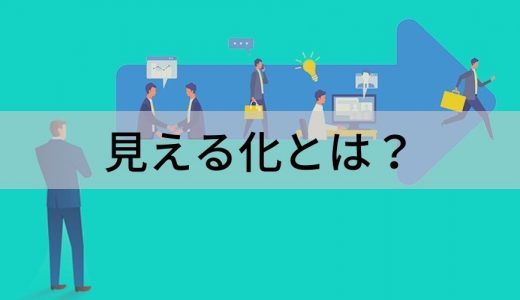
見える化とは? 必要な理由、メリット、具体例を簡単に
見える化とは、さまざまな活動や状況を視覚化することです。ここでは見える化について、さまざまなポイントから解説します。
1.見える化とは?
見える化とは、組織にて業務・財務・そのほかさまざまな活動を具...
②業務アサインを適切に行う
タスクを割り振る際は、メンバーのスキルや得意分野、そして業務の優先度を考慮することが大切です。
ただし、テレワークでは一人ひとりの仕事量や忙しさが見えにくく、仕事が特定の人に偏ってしまう可能性があります。そうならないように、定期的なミーティングや進捗報告を通じて、各メンバーの状況をしっかり把握しましょう。
そのうえで業務を適切に割り振れると、誰かに負担が集中するのを防ぎ、チーム全体の効率や成果を安定して保てます。
③報連相のルールを徹底する
リモートワークでは、対面でのやりとりがない分、情報の行き違いや伝達漏れが起こりやすくなります。そうした問題を防ぐためには、「報告・連絡・相談(報連相)」のルールを明確にし、全員で守ることが大切です。
たとえば、下記のような基本的なルールをあらかじめ決めておきましょう。
- 重要な話はチャットではなくビデオ通話で伝える
- 急ぎの連絡は電話ですぐに行う
- 毎日決まった時間に業務報告を共有ツールで提出する
また、既読確認ができるツールを使い、24時間以内の返信をルール化することで、情報の滞留や対応の遅れを防げます。
④セルフマネジメントを促進する
テレワークでは、集中力が続かなかったり、仕事のペースが乱れやすかったりする人もいます。そうした従業員には、少しずつセルフマネジメント力を身につけられるようにサポートすることが大切です。
まずは、業務の目標やゴール、その人に期待されている役割や成果をきちんと伝えましょう。
そのうえで、進捗状況を定期的に確認しながら、フィードバックやアドバイスを行います。すると、従業員自身が計画的に仕事を進められるようになり、徐々に自己管理力が養われていくのです。

セルフマネジメントとは? 自己管理能力を高める方法を解説
セルフマネジメントとは、自分の思考や感情、行動を管理して自己パフォーマンスを向上させること。ビジネスパーソンに欠かせないスキルの1つであり、後天的に身につけることが可能なスキルです。
今回はセルフマネ...
⑤ミドルマネージャーを育成する
テレワーク環境では、現場を支えるミドルマネージャーの役割がこれまで以上に重要になります。彼らは、経営層の方針を理解しながら、現場メンバーの声にも耳を傾ける「橋渡し役」です。
リモートでも効果的にチームをまとめられるように、ミドルマネージャーにはマネジメントスキルを高める研修や、実践的なトレーニングの機会を積極的に用意しましょう。
こうしたサポートによって、組織内での情報共有や方針の浸透がスムーズに進み、テレワークでも強いチームづくりが可能になります。

ミドルマネージャー/中間管理職とは?【役割を解説】
企業を取り巻く環境が激変する現在、組織を支えるミドルマネージャーに求められる役割も大きく変化しています。ここでは、ミドルマネージャーに求められる役割と、その育成方法、働き方を見直す取り組みについて紹介...
6.テレワークマネジメントの注意点
テレワークで成果を上げるために、注意すべきリスクもあります。あらかじめ注意点を把握しておくと、マネジメント上のトラブルを未然に防ぎ、テレワーク運用をよりスムーズに進められるでしょう。
セキュリティ対策を行う
テレワークでは、自宅や外出先など社外の環境から会社のシステムにアクセスする機会が増えるため、情報漏えいのリスクが高まります。そのため、安全に業務を行うための対策を施しましょう。
たとえば、VPN接続の徹底、パスワードに加え認証コードなどを使う多要素認証の導入、パソコン・スマートフォンデータの暗号化などが考えられます。
さらに、従業員に対して定期的なセキュリティ研修を実施し、日頃から情報を正しく扱う意識を高めていくことも大切です。
定期的なコミュニケーションを図る
テレワークでは、自然な会話の機会が減るため、意識的にコミュニケーションの場をつくらないと、チームのつながりが弱くなってしまうおそれがあります。
それを避ける例として、週に3回のチームミーティングに加え、毎日15分ほどの朝礼や昼礼を取り入れると効果的です。
また、雑談専用のオンラインルームを常時開けておいたり、コーヒー休憩をビデオ通話で一緒に過ごしたりするなど、リラックスできる時間を共有する工夫もおすすめです。
Web会議ではカメラをオンにして、お互いの表情を確認することで、ちょっとしたモチベーションの変化にも気づきやすくなります。
適切なツールを導入する
テレワークでは、社員の働き方や業務の進み具合を正しく把握するために、専用のツールが欠かせません。具体的には、次のようなツールが多くの企業で活用されています。
- ビジネスチャットツール:リアルタイムでの情報共有や迅速なコミュニケーションに最適。
- タスク管理ツール:各メンバーの業務内容や進捗を可視化し、チーム全体の生産性を向上。
- 人事評価システム:目標設定から評価までを一元管理し、テレワーク環境下でも適切な評価を実現。
- 勤怠管理システム:出退勤時刻や休憩時間を正確に記録し、労働時間を正しく管理。
これらのツールを適切に組み合わせることで、テレワーク下でも組織運営の精度を高められます。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード7.テレワークマネジメントの企業事例
テレワークの導入により、多くの企業が新しいマネジメント手法を模索中です。ここでは、株式会社セレブリックスと阪急阪神不動産株式会社の事例を紹介します。
具体的な成功例を参考に、自社に適した取り組みを考えるヒントにしてください。
株式会社セレブリックス
株式会社セレブリックスは、営業支援サービスを提供する企業で、コロナ禍を契機にテレワークを本格導入しました。同社は、多様な働き方に対応するべく人材管理強化の必要性を感じ、人材管理システム「カオナビ」を導入。
中でも社員のコンディション把握を目的に、スマートフォンからも回答できる「パルスサーベイ」を活用しています。回答率は常に7〜8割と高水準を維持しており、リアルタイムな社員の状況把握が可能です。
調査の結果、テレワーク中における上司からのフォロー不足や、メンタルスコアの低下といった課題が浮き彫りになりました。
そこで、面談希望者や健康スコアが一定水準を下回る社員に対してフラグを立て、1on1ミーティングを積極的に実施しました。
さらに、リモート環境下で減りがちな社内交流を促進するため、スキル共有や経験報告ができる「ボイスノート」機能を活用しています。
これらの情報は「プロファイルブック」で一元管理され、本人の志向やチームのニーズに応じた人員配置と登用にも役立てられています。
参照:カオナビ導入事例「コロナ後に加速した【多様化した働き方】をカバーできた理由」
阪急阪神不動産株式会社
阪急阪神不動産株式会社は、2018年4月に阪急不動産、阪急電鉄、阪神電気鉄道の不動産部門が統合して誕生した企業です。
多様な働き方が求められる中、部門間の一体感を高め、社員同士の連携強化と業務のデジタル化を進めるために、人事管理システム「カオナビ」を導入しました。この取り組みにより、以下のような具体的な成果が得られています。
- 社員情報の可視化:趣味や特技なども含めた詳細な社員情報を共有。お互いの“顔”に加えて“人となり”も見える化。所属部署を超えた連携の促進。
- 評価業務の効率化:目標設定や人事考課をシステム化。集計や確認作業を大幅に削減し、評価に費やす時間を確保。
- スムーズな課題の調査・分析:「ボイスノート」のアンケート機能を活用し、設問の作成から配信、集計までを円滑に実施。
オンライン環境でも表情を確認しながらやり取りできる「カオナビ」の存在が、社員同士のつながりを保つうえで大きな支えとなっています。
参照:カオナビ導入事例「統合に伴う「新たな組織文化」を醸成する人事を目指して」
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)

