部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
従業員の突然の退職は、チームや業務に大きな影響を与えます。しかし実際には、退職を考えている人には、いくつか共通した前兆や特徴があります。
突然の離職を防ぐためには、こうしたサインを早期に察知し、適切に対応することが重要です。
この記事では、仕事を本当に辞める人に見られる行動の変化や退職の主な原因、離職しやすい人の特徴に加えて、上司や人事担当者が取るべき具体的な対応策・予防策までをわかりやすく解説します。
1.仕事を本当に辞める人の6つの前兆
会社で「最近、あの人ちょっと様子が違うな」と感じたことはありませんか?それは、もしかすると「本当に仕事を辞める人」が見せる前兆かもしれません。ここでは、仕事を辞める人に共通する6つの前兆を詳しく解説します。
仕事の効率や生産性が落ちる
仕事を辞めようと考えている人は、仕事への意欲が低下し、効率や生産性が落ちる傾向があります。以前は積極的に取り組んでいた業務に対して消極的になり、締め切りに間に合わなかったり、ミスが増えることがあります。
これは、現在の職場に対する関心が薄れ、新しい環境への期待が高まっているためかもしれません。また、転職活動に時間を割いているため、仕事に集中できていない可能性もあります。
新しい仕事に消極的になる
退職を考えている人は、新たなプロジェクトや重要な役割を避けることがあります。これは、「どうせ辞めるのだから、新しいことを始めても意味がない」という考えが背景にあるかもしれません。
また、退職時の引き継ぎを考えると、新しい仕事を増やしたくない、関与しない方がよいという心理も働いているでしょう。
長期的なプロジェクトへの参加を躊躇したり、新しいスキルの習得に消極的になったりする様子が見られたら、退職の兆候かもしれません。
会議での発言が減る
会議中の発言が急に少なくなることも、退職を考えている人の特徴の一つです。これまで積極的に意見を述べていた人が、突然黙り込むようになったら要注意です。
この行動の背景には、現在の仕事への興味喪失や、自分が関与しない将来の計画について無責任な発言を避けたいという思いがあるかもしれません。
また、退職の意思が固まっているため、会社の将来に関する議論に参加する必要性を感じていない可能性もあります。
遅刻や早退、休みが増える
これまできちんと出社していた人が、急に遅刻や早退、欠勤を繰り返すようになるのも、明確な前兆のひとつです。
表向きには「体調不良」や「家の用事」と説明していても、実際には転職活動の面接や企業説明会などに参加しているケースもあります。
また、退職を決めた後、有給休暇を計画的に消化している可能性も考えられます。
ただし、精神的なストレスや職場へのモチベーション低下によって、出社自体が苦痛になっていることもあるため、従業員の状況を理解しようとする姿勢が大切です。

モチベーションとは? 意味や下がる原因、上げる方法を簡単に
従業員のモチベーションの可視化と分析ができる「カオナビ」
⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから
従業員のモチベーションが上がらずにお悩みではありませんか? カオナビなら、従業員のモチベ...
周囲とコミュニケーションが減る
退職を考えている人は、職場の人間関係を深めようとせず、むしろ距離を置くようになります。
例えば、ランチをひとりで取るようになる、雑談の輪に加わらなくなる、飲み会を避けるようになる、などが挙げられます。
この行動の背景には、退職の意思が周囲に気づかれないようにする意図や、人間関係の深まりによって退職が難しくなることを避けたいという心理があるかもしれません。
私用による離席が増える
勤務中に頻繁にスマホを見たり、長時間席を外すようになる場合、それも退職を考えているサインの一つです。多くの場合、転職活動の連絡対応や面接の調整など、私用での対応が増えている可能性があります。
また、気持ちが仕事に向いていないため、トイレや休憩スペースに行く頻度が増えるということもあります。これらの行動が習慣化しているときは、本人が心の中ですでに次のステップに気持ちを切り替えている証拠とも考えられます。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.仕事を辞めてしまう原因・理由
職場で「辞めたい」と感じる人が増えている背景には、さまざまな理由があります。ここでは、仕事を辞めてしまう主な原因を詳しく解説します。
給与や評価に不満がある
多くの従業員が退職を考える大きな要因の一つが、給与や評価に対する不満です。努力しても成果が評価に反映されないと感じると、モチベーションが低下し、他の職場を探す動機となります。
特に、優秀な人材ほど自分の市場価値を理解しており、現状の待遇に満足できない場合、転職を検討する傾向があります。
企業側は、公平で透明性の高い評価制度を構築し、給与体系の見直しや成果に応じた報酬制度の導入なども検討する必要があるでしょう。

人事評価の不満は退職のリスク!【離職を防ぐ方法とは?】
人事評価は社員のモチベーションを大きく左右するものです。
自分が思っていたよりも評価結果が低く理由に納得できないと、社員は不満を抱き、退職を考えるきっかけになります。
人事評価に不満を抱いている社員は...
やりがいや成長を感じられない
仕事に対するやりがいや自己成長の実感が得られないと、従業員は職場に対する魅力を感じなくなります。特に若い世代や、キャリア志向の強い人にとって、自己成長の機会は非常に重要です。
現状に停滞感を覚えると、新しい挑戦やスキルアップの機会を求めて転職を考えることがあります。そのため、企業は従業員に対して適切な挑戦の機会を提供し、個々の能力や興味に合わせたキャリアパスを示すことが求められます。

やりがいとは?【わかりやすく解説】搾取、種類、見つけ方
1.やりがいとは?
やりがいとは、「ものごとを行った際の充足感」や「やってよかった思う気持ち」のこと。やったことに対する効果や価値、手応えなどを示す言葉です。やりがいの「やり(遣り)」は「やること...
人間関係がうまくいっていない
職場の人間関係は、働く上での満足度に大きく影響します。上司や同僚との関係が悪化すると、職場での居心地が悪くなり、退職を考える原因となるでしょう。
特に、上司からの過度なプレッシャーや、同僚とのコミュニケーション不足、チームワークの欠如などが、職場環境の悪化につながります。
企業は、オープンなコミュニケーションを促し、チームビルディング活動を通じて良好な人間関係を構築するなどの取り組みが求められます。
また、ハラスメント防止のための研修や、相談窓口の設置など、従業員が安心して働ける環境づくりに努めることが重要です。

ハラスメントとは? 意味や定義、種類一覧、実態、対策を簡単に
ハラスメントは相手に嫌がらせを行うこと。1980年代後半からセクシャルハラスメントという言葉が飛び交うようになり、近年はパワハラ、マタハラ、モラハラなどさまざまなハラスメントが社会問題になっているので...
メンタルヘルスに不調がある
過度なストレスやプレッシャーにより、メンタルヘルスが悪化すると、仕事を続けることが困難になります。
厚生労働省が令和5年に実施した調査によると、メンタルヘルスの不調を理由に、直近1年間で1カ月以上の連続休職や退職に至った従業員がいた企業の割合は13.5%に達しました。
長時間労働、過度なストレス、人間関係のトラブルなどが原因で、心身の健康を損なうケースが増えています。
企業は、ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の開催、産業医や専門家との連携、労働時間の適正管理など、具体的な対策を講じる必要があるでしょう。
また、管理職への教育を通じて、部下の変化に気づき適切なサポートができる体制を整えることも大切です。
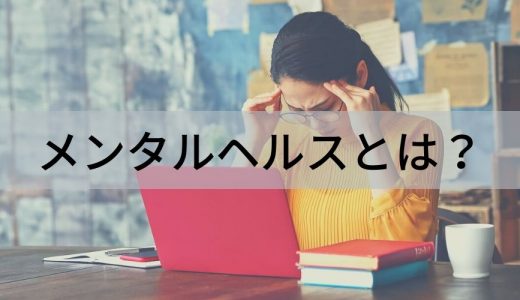
メンタルヘルスとは? 不調のサイン、職場でできるケアや対策を解説
メンタルヘルスとは、精神面・心の健康状態のこと。メンタルヘルスが不調な状態では仕事へのモチベーションや集中力などが低下し、生産性や業績の低下を招く恐れがあります。従業員の心身の健康のため、安定した経営...
出典:厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」
家庭の事情
結婚、出産、育児、介護などのライフイベントにより、現在の仕事との両立が困難になる場合、退職を選択することがあるでしょう。
企業は、テレワークや休暇の取得推進など、従業員のライフステージの変化に柔軟に対応できる制度や環境を整備すること求められます。
別業界に興味がある
キャリアアップや新しい分野への挑戦を求めて、別の業界や職種に転職を考える人も少なくありません。
こうした人に対しては、社外での経験が積める「越境学習」として、他社への出向や副業を認めるなどの柔軟な制度を取り入れることで、離職を防げる場合もあります。
ただし、会社の取り組みだけでは引き止めが難しいこともあります。その場合は、本人の気持ちを尊重し、前向きな形で送り出す姿勢も大切です。
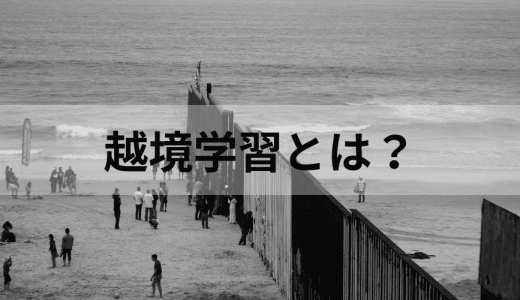
越境学習とは? 導入のメリットや具体的な手法、企業事例を解説
近年、ビジネス環境の変化が加速する中で、実践的な学びの手法として「越境学習」への関心が高まっています。これは、組織の枠を越え、他業界や他分野での実践を通じて学びを深める取り組みです。
その結果、視野の...
3.仕事を辞めてしまいやすい人の特徴
職場での退職は、個々の性格や価値観が大きく影響します。ここでは、仕事を辞めてしまいやすい人の特徴を詳しく紹介します。
責任感が強い
責任感が強い人は、与えられた業務を完璧にこなそうとする傾向があります。しかし、その真面目さから過度な負担を抱え込みやすいのです。
特に、仕事を断ることが苦手な場合、業務量が増えすぎて心身ともに疲弊してしまうことがあります。
また、愚痴を言わず黙々と仕事をこなすため、周囲からは問題が見えづらく、突然退職するケースも少なくありません。企業側は、業務の負担を適切に分配し、従業員のストレス状況を定期的にチェックすることが重要です。

責任感とは? ビジネスで必要な理由、責任感が強い人の特徴
責任感は、周囲との信頼関係や仕事の成果にかかわる重要な要素です。今回は、責任感の定義からその重要性、強い責任感を持つ人の特徴、そして責任感の強め方などについて紹介します。
1.責任感とは?
責任感...
内向的
内向的な性格の人は、不満や悩みを周囲に相談できず、自分の中で抱え込んでしまいます。そのため、問題が深刻化しても周囲が気づきにくく、突然の退職につながるケースも。
企業としては、内向的な従業員にも安心して相談できる環境を整えたり、定期的な面談を実施したりすることで早期対応が可能になります。
キャリア志向が強い
キャリア志向が強い人は、自分の成長やスキルアップに敏感であり、現状の職場環境や仕事内容に限界を感じた場合、退職を決断することがあります。
特に会社の将来性や評価制度への不満があると、新しい環境で自分の価値を高めたいと考えることがあるでしょう。このような人材には、明確なキャリアパスや成長機会を提供することで、退職リスクを軽減することが可能です。
ストレス耐性が低い
ストレスに対する耐性が低い人は、職場でのプレッシャーや人間関係のトラブルに過敏に反応しやすいです。小さな問題でも大きな負担と感じ、心身の不調を引き起こすことがあります。
その結果、ストレスから逃れるために退職という選択肢を取ることがあるでしょう。特に、人間関係のトラブルや過度な業務負担は、このタイプの人にとって大きな問題となります。
企業側は従業員のストレスレベルを把握し、適切なサポート体制やストレス軽減策を導入する必要があります。
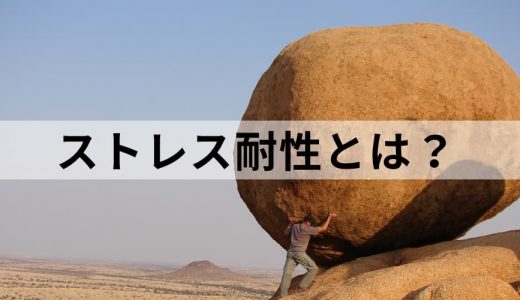
ストレス耐性とは? 高い人・低い人の特徴、高める方法を解説
従業員のストレスを把握できていますか?
アンケートやサーベイ、豊富な分析機能でストレス対策をサポートします。
⇒ 【公式】https://www.kanavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロ...
4.仕事を辞める前兆がある人への対応方法
従業員が退職を考えている際には、必ず何らかのサインが現れます。これらの前兆を見逃さず、適切な対応を取ることで、人材の流出を防ぐことが可能です。以下に、具体的な対応方法を解説します。
早めに話を聞く場を設ける
退職の兆候が見られる従業員には、早期に話を聞く場を設けることが重要です。定期的な1on1面談やカジュアルなランチミーティングなど、リラックスした雰囲気で話せる機会を作りましょう。
この際、従業員の不満や悩みを丁寧にヒアリングし、共感する姿勢を示すことが大切です。
ただし、無理に深掘りした質問や押し付けがましいアドバイスは避けるべきです。従業員が自分の気持ちを吐き出すことで、冷静に退職について再考する可能性もあります。
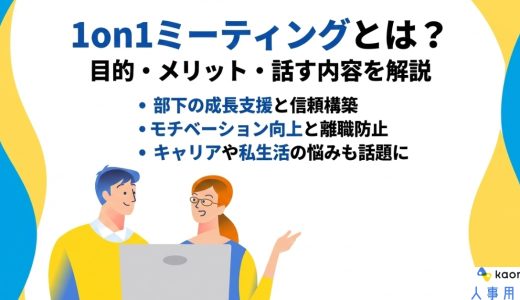
1on1とは? 目的や導入効果、面談との違いとやり方を簡単に解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入す...
キャリアプランを一緒に考える
退職を防ぐためには、従業員のキャリアプランを一緒に考えることが効果的です。キャリア面談で本人の目標や希望を整理し、それに沿った成長機会やキャリアパスを提示しましょう。
例えば、新しいプロジェクトへの参加やスキルアップのための研修制度など、従業員が将来に希望を持てるような提案が必要です。
また、キャリアチェンジや昇進の可能性についても具体的に話し合うことで、会社内での活躍の道筋を示すことができます。

キャリアプランとは? 重要な理由や年代別の考え方、書き方、例文を解説
従業員のキャリアプランを支援するためのタレントマネジメントとは?
概要や具体的なやり方をわかりやすく解説!
⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
キャリアプランとは、将来...
待遇や配置を見直す
従業員が抱える不満が待遇や配置、人間関係に関する場合、それらを見直すことも有効です。給与や福利厚生などの改善だけでなく、業務量の調整や適切な配置転換も検討しましょう。
特に、人間関係や業務内容が原因の場合は、本人と相談しながら解決策を模索する姿勢が求められます。企業側が協力的な態度を示すことで、従業員は会社への信頼感を取り戻し、退職意向を再考する可能性があります。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.仕事を辞める人の引き止め方
従業員の退職は、組織にとって大きな損失となり得ます。特に、優秀な人材の離職は、業務効率の低下や他の従業員の士気に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、退職の意向を示す従業員に対して、適切な引き止め策を講じることが重要です。ここでは、効果的な引き止め方法を具体的に解説します。
組織にとって必要な存在であることを伝える
従業員を引き止める際に重要なのは、その人が組織にとって不可欠な存在であることを具体的に伝えることです。これまでの業務実績やチームへの貢献など、客観的事実を交えて評価しましょう。
ただし、曖昧な褒め言葉ではなく、事実ベースの説明が効果的です。企業側が真摯な姿勢を示すことで、従業員は自身の価値を再認識し、退職を再考する可能性があります。
一緒に原因を探り、前向きな対応策を検討する
退職を考える背景には、業務上の課題や人間関係、キャリアの停滞感など、さまざまな要因が存在します。これらの問題を解決するためには、従業員とのオープンなコミュニケーションが不可欠です。
まずは、退職を考えるに至った具体的な理由を丁寧にヒアリングし、その上で共に解決策を模索しましょう。
例えば、業務量の過多が原因であれば、タスクの再分配や業務プロセスの見直しを検討します。キャリアアップを望む場合は、社内公募制度や資格取得支援制度の活用を検討できるでしょう。
このように、具体的な解決策を提示し、実行に移すことで、従業員は組織が自分の声に耳を傾け、改善に取り組んでいると感じることができます。
産業医への相談や休養を勧める
メンタルヘルスの不調が疑われる場合は、産業医やカウンセラーとの面談を手配し、従業員が抱えるストレスや悩みを専門的にケアしましょう。場合によっては、一定期間の休養を提案し、心身の回復を図ることも必要です。
また、休職中も定期的に連絡を取り合い、復帰後の労働条件について計画を立てることで、従業員は安心して回復に専念できます。企業としては専門家と連携しながら慎重に対応することが求められます。

産業医とは? 種類、職務内容、設置要件
産業医とは、社員の健康管理を行う医師のこと。今回は産業医の職務内容、導入するメリットやデメリットについて説明します。
1.産業医とは?
産業医とは、社員の健康状態を良い状態に管理するため、専門的な立...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.仕事を辞める人を減らすためにできること
一度仕事を辞めたいと意思を固めた従業員の気持ちを変えるのは、簡単なことではありません。だからこそ、日頃から「この職場で働き続けたい」と感じてもらえるような環境づくりが必要です。
さいごに、従業員の離職を未然に防ぐために企業が実践できる取り組みをご紹介します。
多様な働き方を取り入れる
多様な働き方を導入することで、従業員の離職を防ぎ、生産性を向上させることができます。
フレックスタイム制やテレワークなどの柔軟な勤務形態を取り入れることで、従業員は育児や介護との両立がしやすくなり、ワークライフバランスを充実させることができるでしょう。
また、副業や兼業を認めることで、優秀な人材の流出を防ぎながら、従業員のスキルアップや所得増加の機会を提供できます。これらの取り組みは、従業員のモチベーション向上につながり、結果として企業の競争力強化にもつながります。
風通しの良い職場環境をつくる
職場の雰囲気が良く、意見や相談がしやすい環境は、社員が辞めにくくなる大きなポイントです。
そのためには、定期的な1on1面談の実施や、匿名で意見を出せる「意見箱」を設置を通して、従業員の声をきちんと受け取れる仕組みをつくるとよいでしょう。
上司がしっかり話を聞いて、出てきた意見を職場改善に活かすことで、信頼関係も深まります。
また、チーム内外のコミュニケーションを活性化させる取り組みも、風通しの良い職場づくりに効果的です。このような環境は、社員の満足度と定着率を高めます。
キャリア支援を行う
従業員の離職を防ぐには、キャリア支援の充実が欠かせません。定期的にキャリア面談を行い、目標や悩みをしっかり聞いたうえで、その人に合った研修や部署の異動などを提案すると、成長を実感しやすくなり、仕事への意欲も高まります。
また、メンター制度やワークショップ、資格取得の支援など、自分のキャリアを自ら考えられる仕組みを用意することで、自主性が育ち、長く働き続ける人も増えるでしょう。
定期的にストレスチェックを実施する
従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐためには、定期的なストレスチェックの実施が有効です。
ストレスの度合いや原因を早期に把握できるため、必要に応じてカウンセリングの案内や、仕事の内容・勤務時間の見直しなどの対応ができます。
また、ストレスチェックの結果を分析して職場全体の問題点を見つけ、環境の改善につなげることも可能です。
こうした取り組みによって、従業員が長く働きたいと思える環境が整えば、メンタルヘルス不調による退職も防げるでしょう。
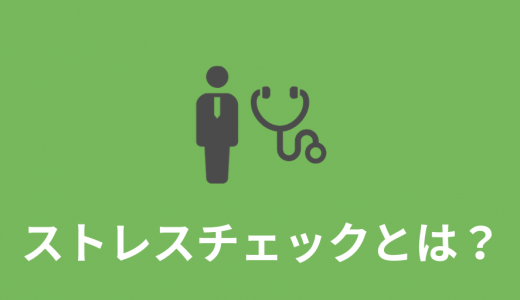
ストレスチェックとは?【実施方法を簡単に】義務化、目的
ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正によって50人以上の労働者がいる事業場で義務付けられた検査です。
定期的に労働者のストレスをチェックすることで、労働者が心身の状態に気付き、メンタルヘルスの不調...
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

