マネジメントとは、経営管理・組織運営の手法のこと。マネジメントするうえで、なぜマネジメントが必要なのか、どういった役割やスキルを持って課題解決に取り組めばよいのかを知っていると知っていないとでは、マネジメントの質にも差が出るでしょう。
今回はマネジメントとは何かをふまえ、その必要性や役割、求められるスキルやマネジメント能力を高める方法などをご紹介します。
目次
1.マネジメントとは?
マネジメントとは、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を効率的に運用し、目標達成のために組織を機能させることです。「経営管理」や「組織運営」とも言い換えられます。アメリカの経営学者P .F.ドラッカーは、マネジメントを「組織に成果を上げさせるための道具、機能、機関」と定義しています。
2.マネジメントの必要性
マネジメントは企業の目標達成や持続的な成長・発展のために必要です。マネジメントによって組織が進むべき方向(目標)に向かって経営資源を効率的に活用・最適化し、達成するための組織運営が行えます。
目標達成のためにはマネジメントを通して計画を策定、適切なアクションを実行することが重要です。具体的には、スムーズな業務遂行のために取り組むべき目標や優先順位を明確化し、経営資源を最大限活用して効率的な組織運営に取り組みます。
マネージャーはチームメンバーが目標達成に向けて動くための指揮役であると同時に、メンバーや取り組みの評価を行い、改善に必要な戦略的な計画を実行する役割を担うのです。
3.マネージャーとは?
マネージャーとは、企業の目標達成に向けて組織やチームのマネジメントを行う人材です。一般的には管理職を指します。マネージャーという役職の定義やその仕事内容は企業によって様々ですが、基本的には組織の目標設定、その達成に向けたメンバーの管理やサポートが主な業務となります。
ニュアンスが似ているリーダーとの違いは、リーダーが「人や組織の目的地を決め、先導する人」であるのに対して、マネージャーは「目的地に向かう道を整え、サポートする人」という点で異なります。

マネージャーとは? 役割や仕事、スキル、リーダーとの違いを解説
マネージャーとは、組織やチームをマネジメントする管理職です。ひとくちにマネージャーといっても、その種類や役割は多岐にわたります。
今回はマネージャーについて、役割や種類、仕事内容や必要な能力・スキル、...
4.マネジメントの役割・業務内容
ここでは、マネジメントの役割・業務内容を詳しくみていきます。
- 目標設定と戦略策定
- リソース管理・配分
- リーダーシップ・チームビルディング
- プロジェクト管理
- 部下の育成・評価
①目標設定と戦略策定
組織や自分自身、部下の目標設定と管理を行い、組織・マネージャー自身・部下が向かう方向を示す役割を持ちます。
目標は組織の方向性を統一し個人の行動を連動させるため、組織の掲げるミッションや経営方針を踏まえて設定することがポイントです。また、目標を達成するための計画や戦略を策定することも重要な仕事になります。
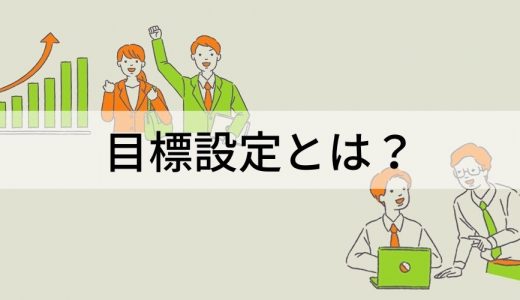
目標設定とは?【設定のコツを一覧で】重要な理由、具体例
目標設定は、経営目標達成や個人のレベルアップのために重要なもの。適切な目標設定ができないと、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやるべきことも洗い出せなくなってしまうでしょう。
今回は...
②リソース管理・配分
経営資源を最大限活用し、組織運営を最適化するために必要な場所に必要なリソースを配分・管理します。その後も、臨機応変に調整や再分配を行うのです。
この際、ただ配分するだけでなく、全員が最大限のパフォーマンスを発揮できるよう人材の適材適所を見極めるとよいでしょう。

リソース管理とは?【やり方をかんたんに】重要性、ツール
リソース管理とは、企業活動に必要な経営資源を効率的に活用できるよう管理することです。管理対象となる主なリソースは、ヒトやカネ、モノや情報など。リソースが適切に管理できていなければ、適切かつ円滑な企業活...
③リーダーシップ・チームビルディング
チームメンバーの指導やコーチング、モチベーション管理(動機づけ)といったリーダーシップやチームビルディングもマネジメントの重要な役割です。
モチベーションは生産性にもかかわるためとくに重要で、チームビルディングはメンバー間の信頼構築をサポートするために欠かせません。
人材に関するリソース配分もチームビルディングの一種で、よいチームは目標達成への効率化や自律的なスキルアップ、従業員エンゲージメントの向上が望めます。

チームビルディングとは? 手法や効果、やり方、具体例を簡単に
1.チームビルディングとは?
チームビルディングとは、組織のパフォーマンス向上を図るための活動を意味する言葉で、個々人の能力や個性を最大限に発揮するための環境づくりや取り組み全般を指します。ワー...
④プロジェクト管理
マネジメントでは、プロジェクト進行におけるマネジメントの役割・業務も担います。具体的な業務は、進捗状況の把握やプロジェクトにおける問題解決、スケジュール管理やリスク管理など。
またマネジメントをとおして、プロジェクト成功のためチームビルディングも行います。

プロジェクトマネジメントとは?【やること・効果を簡単に】
プロジェクトマネジメントとは、期日までに目的を達成する管理手法です。ここでは、プロジェクトマネジメントについて解説します。
1.プロジェクトマネジメントとは?
プロジェクトマネジメントとは、定められ...
⑤部下の育成・評価
組織や部下の目標に対する評価と改善も重要な仕事内容です。効率的に目標を達成し、組織の成長へとつなげるためには目標に対する評価が重要です。また適切な評価は、部下のモチベーションアップにも貢献し、組織力の向上にもつながります。
部下によって育成方法は異なるため、相手の適性や価値観、強み・弱みを把握したうえで、一人ひとりに即した育成方法を取り入れるのが重要です。適切な育成により部下と意思疎通できればよいチームが構築でき、目標も達成しやすくなります。
5.マネジメントとリーダーシップの違い
マネジメントは目標の設定・達成のため組織運営を行うのに対し、リーダーシップは目標を達成するために方向性を示す役割を持つのです。目標を達成するといった目的は同じであるものの、求められる能力に違いがあります。
またリーダーシップの管理対象はヒトですが、マネジメントはすべての経営資源が対象です。そしてマネジメントは目標達成のための方法を示す(how)のに対し、リーダーシップは手段(what )を示す点でも違いがあります。
なお、リーダーシップはマネジメントに必要な能力のひとつです。

リーダーシップとは? 種類や理論、ある人の特徴、高め方を解説
リーダーシップは、組織やチームを成功へ導くために必要不可欠な能力です。現代のビジネスやコミュニティでは、その重要性がますます高まり、リーダーシップのスタイルも多様化しています。
この記事では、リーダー...
6.マネジメントの種類
ひとくちにマネジメントといっても、組織におけるポジションや役割によって求められるマネジメントレベルは異なるもの。ここでは、マネジメントの種類を解説します。
- トップマネジメント
- ミドルマネジメント
- ローアーマネジメント
- 業務別マネジメント
①トップマネジメント
会長や社長、常務や専務などの取締役会メンバーや執行役員などによる、経営層のマネジメント。役割は、企業の基本方針や経営方針を決定し、経営計画や戦略を策定することです。経営に関する意思決定や最終的な責任を担い、企業・組織全体の統括を行います。

トップマネジメントとは? 意味、役割、スキルなどを解説
企業のトップの力を最大限引き出すことができれば、生き残るために不可欠な強い企業づくりに役立ちます。そこで注目を集めているのがトップマネジメントです。
ここでは、
トップマネジメントとは何か
トップマ...
②ミドルマネジメント
部長や課長、係長やマネージャーなどの中間管理職が担うこと。経営陣と現場の橋渡しとして機能します。
ミドルマネジメントでは、トップマネジメントの決定や考えを正しく理解し、現場に伝えることが求められるのです。反対に、現場の意見を経営陣に伝える役割も持ち、組織の意思疎通に欠かせない立場といえます。
また経営資源を実際に活用するポジションであり、チームや部下の目標設定、人材育成やプロジェクト管理などを実行し、業務の根幹を支える役割を持つのです。
③ローアーマネジメント
チームリーダーや現場監督など、現場レベルのマネジメントのこと。目標達成に向けた計画や戦略を達成するため現場のメンバーを指揮監督し、現場の業務遂行を支える役割を持つのです。
ミドルマネジメントの指示を具体的に現場に反映し、実行する重要な役割を担い、進捗管理やタスク割り当て、チームビルディングや課題解決などを行います。
④業務別マネジメント
業務に応じて、求められるマネジメントは次のようにさまざまです。
- チームマネジメント
- リスクマネジメント
- プロジェクトマネジメント
- プロセスマネジメント
- メンタルヘルスマネジメント
業務レベルのマネジメントは、ミドルマネジメントやローアーマネジメントにおいて求められることが多く、状況に応じた使いわけが重要です。
7.マネジメントの課題と解決策
ここでは、マネジメントにおいてよくみられる課題と解決策をみていきます。
- 部下とうまくコミュニケーションできない
- 部下の生産性が上がらない
- 強いプレッシャーを抱えてしまう
- マネージャー自身が業務過多になる
- 課題や問題を解決できない
①部下とうまくコミュニケーションできない
たとえば「部下が指示どおり動いてくれない」「報連相ができていない」「部下との関係を構築できない」など。素晴らしいコミュニケーションがとれれば、チームの状況もよくなり、従業員エンゲージメントの向上にもつながります。
解決策としては信頼関係の構築が有効であり、具体的には次のような策がおすすめです。
- 必要に応じた声掛け
- コミュニケーションツールの活用
- チーム内の情報共有ルールの明確化
- 1on1ミーティングの実施

1on1ミーティングとは? 目的や効果、やり方、話すことを簡単に
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入する...
②部下の生産性が上がらない
生産性の低下は目標達成が遠のくだけでなく、モチベーションが低下してしまう重大な課題です。そもそも「従業員のモチベーションが高くない」「割り振っている業務や配置が適していない」場合、業務プロセスに改善の余地がある可能性もあります。
下記は、解決策の一例です。
- 部下と面談やミーティングをとおしてコミュニケーションを図り、モチベーションを高める
- 業務プロセス、ワークフローを見直す
- 職場環境や配置、割り振っている業務の見直し
③強いプレッシャーを抱えてしまう
マネジメントしている側の課題に、強いプレッシャーを抱えてしまうことが挙げられます。
「成果を出さなきゃいけない」「目標を達成しなきゃいけない」というプレッシャーや、リーダーとしての責任ある立場に感じるプレッシャーなどその内容は人によってさまざま。
これらは、マネジメント経験が浅い人に見られがちな課題です。「マネジメントは経験から培われるもの」「失敗や成功から学ぶことが多い」といった前提があると理解しておきましょう。
マネジメントする立場の努力だけではどうにもならないことも多々あります。よって自分を追い込みすぎないことが非常に大切なのです。なおた具体的な解決策は次のようになっています。
- 達成可能な目標を設定する
- セルフマネジメント、セルフケアを身につける
段階的に達成できる目標を設定し、成功体験を積み上げれば自信もつきます。それによりモチベーションが維持されて、マネジメントにも取り組めるようになるでしょう。
④マネージャー自身が業務過多になる
「部下を信頼できず結局自分で対応してしまう」「人員不足からプレイヤー業務が多くマネジメントに当てる時間がない」といった課題もよくみられます。こうした課題への解決策は、下記のとおりです。
- 自身の考え方を変える(例:失敗から学ぶこともある、といったもの)
- 業務内容やワークフローを見直す
- メンバーのスキルや割り振っている業務を精査する
⑤課題や問題を解決できない
「部下のトラブルをどう解決すればいいかわからない」「部下からの相談に対して適切な解決策が見つけられない」「解決のために計画を立てても現場に反映されない」といった課題をもつ人も多いでしょう。下記は、具体的な解決策です。
- 積極的にほかの管理職やメンバーに相談する
- 問題や課題を言語化、可視化してみる
- ミーティングや普段のコミュニケーションをとおしてメンバーとの意思疎通を図り、共通認識を得る
1人で抱え込むのではなく、自分の課題を可視化し、周囲に相談したり、意思疎通を図る姿勢を見せることが大切です。
8.マネジメントで求められるスキル・資格一覧
ここでは、マネジメントで求められるスキルや持っているとよい資格をご紹介します。
マネジメントで求められるスキル一覧
マネジメントでは、以下のようなスキルが求められます。各スキルについて詳しくみていきます。
- コミュニケーションスキル
- 問題解決スキル
- リーダーシップ力
- プロジェクトマネジメントスキル
①コミュニケーションスキル
業務やプロジェクトを円滑に進行するため、信頼関係を構築するために必要なスキルです。
日常的にチームメンバーとかかわるため、マネジメントでは適切なコミュニケーションが不可欠です。ただし一方的なコミュケーションではなく、意思疎通するための双方向的なコミュニケーションが求められます。
また、コミュニケーションスキルは適切なフィードバックを提供するためにも重要なスキルです。
②問題解決スキル
組織内で発生する問題を解決するスキルです。マネジメントでは問題を明確にし、迅速かつ的確な解決策を立案・指示する能力が求められます。問題解決スキルがないと、組織がよい方向へ向かえず、チーム全体の状況が悪化してしまう恐れもあるのです。
③リーダーシップ
目標達成に向けて部下やチームメンバーを引っ張っていくスキルです。目標やビジョンを設定・提示し、モチベーションを向上・維持していくために求められます。
マネジメントする立場にある人がリーダーシップに欠けていると、チームの統率力が弱まり、同じ方向に進めなくなってしまうでしょう。
④プロジェクトマネジメントスキル
業務やプロジェクトの進捗管理や優先順位づけを行い、ゴールから逆算して効率的に組織を運営するスキルです。
具体的には、計画立案やスケジュール作成・調整、リソース調整や実行などプロセスの最適化・効率化を図るといったもの。目標達成のためスケジュールやリソースを正しく管理し、チームとプロジェクトを正しい方向へと導くために求められます。
マネジメントにあるとよい資格一覧
下記は、マネジメントにあるとよい資格一覧です。
- PMP
- プロジェクトマネジメント・アソシエイト
- メンタルヘルス・マネジメント検定
①PMP
プロジェクトマネジメント資格、通称「PMP」は、アメリカの非営利プロジェクトマネジメント協会「PMI」が認定する資格です。
PMBOKガイドにもとづいてプロジェクトマネジメントの知識を学べ、取得によって社内外にプロジェクトマネジメントの専門家であるとアピールできます。なお取得後は、3年ごとに更新が必要です。
②プロジェクトマネジメント・アソシエイト
プロジェクトマネジメント・アソシエイトは、現場で習得すべきプロジェクトマネジメントの基本知識と技術を習得できる資格です。PMOの基本が学べ、人材育成やプロジェクトを進める際の判断に役立ちます。
研修から試験まですべてオンラインで完結できるため、慌ただしい人にもオススメです。
③メンタルヘルス・マネジメント検定
部下やチームメンバーのメンタルヘルス管理もマネジメントのひとつであり、メンタルヘルス・マネジメント検定はメンタルヘルス管理に役立つ資格です。
Ⅰ〜Ⅲの3種類があり、マネージャーレベルはⅡ〜Ⅰに該当します。Ⅲ種はセルフケアとなるため、マネージャー自身のセルフケアにも役立つのです。
9.マネジメント能力を高める方法
最後に、マネジメント能力を高める方法を3つお伝えします。
- マネジメントの知識を身につける
- マネジメントに必要なスキルを磨く
- 経営陣と連携する
①マネジメントの知識を身につける
マネジメントは経験によって培われるものの、知識があればその精度はさらに高まります。またマネジメントスキルは業種職種に関係なく共通するため、書籍やセミナー、研修などでマネジメントに関する知識を体系的に学んでみるのもよいでしょう。
知識をインプットするため、資格を取得するのもオススメです。実務でアウトプットしてマネジメント能力を高め、自分のものにしてみてください。
②マネジメントに必要なスキルを磨く
コミュケーションスキルやリーダーシップなど、マネジメントに必要なスキルを磨くのも大切です。
なかでも、コミュニケーションスキルや問題解決スキルは重要度が高いもの。現状の自分のスキルを棚卸しし、不足するスキルやより磨く余地のあるスキルを洗い出してみましょう。
③経営陣と連携する
経営陣と連携すると、経営視点を養って視座が高まります。また、マネジメントの方向性が会社とずれないよう経営陣の情報をキャッチアップするのも大切です。
とくに中間管理職によるミドルマネジメントでは、経営陣の考えを理解し、部下やチームメンバーに浸透させることが求められます。現場と経営陣の橋渡しの役割があると意識し、適切に動いていけばマネジメント能力も高まるでしょう。
