部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人材不足が深刻化するなか、社内で人材を育てる「後進の育成」が注目されています。
育成を後回しにすれば、技術の喪失や競争力低下など、組織の成長に大きなリスクをもたらしかねません。
本記事では、育成の重要性やリスクから、進め方、成功事例まで網羅的に解説します。
1.後進の育成とは?
後進の育成とは、将来の組織を担う人材を育てる取り組みです。企業や組織においては、ベテラン社員が若手社員に対して知識やスキルを伝えるだけでなく、価値観や行動指針といった組織文化の継承も重要な要素になります。
技術やノウハウを次世代へと確実に引き継ぐことは、組織の持続的な成長と競争力の維持につながります。後進育成は単なる教育ではなく、未来への投資ともいえる重要な経営課題です。
使い方
「後進の育成」という表現は、ビジネスや教育の現場で頻繁に使われます。特に組織においては、ベテラン社員が若手社員の成長を支援する役割として用いられます。以下に、代表的な使い方を整理しました。
| 表現 | 意味 | 使用例 |
| 後進の育成に尽力する | 育成に積極的に取り組む姿勢を示す | 彼は自身の業務をこなしながら、後進の育成に尽力している |
| 後進の育成にあたる | 指導・教育を実際に担当していることを示す | ベテラン社員が後進の育成にあたることで、知識が継承されている |
| 後進の育成に力を注ぐ | 組織的に育成に注力していることを示す | 当社は、将来を見据えて後進の育成に力を注いでいます |
これらの表現は意味が似ているようでいて、微妙にニュアンスが異なります。業務の中で状況に応じて適切に使い分けることで、育成に対する姿勢や立場を明確に伝えられるでしょう。
言い換え方
「後進の育成」は、文脈や対象者によって柔軟に言い換えが可能です。たとえば、代表的な言い換え表現は以下のとおりです。
| 言い換え表現 | 主な使用文脈 |
| 後継者の育成・教育 | 経営・幹部候補の育成など |
| 後輩の育成・教育 | 職場での一般的な人材育成 |
| 弟子の育成・教育 | 職人や芸術分野など |
| 伝承者の育成・教育 | 伝統技術や文化の継承場面など |
いずれの表現も、本質的には次世代に知識・スキル・価値観を伝えるという共通の意味合いを持っています。適切な場面で使い分けましょう。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.後進の育成が重要な理由
後進の育成が重要視される背景には、深刻化する人材不足の問題があります。外部からの採用だけでは即戦力の確保が難しく、近年では長期的な視点での人材戦略が求められています。
社内で計画的に人材を育てることで、専門性の高い知識やスキルを継承し、組織全体の競争力を維持できます。また、若手社員が成長機会を得られる環境を整えることは、エンゲージメントを高め、離職の防止にもつながります。
後進育成は、組織の持続的成長を支える基盤といえるでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.後進の育成に取り組むメリット
後進の育成に取り組むことは、単に人材を育てるだけでなく、組織全体にもさまざまなプラス効果をもたらします。ここでは、以下の主なメリットを紹介します。
- 組織の持続的成長と競争力の維持
- 従業員のモチベーション向上
- 従業員の定着率向上
- 技術やノウハウの継承
- コミュニケーションの活性化
組織の持続的成長と競争力の維持
後進の育成は、組織の持続的な成長と競争力の維持に直結します。ベテランから若手へと知識や技術を継承することで、組織の中核を担う人材が継続的に育ちます。
また、新しい視点や発想を持つ若手の成長は、市場の変化に対する柔軟な対応力を高める要因にもなります。将来的にリーダーとして活躍できる人材の層が厚くなれば、組織全体のリーダーシップ基盤も強化され、安定した経営につながるでしょう。
従業員のモチベーション向上
後進の育成は、育成される側の成長実感を高め、仕事への意欲向上につながります。自身のスキルや知識が深まり、成果として実感できることで、前向きに業務へ取り組む姿勢が生まれます。
また、育成を担う側の従業員にとっても、指導を通じて自らの理解を深めたり、気づきを得たりするよい機会になります。こうした双方向の成長が、組織全体のモチベーション向上と活性化を促し、職場環境の改善にもつながるでしょう。

モチベーションとは? 意味や下がる原因、上げる方法を簡単に
従業員のモチベーションの可視化と分析ができる「カオナビ」
⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから
従業員のモチベーションが上がらずにお悩みではありませんか? カオナビなら、従業員のモチベ...
従業員の定着率向上
後進の育成に取り組むことで、若手社員は自身の成長過程やキャリアパスを明確に描けるようになり、将来への不安を軽減できます。
また、メンター制度などを通じて先輩社員との信頼関係が築かれることで、職場への安心感や帰属意識も高まるでしょう。
こうした環境は従業員の定着率向上に直結し、優秀な人材の流出防止や安定した組織運営につながります。育成体制の整備は、長期的な人材確保戦略として極めて重要です。
技術やノウハウの継承
後進の育成は、企業が持つ重要な技術やノウハウを次世代へ確実に継承する手段です。
具体的には、ベテラン社員の退職によって知見が失われるリスクを抑え、組織全体で共有・活用できる体制を整えられます。
特定の人材に依存しない仕組みを構築できれば、事業の継続性と安定性を高められるでしょう。
コミュニケーションの活性化
後進の育成によって、職場内の交流が自然と増え、日常的なコミュニケーションが活性化します。育成の過程では、若手と先輩の間に信頼関係が築かれ、相互理解が深まります。
こうした関係性はチーム全体の連携を強化し、組織の一体感やパフォーマンス向上につながる大きな基盤となるでしょう。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.後進の育成に取り組まないリスク
ここでは、育成を怠ることによって発生し得る代表的な3つのリスクを解説します。
- 技術やノウハウの喪失
- 企業の成長性や競争力の低下
- 従業員のモチベーション低下
技術やノウハウの喪失
後進の育成を怠ることで、企業にとって重要な技術やノウハウが失われるリスクが高まります。特にベテラン社員の退職や引退の際に、長年培われた知見が適切に継承されていない場合は、業務品質の低下やトラブルの発生につながりかねません。
その結果、生産性の低下や取引先からの信頼失墜など、企業全体へ悪影響が広がる可能性があります。組織の持続性を確保するうえで、技術継承は不可欠です。
企業の成長性や競争力の低下
後進の育成を怠ると、将来の幹部候補や現場を支える人材が不足し、企業の成長性が損なわれます。
若手人材が十分に育たなければ、新しいアイデアや技術革新が生まれにくくなるでしょう。それが原因で、急速に変化する市場環境に適応できず、競争力を失う恐れも考えられます。
また、育成の仕組みが整っていない職場では、従業員が将来に不安を感じ、「この会社に未来はない」と判断して離職する可能性も高まります。
従業員のモチベーション低下
育成の機会が乏しい職場では、従業員が自身の成長や将来像を描けず、仕事へのモチベーションが低下します。
特に若手社員にとっては、キャリアが不透明な環境は不安要素となり、成長機会を求めて他社へ転職するケースが増加します。
人材の流出は、企業にとって大きな損失です。結果として、残された従業員の業務負担が増加し、組織全体の士気や生産性の低下につながるリスクもあるでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.後進の育成をする上での企業の課題
後進の育成は重要である一方で、企業にとっては多くの課題がともないます。ここでは、育成を円滑に進めるうえで、立ちはだかる代表的な課題を紹介します。
指導者のスキルが不足している
後進を効果的に育成するためには、指導者自身の教育スキルが不可欠です。業務に精通しているベテラン社員であっても、必ずしも指導力を備えているとは限りません。
指導方法が適切でなければ、知識やノウハウが十分に伝わらず、育成の効果も限定的になります。そのため、指導者向けに研修やトレーニングを実施し、教育スキルを体系的に高めることが、組織全体の育成力向上につながります。
育成のための時間とリソースが不足している
多くの企業では日常業務に追われ、後進の育成に十分な時間や人員を割くことが難しい状況です。
こうした課題を解消するには、育成を単なる付随業務ではなく、業務の一部として明確に位置づけ、定期的な時間を確保する仕組みが必要です。
また、オンライン学習ツールの導入などにより、時間や場所の制約を緩和し、現場の負担を抑えるなど、育成を継続する工夫も求められるでしょう。
育成を阻害する企業体質がある
企業の文化や体質そのものが、後進の育成を妨げることもあります。
たとえば、優秀な人材を囲い込みたいという部門間の競争意識や、育成の必要性を軽視する組織風土がある場合、育成活動が十分に機能しません。
こうした状況を打破するには、経営層が育成の意義を明確に示し、組織全体で育成を支える意識と協力体制を築くことが大切です。
成果が見えにくく評価が難しい
後進の育成は成果が目に見えにくく、数値化も難しいため、評価が曖昧になりやすいという課題があります。指導者の努力や育成の効果が正しく認識されなければ、モチベーションの低下を招く恐れもあるでしょう。
この問題に対処するには、育成プロセスや指導内容に対する評価基準を整備し、定期的にフィードバックを行う仕組みを設けることが重要です。公正な評価が育成の質と継続性を支える土台となるでしょう。

評価基準とは?【作り方をわかりやすく】目的、項目の具体例
評価基準とは評価するための水準であり、公平かつ客観的な評価を行ううえで重要な指標です。人事評価への不満は優秀人材の離職の原因ともなり、最悪のケースでは業績不調を招く恐れもあります。
今回は、評価基準と...
育成される側の主体性を引き出せない
育成される側が受け身の姿勢でいると、どれだけ優れた指導を行っても育成効果は限定的になります。主体性を引き出すためには、まず本人に将来のキャリアを考えさせ、その実現に必要なスキルや知識を自覚させることが重要です。
また、育成プログラムの内容や進行方法について、対象者の意見を反映させることで、自ら学ぶ意欲を高められます。育成の成功には、受け手の主体性が欠かせません。

主体性とは? 対義語、ある人・ない人の特徴、高める方法を解説
1.主体性とは?
主体性とは、周りの意見や第3者からの指示などに頼らず、自らの判断・考えにもとづいて行動する性質のこと。ここでは下記3つから説明します。
自主性との違い
自責思考が基本
対義語は...
6.後進の育成の進め方
後進の育成を効果的に進めるには、計画的かつ段階的な取り組みが求められます。
ここでは、育成を進めるうえで押さえておくべき以下のステップを解説します。
- 現状を分析する
- 育成対象者を選定する
- 目標を設定する
- 育成者の現状を把握する
- 育成方法を決定する
- 育成計画を立てる
- 施策を実行・改善する
①現状を分析する
育成を始める前に、まずは組織の現状を正確に把握します。
人材構成や業務プロセスの分析によって、どの分野やポジションで後進育成が必要なのかを明確にできます。このステップを踏むことで、育成の方向性や対象者の選定がより的確になるでしょう。
②育成対象者を選定する
現状分析のあとは、育成対象者の選定を行います。
後継者としての適性や成長意欲のない人材を無理に育てても、期待通りの成果は得られません。
将来的に成長が見込める人物を見極め、的確に選ぶことが育成の成功に直結します。
③目標を設定する
後進の育成を効果的に進めるには、明確な目標設定が欠かせません。
何を身につけさせたいのか、どの段階で育成のゴールとするのかを明確にすることで、育成の方向性が定まります。目的に応じた具体的な目標が、実効性のある育成につながるでしょう。
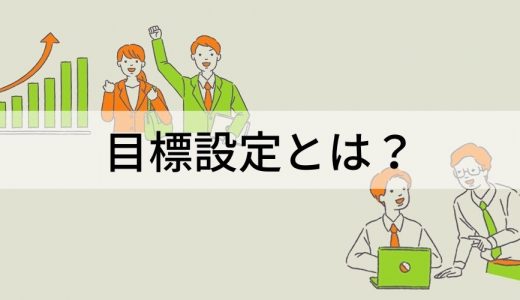
目標設定とは?【設定のコツを一覧で】重要な理由、具体例
目標設定は、経営目標達成や個人のレベルアップのために重要なもの。適切な目標設定ができないと、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやるべきことも洗い出せなくなってしまうでしょう。
今回は...
④育成対象者の現状を把握する
育成を効果的に進めるには、対象者の現状を正確に把握することが重要です。
スキルや知識、業務経験、本人の意欲や人間関係の状態までを事前に把握します。それにより、一人ひとりの特性や課題に応じた最適な育成プランが立てられます。
画一的な指導ではなく、個別的な指導が成果を高めるカギになるでしょう。
⑤育成方法を決定する
対象者の現状と目標が明確になったら、それに応じた育成方法を選定します。
育成手法には、以下のように幅広い選択肢があります。
- OJT
- OFF-JT
- メンター制度
- eラーニング
重要なのは、対象者の特性や目指すゴールに合わせて、これらの手法を適切に組み合わせることです。さまざまな手法の活用によって、実践的かつ効果的に育成できるでしょう。
⑥育成計画を立てる
育成方法が決まったら、次は具体的な育成計画を立てます。この計画には、育成目標の明確化、達成に向けた具体的なアクション、実施スケジュール、必要なリソース、評価方法などを盛り込みます。
詳細な計画の策定により、育成の進捗状況が可視化でき、目標達成に向けた管理や改善がスムーズに行えます。育成の成果は、計画の精度によって大きく左右されるため、極めて重要な工程です。
⑦施策を実行・改善する
育成計画が整ったら、それを実行に移します。計画通りに進めるだけでなく、進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて柔軟に見直しましょう。
育成対象者・育成者・管理者の三者が密に連携し、フィードバックをもとに状況に応じた対応策を講じることで、計画の精度と実効性が高まります。こうした改善の積み重ねが、効果的な育成を実現するポイントです。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード7.後進の育成のポイント
後進の育成を成功させるには、計画的な手順に加え、実践のなかで意識すべきポイントを押さえることが重要です。ここでは、効果的な育成を実現するために企業が取り組むべき具体的な工夫を紹介します。
教育体制を整備する
効果的な後進育成には、組織としての教育体制の整備が欠かせません。
指導者だけに育成を任せていると、負担が一人に集中し、不満の原因にもつながります。指導者の負担を軽減するためにも、会社全体で育成を支援する仕組みが必要です。
たとえば、業務分担を見直して指導者の負荷を軽減したり、周囲のメンバーと連携しやすい環境を整えたりすることで、育成の継続性と質を高められます。組織ぐるみで支える体制が、育成の土台となるでしょう。
指導者のスキルを向上させる
後進育成の成果を高めるには、指導者自身のスキル向上が重要です。業務知識だけでなく、ティーチングやコーチング、信頼関係を築くためのコミュニケーション能力も不可欠です。
特に、1on1ミーティングの効果的な進め方などを学ぶことで、指導の質を大きく向上できます。継続的なスキルの習得を通じて、育成の成果を最大限に引き出しましょう。
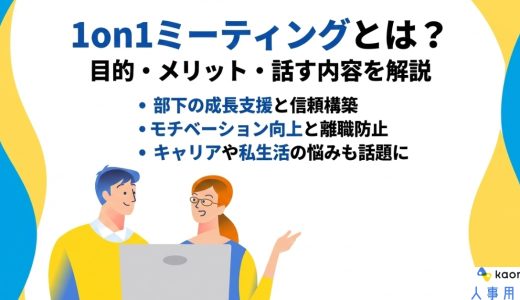
1on1とは? 目的や導入効果、面談との違いとやり方を簡単に解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入す...
離職防止のための制度を整える
育成に注力しても、育った人材が離職しては組織にとって大きな損失となります。そのため、後進の育成とあわせて離職防止のための制度整備が不可欠です。
たとえば、メンター制度を導入し、業務外の悩みも相談できる環境を整えることで、精神的なサポートを強化できます。
また、キャリアパスの明確化や適切な評価制度の整備により、組織への帰属意識を高め、長期的に働ける環境づくりが実現できるでしょう。
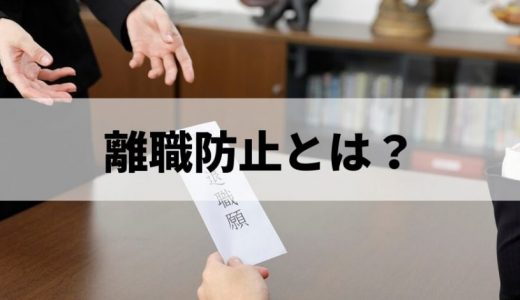
離職防止の取り組みアイデア一覧!原因と離職兆候、事例も解説
従業員の離職は企業にとって痛手であり、大きな損失です。しかし、突然の離職が発生してしまうケースも珍しくありません。従業員の離職を防ぐには、適切な方法で日々対処していくことが重要です。
今回は離職防止に...
人材育成ツールを活用する
人材育成を効率的かつ効果的に進めるには、育成ツールの活用が有効です。たとえば、eラーニングを導入すれば、受講者は時間や場所を問わず自分のペースで学習でき、継続的なスキルアップが期待できます。
また、目標管理ツールやスキル管理ツール、タレントマネジメントツールを活用すれば、育成状況の可視化や進捗管理が容易になり、指導者と従業員双方にとって学習効果の高い環境を整えられます。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード8.後進の育成に役立つ手法
後進の育成を効果的に進めるには、状況や目的に応じた適切な育成手法を取り入れることが重要です。ここでは、実践で活用しやすく、多くの企業でも導入されている代表的な育成手法を紹介します。
OJT
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)は、日常業務のなかで上司や先輩が直接指導を行う育成手法です。実務を通じて知識やスキルを習得できるため、即戦力としての能力を効率よく伸ばせるのが特徴です。
ただし、指導者のスキルや教え方によって、育成効果に差が出やすいため、指導体制の整備が欠かせません。また、体型的な知識の習得には不向きな面もあるため、ほかの手法と組み合わせるように工夫しましょう。

OJTとは? 意味や目的、メリット、進め方、OFF-JTとの違いを簡単に
OJT(On the Job Training)は、実際の業務を通じて従業員を育成する方法として、多くの企業で採用されています。
座学では学びきれない実践的なスキルを習得できるのが特徴で、新入社員や異...
メンター制度
メンター制度は、若手社員(メンティー)に対して、先輩社員(メンター)が業務面だけでなく、精神的なサポートも行う育成手法です。
メンターはキャリア形成や職場での悩み相談にも応じることで、メンティーの安心感や信頼感を高め、仕事への前向きな姿勢を引き出します。これにより、モチベーション向上や離職防止にも効果を発揮します。
制度の効果を最大化するには、メンターとメンティーの相性を考慮した適切な人選が重要です。

メンター制度とは? メリット・デメリット、成功事例を簡単に
メンター制度を運用するための、従業員情報を管理できていますか?
タレントマネジメントを行うことで、人員管理を効率化できます!
⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
...
自己啓発支援
自己啓発支援は、従業員が自ら専門知識やスキルを高める取り組みを企業が後押しする手法です。
たとえば、会社が認定する資格の受験料を全額補助したり、外部セミナーや社内外の勉強会への参加を奨励したりするなどです。これによって、学習意欲を高められます。
また、eラーニングの導入で、従業員が自分のペースで学べる環境を整える方法もあります。さまざまな学びの機会を提供することが、成長を促すカギとなるでしょう。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
9.後進育成に力を入れる企業事例
後進の育成に力を入れている企業は、独自の制度や取り組みを通じて、人材の成長を促し、組織力の向上につなげています。ここでは、実際に成果を上げている企業の事例を取り上げ、具体的な取り組み内容とその効果を紹介します。
双日株式会社
双日株式会社では、「人材こそが価値創造の原動力である」という理念のもと、長期的な視点で人材育成に取り組んでいます。
特に、専門性の向上と環境変化への対応力の強化に力を入れているのが特徴です。若手社員には、OJTや研修を通じて多様な業務経験を積ませ、広い視野と周囲を巻き込む力の育成を図っています。
同社では、35歳までを「実践世代」と定義し、成長機会を意図的に提供しています。若手社員を早期に重要なポジションへ登用したり、社外派遣や海外駐在の機会を設けたりするなど、積極的なチャレンジへの支援が魅力です。
また、全社員に対してITパスポートの取得を促すなど、デジタル人材の育成にも注力しており、変化に強い人材基盤の構築を進めています。
SCSK株式会社
SCSK株式会社は、「共創ITカンパニー」の実現に向けて、人材育成を経営戦略の中核と位置づけています。
変化に柔軟に対応できる人材を育てるため、社員一人ひとりが将来のキャリアビジョンを上司と共有し、企業の方向性と整合を図る仕組みを整備していることが特徴です。
具体的には、入社後5年間で合計1,350時間におよぶ教育プログラムを実施し、基礎力と専門性の両立を図っています。
さらに、入社4〜5年目には、初期配属とは異なる部署へ異動するローテーション制度を導入し、視野の拡大と適応力の強化を促進しています。
これらの施策に加え、応用情報技術者試験の合格とTOEIC600点以上の取得を必須とするなど、明確な成果目標を設定しています。これらは、社員の成長を着実に支援している好例といえるでしょう。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)

