従業員の離職は企業にとって痛手であり、大きな損失です。しかし、突然の離職が発生してしまうケースも珍しくありません。従業員の離職を防ぐには、適切な方法で日々対処していくことが重要です。
今回は離職防止について、企業が力を入れるべき理由や離職防止しないと発生するリスク、具体的な対策アイデアや企業の取り組み事例などを詳しくご紹介します。
目次
1.離職防止とは?
離職防止とは、従業員の離職を防ぐために施策を講じること。従業員の離職は企業にとって損失であるだけでなく、離職率の高い企業は求職者側から見てもリスクがあると判断されかねません。
従業員が離職してしまう理由は人によってさまざま。原因を突き止めたうえで多角的な取り組みが重要です。
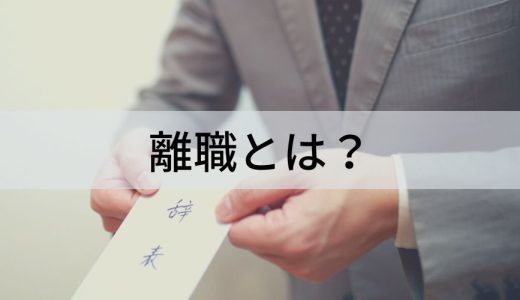
離職とは?【理由や防止策をわかりやすく】離職率、兆候
離職とは、退職や失業などによって職を離れた状態のことです。ここでは退職との違いや離職理由、離職防止に効果的な施策などについて解説します。
1.離職とは?
離職とは、退職や失業などの理由で職業から離れ...
リテンションマネジメントとは?
リテンションマネジメントとは、従業員の離職を防いで人材を定着させるためのマネジメントで人事管理手法のひとつです。リテンションは「維持」「引き留め」といった意味を持ちます。
人材不足が深刻な課題となるなか、いかに今いる人材を定着させるかが重要となっています。優秀な人材や既存の人材を確保し続けるには、労働環境や人事制度を整備して従業員を適切に管理し、離職を防ぐことが重要なのです。

リテンションマネジメントとは? やり方やメリット、事例を解説
リテンションマネジメントとは、長期的に人材を定着させるための管理および施策を指します。リテンションマネジメントのメリット、やり方、事例などを解説します。
1.リテンションマネジメントとは?
リテンシ...
2.離職防止対策のアイデア一覧
離職防止対策はただ実施するのではなく、自社に多い離職理由や課題に合わせて取り組むことがポイントです。そのためにも、実際の離職理由や離職兆候のある従業員からのヒアリング、パルスサーベイなどをとおして自社の状況を可視化しましょう。
下記アイデアを参考に、自社の課題にあわせて離職防止に有効な施策を実施してみてください。
- コミュニケーション促進のアイデア一覧
- 労働条件・環境整備のアイデア一覧
- モチベーションアップのアイデア一覧
①コミュニケーション促進のアイデア一覧
良好な人間関係の構築や風通しのよい職場づくりには、コミュニケーションの活性化が欠かせません。下記は、コミュニケーション促進のアイデア一覧です。
- 1on1ミーティングの実施
- メンター制度の導入
- コミュニケーションツールの導入
- 社内イベントの開催
- ランチミーティングの導入
- 飲み会や食事への手当
- オープンスペースの設置
- 社内ブログ・社内報・SNSの活用
- サンクスカードの導入
上司と部下の信頼関係構築や社内のコミュニケーションの円滑化、コミュニケーションが起こりやすい環境づくりなど、実施できる施策はさまざまです。

1on1ミーティングとは? 目的や効果、やり方、話すことを簡単に
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入する...
②労働条件・環境整備のアイデア一覧
給与や労働環境、待遇や評価に関する離職防止対策のアイデアです。
- 多様な働き方の導入(リモートワークやフレックスタイムなど)
- 福利厚生の充実
- ノー残業デーの導入
- 子育て、介護支援制度の充実
- 評価制度の見直し
- インセンティブ制度の導入
- 業績に応じた報酬プログラムの導入
- ストレスチェックの導入
- パルスサーベイの実施
- 労働環境の見直し(設備や気温など)
- 労働時間管理
個の事情にとらわれない働き方ができる制度や環境、頑張りに応じて適切に評価・給与に反映される制度などの仕組みづくりがポイントです。まずどれくらいの従業員がどういった点に不満を抱えているのかを洗い出してから、制度化・仕組み化しましょう。
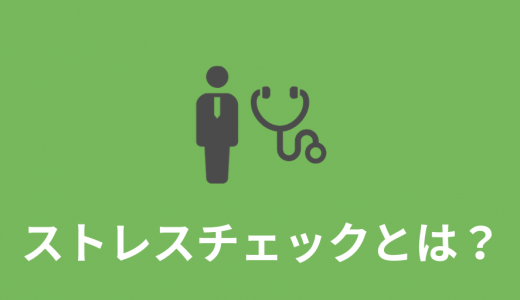
ストレスチェックとは?【実施方法を簡単に】義務化、目的
ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正によって50人以上の労働者がいる事業場で義務付けられた検査です。
定期的に労働者のストレスをチェックすることで、労働者が心身の状態に気付き、メンタルヘルスの不調...
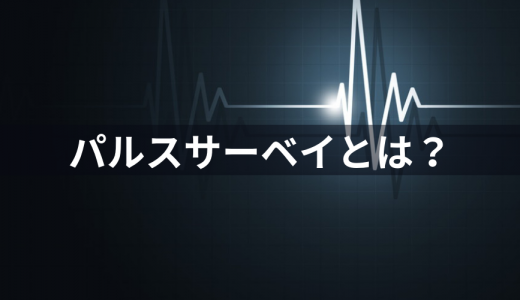
パルスサーベイとは? 意味や目的、導入メリット、質問項目例
パルスサーベイとは、従業員の離職防止や満足度向上を目的に短いスパンで行う意識調査のこと。従業員の離職や満足度に課題を抱えている場合、解決の糸口としてパルスサーベイの実施を検討している企業も多いでしょう...
③モチベーションアップのアイデア一覧
仕事への意欲やエンゲージメント向上に関する離職防止対策のアイデアです。
- 適材適所な人材配置
- 社内公募制の導入
- 資格取得支援制度の導入
- 外部セミナー等の参加費補助
- キャリア相談室の設置
- キャリアパスの明確化
- 役職ごとに応じた研修の実施
従業員が自らチャレンジできる環境や自分の能力を発揮できる環境は、意欲やモチベーションの向上に欠かせません。また自社で長く働いてもらうためにも、キャリアパスの明確化やキャリアに応じてステップアップできる環境も整備しましょう。
3.離職防止に企業が力を入れるべき理由
企業は、以下のような理由から離職防止に力を入れるべきといえます。
- 人材確保が難しい状況にあるため
- 教育・採用コストの損失が大きいため
- 人材の流出が加速しつつあるため
①人材確保が難しい状況にあるため
少子高齢化の日本では労働人口が減少し、人材確保が難しい状況にあります。
2020年の労働力調査によると、労働力人口は前年比で5万人減少。くわえて総務省発行の『令和4年版情報通信白書』によると、生産年齢人口は2050年には5,275万人に減少すると推定されているのです。
この数値は2021年から29.2%の減少となり今後増加の見込みはほぼなく、人材確保の難易度は引き続き上昇していくと予想されます。そのため、確保済みの人材をいかに定着させるかが重視されているのです。
参考 令和4年版情報通信白書総務省②教育・採用コストの損失が大きいため
リクルート就職みらい研究所が発行した『就職白書2020』によると、19年度新卒採用にかかった1人あたりの採用コストは93.6万円、中途は103.3万円です。
くわえて研修や資格取得支援など、戦力化のための教育コストもかかっています。採用や教育にこれだけのコストがかかっても、早期離職や戦力化した頃の離職も珍しくないのが現状です。
離職が発生すると新しい人材の確保が必要となり、再び採用や教育へのコストが発生します。ひんぱんに離職が起こってはコストも回収できず、企業の持続的な成長が困難な状況に陥ってしまうでしょう。
参考 就職白書2020就職みらい研究所③人材の流出が加速しつつあるため
現代、終身雇用制度が実質崩壊し、キャリア形成のために転職が一般化しています。つまり人材が流出しやすい環境といえるのです。
優秀な人材ほど見切りをつけるのが早く、雇用口も多いため転職しやすいといえます。自社の優秀な従業員の離職を防ぐためにも、離職防止が欠かせません。
4.離職防止しないと発生するリスク
離職防止をしないと、次のようなリスクが発生します。各リスクについて詳しく解説しましょう。
- 既存従業員の負担増加
- 優秀な人材の流出
- 企業イメージの低下
①既存従業員の負担増加
離職者が出るとその穴を埋めるため、離職者と同じ部署やチームの従業員の業務負担が増加します。その結果、一人あたりの業務負担が増えるため生産性や品質が低下する可能性もあるのです。
定期的な離職発生により慢性的な人手不足状況にあるため、既存の従業員が不満から離職を選択する恐れもあります。こうした離職・人手不足の悪循環が発生すると、一向に人手不足の状況は改善されません。
さらに離職者が増えると連鎖的に従業員のモチベーションも低下しやすくなる点も大きなリスクです。
②優秀な人材の流出
近年、人的資本が重視されているように、企業に新たな価値やイノベーションをもたらす「ヒト」の重要度が高まっています。優秀な人材は企業に革新的なイノベーションをもたらし、発展へ導くことに期待できる存在です。
逆をいえば、優秀な人材の流出は企業力の低下・成長の鈍化を招いてしまいます。
またノウハウや経験を身につけた優秀な人材が、競合に転職してしまう可能性もあるでしょう。その結果、競合の企業力向上に貢献してしまうだけでなく、優秀人材の育成・採用にさらなるコストがかかってしまいます。
③企業イメージの低下
離職率の高さは、企業イメージの低下を招いてしまいます。求職者にとって離職率は重要なポイントであり離職率が高い企業は何らかのリスクがあると判断されてしまうのです。結果、優秀な人材どころか、そもそも応募が来ない事態になりかねません。
5.従業員が離職する理由
離職理由は、従業員によってさまざまです。なかには、離職時に本当の理由を言わないケースもあるため、原因を突き止めるのが難しいケースも珍しくありません。しかし、適切な離職防止を行うには理由を知ることが欠かせません。
厚生労働省『令和3年雇用動向調査結果の概況』によると、離職理由のトップ3は次のとおりです。
- 労働時間、休日等労働条件が悪かった
- 職場の人間関係が好ましくなかった
- 給与等収入が少なかった
ここでは、よくある離職の理由をみていきます。
- 労働条件・給与・待遇への不満
- 人間関係へのストレス
- 会社の将来に対する不安
- 能力や個性を生かせない
①労働条件・給与・待遇への不満
- 長時間労働が改善されない
- サービス残業が多い
- 給与が少ない、上がらない
労働条件や給与、待遇に不満を感じていると、モチベーションが低下し、離職を考える大きなきっかけとなってしまいます。きちんと評価されたうえで給与や待遇に反映されているか、ワークライフバランスを確保できる労働条件・環境であるか、が重要です。
②人間関係へのストレス
- パワハラなどのハラスメントが横行している
- 上司との関係性がよくない
- 職場の雰囲気が悪い
- 悩みを相談できる相手がいない仕事や労働条件に不満がなくとも、人間関係にストレスがあると離職のリスクも高まるもの。人間関係の不満を早期発見し、配置転換などで対処するといった企業側が対応する姿勢も重要です。
③会社の将来に対する不安
- 業績が不安定
- 年収アップが望めない
- 仕事にやりがいを感じられない
- 業務内容が自分の成長につながらない
会社に居続けることに不安を感じて離職を選ぶ人も珍しくありません。業績が安定していても、従業員が会社に不安を抱える場合もあるため要注意です。
④能力や個性を生かせない
- スキルが生かせない
- 当たり障りのない業務しか任されない
- 希望の部署に配属されない
能力や個性が生かせないため評価にも反映されず、やりがいやモチベーションの低下から離職につながる場合もあります。そうした事態を回避するためにも、従業員の能力や個性を把握して、適材適所な配置にしていきましょう。
6.離職兆候がある従業員の特徴
離職兆候がある従業員の特徴を押さえ、該当する特徴が見られたら早期に対策しましょう。下記は、離職兆候がある従業員の特徴です。
- 遅刻や欠勤が増える
- 仕事への意欲が低下している
- コミュニケーションが減る
①遅刻や欠勤が増える
健康上の問題や家庭の事情が理由になる場合もあるものの、遅刻や欠勤の増加は離職兆候のひとつとしてとらえられます。離職の兆候となるケースでは、従業員が仕事へのモチベーションが低下し、やる気を失っている状態です。
また遅刻や欠勤がなくとも「仕事を早く切り上げるようになる」「新しいプロジェクトやチームへの参加を避けるようになっている」場合も要注意です。
②仕事への意欲が低下している
「ミスが増える」「反省しない」「業務効率が下がる」などの場合、意欲が低下し、仕事への関心が薄れている状態です。「注意力が低下している」「責任を感じなくなっている従業員がいる」場合は注意しましょう。
③コミュニケーションが減る
「挨拶をしない」「雑談が減る」「単独行動が増えている」場合も注意が必要です。ただし明らかに元気がないといった見違えるほどの異変は、心身の健康に問題がある可能性もあります。その場合は、早期に対応しましょう。
7.離職防止ツールとは
離職の兆候をキャッチし、離職防止の早期対処に活用できるもの。ツールによって異なるものの、具体的な機能は下記のようにさまざまです。
- 満足度やモチベーションの可視化
- パルスサーベイ、アンケート
- コミュニケーション活性化の仕組み
- 離職理由や離職兆候の分析
離職防止ツールでは従業員の状況をリアルタイムでチェックでき、必要なフォローができます。たとえば、離職兆候のある従業員をピックアップし、面談をとおしてフォローできるのです。
さまざまなデータを用いて多角的に分析できる機能を備えているため、効果的な離職防止対策に有効といえます。
従業員情報を一元化・見える化するタレントマネジメントシステム「カオナビ」なら、従業員のびっくり退職を防ぐモチベーション・離職分析機能を備えています。定期的なサーベイや分析で離職兆候をキャッチし、早期ケアにも活用可能。
従業員のコンディションを定点観測できるだけでなく、残業時間といったさまざまな要素と掛け合わせたマトリクス分析ができ、多角的に離職兆候・原因を分析して適切な離職防止対策を検討できます。

タレントマネジメントシステムとは? 機能や比較のコツを簡単に
タレントマネジメントに必要な機能が揃っています。
カオナビなら、人的資本の情報開示やリスキリングの効率化にも対応!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料...
8.離職防止の取り組み事例
ここでは、離職防止の取り組み事例を3社からご紹介します。
サイボウズ
100人100とおりの働き方を実現し、働きやすい会社として多くのメディアで取り上げられるサイボウズ。同社では、下記のような取り組みによって離職率28%から4%まで引き下げました。
- 働き方改革:6年間の育休制度を策定
- 人生のイベントにあわせて働き方をいつでも変更できる選択型人事制度の導入
- 上司に申し出ることで突発的なテレワークが可能な「ウルトラワーク制度」の導入
- 社内部活動によるコミュニケーションの活性化
メンバーそれぞれが働き方を柔軟に定義できるような環境で離職防止だけでなく、生産性アップにも効果がみられました。
ジオコード
ジオコードでは、離職防止の一環として、サッカー休暇制度やエンドレスサマー制度などユニークな福利厚生制度を導入。1年に数回、福利厚生の改善や導入を実施しています。
また福利厚生の内容は社員からアイデアの募集を行い、そのまま採用されることもあるそうです。こうした取り組みは従業員の満足度も高く、モチベーションアップを実現。
離職率は年々低下し、社内のコミュニケーションも活性化するといったさまざまな効果がみられているのです。
ビースタイル
ビースタイルでは、下記のような取り組みを行った結果、離職率が20%から8%にまで改善しました。
- ビジョンの見直し
- 会社の気持ちを表明するバリューズアワード
- 幹部に率直な意見を伝える全社日報
- 1on1によるマネージャークラスとのランダムな面談
- 社内運動会
- 選択時短勤務制度
- 新規事業プランコンテスト
従業員のモチベーションや働きやすさ、企業と従業員のつながりに着目し、組織文化の浸透や意欲向上、ワークライフバランスに配慮した施策に取り組みました。
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

