近年、ビジネス環境の変化が加速する中で、実践的な学びの手法として「越境学習」への関心が高まっています。これは、組織の枠を越え、他業界や他分野での実践を通じて学びを深める取り組みです。
その結果、視野の拡大やイノベーションの創出、キャリア自律の推進など、さまざまなメリットが期待できます。
この記事では、越境学習の概要やその重要性、導入のメリット・デメリットまで幅広く解説します。具体的な手法や導入後に成果を上げている企業事例まで紹介するので、自社での導入を検討している方は参考にしてみてください。
1.越境学習とは?
越境学習とは、従業員が自らの所属する組織や部署の枠を越えて、新たな環境で知識と経験を積む学習方法を指します。具体的には、他企業への出向や海外留学、ボランティア活動などです。
こうした普段とは異なる環境に身を置くことで、業務に直結するスキルだけでなく、柔軟なコミュニケーション力や異なる価値観を理解する力も身につきます。
また、社外の視点に触れることで、従来の業務を客観的に見直せるのも魅力です。新たな気づきや行動の変化、自己成長への意欲を高めることにもつながります。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.越境学習が注目される理由
越境学習は現代のビジネス環境において、多くの企業が直面する課題を解決する手段として注目されています。ここでは、その理由を詳しく説明しましょう。
ビジネス環境の急激な変化への対応
越境学習が注目されている背景には、ビジネス環境の急激な変化と、将来を見通すことが難しい「VUCA」と呼ばれる状況があります。VUCAとは、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字を取った言葉で、現代社会の特徴を表しています。
| VUCA |
| 変動性(Volatility) |
| 不確実性(Uncertainty) |
| 複雑性(Complexity) |
| 曖昧性(Ambiguity) |
このように変化の激しく先が読めない時代では、従来のような安定したャリアパスを描くことが難しい状況です。
そのため、企業は社員に対して新しい環境で学ぶ機会を与え、柔軟な発想や広い視野を持つ人材を育てることが求められています。
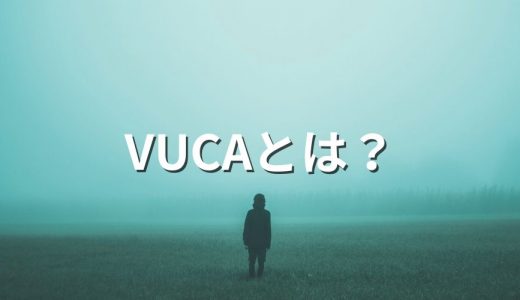
VUCA(ブーカ)とは? 意味や時代を生き抜くためのポイントを解説
VUCAとは、急速に変化して予測困難な環境を意味するワードで、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」...
イノベーションを促進する人材の育成
企業が持続的に成長するためには、革新的なアイデアや新しい価値の創出が不可欠です。しかし、同じ組織内での経験や視点だけでは、新しい発想を生み出すことは難しいでしょう。
越境学習を通じて、従業員が異業種や異文化の環境で経験を積むことで、多角的な視点と柔軟な思考を養えます。これにより、組織内でのイノベーションが促され、新しいビジネスチャンスの創出につながっていくのです。

イノベーションとは? 意味や使い方、具体例をわかりやすく
イノベーションは、企業が成長を続ける上で欠かせないものです。革新を起こすようなアイデアや技術、手法について常に思考を巡らせていなければ、新たな製品やサービスは生まれず、市場がマンネリ化してしまい、企業...
キャリア自律の重要性の高まり
平均寿命の延びにより、「人生100年時代」と呼ばれる現代では、個々のキャリアが長期化しています。その中で、組織に依存せず、自らのキャリアを主体的に設計・構築する「キャリア自律」の重要性が高まってきました。
越境学習は、従業員が自分のキャリアを見つめ直し、新たな挑戦に踏み出す機会になります。これにより、自己成長を実感し、組織内外での価値を高められるでしょう。

キャリア自律とは? 企業が支援するメリットや方法、事例を解説
キャリア自律とは、従業員一人ひとりが主体的にキャリアを考え、自律的にキャリア開発を行うことです。社会構造の変化や多様な価値観などが普及したことで、企業ではキャリア自律を促し、支援することが求められつつ...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
3.越境学習のメリット
実際に越境学習を取り入れると、どのような成果が期待できるのでしょうか。ここでは、従業員側と企業側の視点で具体的なメリットを紹介します。
従業員側の4つのメリット
まずは、従業員側のメリットを4つの観点からわかりやすくご紹介します。
- 転職せずに新たな視点やスキルを得られる
- 人脈やネットワークが広がる
- 自己理解を深められる
- キャリアの選択肢を広げられる
①転職せずに新たな視点やスキルを得られる
越境学習の大きな魅力は、現職を維持したまま他の業界や職種の経験ができることです。たとえば、他社への出向や異業種との交流などを通じて、普段の業務では得られない知識やスキルを身につけられます。
転職のような大きなリスクや負担を抱えることなく、新しい仕事にチャレンジしたり、自分を成長させたりできる点が魅力です。
②人脈やネットワークが広がる
別の会社や業界での経験を通じて、普段出会えないさまざまな人と関わるチャンスが生まれます。これにより、社外での人脈を築き、ビジネスネットワークを拡大できるでしょう。
新たな人脈は、将来的なビジネスチャンスの創出や情報収集の面で大きなメリットとなります。また、多様なバックグラウンドを持つ人々との交流は、異なる価値観や考え方を理解する力を養ってくれるはずです。
③自己理解を深められる
慣れ親しんだ環境を離れ、新しいフィールドで活動することで、従業員は自身の強みや課題を再認識する機会を得ます。
未知の状況に直面することで、自分の価値観やスキルセットを見つめ直し、自己理解を深められるでしょう。このプロセスは、自己成長やキャリア設計において非常に重要です。
④キャリアの選択肢を広げられる
越境学習を通じて身につけた新しい経験やスキルは、従業員にとってキャリアの選択肢を広げるきっかけになります。新しい分野の仕事やこれまでとは違う役割にもチャレンジしやすくなり、将来の働き方の幅が広がるでしょう。
また、異業種や異なる職種での経験を通して、考え方が柔軟になり、変化にもスムーズに対応できる力が身につきます。さまざまな環境で活躍できる人材へと成長できるのです。
企業側のメリット
企業側が越境学習を取り入れることで期待できる効果には、次のようなものがあります。
イノベーションが促進される
従業員が越境学習を通じて外部の新しい知識や視点を持ち帰ることで、組織内に新たなアイデアや革新的な思考がもたらされます。
こうした刺激は、既存の業務プロセスの改善や新規事業の創出など、企業にとってイノベーションの推進につながる布石となるものです。多様な経験を持つ従業員が増えることで、組織全体の創造性や柔軟性も向上するでしょう。
キャリア自律を促せる
越境学習の機会を提供することで、従業員は自身のキャリアについて主体的に考えるようになります。こうした意識が芽生えると、自己成長への意欲は高まり、自律的なキャリア形成が促進されるでしょう。
また、与えられた仕事をこなすだけではなく、自分で課題を見つけて行動できる人材へと成長することが期待されます。
こうした成長が、最終的には従業員のモチベーション向上や仕事への関わり方の変化につながり、職場全体の活気と生産性の向上にも結びつくでしょう。
人材育成につながる
越境学習は、従業員に対して通常の業務では得られない経験やスキルを提供するため、効果的な人材育成手法となります。
とくに、リーダーシップや決断力、タフなメンタル、コミュニケーションスキルなど、将来のリーダーに必要な能力を養う場として有効です。
このような力を備えた人材が増えることで、組織全体の人材の質が底上げされ、競争力の強化につながります。

人材育成とは? 目的や手法、大切なこと、取り組み方、成功事例を解説
人材育成とは、企業が業績を上げて経営目的を達成するために従業員を育成する取り組みをいいます。従業員を役職や職種、入社年数などで分けてグループごとにスキル習得を促します。
従来、人材育成は人事部や人材育...
人材流出を防止できる
「今とは違う仕事や環境に挑戦したい」と感じたとき、多くの人が転職を考えるようになります。そのような場合に、会社にいながら他の企業や団体で経験を積める越境学習の機会があれば、新たな視点や成長の手応えを得られるでしょう。
このような制度を会社側が用意することで、社内でもさまざまなキャリアの可能性を実感でき、結果的に離職防止にもつながります。優秀な人材が外部へ流出するのを防ぎ、組織内で長期的なキャリア形成を促すうえでも効果的です。

人材流出とは?【原因と対策一覧】企業事例、経営リスク
人材流出とは、何らかの理由で自社の人材が外部に流出してしまうこと。終身雇用制度が実質崩壊し、新卒入社から定年まで働くことが一般的でなくなった現代では、人材流出が経営課題の1つとなっています。
今回は人...
4.越境学習のデメリット
越境学習は、従業員と企業の双方に多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットもあります。ここでは、従業員側と企業側のデメリットをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
従業員側のデメリット
従業員にとっての主なデメリットとしては、以下の点が考えられます。
業務負担が増える
副業やプロボノなどで越境学習に取り組む場合、通常の業務に加えて新しい仕事や責任を抱えることになります。勤務時間が長くなったり、仕事量が増えたりするかもしれません。
その結果、ワークライフバランスが崩れ、本業のパフォーマンスに影響が出てしまう可能性があるでしょう。
また、越境学習に参加した人の仕事を残ったメンバーがカバーすることになれば、チーム全体の負担が増し、プロジェクトの遅延を招くおそれもあります。
キャリアとのズレが生じる可能性がある
越境学習で得られる経験やスキルが、必ずしも従業員のキャリアパスと一致しないことがあります。たとえば、異業種での経験が自社内で評価されにくい場合、キャリア形成において期待した効果が得られないかもしれません。
また、越境学習中に新たな興味や関心が生まれ、現在のキャリアから方向転換を検討するケースも想定されるでしょう。その結果、キャリアに迷いが感じたり、モチベーションの低下を招いたりするリスクがあります。
企業側のデメリット
企業側には、以下のようなデメリットや注意点があります。
費用やプログラム実施の負担が増える
越境学習の導入には、プログラムの設計や運営に伴うコストが必要となります。具体的には、外部研修や留学プログラムの参加費用、従業員の出向に伴う経費などです。
さらに、これらのプログラムを効果的に実施するためには、専任の担当者やサポート体制の整備が必要となり、人的リソースの負担も増加するでしょう。コストが大きくなると、企業として継続的に取り組めなくなる場合があります。
費用対効果を感じにくい
越境学習の成果は定量化しにくく、投資に対する効果を測るのが難しいケースもあります。従業員が身につけたスキルと知識が、会社の業績や組織の成長にどれだけ役立っているのかが見えにくいのです。
さらに、効果が表れるまでに時間がかかることも多く、すぐに結果を求める企業にとっては、費用対効果を疑問視する要因となりえます。そのため、導入をためらう企業も少なくありません。
自発的に参加する従業員が少ない可能性がある
越境学習は、従業員の主体的な参加が求められますが、すべての従業員が積極的に参加するとは限りません。
とくに、現状の業務に満足している従業員や、新しい環境への適応に不安を感じる従業員にとって、越境学習は魅力的な選択肢とはならない場合があります。
また、企業側が越境学習の意義や目的を十分に伝えられていないと、従業員の理解不足や関心の低さから、参加者が集まらないケースも考えられます。
このような状況では、越境学習の効果が限定的となり、企業の期待する成果を得ることは難しいでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.越境学習の代表的な手法
ここでは、代表的な越境学習の手法を6つ紹介します。
- 他企業への出向
- ビジネススクール・社会人大学院
- 副業・兼業
- ワーケーション
- 海外留学・駐在
- プロボノ
他企業への出向
他企業への出向は、一定期間、自社の従業員を他の企業に派遣し、異なる企業文化や業務プロセスを経験させる手法です。
従業員はこれまでになかった視点やスキルを身につけられ、元の職場へ戻ったときにその経験を活かすことが期待されます。
たとえばベンチャー企業へ出向した場合、スピード感ある意思決定や柔軟な考え方を学べるかもしれません。このような経験を元の職場に還元できると、イノベーションの促進や組織の変革にもつながるでしょう。

出向とは? 左遷や派遣との違い、種類、企業の注意点を簡単に
人事戦略の一環として社員を出向させることがあります。関連会社に出向させるには辞令だけでなく、本人と取り交わす複数の契約書が必要になります。契約書には明記しておくべき項目がある等、注意するべき事項を説明...
ビジネススクール・社会人大学院
ビジネススクールや社会人向けの大学院に通うことで、経営に関する知識や専門的なスキルを体系的に学ぶ方法です。
そこでは、さまざまな職種・業界経験のある人たちと一緒に学ぶため、異なる考え方や新しい人とのつながりを得ることもできます。
たとえばMBA(経営学修士)プログラムに参加すると、リーダーシップや戦略的思考を養い、実際のビジネス課題に対する解決能力を高められるでしょう。
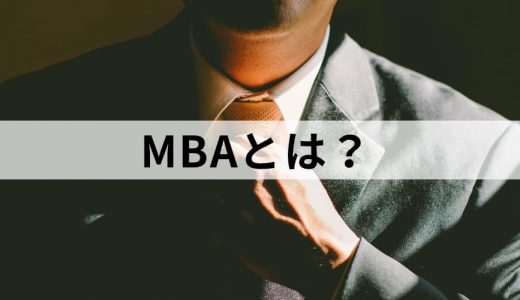
MBA/経営学修士とは?【取得したらどうなる?】タイプ
MBAは、Master of Business Administrationの略で、日本では経営学修士と呼ばれています。経営学の大学院修士課程を修了すると与えられる学位のことです。
1.MBAとは?...
副業・兼業
本業以外に他の仕事を持つ中で、異なる業界や職種の経験を積める手法です。この取り組みによって、新たなスキルの獲得や人脈の広がりが期待されます。
従業員が自主的に副業や兼業を行うことで、事業の仕組みやビジネスへの向き合い方についても理解が深まる点がメリットといえるでしょう。
さらに、副収入の増加が生活の安定や仕事への満足感につながり、結果として離職の抑制や人材の定着につながることも考えられます。
ワーケーション
ワーケーションは、「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた造語で、観光地など普段の職場とは異なる場所でリモートワークで働くことをいいます。
新しい環境に身を置くことで、リフレッシュしながら創造性や生産性を向上させる効果が期待できるでしょう。地域の人々との交流を通じて、新たな視点やアイデアを得られるかもしれません。

ワーケーションとは? 普及に影響するデメリットとは?
ワーケーションとは「ワーク」と「バケーション」を組み合わせたニューノーマルな働き方のことです。ここではワーケーションのメリットやデメリット、導入企業の例について解説します。
1.ワーケーションとは?...
海外留学・駐在
海外留学や駐在も、代表的な越境学習の方法のひとつです。海外の大学や企業で学ぶ、または働くことで、異文化理解や語学力を向上させられます。
加えて、グローバルな視点を養えるため、国際的なビジネス展開や多文化共生の場面での対応力が高まる点も魅力です。
海外の支社に駐在した場合、その地域の市場特性やビジネス慣習の深い理解につながり、自社のグローバル戦略に貢献できます。
プロボノ
プロボノは、専門的なスキルと知識を活かして、NPOや地方自治体などの非営利組織に対して無償で支援を行う活動です。この活動を通して、社会貢献をしながら自身のスキルアップや新たな経験を積むことができます。
企業が従業員のプロボノ活動を後押しすることは、社会貢献への取り組みを強化するうえでも有効であり、CSR(企業の社会的責任)の実現にも寄与します。
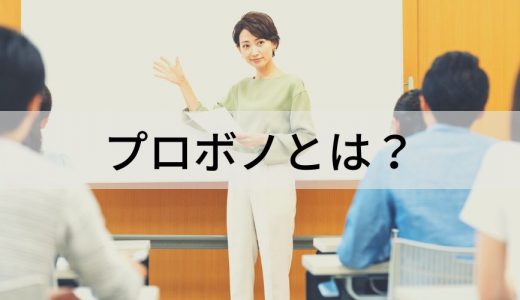
プロボノとは?【簡単に】活動例、ボランティアとの違い
プロボノとは、自身が持っている専門的な知識やスキルを無償で提供する活動のことです。プロボノの意味やメリット・デメリット、活動事例や参加の仕方について解説します。
1.プロボノとは?
プロボノとは、仕...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.越境学習導入の注意点
越境学習を効果的に導入するためには、以下のポイントに注意が必要です。
目的と目標を明確にする
越境学習を取り入れる際には、企業として「何のために行うのか」「どのような力を身につけさせたいのか」といった目的と目標を明確に設定する必要があります。
目的が曖昧なまま実施すると、参加者にとっても「なぜやるのか」がわからず、十分な効果が得られないかもしれません。
たとえば「若手社員の視野拡大」や「次世代リーダーの育成」といったように、組織の課題や人材像に応じてゴールを明確にすることで、プログラム設計や評価指標も定まりやすくなります。
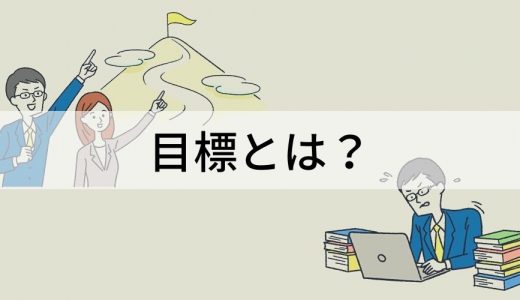
目標とは? 意味、目的やゴールとの違い、設定のコツを簡単に
面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決
クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
中長期的な視点で取り組む
越境学習は短期間で劇的な変化を生むものではありません。多くの場合、現場での経験が自身の行動や思考に反映されるには時間がかかります。
そのため、一度きりの学習機会として終わらせるのではなく、継続的な取り組みとして捉えることが大切です。
実施後のフォローアップや社内での振り返りの場を設け、得た学びを日常業務に活かすサイクルをつくりましょう。企業としても「育成」の観点から中長期で成果を見守る姿勢が求められます。
志望理由を見極める
越境学習の効果を高めるには、参加する本人の動機が非常に重要です。「他社で働けるなら楽しそう」「今の業務から逃れたい」といった志望理由では、学びへの姿勢が受け身になり、本質的な成長につながらないおそれがあります。
企業側は、面談やエントリーシートなどを通じて、なぜ越境学習に挑戦したいのか、将来的にどう活かしたいのかといった本人の考えを丁寧に確認し、主体的に学べる人材を選出することが大切です。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード7.越境学習の効果の高め方
越境学習を最大限に活用するために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 自発性を尊重する
- 振り返りと業務への活用を行う
- 組織内で成果共有をする
自発性を尊重する
越境学習の成果を高めるためには、従業員の自発的な参加が不可欠です。企業が一方的に参加を強制すると、従業員のモチベーションが下がり、十分な学びにつながらないかもしれません。
一方で、自分の仕事や将来に課題を感じている人は、越境学習の価値を理解し、自ら進んで取り組むことが多いです。企業は従業員が「やってみたい」と思えるような制度や環境を整えることがポイントになります。
振り返りと業務への活用を行う
越境学習は、参加しただけで満足してしまうと、せっかくの学びが業務に活かされない懸念があります。学習を終えた後に、自分が何を感じ、何を得たのかを振り返り、それを仕事にどう活かすかを考えることが大切です。
企業側も、従業員が経験をしっかり整理し、実務につなげられるように、振り返りの時間やサポートの場を積極的に用意しましょう。
組織内で成果共有をする
越境学習の成果を会社全体で活かすには、参加者が得た知見やスキルを社内で共有することが大切です。
報告会やワークショップなどを開いて、学んだ内容を他の従業員にも伝えましょう。組織全体のスキルアップや新しいアイデアの創出につながります。
さらに、こうした共有の機会をつくることで、越境学習に対する理解や興味が社内に広がり、次に挑戦したいと思う人も増えていくでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード8.越境学習の企業事例
さいごに、越境学習を取り入れている企業の具体的な取り組みをご紹介します。
花王グループカスタマーマーケティング株式会社
花王グループカスタマーマーケティング株式会社では、VUCA時代に対応する変革型リーダーの育成を目的として、2020年より越境学習を導入しました。
同社は、リーダー候補者向けの研修プログラムを一新し、社外の異なる環境での経験で得た主体的な気づきを重視しています。
従来の「正解を教える研修」から脱却し、異業種の人々と協力して課題解決する実践的な研修プログラムを実施。
年齢や性別、役職、業種など多様な背景を持つ社外のメンバーと共に、本業とは直接関係のない社会課題や、他社・他団体が抱える課題に挑みました。これにより、柔軟な発想力や新たな視点を養うのが目的です。
この取り組みを通して自ら気づきを得ることで、思考の幅が広がり、自分の価値観や考え方を見つめ直すきっかけにつながっています。
また、「自分はどうありたいのか」や「会社で何を果たすべきか」といった点を、改めて真剣に考えるようになる人も増えているようです。
参照:経済産業省「越境学習によるVUCA時代の企業人材育成」
NECマネジメントパートナー株式会社
NECマネジメントパートナー株式会社では、社会課題の現場での体験を通じてイノベーション人材を育成する「社会課題体感型人材開発プログラム」を導入しました。
このプログラムには、従業員が新興国のソーシャル・エンタープライズやNPOに数か月間参加し、現地の社会課題解決に取り組む「留職プログラム」などがあります。
越境型プログラムで得た経験を言語化して整理できるよう、十分な内省と振り返りの時間を設けているのも特徴です。自身の学びや気づきを明確にすると同時に、それを周囲へ共有することを重視。
また、上司にもプログラムに関与してもらい、参加者の変化を見逃さずに受け止め、認める姿勢を持ってもらうことも推進しています。これは、学んだことを職場で活かしやすくする工夫の一つです。
その結果、インドにおいて、生活習慣病予防を目的とした健康診断サービスを新たに展開するなど、具体的な取り組みが成果として形になりました。
成果は新規事業の創出に限られません。社会課題への関心が高まったり、仕事への向き合い方が変わったりと、個人の意識や行動にさまざまな変化が生まれているようです。
自らの意思で異動を決めた人や、異動はしなくても社内で自主的な活動を始めた人など、多様なアクションが見られるように変化しています。
参照:経済産業省「越境学習によるVUCA時代の企業人材育成」
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

