コンセプチュアルスキルを見える化して効果的な人材育成を実現!
タレントマネジメントの基礎知識や、システムについて解説。
⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
具体的には、企業のビジョンや目標を明確にし、部下や同僚に適切に伝える際に求められます。全体像と個別の問題を同時に考えられるこの能力は、組織の成功に寄与します。
目次
コンセプチュアルスキルの見える化なら「カオナビ」 ⇒こちらから
1.コンセプチュアルスキル(概念化能力)とは?
コンセプチュアルスキルとは、知識や情報など複雑な事象を概念化し、抽象的な考えや物事の本質を理解するためのスキルです。概念化能力ともいわれます。コンセプチュアルスキルはより上位のマネージャーになるほど求められる能力として、アメリカ・ハーバード大学の経営学者、ロバート・カッツ氏が提唱しました。
コンセプチュアルスキルが高い人材には「ひとつの経験から多くのことを学ぶ能力に長けている」「業務を合理的に遂行し、効率的に働くことができる」といった特徴があります。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
●1on1の進め方がわかる
●部下と何を話せばいいのかわかる
●質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【コンセプチュアルスキルの高い人材を発掘しやすく!】
アンケート結果や評価データを蓄積して、社員一人ひとりのスキルを可視化。
現場に眠るスキルも発掘でき、戦略的育成プランが立案できる「カオナビ」
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
2.コンセプチュアルスキル(概念化能力)とカッツモデル
概念化能力ともいわれるコンセプチュアルスキルは、経営学者ロバート・カッツ氏が提唱したカッツモデルを軸にしています。カッツモデルやコンセプチュアルスキルを構成する能力、コンセプチュアルスキルを高める利点などを見ていきましょう。
ビジネススキルを体系化したカッツモデル
カッツモデルは管理職に求められるビジネススキルを体系化したもの、マネジメント層を3つの階層に分類しています。
- ローワー(下級)マネジメント
- ミドル(中級)マネジメント
- トップ(上級)マネジメント
また、マネジメント層に求められるスキルバランスを以下のように表しています。
- テクニカルスキル:マネジメント層に求められるスキルで、業務を適切に遂行するため必要な知識や技術、熟練度が含まれる。
- ヒューマンスキル:人間関係を円滑にして力を最大化するための対人関係能力
- コンセプチュアルスキル:複雑な事象を概念化して本質を把握する能力

カッツモデルとは? 3つのスキルや人材育成への活用方法を解説
カッツモデルとは、ビジネスパーソンに必要とされる能力を階層別やスキル別に分類したフレームワークのことです。メリット、構成、活用方法などを解説します。
1.カッツモデルとは?
カッツモデルとは、階層別...

テクニカルスキル(業務遂行能力)とは?【簡単に】具体例
テクニカルスキルとは、与えられた業務を適切に遂行するために欠かせない知識や技術、能力のことです。ビジネスパーソンに欠かせないとされるテクニカルスキルについて、見ていきましょう。
1.テクニカルスキル...

ヒューマンスキル(対人関係能力)とは? 種類一覧と高め方
人材のスキル管理にお悩みではありませんか?
スキル情報を蓄積・可視化でき、従業員の強みを伸ばすことができます
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウン...
コンセプチュアルスキルを構成する能力の種類
コンセプチュアルスキルを簡単な言葉で言い換えると、「考える力」「形のないものを扱う力」と表現できます。
コンセプチュアルスキルに長けた人材には「ひとつの経験から多くを学び、対応する能力に長けている」「業務を合理的に遂行し、効率的に働くことができる」といった特徴があるため、「本質を見抜く能力」ともいわれるのです。
コンセプチュアルスキルは先天的な要素、いわゆる「地頭の良さ」を含むと考えられていますが、構成する能力には「ロジカルシンキング(論理的思考)」や「ラテラルシンキング(水平思考)」「多面的視野」「詩的好奇心」などさまざまな要素があります。
コンセプチュアルスキルを高めるメリット
コンセプチュアルスキルを高めるメリットには、経済のグローバル化に対応しやすくなるといった点が挙げられます。
近年、進展するグローバル化は、企業の人事制度から働き方まで幅広く影響を及ぼしています。また、係長や課長クラスに対し、企画や戦略の立案とともに実現するための「調整能力」を求める場面が増えました。
つまり、カッツモデルが提唱された頃に比べてローワーマネジメント層に求められるコンセプチュアルスキルが格段に高まっているのです。組織全体の底上げを図り、生産性を向上させる、これがコンセプチュアルスキルを高める目的といえるでしょう。

人材データベースから素質を見極め、コンセプチュアルスキルの育成に活用!
「カオナビ」なら社員一人ひとりが保有するスキルを管理できます。
⇒カオナビのPDF資料を無料ダウンロードする
3.コンセプチュアルスキル(概念化能力)の要素と具体例
コンセプチュアルスキルを構成する要素について例とともに見ていきましょう。
コンセプチュアルスキルは、先天的な要素(地頭の良さ)が強い点に注意が必要です。トレーニングで後天的に伸ばすことも可能ですが、短期的に伸ばすのは難しい点を念頭に置いておきましょう。
- 論理的思考を意味する「ロジカルシンキング」
- 水平思考を意味する「ラテラルシンキング」
- 批判的思考を意味する「クリティカルシンキング」
- 複数の課題に対応していく「多面的視野」
- 多様な価値観を受け入れられる「受容性」
- 臨機応変に対応できる「柔軟性」
- 新しいものを取り入れていく「知的好奇心」
- 物事に深い興味を寄せる「探究心」
- リスクを恐れない「チャレンジ精神」
- 全体像を把握する「俯瞰力」
①論理的思考を意味する「ロジカルシンキング」
ロジカルシンキングとは、物事を筋道立てて矛盾なく整理し、相手に分かりやすく説明する能力のことです。複雑な問題に直面した際も、感情や感覚に頼るのではなく、原因を分解・整理して本質的な課題を特定し、優先順位をつけて解決に導きます。
たとえば、「売上が落ちている」という漠然とした問題に対し、「どのエリアで、どの商品が、いつから落ちているのか?」と要素を分解し、「リピート率の低下が根本原因だ」と結論を導き出すような思考プロセスがロジカルシンキングです。
ビジネスではひとつの仕事に対してさまざまな要素が絡まり合っているため、問題の発生原因はひとつではなく、複数の事象が複雑に影響している場合が多いです。
ロジカルシンキング(論理的思考)ができると、これらの問題にどんな課題が含まれているかを分解、整理できます。物事を体系的に整理して筋道を立て、矛盾なく考え、一つひとつ優先度を付けて解決できる能力なのです。
ロジカルシンキングを学ぶ研修では「組織の課題を的確に認識する能力」「相手のニーズを的確に把握し応える能力」を養うトレーニングを行います。

ロジカルシンキング(論理的思考)とは? 鍛える方法を簡単に
論理的思考と訳されるロジカルシンキング。物事を体系立てて整理するための思考法として、多くの企業から注目を集めているのです。
ロジカルシンキングの意味
ロジカルシンキングのメリット
具体的手法
フレー...
②水平思考を意味する「ラテラルシンキング」
ラテラルシンキングは固定概念や既存の論理にとらわれず、物事を多角的に考察して、直感的で斬新なアイデアを生み出す能力のことです。これまで当たり前、当然とされてきた常識や固定概念を取り払い、物事を多角的に捉えます。
ロジカルシンキングが論理を垂直に深掘りしていくのに対し、ラテラルシンキングは前提を疑い、水平方向に視野を広げます。有名な例として「エレベーターが遅い」というクレームに対し、「高速化する」のではなく「待ち時間の体感を短くするために鏡を設置する」という解決策があります。
ラテラルシンキングは直感的で斬新な発想を生み出すため、日々変わり続けるビジネスシーンや新規事業の立ち上げなどに活躍するのです。
ラテラルシンキングを活用するには「前提を疑う」「物事を別のものに見立てる、抽象化する」「事象のすべてを新しい発想の糸口に使う」といったコツが欠かせません。
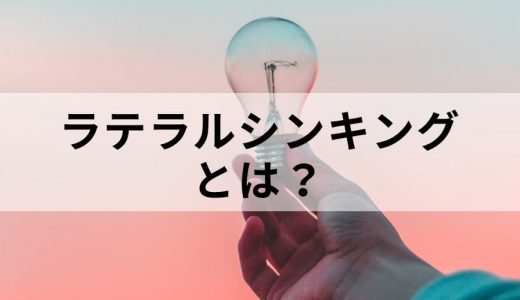
ラテラルシンキング(水平思考)とは?【鍛え方】例題
1.ラテラルシンキング(水平思考)とは?
ラテラルシンキングとは、問題を解決するために固定観念や既存の論理にとらわれず、「物事を多角的に考察する」「新しい発想を生み出す」ための思考法のことです。日...
③批判的思考を意味する「クリティカルシンキング」
クリティカルシンキング(批判的思考)とは、物事を分析的に捉えて思考する能力のことで、現状の前提を疑い、思考の偏りを見つけることで正しい結論を導き出す思考法です。
プロジェクトから不安を取り除いたり、サービスの質を向上させたりするための発想を生み出すためには不可欠といえます。
またクリティカルシンキングには批判的な要素が含まれますが、否定的な見解を伴う思考ではありません。プロジェクトを進める際にリスクヘッジを行う上で重要な考え方で、論理構成や分析内容などを内省するといった意味合いで用いられます。
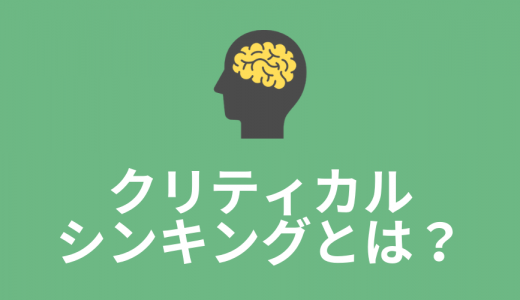
クリティカルシンキング/批判的思考とは?【鍛え方・具体例】
クリティカルシンキングを直訳すると「批判的思考」。この批判的思考をビジネスの世界でポジティブに活用すると、直訳とは違った側面が発見できるのです。
ここでは、
ビジネス界におけるクリティカルシンキング...
④複数の課題に対応していく「多面的視野」
多面的視野とは、ひとつの課題に対して複数のアプローチで検討を加えられる思考法のことで、クリティカルシンキング(批判的思考)と合わせてリスクヘッジで重要な役割を果たします。
またラテラルシンキング(水平思考)と合わせて従来にない斬新な発想を生み出す際にも有効です。
多面的視野を養うと「新しい可能性を発見できる」「行き詰まった思考を打開できる」「創造的な解決ができる」といったメリットが生まれます。多角的視野を持つと、問題に対して、複数のアプローチから検討できるようになるのです。
⑤多様な価値観を受け入れられる「受容性」
会議の場で他のメンバーと真逆の意見になるケースは珍しくありません。
しかし会議で重要なのは「相手を言い負かす」「言い伏せる」ではなく「他者と自分の意見を比較検討してより良い解答を導き出す」こと。自分とは異なる価値観を受け入れると、会議の質がより一層高まります。
グローバル化の進展に伴い、多様な価値観を受け入れられる「受容性」は非常に重要な能力です。より良い解答を導き出すためにも、自分とは異なった他人の主張を受け入れる懐の深さが必要でしょう。
⑥臨機応変に対応できる「柔軟性」
コンセプチュアルスキルには、臨機応変に対応できる「柔軟性」も含まれます。これは、予期せぬ事態や環境の変化に対し、従来のやり方や固定観念に固執せず、最適な対応を選択できる能力です。
たとえば、あるプロジェクトが計画通りに進まなくなった際、「計画にないから対応できない」と考えるのではなく、「目的を達成するためには、今あるリソースでどのような代替案が考えられるか?」と即座に思考を切り替え、新たな解決策を模索する姿勢が求められます。
この柔軟性があるからこそ、変化の激しい時代でも組織は前進し続けることができるのです。
⑦新しいものを取り入れていく「知的好奇心」
ビジネスシーンでは、常に未知のものへ興味を持ち続けることも重要です。「好奇心」は行動を起こす際のエネルギーとして非常に大きな要素で、新規事業に取り組む際などは「最初の一歩」の速さで実現できるか否かが決まる場合もあります。
未知のものに対して興味を示し、自ら取り入れられる「知的好奇心」は行動力の核として武器になる能力でしょう。さまざまな事柄に興味を持ち、問題を掘り下げるうちに新しいアイデアや根本的な原因が見えてくるかもしれません。
知的好奇心を高めるために有効な方法は、「心身にゆとりを持つ」「適度に課題を設定する」「多角的な思考を用いて物事を掘り下げる」などです。
⑧物事に深い興味を寄せる「探究心」
物事に深い興味を寄せる「探究心」もコンセプチュアルスキルを構成する重要な能力です。これは、物事の表面的な情報だけでなく、その背景にある「なぜそうなっているのか?」という根本的な理由や構造を深く掘り下げて理解しようとする姿勢を指します。
たとえば、顧客から「この機能が使いにくい」というフィードバックがあった際に、単にUIを修正するだけでなく、以下のように問い続けます。
- 「顧客は『なぜ』この機能を使おうとしたのか?」
- 「その背景にある本当の目的は何か?」
上記のように深く問い続けることで、顧客自身も気づいていない本質的なニーズを発見し、革新的な改善に繋げることができます。この探究心が、表面的な問題解決を超える洞察を生み出すのです。
⑨リスクを恐れない「チャレンジ精神」
最初から無理だと諦めることなく果敢に挑戦する気概を持つ「チャレンジ精神」も、コンセプチュアルスキルを構成する要素のひとつです。
挑戦する前から「絶対無理」「こんなこと自分にできるはずがない」「今まで成功した前例がない」とシャットアウトしてしまっては、できるものもできなくなります。
困難な課題や未経験の分野でも果敢に挑戦し、行動を起こせるチャレンジ精神は自身の成長だけでなく周囲の人に訴えかける効果もあるのです。
チャレンジ精神がなく、行動も起こさないような人に待っているのは衰退。世界で「一流」と呼ばれている人たちも、限界やリスクを恐れず常に新たな課題や目標に向かってチャレンジし続けているのです。
⑩全体像を把握する「俯瞰力」
主観的視野と客観的視野のバランスともいえる「俯瞰力」は、物事の全体像を、まるでヘリコプターから見下ろすように高く広い視点から正確に把握する能力のことです。
物事の全体像を正確に把握するために欠かせない能力で、自分が置かれている状況、また今後の見通しを冷静に見つめ、的確な判断を下すためには必要です。
たとえば、ある業務の担当者が自分の作業効率だけを考えても、隣の部署の業務に悪影響が出ていれば、全体としては非効率でしょう。俯瞰力があれば、そうした部分最適に陥らず、組織全体にとっての最適解を考えることができます。特にプロジェクトリーダーなど、多くの要素を調整する立場に必須の能力です。
俯瞰と似た言葉に「客観」がありますが、客観は自分ではない第三者の視点から物事を観察すること。対して自分も第三者も含めた全体を見る俯瞰力は、プロジェクトリーダーに求められる能力です。
俯瞰力が不足していると視野が狭くなり、正しくないことに対しても判断ミスを犯す危険があります。仕事の要領や段取りをよくするには欠かせない能力でしょう。
先天的な要素が強いコンセプチュアルスキルを効率的に伸ばすには、これらのスキル・個性を持つ人材に焦点をあてることがポイント。
効率的にスキルの可視化&スキル管理ができる「カオナビ」!
導入効果や機能一覧をわかりやすく解説。
⇒カオナビのPDF資料を無料ダウンロードする
4.コンセプチュアルスキル(概念化能力)が高い人の特徴
コンセプチュアルスキルを構成する要素は多岐にわたりますが、これらのスキルが高い人材には、日々の業務において以下のような共通した特徴が見られます。
- 特徴①:話が分かりやすく、要約がうまい
- 特徴②:常に効率的に仕事を進められる
- 特徴③:予期せぬトラブルにも冷静に対応できる
自社の人材を見極めたり、自身が目指す姿をイメージしたりする上で参考にしてみてください。
特徴①:話が分かりやすく、要約がうまい
コンセプチュアルスキルが高い人は、複雑な議題や長時間の会議内容も、要点を的確に整理し、誰にでも分かりやすく伝えることが可能です。何が本質で、何が枝葉末節かを見極める力があるため、「この問題の核心はAとBの対立です」「今日の決定事項は3点です」と簡潔に要約できます。
その場の情報を整理するだけでなく、他者の理解を促進する言語化力に優れており、「あの人に聞けば分かる」と信頼される存在になります。話が明快でロジカルなため、共通認識を早く持てることも大きな強みです。
特徴②:常に効率的に仕事を進められる
業務に取り組む際、単なる作業としてではなく、「この業務の目的は何か」「どこにインパクトがあるのか」を常に意識しています。全体像と本質を把握した上で行動するため、無駄な工程に時間をかけず、必要なタスクに的確に集中できます。
また、やり方に固執せず、より効率的なアプローチを探る柔軟性も併せ持っている点も、コンセプチュアルスキルが高い人の特徴です。目的思考と優先順位の判断に長けており、結果的にチーム全体の生産性向上にも寄与します。常に「より良く・より早く」を実現できる実行力が魅力です。
特徴③:予期せぬトラブルにも冷静に対応できる
予期せぬトラブルが起きたときも、コンセプチュアルスキルが高い人は、感情的にならず冷静に状況を判断できます。表面的な現象に振り回されることなく、問題の構造や根本原因をすばやく特定し、場当たり的ではない本質的な解決策を導き出します。
その姿勢は周囲にも安心感を与え、信頼される存在となるでしょう。
パニックを防ぎつつ、課題を機会に変える力があるため、リスクマネジメントや危機対応においても大きな価値を発揮します。「何が起きても任せられる人」として評価される理由がここにあります。
コンセプチュアルスキルを見える化して効果的な人材育成を実現!
タレントマネジメントの基礎知識や、システムの選び方について解説。
⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
5.コンセプチュアルスキル(概念化能力)の自己診断チェックリスト
まずは現在の自分のスキルレベルを確認してみましょう。
以下の10項目に、あなたが「普段の業務でできている」と思うものがあれば、チェックを入れてみてください。
▢会議や打ち合わせの内容を、要点3つ以内で説明できる
▢上司からの指示に対し、「目的」や「背景」を自分の言葉で説明できる
▢複数の課題があるとき、何から取り組むべきか優先順位を判断できる
▢自分の仕事が他部署や会社全体にどう貢献しているかを意識している
▢うまくいかないとき、すぐに別のやり方を試す柔軟性がある
▢意見が異なるときでも、まずは相手の意図を理解しようとする
▢わからない専門用語や仕組みがあれば、自分で調べて理解しようとする
▢成功や失敗の理由を「なぜ?」と分析する習慣がある
▢業界のニュースや他社の動向など、外部情報を日頃から収集している
▢「自分が経営者だったら?」という視点で物事を考えることがある
診断結果
7個以上チェックがあった方
すでに高いコンセプチュアルスキルを持っています。
この記事を活用してさらに磨きをかけ、チームや組織により大きな価値を提供していきましょう。
4〜6個チェックがあった方
土台となる素養が十分に備わっています。意識的に思考力を鍛えることで、スキルは一気にレベルアップします。
この記事で紹介するトレーニング法を、ぜひ日常に取り入れてみてください。
3個以下だった方
これからコンセプチュアルスキルを大きく伸ばせるチャンスです。
最初の一歩は「意識すること」です。本記事で紹介するトレーニングから、気になるものを1つ選んで、まずは明日から試してみましょう。
人材データベースから素質を見極め、コンセプチュアルスキルの育成に活用!
「カオナビ」なら社員一人ひとりが保有するスキルを効率的に管理できます。
⇒カオナビのPDF資料を無料ダウンロードする
6.コンセプチュアルスキル(概念化能力)を人材育成につなげるポイント
「地頭の良さ」ともいわれるコンセプチュアルスキルが高い人材は、先天的に大きなアドバンテージを持った人材ともいえます。しかしどうやって人材育成につなげればよいのでしょう。コンセプチュアルスキルを人材育成に活かすためのポイントを見ていきます。
職級に合った研修を行う
コンセプチュアルスキルは、カッツモデルが示す通り、上位のマネジメント層ほど求められる比重が大きくなります。そのため、全社員に画一的な研修を行うのではなく、職級ごとに求めるスキルレベルを定義し、それに合った研修を設計することが重要です。
| 対象 | 研修内容 |
|---|---|
| 若手社員向け | ロジカルシンキングや問題解決の基礎など、業務遂行能力に直結する思考法を学ぶ研修 |
| 管理職向け | 多面的視野や俯瞰力、戦略的思考など、部門やチームを率いるために必要な、より高度で抽象的な思考法を学ぶ研修 |
診断テストなどを活用して事前に社員のスキルレベルを「見える化」し、個々の強みや課題に合わせた育成計画を立てることが、効果的な人材育成の第一歩となります。
人材教育には理解を求めることが必要
コンセプチュアルスキルが長けている人には「本質を見抜く能力が高い」「物事を合理的に判断できる」といった特徴があります。しかし反対に言えば「合理性に欠けることに対して頑固な姿勢を示すケースがある」ということでもあるのです。
コンセプチュアルスキルが高い人の育成には「きちんと納得してもらう」「理解を求める」などが非常に重要となります。
上司と部下、管理職と一般社員などポジションをベースにした指示では理解されない場合も。あくまで「問題に対して、その意見は理にかなっているか」に注目して論議しましょう。
一般社員の意見も柔軟に取り入れる
コンセプチュアルスキルは一般的に幹部社員やマネジメント層に求められる能力ですが、「一般社員に備わっているケースもある」場合もあると覚えておきましょう。
若手社員が現場での業務を行いながら「この部分はこうしたほうがいいのでは?」「もしかしたら、これは違うのではないでしょうか?」などと提言してくることはないでしょうか。
つまり、マネジメント層でなくともコンセプチュアルスキルが高い人材は存在するのです。上司や人事担当者は部下からの意見も柔軟に取り入れる姿勢を持ちましょう。
一般社員だからといって頭ごなしに否定してはいけません。提案を真摯に受け止め柔軟に対応していくと、業務だけでなく組織そのものも活性化するでしょう。
効率的にスキルの可視化&スキル管理ができる「カオナビ」!
コンセプチュアルスキルの育成に活用できます。
⇒カオナビのPDF資料を無料ダウンロードする
7.すぐに実践できるコンセプチュアルスキルの鍛え方
コンセプチュアルスキルは、日々の意識やトレーニングで後天的に伸ばすことも可能です。ここでは、個人が業務の中で実践できる具体的な鍛え方を紹介します。
- 鍛え方①:抽象化と具体化を往復する
- 鍛え方②:「なぜ?」を5回繰り返す(なぜなぜ分析)
鍛え方①:抽象化と具体化を往復する
コンセプチュアルスキルを鍛える上で重要なのが、この「抽象」と「具体」の思考の行き来です。
| 思考法 | 意味・目的 | 具体的な方法 | 例 |
|---|---|---|---|
| 抽象化(「つまり?」) | 複数の事象から共通点や本質を見抜く | 「結局何が言いたいのか?」を言語化する習慣をつける | 成功事例を分析して、「成功の共通因子」を見つける会議の内容を一言でまとめる |
| 具体化(「たとえば?」) | 抽象的な概念を具体的な行動に落とし込む | 理念や方針に基づいて「今日できる行動は何か?」を考える | 「顧客第一」という理念 ↓ 今日の対応でそれをどう実践するか考える「生産性向上」という目標 ↓ 作業時間を10%短縮できる業務を見つける |
抽象化:「つまり、どういうことか?」と考える
複数の具体的な事象から共通点や法則性を見出し、本質を抜き出す思考です。
たとえば、複数の成功事例を分析し、「成功の共通因子は何か?」を言語化したり、会議の議論を「一言で言うと〇〇だ」と要約したりする習慣が有効です。
具体化:「たとえば、どういうことか?」と考える
抽象的な概念や方針を、具体的な行動や事例に落とし込む思考です。
たとえば、「顧客第一」という企業理念に対し、「今日、私がこの理念を体現するためにできる具体的な行動は何か?」を一つ考えたり、「生産性向上」という目標に対し、「自分の業務のどの作業を10%短縮できるか?」と自問したりしましょう。
上記を何度も考えることで、具体化のトレーニングになります 。
鍛え方②:「なぜ?」を5回繰り返す(なぜなぜ分析)
表面的な事象の背後にある、より深く、本質的な原因を突き止めるための強力な手法です。
【具体例】
| ステップ | なぜ?の問い | 内容 |
|---|---|---|
| 1回目 | なぜ報告書の提出が遅れたのか? | 作業に時間がかかった |
| 2回目 | なぜ作業に時間がかかったのか? | データ探しに手間取った |
| 3回目 | なぜデータ探しに手間取ったのか? | 保管場所がわかりづらい |
| 4回目 | なぜ保管場所がわかりづらいのか? | フォルダが整理されていない |
| 5回目 | なぜ整理されていないのか? | 運用ルールが決まっていなかった |
上記のように問いを重ね、根本原因にたどり着き、本質的な解決策を考えることができます。
【スキル管理でこんなお悩みありませんか?】
●従業員のスキルや能力が把握できていない
●スキルマップの作成や管理に時間がかかっている
●スキルと評価精度をうまく連動できない
●一人ひとりに合った配置・育成ができていない
●幹部・後継者候補の発掘がうまくいかない
こうしたスキル管理の悩みを効率的なシステムと充実サポートで解決に導きます。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」
⇒紹介資料の無料ダウンロードはこちらから
コンセプチュアルスキル(概念化能力)のQ&A
①論理的思考を意味する「ロジカルシンキング」
②水平思考を意味する「ラテラルシンキング」
③批判的思考を意味する「クリティカルシンキング」
④複数の課題に対応していく「多面的視野」
⑤多様な価値観を受け入れられる「受容性」
⑥臨機応変に対応できる「柔軟性」
⑦新しいものを取り入れていく「知的好奇心」
⑧物事に深い興味を寄せる「探究心」
⑨リスクを恐れない「チャレンジ精神」
⑩全体像を把握する「俯瞰力」
いずれも先天的な傾向の強い能力です。トレーニングで後天的に伸ばすことも可能ではあるものの、長期的に取り組む姿勢が求められます。

