モチベーション分析・離職分析にはカオナビ!
定期的なサーベイや分析で、社員エンゲージメントを高められます。
⇒PDFを無料ダウンロード
退職代行を使われた企業でも、正しい対応方法を知っていれば、トラブルを避けてスムーズに退職手続きを完了できます。
この記事では、退職代行サービスから連絡が来た際の手続きから注意点まで詳しく解説します。
また、利用されないための対策についても適切な知識と対策により、退職代行を使われるリスクを大幅に減らし、社員の定着率向上と企業イメージの向上を実現できるでしょう。
退職代行とは?

退職代行とは、従業員に代わって会社に退職の意思を伝え、退職手続きを代行する有料サービスです。
下記の理由により、自分で退職手続きを行うことが困難な労働者が増え、サービス利用者が増えています。
- 直接上司に退職を切り出しにくい職場の雰囲気
- パワハラやブラック企業による退職妨害
- 長時間労働や精神的負担による心身の疲弊
- 退職に関する法的知識の不足 など
退職代行は現代の労働問題を反映した新しいサービスですが、根本的な職場環境の改善も重要な課題として残されています。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
●1on1の進め方がわかる
●部下と何を話せばいいのかわかる
●質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見られる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
退職代行を使われたときにおこなうべき会社・人事の対応

従業員から退職代行サービスを通じて退職の申し出があった場合、会社や人事担当者は、まず落ち着いて事実関係を確認することが大切です。
具体的には、以下の対応をおこなうようにしましょう。
- 退職代行業者の身元・資格を確認する
- 従業員本人の退職の意思を確認する
- 退職への回答書を作成する
- 従業員の雇用形態を確認する
- 退職届を受け取る
- 退職日までの従業員の取り扱いを決める
- 業務の引き継ぎ依頼をする
- 貸与品を返却してもらう
- 退職届を受理する
今後の手続きが円滑に進むよう、初期対応で慎重な判断で対応していきましょう。
以下の記事では、退職手続きの流れについて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
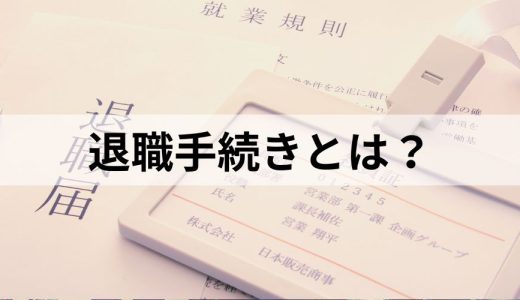
退職手続きの流れとやるべきこととは? 必要な書類も簡単に
従業員の退職に伴い、企業・従業員側ではそれぞれ手続きが発生します。退職手続きは流れに沿って順番に行う必要があり、それぞれ各種手続きに必要な書類も多いため、漏れなく対応することが重要です。
今回は企業側...
退職代行業者の身元・資格を確認する
退職代行業者から連絡を受けた際には、その業者がどのような組織であり、法的にどのような権限を持っているのかを確認する作業が重要です。
退職代行サービスを提供する業者には、以下の3つの形態が存在します。
- 民間企業
- 労働組合
- 弁護士事務所
それぞれの形態によって、会社に対して行える業務の範囲、特に退職条件に関する交渉権の有無が法律で明確に定められています。
たとえば、民間企業が運営する代行業者の場合、退職の意思を伝える「使者」としての役割は担えますが、有給休暇の取得交渉や未払い賃金の請求といった法律事務に関する交渉を行うことは「非弁行為」として弁護士法に抵触する可能性があります。
まずは、退職代行業者の基本情報と運営母体がどこであるのかを確認しましょう。
従業員本人の退職の意思を確認する
退職代行業者から退職の通知があった場合、本当に対象となる従業員ご本人の意思に基づいているのかを慎重に確認しましょう。
ごく稀に第三者によるなりすましや、従業員が不本意な形で退職手続きを進められているケースがあるためです。
本人の意思に基づかない退職処理は、後日、不当解雇などの重大な労務トラブルに発展する危険性があります。まずは、退職代行業者に対し、従業員本人が退職の意思表示や手続きを委任したことを証明する委任状の提出を求めましょう。
状況に応じて、記録が残るメールなどの手段で従業員本人に直接退職の意思を確認することも検討しましょう。直接連絡する際は高圧的な印象を与えないよう、言葉遣いに十分配慮することが求められます。
退職への回答書を作成する
従業員本人の退職意思が確認でき、退職代行業者の正当な権限も認められた場合、企業としては退職の申し出を受理する旨と今後の手続きを記載した回答書を作成し、通知しましょう。
書面での通知は、企業側の正式な意思表示として記録に残るため、後の誤解や認識の齟齬を防ぎ、退職手続きの透明性を高める上で有効です。
回答書には、下記について具体的かつわかりやすく記載します。
- 退職を承認する旨
- 確定した退職日
- 業務の引き継ぎに関する事項
- 有給休暇の残日数と取り扱い
- 貸与している物品の具体的な返却方法と期限
- 最終給与の計算方法や支払日
- 社会保険の手続き
- 離職票など退職後に交付が必要な書類について
回答書は、退職代行業者を通じて、または従業員本人に直接送付します。
従業員の雇用形態を確認する
従業員から退職代行サービスを通じて退職の申し出があった際には、まず従業員の雇用形態を正確に確認しましょう。
雇用形態によって適用される労働法規や就業規則の条項、退職に関するルールが異なるためです。
たとえば、正社員の場合、民法第六百二十七条に基づき、原則として退職の申し入れから2週間が経過することで雇用契約が終了します。
一方で、有期雇用契約の従業員の場合、第六百二十八条により「やむを得ない事由」が必要とされ、原則として契約期間満了までの勤務義務があります。ただし、この場合でも会社と従業員双方の合意があれば、契約期間中の退職は可能です。
このように、雇用形態によって法的な取り扱いが大きく変わるため、最初に雇用契約書や社内記録で確認し、それぞれのケースに応じた慎重な対応が求められます。
退職届を受け取る
退職代行サービスを通じて従業員から退職の意思が伝えられた場合であっても、企業としては、従業員本人から正式な退職届を提出してもらうことが原則です。
退職届は、以下を書面で確認するための重要な書類となります。
- 従業員自身の最終的な退職意思
- 希望する退職日
- 退職理由
口頭での意思表示や代行業者からの通知のみでは、後日になって「本意ではなかった」といった主張がなされるリスクが完全には排除できません。多くの企業では、社内規程においても退職時の退職届提出を義務付けています。
郵送でのやり取りが基本となるため、返送先の部署、住所、そして返送期限などを明確に伝えることが重要です。
退職日までの従業員の取り扱いを決める
退職代行サービスを利用した従業員の退職日が決まった後、その日までの従業員の扱いを明確に定め、本人または退職代行業者に通知することが重要です。これにより、双方の誤解を防ぎ、不要なトラブルを避けられます。
まず確認すべきは、年次有給休暇の残日数です。従業員には残っている有給休暇を消化する権利があり、企業は原則としてこれを拒否できません。
従業員が退職日までの全労働日を有給休暇の消化に充てることを希望した場合、最終出社日は実質的に退職の申し出があった日、あるいはその直後となることもあります。この場合、出社は不要であることを明確に伝えます。
また、有給休暇を一部消化し、残りの期間は出社するのか、あるいは全期間欠勤扱いとするのかなど、具体的な出社状況を確定させます。
出社しない場合でも、業務の引き継ぎや貸与品の返却など、必要な連絡が生じる場合に備えて、連絡方法と社内の担当窓口を伝えておくことが望ましいでしょう。
給与計算や社会保険の手続きにも影響するため、正確に決定し、書面で通知することが後の混乱を防ぐために有効です。
業務の引き継ぎ依頼をする
従業員が退職代行サービスを利用して退職する場合でも、企業としては、業務の停滞を防ぎ、他の従業員への負担を軽減するために、可能な範囲で業務の引き継ぎを依頼することが重要です。
ただし、退職代行を利用する従業員の多くは、会社との直接的なコミュニケーションを避けたいと考えているため、依頼方法には配慮が必要です。
まず、引き継ぎが必要な業務内容、関連資料の保管場所、進行中の案件の状況などを具体的にリストアップします。その上で、退職代行業者を通じて、従業員本人に協力を依頼します。
本人が出社を拒否している場合は、書面やデータでの情報提供、あるいは電話やオンライン会議システムを通じた短時間での説明などを提案してみましょう。
強制はできませんが、企業が直面している状況や引き継ぎの必要性を丁寧に説明し、協力をお願いする姿勢が大切です。
もし、従業員からの協力が全く得られない場合に備えて、上司や同僚へのヒアリング、残された資料の確認など、他の方法で情報を収集する準備も並行して進めておくことが賢明です。
貸与品を返却してもらう
従業員が退職する際には、会社から貸与されていた物品を全て返却してもらう必要があります。
貸与品には、以下が含まれます。
- パソコン
- スマートフォン
- 社員証
- 入館キー
- 制服
- 作業着
- 顧客名簿
- 業務マニュアル
- 健康保険被保険者証
退職代行サービスを利用している従業員に対しても、この返却義務は同様に発生します。
企業としては、まず返却してもらうべき貸与品の一覧を作成し、それを退職代行業者を通じて従業員本人に明確に伝えます。その際、各物品の具体的な返却方法と返却期限を具体的に指示することが重要です。
特にパソコンやスマートフォンなどの情報機器については、企業情報や個人情報が含まれている可能性があるため、返却前のデータ消去や取り扱いについても注意を促す必要があります。
健康保険証については、退職日の翌日以降に速やかに返却してもらうよう伝えます。返却された物品は、事前に作成したリストと照合し、すべて揃っているかを確認しましょう。
退職届を受理する
従業員本人から正式な退職届が提出され、その内容に不備がないこと、退職に関する諸条件について企業と従業員双方の合意が形成された段階で、企業は退職届を正式に受理します。
この受理行為は、従業員の退職が会社によって承認されたことを示す重要な手続きです。退職届を受理することにより、その後の社会保険の資格喪失手続きや、必要に応じて発行する離職票の準備など、次の事務処理へ円滑に移行できます。
また、退職の事実を法的に確定させ、将来的な「退職した・しない」といった無用な紛争を予防する上でも意義があります。実務としては、人事担当者が提出された退職届の内容を最終確認し、受理日を記録します。
受理した旨を従業員本人への通知は必須ではありませんが、双方の認識を合わせるために望ましい対応と言えるでしょう。受理した退職届は、労働関連法規に基づき、定められた期間、適切に保管する必要があります。
以下の記事では、退職証明書について解説していますので、書き方にお悩みの方はぜひご覧ください。

退職証明書とは? 書き方と記載事項、テンプレ、もらい方を解説
すでに会社を退職していることを証明し、また確かにその会社に在籍していたことを証明する、それが退職証明書です。また、新しい会社で社会保険に加入する際、以前所属していた会社での被保険者資格を失っていること...
モチベーション分析・離職分析にはカオナビ!
社員エンゲージメントの高め方について解説しています。
⇒PDFを無料ダウンロード
退職代行を使われたときにトラブルを避ける方法

退職代行サービスからの連絡は、多くの企業担当者様にとって予期せぬ出来事であり、対応に苦慮されることも少なくありません。
「どのように対応すれば良いのだろうか」「法的に問題はないのだろうか」といった不安を感じることは自然な反応です。
これから解説する主なポイントは以下の通りです。
- 退職代行を行う民間業者との交渉における注意点
- 従業員本人との直接的な対話の可否とその限界
- 有給休暇の申し出に対する適切な処理方法
- 退職手続きを迅速かつ正確に進めることの重要性
- 万が一トラブルが発生した場合の、弁護士への相談という選択肢
退職代行の民間業者との交渉は控える
特に、弁護士資格を持たない民間の退職代行業者が行える業務は、法律によって制限されています。
具体的には、従業員本人の退職意思を会社に伝える役割が主であり、以下のような具体的な労働条件に関する交渉は、原則としておこなえません。
- 有給休暇の取得交渉
- 未払い残業代の請求
- 退職日の調整
もし民間業者がこれらの交渉を積極的に行おうとする場合、それは弁護士法第72条で禁止されている「非弁行為」に該当する可能性があります。
弁護士法第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
企業が非弁行為を行う業者と交渉し、何らかの合意に至ったとしても、その合意自体が法的に無効と判断されるリスクがあります。
そのため、民間業者から労働条件に関する交渉を持ちかけられた際は、交渉には応じられない旨を明確に伝え、従業員本人またはその正式な代理人と協議する姿勢を示すことが肝要です。
従業員との対話は強制できない
退職代行サービスを利用するということは、多くの場合、従業員ご本人が会社と直接コミュニケーションを取ることを避けたいと考えている背景があります。
企業側が従業員本人との直接の対話を強く求めることは、望ましくありませんし、法的に強制できません。
退職代行業者から提出される委任状には、通常、従業員本人への直接連絡を控え、すべての連絡を代行業者経由で行うよう求める記載があります。
もし企業がこの意向を無視して、本人に執拗に連絡を取ろうとすれば、従業員にさらなる精神的苦痛を与えることになり、場合によっては新たなトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
業務の引き継ぎや貸与物の返却など、実務上必要なやり取りは、原則として退職代行業者を通じて行うことになります。
出社を伴わない形での引き継ぎ方法や、貸与物の郵送返却など、リモートでのコミュニケーションを前提とした手続きを検討する必要があります。
本人の真摯な退職意思の確認は重要ですが、それも代行業者への委任状や、必要に応じて代行業者を通じた書面での確認に留めるのが賢明です。
有給休暇の消化を進める
退職する従業員の方から年次有給休暇の取得申請があった場合、企業は原則としてこれを承認し、取得を促す必要があります。
年次有給休暇は労働基準法で定められた労働者の正当な権利であり、企業側が一方的に拒否することは、法違反となる可能性があります。
特に退職時には、残っている有給休暇をまとめて消化したいという申し出が多く見られます。
企業としては、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、取得時季を変更する権利(時季変更権)がありますが、退職日があらかじめ決まっている従業員に対してこの権利を行使できる場面は非常に限られています。
実質的には、退職日までに残りの有給休暇をすべて使い切れるよう、企業側が配慮し、業務の調整を行うことが求められます。
また、以下の記事では、有給休暇の消化義務について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
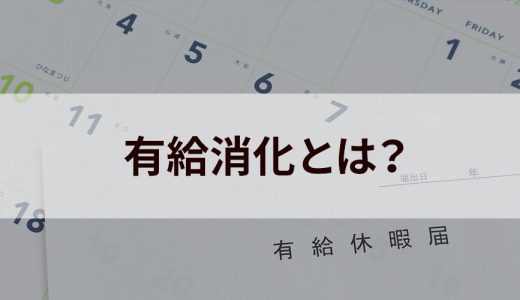
有給消化とは?【消化義務の日数・罰則】退職時の注意点
有給消化とは、従業員が保有する有給を取得すること。有給は従業員の心身のリフレッシュを目的とした制度であり、労働基準法の改正によって1年間で最低5日間の有給消化が義務化されました。
今回は有給消化につい...
速やかに退職手続きを進める
従業員ご本人からの退職の意思が明確に確認され、退職日が確定した後は、企業は関連する退職手続きを遅滞なく進めることが求められます。
手続きの遅延は、従業員の方に不利益を与えるだけではなく、企業の管理体制に対する不信感を招き、新たなトラブルを引き起こす可能性があります。
主な退職手続きには、下記の事務作業があります。
- 社会保険の資格喪失手続き
- 雇用保険の離職手続き
- 源泉徴収票の発行
- 会社からの貸与品の返却確認
法的に定められた期限がある手続きも多いため、企業は速やかな対応が必要です。
たとえば、雇用保険の離職票の発行が遅れると、従業員の方が失業給付の受給手続きを速やかに開始できないといった事態が生じます。
企業としては、退職する従業員の方がスムーズに次のステップへ進めるよう、また法的な義務を遵守するためにも、効率的かつ正確な事務処理体制を整えておくことが不可欠です。
退職代行サービスを利用された場合でも、必要な書類のやり取りは代行業者を通じておこない、迅速に手続きを完了させるよう努めましょう。
トラブルが発生したらまずは弁護士に確認する
退職代行サービスの利用をきっかけとして、万が一、元従業員の方との間で法的なトラブルが発生してしまった場合、速やかに弁護士に相談し、専門的なアドバイスを求めることが最も賢明な対応策です。
具体的なトラブルには、以下が考えられます。
- 未払い残業代の請求
- 退職金に関する見解の相違
- 在職中のハラスメントを理由とした損害賠償請求 など
労働法規や過去の判例が複雑に絡み合っていることが多く、法的な知識がないまま対応しようとすると、かえって企業の立場を不利にしてしまうおそれがあります。
弁護士に早期に相談することで、まず何が法的な問題点なのか、企業側にどのような責任や権利があるのかを正確に把握できます。
その上で、具体的な証拠に基づいて、最適な解決策について助言を受けられるでしょう。
初期対応を誤ると問題が長期化・複雑化する可能性もあるため、専門家のサポートを得て冷静かつ適切に対処することが、企業のリスクを最小限に抑える上で非常に重要です。
モチベーション分析・離職分析にはカオナビ!
社員エンゲージメント向上の施策事例を解説。
⇒PDFを無料ダウンロード
退職代行サービスを利用されないための対策

退職代行の利用は、多くの場合、企業内部に存在する何らかの課題を示唆しています。
根本原因に目を向け、従業員が安心して働き、必要であれば直接対話を通じて円満に退職を申し出られるような、建設的な職場文化を育むための戦略を紹介します。
具体的な対策は以下の通りです。
- 退職代行を使われた理由を追求する
- 従業員と良好な関係を構築する
- 労働環境を改善する
- 採用のミスマッチを減らす
- 退職希望の場合のフローを明確にしておく
- 1on1ミーティングをおこなう
それぞれ解説していきますので、参考にしてください。
退職代行を使われた理由を追求する
従業員が退職代行サービスを利用して会社を去ったという事実は、企業にとって重く受け止めるべき事態です。
背景には、単に「退職の意思を伝えたい」という表面的な理由だけではなく、より根深い問題が隠されている可能性が高いと考えられます。
再発防止の第一歩として重要なのは、なぜ従業員が直接の対話を避け、第三者を介する必要があったのか、その根本的な原因を徹底的に追求することです。
たとえば、以下が有効な手段となり得ます。
- 過去の退職者のデータ分析
- 守秘義務に配慮した上での元同僚や上司へのヒアリング
- 特定の部署で同様の不満が潜在していないかを確認するための匿名アンケート など
表面的な事象に捉われず、組織全体の問題として原因を分析し、具体的な改善策につなげていく姿勢が求められます。
原因究明を怠ると、同様のケースが繰り返され、企業にとって大きな損失となるでしょう。
従業員と良好な関係を構築する
従業員が退職代行サービスを検討する背景には、コミュニケーション不全や信頼関係の欠如が存在することが少なくありません。
このような状況を改善し、従業員が安心して自身のキャリアや悩みについて話せる環境を作るためには、日頃から意識的に良好な人間関係と信頼関係を構築していく努力が不可欠です。
具体的には、経営層や管理職が率先してオープンなコミュニケーションを心がけ、従業員一人ひとりの声に真摯に耳を傾ける姿勢を示すことが重要です。
定期的な面談の機会を設けるだけでなく、日常的な声かけや感謝の言葉を伝えることも効果的でしょう。
また、社内イベントや部署を超えた交流の場を設けることで、風通しの良い、心理的に安全だと感じられる職場全体の雰囲気を作り出すことも、従業員の孤立を防ぎ、信頼感を育む上で有効な手段と言えます。
以下の記事では、人事評価と退職の関係について解説していますので、従業員との関係構築にお悩みの方はぜひご覧ください。

人事評価の不満は退職のリスク!【離職を防ぐ方法とは?】
人事評価は社員のモチベーションを大きく左右するものです。
自分が思っていたよりも評価結果が低く理由に納得できないと、社員は不満を抱き、退職を考えるきっかけになります。
人事評価に不満を抱いている社員は...
労働環境を改善する
従業員が退職代行という手段を選ばざるを得ないほど追い詰められる状況を防ぐためには、企業が提供する労働環境そのものを見直し、継続的に改善していく取り組みが極めて重要です。
具体的には、まず長時間労働が常態化していないか、サービス残業が黙認されていないかなど、労働時間管理の適正化が求められます。
勤怠管理システムを適切に運用し、従業員の労働時間を正確に把握し、法定時間を超える労働に対しては適切な割増賃金を支払うことはもちろん、過度な業務負荷がかからないよう業務分担の見直しも必要です。
次に、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントといった、あらゆる形態のハラスメントを許さないという断固たる方針を明確にし、以下を徹底することが不可欠です。
- 全従業員への啓発研修
- 相談しやすい窓口の設置と実効性のある運用
- 発生時の厳正な対処
加えて、努力や成果が正当に評価され、給与や処遇に反映される公正な人事評価制度の運用も、従業員のモチベーション維持と不満の蓄積防止に繋がります。
採用のミスマッチを減らす
入社後間もない従業員が退職代行サービスを利用するケースには、採用ミスマッチが生じていた可能性を示唆しています。
採用ミスマッチを防ぐためには、採用活動全体を通じて、企業側が候補者に対して誠実かつ正確な情報を提供し、同時に候補者の価値観やスキル、社風への適性を慎重に見極める努力が不可欠です。
求人情報を作成する際には、魅力的な側面だけでなく、仕事の厳しさや企業が抱える課題についても可能な範囲で具体的に伝えることで、入社後のギャップを減らすことができます。
選考過程においては、以下をおこなうことも有効です。
- スキル面だけでなく、企業文化への共感度の確認
- ストレスを感じやすい状況への対処方法の確認
- 複数の面接官による多角的な視点での評価
また、候補者が企業の実際の雰囲気を知る機会として、職場見学や現場社員との座談会などを設けることも、ミスマッチの予防に繋がるでしょう。
入社前の期待と入社後の現実の乖離を小さくすることが、早期離職の防止には極めて重要です。
退職希望の場合のフローを明確にしておく
従業員が退職を考えた際に、「誰に、いつまでに、どのように伝えればよいのか」「その後の手続きはどう進むのか」といった社内の正式な手続きが不明確であったり、複雑であったりすると、従業員は退職を申し出ること自体に大きな心理的負担を感じてしまいます。
結果として、直接的なコミュニケーションを避け、退職代行サービスを利用する一因となり得ます。
このような事態を防ぐためには、企業として退職に関する社内フローを明確に整備し、それを全従業員に対して事前に分かりやすく周知しておくことが非常に重要です。
具体的には、就業規則に退職に関する以下の様な一連の流れを具体的に説明することが望ましいでしょう。
- 退職届の提出方法
- 業務の引き継ぎ
- 有給休暇の消化
- 貸与品の返却
標準的な退職届のフォーマットを用意しておくことも、従業員の手間を省き、手続きを円滑に進める助けとなります。
手続きの透明性を高めることで、従業員の不安を軽減し、直接的な申し出を促す効果が期待できるでしょう。
1on1ミーティングをおこなう
上司と部下が1対1で定期的に行う「1on1ミーティング」は、従業員の抱える不満やキャリアに関する悩みを把握し、退職代行サービスの利用に至る前に対処するための非常に有効なコミュニケーション施策です。
1on1ミーティングの目的は、業務の進捗管理や評価ではなく、以下の点に重きを置きましょう。
- 部下の成長支援
- 課題の早期発見と解決
- 信頼関係の構築
たとえば、週に1回15分から30分、あるいは月に1回30分から1時間程度の時間を確保し、部下が安心して本音を話せる雰囲気を作ることが重要となります。
話すテーマは、以下のように、多岐にわたって構いません。
- 業務上の困りごとや改善提案
- キャリアパスに関する希望
- 職場の人間関係
- プライベートな悩み
大切なのは、上司が評価者の立場で臨むのではなく、部下の話に真摯に耳を傾け、共感し、必要に応じて具体的なアドバイスやサポートを提供する姿勢です。
この積み重ねが、従業員のエンゲージメントを高め、問題が深刻化する前のアラートとして機能し、結果として退職代行に頼る必要のない職場環境づくりに貢献します。
以下の記事では、1on1ミーティングについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
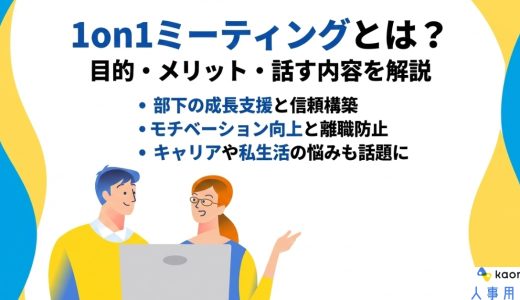
1on1とは? 目的とやり方、メリットや話すことがなくても失敗しない方法を解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
現在では多くの企業が導入する1on1とは、上司と部下が定期的...
1on1で何を話せばいいか悩んでいませんか?
話す内容や、質の高い質問項目を解説!
⇒「1on1ミーティングガイド」を無料ダウンロード
退職理由の分析にはカオナビがおすすめ

退職理由の分析において、カオナビは従来の課題を包括的に解決できるぴったりなツールです。
多くの企業が抱える以下のような問題に対して、カオナビは体系的なアプローチを提供します。
- 退職理由がわからない
- 社員が何に不満をもっているか把握できていない
定期的なパルスサーベイを実施し、個人・所属ごとの結果や推移を蓄積することで、社員のコンディションをリアルタイムで把握し、離職の兆候を早期に発見できます。
さらに、残業時間とサーベイの平均点で分布を把握したり、相関関係を分析する機能により、データに基づいた客観的な離職リスク評価が可能になります。
退職面談やアンケートの結果も体系的に蓄積され、定量・定性両方のデータを収集・可視化することで、表面的な理由ではなく根本的な退職要因を明確化できるでしょう。
これらの分析結果は人事部門と現場管理者間でリアルタイムに共有され、組織全体で効果的な離職防止策を実行する基盤となります。
人材戦略にお悩みでしたら、ぜひ一度「カオナビ」をご検討ください。
離職防止の分析にカオナビを活用する
カオナビが退職防止に役立った事例
ここからは、カオナビを退職防止に役立てた事例を3つ紹介していきます。
- SGグループ株式会社
- 株式会社松屋フーズ
- 株式会社グローバルキッズ
それぞれご紹介していきますので、参考にしてください。
SGグループ株式会社
SGグループ株式会社では中途採用社員の早期離職が課題となっていました。当初は1on1面談で対応していましたが、人事のリソース不足により限界が生じていました。
そこでカオナビのパルスサーベイ機能を導入し、健康面ややりがいなど10項目で社員の状態を定期的に調査する仕組みを構築しました。
また、自動メール送信機能により手間なく運用でき、社員も気軽に面談希望を出せるようになったとのことです。
その結果、月20〜30名実施していた面談が2名程度に削減され、本当に面談が必要な社員に集中できるようになりました。
パルスサーベイの推移データにより離職兆候を早期発見でき、面談前の情報収集も効率化し、業務の負担を削減できました。
現在は全社員に対象を拡大し、組織の健康診断として活用を継続しています。
出典:離職防止にパルスサーベイを活用!組織の“健康状態”を可視化して分かったこと
株式会社松屋フーズ
松屋フーズでは外食業界の深刻な人手不足に直面していました。全国に散らばった社員の人材情報がバラバラで見えにくく、退職者分析をExcelで行うのに膨大な時間がかかっており、社員一人ひとりの隠れた能力の見える化が課題となっていました。
そこでカオナビを導入し、以下の対応をおこないます。
- PROFILE BOOKで人材情報を一元化
- SHUFFLE FACEによるマトリックス分析で社員同士の組み合わせを検討
- SYNAPSE TREEで異動先での相性を考慮した配置シミュレーション
その結果、適材適所の人材配置により社員と店長のマッチングが向上し、離職防止につながりました。
データ整備作業が効率化され、具体的な離職防止対策を考える時間を確保できるようになり、人材活用の質が大幅に改善されました。
出典:「カオナビ」で人材情報を一元化。店舗の社員と店長のマッチングが可能になり離職防止につながる
株式会社グローバルキッズ
保育所運営のグローバルキッズでは、職員が1,000名を超えた際に、顔と名前が一致しなくなる課題に直面していました。
保育業界では待遇面での差別化が困難なため、コミュニケーションによる従業員満足度向上が重要です。
カオナビ導入により、以下が可能となりました。
- 代表が全職員の顔写真と情報を確認
- 研修管理によるキャリアパス形成
- 行政監査への迅速対応
- 離職者データ分析による採用ミスマッチ防止
その結果、離職率が16%から10%以下に改善し、厚生労働省発表の全国私立保育園の平均離職率である12%を下回りました。
2,439人の職員の従業員満足度向上により、人材定着という保育業界の重要課題解決に成功した事例です。
出典:カオナビを2年半活用した結果、職員2,439人の従業員満足度が向上し、離職率は全国平均以下になりました
モチベーション分析・離職分析にはカオナビ!
定期的なサーベイや分析と早期のケアで、社員エンゲージメントを向上できます
⇒PDFを無料ダウンロード
まとめ|従業員の労働環境を整え、退職防止に努めよう
退職代行を使われた際、企業はまず冷静に対応することが肝心です。
退職代行業者の正当性や本人の退職意思を確かめ、法務・実務手続きを適切に進めることで、トラブルを最小限に抑えられます。
しかし、より重要なのは、なぜ従業員がその手段を選んだのか根本原因を探ることです。
社内コミュニケーションや労働環境の問題点を見つけ、具体的な改善策を実行に移す必要があります。
定期的な面談の実施や相談しやすい窓口設置、退職手続きの明確化も再発防止に役立ちます。
従業員が安心して働ける環境を整え、良好な関係を築くことが、退職代行の利用を防ぎ、ひいては企業の発展へと繋がるでしょう。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見られる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

