人財とは、従業員を会社の財産、宝と考えていることを示す言葉です。近年、コーポレートサイトや採用サイト、求人票などで「人財」という言葉を見かける機会が増えてきました。
人財という言葉自体は良い意味を持つ一方、本来とは異なるイメージを持たれてしまうこともあります。今回は人財について、人材との違いや、企業が人材を人財と表現するメリット、注意点などを解説します。
目次
1.人財とは?
人財とは、「人材」の当て字であり、経営資源の一つである「人」は会社の財産だと意味する言葉です。「財」には、従業員は企業にとって有益であり、宝であるとの考えを示すメッセージが込められています。
近年、従業員を企業の資本と考え、投資によって価値を引き出し、利益の最大化を図る「人的資本経営」への注目が高まっています。「従業員=投資する資本」と捉えることからも「人財」という言葉が使われるようになりました。
そもそも人材の意味は?
人材は、才能があり、役に立つ人・有能な人物を指す言葉です。「材」という漢字には「才能」や「才能のある人」といった意味があります。企業における人材とは、業務を遂行するために役立つスキルや知識、能力を持つ人のこと。
個人の成果だけでなく、企業の力を高め、利益を創出するための力を持つ人という意味があります。さらに、現時点でそのような能力がなくても、将来的に成長し、能力を発揮する可能性がある人も含まれます。よって新入社員や内定者、さらには就職や転職活動中の人も「人材」として考えられるのです。
なお、「材」という言葉から「人材=材料」というイメージが持たれるかもしれません。しかし人材に「企業を構成する材料」「使い捨ての材料」といったような意味合いはありません。
具体的な人財の使い方
人財は、下記のように使われる言葉です。
- 企業の成長と発展に必要なのは、単なる人材ではなく、未来を創造できる人財だ。
- 我が社では、人材ではなく人財を育てることに力を入れています。
- 次世代リーダー育成に向けて、特別な「人財プログラム」を実施しています。
企業が従業員の重要性や価値に重きを置いていると伝えたい場合に「人財」が使われる傾向にあります。従業員は企業が大切にする「財宝」「財産」であり、企業の資本として投資する対象であるという意味も込めて使われています。
2.人材を人財と書く理由
あえて「人財」と書く理由は、「従業員を大切に扱う企業」というメッセージを伝えるためです。「人財」と書くことで、従業員一人ひとりを他の人には代えられない唯一無二の存在であると考えていることを強調できます。
従業員を宝と考える企業は、大切に扱われ、成長のために投資してもらえる企業として、従業員のエンゲージメントも高まりやすいでしょう。
ただし、人財だからと人材に劣るわけではありません。また、「人財」のとらえ方は企業や個人によってさまざまです。そのため、人材を人財と書くにあたっては、自社がどう人財を定義づけしているかまで伝えることがポイントです。
3.人材を人財と表現するメリット
人財と表現するメリットに、下記があります。メリットを詳しくみていきましょう。
- 企業イメージの向上
- 従業員の価値認識の転換
①企業イメージの向上
従業員は「企業の宝」であり、大切に扱うという意味を込めて人財と表記すると、従業員を大切にする会社とのイメージを社内外にアピールできるでしょう。ハラスメントや長時間労働など、労働環境の問題が増えるなか、求職者はより良い労働環境を求めています。
また、取引先など社外のステークホルダーは企業の持続的な成長可能性のため、従業員エンゲージメントや社外イメージといった点に着目しつつあります。人財という表現により、こうしたポイントをアピールできる点はメリットでしょう。
②従業員の価値認識の転換
近年、「人材を資本ととらえ、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」である、「人的資本経営」が注目を高めています。人的資本経営では、人材を消費する資源ではなく、投資して価値を高める資本ととらえます。
人的資本経営を推進するには、従業員を財産そして投資の対象ととらえる人的資本の考えを定着させることが必要です。「人財」という表現を使うと、従業員が投資対象である人的資本との認識が定着し、従業員に対する価値認識の転換にもつながります。

人的資本経営とは?【具体的な取り組み方】情報開示項目
人的資本経営とは従業員を「資本」と捉えて人材投資を行い、価値の最大化を目指す経営方法です。
近年、人的資本経営が重要視されているものの、人的資本経営とは具体的に何をすべきなのか、どのように実践すればよ...
4.人財を使う際の注意点
人財という言葉自体に悪い意味はないものの、人によってはネガティブなイメージを持ってしまう場合があります。人財を使う際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 実態が伴っていないと不信感が生まれる
- 否定的にとらえられるケースもある
- 人財を使うだけでメリットは得られない
①実態が伴っていないと不信感が生まれる
人財と表現することで「従業員を大切にする会社」とのイメージが持たれる効果は事実です。しかし、実態が伴っていないと人財という言葉自体にネガティブなイメージが持たれてしまいます。
人財とうたっているにもかかわらず、労働環境が整っていないなど、実態は従業員を大切にしていないケースも存在するからです。最も重要なのは実情であり、実際に従業員を大切にするために企業側が努力していること。これが人財を使う大前提です。
②否定的にとらえられるケースもある
人財という言葉自体に否定的な意味はなく、むしろ良い意味を持つ言葉です。しかし、「胡散臭い」「怪しい」など、一部否定的な意見もあります。その原因は、前述したように実態が伴っていない企業があることです。
人財という言葉を使っていなくても従業員を大切にする会社はたくさんあり、そういった企業には自然と人が集まります。しかし、あえて人財という言葉を使うことで、ブラック企業であることを誤魔化していると感じ取られてしまう恐れがある点には注意しましょう。
③人財を使うだけでメリットは得られない
人財という言葉を使ったからといって、採用面で有利になることはありません。人財という言葉は、あくまで表現の一つ。人財と表現しているからと実際に従業員を大切にする会社であるとは限らず、企業がそのつもりでも従業員にとっては、そのように感じられない可能性もあります。
「人材」と表現することとの優劣はないため、特別なメッセージや理由がなければ、あえて人財を使わないことも戦略でしょう。
5.人材を人財に変える育成方法
人材を人財に変えるには、企業側が主体的に育成に取り組むことが大切です。人材と人財に優劣はないものの、自社の人財を定義した上で育成に取り組むと、従業員も自分たちが人財として大切にされ、育成に投資してもらえていると認識できます。
ここでは、人材を人財に変える育成方法とそのポイントをご紹介します。
明確な目標設定
自社が目指す人財へと成長させるには、その指標となる目標設定が不可欠です。そのため、まずは自社の目指す人財がどういった人物像なのかを明確にしましょう。そのうえで、組織側と従業員側で擦り合わせながら適正やキャリア志向に沿った目標を設定します。
目標は客観的に判断できる指標であり、人財へと近づくことが企業の成果にもつながるかが重要です。
従業員(組織)の目標達成までの進捗を上司が管理・フォローすることをMBO(目標管理制度)といいます。上司と従業員が二人三脚で目標達成に取り組むことは、目指すべき人財への目標から逸れることなく、モチベーションを高められます。
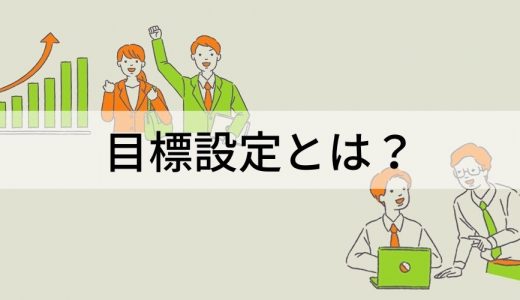
目標設定とは?【設定のコツを一覧で】重要な理由、具体例
目標設定は、経営目標達成や個人のレベルアップのために重要なもの。適切な目標設定ができないと、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやるべきことも洗い出せなくなってしまうでしょう。
今回は...
OJT
OJTは「On The Job Training」の略称で、先輩にあたる従業員が業務に必要なスキルや知識を実践しながら教える育成方法です。人が人を育てる風土が醸成でき、継続的な実施によって効率的な人財育成が可能となります。
OJTを人財育成につなげるには、先輩となる従業員が企業の掲げる人財像であるかどうか、がカギになります。身近な存在が手本となれば、企業が求める人財像を理解しながら必要な能力を身につけられるでしょう。

OJTとは? 意味、教育や研修の方法、OFF-JTとの違いを簡単に
OJTとは、実務を通してマンツーマン指導により知識・スキルを身につける育成手法です。実務を通した研修となるためスキル・知識の定着化が早く、新人や未経験者の早期戦力化に期待できます。
OJTとは何かをふ...
Off-JT
Off-JTは「Off-the-Job Training」の略称で、現場から離れて実施する育成方法です。たとえば、会議室での座学研修や外部セミナーへの参加、オンライン学習などが該当します。
現場で必要な能力の土台となる知識やスキルを体系的に学べる機会で、OJTとうまく組み合わせると効率的に能力を高められます。主な手法に、社内外研修やeラーニングがあり、必要なスキルや高めたいスキル、不足するスキルなど、目的にあわせて柔軟に育成できるのです。

OFF‐JTとは|OJTとの違い、メリットや具体例などを紹介
人材情報から戦略的育成を!
カオナビならOFFJTなどの研修履歴がわかるから、計画的な人材育成ができます。
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロー...
自己啓発
自己啓発とは、個人が自発的に行う学習のこと。自己啓発を促すと、従業員が主体的に人財になる必要な行動を取れるようになります。現場の人手不足や必要なスキルの多様化により、受け身の学習だけでは効率的な成長は難しくなっているもの。
そのため、自己啓発により、従業員が主体的に学習に取り組める機会を設けることが大切です。自己啓発を促すには、企業は資格取得支援や外部セミナーや勉強会、書籍購入費の負担などといった施策が有効です。
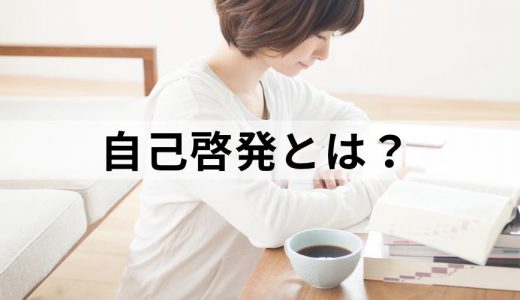
自己啓発とは? 意味や仕事での効果、やり方や具体例を簡単に
自己啓発とは、自分に本来備わっている能力を伸ばすために行う行為のこと。
自己啓発では、精神的な成長を促して、
より高い能力
より大きい成功
より充実した生き方
より優れた人格
などを目指していきま...
メンター制度
メンター制度は、先輩社員が後輩社員を指導・サポートする育成制度です。後輩社員の不安や悩みを解消し、定着率向上や早期離職を防ぐことを目的としています。
メンター制度の対象となる従業員は、今後人財へと成長していく重要な存在。早期離職してしまっては、人材を人財に変えられません。人材を人財へと成長させるには、定着率向上や早期離職を防止することも必要です。

メンター制度とは? メリット・デメリット、成功事例を簡単に
1.メンター制度とは?
メンター制度とは、年の近い先輩社員が新入社員や若手社員をサポート・育成する制度のこと。業務に関する支援だけでなく、人間関係やキャリアなど、幅広くサポートする点が特徴。不安や...
6.人材と人財以外のジンザイ
人材の同音異義語には、人財のほか「人罪」「人在」があります。人材と人財以外のジンザイについても意味を押さえてみましょう。
人罪
人罪とは、他人や組織に悪影響を及ぼす人を指す言葉です。悪意のある問題やミスだけでなく、悪意がなくともひんぱんに周りに迷惑をかけたり、仕事をサボって成果を出さずに給料だけもらったりするような人が人罪にあたります。
「罪」には「問題を起こす」という意味から「災い」の意味合いもあり、人罪を「人災」と表現する場合もあります。漢字の意味からもわかるように、100%悪い意味を持つ言葉です。
人在
人在は、会社にただいる(在る)だけの人を意味する言葉です。過去に実績はあるが今以上の成長見込みはなく将来性がない、仕事に大きな問題はないが熱意のない指示待ち人間であるような人を指します。
終身雇用制度の時代では、それでも企業の発展に問題はなく、従業員も年数の経過とともに出世できるのが一般的でした。
しかし、ビジネス環境の変化が激しい現代では、主体的に考えて動き、企業の利益を最大化できる人材が求められます。よくも悪くも平均レベルで留まる人は、企業の発展には貢献しにくく、評価にもつながりにくいでしょう。
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

