通勤手当とは、従業員の通勤にともなう費用を企業が支給する福利厚生です。交通費との違い、課税ルール、制度を運用するポイントなどを解説します。
目次
1.通勤手当とは?
通勤手当とは、従業員が通勤に要する費用を補助する福利厚生のこと。労働基準法では通勤手当の支給を義務づけておらず、企業の裁量で支給の有無や金額、支給方法などを自由に定められます。
そのため支給条件、支給額、支給形式などは企業によってさまざまです。支給形式では、基本給とは別に通勤手当として支給、もしくは定期券など物品での支給が多く見られます。

手当とは? 主な種類一覧、課税・非課税対象をわかりやすく
初期費用無料! めんどうな紙の給与明細の発行がWEBでカンタンに。
「ロウムメイト」で時間が掛かっていた給与明細発行業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
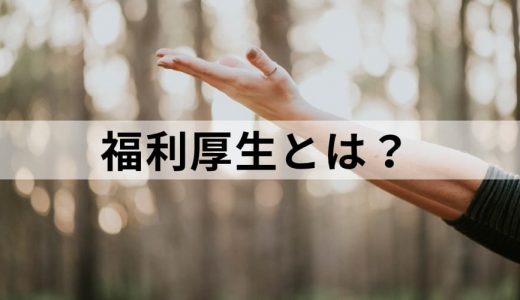
福利厚生とは?【制度を簡単に】種類一覧、人気ランキング
導入している福利厚生、本当に従業員エンゲージメント向上に貢献していますか?
カオナビなら必要・不要な福利厚生を見える化し、エンゲージメント向上&コスト削減!
⇒ 【公式】https://www.kao...
通勤手当の支給義務はない
通勤手当の支給について法的義務はありません。しかし就業規則や給与規定に明示されている場合は労働条件とみなされて、労働契約法による支給義務が生じます。
たとえば雇用契約書や労働条件通知書で各従業員と合意した支給額と、就業規則や給与規程で規定された支給額が異なる場合は、高い方の金額を支払わなければなりません。
通勤手当の非課税限度額の引き上げとは?
2016年の所得税法改正において、通勤手当の非課税限度額が変更されました。
通勤手当は一定の限度額まで非課税とされており、支給額は通勤に使用する交通機関や交通用具(自動車や自転車など)の種類、および通勤距離に応じて非課税限度額(上限)が設けられています。
2016年の改正では、交通機関または有料道路を利用する場合の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。また定期乗車券や交通用具を併用する場合も同額が適用されるのです。
2.通勤費と交通費の違い
通勤費(通勤手当)と混同されやすい用語に「交通費」があります。双方の違いは、「いつ発生する費用か」「給与の一部か経費か」の2点です。
就業中かどうかの違い
通勤費は文字通り「通勤時に発生する費用」、交通費は「業務に関連して発生する費用」です。通勤費は従業員によって発生の有無が異なるものの、交通費は営業の外回りや出張などの業務を担当する従業員へ生じます。
勘定科目における違い
通勤費と交通費は、経理上の勘定科目が異なります。
通勤費は給与手当と同等に「従業員の所得」、交通費は経費として扱い「旅費交通費」や「出張旅費」で処理するのです。そのため通勤費は非課税限度額を超えた分は課税対象、交通費は全額非課税となります。

交通費とは? 通勤手当との違い、支給要件、計算方法を簡単に
交通費とは、乗り物に乗車する際にかかる費用のこと。ビジネスにおける交通費について、支給要件や計算方法などから解説します。
1.交通費とは?
交通費とは、鉄道や飛行機、バスや船などに乗車する際にかかる...
3.通勤手当の相場
通勤手当は企業が自由に定められるうえ、地域によって交通事情が異なるため、決まった相場は存在しません。
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査の概況」によると、2019年11月における1か月あたりの通勤手当の平均支給額は、労働者1人あたりで1万1,700円。
企業の規模によって3,000円程度の差があるものの、多くの企業で1万円以上を支給しています。
4.通勤手当への所得税の課税・非課税のルール
通勤費は給与の一部として支給される所得であり、通勤費の非課税限度額を超えた金額は、所得税の課税対象となります。
基本は非課税対象
企業が従業員に支給する各種手当は、基本的にすべて課税の対象です。ただし通勤手当は、「会社に出勤するための実費」と解釈されるため、一定額までは非課税といえます。
通勤方法によって非課税限度額は異なり、最少で4,200円、最大で15万円。通勤方法による上限額については次項で詳しく説明します。
非課税限度額を超過した分は年末調整で計算
企業は年末調整時に、通勤手当の非課税限度額を超えた分を給与所得へ含める必要があります。そのため企業は従業員ごとに超過分を把握していなければなりません。
とくに交通費や通勤手当の上限を設けていない企業や、長距離通勤をしている従業員が多い企業は注意が必要です。
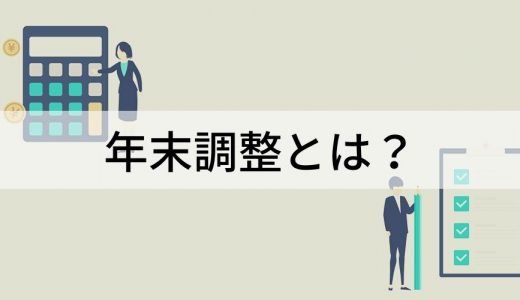
年末調整とは? 確定申告との違い、対象者、流れ、計算、適用される控除
年末調整とは、1年間に支払った所得税の過不足を調整する作業のことです。ここでは必要な理由や確定申告との違いなどさまざまな点から、年末調整について解説します。
1.年末調整とは?
年末調整とは、所得税...
5.非課税で支給できる通勤手当の範囲
通勤手当は通勤手段によって非課税限度額が異なり、詳細は国税庁のホームページで確認が可能です。ここでは3パターンの非課税限度額について説明します。
マイカーや自転車での通勤
車通勤および自転車通勤の場合は、片道の距離によって1か月あたりの非課税限度額は異なります。
- 2キロメートル未満:全額課税
- 2キロメートル以上10キロメートル未満:4,200円
- 10キロメートル以上15キロメートル未満:7,100円
- 15キロメートル以上25キロメートル未満:1万2,900円
- 25キロメートル以上35キロメートル未満:1万8,700円
- 35キロメートル以上45キロメートル未満:2万4,400円
- 45キロメートル以上55キロメートル未満:2万8,000円
- 55キロメートル以上:3万1,600円
出典:国税庁「マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表」
有料道路や駐車場代が通勤手当の扱い
マイカー通勤で有料道路を利用する場合、通行料も通勤手当として支給されます。
有料道路
「有料道路を通ることで時間が大幅に短縮される」「その道路を通らないと通勤できない」などのケースで認められます。非課税限度額は、距離に応じた非課税限度額と有料道路の通行料を合算し、1か月あたり15万円までです。
駐車場
通勤手当の非課税限度額に含めません。企業が借りた駐車場代は経費として処理し、従業員が個人名義で借りた場合は給与の一部として支給します。
公共交通機関での通勤
鉄道やバスなど公共交通機関だけを使った場合、通勤手当の非課税限度額は、1か月あたり15万円です。
ただし「もっとも経済的(運賃が低い)で合理的(所要時間が短い)な経路や方法」を選択する必要があります。
たとえば新幹線のグリーン車で通勤する場合、乗車料金のほかにグリーン料金が必要。しかしグリーン車の利用は経済的とはいえないため、非課税限度額に含められません。
複数の交通手段を併用した場合
マイカーや自転車と公共交通機関を組み合わせて通勤する場合も、非課税限度額は15万円です。交通費の計算では、マイカーや自転車の通勤距離に応じた非課税限度額と、鉄道やバスの定期券料金などを合計します。
なおタクシーでの通勤は、深夜などで交通機関を利用できない場合に限り、非課税限度額へ含められるのです。
6.通勤手当の決め方と計算方法
通勤手当の詳細は各企業が自由に決定できます。ここでは通勤手当の決定方法と支給額の計算方法について説明しましょう。
通勤手当の決め方
通勤手当における支給の有無、金額、支給するタイミングなどは、企業が自由に決められます。ただし支給する場合は給与の一部となるため、就業規則や雇用契約に明確に記載し、すべての従業員に詳細を周知しなければなりません。
支給額の計算方法
通勤手当の計算方法は、交通手段によって異なります。ここではマイカーでの通勤、交通機関での通勤、自転車での通勤における計算方法を説明しましょう。
マイカー通勤の場合
法律ではマイカー通勤手当の計算方法についての規定がなく、企業で算定方法を決めなければなりません。実際にはガソリン単価、通勤距離、燃費性能などを考慮したうえで、次のような計算方法が一般的です。
1日の通勤手当=1kmあたりのガソリン単価 × 片道km数 × 2(往復)
たとえば「片道5km、月20日勤務、1kmあたりのガソリン単価が15円」の場合は、次の計算を行います。
- 15円×5km×2=150円(1日の通勤手当)
- 150円×20日=3,000円(1か月の通勤手当)
「2km以上10km未満」の非課税限度額は4,200円であるため、上記の計算で算出した交通費は全額非課税です。
交通機関での通勤の場合
鉄道やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合は、次のうちいずれかの計算式を用いるのが一般的です。
- 該当区間の通勤定期代1か月分
- 片道運賃×2×出勤日数
従業員はもっとも経済的で合理的な経路と運賃を申告しなければなりません。
自転車の場合
自転車通勤の場合、運賃やガソリン代などの費用はかかりません。そのため「距離にかかわらず同額を一律で支給」「一定の距離以上は、マイカーと同様に距離に応じた金額を支給」などで対応している企業がみられます。
なお駐輪場の料金は、非課税限度額に含められません。
7.通勤手当の社会保険における扱い
社会保険において通勤手当は報酬として扱われ、保険料を算出する際の標準報酬月額に含まれます。厚生年金保険法では、労務の対償として支給されるあらゆる報酬が標準報酬月額の対象とされるためです。
たとえば通勤手当として6か月分の定期券代を支給した場合、その料金を月数で割って1か月分として換算したうえで、各月の標準報酬月額に含めます。

標準報酬月額とは? 決め方・計算方法・調べ方をわかりやすく
社会保険料の計算に不可欠な「標準報酬月額」は、従業員の月給をもとに社会保険料の算出を行う基準値のこと。従業員の報酬に応じた適切な社会保険料の計算は、事業運営において重要な要素で、正確な知識を持つことは...
8.通勤手当制度を設計・運用する際のポイント
通勤手当を導入する際は、運用のしやすさ、公平性、わかりやすさなどを考慮したうえで制度を設計しましょう。また規程が常識的な範囲を逸脱しないよう注意が必要です。ここでは通勤手当制度を導入する際のポイントについて説明します。
シンプルな制度
全社が一律の制度を採用することを前提とし、多くの特例を設けたり、手当額の計算が煩雑になったりするような規程は避けるべきです。ルールをシンプルにすれば従業員からの問い合わせが減少し、運用コストや人事部門の業務負担を軽減できます。
明確な条件や計算方法
通勤手当を導入する際には、支給の具体的な条件、支払い方法、タイミングや頻度、金額の算定方法などを明確に定めることが大切です。
ルールを明示すると従業員の誤解や不満が抑えられ、よりスムーズに制度を運用できます。
就業規則に明文化
通勤手当の支給条件や上限額を具体的に定めたら、就業規則に明文化します。以下の4項目は必ず明記しましょう。
- 支給要件
- 支給金額の算出方法
- 通勤手段ごとの取り扱い方法
- 通勤手当の申請方法
「通勤に要する実費に相当する金額を支給する」といった曖昧な表現は避け、具体的で明確な規定を記載することが重要です。
在宅やテレワークへの対応
在宅やテレワークなどで出社回数が減少する可能性もあります。このようなケースにおける通勤手当の規程も決めておくと安心です。たとえば「出社日数に応じて実費精算」「通勤手当の代わりに在宅勤務手当を支給」などの対応が挙げられます。
9.通勤手当制度の注意点
通勤手当の導入や運用に際して、懸念点やリスクがいくつかあります。ここでは3つの注意点を解説しましょう。
不正受給を防止
従業員が通勤にかかった費用を自己申告するため、不正受給のリスクがあります。不正受給を防ぐには、申告内容の整合性を確認することが重要です。
とくに注意が必要なのは、申告された通勤経路が「もっとも効率的かつ合理的であるか」です。通勤手当を増やすために、本来の通勤経路とは異なる高額な経路を故意に申告するケースも見られるため、管理者は全員分の申告内容を確認する必要があります。
雇用形態による格差の発生
雇用形態によって通勤手当に格差が生じないように設定しなければなりません。パートやアルバイトなどの非正規雇用者についても、正規雇用の従業員と同じ計算方法で通勤手当を支給します。
なお出勤日数や通勤手段の違いによる支給額の差異は問題ありません。たとえば非正規雇用者は正社員よりも出勤日数が少ないため、通勤手当が低額になるといったケースです。
変更や廃止の際の手続き
通勤手当の廃止や減額は、給与や福利厚生を減らすことになるため、「労働条件の不利益変更」に該当する可能性もあります。労働条件の不利益変更を実施する際は、従業員の合意を得なければなりません。
また通勤手当の支給額が減少すると所得も減少するため、厚生年金の給付額が減る可能性もあります。通勤手当を廃止や減額する際は代替案を提示し、労働者の理解と納得を得ることが重要です。
10.通勤手当の不正受給となるケース
従業員が虚偽の交通費を申告すると、「不正受給」とみなされます。故意に不正受給した場合は、解雇処分にもなりかねません。ここでは不正受給となるケースを解説します。
申告している住所以外から通勤するケース
転居後に住民票を移動せず、前の住所のまま定期代の支給を受け続けるケースが該当します。申告している経路よりも実費の交通費が安くなった場合は、横領とみなされる恐れもあるのです。
そのため改築や家庭の事情で住んでいる場所が一時的に変わる場合も、会社へ申告した方が無難です。
申告している経路以外から通勤するケース
会社が指定した、または従業員が申告した通勤方法や経路ではなく、より安価な方法や経路を使っているケースです。たとえば自転車で通勤していることを隠して、交通機関の定期券代を詐取するといった状況が挙げられます。
住所の変更がなくとも、実費額よりも支給額が高額であった場合は不正受給に該当します。
定期券解約の払戻金を領得するケース
購入した定期券を解約して払戻金を受け取り、実際は自転車や徒歩で通勤しているケースです。
意図的に現金化していため、一般的には不正受給のなかでも悪質だと判断されます。そのため返還や懲戒といった社内の処分だけでなく、告訴される可能性もあるのです。

