部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
近年、人材育成を目的にメンター制度を取り入れる企業が増えています。制度の導入を成功につなげるためには、メンターに関する理解が欠かせません。今回は、メンターの意味や役割、メンタリングの方法、メンターの育成方法などを解説します。
目次
1.メンターとは?
メンターとは、単なる「仕事の指導役」ではなく、若手や新入社員(メンティー)のキャリア形成や精神的な悩みに寄り添い、対話を通じて自発的な成長を促す「信頼できる相談相手」です。その語源は、古代ギリシャの叙事詩『オデッセイア』に登場する賢人「メントール(Mentor)」に由来し、王の息子を優れた人物に導いた逸話から、指導者・助言者の意味で使われるようになりました。
近年、多くの企業がメンター制度を導入する背景には、新入社員の早期離職という深刻な経営課題があります。メンターは、業務スキルを教えるだけでなく、職場での人間関係や将来のキャリアパスといった、メンティーが一人で抱え込みがちな不安を解消する「心理的安全性」の提供者としての役割が期待されています。
メンティーとは?
メンター制度において、支援する側の先輩社員を「メンター(Mentor)」、支援を受ける側の後輩・新入社員を「メンティー(Mentee)」と呼びます。
- メンター:指導や助言を与える側の人(先輩社員)
- メンティー:指導や助言を受ける側の人(後輩社員)
- メンタリング:メンターがメンティーに行う面談などの指導
重要なのは、この関係が一方的な「指導・被指導」の関係ではないという点です。メンターはメンティーの自発的な気づきや成長を促す伴走者であり、メンティーは受け身で教えを乞うだけでなく、自らの課題や考えを積極的にメンターに投げかける主体者となります。この相互作用が、メンタリングの効果を最大化します。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.メンター制度とOJT、コーチングの違い
人材育成の方法として、OJTやコーチングを取り入れる企業も多いでしょう。メンター制度は、OJTやコーチングと似ている部分もあるものの、目的やアプローチ方法が異なります。以下で、それぞれの違いを見てみましょう。

メンター制度とは? メリット・デメリット、成功事例を簡単に
メンター制度を運用するための、従業員情報を管理できていますか?
タレントマネジメントを行うことで、人員管理を効率化できます!
⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
...
OJTとの違い
OJT(On-the-Job Training)が「業務遂行能力の向上」を目的とし、直属の上司や先輩が具体的な業務手順を教える「タテの関係」での指導であるのに対し、メンター制度は「キャリアを含めた全人格的な成長支援」を目的とします。
そのため、メンターはあえて直属ではない他部署の先輩社員が担うことが多く、利害関係のない「ナナメの関係」で、業務の悩みからプライベートな相談まで、幅広いテーマについて対話できるのが大きな違いです。OJTが「今日の業務」の成功を支援するなら、メンターは「未来のキャリア」の成功を支援する存在と言えるでしょう。

OJTとは? 意味や目的、メリット、進め方、OFF-JTとの違いを簡単に
OJT(On the Job Training)は、実際の業務を通じて従業員を育成する方法として、多くの企業で採用されています。
座学では学びきれない実践的なスキルを習得できるのが特徴で、新入社員や異...
コーチングとの違い
コーチングとメンター制度は、目的が異なっています。
- コーチング:相手の目標達成を目的として伴走・支援を行う方法。コーチは、傾聴・質問・承認を用いて本人に「気づき」を促し、目標達成に向かう思考や行動を引き出す
- メンター制度:必ずしもメンティーの具体的な目標達成を目的としない。相手の精神的なサポートとなり、キャリア全体の成功を支援することが目的

コーチングとは? 意味、ビジネスでの効果、やり方を簡単に
コーチングは、運動や勉強、技術の指導において、学習や成長を促進するアプローチです。この方法は、クライアントの潜在能力に働きかけ、最大限に力を引き出すことを目的としています。単なる指導にとどまらず、相...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
3.メンターの役割
メンターになったけれども求められている役割がよくわからない、という人も多いのではないでしょうか。以下では、メンターの役割を具体的に解説します。
精神的支えとなる
メンターは、メンティーの悩みや不安に耳を傾けることで、精神的な支えとなります。会話の内容は、職場の悩みだけに限りません。
プライベートの不安や心配ごとも共有できる存在になることが理想的です。一般的に、ペアになる相手は他部署から選ばれるため、客観的な立場で話を聞けるメリットがあります。ここでメンターに求められるのは、指導ではなく傾聴です。
ロールモデルとなる
若手社員や中途社員にとって、メンターはロールモデルとしての役割も果たします。仕事への向き合い方や、関係者との接し方を示すお手本としての役割です。なお、メンティーの視点から見ると、メンターは以下2つのタイプに分かれます。
- メンティーと価値観が近しい「話しやすいメンター」
- メンティーと価値観が異なる「学びのあるメンター」
メンタリングの早期でこれらの違いを把握しておくことで、関係性を構築しやすくなり、「合う・合わない」といった悩みも発生しづらくなるでしょう。

ロールモデルとは? 意味やメリット、具体例、見つけ方を簡単に
ビジネスパーソンに欠かせないロールモデルをご存じでしょうか?ロールモデルの存在は、自分の現状認識と成長に役立つのです。
ロールモデルとは何か?
役割
効果や影響
どのような手法でロールモデルを利用す...
成長を促す
メンティーの成長を促す手助けも、メンターの役割です。メンターは、メンティーから相談を受けた事柄に対してすべてに解決策を与えたり、あれこれ指図する必要はありません。メンティー自身が課題に向き合えるよう、サポートすることが重要です。
あくまでも傾聴・問いかけを基本にして、必要であればアドバイスをしたり社内の相談先につなぐなどして支援します。
部署間の交流を促す
メンターは、メンティーと周囲の交流を促し、部署を超えた関わりを取り持つ役割も担います。他部署の人と関わることで、メンティーは組織の全体像を掴みやすくなり、業務の円滑化も期待できます。
部署間の連携・ネットワークが促進され、組織全体の活性化につながることは組織にとってもメリットです。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.メンターに適した人材|良いメンターとは?
メンターに適した人材にはどのような特徴があるのでしょうか。以下5つのポイントで解説します。
人材育成に対する意欲がある
若手社員の育成をサポートする意欲がある人材は、メンターに適していると言えます。メンターの役割は、メンティーの精神的な支えとなりアドバイスや支援を行うこと。長期的な関係性を築くために、「成長を助けたい」といった意欲が必要になります。
高圧的でなくフラットに接することができる
年齢の差に関わらず、高圧的でなくフラットな関係を構築できる人物がよいでしょう。メンターとメンティーは、ささいな心配ごとも相談できる関係性が理想です。メンターとなる先輩社員が高圧的であったり、相手を見下すような態度があると、若手社員は萎縮しやすくなります。
コミュニケーション能力がある
メンターにとって、メンティーとしっかり対話ができるコミュニケーション能力は重要です。たとえば、一方的に「話す・教える」ではなく、「傾聴」や「共感・受容」といったスキルが求められます。
感じたことや考えたことを言語化し、誠実に、齟齬なく相手に伝えられる能力があると、なおよいでしょう。このような対話のスキルは、トレーニングによって向上させることも可能です。
業務や組織への理解度が十分である
業務や組織への理解が十分にあることも、メンターに適した人材の要素です。組織内のできごとに関する相談を聞いたり、アドバイスを与えたりするには、インフォーマルな情報も含めて知っている人物がなおよいでしょう。
業務上の利害関係がない
他部署の先輩社員など、メンティーにとって業務上の利害関係がない人物がメンターに適任です。メンターは、実務的な指導をする立場ではなく、「良き指導者」「助言者」としての存在です。直属の上司や先輩であると、評価に影響する可能性があり、メンティーは気兼ねなく相談できません。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
5.メンター制度のメリット
メンター・メンティー・企業のそれぞれの立場における、メンター制度のメリットを解説します。
メンター側のメリット
メンター自身の成長も、この制度の重要な効果です。メンティーの成長に責任を持つ経験は、将来の管理職に求められる傾聴力、質問力、フィードバック能力といった「疑似マネジメント経験」を積む絶好の機会となります。部下を持たない段階から人材育成の難しさとやりがいを学ぶことで、自身のリーダーシップ能力を飛躍的に高めることが可能です。
また、自分とは異なる価値観を持つ若手社員(メンティー)と真剣に向き合うことで、自らの常識や固定観念を問い直すきっかけとなり、「新たな視点」を得られます。これは、組織の多様性を理解し、イノベーションを生み出す土壌を育む上でも非常に有益です。
メンティー側のメリット
メンティーにとって大きなメリットは、安心して何でも相談できる「心理的安全性」が確保されることです。直属の上司には相談しにくい業務上の些細な疑問や人間関係の悩み、将来への漠然とした不安などを、利害関係のない先輩であるメンターに打ち明けられる環境は、新入社員が抱えがちな「孤立感」を解消します。
さらに、メンターとの対話を通じて、自分自身の強みや価値観を再発見し、中長期的なキャリアプランを具体的に描く「キャリアの羅針盤」を得ることが可能です。目の前の業務をこなすだけでなく、その仕事が将来どう繋がるのかを理解することで、仕事へのモチベーションが大きく向上します。
企業側のメリット
企業にとって最も直接的なメリットは、新入社員の定着率向上、すなわち「離職率の低下」です。厚生労働省の調査では、依然として大卒新入社員の約3割が3年以内に離職しています。メンター制度は、この課題に対する極めて有効な打ち手です。
さらに、メンター制度は部署や世代を超えたコミュニケーションを活性化させ、互いに助け合い、学び合うという「組織文化の醸成」に貢献します。これは、単なる業績向上に留まらない、企業の持続的な成長を支える無形の資産となります。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.メンター制度導入の流れ
メンター制度の導入は、単に担当者を割り当てるだけでは機能しません。形骸化させず、確実に成果を出すためには、以下のステップに沿った慎重な設計と準備が不可欠です。
- 目的とゴールの設定
- 運用ルールの設計
- メンターとメンティーのマッチング
- 事前研修の実施
- メンタリングの実施と振り返り
- 効果測定と改善
目的とゴールの設定
なぜ導入するのかを明確にします。「新入社員の3年後定着率を10%向上させる」「女性管理職候補の育成」など、具体的なKPIを設定することが成功の鍵です。
運用ルールの設計
以下のような細かなルールを事前に定めます。
- 面談の頻度(月1回1時間など)
- 報告義務の有無
- 活動場所(社内会議室など)
- 費用(カフェ代など)の精算方法
- 守秘義務の範囲 など
これにより、メンターの負担を軽減し、メンティーの安心感を醸成します。
メンターとメンティーのマッチング
マッチングは、最も重要なプロセスです。性格診断ツールを活用したり、双方のキャリア志向や価値観をヒアリングしたりして、メンターとメンティーをマッチングします。
安易なくじ引きや思いつきでペアを組むのは避けましょう。基本は、利害関係の生じない他部署の先輩(入社3~7年目程度)が理想的です。
事前研修の実施
メンターとメンティー双方に研修を行います。特にメンターには、傾聴のスキル、質問の仕方、やってはいけないこと(説教や自慢話など)を具体的に伝え、役割への理解と意識付けを徹底します。
メンタリングの実施と振り返り
制度を開始した後も、人事部が定期的に双方からヒアリングを行い、関係性が良好に機能しているか、問題は発生していないかを確認します。問題があれば、ペアの変更も視野に入れます。
効果測定と改善
設定したKPI(定着率、満足度アンケートなど)を元に、定期的に制度の効果を測定し、次年度の運用改善に繋げます。やりっぱなしにしないことが、制度を組織に根付かせる上で重要です。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
7.メンタリングを行う際のポイント
メンタリングを行う際の心得として、4つのポイントを紹介します。
個人ごとの違いを理解する
メンタリングを行うにあたって、価値観や成長スピードは個人ごとに違うと理解するのはひとつのポイントです。仕事や人生に何を求めるかといった価値観や、気づきを得て変化するまでの成長スピードなどは、人それぞれ異なるでしょう。
メンター自身の型に当てはめて、「なぜこうしないんだろう」と考えないよう注意が必要です。メンティーの成長を促したい気持ちで焦らず、相手のペースを理解する意識を持つとよいでしょう。
命令・説教・否定をしない
メンタリングは「命令・説教・否定」ではなく、あくまでも「傾聴・質問・承認」を重視します。メンティーの口から愚痴や他者への批判などが出ても、否定する言葉は避けましょう。
同時に、うわべだけの雑談や同調で終わらせず、「なぜそう感じたのか?」「どうなると理想的なのか?」といった質問を投げかけることで本人の気づきを促し、成長をサポートします。
話した内容を他言しない
メンタリングの中で話した内容は、絶対に他言しません。たとえばメンティーが抱える体調面の不安やその他のあらゆる事象など、上司に相談が必要だと思うことがあっても、メンターが口外してはいけません。
メンティー本人から上司へ直接相談するように促すか、メンティーの同意を得た上でメンターから報告しましょう。
評価と関連づけない
メンタリングの内容を人事評価に関連付けないようにしましょう。制度としては人事評価と切り分けた上で、メンターおよびメンティーが、話した内容を口外しないことを前提とします。話が漏れると、意識的・無意識的に関わらず、人事評価に影響する可能性があるためです。
また万が一人事評価に影響した場合、メンタリングの信頼関係を失うだけでなく、従業員から組織に対する不信感に直結します。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード8.メンタリングのやり方
メンタリングでは、人事面談や1on1と違ったアプローチが必要です。以下で、具体的なメンタリングの方法を解説します。
メンティーの話を傾聴する
メンタリングの基本は傾聴(相手の言うことを否定せず、耳も心も傾けて相手の話を聴くこと)です。途中で話を遮らず、メンティーの言葉を聞き逃しません。頷くなどして話を聞いている、受け入れていることを表現します。メンティーが気後れせずに話せる気配りを心がけます。

傾聴とは? 意味や効果、三原則、具体的なやり方をわかりやすく
傾聴とは、「耳」「目」「心」を傾けて真摯な姿勢で相手の話を聴くコミュニケーションの技法。相手との信頼関係を築くだけでなく、傾聴を通して自分自身を知り、感情のコントロール等精神的成長を促すきっかけにも...
ポジティブな言葉に言い換える
相手の言葉を前向きな言葉に置き換える「リフレーミング」で、メンティーの不安を和らげます。
たとえば「頑固」→「意志の強い」、「冷たい」→「凛とした」などです。悩みや不安を抱えていると客観的な視点を失いやすくなります。メンターがリフレーミングすることで、メンティーが前向きな気持ちに切り替えるサポートをします。
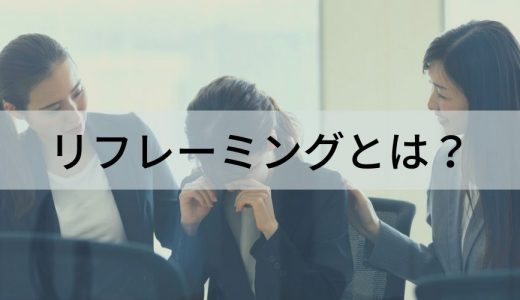
リフレーミングとは? 意味や効果、5つの手法とやり方、具体例
1.リフレーミングとは?
リフレーミング(reframing)とは、物事の枠組みを変え、違う視点から見ることを意味する心理学用語です。欠点や不安といったネガティブな物事も、考え方の前提を変えること...
メンティーの反応をよく観察する
対話をしながら、メンティーの表情や声の調子をよく観察します。何か言いたいことがあるようであれば、質問を投げかけ、言語化をサポートしましょう。また、メンターだけが早口になっていないかなど、話すペースを観察しなるべく相手に合わせるのもポイントです。
話の内容を短くまとめて繰り返す
メンティーが話した内容を簡潔にまとめて繰り返します。その際メンターの主観が入らないよう、「〇〇さんが〜〜と言って、△△さんが〜〜と返事をしたんだね」など、客観的な事実をピックアップするとまとめやすいでしょう。簡潔にまとめて繰り返すことで、話を聞いている安心感を与えつつ、相談内容を整理できます。
対話を通じて気づきを促す
メンターは、対話を通じてメンティーの気づきを促します。相談内容に対して、メンターが直接的な答えを与える必要はありません。メンターは「どう感じたのか?」「どうなると理想的か?」といった質問を交えて、メンティー自身が答えに辿り着けるように対話します。
その際、コーチングの質問形式を参考にするとよいでしょう。自身の経験が役立ちそうなアドバイスがあっても押し付けず、ヒントを与える程度に留めます。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード9.メンターの育成方法
メンター制度を成功に導くためには、メンターの育成が重要です。ここでは、人事部門の担当者が知っておきたい、メンターの育成方法を紹介します。
導入担当者がメンタリングを理解する
制度の導入担当者が、メンタリングの概要と効果、メンターの役割やメンティーへの影響などメンタリングを理解していることが非常に重要です。メンターとメンティーを選出すれば理解なしにメンタリングを実施できます。それゆえに形だけで制度を導入すると、多くの場合は失敗に終わってしまうため注意が必要です。
目的・制度を設計する
目的の設定や制度設計も、成功を左右するポイントです。メンター制度において重要なステップであるため我流で行わず、場合によっては外部サービスを利用するなどして既存のノウハウを活用します。設定するのは、主に以下のような項目です。
- 目的
- メンタリングを実施する期間、頻度
- メンター・メンティーの選出方法
- メンタリングの実施方法、場所、時間
- 守秘義務などのルール
- メンター・メンティーへの研修内容
- 効果測定の指標(満足度・離職率、など)
関係者へ周知する
メンタリングを成功に導くには、周囲の協力が不可欠です。メンターを担当する従業員の上司・チームメイトには、制度の全体像や実施内容を理解してもらい、協力を仰ぎましょう。なお、理解を助けるためには口頭の説明だけではなく、メンタリングを模擬体験してもらうなども効果的です。
メンターを選出する
メンターの選出とメンティーとのマッチングには細心の注意を払います。メンターの選出方法には、応募、推薦、指名などがあるため、組織風土に合わせて選択しましょう。また、「4.メンターに適した人材|良いメンターとは?」で紹介した特徴も、選出する際のポイントになります。
メンターに教育を行う
メンターの教育には十分な時間をかけます。主に、以下のような研修を通して教育を行います。制度概要・ルールの説明:基礎知識として、制度の概要を説明する
- コミュニケーション技法の教育:「傾聴・受容・共感」といった基本的なコミュニケーションの技法を身につける
- コーチング力の教育:「傾聴・承認・質問」といった基本的なコーチングの技法を身につける
前提として、個人の知識量や資質には差があるため、研修を通して一定のノウハウを習得してもらいメンタリングの効果を引き上げます。
フォローアップする
メンタリングを成功に導くためには、メンターをサポートするフォローアップも重要です。
メンタリング期間の開始後は、定期的な研修や座談会を実施し、コミュニケーション技法やコーチング技法の復習、またメンターの不安解消を行います。メンターがいつでも相談できる体制を確保し、メンターには相談先を明確に伝えておきましょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード10.メンター制度 導入・運用チェックリスト
メンター制度の導入・運用する際、以下のチェックリストを活用してみてください。
【フェーズ1:制度の設計・準備】
□ 制度の目的やKPI(例:3年後の離職率を◯%改善)が明確に設定されている
□ 経営陣や関係部門の合意を得ている
□ 面談頻度、費用、守秘義務などの運用ルールが整っている
□ メンターの選定基準(例:入社3~7年目・他部署所属など)が明確
□ メンターの貢献を評価する仕組み(人事評価など)が設計されている
□ マッチング方法(性格診断やヒアリングなど)が決まっている
□ メンター・メンティー向けの研修プログラムが準備されている
□ 相性が合わない場合の相談窓口と対応フローが整っている
【フェーズ2:制度の実施・運用】
□ 制度の目的とルールが、社内でしっかり周知されている
□ メンター・メンティー双方に事前研修を行っている
□ メンタリング活動がスムーズにスタートできている
□ 人事部が定期的なモニタリング(ヒアリング等)を計画している
□ メンター同士が情報交換・相談できる場を設けている
【フェーズ3:評価・改善フェーズ】
□ 効果測定の方法(KPI計測、アンケートなど)が明確に定まっている
□ 効果測定とレポート作成を定期的に行っている
□ 測定結果をもとに改善策や次回の運用計画を立てている
□ 成功事例や感謝の声を収集し、社内で共有している
□ 制度が「形だけ」になっていないか、定期的にチェックしている
メンター制度の導入に関わる方と共有し、運用の質を高めていきましょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード11.メンター制度に関するよくある質問(Q&A)
Q1.メンター制度の効果はどう測定すればよいですか?
A.「定量的指標」と「定性的指標」の両面から評価するのが基本です。
【定量的指標】
| 指標 | 詳細 |
|---|---|
| 離職率・定着率 | メンター制度導入の前後や、対象者と非対象者で比較し、効果を数値で確認します。最も重視すべきKPIです。 |
| エンゲージメントサーベイのスコア | 「上司・同僚との関係性」「成長の実感」などの項目の変化を測ります。 |
| 1on1面談の実施率・満足度 | メンター制度が適切に機能しているかを確認する指標になります。 |
【定性的指標】
| 指標 | 詳細 |
|---|---|
| 満足度アンケート | メンター・メンティー双方に、制度への満足度や改善点をヒアリングします。 |
| 成功事例の収集 | 「メンターの支援でプロジェクトを成功させた」「メンティーの影響で資格を取得した」など、具体的な成果エピソードを集めて社内で共有します。 |
これらの指標を組み合わせることで、制度の「ROI(投資対効果)」を多面的に評価できます。
Q2.メンターとメンティーの相性が悪いときは?
A.最も大切なのは、問題を放置しないことです。
事前に「相性に課題がある場合は人事に相談できる」ことを、制度設計段階で明確に伝えておきましょう。これは能力の問題ではなく、より良い関係性を築くための前向きな対応です。
実際に相談があった際は、人事が双方から丁寧にヒアリングを行います。このとき、どちらかを責めるような対応は避けましょう。
改善が難しいと判断した場合は、速やかに再マッチングを行います。この迅速かつ丁寧な対応が、制度全体への信頼を支えるカギです。
Q3.メンターへのインセンティブは必要ですか?
A.絶対に必要とは言えませんが、「貢献を正しく評価する仕組み」があると制度は活性化します。
特に金銭的報酬よりも、評価やキャリアに繋がる形が効果的です。
具体的には以下のとおりです。
| インセンティブ | 詳細 |
| 人事評価に反映 | 「人材育成への貢献」などの項目を設定し、メンターとしての活動を正式に評価します。 |
| キャリアパスとの連動 | 将来の管理職候補には、メンター経験が有利になるよう制度設計します。 |
| 表彰制度の導入 | 成果を上げたメンターを「ベストメンター」として表彰し、全社で称賛します。 |
「メンター経験=自分の成長にもつながる」という内発的なモチベーションを促しつつ、会社としてもその貢献を正当に評価する姿勢が大切です。
Q4.リモートワーク中心でも、メンター制度は機能しますか?
A.はい。むしろリモート環境では、メンター制度の役割がより重要になります。
リモートワークでは雑談や部門間の交流が減るため、新入社員の孤立を防ぐ仕組みが不可欠です。
運用面での工夫として、以下の方法が効果的です。
| 方法 | 詳細 |
| 定期的なオンライン面談 | 月1回など、ビデオ会議で顔を合わせる時間を確保します。 |
| チャットツールの活用 | 日常の相談がしやすいよう、専用のチャットグループを用意します。 |
| 雑談タイムの意図的な設置 | 面談の冒頭数分を雑談にあてるなど、関係構築の工夫を取り入れます。 |
| オフライン交流の機会を設ける | 四半期に一度のランチ会など、可能な範囲で対面交流を実施するのも効果的です。 |
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

