人事のDX(HRDX)という言葉をご存じでしょうか? 働き方改革や新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、労働環境は大きく変わりつつあります。そこで注目を集めているのがHRDXです。この記事ではHRDXについて、メリットや関連する人事施策、DXの進め方、事例などをくわしく解説します。
1.そもそもDXとは?
DXとは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略語です。これは単なるデジタルツールの導入を指す言葉ではありません。デジタル技術とデータを活用して、ビジネスモデルや、組織、業務プロセス、企業文化そのものを根本から「変革」し、新たな価値を創出して競争上の優位性を確立するという、経営戦略レベルの取り組みを指します。
国内では、経済産業省が「企業の成長や競争力強化のためにデジタル技術を活用し、新たなビジネスモデルを創出、改革すること」とし、推進しています。
よく混同されがちなのが「デジタライゼーション」です。これはITを使って既存の業務を効率化することで、DXはさらにその先、ビジネスモデルそのものを変えていくことです。

【図解】DX(デジタルトランスフォーメーション)とは? 意味や推進など
近年、急激に注目を集めるDX(デジタルトランスフォーメーション)。ビジネスやプライベート問わず見聞きする言葉ですが、一方で「そもそもDXとは何なのか?」「具体的に何をすればいいのか」という声もよく聞か...
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.人事部門のDX(HRDX)とは?
最近では、人事部門でもDX(HRDX)への関心が高まっています。人事部門のDXには大きくふたつの考え方があります。
①業務負荷を減らし「考える時間」を生み出す
ひとつめは、ITツールを活用することで業務負荷を減らし、創造的な業務に時間を割けるようにすることです。紙やExcelを使用した、日々のルーティン業務に多くの時間を割いている人事部門も少なくありません。ITを活用し、業務効率化を図ることで、従業員と向き合う時間や、人事施策などを練る時間が確保できます。
②データを戦略人事に活かす
人事DXのもう一つの、そしてより重要な目的が、データを活用して「戦略人事」へと進化することです。戦略人事とは、従来のような労務管理や給与計算といった管理的業務(オペレーション)に留まらず、経営戦略と連動した人事戦略を立案・実行し、事業の成長に直接貢献する人事のあり方を指します。
具体的には、DXによって点在していた従業員一人ひとりのスキル、経歴、評価、研修履歴、さらにはエンゲージメントやキャリア志向といった多様な人事データが一元的に可視化されます。このデータを分析(ピープルアナリティクス)することで、以下のような戦略的な打ち手が可能です。
- 客観的データに基づく適材適所の人材配置
- ハイパフォーマーの特性分析と、その要素を組み込んだ採用・育成基準の策定
- 離職の予兆分析と、個別最適化されたリテンション施策の実行
- 将来の事業計画に必要な人材ポートフォリオの予測と、計画的な後継者育成
業務効率化と戦略人事は両輪であり、データ活用なくして戦略人事の実現はあり得ません。

ピープルアナリティクスとは? メリットや進め方、事例を解説
ピープルアナリティクスとは社員のデータを分析して組織の問題解決に導く手法のことです。ここではピープルアナリティクスが注目される理由や実施のメリット、活用するデータや課題などについて解説します。
1....
3.人事部門のDXがもたらす未来
人事部門のDXによって何が、どう変わるのでしょうか? 4つご紹介します。
①従業員の状況の可視化
DXによってあちこちに散らばった人事データが集約され、従業員一人ひとりの状況が可視化されます。紙やExcel、あるいはマネージャーのパソコン内などに散在している情報を、クラウドなどで一元管理します。そうすることで従業員のスキルや資格、過去の評価、現在のモチベーションなどあらゆる情報を、いつでも見ることが可能です。
②可視化・蓄積したデータをもとにした分析
データを蓄積し可視化したあとは、それを加工・編集しさまざまな分析ができます。たとえば、大きな成果をあげている従業員(ハイパフォーマー)の特性を分析できれば、人事評価やマネジメントに組み込めます。早期離職者の傾向を分析すれば、退職予備軍を事前に予測し、適切な対応をとることも可能です。
③最適な人材配置や人材採用の実現
勘や経験、あるいは一部の上司の主観に頼った人材配置は、ミスマッチや従業員の不満を生む温床です。人事DXは、人材配置に客観的なデータという「揺るぎない根拠」をもたらします。
例えば、タレントマネジメントシステムを活用すれば、従業員のスキルや、経験、過去の評価、キャリア志向、1on1の面談記録までを一元的に可視化できます。これにより、「このプロジェクトには、〇〇のスキルを持ち、過去に同様の課題解決経験があるAさんが最適だ」といった、データに基づいた最適な人材配置が可能です。
異動シミュレーション機能を活用すれば、配置後の組織パフォーマンスの変化を予測することも可能になります。
採用活動においても同様です。自社で高い成果を上げているハイパフォーマーたちの経歴、スキル、コンピテンシー(行動特性)を分析し、「活躍人材モデル」を定義します。
このモデルを基に採用基準を設定し、面接での評価項目に落とし込むことで、感覚的な「優秀そう」から脱却し、入社後に本当に活躍してくれる可能性の高い人材を見極める精度が飛躍的に向上するのです。結果として、採用のミスマッチが減少し、早期離職率の低下にも繋がります。
④従業員のワークエンゲージメント向上
DXによってデータ活用が進めば、従業員のワークエンゲージメントを高める効果も期待できます。データをエビデンスとした公平で納得感のある評価制度の整備は、そのひとつでしょう。年功序列や上司の主観による評価では、従業員の納得を得ることは難しくなってきています。評価にデータを加えることで信憑性が増し、公平性と納得感を高められます。
エンゲージメントサーベイを定期的に実施し、従業員のモチベーションを可視化すれば、モチベーションの下がっている従業員やチームに対して、フォロー面談なども実施可能です。
評価・目標設定の「添削・校正」はAIにお任せ。人事の約4割が注目する「生成AI仕事術」とプロンプト集をプレゼント⇒資料を無料ダウンロード4.DXを推進するための人事制度や評価制度とは?
DXを推進するには人事の観点からどのような仕組みが必要でしょうか? キーワードは「評価」「コミュニケーション」「働きやすさ」です。
①公平で納得感のある評価制度
DX時代の評価制度は、単に賞与や昇格を決めるためのものではなく、従業員の成長を促進し、組織全体のパフォーマンスを最大化するための戦略的ツールと位置づけられます。特にテレワークが普及した現代において、プロセスが見えにくい中での公平性の担保は喫緊の課題です。
人事DXは、この課題に対して「データの可視化」という明確な解決策を提示します。例えば、システム上に記録された目標(OKRなど)の進捗状況、同僚や部下からの360度フィードバック、プロジェクトへの貢献度といった定量・定性データを組み合わせることで、評価者の主観や印象に左右されにくい、エビデンスに基づいた評価が可能です。
これにより、従業員は「なぜこの評価なのか」を具体的に理解でき、評価に対する納得感が高まります。納得感のある評価は、従業員のエンゲージメントを向上させるだけでなく、「次は〇〇のスキルを伸ばそう」といった具体的な成長目標の設定にも繋がり、自律的なキャリア形成を促します。公平な評価制度の構築は、DX推進そのものへの求心力を高める上でも不可欠な要素です。
②従業員の情報を吸い上げ共有するための仕組み
人事におけるDXでは、従業員の情報や状況をいかに収集し、集約するかが大切です。とくに最近増えつつあるテレワークでは、従業員の顔が見えづらく、コミュニケーションの機会も減りがちです。オンラインの1on1ミーティングを実施し、従業員の課題や悩みをキャッチアップするなど、情報収集と共有の仕組みは不可欠といえるでしょう。
③選択可能な働き方
テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を整備することもDXには有効です。必要な人材を定義し採用できたとしても、活躍できる環境を整えなければ、取り組みも中途半端に終わるでしょう。地方の人材や子育て中の人材など、選択可能な働き方を整備することは、DXの効果を高めると同時に、企業の採用力を高めることにもつながります。
④複線型の柔軟なキャリアパス
ゼネラリストやスペシャリストなど、従業員のキャリアパスを柔軟にすることで、DXの効果をより高められます。たとえ従業員のニーズやスキルなどを可視化したとしても、単線型のキャリアパスしか描けない仕組みでは、その能力をフル活用できません。柔軟なキャリアパスが描ける仕組みを整えることで、データをもとにしたタレントマネジメントもしやすくなります。
管理職よりも待遇のよいスペシャリストなど、給与制度も柔軟にすれば、IT人材も確保しやすくなりさらにDXも推進できるでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
5.人事部門のDXにおける課題
DX推進の旗を掲げるのは簡単ですが、実行するにあたっては課題もあります。人事部門がDXを推進するにあたって直面する課題とは何でしょうか?
①あちこちに散在する人事データ
人事DXを始めようとした担当者の多くが、最初に直面するのがこの「データの壁」です。多くの場合、人事データは存在しないわけではありません。しかし、Excelの評価シートや、各部署で管理するスキルシート、紙で保管された履歴書、給与システム内の基本情報、現場マネージャーの頭の中にしかない面談記録など、組織の至る所にバラバラの形式で「散在」しています。
この状態では、データを横断的に分析してインサイトを得ることは不可能です。例えば、「どの部署の、どのようなスキルを持つ社員が離職しやすいのか」を分析しようにも、必要なデータが統合されていなければ手も足も出ません。
したがって、人事DXの第一歩は、これらの散在するデータを一元的に集約し、いつでも活用できる状態にするための「データ基盤」を構築することです。これは地道で労力のかかる作業ですが、この最初のハードルを越えなければ、その後のデータ分析や戦略立案は絵に描いた餅で終わってしまいます。まずは、どのようなデータがどこに、どのような形式で存在するのかを洗い出す「データの棚卸し」から始める必要があります。
②紙やExcelによる業務負荷
評価業務や採用業務など、紙やExcelで業務を行っているケースは少なくありません。とくに評価業務などは従業員数が多くなればなるほど、負荷も高くなります。ルーティン業務に時間をとられすぎていることが原因で、新しい仕組みや施策を検討する余裕がない場合は、業務負荷をどうやって減らせるかを検討する必要があります。
③既存システムが抱える技術的負債
「技術的負債」とは、長年の継ぎ足し開発やカスタマイズによって複雑化・ブラックボックス化した既存システム(レガシーシステム)が、新たな変革の足かせとなっている状態を指します。
人事部門においては、「特定の担当者しか仕様を理解していない給与計算システム」や「事業部ごとに独自に導入され、連携が不可能な複数の勤怠管理ツール」などが典型例です。これらのシステムは、日々の業務を回す上では問題ないように見えても、いざ全社的なデータ連携や新しいツールの導入を試みた際に、大きな障壁となります。
例えば、全社の人材データを分析しようとしても、古いシステムからデータを出力するだけで膨大な手間がかかったり、そもそも必要なデータが取り出せなかったりするケースは少なくありません。
経済産業省のDXレポートでも、この技術的負債がDX推進を阻む主要因であると指摘されており、放置すれば維持管理費の高騰や深刻なセキュリティリスクに繋がります。目先の業務に追われ、問題の先送りを続けるのではなく、将来の競争力確保のために、勇気を持って最新のプラットフォームへの移行を検討することが不可欠です。
④現場や経営トップとの温度差
DXの意義や効果などについて、経営層や事業部門などとギャップが生じてしまうこともあります。DXを推進するには、ITツールやサービスの導入、業務フローの刷新などコストや労力が必要です。コスト削減など明確な費用対効果が出しにくい場合もあるでしょう。現場の事業部門のなかには、変化するオペレーションに対し、ネガティブなイメージをもつ従業員もいるかもしれません。
「笛吹けども踊らず」ということわざがあるように、経営トップがいくら発信してもいざやるとなると、現場の理解が得られずなかなか進まないこともあるでしょう。これからの「あるべき姿」を共有し、目標として定めることが重要です。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード6.人事部門のDXを推進する5つのステップ
人事部門のDXを推進するには手順が大切です。闇雲に取り組んでもうまくいきません。ここでは人事部門のDXを推進する手順について、5つのステップに分けて解説します。
①DXの目的や目標を決め、共有する
人事DXの推進で多い失敗が、「ツールの導入」そのものが目的化してしまう「手段の目的化」です。これを避けるため、プロジェクトの最初に「なぜDXをやるのか?」「DXを通じて、3年後に会社と人事部をどのような状態にしたいのか?」という目的とビジョンを徹底的に議論し、言語化することが重要です。
「人事業務の工数を30%削減する」といった業務効率化の視点だけでなく、「データに基づいた人材配置により、新規事業部門の成功率を向上させる」「従業員エンゲージメントを10ポイント改善し、離職率を5%低下させる」といった、経営目標に直結する形で設定します。
設定した目的とビジョンは、経営層はもちろん、現場の従業員まで、あらゆるステークホルダーと共有し、納得感(コンセンサス)を形成する必要があります。なぜなら、人事DXは人事部だけで完結するものではなく、全社の協力が不可欠だからです。明確な旗印を掲げ、全員が同じ方向を向いて進むこと。これが、プロジェクトが迷走せず、推進力を維持するための絶対条件です。
②業務フローとデータの棚卸しを行う
DXを推進する際には、現状把握が重要です。現在の業務フローをあらためて整理し、業務で取り扱うデータの種類や介在するシステムなどを棚卸ししましょう。その際には、フローチャートなどにするとよりわかりやすく、共有もしやすくなります。あらかじめ定めた目標の実現にあたって、足りないデータがあるならば、明確にしておくと、ツールや仕組みを検討する際に活かせます。
③デジタル化する業務を特定する
現状の課題を洗い出したら、次にそれら全てに一度に着手しようとしないことが成功の鍵です。大規模な一斉導入は、現場の混乱を招き、予算的にも大きな負担となり、結果的に頓挫するリスクを高めます。
ここで重要になるのが、「スモールスタート」の原則です。まずは、以下の2つの軸で取り組むべき業務の優先順位を決定します。
| 軸 | 詳細 |
|---|---|
| 効果の大きさ | その業務をデジタル化した場合、コスト削減や工数削減、戦略的意思決定への貢献度がどれだけ大きいか。 |
| 実現可能性 | 導入コスト、期間、技術的な難易度、現場の協力が得やすいかなど、実現のしやすさ。 |
一般的には、「インパクトが大きく、かつ実現可能性も高い」領域から着手するのが定石です。例えば、「給与明細の電子化」や「勤怠管理システムの導入」は、多くの従業員が効果を実感しやすく、比較的導入のハードルも低いため、最初の成功体験を積むには最適です。
この小さな成功体験が、社内に「DXは我々にとって有益だ」という認識を広げ、より難易度の高い変革への推進力を生み出します。
④ITツールなどの仕組みを導入する
評価システムやタレントマネジメントシステムなど、DX推進に必要なITツールを選定し、導入しましょう。その際に局所最適に陥らないように、システムの要件定義をする必要があります。あとから機能を拡張できるか、幅広い業務に活用できる汎用的なプラットフォームかといった観点も重要です。
⑤必要であればツールにあわせて業務フローを変える
最新のITツールを導入しても、従来の紙やExcelを前提とした非効率な業務フローをそのまま踏襲していては、効果は半減してしまいます。例えば、「システム上で申請された内容を、わざわざ印刷してハンコをもらいに行く」といった運用では、何のためにツールを導入したのか分かりません。
真のDXは、ツールという「新しい乗り物」を手に入れることではなく、その乗り物に合わせて「道路(業務フロー)」自体を最適化することです。優れたクラウドサービスには、多くの場合、業界のベストプラクティス(最も効率的で優れた業務プロセス)が組み込まれています。
したがって、「自社のやり方に合わせてツールをカスタマイズする」のではなく、「ツールの標準機能に合わせて自社の業務フローを見直す」という発想の転換が求められます。もちろん、現場からは一時的な反発が起こるかもしれません。
しかし、長期的な視点で見れば、この変革こそが組織全体の生産性を飛躍的に向上させるのです。既存のやり方への固執は、DXにおける最大の「抵抗勢力」の一つだと認識する必要があります。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
7.人事DXの準備度チェックリスト
人事DXを成功させるには、自社の「現在地」を客観的に把握することが不可欠です。以下の20の質問に「はい」「いいえ」「どちらともいえない」で答えて、準備度を診断してみましょう。「はい」の数を数えてください。
【カテゴリー1:ビジョン・戦略】
- 経営戦略と連動した、人事DXの明確な目的(KGI/KPI)が設定されているか?
- 人事DXの目的とビジョンが、経営層から現場の従業員まで共有され、理解されているか?
- 人事DXが、単なるコスト削減ではなく、企業価値向上のための「投資」として認識されているか?
- 人事部門は、経営会議などで戦略的な意思決定に関与できているか?
- DX推進の責任者が明確に任命されており、必要な権限が与えられているか?
【カテゴリー2:データ・基盤】
- 従業員の基本情報、スキル、経歴、評価などのデータが、紙やExcelではなくデジタルで管理されているか?
- 散在している人事データが一元的に管理され、必要な時にすぐ取り出せる状態か?
- データ活用のための倫理規定やセキュリティポリシーが定められ、周知されているか?
- 長年利用している「技術的負債」となっているレガシーシステムは存在しないか?
- 導入している(または検討中の)システムは、他のシステムと連携(API連携など)が可能か?
【カテゴリー3:人材・組織文化】
- 経営層は、DX推進に対して強いリーダーシップとコミットメントを示しているか?
- 現場の従業員を巻き込み、意見を吸い上げる仕組み(ワークショップなど)があるか?
- 新しいことへの挑戦や、失敗から学ぶことを許容する文化があるか?
- 人事担当者は、データ分析の基礎的なスキルや知識を学ぶ意欲があるか?
- IT部門や他事業部と、円滑に連携できる関係性が築けているか?
【カテゴリー4:業務プロセス】
- 現状の人事業務フローが可視化され、課題が洗い出されているか?
- 多くの人手と時間を要している非効率な定型業務は存在しないか?
- 業務プロセスを、導入するツールに合わせて変革することに抵抗はないか?
- 従業員からの申請や手続きは、オンラインで完結するものが増えているか?
- 施策の効果を測定し、継続的に改善していくPDCAの仕組みが回っているか?
診断結果
「はい」が16個以上:準備万端!推進リーダーレベル
貴社は人事DXを推進する準備が十分に整っています。明確なビジョンと強力なリーダーシップのもと、ロードマップに沿って着実に実行していく段階です。さらなる高みを目指し、AI活用なども視野に入れましょう。
「はい」が10〜15個:準備はOK!実践レベル
DX推進の土台はできています。いくつかの課題はありますが、優先順位をつけて一つずつ解決していけば、大きな成果が期待できます。特に「いいえ」が多かったカテゴリーの壁を乗り越えることに注力しましょう。
「はい」が5〜9個:まだ準備段階!まずはスモールスタートから
DXの必要性は認識しつつも、具体的な準備はこれからのようです。焦って大規模な導入を進めるのは危険です。まずはインパクトの大きい業務の効率化など、小さな成功体験を積むことから始めましょう。
「はい」が4個以下:意識改革から始めよう
まずは、なぜDXが必要なのか、その目的とメリットを社内で共有し、意識を合わせることから始める必要があります。経営層や関連部署を巻き込み、危機感と期待感を醸成することが最初のステップです。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
8.カオナビの導入によって人事のDXを推進した成功事例
①ルーティン業務を効率化し「考える時間」を捻出|株式会社デンソー
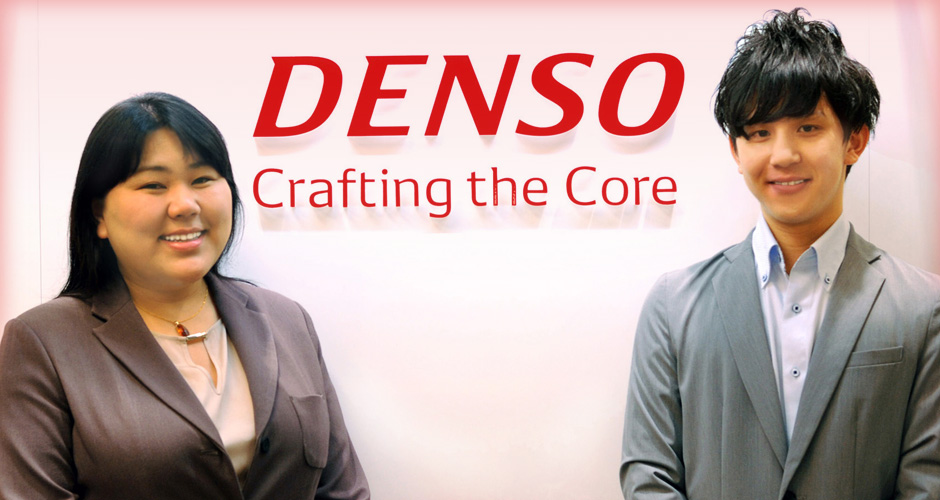
ルーティン業務を効率化し「考える時間」を捻出|株式会社デンソー
自動車部品メーカーとして時代の最先端を走り続ける株式会社デンソー。グループで約16万人の従業員を抱える同社は人材情報が事業部門などに散らばっており、評価などのルーティン業務に多くの時間を割いていました。業務を効率化し「より創造的な業務に時間を費やす」ことを目的に、人材データベースであるカオナビを導入しました。
課題
- 人材情報が散在しているため、ルーティン業務に多くの時間をとられていた
- ルーティン業務に時間をとられすぎ、「考える時間」を捻出できずにいた
成果
- 人材情報が一元化され、昇格会議においてもペーパーレスを実現
- 紙資料が減りルーティン業務を減らせたことで「考える時間」を捻出できた
②約2,000名の人事情報を一元化しタレントマネジメントに活用|サトーホールディングス株式会社
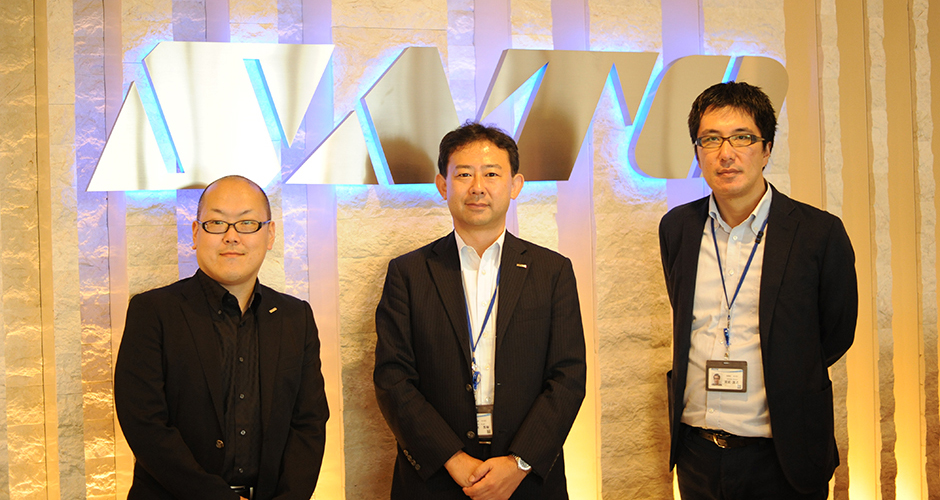
約2,000名の人事情報を一元化しタレントマネジメントに活用|サトーホールディングス株式会社
「自動認識ソリューション」で国内シェアナンバーワンを誇るサトーホールディングス株式会社。同社では中期経営計画における人材戦略ロードマップのひとつとして、タレントマネジメントへの注力を決定。しかしそのために必要な約2,000名の人事情報は国内の各拠点に散らばっていました。そこでカオナビを導入し、人材情報の一元化に取り組みました。
課題
- タレントマネジメントを推進するために必要な約2,000名の人事情報が拠点ごとなどに散在していた
- 散在した人事データを集約する作業が、現場にとって大きな負担となっていた
成果
- 人事で取得できる情報をすべてデータベースとして一元管理でき、業務を効率化できた
- 可視化したデータを次期役員候補の選出会議で活用、タレントマネジメントの第一歩を踏み出せた
③散在したデータを一元化し人事戦略に活用|フジッコ株式会社
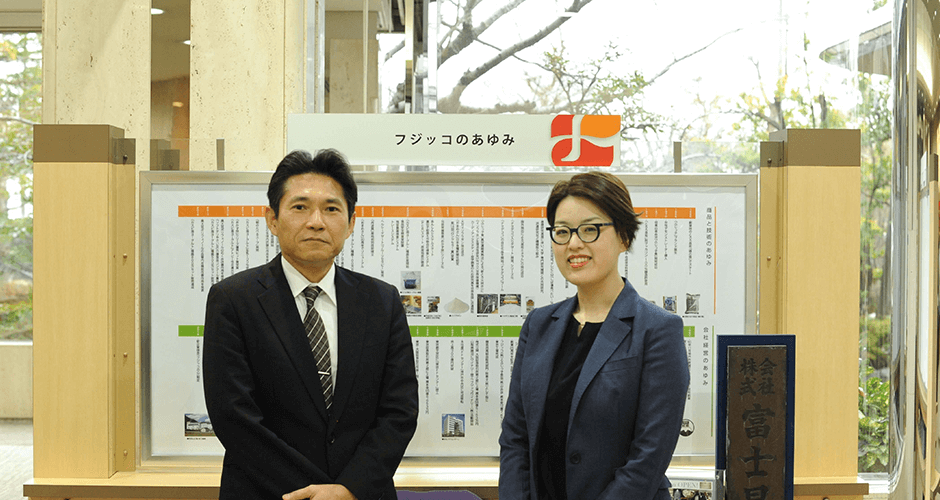
日本を代表する食品メーカーであり、2020年に創業60周年を迎えたフジッコ株式会社。従業員一人ひとりの能力をフル活用するため、抜本的な人事制度改革に取り組んでいます。しかし散在する人事データや、人事部門への問合せ業務の負担、紙やExcelを使った評価業務がそのための大きな障壁となっていました。そこで人事情報を一元管理すべく、人材データベース「カオナビ」を導入。人事改革への一里塚となりました。
課題
- 人事データが関係各所に散らばり、最新の人事データを施策に活かせずにいた
- 人事異動の際には人事部への問合せが急増、大きな業務負担に
- 紙やExcelの評価フローが現場と人事の両方の負担になっていた
成果
- 人事情報の一元管理を推進できた
- 使いやすいUIで人事部への問合せも減らせた
- 紙とExcelで行っていた評価業務を新たなフローへ、今後の工数削減を期待

【DX事例15選】国内・海外企業・自治体のDX推進・成功事例集
デジタル競争の激化、人材不足、コロナ禍などを背景に多くの企業が必要性を感じるDX(デジタルトランスフォーメーション)。しかし実際に取り組む企業は少なく、また適切にDXを推進できている企業はほんのひと握...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
9.人事DXに関するよくある質問(Q&A)
Q1.ツールを導入したのに、現場の社員がなかなか使ってくれません。どうすればいいですか?
A.よくある原因は以下の3つに分けられます。各原因に対して、効果的な対応策をまとめました。
| 原因 | 具体例 | 対応策 |
|---|---|---|
| 使い方が分からない | 初めて触るツールで、どこを操作すればよいか分からない | ・丁寧な研修会の実施 ・図解や動画を使った分かりやすいマニュアルの提供 |
| メリットを感じない | 「使っても仕事が楽にならない」「導入の意味が分からない」 | ・個別業務に即したメリットを明示する(例:「〇〇の作業が半分に短縮されます」など) |
| 面倒くさい(手間・負担が大きい) | 入力項目が多い、他システムとの連携がなく手動で入力が必要 | ・入力項目の最小化 ・他システムと連携し自動入力を実現 ・「使うのが楽」な設計 |
加えて重要なのは、上層部が率先して使うことです。経営層や部門長がツールを活用する姿勢を見せることで、現場にも浸透しやすくなります。
Q2.経営層から「ROI(投資対効果)はどうなっているんだ?」と言われています。どう説明すればいいですか?
A.まず、人事DXのROIは短期的な売上向上のような直接的な指標だけでは測れないことを率直に伝えましょう。その上で、以下の3つを伝えることが大切です。
| 分類 | 内容 | 説明の仕方 |
|---|---|---|
| ① 定量的効果 | ・業務効率化による工数削減 ・離職率の低下によるコスト削減 |
・「〇〇業務の年間工数 × 人件費」で試算 ・「採用・教育コストの軽減額」で試算 |
| ② 定性的効果 | ・従業員エンゲージメントの向上 ・意思決定のスピード向上 ・組織の柔軟性・対応力向上 |
・定量化しづらいが、長期的に大きな競争力強化につながる価値として説明 |
| ③ 投資としての視点 | ・DXは「コスト削減」ではなく「将来の競争力への投資」 | ・単年度での回収ではなく、中長期的視点での価値創出として捉えるように経営層と認識を共有することが重要 |
重要なのは、DXがコストではなく、未来の競争力を確保するための「投資」であるという視点を共有することです。
Q3.予算がほとんどありません。何から手をつければ良いですか?
A.予算がない場合、高価なツール導入は不可能です。しかし、やれることはあります。まずは「①意識改革」と「②既存ツールの徹底活用」から始めましょう。
全社で「データに基づき意思決定する」という意識を共有するだけでも大きな一歩です。
また、多くの企業がすでに導入しているMicrosoft 365やGoogle Workspaceには、アンケート作成(Forms)、データ分析(Excel/Spreadsheet)、業務自動化(Power Automate/Apps Script)などの機能が備わっています。
これらを最大限活用し、「手動でのデータ集計を自動化する」「簡単な従業員満足度調査を実施する」といった「ゼロ円DX」から始め、小さな成功を積み重ねて将来の予算獲得に繋げましょう。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)

