近年、多くの企業で導入が進んでいる1on1。部下の育成やエンゲージメント向上に効果的とされる一方で、現場では「正直、やめてほしい…」という声も聞かれます。
実際には、形だけの1on1が続いたり、上司のスキル不足や目的の不明確さから、かえって負担になったりしてしまうケースも少なくありません。
この記事では、1on1ミーティングの本来の目的や具体的なメリット・デメリットを整理し、「やめてほしい」と言われる背景を明らかにします。あわせて、時間のムダにならず効果が出る1on1の実践方法についても紹介します。
目次
1.1on1ミーティングとは?

1on1ミーティングとは、主に上司と部下が1対1で定期的に行う面談のことです。一般的には週に1回から月に1回程度の頻度で実施し、業務の進捗や課題に加えて、キャリアの悩みや私生活に関する話題まで幅広く話し合います。
最大の特徴は、評価や査定を目的としたものではなく、部下の成長やモチベーション向上を支援するための場である点です。テレワークなどによって対面コミュニケーションが減った現在では、柔軟な対話の機会を確保する場としても重要です。
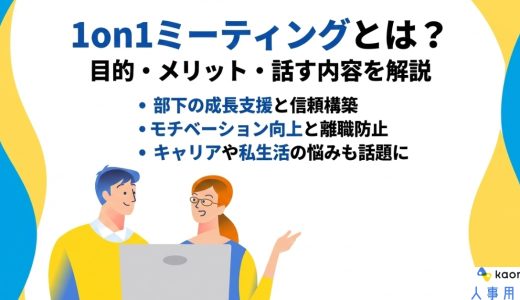
1on1とは? 目的や導入効果、面談との違いとやり方を簡単に解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入す...
1on1ミーティングの目的
1on1ミーティングの主な目的は、部下の成長を支援し、抱えている悩みや課題に早期に対応することです。上司が丁寧に話を聞けば、小さな兆候にも気づきやすくなり、問題への迅速な対応が可能になります。
また、一緒に課題の解決策を考えることで、上司は部下の気づきを促し、結果として部下の成長を後押しできます。
こうした継続的な対話は信頼関係を深め、仕事への前向きな姿勢を引き出すだけでなく、離職防止にも効果を発揮します。そのためには、上司と部下の間に相互理解と信頼が築かれていることが欠かせません。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.1on1ミーティングのメリット

1on1ミーティングには多くの利点があります。ここでは、その具体的な効果やメリットについて詳しく解説します。
- 上司と部下に信頼関係が生まれる
- 部下の心身の不調に早く気付ける
- 部下のモチベーションが向上する
- 人事評価への納得感が高まる
- 優秀な人材の離職を防げる
- 人材マネジメントコストを軽減できる
- 生産性がアップする
- 経営理念や企業文化が浸透する
- 部下の急な退職を防げる
①上司と部下に信頼関係が生まれる
1on1ミーティングの最大の特徴は、上司と部下が定期的に行う1対1の対話を通じて、信頼関係が築ける点です。普段の業務ではなかなか話す機会がない上司とも、時間をかけた対話によってお互いの考えや価値観を理解し合えます。
特に、上司が部下の話を落ち着いて聴く姿勢を持つことで、部下は「自分の気持ちを分かってくれている」と感じ、本音を話しやすくなるでしょう。
こうした信頼関係は、仕事での協力や相談のしやすさにもつながり、チーム全体の雰囲気を良くする効果も期待できます。
②部下の心身の不調に早く気付ける
近年、業務の負担やストレスが原因で、体調やメンタルに不調をきたす社員が増加しています。
1on1は、部下の様子を定期的に観察できる貴重な機会です。普段の業務中には気付きにくい小さな変化や悩みも、1対1の場なら気軽に話しやすくなります。
たとえば、表情が暗い、言動がいつもと違うといったサインに早く気付ければ、心身の不調やストレスの蓄積を早期に発見し、適切なフォローやサポートにつなげられます。
これにより、深刻な問題に発展する前に対処できるため、組織全体の健康管理にも役立ちます。
③部下のモチベーションが向上する
ロチェスター大学のエドワード・デシ教授が提唱した「内発的動機付け理論」では、以下の3つの欲求が満たされることで、人は自発的に意欲を高めるとされています。
- 他者とのつながり(関係性への欲求)
- 自分の力を発揮したいという気持ち(有能さへの欲求)
- 自ら選択・判断したいという思い(自律性への欲求)
1on1ミーティングでは、上司との対話を通じてこれらの欲求が自然と満たされるため、部下のやる気や仕事への前向きな姿勢が促進されます。

内発的動機付けとは?【外発的動機付けとの違い】具体例
内発的動機付けとは、自分自身の内側から生まれる動機付けのことです。ここでは内発的動機付けの具体例や外発的動機付けとの違い、活用するメリット、デメリットなどについて解説します。
1.内発的動機付けとは...
④人事評価への納得感が高まる
1on1は本来、人事評価を直接行う場ではありません。ただし、日ごろの1on1を通じて上司が部下の取り組みや努力の過程を把握しておくことで、人事評価の際に、その根拠を明確に説明できるようになります。
1on1の中で「なぜその評価になったのか」「どの点を評価しているのか」といった背景を丁寧に伝えられれば、部下の納得感が高まります。
さらに、部下が感じている評価に対する違和感や、上司との間にある認識のズレも、このような対話によって解消できるでしょう。
⑤優秀な人材の離職を防げる
優秀な人材ほど、仕事の悩みや不満を抱えたまま退職してしまうケースが少なくありません。1on1ミーティングを通じて、日頃から部下の声に耳を傾け、困りごとやキャリアの希望を把握しておくことで、早期にフォローや対策ができます。
特に、任せっきりになりがちな優秀な部下にも定期的に声をかけることで、早期離職のリスクを大幅に減らせるでしょう。
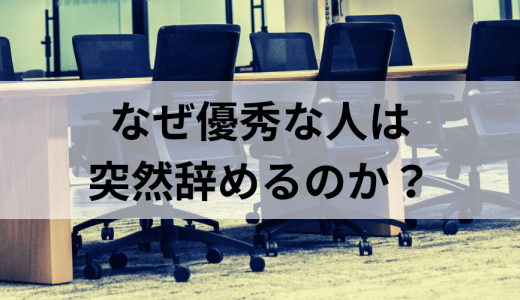
なぜ優秀な人は突然辞めるのか? 理由と対策、兆候やリスクを解説
優秀な人の離職は、企業にとって大きな損失です。しかし、優秀な人は需要が高く転職しやすいため、問題が改善されないと早期に辞める傾向にあります。
優秀な人が突然辞めることが多い企業は、その根本的な問題を解...
⑥人材マネジメントコストを軽減できる
定期的な1on1の実施によって、上司が伝えた内容以上の意図を部下が汲み取れるようになります。部下の成長が促進されることで、教育や指導にかかる時間も効率化され、マネジメント全体の負担が軽くなるでしょう。
また、報告・連絡・相談が日常的に行われると、現場で起こり得る問題にも早い段階で気づけます。こうした継続的なコミュニケーションが、業務トラブルの予防や対応の迅速化につながり、人材マネジメントにかかる手間やコストの軽減につながります。
⑦生産性がアップする
1on1ミーティングを取り入れると、組織全体と個人それぞれの生産性が高まります。上司と部下が1対1で対話を重ねることで、部下の性格や得意分野、抱えている課題などを深く把握できるからです。
その結果、個々に適した業務の割り振りや支援がしやすくなり、ミスや非効率な作業を削減できるでしょう。
また、こうした対話の積み重ねによって、部下自身が現状を振り返り、自律的に課題に取り組む習慣が育ちます。これにより、チーム全体のパフォーマンス向上も期待できます。
自分の仕事に主体的に関わる姿勢が強まることで、より高い成果を目指す意識が育まれるでしょう。
さらに、継続的なコミュニケーションは、心理的安全性の高い職場づくりにもつながります。
「意見が言いやすい」「失敗を恐れずに相談できる」といった雰囲気によって、アイデアや意見が活発になり、チーム全体の生産性を底上げする効果も見込めます。
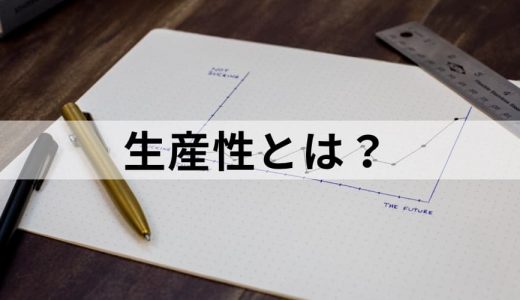
生産性とは? 意味や計算式、低い理由、向上の取り組みを簡単に
組織の生産性をあげるなら
人材情報を戦略的に活用できる「カオナビ」
⇒人事管理システム「カオナビ」の資料はこちらから
生産性を向上させるためには、単にオートメーション化するのではなく、社員の労働環境...
⑧経営理念や企業文化が浸透する
近年は、Z世代を中心とした若い社員の間で、給与や福利厚生だけでなく、SDGsへの取り組みや社会貢献といった企業の姿勢を重視する傾向が強まっています。
こうした価値観の変化を受けて、経営理念や行動指針など、企業文化の発信に力を入れる企業が増えてきました。
ただし、理念や指針は抽象的な表現になりやすく、日々の業務の中では社員に浸透しづらいのが実情です。
そこで効果的なのが1on1ミーティングです。上司が対話の中で「理念が仕事とどう関わっているのか」「会社が何を大切にしているのか」といった点をわかりやすく伝えれば、社員の理解が深まり、実際の行動にもつながりやすくなります。
一人ひとりの判断基準が明確になれば、迷わずに動けるようになり、結果として企業文化が自然に職場に根付いていくでしょう。
⑨部下の急な退職を防げる
突然の退職、いわゆる「びっくり退職」は、企業にとって大きな痛手です。人が辞めるたびに、新たな採用や育成に時間と費用がかかるだけでなく、離職の多さが企業イメージに悪影響を与え、採用活動にもマイナスの影響が出る恐れがあります。
こうした事態を防ぐためには、定期的な1on1ミーティングが効果的です。日常業務では見えづらい部下の不満や悩みを早い段階でキャッチできるため、必要に応じたフォローや職場環境の見直しが可能です。
特に、普段は言いづらい問題も1on1の場であれば話しやすく、退職の兆しにも気づけるかもしれません。つまり、1on1を通じて、突然の人材流出を防げる可能性が高まるのです。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.1on1ミーティングのデメリット
1on1ミーティングには、多くのメリットがある一方で、以下のデメリットもあります。
- 現場の負担が大きい
- 上司に高度なスキルが求められる
- 目的が曖昧で形骸化しやすい
- 効果が定量化しにくい
①現場の負担が大きい
1on1ミーティングは、上司・部下ともに定期的に時間を割く必要があり、その分現場の業務負担が増します。特にプレイングマネージャーのような自らも業務を抱えながら部下の管理も行う立場では、1on1の準備や実施に割く時間が重荷となります。
また、フォローアップのためにはさらなる時間とエネルギーが求められるため、業務が過密な部署では本来の仕事に支障が出る人も多いでしょう。
②上司に高度なスキルが求められる
効果的な1on1を実現するためには、上司に高い傾聴力やフィードバック力、質問力が必要です。しかし、こうしたスキルが十分でない場合、1on1が単なる雑談や一方的な説教の場になる恐れがあります。
上司のスキル不足によって、部下は「話しても意味がない」と感じることが増えます。結果的に部下の信頼を失ったり、育成機会が活かされなかったりする可能性があるため、上司への支援・訓練が不可欠です。
③目的が曖昧で形骸化しやすい
1on1ミーティングの目的や意義が明確でないまま導入されると、「何を話せばいいのか分からない」「話すことがない」という状態に陥りやすくなります。会話のネタが尽きると、ただの形式的なやり取りに終始してしまい、部下のやる気をそぐ原因にもなりかねません。
さらに、経営層と現場で1on1に対する理解や期待が一致していないケースも見られます。こうしたギャップがあると、現場では「意味がない」「ただの時間の浪費」と受け止められ、不満や反発を招く要因にもなります。
④効果が定量化しにくい
1on1ミーティングは部下の成長や信頼関係の構築といった「見えにくい成果」を目指すため、効果を数値で測るのが困難です。短期間で成果が見えづらいため、上司や組織としても「本当に意味があるのか」と疑問を感じやすく、継続が難しくなる場合があります。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード4.1on1ミーティングをやめてほしいと思う理由は?

近年、1on1ミーティングは多くの企業で導入されている一方で、「やめてほしい」などネガティブな声もあがっています。その背景には、コミュニケーションの非効率さや、準備や時間的な負担が大きい点が考えられます。
業務量が多く時間がない
業務に追われている現場では、1on1ミーティングの時間を確保すること自体が大きな負担です。特に、人手不足の部署や、締め切り間近の時期、プロジェクトの山場を迎えているときは、1on1の時間が本来の業務を圧迫します。
結果として、ミーティングの意義を感じられず、「やめてほしい」という声が上がる場合もあります。
目的がわからず話す内容がない
1on1の目的が上司・部下で共有されていないと、話す内容が見つからず、無駄な時間になる可能性があります。毎回同じ話を繰り返したり、特に話題がないまま時間が過ぎたりすると、「意味がない」と感じられ、双方にとって負担になりかねません。
その結果、「1on1はやめてほしい」と思われる原因になります。成長支援や課題の早期発見といった本来の1on1の目的を果たせなくなり、かえって逆効果になる恐れもあるのです。
強制される感覚がストレスになる
1on1の出席が強制的に感じられると、部下にとって大きなストレスになります。対話の中身よりも“やること自体”が目的になる場合、本来の意義が薄れる可能性があります。
さらに、ミーティングの頻度が多すぎたり、スケジュールに柔軟性がなかったりすると、「自分の仕事のリズムが崩れる」と感じる人も少なくありません。強制的な印象が強まれば、部下は萎縮して、1on1に対して「もうやめてほしい」と感じるでしょう。
上司のスキルや準備が不足している
1on1を意味のある時間にするためには、上司が適切な質問力や傾聴力、進行スキルを備えていることが必須です。もし上司にコミュニケーション能力や準備が不足していると、1on1は有意義な場になりません。
たとえば、前回話した内容を聞き返されたり、毎回同じ質問ばかりされたりすると、部下は「この時間は意味がない」と感じます。過去の会話内容を記録し、次回に活かすことは、1on1を継続するうえで最低限の工夫といえるでしょう。
上司の一方的な説教やアドバイスになる
本来、1on1ミーティングは部下を支えるための時間です。しかし、現実には上司からの一方的な指摘や説教、アドバイスばかりになるケースもあります。
こうした状況では、部下は「自分の意見を聞いてもらえない」と感じ、本音を話しづらくなります。その結果、ミーティングがかえってストレスの原因になり、不満につながる場合もあるでしょう。
また、上司が結論を急いで解決策を提示する姿勢も、圧迫感を強め、本来の1on1の意図からかけ離れてしまいます。
相性が合わないと避けたくなる
上司と部下の性格や価値観がかみ合わないと、1on1そのものが苦痛に感じられることがあります。信頼関係が十分に築けていない場合、プライベートな話題や悩みを打ち明けることに抵抗を感じ、ミーティングを避けたいと考える人もいます。
その結果、部下は1on1に対してネガティブな感情が強まるでしょう。
課題解決や人材育成につながっていない
1on1が実際の課題解決や人材育成に結びついていない場合、「何のためにやっているのか分からない」と感じる部下も多いです。
ミーティングの内容が具体的な成果や成長に反映されないと、形だけの取り組みと受け止められ、「やめてほしい」と思われる要因となるでしょう。その結果、部下のやる気が下がったり、不満を抱えたりする原因にもなります。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.時間のムダにしない効果がでる1on1ミーティングのやり方
1on1ミーティングを「やめてほしい」と感じさせず、実際に効果を生み出すためには、いくつかの工夫が必要です。ここでは、1on1を実りある時間にするために、特に意識しておきたい7つのポイントを紹介します。
- 明確な目標を設定し周知する
- アジェンダは部下主導で進める
- 心理的安全性を高める
- 1on1に必要なスキルを身に付ける
- 適切な頻度と時間配分を工夫する
- アクション・フォローアップを明確にする
- ツールを活用する
明確な目標を設定し周知する
1on1を意味のあるものにするには、目的の共有が不可欠です。上司と部下で事前に「なぜ1on1をやるのか」「何を達成したいのか」などの目標を設定することで、話題の無駄を減らせます。その結果、対話の質が向上するでしょう。
たとえば、成長支援や課題発見、キャリア相談など、目的を具体化しておくと、「ただ時間を過ごすだけ」と感じられるリスクが低くなります。
アジェンダは部下主導で進める
1on1のアジェンダは上司が決めるのではなく、部下が主体的にテーマや課題を設定します。部下が主役となることで「自分のための時間」という意識が生まれ、前向きな姿勢で臨めるようになります。
上司は聞き役に徹し、部下の話を引き出すことを意識しましょう。そうとはいえ、部下が毎回ゼロから話す内容を考えるのは大きな負担です。そこで、話題の方向性をあらかじめ3つの観点から整理しておくと、会話が進めやすくなります。
- 日々の業務や仕事上の課題に関すること
- 将来のキャリアや目標に関すること
- プライベートや価値観に関すること

1on1のアジェンダ一覧|話すことがないを回避する具体例
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
世界的なIT企業や革新的なベンチャー企業が集まるアメリカ・シリ...
心理的安全性を高める
率直な意見や悩みを安心して話せる雰囲気づくりが重要です。心理的安全性を高めるためには、次の取り組みが効果的です。
- 日頃から声かけや雑談を交わす習慣をつくる
- ミーティングの冒頭では、いきなり本題に入らず軽い会話で場を和ませる
- 上司自身も時には弱みや失敗談を共有する
- 社員が悩みや不安を抱えたときに、気軽に相談できる専用の窓口を社内に設置する
心理的安全性が高まると、部下が本音を話しやすくなり、建設的な対話が実現します。
1on1に必要なスキルを身に付ける
上司には傾聴力や共感力、質問力といったコミュニケーションスキルが求められます。部下の話を否定せずに受け止め、適切な質問で思考を深めるサポートができるよう、日頃からスキルを磨くことが大切です。
そのため、1on1ミーティングを導入する際には、上司向けに研修を実施し、効果的な進め方や必要なコミュニケーションスキルの習得を促すのも有効です。
適切な頻度と時間配分を工夫する
1on1は週1回、隔週、月1回など、業務状況に応じて無理のない頻度で実施しましょう。忙しい時期は30分など短時間でも構いません。オンラインの活用も有効です。
頻度や時間が多すぎると負担になりやすいため、現実的なスケジュールを組むことが継続のコツです。
アクション・フォローアップを明確にする
1on1ミーティングの最後には、話し合った内容をもとに具体的な行動に落とし込むことが重要です。次回までの目標や具体的なアクションを明確にし、その内容を記録に残しておきましょう。
そうすることで、次回の1on1で振り返ることができ、着実な成長や課題の解決につなげられます。
ツールを活用する
1on1ミーティングをスムーズに進めるには、専用のシートやツールを使うのがおすすめです。話した内容を整理しやすく、次回の振り返りにも役立ちます。
また、ツールの導入によって、ミーティングの準備や記録の手間が省け、上司・部下の負担を軽減できます。
カオナビが提供する「1on1ミーティングガイド」は、効果的な進め方や実践シートがまとめられており、現場での運用に役立つ資料です。無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してください。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード6.まとめ
1on1ミーティングは適切に活用できれば、コミュニケーションの活性化や部下の成長支援など多くのメリットがあります。しかし、場合によっては「やめてほしい」と感じる従業員もいます。その背景には、目的の曖昧さ、上司のスキル不足、現場への負担などが挙げられます。
1on1の目的を明確にし、適切な頻度や運用方法を工夫することで、デメリットを最小限に抑え、効果的な人材育成や組織活性化につなげることが可能です
もし「やめてほしい」という声が多い場合は、現場の声を丁寧に拾い上げ、運用方法の見直しや上司への研修、柔軟なスケジュール調整など、現実的な改善策を検討しましょう。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入すれば、1on1ミーティングの内容や社員情報を一括で管理でき、進行状況の把握や過去のやり取りの振り返りにも活用できます。1on1の質を高めたいと考える企業にとって、非常に心強いサポートツールといえるでしょう。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)

