目標管理(MBO・OKR)を効率化し、従業員エンゲージメント向上。
人事評価システム「カオナビ」で、部下の目標達成を充実サポート!
⇒
【公式】https://www.kanavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
「SMARTの法則」は、目標を具体的で達成可能な形に落とし込み、実行力を高めるためのフレームワークです。ビジネスシーンはもちろん、自己成長やキャリアを考えるうえでも役立つため、現在も多様な場面で活用されています。
この記事では、SMARTの各要素の意味や設定方法をわかりやすく解説します。営業、人事、マーケティングなどの部門別の具体例や、発展型フレームワーク、活用するメリットまで紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
1.SMARTの法則とは?

SMARTの法則は、目標を効果的に設定するためのフレームワークであり、ビジネスや自己成長の場面で広く活用されています。1981年にジョージ・T・ドラン氏によって提唱されて以来、世界中の企業や組織で定番の手法となっています。
SMARTの法則とは、目標の作り方のこと。SMARTとは、
- Specific:「具体的、分かりやすい」を意味
- Measurable:「計測可能、数字になっている」を意味
- Achievable:「同意して、達成可能な」を意味
- Relevant:「関連性」を意味
- Time-bound:「期限が明確、今日やる」を意味
それぞれの頭文字を取った言葉で、これら5つの要素は、目標を達成し成功をつかむための5因子とされているのです。
これらの基準を満たすことで、目標が曖昧にならず、達成に向けた具体的な行動計画を立てやすくなります。
【従業員の目標達成をサポートする機能が揃っています!】
人事担当者からマネージャー、従業員まですべての目標管理・評価業務を効率化するなら、人事評価システム「カオナビ」です!
●フィードバックに役立つ人材情報を把握できる
●目標進捗を一覧で確認できる
●1on1などの面談管理が簡単にできる
●従業員エンゲージメントを見える化できる
●MBOやOKRシートのテンプレートが利用できる
2.SMARTの法則による目標の立て方

ここでは、SMARTの法則の5つの要素を一つずつ詳しく解説します。効果的な目標を立てるには、それぞれの要素を正しく理解し、活用することが大切です。目標設定の際に押さえておきたいポイントを、5つの観点から順を追って見ていきましょう。
①Specific(具体性)
Specificは、英語で「明確な」「具体的な」といった意味を持つ言葉です。SMARTの法則では、誰が見ても理解できる明確な目標設定が求められます。
曖昧な表現では、何を達成すべきかが分からず、行動に移しにくくなります。具体例を参考にしながら、すぐに実行できる明確な目標を立てましょう。
Specificな目標の具体例
たとえば「売上を伸ばす」という目標では、誰が、どの程度伸ばすのか、どの商品やサービスで伸ばすのかが不明確です。
これに対し、以下のように設定すれば、目指すべきゴールが明確になり、日々の行動計画も立てやすくなります。
- 新入社員が既存顧客へのアップセル提案を行い、月間平均売上を15%アップさせる
- 第一営業部が新規顧客を20社獲得し、売上を100万円増加させる
- マーケティング担当者がWeb広告のコンバージョン率を1.5倍にして、月商300万円を達成する
具体的な目標があれば、関係者全員が同じ認識を共有できます。チームで協力して取り組む際にも効果的です。
②Measurable(測定可能性)
Measurableは、「測定可能な」「測定可能性」といった意味を持つ英単語です。SMARTの法則では、数値化できる目標設定が重要です。
数値や指標で進捗を確認できる目標にすることで、現時点での達成度や残された課題が把握しやすくなり、達成に向けた調整もスムーズに行えます。
Measurableな目標の具体例
たとえば「品質を向上させる」という抽象的な目標では評価が曖昧ですが、以下のように設定すれば、進捗や改善余地が明確になります。
- 商品出荷前の不良品率を、現状の5%から3%以下に削減する
- コールセンターへの品質に関するクレーム件数を、月20件から月10件未満に減らす
- 顧客満足度アンケートの平均スコアを、4.2点から4.5点以上に引き上げる
数値化により、仮に目標に届かなかった場合でも次の改善策が設計しやすくなります。また、PDCAのサイクルを回すためにも、数値で評価できる目標設定が重要です。
そうすることで、以下2点を客観的に振り返れます。
- 実際に行動を起こせたか
- その結果が目標にどれだけ貢献したか
③Achievable(達成可能性)
Achievableは、「実現できる」「到達可能な」などの意味を持つ英単語です。実現可能な範囲で目標を設定することを指します。
高すぎる目標は途中で挫折する原因となり、逆に簡単すぎると成長や達成感が得られにくくなります。過去の実績や現在のリソース、スキルなどを考慮し、努力すれば手が届くレベルの目標を立てましょう。
Achievableな目標の具体例
Achievableな目標は、人それぞれの現在の状況によって異なります。
たとえば、月に5社の新規顧客を獲得している人に対して、急に「来期は毎月20社」という高すぎる目標を課すことは、現実的ではありません。やる気を失ってしまう恐れもあります。
重要なのは、少し頑張れば届きそうなラインに設定することです。「来期は毎月7社を目指す」といった具合に、今より少し高い目標を掲げることで、達成感とやりがいの両方を得られます。
適度な挑戦を含んだ目標は、成長意欲を引き出し、継続的な成果にもつながるでしょう。
④Relevant(関連性)
Relevantは、「関連性がある」「適切な」といった意味を持つ英単語です。この要素は、目標が自分自身や組織のビジョン、方針、価値観と関連しているかを指します。
たとえ目標を達成できたとしても、会社やチームの方向性とずれていれば、全体の成果には結びつきません。一方で、組織の目的と結びついた目標であれば、メンバーのやる気や納得感も高まります。
Relevantな目標の具体例
たとえば、DX推進を目指す企業であれば、以下のような目標が考えられます。
- 今期中に業務で使うExcel資料をすべてクラウド対応へ切り替える
- DX人材の育成に向け、全従業員を対象としたITリテラシー研修を実施し、受講率95%以上を達成する
- マーケティングのデジタル化を促進するため、今期中にMA(マーケティングオートメーション)ツールを導入し、月間リード数を20%増加させる
目標を達成した結果、どのような成果が得られるのか(たとえば売上アップやスキルの向上など)を明確にすることで、「取り組む意味」がわかります。それにより、モチベーションが高まり、新たな目標達成につながりやすくなるでしょう。
⑤Time-bound(期限が明確)
Time-boundは、「期限が明確」「期限付き」といった意味を持つ英単語です。期限を明確に定めることは、目標達成に向けた行動を計画的に進めるうえで不可欠です。
期限が設定されていないと、行動が後回しになり、結果的に目標が未達成に終わることもあります。「今月の締め日まで」「3ヶ月後までに」「1年後のTOEIC試験まで」など、具体的な期限を設ければ、進捗管理がしやすくなり、集中力や達成意欲も高まります。
Time-boundな目標の具体例
ある企業では、従業員の残業時間の多さが課題となり、「業務効率化による働き方改革」を目標として掲げました。しかし、この目標には期限が設定されていませんでした。
業務改善に取り組む従業員は、期限が決まっていないと、いつまでに何をやるかが曖昧になり、実行までに時間がかかります。その結果、せっかくの取り組みもなかなか形にならない可能性があります。
- 今期中に業務改善提案制度を導入し、チームから10件以上の改善案を集めて実施に移す
- 今月末までに社内の定型業務マニュアルを10本作成し、業務の属人化を解消する
- 来月末までに業務フローを見直し、承認プロセスのステップを現状の5段階から3段階に簡素化する
このように、あらかじめ期限を決めておけば、そこから逆算してスケジュールを立てられ、スムーズに行動へ移せます。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.SMARTの法則に則った目標設定の方法とは?

SMARTの法則を活用した目標設定には、具体的にどのような方法があるのでしょうか。ここでは、それぞれの分野で役立つ具体的な目標例を紹介します。目標づくりのヒントとして参考にしてみてください。
経営の目標設定例
経営の目標は、会社全体を見据えて中長期のビジョンに沿った成果を目指すものです。ここでは、海外展開に関する目標を例として取り上げます。
| 大まかな目標 | 海外展開を強化する |
| Specific(具体性) | 新たにアジア圏の2か国に進出し、販路を拡大する |
| Measurable(測定可能性) | 売上の海外比率を現状の5%から10%に引き上げる |
| Achievable(達成可能性) | すでに現地での市場調査やパートナー企業との連携が進んでおり、販促体制の構築も現実的 |
| Relevant(関連性) | 中期経営計画におけるグローバル戦略の一環であり、会社の成長に直結する |
| Time-bound(期限が明確) | 次の年度末(2026年3月)までに達成を目指す |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 「2026年3月末までにアジア2か国へ新規進出し、海外売上比率を10%に引き上げる |
こうした目標は、各部門の役割に合わせて具体的なKPI(重要業績評価指標)に落とし込むことが大切です。
たとえば、製造部門では「海外需要に応えるため、稼働率を120%まで高める」、人事部門では「現地で20名の人材を採用する」、営業部門では「グローバルに対応可能な人材を10名育成する」などのように、部門ごとの目標を明確にします。
経営の方針を現場での具体的な行動につなげることで、全社一体となって成果を出せる体制が整います。
営業部門の目標設定例
営業部門では、数値目標を立てやすいのが特徴です。たとえば「新規顧客の開拓」という目標を例に考えてみましょう。
| 大まかな目標 | 新規顧客を開拓する |
| Specific(具体性) | 法人向けの新規顧客を開拓する |
| Measurable(測定可能性) | 次の四半期で15社の新規契約を獲得する |
| Achievable(達成可能性) | 現在月4〜5件の契約実績があるため、四半期で15社は現実的な水準 |
| Relevant(関連性) | 営業部の売上強化方針に沿っており、チーム全体のKPIにも貢献 |
| Time-bound(期限が明確) | 次の四半期内に達成 |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 次の四半期までに新規法人顧客15社と契約を締結する |
上記目標は、何を・どれだけ・いつまでに達成するかが明確で、進捗も数値で可視化できます。過去の実績をもとに現実的なラインで設定されているため、達成できる見込みも十分あります。
さらに、インセンティブや昇進などの評価制度と結びつけることで、従業員のやる気を引き出す効果も期待できるでしょう。
総務部門の目標設定例
総務部門は、バックオフィスの役割を担うため、定性的な目標になりがちです。しかし、組織全体の運営効率や職場環境の改善といった視点を持ち、業務の効率化やコスト削減に注目すれば、数値を用いた具体的な目標設定が可能になります。
ここでは、総務部が取り組む「オフィスのランニングコスト削減」に関して、SMARTの法則を用いた目標例を紹介します。
| 大まかな目標 | オフィスランニングコストを削減する |
| Specific(具体性) | 削減対象を「オフィスのランニングコスト」と明確にし、電気代・通信費・備品費などの継続的な経費に焦点を当てる |
| Measurable(測定可能性) | 前年の実績と比較して、合計コストを10%削減する |
| Achievable(達成可能性) | 契約内容の見直しや使用状況の最適化、ペーパーレス化などの対策によって、十分に実現可能な範囲である |
| Relevant(関連性) | 全社的な経費削減や利益率向上の方針に合致しており、総務部門としての役割とも一致している |
| Time-bound(期限が明確) | 来年度末(2026年3月末)までに削減の達成を目指す |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 2026年3月末までに、オフィスのランニングコストを前年対比で10%削減する |
総務部門の目標が過度になると、他部門との摩擦を生み、かえって業務全体の効率を損なう恐れがあります。そのため、自社の状況を正確に把握したうえで、実現可能な範囲で目標を立てることがポイントです。
人事部門の目標設定例
人事部門では、採用活動や人材育成、働き方の見直しなどが中心的な取り組みになります。
たとえば「有給休暇の取得率を向上させる」といった課題も、人事の重要なテーマの一つです。これを効果的に達成するには、SMARTの法則を使って具体的な目標を設定するとよいでしょう。
| 大まかな目標 | 有給休暇の取得率を上げる |
| Specific(具体性) | 「有給休暇の取得率を上げる」という具体的な行動目標を設定している |
| Measurable(測定可能性) | 有給休暇取得率85%を目指す |
| Achievable(達成可能性) | 前年度の取得率は70%だったが、社内制度の見直しや取得推奨キャンペーンなどを実施しており、無理のない改善目標といえる |
| Relevant(関連性) | 従業員の健康管理やワークライフバランスの推進といった組織方針に合致しており、離職防止や満足度向上にもつながる |
| Time-bound(期限が明確) | 今年度末までに達成を目指す |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 今年度末までに、全従業員の有給休暇取得率を85%以上に引き上げる |
人事は人を対象とするため予測が難しい側面があります。そのため、目標を実現するには、あらかじめ達成までの具体的な手順や対策を考えておくことが大切です。
マーケティング部門の目標設定例
マーケティング部門では、集客やブランド認知度向上などが目標となります。ただし、指標の種類が多いため、組織としての方針を明確にしたうえで、優先すべき項目を選び、目標を設定することが重要です。
ここでは、「サービスの認知度向上」におけるマーケティング部門のSMARTの法則を活用した目標例を紹介します。
| 大まかな目標 | サービスの認知度を向上させる |
| Specific(具体性) | Instagramを活用し、サービスに関する情報発信を強化する |
| Measurable(測定可能性) | Instagramから自社ECサイトへの流入数を1.5倍に増やす |
| Achievable(達成可能性) | 過去の投稿分析により、Instagramは自社商品との相性が良く、一定の反応が得られている 投稿頻度や内容の改善でさらに成果が見込める SNS運用チームも社内に整備されている |
| Relevant(関連性) | ブランド認知の拡大と新規顧客の獲得は、マーケティング戦略の重要な柱であり、売上向上にも直結する |
| Time-bound(期限が明確) | 2025年12月末までに達成を目指す |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 2025年12月末までに、Instagramから自社ECサイトへの流入数を1.5倍に増やす |
サービスの認知度を高める方法としては、以下が挙げられます。
- オウンドメディアでの情報発信の強化
- Web広告の活用
- インフルエンサーによるプロモーション
ただし、やみくもに手法を選ぶのではなく、過去の実績データをもとに、効果が見込める施策や注力すべき媒体を見極めたうえで、目標を設定するとよいでしょう。
技術部門の目標設定例
技術部門では、作業の効率化や製品の品質向上、安全対策の強化などが主な課題となります。今回は「不良品率を下げる」というテーマをもとに、SMARTの法則を使った技術部門での目標設定の例を紹介します。
| 大まかな目標 | 不良品率を下げる |
| Specific(具体性) | 製造ラインAで発生している出荷前検査の不良品を対象に、工程ごとのチェック体制と作業手順を見直し、不良品率を下げる |
| Measurable(測定可能性) | 現在の不良品率1.8%を、1.0%以下に減らす |
| Achievable(達成可能性) | 過去の改善実績や、すでに進めている標準化・作業教育の強化施策により、十分に達成可能な範囲である |
| Relevant(関連性) | 製品品質の向上は顧客満足度やブランド信頼に直結し、部門だけでなく企業全体の目標と一致している |
| Time-bound(期限が明確) | 2025年12月末までの達成を目指す |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 2025年12月末までに、製造ラインAの不良品率を1.8%から1.0%以下に削減する |
このように、対象と期限が明確になることで、どの作業を優先すべきか判断しやすくなるでしょう。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.SMARTの法則の発展型3例

SMARTの法則は、さまざまな目標設定において高い効果を発揮しますが、近年ではこの考え方をさらに発展させた新たなフレームワークも登場しています。では、その進化版SMARTの法則とはどのような内容なのでしょうか。詳しく解説しましょう。
- SMARTER
- SMARTTA
- SMARRT
①SMARTER
SMARTERは、従来のSMARTの法則に以下の2つの要素を加えた発展型です。
- Evaluated(評価されていること)
- Recognized(承認されていること)
まず、SMARTの5要素(具体性・測定可能性・達成可能性・関連性・期限が明確)を満たしたうえで、その目標が上司などから適切に評価され、正式に認められているかどうかを重視します。
上司や同僚からの評価や承認を受けることで、目標への取り組みが現実味を帯び、モチベーションの維持にもつながります。
また、目標設定の時点で上司と方向性をすり合わせておくことで、組織の方針とズレのない目標となり、より精度の高い人材育成や人事評価にもつなげられるでしょう。
②SMARTTA
SMARTTAは、SMARTに以下の2つの要素を加えたモデルです。
- Trackable(追跡可能な)
- Agreed(合意された)
Trackableとは、目標に向けたこれまでの行動や進捗を正しく確認できる状態を指します。状況を振り返ることで、今どこまで達成できているのか、これから何をすべきかが明確になり、次のステップに迷いがなくなります。
Agreedは、関係者間で目標内容に対する共通認識があるかどうかを示す要素です。個人が勝手に目標を立てるだけでは、チーム全体の成果につながりません。
この観点を取り入れることで、目標がチーム全体に共有され、方向性を一致させながら行動できます。その結果、協力体制が強まり、全員で目標を達成しようとする一体感も生まれます。
③SMARRT
SMARRTは、SMARTに「Realistic(現実的な)」を加えた発展形です。Achievable(達成可能)と意味が重なる部分も多く、SMARRTではこの2つの要素をほぼ同じものとして扱っても差し支えありません。
あえて似た視点を加えることで、実行可能性に対する意識がより強まり、現実に即した具体的な目標が立てられます。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
5.SMARTの法則を用いた目標設定のメリット

企業が目標を設定するのは、それが計画の妥当性や成果を評価する基準になるからです。事業の成功は、ただ何となく進めた結果得られるものではなく、明確に立てられた戦略や計画に基づいて行動した結果として現れます。
SMARTの法則を用いた明確な目標設定によって、その計画が実際に効果を発揮したかどうかを客観的に確認でき、企業活動の振り返りや改善にも役立ちます。ここでは、SMARTの法則を用いて目標設定をするメリットを具体的に確認しましょう。
業務改善・成果創出につながる
SMARTの法則にもとづいた目標、つまり「具体的・数値化・現実性・整合性・期限」という要素を含む目標は、仕事を計画的かつ効率よく進めるための基盤です。
たとえば「月末までに不良品率を○%以下に抑える」といったように、期限と数値を明確に設定することで、週ごとの進捗確認や問題発生時の早期対応が容易になります。
目標がはっきりしていると、やるべき行動に集中できるため、全体の生産性向上にもつながります。
SMARTの法則が業務改善・成果創出に貢献する仕組み

SMART目標は、PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)の流れと非常に相性が良く、業務改善を効率的に進めるための指針になります。
「Specific(具体性)」を意識することで、「誰が・何を・どうやって行うか」が明確になり、無駄な作業を防げます。
「Measurable(測定可能性)」は進捗や成果を数値で定量的に把握できるため、達成状況を客観的に評価しやすくなるでしょう。「Achievable(達成可能性)」によって、現実的な範囲を検討でき、無理のない改善活動が可能です。
「Relevant(関連性)」があると、個人やチームの目標が組織全体の方向性と一致し、一体感が生まれます。そして「Time-bound(期限の明確化)」によって、計画的に実行でき、改善のサイクルを素早く回せます。
こうして小さな成功と振り返りを繰り返すことで、改善意識が組織文化として根付き、結果として業務効率や成果への貢献も加速度的に高まります。
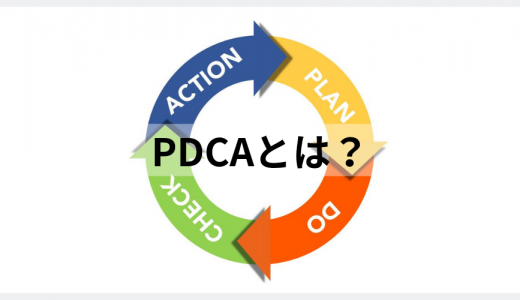
PDCAとは?PDCAサイクルはもう古い?意味やOODAとの違いを解説
目標の進捗確認や振り返りをもっと簡単に!
カオナビなら、全社員の目標や進捗を管理できるからPDCAの運用も効率化できます。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPD...
公平な評価が可能になる
SMARTの法則で設定された目標は、測定可能な数値や期限が明確に定義されているため、評価基準が曖昧になりません。「何をどの程度達成したか」がわかりやすく、個人やチームの成果を客観的かつ公平に評価できます。
評価の透明性が高まることで、従業員も納得しやすくなり、人事考課の信頼性も向上します。

評価基準とは?【作り方をわかりやすく】目的、項目の具体例
評価基準とは評価するための水準であり、公平かつ客観的な評価を行ううえで重要な指標です。人事評価への不満は優秀人材の離職の原因ともなり、最悪のケースでは業績不調を招く恐れもあります。
今回は、評価基準と...
従業員のモチベーションが向上する

SMARTの法則にもとづいた目標は、達成すべき内容が明確なため、従業員は自分が何をすれば良いのかを理解しやすくなります。進捗や成果が目に見える形で把握でき、達成感や成長実感を得やすく、モチベーションの維持・向上につながります。
さらに、期限の設定によって、計画的に行動できます。目標達成時には大きな満足感も得られるでしょう。

モチベーションアップの方法は? 要素、理論、名言などを紹介
従業員のモチベーションを可視化し、不満や離職の原因を明らかに。
人材管理システム「カオナビ」で、従業員のエンゲージメントを向上!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...
チームワークが強化される
SMARTの法則にもとづいて目標を設定すると、チーム全体で目指す方向性を共有できます。
各自の役割や連携体制が明確になるため、メンバー同士が協力しながら同じゴールに向かって進むことができ、自然とコミュニケーションも活発になります。その結果、チームに一体感が生まれ、パフォーマンスの向上や組織全体の成果アップにもつながるでしょう。

チームワークとは? メリットや高める方法、必要なスキルを簡単に解説
組織活動において、チームワークは欠かせない要素です。複数人で構成される部署やプロジェクトチームでは、独創的な個人プレーだけが先行してしまうと組織としての方向性を見失ってしまうこともあります。
チーム...
自己成長やキャリアアップにつながる
SMARTの法則は日々の業務だけでなく、個人の成長やキャリア設計にも有効なフレームワークです。具体的な目標を持つことで、自身がどのようなスキルや経験を積むべきかが明確になり、計画的なキャリアアップが可能です。
また、現実的な目標設定は、無理なく着実にステップアップするための指針となり、長期的なキャリア形成にも役立ちます。
さらに、目標達成のための行動を積み重ねることで、自己管理能力や課題解決力も養われ、将来のキャリアパスを主体的に描けるようになるでしょう。

キャリアパスとは? 意味や書き方、具体例、制度のメリット、導入手順を解説
キャリアパスを設定するには、タレントマネジメントが必須です!
タレントマネジメントの基礎知識や、やり方をわかりやすく解説。
⇒ タレントマネジメントシステム解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.提唱者:ジョージ・T・ドラン(George T. Doran)の考え

SMARTの法則は、ジョージ・T・ドランが1981年に提唱したものです。ドラン氏は当時、Washington Water Power Companyのコンサルタントや企業計画担当ディレクターとして活動していました。
経営者や管理職が目標を効果的に設定し、組織の成果につなげるための実践的な手法として、このフレームワークを発表しました。
「There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives」

ドラン氏が『Management Review』誌に発表した論文「There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives」では、目標設定の重要性とともに、SMARTの各要素がなぜ必要なのかを解説し、従来の曖昧な目標設定から脱却するための指針を示しています。
興味深いのは、当初のSMARTの法則は必ずしも5つ全てを厳密に満たす必要はなく、状況や目的に応じて柔軟に活用することが推奨されていた点です。
つまり、現場の実態や経営環境を踏まえたうえで、最適な目標設定を目指す考え方が根底にありました。
提唱後の普及とさまざまな改良
ドラン氏の提唱後、SMARTの法則は世界中で広く認知され、多くの経営コンサルタントや著名人によってさまざまな改良やバリエーションが生まれました。
一方で、「柔軟性が不足している」「長期的な目標には不向き」といった指摘もあり、目標追求の行動が創造性を阻害する可能性を懸念する声も出ています。
こうした批判や議論を経ながらも、SMARTの法則は現在も多くの企業や組織で、目標達成のための有効なフレームワークとして活用され続けています。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
7.SMARTの法則のQ&A
ここでは、SMARTの法則に関するよくあるQ&Aを紹介します。
Q1. SMARTの法則とは何ですか?
SMARTの法則は、目標設定を効果的に行うためのフレームワークです。
Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)の5つの要素の頭文字を取って、SMART(スマート)の法則と呼びます。
5つの要素を満たすことで、目標の明確化と実現性を高めます。
Q2. SMARTの法則で目標設定はどうやるの?
まず、目標を具体的(Specific)に設定します。曖昧な表現ではなく、「何を達成するのか」が明確であることが大切です。
次に数値などで進捗や成果を測定できるよう(Measurable)に指標を盛り込みましょう。そのうえで、設定した目標が現実的に実現可能か(Achievable)を確認します。
また、「目標達成の先にどのような成果や価値があるのか」「その目標は何の目的のために設定するのか」といった、目標の意義や方向性(Relevant)を見極めます。さいごに、期限(Time-bound)を明確にし、いつまでに達成するかを設定します。
これら5つの要素を意識することで、計画的に実行でき、成果を客観的に評価できる目標設定が可能です。
Q3. SMARTの法則のメリットとは?
SMARTの法則の活用によって、目標が具体的かつ明確になり、行動計画を立てやすくなります。数値で進捗を管理できるため、成果の評価も公平に行えます。
現実的で達成可能な目標は途中で挫折しにくく、モチベーション維持にも効果的です。
また、組織全体で目標を共有することでチームワークが強化され、業務改善や成果向上にもつながります。結果として、個人の成長も促されるのが大きなメリットです。
Q4. SMARTの法則で目標を立てる際の注意点は?
SMARTの法則は目標設定に役立つ一方で、使い方には注意が必要です。
まず、具体性(Specific)にこだわりすぎると、短期的な成果ばかりを追い求めてしまい、顧客との信頼構築や創造性の向上といった抽象的だが重要な要素を見落とす恐れがあります。
また、達成可能性(Achievable)を重視しすぎると、無難な目標ばかりになり、挑戦による成長の機会が失われるリスクも考えられます。
これを防ぐには、ストレッチ目標を取り入れる工夫が有効です。さらに、SMARTは短期目標に偏りやすいため、中長期的なビジョンや組織の未来像を意識したバランスの取れた目標設定が重要です。柔軟な発想と長期的視点を忘れず、活用しましょう。
Q5. SMARTの法則は時代遅れですか?
近年、変化の激しいビジネス環境にはSMARTの法則が合わなくなってきたという意見も見られます。しかし実際には、現在も多くの企業や組織で、スタンダードな目標設定手法として使われています。
さらに最近では、SMARTERなどの応用型も登場し、実務で使いやすい形に進化しています。
大切なのは、時代や状況に合わせて柔軟に使いこなすことです。そうすれば、SMARTの法則は今後も有効な目標設定の手法として役立てられるでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード8.まとめ
SMARTの法則は、目標設定を確実に成果へと結びつけるための有効なフレームワークです。Specific(具体性)、Measurable(測定可能性)、Achievable(達成可能性)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限が明確)の5つの視点を取り入れることで、誰にでもわかりやすく実行しやすい目標が立てられます。
このような目標は、業務の優先順位付けや進捗の把握に役立ち、成果の最大化にもつながります。目標設定に迷ったときは、ぜひSMARTの5つの視点を意識してください。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」は、こうしたSMART目標の設定から評価、育成までを一元管理でき、目標達成を効率的に支援します。従業員の目標管理を強化し、戦略的な人材育成を行いたい企業に最適です。
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

