業務委託契約とは、業務の一部を企業や個人に委託する場合に締結する契約形態です。一般的な雇用契約とは異なる点も多く、業務委託契約には別途専用の契約書が必要となります。
今回は業務委託契約について、契約の種類や雇用契約との違い、契約書の記載事項や締結の流れなどをわかりやすく解説します。
目次
1.業務委託契約とは?
業務委託契約とは、企業が業務の一部を外部の企業や個人に委託する際に締結する契約形態のことです。雇用関係にはならず、業務の一部のみ委託する場合に締結します。
一般的な雇用契約とは異なり、対等な立場で委託された業務を遂行します。指揮命令権がない形で業務を遂行するため、業務の進め方や時間は委託された側の自由です。業務委託契約には、主に下記2種類の契約形態があります。
請負契約
請負契約とは、業務委託契約の1つであり、民法632条に規定のある成果物に対して報酬を支払うという契約形態です。仕事の完成を目的とした契約であり、成果物を完成させて納品できたかのみ問われるため、成果物を完成させるにあたってどのような業務を行ったか、どれくらい働いたかは問われません。
以下のような職種は、請負契約を結ぶことが多いです。
- デザイナー
- プログラマー
- ライター
- コンサルタント など

請負契約とは? 業務委託や準委任契約との違いをわかりやすく
業務を外部に委託する際には、業務内容に応じて、「請負契約」と「委任契約」のどちらかを結ぶ必要があります。よく似ている二つの契約であるものの、これらの違いを理解して適切な契約形態を選択することが重要で...
委任契約・準委任契約
業務の遂行に対して報酬を支払う契約です。民法643条に規定されている委任契約は法律行為を扱う業務遂行、民法656条に規定されている準委任契約は法律行為でない業務遂行に伴う契約形態です。
以下のような職種が委任契約・準委任契約に該当します。
| 委任契約 | ・医師 ・弁護士 ・不動産仲介業 など |
| 準委任契約 | ・研究・調査業務 ・エステティシャン ・美容師 ・受付 ・事務 など |
委任契約に該当する職種は専門性が高く、多くは国家資格が必要な仕事です。

準委任契約とは? 請負契約などとの違い、契約書や印紙を解説
準委任契約とは、法律行為を取り扱う通常の委任契約とは違い、民法第656条や第第643条によって「法律行為以外の事務の処理を受任者に委任すること」と規定されています。
また受任者に業務遂行の裁量が任され...
2.業務委託契約と雇用契約の違い
業務委託契約と雇用契約の大きな違いは、指揮命令権の有無です。業務委託契約に指揮命令権はありません。
雇用契約では使用者である企業側に指揮命令権があるため、業務内容や就業時間、業務の進め方について具体的に指示できます。対して、業務委託契約では委託する側に指揮命令権がないため、雇用契約者と同じように具体的な指示はできません。
また、業務委託契約では成果物や業務の遂行といった明確な対価に対して報酬が発生しますが、雇用契約では労働力に対して報酬が発生します。業務委託契約は、報酬の対価が明確である点が特徴です。
3.業務委託契約の種類
業務委託契約には、報酬形態別に3種類の契約形態があります。各契約形態を詳しくみていきます。
毎月定額型
毎月定額型は、継続的に委託する業務に対して毎月一定額の報酬が支払われる契約です。
| メリット | ・月額固定でコスト管理しやすい ・委託者・受託者の双方が収支予測をたてやすい |
| デメリット | ・報酬の変動がなく受託者のモチベーションが低下するリスクがある |
毎月定額型での契約になることが多い代表的なものが、顧問契約です。また、警備や清掃、機械保守など、毎月継続的に一定の業務を委託する場合も毎月定額型の契約となるケースが多いです。
成果報酬型
成果報酬型は、業務の成果に応じて報酬有無や額が決まる契約です。
| メリット | ・委託量に応じて支出をコントロールできる |
| デメリット | ・成果が多いほど支出が増える ・受託者は収支が安定しにくい ・やった分だけ報酬が受け取れるためモチベーションが上がりやすい |
たとえば、営業であれば受注獲得件数、ライターであればコンテンツの納品数や対応数によって報酬額が決まります。なかには、売上や利益に応じて報酬が決まる店舗運営業務などもあります。
単発業務型
単発業務型は、1回の業務に対してあらかじめ決められた報酬を支払う契約です。
| メリット | ・支出のコントロールがしやすい ・成果に対する報酬が明確 |
| デメリット | ・受託者は収入の安定性に欠ける |
継続的な委託を前提とせず、単発で業務を委託する場合は単発業務型となります。システム開発や建築設計、Webデザインやライティング業務などの契約に用いられることが多い契約形態です。
4.業務委託契約のメリット
業務委託契約は、委託する側・される側にそれぞれ下記のようなメリットがあります。
| 委託する側 | ・ニーズに応じて業務を委託できる ・外部の専門的な人材やノウハウが活用できる ・人件費を抑えられる |
| 委託される側 | ・自由度の高い働き方ができる ・収入アップが目指しやすい ・人間関係の悩みが生じにくい |
それぞれのメリットを詳しくみていきます。
委託する側
委託する側のメリットは、以下3つです。
- ニーズに応じて業務を委託できる
- 外部の専門的な人材やノウハウが活用できる
- 人件費を抑えられる
ニーズに応じて業務を委託できる
繁忙期で人手が足りない時期のみ単発で委託するなど、必要な時に必要な分だけ業務を発注できます。業務委託契約では最低賃金や解雇など、労働法に関する規制が適用されないため、柔軟な業務発注が可能です。
外部の専門的な人材やノウハウが活用できる
専門性の高いスキルやノウハウを持つ人材を採用するのは容易ではありません。しかし、業務委託契約であれば採用ほど手順が煩雑ではないため、効率的に必要なスキルやノウハウを持つ人材を活用できます。
自社だけでは困難な業務の対応が必要、専門的な人材のリソースを増やしたいときのみなど、ニーズに応じて適切かつ効率的に専門的な業務や新規業務が行えるようになります。
人件費を抑えられる
業務委託契約では、業務量や質に応じて報酬を支払います。とくに成果報酬型や単発業務型であれば委託した分だけ、依頼したい分だけの報酬で済みます。さらに、業務委託契約では受託者の社会保険料の負担が発生しないため、総合的な面で人件費を抑えることが可能です。
委託される側
委託される側のメリットは、以下3つです。
- 自由度の高い働き方ができる
- 収入アップが目指しやすい
- 人間関係の悩みが生じにくい
自由度の高い働き方ができる
雇用契約ではないため、業務の進め方や働く時間、場所は個人の自由です。委託する側と対等な立場にあるため、具体的な指示に拘束されることなく働けます。業務量にもよりますが、家庭やプライベートと両立しやすい働き方を実現しやすいでしょう。
収入アップが目指しやすい
成果報酬型の契約であれば、仕事した分だけ報酬が得られます。単価や業務内容、業務量によっては、会社員として働くよりも高収入が得られる可能性があります。また、業務単位での報酬となるため対価が可視化され、モチベーション向上にも繋げやすい点はメリットです。
人間関係の悩みが生じにくい
基本的には個人で働くことが多いため、組織特有の人間関係の悩みが生じにくいでしょう。委託者とは対等な立場であるため上下関係はなく、完全に個人で仕事を受けている場合にはマネジメントや他の人の業務を手伝うこともないため、自分の仕事だけに集中できます。
5.業務委託契約のデメリット
一方で、委託する側・される側には下記のようなデメリットもあります。
| 委託する側 | ・社内にノウハウが蓄積されにくい ・具体的な指示が下せない |
| 委託される側 | ・自分で仕事を見つけなければならない ・収入が不安定 ・労働基準法が適用されない |
それぞれのデメリットを詳しくみていきます。
委託する側
委託する側のデメリットは、以下2つです。
- 社内にノウハウが蓄積されにくい
- 具体的な指示が下せない
社内にノウハウが蓄積されにくい
委託先はあくまで外部であるため、ノウハウは蓄積しにくいもの。雇用契約であれば周囲の人に業務を教えたり、マニュアルを作ったりとノウハウを蓄積するための業務も任せられますが、業務委託では業務外・契約外のことは指示できません。
具体的な指示が下せない
業務委託契約では、委託する側に指揮命令権がありません。そのため、業務の進め方や時間配分などを具体的に指示することは不可能です。重要なのは納品物であり、社内と同じ進め方や進捗を見ながらの指示ができないため、品質は受託者の能力や意欲に依存しやすい点はデメリットでしょう。受託者が悪質な場合、納期までに納品されないケースも少なくありません。
委託される側
委託される側のデメリットは、以下3つです。
- 自分で仕事を見つけなければならない
- 収入が不安定
- 労働基準法が適用されない
自分で仕事を見つけなければならない
組織に所属していれば、仕事を渡されます。しかし、業務委託契約で働く場合は自分で営業して契約を取り付ける必要があります。仕事が見つからなければ、当然収入は0です。
収入が不安定
経営状況や他に優秀な人材が見つかったなどの理由から、突然契約が打ち切られる場合もあります。雇用期間の定めがあるわけではではないため、安定とはいえない働き方です。また、発注量や発注時期についても委託する側に裁量があるため、毎月定額型での契約でない限り安定して業務を受注できるとは限らず、収入が不安定になりやすいでしょう。
労働基準法が適用されない
雇用契約でないため労働基準法が適用されず、労働者としての立場が弱い点はデメリットです。また、保険料や住民税の支払い、会計処理や事務など、会社が代行してくれている作業もすべて自分自身でやる必要があります。
6.業務委託契約書とは?
業務委託契約書とは、業務委託契約を締結する際の契約書です。業務委託契約は口頭で交わした約束でも効力がありますが、認識の相違があった場合に「言った」「言わない」の水掛け論になってしまう可能性があります。委託する側・される側の双方が委託内容に合意を得たことを証明するためにも、業務委託契約書の締結が必要です。
委託する業務内容や報酬形態、納期や報酬支払い日など、業務委託契約書によって法律関係を明確にすることで、双方に認識のズレなく業務の委託・業務の遂行が可能となります。

業務委託契約書とは? 記載事項と作成時の注意点を簡単に
業務委託契約書とは、発注者が受託者に業務を委託する契約書です。ここでは、業務委託契約書について解説します。
1.業務委託契約書とは?
業務委託契約書とは、「業務を発注者が受託者に委託する」「受託者が...
7.業務委託契約書の主な記載事項
トラブルを防ぐためにも、業務委託契約書は作成することが望ましいです。決まった形式はありませんが、一般的に業務委託契約書には下記項目を記載します。
- 委託業務の内容
- 委託量
- 支払い条件・支払い時期
- 契約期間
- 秘密保持
- 成果物の権利
- 契約不適合責任
- 禁止事項
- 再委託
- 契約解除
- 損害賠償
- 有効期間
テンプレートを用意しておくと、必要な時に簡単に作成できます。下記で、業務委託契約書の主な記載事項をみていきます。
委託業務の内容
委託する業務内容を具体的に記載します。委託量が多い場合は別途資料を添付するなどし、その旨も記載しましょう。受託者が意味を取り違えることがないよう、書き方には注意が必要です。
委託料
報酬の支払い条件や単価を記載する項目です。成果報酬型・成功報酬型の場合は算定方法について定めがあるか、材料費や交通費などの経費が報酬に含まれるかも明記します。また、税抜・税込が明記されているもチェックしましょう。
支払い条件・支払い時期
報酬が納品後に支払われるのか、着手金の有無や支払い金融機関に条件があるかを記載します。委任契約の場合は毎月◯日に請求書に従い支払うなど、具体的な記載が必要です。あわせて、支払い方法やタイミング、手数料の扱いについても明記しましょう。
契約期間
業務の開始日と終了日を明確に記載します。あわせて、自動更新の有無やその方法も提示します。
秘密保持
秘密保持が必要な場合に記載します。秘密保持とは、業務において委託者と受託者の間で共有した情報を第三者に知らせてはならない取り決めです。権利や社内ノウハウなど、外部に漏らさない方がいい情報は多いため、基本的には記載します。
成果物の権利
成果物が知的財産権を有する場合、権利の帰属先がどこになる旨を記載します。成果物が知的財産権を有するケースは研究や著作物制作、デザインやシステム開発などです。権利が受託者から委託者に移る場合には、そのタイミングも明記します。
契約不適合責任
成果物が契約内容に適合していないことが発見された場合、成果物に対してどう対応するかを記載します。「修正または代替品を納品する」「委託者が被った損害を受託者に賠償する」といった内容が一例です。
これまでこの項目は「瑕疵担保責任」でしたが、2020年の民法改正により廃止されて「契約不適合責任」の規定ができました。
禁止事項
委託者が受託者に対して業務を行う上で原則禁止する事柄を記載します。契約後は具体的な指示ができないため、禁止事項はあらかじめ明確にしましょう。
再委託
再委託とは、受託者が自分自身では業務を行わず、第三者に委託することです。実際に業務を行うのは受託者自身でなければならないか、あるいは第三者に下請け的に流していいのかを記載します。再委託を可能とする場合は、その要件や範囲も明記しましょう。
契約解除
委託者及び受託者の責任おいて、契約を解除できる条件を記載します。賠償責任にも関わる重要な規定であり、無条件で契約解除ができる条件や期間、一般的な解除条件などを明記します。
損害賠償
契約解除や契約違反があった場合の損害賠償有無や補償額の有無を記載します。訴訟になる場合、第一審の裁判所がどこになるかも明記しましょう。
有効期間
「締結日より1年間」など、当該契約の有効期間を記載します。自動更新される場合には、いつから自動更新になるのか、それ以降も自動更新があるのかも記載します。
8.業務委託契約締結の流れ
業務委託契約は、下記流れで締結します。
- 委託先の決定
- 業務内容の協議
- 業務委託契約書の締結
①委託先の決定
まずは、委託先を選定します。委託先の見つけ方は、公募や紹介などルートはさまざまです。候補となる委託先が複数いれば、テストやポートフォリオ、実績の確認などを通じて本契約を検討します。
②業務内容の協議
契約したい委託先が決定すれば、業務内容や報酬などの契約条件を協議し、双方が納得できるよう交渉します。必要であれば、この段階で見積書を作成し、提出した上で協議するとスムーズです。
③業務委託契約書の締結
業務内容など契約条件に双方の合意が得られれば、業務委託契約書を締結します。あらかじめ用意してあるテンプレートを使用、または新規で業務委託契約書を作成し、委託先に送付して締結しましょう。
契約方法は、紙または電子契約です。締結した業務委託契約書は会社法上10年間の保存が必要であり、電子契約の場合は電子帳簿保存法に従って保存します。
9.業務委託契約の注意点
業務委託契約を行う場合、以下2点に注意が必要です。
偽装請負に気を付ける
業務委託契約では、委託者は受託者に対して契約外の業務を委託したり、具体的な指示を下したりすることは禁止されています。それにもかかわらず、直接指示するなど業務委託契約の範囲を超えた労働をさせると「偽装請負」とみなされます。
偽装請負は、本来締結すべき労働者派遣契約を締結せず請負契約で労働者派遣を行なっている状態です。違法行為として罰則の対象となるため、注意しましょう。
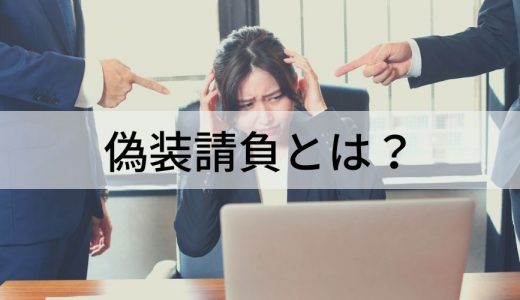
偽装請負とは? 違反となる判断基準や対策方法は?
偽装請負とは請負契約であるにもかかわらず、実際は労働者派遣であること。起こる原因や代表的なパターン、判断基準などについて説明します。
1.偽装請負とは?
偽装請負とは、形式的には業務処理請負でありな...
下請法に抵触しないよう注意する
業務内容によっては、下請法が関係してきます。下請法は正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、個人事業主や資本力の小さい企業を守るための法律です。下請法の対象となるのは、下記4つの取引です。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
下請法が適用される契約では、委託者に書面の交付義務や支払期日を定める義務、遅延利息の支払義務などが発生します。存在や内容を知らずに下請法に抵触するケースも少なくないため、対象となる取引において業務委託契約を結ぶ場合にはしっかりと確認しましょう。

下請法とは? 下請法の概要や目的、親事業者の禁止事項について
下請法とは、親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護するための法律のこと。ここでは下請法の概要や目的、親事業者の禁止事項について見ていきましょう。
1.下請法とは?
下請法...
