企業経営に必要なタレントマネジメントを効率化したい人必見!
タレントマネジメントのやり方や、システムの選び方を解説
⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
事業計画書は、企業が事業を運営するための方向性を示す重要な資料です。目標達成に向けた具体的なステップやビジネスモデルの分析、市場調査などを盛り込むことで、経営資源を効果的に活用する指針となります。また、金融機関から融資を受けたり、投資家から出資を受けたりするために、事業の成功可能性を示す資料としても用いられます。
読者の中には「事業計画書を作成したいけれど、作成方法がわからない」という人がいるかもしれません。事業計画書には説得力のある内容が求められるため、何を記載するべきか理解したうえで作成する必要があります。
本記事では、事業計画書の概要や記載するべき項目、記入例などを解説します。事業計画書のテンプレートに関する情報も掲載しているため、事業を始める予定の人はぜひ最後までご覧ください。
1.事業計画書とは?
事業計画書とは、今後どのように事業を運営していくかを内外に示す計画書です。英語では「business plan」と呼ばれています。創業者が頭の中に描いているイメージを、事業計画書で具体的にまとめることで、実現可能か否かの判断を下せるのです。
なお、そもそも事業計画とは、事業の目標を達成するための戦略や行動プランを指します。従業員や融資先、提携する会社など、さまざまな要素を考慮しながら内容を考えます。1~5年先の、比較的近い将来における戦略・行動プランを練ることが多いです。

事業計画を事業計画書に記すことで、経営の方向性を整理できます。また、事業がうまくいかない場合に事業計画書を見直すと、経営戦略の改善点を考えやすくなります。

事業計画書と創業計画書の違い
創業計画書も、事業の計画と戦略を記述する書類です。政府系金融機関からの融資を得るために、原則として事業を始める前に作成します。
事業計画書は事業を始める前だけでなく、開業後も作成する可能性がある書類です。記載内容は互いに似ていますが、事業の途中で作成するかどうかで違いが見られます。
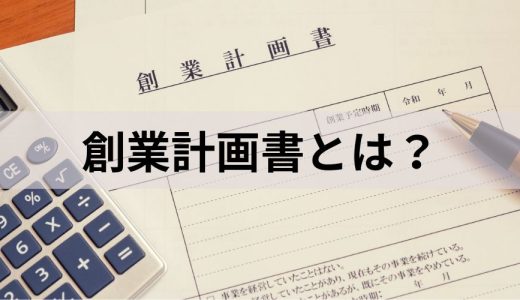
創業計画書とは?【書き方と記入例】テンプレート、事業計画書
創業計画書とは、新しい事業を始める際に作成する計画書のことです。事業計画書との違い、テンプレートの入手方法、書き方などを解説します。
1.創業計画書とは?
創業計画書とは、事業の計画と戦略を詳細に記...
事業計画書と経営計画書の違い
経営計画書とは、企業の中長期的な経営目標や方針を示す書類です。リーダーの想いやビジョンも明確化されます。一方で事業計画書は、詳細な戦略や財務計画など、経営計画書の内容を実現するための行動プランを記載します。
両者は記載する内容が異なり、経営計画書の内容をより具体化したものが事業計画書であるというイメージです。
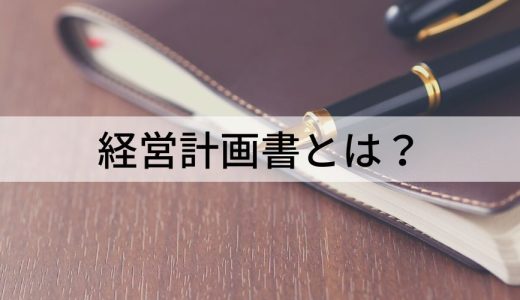
経営計画書とは?【作り方をわかりやすく】テンプレート
経営計画書とは、中長期的な会社の経営方針を示した計画書のこと。経営者の想いやビジョンを明文化した重要な資料であり、社内外に広く活用されます。
今回は経営計画書とは何かをふまえて、経営計画書の重要性や作...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
●1on1の進め方がわかる
●部下と何を話せばいいのかわかる
●質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【タレントマネジメントシステムなら「カオナビ」!】
カオナビの特徴がわかる資料をプレゼント!
●解決できる人事課題を一覧で紹介
●機能を把握できる図解付き
●具体的なサポート内容も把握できる
2.事業計画書の目的
事業計画書の目的は、公的・民間の金融機関や投資家などからの資金調達です。
企業資金の出所は、返済義務のある「融資(借入)」と、返済義務のない「出資・投資」に分かれます。どちらを選ぶにしても、説得力のある事業計画書を提示できなければ、資金の調達は難しくなります。
金融機関は、将来の返済能力が見込めない事業者に対して、お金を貸そうとは思いません。また、投資家も成長が見込めない事業者に対しては、気軽に出資できません。事業の継続的な収益性を示すために、事業計画書で信頼を得る必要があります。


資金調達とは? 具体的な方法とメリット・デメリットを解説
資金調達では、経営に必要な運転資金を集めることができます。起業する際や新規事業を立ち上げる際、経営難を乗り切る際など、さまざまな目的で資金調達が活用されます。
今回は資金調達の具体的な方法やメリット・...
人事業務を効率化して、ほかの作業の時間を作るなら「カオナビ」!
書類のペーパーレス化や社員データの一元管理を実現!
導入効果がわかる資料をダウンロード⇒こちらから
3.事業計画書を作るメリット
続いて、事業計画書を作ることで得られるメリットを解説します。
- 思考整理と可視化
- 方向性の共有
- 資金調達が容易になる
メリットを知ることで、事業計画書の重要性がわかり、より丁寧に作成する意識が高まります。事業を始める予定の人はぜひ確認してください。
思考整理と可視化
事業計画書に改めて書き出すことで、自分の思考を整理できます。
- 事業の概要
- 事業の目的
- 売上目標や今後の流れ
- 企業を取り巻く環境(競合や市場規模など)
頭の中で思い描くだけでなく、実際に書き出して可視化することで、自分の思考を整理したり客観的に検討したりできます。また、新しい気付きやアイデアが生まれる可能性もあります。
方向性の共有
起業は一人だけで始めるケースのほか、従業員を抱えて法人として始める場合もあります。法人として始める場合、事業計画を共有していないと、規模が大きくなった際に関係者と同じ方向を向いて事業を運営することが難しくなる可能性が高いです。
事業計画書により「事業が今後どのような方向に進むのか」を関係者と共有すると、従業員と意思統一を図りやすくなります。
また、社外へ事業の方向性を説明する際に、あらかじめ事業計画書を作成することで内容が伝わりやすくなる点もポイントです。
資金調達が容易になる
資金調達の際、銀行をはじめとする資金提供者に対して「どのような事業を何のために進めようとしているのか」「事業によって何ができるか」をアピールしなくてはなりません。口頭で説明すると時間がかかり、必要事項がうまく伝わらない可能性が高いです。
相手が知りたい内容をまとめた事業計画書を提出できれば、口頭での説明よりも短時間で正確に伝えられるため、説得力が増します。
事業計画をよく考えて作成することで、資金面での問題と改善策もおのずと浮き彫りになり、今後の収益向上の見込みも示せるでしょう。そのため、将来を見据えた審査をしてもらえる可能性も高まります。
また、融資審査の短縮化を期待できる点もポイントです。事業計画書に、審査に必要な情報が記載されていれば、銀行内で精査する際に内容が伝わりやすくなります。

煩雑な人事業務は専用システムで効率化!
システムの選び方がわかる資料をプレゼント!
⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】をダウンロードする
4.事業計画書の項目や記入例
では、いよいよ事業計画書の作成について解説します。事業計画書はどのように作って、また、何を書けばよいのでしょうか。記載する項目として、以下が考えられます。
- 企業の概要
- 事業の概要
- 事業のコンセプト
- 競合や市場規模など環境面
- 自社の強みと弱みなど現況
- サービスや商品の概要
- 販売戦略やビジネスモデル
- 体制や人員計画
- 財務計画
- 開業当初のスケジュール
項目や記入例を把握することで、必要な内容が盛り込まれた事業計画書を作成できます。事業計画書を書く前に、ぜひ確認してください。
①企業の概要
企業の概要の記載項目はさまざまですが、たとえば以下を記載します。
- 商号
- 企業の住所
- 連絡先
- 代表者や役員の氏名
- 株主構成
- 電話番号
- メールアドレス
- ホームページのURL
また、代表者の経歴も詳細に書きましょう。「事業に関連する経験をどれくらい積んだか」「どれくらいノウハウやスキルを保持しているか」など、代表者の事業に対する思いを含めてまんべんなく記載します。
起業の動機も記載すると、事業への本気度をより強くアピールできます。
記載例
【企業名等】
代表者名 山田 健
企業名・屋号 Roastery KITE(仮)
所在地 ○○県○○市○○2-12-3
設立年月日 2025年4月1日(予定)
資本金 300万円(個人)
事業内容 スペシャルティコーヒーの焙煎・EC販売・カフェや飲食店向け業務用販売
【経営者の経歴等】
<経歴>
●2015~2024 〇〇珈琲(株) 焙煎/商品開発(年間焙煎量約12トン、担当店舗売上130%を2年連続達成)
<資格>
●Qグレーダー
●SCAコーヒー資格(上級)
【起業の動機】
学生時代に訪れた農園で生産者の情熱に触れ、スペシャルティコーヒーの魅力を実感した。大手のコーヒー製造企業で10年間、焙煎や商品開発に携わる中で「生産者と消費者を直接つなぐ事業をしたい」という思いが強まった。会社員時代に築いた産地とのネットワークを活かし、鮮度と品質にこだわったコーヒーを地域から全国へ届けることを目指して独立を決意した。
②事業の概要
どのような事業を始めようとしているかを具体的に書きます。意識するのは下記の3点です。
- 誰に
- 何を
- どのように提供するか
上記の3点を明確にするだけでも、大まかな概要を相手に伝えられます。
【具体例】
- 誰に…20~30代の女性を中心とした若者に
- 何を…ワインにこだわった専門店を
- どのように…都市部の繁華街にバル形式で出店する
上記のように説明できれば伝わりやすいです。
関係者が多く、簡潔に伝えるのが難しい場合は、サービスの流れや事業の全体図を示すとわかりやすくなります。
記載例
【ターゲット顧客】
●20〜30代の在宅ワーカーで、自宅で過ごす時間を豊かにしたいと考える層
●「カフェに行かなくても、自宅で本格的なスペシャルティコーヒーを楽しみたい」というニーズを持つ層
【商品・サービスの提供方法・仕組み】
●自社焙煎所で少量ずつ焙煎し、オンラインショップで全国販売する。
●味や香りの特徴をわかりやすく表示し、初心者でも自分に合う豆を選びやすい仕組みを整える。
③事業のコンセプト
「なぜ事業を始める必要があるか」「事業を通して何を成し遂げる予定なのか」を明確にする箇所です。できるだけ簡潔にわかりやすく表現しましょう。事業を通じた自社のミッション・自社の特徴・自社ならではの強みのほか、顧客のメリットを記載します。
事業を通じて達成したい社会貢献の内容や、どういった顧客を喜ばせたいかを盛り込むと、相手に熱意が伝わり、ビジネス経験が乏しい創業者でも資金調達を実現しやすくなります。
また、事業を運営する中、迷ったときに立ち返る道しるべにもなるはずです。
記載例
●自家焙煎の鮮度と品質にこだわり、20〜30代の在宅ワーカーや地域の小規模カフェに「毎日楽しめる本格コーヒー」を届ける。わかりやすい味の表示を心がけ、選びやすさも重視する。
●1年後の売上高240万円、3 年後の売上高600万円を目指す。
④競合や市場規模など環境面
競合他社の強みや、取り扱うサービスや商品の市場規模はどのくらいかを記載する項目です。
競合他社は3社程度設定し、それぞれの強みを分析したうえで記載してください。競合の強みや弱みを分析すると、自社の独自性や強みを発見できます。
分析の際は、以下の4つの軸を意識すると効果的です。
- 何を売っているか(商品)
- いくらで売っているか(価格)
- どういった流通経路で売っているか(流通)
- ブランド戦略・PR戦略など、どのような戦略で売っているか(販売戦略)
記載例
主な競合は「大手コーヒーチェーン」「オンライン専門のコーヒー通販」「地域密着型カフェ兼豆販売店」の3社である。
1.大手コーヒーチェーン
ブランド力は高く、安定した集客が可能。価格帯は1杯400~600円で顧客は店舗中心。個性や鮮度の面では限定的。
2.オンライン専門コーヒー通販
新鮮な豆を宅配する仕組みを持つが、味や選択肢の幅が複雑で初心者には選びにくい。
3.地域密着型カフェ兼豆販売店
顧客との接点は強いが、販路が限定的で拡大余地が小さい。
以上より、自家焙煎と選びやすさに注力し、オンライン定期便を活用することで、競合と差別化が可能と考える。
また「○○(調査の名称)」のデータによると、スペシャルティコーヒー市場は拡大傾向にあるため、市場の状況から見ても高品質なコーヒーに特化した事業は追い風であるといえる。
➄自社の強みと弱みといった現況
SWOT分析(「強み・弱み・機会・脅威」を洗い出す手法)をはじめとするフレームワークを使って、自社の強みや弱みなどを書きます。
弱みを書く際は、どのように改善するかの施策も記載しましょう。強みを書く際は、技術・組織力・企業風土などの観点から、自社が顧客から選ばれる理由を分析します。
「顧客にとっての価値」「顧客の負担」「利便性」などを軸にして分析することが大切です。
記載例
●スペシャルティコーヒーの知識と抽出技術に長けており、自宅で本格的なコーヒーを楽しみたい層に対して高品質な商品を提供できる。独自に焙煎した豆やオリジナルレシピを活用し、他店との差別化を図ることが可能。
●在宅ワーカー向けにオンライン販売・定期便サービスを整備しており、利便性の高い購買体験を提供できる。
●弱みとして、ブランド認知度がまだ低く、集客力に課題がある。改善策としてSNSやブログによる情報発信、オンライン広告の活用、口コミ・レビュー促進を計画している。
●仕入れ・在庫管理の経験が浅いため、初期は少量から運営し、運営ノウハウを蓄積することで安定的な供給体制を整える予定。

【図解】SWOT分析とは? 目的や具体例、やり方やテンプレートを紹介
SWOT分析は、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの視点から自社の状況を整理し、最適な戦略を立てるためのフレームワークです。...
⑥サービスや商品の概要
自社で取り扱うサービスや商品について、内容や提供方法などの概要を書きます。競合他社との違いも説明しながらアピールしましょう。
顧客に提供するサービスにおける「目に見える価値」と「目に見えない価値」や付随するサービス、商品の価格などについても、アピールできる部分があれば記載します。
記載例
【商品】
●自家焙煎したスペシャルティコーヒー豆(シングルオリジン・ブレンド各種)
●コーヒードリッパーやミルなど抽出器具、簡単に使えるレシピカード付き
【サービス】
●定期便サービスによる月1回のコーヒー豆配送
●オンラインでの抽出方法・保存方法の動画・記事提供
●購入者向けのカスタマーサポート(問い合わせ・相談対応)
【価格】
●スペシャルティコーヒー豆 200g 1,200~1,800円
●抽出器具 1,500~4,000円
●定期便 1回 1,500~2,000円
【提供体制】
●注文は自社ECサイトおよび主要ネットモール経由で受付
●配送は契約物流会社を活用し、鮮度を保ったまま全国配送
●事業開始時は自宅の小規模焙煎設備で対応し、需要拡大に応じて外注・委託を検討
⑦販売戦略やビジネスモデル
取り扱うサービスや商品の流通経路をはじめ、商材のセールスポイントや市場の状況を踏まえた販売戦略・ビジネスモデルを記載します。顧客に自社の商品やサービスを認知させ、購入に至るまでの仕組みを説明しましょう。
顧客に商品・サービスが届くまでのプロセスや代金回収の仕組みを思い描き、利益を生み出す仕組みを分析したうえで記載することが大切です。
記載例
【商品・サービスの提供方法・仕組み】
●自家焙煎スペシャルティコーヒー豆や抽出器具を自社ECサイトを中心に販売する。
●商品ページでは豆の産地・焙煎度合い・味の特徴・抽出方法をわかりやすく表示し、購入者が自分好みのコーヒーを選びやすいように工夫する。
●定期便サービスを導入し、月1回の配送で継続購入を促進させる。
【販売促進・集客方法】
1) コンテンツマーケティング
コーヒーの淹れ方や豆の特徴を解説するブログ・動画を定期配信。SEO対策を意識し、自社サイトへの集客を図る。
2) SNS連動
InstagramやX(旧Twitter)で焙煎の様子や季節限定商品の紹介を行い、ブランド認知を拡大させる。
3) 顧客レビュー活用
購入者のレビューをサイトに掲載し、味や使いやすさの信頼性を訴求する。レビュー投稿者には次回購入時割引クーポンを付与してリピート率を向上させる。
【収益モデル】
●「商品販売単価×販売数量」による直接収益と、定期便による安定収益を確保する。
●初期投資を抑え、小規模焙煎からスタートし、需要拡大に応じて生産委託や外注を活用することで利益率を維持する。
⑧体制や人員計画
どのような体制で事業を進めるか、人員計画を書きます。長期的な視点に立って、従業員の数と人員配置がわかるように書きましょう。意思決定の流れと役割分担を明確にした社内組織図のような、誰でも業務内容が想像できるものを記載すると効果的です。
従業員の人数は、事業を始める際の人数と、今後雇用を予定している人数の両方を記載してください。あまりにも事業の規模に見合わない人数を記載するのは避けましょう。なお、取締役や監査役といった役職は従業員に入らないので注意してください。
また、事業が売上を伸ばすと、その分新たな人員も必要となります。将来的な売上計画を考慮し、人件費や採用にかかる募集費用なども予測した採用計画を立てると、より詳細な内容になります。
記載例
【1年目(事業開始時)】
●経営者が焙煎・品質管理を担当
●出荷・梱包、販売・顧客対応も経営者が担当
【2年目】
●出荷・梱包、販売・顧客の補助として、パートタイム1名を採用予定
●外部委託でデザインや配送補助を繁忙期に活用
【3年目】
●出荷・梱包、販売・顧客の補助として、パートタイム1名を追加で採用予定
●焙煎・品質管理は、2年目で採用した人員とともに2人で対応
●2年目に引き続き、外部委託でデザインや配送補助を繁忙期に活用
●外部委託費用は売上高の約15%を想定
【アルバイト・パートの条件】
時給1,200円、月5日、1日4時間勤務
【経営者の個人所得/役員報酬】
1年目100万円、2年目150万円、3年目200万円を想定
⑨財務計画
事業が将来どれだけ利益を挙げられるか、資産に関する財務計画を記載します。財務計画は大きく3つの項目に分けて記載します。
売上に関する計画
どのように売上を上げるか、原価はどの程度になるかなどを整理しましょう。
売上計画を立てる際は、商品やサービスごとに分けて考えます。見込み客数や競合の経営指標などを参考にして、実現可能な計画を予測して書くとよいでしょう。顧客ごとに分けて考えるのも効果的です。
売上原価計画を立てる際も、売上計画と同様各商品やサービスごとなど、分けて書きましょう。商品・サービスごとに記載することで、売上のうちどの要素を伸ばすのが効率的かを判断する材料にもなります。
記載例
●販売計画
1)自社サイトでのコーヒー豆の販売
スペシャルティコーヒー豆200g
収益の割合:50%
2)定期便でのコーヒー豆の販売
200g×2袋の月次配送
収益の割合:35%
3)自社サイトでの器具の販売
ドリッパー・フィルター等の抽出器具
収益の割合:15%
●年間販売額
1)自社サイトでのコーヒー豆の販売
コーヒー豆200g:1,600円×月300袋×12ヶ月=576万円
2)定期便でのコーヒー豆の販売
(200g×2袋)3,000円×月150件×12ヶ月=540万円
3)自社サイトでの器具の販売
平均単価3,000円×月50件×12ヶ月=180万円
年間合計:1,296万円
利益に関する計画
利益計画は非常に重要視される項目です。
売上・原価・販管費・借り入れ・法人税など、利益を計算するための項目を記載します。利益を計算するには、売上から売上原価・人件費・減価償却費・販売費・管理費・借入利息・法人税などについて、順を追った予測が必要です。
利益の種類は「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引後利益」などがありますが、いずれも予測する際は、上記の費用を把握しなければなりません。
利益計画を立てると「利益を出す事業になるにはどの費用を下げるべきか」が見えてきます。
記載例
【1年目】
●売上高:1,482万円
●売上原価:666万円(売上の45%)
●売上総利益:816万円
●人件費:役員報酬120万円、アルバイトなし
●家賃:60万円
●その他経費(広告費・交通費等):50万円
●営業利益:約586万円
【2年目】
●売上高:2,000万円
●売上原価:900万円
●売上総利益:1,100万円
●人件費:役員報酬240万円、アルバイト120万円
●家賃:60万円
●その他経費:70万円
●営業利益:約610万円
【3年目】
●売上高:2,500万円
●売上原価:1,125万円
●売上総利益:1,375万円
●人件費:役員報酬360万円、アルバイト240万円
●家賃:60万円
●その他経費:90万円
●営業利益:約625万円
※営業外損益や法人税は別途計上予定
資金調達に関する計画
資金調達に関する計画も重要視される項目です。利益計画では利益が出ていても、現金が十分に足りているか不足しているかはわかりません。「利益が出ている=資金がある」とは限らないため、利益計画から資金の残額を把握することはできません。
資金計画は、売上計画と利益計画で出した数値を、資金の増減に合わせて表を作り直すことで計算できます。売上計画や利益計画の内容が曖昧である場合、資金計画の作成も難しくなります。
また、銀行から借り入れる際に返済可能な資金があるかを適切に判断してもらうためにも、資金計画の作成は重要です。
記載例
【必要な投資(設備資金)】
●焙煎機(小型):60万円
●コーヒーミル:8万円
●真空包装機:15万円
●ECサイト制作・撮影:20万円
●設備工事(換気・電気):20万円
●備品・器具:10万円
●許認可・保険等:5万円
→ 設備資金合計:138万円
【運転資金(開業〜初期運転)】
●生豆仕入れ・在庫:30万円
●包材・資材:10万円
●広告・販促:15万円
●初期人件費・諸経費:25万円
→ 運転資金合計:80万円
合計必要資金:218万円
【調達方法】
●自己資金(資本金300万円)より218万円を充当。
●親族等からの借入:0、金融機関借入:0(当面は自己資金で運営し、事業拡大時に追加借入や補助金を検討)。
●資金余剰(自己資金残高約82万円)は予備運転資金および広告追加投下に確保。
⑩開業当初のスケジュール
開業当初のスケジュールでは、事業開始の準備段階から、軌道に乗るまでの行動計画を時系列で示します。一般的には、事業開始から3年後までを見据えたスケジュールを、月単位や四半期単位で記載する形が多いです。
「いつまでに何をやるか」を示す段階的な目標を明記すると、実現性のある計画である旨をアピールできます。自分にとっても、スケジュールを整理できる良い機会であるため、丁寧に作成してみましょう。
記載例
●開業6~3ヶ月前:事業計画の最終確認、資金調達手続き、設備・備品の選定
●開業2~1ヶ月前:仕入れ先契約、ECサイトや販売ページの作成、広告・広報準備
●開業月:開業届提出、初期在庫の受け取り、販促活動開始
●開業1~3ヶ月:ECサイト販売開始、試飲会・イベント出展、顧客からのフィードバック収集
●開業3~6ヶ月:商品改良、定期便の提供開始
●開業6~12ヶ月:販売チャネル拡大、販促施策の強化、顧客管理体制の整備
●開業後1年:売上・利益の分析、商品ラインナップの拡充、リピーター獲得施策
●開業後2~3年目:スタッフ採用・育成、事業拡大、販路・ブランド力の強化

組織と社員の成長につながる「OKR」とは?
概要や導入の効果、具体的な導入手順を紹介!
OKRのことがよくわかる資料をダウンロード⇒こちらから
5.事業計画書のテンプレート

ここからは、事業計画書のテンプレートが手に入る、以下の3つのサイトを紹介します。
- 日本政策金融公庫
- 中小企業基盤整備機構
- Microsoft Office
テンプレートを活用すると、事業計画書をスムーズに作成できます。事業計画書を作成する予定の人は、ぜひ各サイトの詳細を確認してください。

事業計画書の無料テンプレート|必要な項目、書き方のポイント
事業計画書とは事業内容や戦略、利益の見込みなどを記載する書類で、金融機関から事業資金を調達する際に、提出を求められます。テンプレートを活用した事業計画書作成のポイントや注意点を詳しく解説しましょう。
...
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫が無料のテンプレートを配布しています。PDFやExcel形式で汎用性が高く、すぐに活用できます。また記載例のファイルも配布されているため、具体例を参考にしながら作成できる点も魅力です。
詳しい記載方法は電話で問い合わせることも可能です。
参考 各種書式ダウンロード日本政策金融公庫中小企業基盤整備機構
中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営するポータルサイト「J-Net21」では、事業計画書のテンプレートや記入例が公開されています。「飲食業」「小売業」「サービス業」それぞれの記入例が用意されており、自身の事業に近いサンプルを参考にできます。
記入例では図や表も用いられているため、視覚的にわかりやすい事業計画書のお手本として利用可能です。
参考 事業計画書の作成例|起業マニュアルJ-Net中小企業ビジネス支援サイトMicrosoft Office
Microsoft Officeの公式ホームページでは、Officeソフトを利用したドキュメントの作成例を多数載せており、事業計画書の例も公開しています。
作成例はExcelで作られており、合計金額を自動で計算できるように関数が入力されています。ファイル内で事業利益や必要資金を計算しながら作成可能です。
参考 事業計画書 - 無料テンプレート公開中楽しもう Officeタレントマネジメントシステム「カオナビ」とは?
豊富な機能を図解付きの資料でわかりやすく紹介!
カオナビの資料をダウンロード⇒こちらから
6.事業計画書を作成する際の注意点

事業計画書を作成する前に、注意点についても確認しましょう。
- 内容は細かく具体的に記載する
- 簡潔かつわかりやすく記載する
- 競合について書く
- 数値は根拠を明確にしつつ提示する
事前に注意点を確認することで、より明確な事業計画書を作成できます。事業計画書を作成する前に、ぜひご覧ください。
①内容は細かく具体的に記載する
事業計画だけを書くのは不十分です。資金提供者に理解してもらえるよう、計画以外の情報も盛り込みましょう。たとえば、以下の項目を書くと効果的です。
- 企業の沿革や代表者のプロフィール
- 従業員数
- ビジネスモデルの概要
- 取引先
- 解決すべき問題点や課題
上記の項目によって企業の概要が理解しやすくなり、施策と数値計画の意図も伝わりやすくなります。
②簡潔かつわかりやすく記載する
さまざまな内容を記載すると膨大な資料になってしまいそうですが、できるだけ簡潔な内容にしましょう。簡潔であるほうが、読む側に伝わりやすくなります。
事業を知らない人が読んでもわかりやすい内容に仕上げるには、グラフや図解を挿入すると効果的です。図表を作成する際は、デザインに凝りすぎず、シンプルに仕上げることを心がけましょう。また、整合性の取れた内容であるかも気を付けて確認してください。
③競合について書く
競合の調査も重要です。競合についての内容がない場合「入念に考えているか疑わしい」と捉えられてしまう可能性があります。ほかの企業の現状から経営戦略を考えられる場合もあるため、競合調査はしっかり行いましょう。
また、市場環境の調査も重要です。参入予定のマーケットの中で、狙うターゲット層と見込まれる収益を明確にし、事業計画書で説明できれば説得力が増します。
④数値は根拠を明確にしつつ提示する
事業計画書に示した数値に実現性があるかを問われることもあります。特に「売上が5%増加」「売上が50万円増加」などといった、収支見込みに数値を用いる場合です。
変化の激しい経済環境の中で、収支見込みをどのように実現するのか、可能な限り具体的な根拠や裏付けを記載しましょう。
根拠を説明するのは簡単ではありませんが、客観性のあるデータや根拠に基づいた手堅い事業計画書の提出は、融資の際に肝要です。

事業計画の策定にあわせて、人事業務を効率化するシステムの導入も検討しましょう!
専用システムの導入効果や、選び方がわかる資料をプレゼント!
⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする
7.事業計画書の作成に関する相談先
ここからは、事業計画書の作成に関する相談先として、以下の4つを紹介します。
- 日本政策金融公庫
- 商工会議所
- 税理士
- 中小企業診断士
相談先を把握することで、万が一事業計画書の作成でわからない点があった場合に、迅速に解決しやすくなります。事業計画書を作成する前に、ぜひ確認しておきましょう。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、国が100%出資している政策金融機関であり、小規模事業者や創業予定者への融資を主な業務としています。全国の支店に設置されている「創業サポートデスク」で、事業計画書の書き方についてアドバイスを受けられます。
ウェブサイトで配布されている、事業計画書のテンプレートをあわせて使用すると、よりスムーズに作成可能です。
商工会議所
商工会議所は、地域経済の発展を目的として活動する公的な団体で、全国の主要都市に設置されています。経営相談に関する窓口が設けられており、事業計画書の作成をはじめ、さまざまな場面でサポートを受けられます。
イベントやセミナーの案内もしており、ほかの経営者と交流できる可能性がある点も魅力です。
税理士
税理士は、税金に関する申告や相談を業務とする税務の専門家です。事業計画書の中でも特に専門知識が問われる「収支計画」や「資金繰り計画」などの事項について、書き方をアドバイスしてもらえます。
税理士に相談することで、客観的なデータに基づいた数値計画を立てられるため、金融機関を納得させられる事業計画書を作成しやすくなります。
中小企業診断士
中小企業診断士は、企業の経営課題について診断・助言を行う、経営コンサルタントの専門家です。事業計画書の作成方法をアドバイスしてくれるほか、事業戦略からビジネスモデルの妥当性や将来性を評価してくれます。
人によって、マーケティング・財務・生産管理など得意分野が異なるため、自分が相談したい分野に詳しい診断士を選ぶとより効果的です。
【タレントマネジメントを効率化する「カオナビ」!】
事業計画書を作成する経営者には「タレントマネジメント」を行うスキルも必要です。
「カオナビ」なら、タレントマネジメントを効率化!
●社員の能力やスキルが一覧で可視化される
●スキルと合わせて人件費の変動も分かる
●スキルだけではなく人間性やエンゲージメントもわかる
事業計画書のQ&A
- 企業の概要
- 事業の概要
- 事業のコンセプト
- 競合や市場規模など環境面
- 自社の強みと弱みなど現況
- サービスや商品の概要
- 販売戦略やビジネスモデル
- 体制や人員計画
- 財務計画
- 開業当初のスケジュール
