もっと効率的に、成果を出すためのマネジメントを行いませんか?
カオナビなら、人材のスキルや目標に対しての進捗度を一元化し人材育成をサポートします。
⇒
【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
チェンジマネジメントとは、組織が現状のあり様から理想の形に移行し、期待する成果を得るための変革推進手法のことです。
本記事では、チェンジマネジメントの定義や、企業にもたらす効果と価値、変革を推進する上での課題などをわかりやすく解説します。チェンジマネジメントにより組織を理想の形へ変えたい方はぜひ最後までお読みください。
目次
1.チェンジマネジメント(Change Management)とは?
チェンジマネジメントとは、組織が変化に適応し、自らの成長や進化を効果的に実現するための体系的な手法のことです。
企業が変革を成功させるには、全体を見渡した戦略的な対応が重要です。この手法は、リーダーシップの方向性や組織文化、業務プロセスを最適に整える役割を担います。変化のスピードが加速する現代において、チェンジマネジメントの実践は欠かせない取り組みのひとつでしょう。
チェンジマネジメントは、様々なモデルやプロセスを含む包括的な方法論です。経験や勘に頼らず、体制や役割などの具体的なアプローチを通じて、変革における人的側面を支援します。
チェンジマネジメントの定義
チェンジマネジメントは、組織や企業が現状から理想の未来へとスムーズに移行するために必要な変革を、計画的かつ体系的に推進する手法のことです。
変化に伴う混乱や抵抗を最小限に抑え、関係する人々が新しい環境へ迅速に適応できるような支援が重要なポイントです。
保守的なメンバーも上手に巻き込みながら、組織全体がより良くなるために変化する仕組みづくりをおこなうアプローチとも言えます。
組織や企業の中には、変化が苦手なメンバーや現状維持を求めるメンバーもいるため、急激な変革をおこなえば摩擦や軋轢が生じるかもしれません。そこで、チェンジマネジメントの考え方が重要になるのです。
変革のマネジメント
チェンジマネジメントは、日本語では「変革のマネジメント」や「変革管理」と呼ばれることもあります。
この分野でよく知られている書籍に、学習院大学の教授である内野 崇氏が書いた『変革のマネジメント―組織と人をめぐる理論・政策・実践』があります。組織変革を深く理解するための理論的枠組みと実務的アプローチを体系的に扱っている点で有名です。
内野氏は、企業現場でのコンサルティングにおいて豊富な実績を持ち、本書では個人・チーム・組織文化・リーダーシップまで多面的に分析しています。
チェンジマネジメントの始まり
チェンジマネジメントの起源は、1990年代のアメリカです。当時は、「BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)」という業務プロセスの抜本的な見直しが注目されていました。
しかし、「人」の心理的抵抗や組織文化の壁が大きな障害となり、BPRの多くは失敗に終わってしまいます。このような背景から、変革に関わる人々の意識や行動の変化を促すことが不可欠だと認識され、チェンジマネジメントの理論が発展しました。
チェンジマネジメントの目的
チェンジマネジメントの主な目的は、組織内でおこなわれる変革を円滑かつ効果的に推進した上での成果の最大化です。
変革のプロセスでは、従業員や経営層からの抵抗、不安、混乱が避けられません。こうした課題に対して、チェンジマネジメントは、変革のビジョンや目標を明確にし、関係者全員がその意義を理解できるようにします。
【マネジメントの「むずかしい」「時間がかかる」を一気に解決】
人材管理システム「カオナビ」を使ってマネジメントの生産性を大幅改善!
●時間のかかる1on1や360度評価をシステムで効率化できる
●面談記録を簡単に残し、必要な時にすぐ確認できる
●部下の進捗やスキルを一覧で確認できる
●部下のエンゲージメントを見える化できる
2.チェンジマネジメントが企業にもたらす効果と価値

チェンジマネジメントの導入により、組織内での変化を円滑に進めながら、想定されるリスクを抑えることが可能です。環境の変化に対応できる体制が強化され、従業員の主体性や組織への関与意識も高まります。
プロジェクトの成功率が高まる
チェンジマネジメントの適切な導入により、プロジェクトの成功率が大幅に高まります。ただし、それには従業員がどれだけ新しいやり方を受け入れ、実践できるかが重要です。
変化に対して従業員が感じる心理的抵抗をあらかじめ把握およびケアし、システム導入やプロセス改善を円滑に進める仕組みを整備することで、ROI(投資対効果)を最大化できるでしょう。
例えば、人の気持ちを置き去りに制度を刷新しても、従業員の理解不足による運用の形骸化や軋轢、混乱などを招きかねません。
可変革時は、従業員への配慮を忘れないようにしましょう。変革の必要性を理解してもらい、意図に沿った行動をしてもらうことが重要です。
リスクを低減できる
変革の過程には、業務停滞や離職などのリスクがつきものです。チャレンジや改革に伴うリスクの見える化と、従業員への段階的なサポート体制を構築することで、組織における混乱や業務停滞を最小限に抑えられます。
結果として、プロジェクト遅延やコスト超過といった大きな痛手を未然に防ぐ効果が得られるでしょう。
適応力が強化される
チェンジマネジメントによる価値のひとつは、組織そのものに変革適応力を備えさせる点です。単発の改革だけで終わらず、変化に強いマインドセットやプロセスを継続的に整えることで、将来の新たな変化に対応できる組織文化が醸成されます。
具体的には、変革時に活用する共通のフレームワークやガイドラインを整備し、従業員の変革に対する理解や適応力を高めましょう。大きな不安や混乱を生じさせずに組織全体が円滑に成長できる文化の創造が可能です。
市場の変化が激しい現代のビジネス環境では、こうした対応力の高さが競争優位の源泉となります。
従業員エンゲージメントが向上する
リーダーシップの強化や適切なコミュニケーション、トレーニングの実施、必要なリソースの確保などを通じて、従業員の納得感やエンゲージメントが高まります。変革の当事者としての意識を醸成できると、全体的な生産性向上も可能です。
心構えが整っていない状態での変革は、従業員の納得感を損ないます。生産性低下を招きかねないため、注意しましょう。

従業員エンゲージメント向上施策10選! 効果、事例を簡単に解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
3.チェンジマネジメントの課題
チェンジマネジメントには大きなメリットがある反面、以下のような乗り越えるべきハードルも存在します。
- 「チェンジモンスター」が存在する
- 「変革疲れ」を引き起こすことがある
- 計画不足により変革が進まない
「チェンジモンスター」が存在する
チェンジマネジメントを実践する際、もっとも大きな壁となるのが人の抵抗です。新しい仕組みや業務フローを導入しても、現場の従業員が「今までのやり方の方が慣れている」と感じて受け入れを拒むケースは少なくありません。
こうした心理的な抵抗は「チェンジモンスター」とも呼ばれ、変革の成否を左右する要因となります。
具体的には、自分の担当を超えた視野を持たず他領域とのコミュニケーションを図ろうとしない、以前の経営者が手掛けた事業業績が落ち込んでも撤退の議論や決断をしようとしない、などが挙げられます。
「変革疲れ」を引き起こすことがある
変革が連続して起こると、従業員が「変革疲れ」に陥り、組織全体のパフォーマンスが低下することもあります。複数の変革プロジェクトを同時に進行させる場合は、感情的負荷にも配慮して計画を慎重に進めましょう。
計画不足により変革が進まない
チェンジマネジメントを成功させるには、影響範囲の分析や関係者の合意形成、現場への教育・サポート体制の構築が不可欠です。これらが不十分だと、変革の混乱が長引き、成果が出せない状況に陥ります。
情報を発信するときは、概要から順を追って詳細化していくのが一般的です。人は、多くの情報を一度に処理して覚えることが難しいため、概要から詳細へと段階を分けて共有するのが理想的です。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.チェンジマネジメント成功のためのポイント

チェンジマネジメントを成功させるためには、以下のポイントを意識しなければいけません。
- 経営層が推進する
- 従業員の共感を得る
- 小さな成功体験を積み重ねる
経営層が推進する
経営層やマネジメント層がリーダーシップを発揮し、現場を巻き込むことが成功の鍵です。自ら現場に足を運び、変革の必要性について対話を通じて伝え続けましょう。
リーダーが率先して変革を推進し、現場の従業員が積極的に関与できる仕組みを整えることで、組織全体が一丸となって変化に対応できる体制が生まれます。

リーダーシップとは? 種類や理論、ある人の特徴、高め方を簡単に解説
従業員のリーダーシップを育成できていますか?
カオナビならスキルを可視化し、戦略的な育成プランが立案できます!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウ...
従業員の共感を得る
これまでのチェンジマネジメントは、主に計画立案や数値的な分析に重きを置いた、変化のコントロールが中心でした。ただし、この手法だけでは、人が実際に行動を改めたり、新たな習慣を受け入れたりするのは困難です。
近年では、「人間の心理や行動」に焦点を当てたストーリーテリングを活用し、「変化の先にどのような未来があるのか」を伝えたり、コーチングを通じて当事者意識を高めたりする手法が取り入れられています。

コーチングとは? 意味、ビジネスでの効果、やり方を簡単に
コーチングは、運動や勉強、技術の指導において、学習や成長を促進するアプローチです。この方法は、クライアントの潜在能力に働きかけ、最大限に力を引き出すことを目的としています。単なる指導にとどまらず、相...
小さな成功体験を積み重ねる
チェンジマネジメントのもっとも重要な成果のひとつは、変化をポジティブに受け入れ、自ら行動できる人材が育つことです。
そのためには、段階的な成果の設計が欠かせません。最初に小さな成功体験を積み重ねることで、関係者のモチベーションと期待感が高まり、次の変革ステップへ進みたいと思える土台を築けます。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
5.チェンジマネジメントの手法
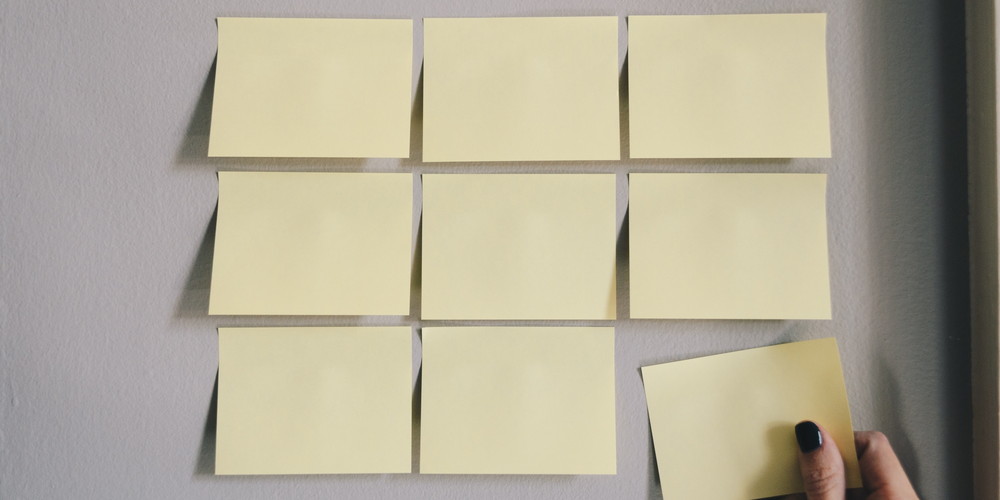
ハーバードビジネススクールの名誉教授である、ジョン・コッター氏は、組織に変革を根付かせるためには、順序立てて進めることが重要と提唱しています。その流れは以下の通りです。
- 危機意識を高め共有する
- 強い変革推進チームを結成する
- 変革ビジョンと戦略を策定する
- 変革のためのビジョンを周知する
- 従業員の自発を促す環境をつくる
- 短期的な成果を実現する
- 成果を活かしてさらなる変革を推進する
- 新しいやり方を組織文化に定着させる
①危機意識を高め共有する
まず、組織全体に対する「現状のままでは将来に大きなリスクがある」という危機感の共有が重要です。経営環境の変化や市場の競争激化など、変革の必要性を具体的なデータや事例で伝えましょう。従業員一人ひとりが当事者意識を持てるようにします。
ジョン・コッター氏は、経営幹部の75%が危機意識を認識しない限り、変革は失敗すると唱えています。そのため、経営幹部が共通の危機意識を持つことも重要です。
②強い変革推進チームを結成する
変革をリードするため、信頼できるメンバーによるチームを結成しましょう。多様な部門や職種から選抜し、組織横断的な連携を図ることで、変革の推進力が高まります。
メンバーの選出基準は以下のポイントを押さえるといいでしょう。
- 権限を持っている
- 高い専門知識を持っている
- 組織から信頼を得ている
- 変革を推進するリーダーシップがある
上記の要素を持ち合わせているメンバーを選ぶと、変革の成功率が上がります。
③変革ビジョンと戦略を策定する
推進チームは、変革後の組織の姿や実現できる価値を明確化し、その上で達成に必要な戦略や戦術を設計します。ビジョンはシンプルかつ具体的で、誰もが理解しやすい内容にしましょう。
④変革のためのビジョンを周知する

策定したビジョンを、全社に対して丁寧に伝えます。一度の説明だけでなく、社内会議、メール、イントラネット、現場への訪問といった複数チャネルで繰り返し発信することが必要です。
従業員にしっかり理解してもらえないと、ビジョンだけが一人歩きして現場の温度感とずれが生じるかもしれません。
⑤従業員の自発を促す環境をつくる
変革を進めるにあたって、制度やプロセスなどの障害を取り除き、従業員が主体的に行動できるよう支援します。具体的には、権限委譲や研修、評価制度の見直しなどです。
この際、変革を妨害するチェンジモンスターが存在する可能性もあります。その場合は、経営陣や変革推進メンバーが、誰がチェンジモンスターになっているか特定し、その要因をうまく解決していかなければなりません。
⑥短期的な成果を実現する
小さな成功体験を積み重ねることで、変革への信頼感とモチベーションを高めましょう。実現した内容は、可視化した上で組織全体へ共有してください。
⑦成果を活かしてさらなる変革を推進する
短期成果によって得た勢いを活かし、次の変革にスムーズにつなげていきます。ひとつ成功して終わりではなく、新しいプロジェクトや仕組みに活かし、変革が一過性で終わらないような継続的な推進が重要です。
例えば、推進チームに新しいメンバーを加えるといった体制拡充も有効でしょう。ときには、解決していたはずの課題が再発し、変革が頓挫してしまうケースもあるため、変革を継続する意識は欠かせません。
⑧新しいやり方を組織文化に定着させる
最終段階では、新しく導入した方法や価値観を社内の評価基準や人材育成制度に組み込むことで「当たり前」にしていきます。組織文化として根付くと、変革が持続し、新たな変化への対応力につながるでしょう。
具体的には、新しい方法と組織成長の関連性について発信し続けることや、次世代のリーダー育成を進めていくことなどが重要です。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.チェンジマネジメントの事例
チェンジマネジメントの成功事例を紹介します。
- IKEA(Ingka Group)
- 富士フイルム株式会社
- アドビ株式会社
IKEA(Ingka Group)
IKEA(Ingka Group)は、デジタル時代に対応するための大規模な変革を実施しました。例えば、デジタル化の加速やオムニチャネル戦略の推進、都心型店舗の展開など、複数の変革を同時に進めることに成功しました。
デジタル分野への大規模投資や、Eコマース基盤の強化、顧客体験向上のためのアプリ導入などが具体的な施策です。さらに、従業員に対しては、経営層が「顧客中心主義」や「長期的なビジョン」を継続的に発信しています。
これらの変革は、トップダウンの指示だけでなく、現場の声を反映しながら進められ、チームに意思決定権を与える分散型リーダーシップが特徴です。
これによりIKEAは、変化をおそれずに受け入れる企業文化を育て、顧客価値の最大化と持続的な成長を実現しています。
富士フイルム株式会社
富士フイルムは、かつて写真フィルム市場の縮小という危機的状況に直面しました。しかし、事業の多角化と新規分野への進出によって劇的な変革を成し遂げています。
鍵となったのが、課長層に対するチェンジマネジメント強化施策「FF-CMP」です。2008年より2泊3日の研修と半年後のフォロー研修を組み合わせ、管理職が自ら変革を体現する意識変革に取り組みました。
従来の手堅い企業文化から、挑戦的でスピード感ある体制へ脱皮する土台を築いています。
アドビ株式会社
アドビ株式会社は、パッケージ型ソフトウェアからクラウドベースの「Creative Cloud」へ移行しました。この取り組みはビジネスモデル転換の象徴的な事例として知られています。
かつてはパッケージ版の売り切り型を主流としていましたが、クラウド型サブスクリプションモデルへの移行を決断しました。これにより、収益構造や顧客との関係性が大きく変化しています。
変革の過程で従業員や顧客への丁寧な説明とサポートを重視し、段階的な移行を進めたことが成功した理由のひとつです。さらに、データ活用や顧客体験の向上にも注力し、変化をチャンスと捉える企業文化を醸成しています。
このような戦略が功を奏し、クラウド移行を成功させ、現在のサブスクリプション中心のモデルへと変革を遂げています。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
7.まとめ
現代の企業は、目まぐるしく変わる市場環境や技術革新に対応しながら、継続的に自らをアップデートしていくことが求められます。
どんなに優れた戦略や先進的なシステムを導入しても、それを運用する人材が変化に対応できなければ、望ましい成果にはつながりません。
そのため、変革を成功へ導くには「人」に着目し、従業員が新たな仕組みに順応できるよう後押ししましょう。自らの行動を前向きに変えていけるような環境づくりが重要です。
チェンジマネジメントは、この人的側面を中心に据え、変化を着実に根付かせるための体系的なアプローチです。組織の変革成功を支える大きな役割を担うでしょう。
