OJTとは、実務を通してマンツーマン指導により知識・スキルを身につける育成手法です。実務を通した研修となるためスキル・知識の定着化が早く、新人や未経験者の早期戦力化に期待できます。
OJTとは何かをふまえながら、OJTを取り入れるメリット・デメリットや具体的な取り組み、進め方などを解説しましょう。
目次
1.OJTとは?
OJT(On the Job Training)とは、上司や先輩社員がマンツーマンで部下や後輩の指導にあたり、実務をとおして知識やスキルを身につける人材育成の手法です。「指導→実践→フィードバック→改善」のサイクルでスキル習得を促します。また1対1の指導から、相互理解を深められるメリットもあります。
厚生労働省 令和3年度『能力開発基本調査』によると、計画的なOJTを行っている企業は59.1%。約半数の企業がOJTを実施しています。
参考 令和3年度「能力開発基本調査」の結果を公表します厚生労働省2.OJTで教育・研修を行う理由
OJTを取り入れている企業は約半数と一般化しつつあります。しかしなぜOJTで教育・研修を行うのでしょうか。ここでは、その理由を解説します。
- 人材の早期戦力化
- 定着率向上
- 人事施策・業務効率の最適化
- 育成側の成長・スキルアップ
①人材の早期戦力化
OJTは実務をとおして必要な知識・スキルを身につけられるため、早期育成につながります。インプット・アウトプットのサイクルが確立されているためスキルの定着も早く、新入社員や未経験者、中途社員の早期戦力化に有効です。
OJTトレーナーを中心にマンツーマンで個人のレベルに合わせた段階的な指導ができるため、教育される側の負担が減る効果も期待できます。
②定着率向上
新入社員や中途社員はわからないことも多く、業務を進めるうえで不安も多いもの。OJTでは、そうした不安を解消しつつ、上司や先輩社員とのコミュニケーションを深めながら指導が受けられるため、孤立化の防止につながります。
また精神的な不安の解消にもつながり、早期離職の防止に有効です。OJTをとおして上司や先輩社員との関係が構築されれば、心理的安全性の向上から帰属意識も生まれるでしょう。
③人事施策・業務効率の最適化
教える側も知識やスキルの再確認となり、さらなるスキルアップにつながります。教えられる側も実務をとおしてスキル・知識のインプット・アウトプットができ、効率的に成長できるため、業務全体における効率化に有効です。
またOJTでは個別に指導するため、対象者の適性や素質が把握しやすい点もメリットのひとつ。育成の方向性が固まりやすく、強みや適性を生かした適材適所な人材配置も検討しやすいため、人事施策の最適化にも役立ちます。
④育成側の成長・スキルアップ
OJTで成長できるのは、教育される側だけではありません。教える側も業務に関するスキルはもちろん、マネジメントや対人スキルの向上が望めるなど、成長の機会が得られるのです。
将来的に管理職を目指す場合、OJTの経験は必ず役に立ちます。スキルアップやキャリアアップの際、OJTがよい機会を与えてくれるでしょう。

OJTトレーナーとは? 役割や抱える悩み、向いている人の特徴を解説
OJT(On the Job Training)は、新入社員や若手社員が実践を通じてスキルや知識を習得する育成手法です。
その指導を担うOJTトレーナーは、業務を教えるだけでなく、計画的な育成や適切な...
3.OJTとOFF-JTの違い
OJTとOFF-JTの主な違いは、研修場所と指導者です。
OFF-JTとは「Off The Job Training」の略で、現場を一時的に離れて研修やセミナーで知識・スキルを体系的に学ぶこと。実務とは別で実施される、新入社員の新人研修や中堅社員向けの管理職研修などの集合研修がOFF-JTにあたります。
一方、OJTは社内で実務をとおして行う研修です。
また、OFF-JTの指導者は職場の上司や先輩ではなく、外部講師や人材育成担当者になります。基本は座学となり、内容に応じてグループワークも行うのです。最近では、eラーニングといったオンライン講座の形式も増えています。
OFF-JTでは体系的に知識・スキルを学べるもののが、すぐにアウトプットできない点はOJTとの違いです。

OFF‐JTとは|OJTとの違い、メリットや具体例などを紹介
人材情報から戦略的育成を!
カオナビならOFFJTなどの研修履歴がわかるから、計画的な人材育成ができます。
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロー...
4.OJTのメリット
OJTのメリットは、以下4つです。各メリットを詳しくみていきましょう。
- 知識・スキルの習得が早い
- 個人のレベルやタイプに合わせた育成ができる
- コミュニケーションの活性化につながる
- 教育コストがおさえられる
①知識・スキルの習得が早い
OJTでは、実務をとおしてインプット・アウトプットを行えるため、知識・スキルの習得や定着が早くなり、早期戦力化に有効です。
マンツーマンできめ細かに指導でき、フィードバックもすぐにできるため、教育される側もわからないことがその場ですぐに聞けます。
②個人のレベルやタイプに合わせた育成ができる
個人のスキルレベルや個性・性格などのタイプ、成長速度に合わせた育成ができる点も大きなメリット。集合研修では画一的な育成しかできず、人によって差が出てしまう場合もあるでしょう。
また、OJTでは苦手なところを重点的に教えるといった、研修内容のカスタマイズも可能です。教育される側も自分のペースやタイプに合った研修・教育が受けられるため、無理なく着実に成長できます。ただし、こうしたメリットを得るには指導者の質が重要です。
③コミュニケーションの活性化につながる
指導側と指導される側は業務をとおしてコミュニケーションを深められ、良好な関係性が築くきっかけになります。コミュニケーションの活性化は、エンゲージメントやモチベーションの向上につながる重要な要素です。
組織・チームとしてもOJTに取り組んでいけば、社内全体のコミュニケーション活性化につながるでしょう。
④教育コストがおさえられる
外部で研修やセミナーを行う必要がないため、教育コストがおさえられる点もメリットです。実務に関するスキルや知識はOJTで身につくため、それ以外に必要な教育にコストがかけられ、教育コストの最適化につながります。
5.OJTのデメリット
一方で、OJTには以下のようなデメリットもあります。
- 指導側の負担が大きい
- 育成成果が指導者に左右される
- 現場のリソースが減ってしまう
①指導側の負担が大きい
指導側は通常業務にOJTがプラスされるため、単純に業務が増えます。指導する側の負担が大きくなり、業務に支障が出ては本末転倒でしょう。指導者に負担が偏らないためにも、指導側への配慮・サポートが求められます。
企業やチーム全体でOJTに取り組む意識を持ち、指導者をフォローする体制を整えることが大切です。
②育成成果が指導者に左右される
OJTは現場社員に育成を一任する手法です。そのため、指導者の能力やスキルレベル、意欲によって、育成結果にばらつきが生じる恐れもあります。
こうしたデメリットを解消するためにも、指導者側の教育やスキルアップにも力を入れる、OJTのマニュアル化やOJTを評価基準に組み込んでモチベーションを上げるなど、企業側が指導者をバックアップしましょう。
③現場のリソースが減ってしまう
チームメンバーがOJTに取り組むと、現場のリソースが減ってしまいます。業務が通常どおり進められず、残業などが発生してしまう場合もあるでしょう。
OJTを実施する分、通常よりリソースが減ってしまうことを念頭に、効率的に業務を進める意識が求められます。管理職は部署やチームの業務状況を把握し、業務の偏りなどがないかをチェックしながらOJTを進めていきましょう。
6.OJTの取り組み具体例
OJTという手法は同じでも、企業によってその取り組み方はさまざまです。ここでは、2社からOJTの取り組みの具体例をご紹介します。
- マルハニチロ
- サントリーホールディングス
①マルハニチロ
マルハニチロでは、新人教育にOJTを導入。入社1年間はOJTリーダーと呼ばれる先輩社員を中心に新人社員をサポートしています。先輩社員は業務の指導のみならず、目標設定や日々の悩みまで相談するなど、あらゆる面で新人社員を支えているのです。
OJTリーダーだけでなく、職場全体で新人を育てる意識をつねに大切に新人教育を行っています。さらに、一人ひとりの成長に合わせてOFF-JTを行って、手厚い人材育成に取り組んでいるのです。
②サントリーホールディングス
サントリーホールディングスでは2007年度よりコーチャー制度(OJT)を整備し、新入社員の育成を強化しています。コーチャーは、新人の配属先が決まってから社長・部長・人事が話し合って決定されるのです。
コーチャーに対しても「新人を教える経験をとおして、今後、部下を育てられる人材になってほしい」と目的を明確にしています。OJTやOFF-JT、自己学習課題などの手厚い研修をとおして新入社員の戦力化に取り組んでいるのです。
7.OJTの進め方
下記で、OJTの進め方をステップ別にご紹介します。
- 目標設定・計画書作成
- 指導者の選定
- OJTの実施
- 評価・改善
①目標設定・計画書作成
OJTを通してどういった成長を望むか、どういった人材を育成したいかを明確化し、目標に落とし込みます。
目標設定は人事と現場が連携し、部署ごとに目指すゴールを細分化することがポイント。ハイパフォーマーの行動特性を把握し、早期戦略化を目指して研修内容を逆算的に決めていくと効率的に進められます。
目標が決まったら具体的なOJT期間や研修内容を決めて、計画書に落とし込みましょう。
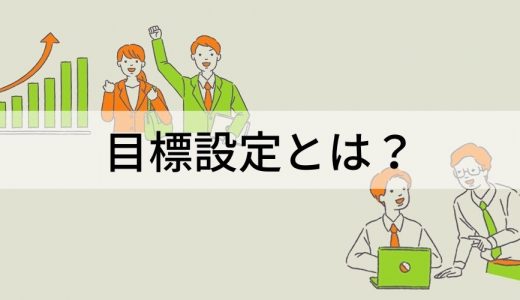
目標設定とは?【設定のコツを一覧で】重要な理由、具体例
目標設定は、経営目標達成や個人のレベルアップのために重要なもの。適切な目標設定ができないと、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやるべきことも洗い出せなくなってしまうでしょう。
今回は...
②指導者の選定
OJTは指導者によって成果が左右される恐れもあるため、適した人材の選定が重要です。適性を見極めて選定したのち、OJT開始まで期間がある場合は必要な研修を受けて、スキルを磨いておくとよいでしょう。
③OJTの実施
OJTは下記ステップで実施し、その後はその繰り返しです。
- Show:やってみせる
- Tell:説明・解説する
- Do:やらせてみる
- Check:評価・指導
まずは実際にやってみせて、業務の流れややり方を理解してもらいます。その際、細かい部分やポイントを説明し、わからない点がないか、確認しながら進めていきましょう。その後はサポート体制をそのままに、実際に業務に対応してもらうのです。
実践後は振り返りを行い、必要に応じて追加で指導します。できている点は褒めて、改善点はしっかり伝えると、モチベーションを上げながら知識・スキルの定着を図れるでしょう。
④評価・改善
計画書に沿ったOJTを実施し、目標まで到達したら双方の評価を行います。評価を踏まえて改善し、次のOJTに生かしていくことが大切です。
8.OJTがうまくいかない原因
なかには、OJT取り入れてもうまくいかなかったといケースもあるでしょう。その場合は、以下のような原因が考えられます。
- 指導側のスキル不足
- 不十分な指導体制
- コミュニケーション不足
- 振り返りの未実施
①指導側のスキル不足
デメリットにもあるように、OJTの成果は指導者のスキルに左右されやすい傾向にあります。うまく教えられていない、質問しにくいなどして、新人がOJTに不満を持ってしまう恐れも。
また、指導側もうまくできないことでストレスがかかり、不調をきたしてしまう可能性もあります。
指導に必要なスキルは、研修をとおして身につけられるのです。適性のある社員を選定するだけでなく、指導者がOJTに必要なスキルが見につけられる環境・機会を企業側が提供するとよいでしょう。
②不十分な指導体制
指導者側に負担がかかりすぎては適切な指導ができません。よって企業全体でOJTに取り組む意識が重要です。業務の調整や指導者への評価・フィードバックできる体制を整えて、組織全体でOJTをフォローする体制を整えましょう。
③コミュニケーション不足
OJT中のコミュニケーション不足は、新人のモチベーション低下や離職につながってしまうもの。コミュニケーション不足の原因は、通常業務が忙しく放置気味になってしまっている、相性的にコミュニケーションが取りにくいなどさまざまです。
慎重な人選だけでなく、OJTの実施状況を部署やチームが把握してフォローできる体制を整えることが求められます。

コミュニケーション能力とは? 低い原因や高める方法を解説
コミュニケーション能力は、他人との人間関係を良好に築くために必要不可欠なものです。また、仕事をするうえでも欠かせない能力の一つといえるでしょう。
今回は、
コミュニケーション能力の定義
コミュニケー...
④振り返りの未実施
教えて、実務を実践させるだけでは不十分です。実践後の成果や課題から、改善して取り組んでいって初めてスキルが向上・定着します。また指導者のやり方に対してもフィードバックを行い、改善から次の指導につなげていくとOJTの質も上がるのです。
9.OJT実施のポイント
下記で、OJT実施のポイントをお伝えします。OJTのメリットを得て成功に導くためにも、ポイントを押さえてOJTに取り組みましょう。
- 育成計画を立てる
- 社内全体で取り組む
- 新入社員への理解を深める
①育成計画を立てる
方針なしにOJTを進めると、企業が求める人材は育成されません。まずは、企業が求める人材像を明確にしたうえで全体に共有し、育成計画に盛り込みましょう。短期的・長期的な目標を決めたうえで育成計画を立てるのも欠かせません。
具体的には半年後・1年後にどうあるべきかを明確にし、そのために必要な期間や経験、研修内容を検討します。育成計画があると育成の進捗も可視化され、指導者のことも評価しやすくなるでしょう。
②社内全体で取り組む
担当者に任せきりにせず、社内全体でOJTに取り組む体制を整えるのがポイントです。担当者の教育体制を整備するほか、OJT期間の業務調整や担当者へのフィードバックを欠かさずやっていくと、社内で一体的に取り組めるためOJTの質も向上します。
バックアップ体制が整っていれば、担当者も安心してOJTに取り組めるでしょう。
③新入社員への理解を深める
OJTはマンツーマンでの指導となるため、担当者と新人の相性、新人を理解したうえでの適切な指導が重要です。新人の能力レベルや性格などのタイプを理解すれば、適切な担当者の選定や指導にも役立ちます。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる


