部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
少子高齢化が進む中、企業にとって「人材の確保と定着」はますます重要な経営課題となっています。中でも注目されているのが、社員の「離職理由」です。なぜ会社を辞めるのか、その背景を正確に知ることで、対策の方向性が見えてきます。
この記事では、20代・30代・40代それぞれの年代別に離職理由を徹底比較。さらに、企業が離職理由を把握すべき理由、定着率を高めた実際の事例、具体的な改善施策まで分かりやすく解説します。
目次
1.最新データで見る離職理由ランキング【年代別完全比較】
厚生労働省が「令和5年雇用動向調査」の結果を発表しました。この調査は、全国の主要な産業を対象に、入職・離職の人数やその内訳(性別・年齢階級)、さらに離職の理由などの実態を把握するために行われたものです。
ここでは、その調査データをもとに、年代ごとの代表的な個人的離職理由を紹介します。
20代の離職理由
まずは、20代や若手社員の離職理由を詳しく見てみましょう。
2位:賃金等が低かった
3位:仕事内容に満足しなかった
4位:人間関係がうまくいかなかった
1位:労働条件(賃金以外)が悪かった
20代の離職理由で最も多かったのは、「労働条件(賃金以外)が悪かった」です。具体的には、長時間労働や休日出勤の多さ、休暇の取りづらさなどが考えられます。
特に若年層はワークライフバランスを重視する傾向が強く、過度な労働時間や柔軟性のない勤務体制に不満を感じやすいです。また、労働環境の改善を求めても上司や経営陣に聞き入れてもらえないと、離職を決意するケースもあります。
2位:賃金等が低かった
「賃金等が低かった」も、20代の離職理由として高い割合を占めています。20代後半になると、生活費や将来の資金計画を考慮する中で、現在の収入に対する不満が増加します。
また、同年代の他社社員との給与比較や、昇給・賞与の見込みが薄いことも離職の要因となるでしょう。
3位:仕事内容に満足しなかった
「仕事内容に満足しなかった」も、20代の離職理由として多く挙げられています。入社前の期待と実際の業務内容とのギャップや、自分の興味・関心と業務の不一致が原因です
また、キャリアアップの機会が少ない、成長を感じられないといった点も不満につながります。
どんな仕事も経験として将来のキャリアに役立つと前向きに捉えられれば良いのですが、興味を持てない業務が続き、やる気を失った状態が長引くと、転職を検討するきっかけになってしまいます。
4位:人間関係がうまくいかなかった
職場の人間関係の悪化も、20代の離職理由として上位に挙げられます。最近ではテレワークやオンライン会議の普及により、社内外での対面のやり取りは減っているものの、職場での人間関係に関する悩みは依然としてなくなりません。
上司とのコミュニケーション不足、パワハラ・セクハラなどのハラスメント、職場の雰囲気の悪さなどが原因に挙げられますす。特に若年層は、職場の人間関係に敏感であり、ストレスを感じやすい傾向があります。
30代の離職理由
次に、30代の離職理由ランキング上位4位を紹介します。
2位:賃金等が低かった
3位:労働条件(賃金以外)が悪かった
4位:会社の将来が不安だった
30代の離職理由は多岐にわたりますが、職場での人間関係や働きやすい環境、将来の安定性を求める傾向が見えます。
1位:人間関係がうまくいかなかった
30代の離職理由で一番多かったのが「人間関係がうまくいかなかった」です。この年代は、管理職やリーダーとしての立場になることが増え、上司・同僚・部下との関係が一段と複雑になります。
特に部下を持つようになると、チーム運営やコミュニケーションに悩む人も多いでしょう。
また、仕事への考え方や進め方の違いが衝突を生み、ストレスを抱えやすくなります。こうした人間関係の問題は、精神的な負担を大きくし、仕事へのやる気や満足感を下げる大きな要因となっています。
2位:賃金等が低かった
「賃金等が低かった」も、30代の離職理由として上位に挙げられます。この年代では、住宅購入や子育てなどのライフイベントが重なり、収入の安定性や将来性を重視する傾向があります。
そのため、給与や賞与が期待に届かないと、将来への不安や不満が強まり、離職を考えるようになるでしょう。
3位:労働条件(賃金以外)が悪かった
30代の離職理由3位は「労働条件(賃金以外)が悪かった」です。30代は、仕事と家庭の両立やプライベートの充実を重視する傾向が強くなります。
そのため、ワークライフバランスが取れない職場や、働き方の柔軟性に欠ける環境では、長く働くことが難しいと感じる人が増えるでしょう。
4位:会社の将来が不安だった
「会社の将来が不安だった」という理由も、30代の離職理由として無視できません。企業の業績悪化や経営方針の不透明さ、業界自体の先行きへの不安などがあると、安定したキャリアを築きたい30代にとっては大きなリスクと映ります。
家庭を持ち、将来設計を立てる人が多いこの年代にとって、会社の安定性や成長性は欠かせない要素です。
40代の離職理由
続いて、40代の離職理由を見てみましょう。
2位:労働条件(賃金以外)がよくなかった
3位:賃金等が低かった
4位:仕事内容に満足しなかった
40代の離職理由には、30代と共通する点も多く見られます。ただ、年齢を重ねるにつれて、職場の人間関係や仕事内容が大きく変化することもあり、そうした変化がきっかけで退職を考える人も多いようです。
ここでは、40代に多い離職理由の上位4つを詳しく見ていきましょう。
1位:人間関係がうまくいかなかった
40代の離職理由で最も多かったのは、「人間関係の悩み」でした。30代と同じく、職場での人付き合いが原因になることが多いようです。
この年代は、上司と部下の間に立つ中間管理職としての役割を担うことが多く、両方の立場に配慮するあまり、精神的な負担を抱えやすくなります。
また、若手社員との価値観の違いや、年上の上司との考え方のズレから、意思疎通に苦労する場面も増えていきます。さらに、社内での派閥や意見の対立がストレスの原因となり、結果的に退職を決断するケースも少なくありません。
2位:労働条件(賃金以外)がよくなかった
「労働条件(賃金以外)」への不満も、40代の離職理由として大きな割合を占めています。例えば、慢性的な残業や休日出勤が続くことで、家庭で過ごす時間が減ってしまい、子どもとの関わりが持てなくなることがあります。
そうした生活が続けば、心身ともに疲弊し、仕事への意欲を失う原因にもなるでしょう。
さらに、表向きには「定時退社」や「残業禁止」を掲げていても、実際には人手不足で業務を終えきれず、やむを得ず自宅で仕事をこなすという実態も見られます。このような状況は、従業員の健康や家庭生活に悪影響を及ぼすとして、問題視されています。
3位:賃金等が低かった
40代になると、キャリアやこれまでの経験に見合った報酬を求める意識が一段と強まります。一方で、昇給や賞与が見込めない、業務量や責任に対して給与が釣り合っていないと感じると、会社に対する信頼が揺らぎ、将来への不安も膨らんでいくでしょう。
さらに、家族を支える立場にある人も多く、生活費や子どもの教育費などの出費が増えるため、収入への不満から転職に踏み切ることもあります。
4位:仕事内容に満足しなかった
「仕事内容に満足しなかった」も、40代の離職理由として挙げられています。40代では、これまでの経験やスキルを活かし、よりやりがいや成長を感じられる仕事を求めます。
しかし、現在の職場で自分のスキルや強みが十分に発揮できていないと感じると、転職を考えるきっかけになるでしょう。
これからの人生をより充実させたいと考える中で、自分の力を正当に評価してくれる職場を求めるのは、ごく自然な流れと言えます。
新しい環境で、これまでの経験を活かしながら成長していきたいという思いが強まるのも、この年代ならではの特徴です。
参照:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.今、企業が離職理由を正確に把握すべき理由
企業が離職理由を正確に把握することは、持続的な成長と組織力強化のために不可欠です。若手社員の3人に1人が3年以内に離職している現状では、企業が原因を見極めて早期に対策を講じることが、安定した経営の基盤となります。
ここでは、離職理由を分析するメリットとその活用方法を解説します。
組織の課題を明確にし、改善策を講じるため
従業員が退職を決意する背景には、職場環境や業務内容、人間関係など、さまざまな要因が存在します。これらの離職理由を正確に把握することで、企業は内部の問題点を明確にし、適切な改善策を講じることができるでしょう。
退職者への面談やアンケートを通して得られる情報は、表面的な理由だけでなく、根本的な原因の発見にもつながります。こうしたデータをもとに組織改革を進めることで、同様の理由による離職を未然に防ぐことができ、企業の健全な成長に繋がります。
従業員のエンゲージメントを向上させるため
従業員が自らの業務に意義を感じ、組織に対する愛着や貢献意欲を持つことは、企業の生産性や創造性を高める上で重要です。離職理由に目を向け、従業員の不満や課題に対処することで、エンゲージメントの向上が期待できます。
エンゲージメントが高い職場は、従業員の定着率が上がり、組織全体のパフォーマンスも向上します。逆に、離職の課題を後回しにすると、職場の士気やモラルの低下を招き、残る従業員の生産性にも悪影響を及ぼすリスクがあるでしょう。
採用・育成コストを削減するため
離職者が増加すると採用や育成にかかるコストが膨らみ、ノウハウや人材の流出による生産性低下も避けられません。近年は採用市場が厳しく、優秀な人材の確保が難しくなっているため、既存社員の定着は企業経営の大きな課題です。
離職理由を正しく把握し、的確な対策を講じることで、離職率を下げ、採用や育成にかかるコストを大幅に削減できます。
企業の評判を守るため
離職理由を放置し、同じ問題が繰り返されると、退職者による口コミやSNSでの評判が悪化し、企業イメージに大きなダメージを与える恐れがあります。現代は情報が広まりやすく、離職率の高さは求職者から敬遠される要因となります。
逆に、離職理由を分析し、改善に努めている企業は「社員を大切にする会社」として評価され、優秀な人材の応募や定着にもつながるでしょう。企業のブランド力維持・向上のためにも、離職理由の把握と改善は不可欠です。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.厚生労働省データから見る離職理由の現状と問題点
厚生労働省が発表した「令和5年雇用動向調査結果の概況」のデータをもとに、離職理由の現状と問題点を解説します。
厚労省が発表する「離職理由」統計の重要ポイント
厚生労働省が発表した「令和5年雇用動向調査結果」によると、2023年の入職者数は約850万人、離職者数は約798万人で、入職超過の状況が続いています。離職率は15.4%と前年より上昇し、特に25~29歳の若年層の離職率が高いことが特徴です。
この結果は、労働市場が依然として流動的であることを示しており、企業にとって人材の定着が大きな課題であることがうかがえます。
男女別で見ると、男性は入職率が14.3%、離職率が13.8%で、わずかに入職が上回っています。女性も同様に、入職率が18.8%に対し離職率が17.3%で、こちらも入職者の方が多い結果となりました。
また、雇用形態別に見ると、フルタイムで働く一般労働者は入職率・離職率ともに12.1%で均衡しています。一方、パートタイム労働者に関しては、入職率が27.5%、離職率が23.8%となっており、入職者の方が多い傾向が見られました。
参照:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
現状の問題点
現状の大きな問題点として、離職理由の多くが「労働条件」や「賃金」、「人間関係」など、企業の制度や職場環境に起因している点が挙げられます。
特に若手社員では「給与水準が低い」「仕事内容に満足しなかった」といった理由が目立ち、経済的安定ややりがいを求めて転職を選ぶ傾向が強まっています。
また、女性の場合は「職場の人間関係」も大きな離職要因となっており、職場内のコミュニケーションやハラスメント対策の遅れが課題といえるでしょう。
データから見える課題と企業への示唆
厚生労働省のデータからは、離職理由の多くが企業の努力次第で改善可能であることが明らかです。
一方で、「その他の個人的理由」も高い割合を占めており、企業側が離職理由を十分に把握できていない、あるいは本音を引き出せていない現状も浮き彫りになっています。
このため、企業は定期的なサーベイや面談を通じて従業員の声を吸い上げ、働き方や待遇、職場環境の改善に積極的に取り組むことが求められます。また、離職防止策を講じる際は、画一的な対応ではなく、年代や属性ごとの傾向を踏まえた施策が必要です。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.社員定着率を劇的に改善した企業の実践事例
ここでは、離職率の改善に取り組み、社員定着率を劇的に改善した企業事例をご紹介します。
サイボウズ株式会社
サイボウズ株式会社は、かつて28%だった離職率を約4%まで改善しました。その背景には、社員のライフスタイルや価値観に応じた柔軟な働き方を可能にする「働き方宣言制度」の導入があります。
週3勤務、時短勤務、リモートワーク、副業など多様な働き方を選べるようにし、さらに最大6年の育児休暇や退職後の復職を可能にする「育自分休暇」なども整備しました。
一方で、働き方の多様化により雑談の減少やメンバーの様子が見えにくいという課題も生じました。これを解決するために導入されたのが「分報」です。
これは社内版X(旧Twitter)のような仕組みで、業務の進捗から日常の感情まで自由に共有でき、リモート環境でもチームのつながりを保つことに貢献しています。こうした取り組みを通じて、社員の満足度や定着率が大きく向上しています。
参照:サイボウズ株式会社「離職率28%、採用難、売上低迷。ボロボロから挑んだサイボウズのハイブリッドワーク10年史」
株式会社エムティーアイ
株式会社エムティーアイでは、タレントマネジメントシステム「カオナビ」の導入をきっかけに、離職率を20%台から10%以下へと大幅に改善しました。
従来は人事情報が一元管理されておらず、社員情報を検索するのに時間がかかっていましたが、カオナビ導入後は人事部全体で情報を共有し、社員の希望やキャリアを加味した適切な人材配置や育成が可能となりました。
さらに、テレワークの全社導入、健康経営の増進など、従業員が心身ともに健康で働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいます。これらの施策により、社員の満足度や働きやすさが向上し、離職理由の根本解決に結びついています。
参照:カオナビ導入事例「カオナビを活用して2年。コミュニケーションが活発化したことで離職率が20%から10%に激減しました」
参照:株式会社エムティーアイ「人事」
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.離職を改善するための効果的な対策と具体的な施策
離職を防ぐためには、どのような取り組みが有効なのでしょうか。ここでは、特に効果が高いとされる8つの具体的な対策を紹介します。
- 待遇や労働環境を改善する
- 評価制度を見直す
- サーベイを実施する
- 社内コミュニケーションを促進する
- 部署異動を促す
- 柔軟な働き方を推進する
- マネジメントスキルを高める
- タレントマネジメントシステムを導入する
待遇や労働環境を改善する
待遇や労働環境の改善は、離職理由の中でも常に上位に挙げられる重要な課題です。具体的な改善策としては、まず給与や賞与の水準を業界平均と比較し、見直しを行うことが挙げられます。
さらに、残業時間の削減など、社員が安心して長く働ける環境づくりが不可欠です。福利厚生の充実も、従業員の満足度向上に直結します。例えば、住宅手当や育児・介護支援、健康診断の実施など、社員のライフステージに合わせた多様な制度を用意することが求められます。
待遇改善は、社員の経済的な安心感を高め、長期的な定着につながります。
評価制度を見直す
将来のキャリアに対して不安を抱える原因として、社内の評価制度や教育体制の不備があることが少なくありません。社員が自分の努力や成果が正当に評価されていないと感じると、モチベーションが低下し、やがて離職につながります。
そのため、評価制度の透明性・公平性・納得性を高めることが重要です。具体的には、評価基準やプロセスを明確にし、評価内容を社員にしっかり説明することで、上司の主観や感情による偏りを防げます。
また、360度評価やバリュー評価など、多面的な評価手法を取り入れることで納得感を高めることも効果的です。
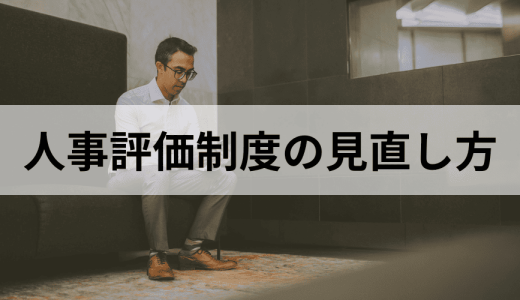
人事評価制度はどう見直す? 見直しの目的やポイント、手順を解説
人事評価制度は、適切なタイミングで見直しが必要です。なぜなら、人事評価制度は企業と従業員の双方に大きく影響する重要なツールであるためです。
人事評価制度が古かったり、機能していないと感じる場合、従業員...
サーベイを実施する
離職を防ぐには、社員がどんな悩みや不満を抱えているかを把握することが不可欠です。そのための手段として、定期的にエンゲージメントサーベイやストレスチェックを実施することが有効です。
特に近年注目されている「パルスサーベイ」は、短時間・高頻度で社員の満足度やストレス度合いを測定できるため、離職の兆候を早期に発見することが可能です。
調査結果をもとに、問題点を迅速に改善することで、社員の満足度向上や離職防止につなげることができます。サーベイは匿名性を担保し、率直な意見を集めることが大切です。
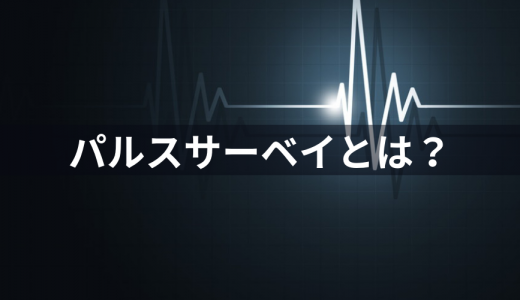
パルスサーベイとは? 意味や目的、導入メリット、質問項目例
パルスサーベイとは、従業員の離職防止や満足度向上を目的に短いスパンで行う意識調査のこと。従業員の離職や満足度に課題を抱えている場合、解決の糸口としてパルスサーベイの実施を検討している企業も多いでしょう...
社内コミュニケーションを促進する
職場の人間関係やコミュニケーションの不足は、離職理由の一因となります。企業は、上司と部下、同僚間の円滑なコミュニケーションを促進する取り組みを行うことが重要です。
具体的には、定期的な1on1ミーティングやチームビルディング活動を実施することで、信頼関係の構築や情報共有の活性化が図れます。
また、社内SNSやチャットツール、リフレッシュスペースの設置など、日常的に気軽に話せる環境づくりも効果的です。
コミュニケーションが円滑になることで、社員同士の信頼関係が強まり、悩みや不満も早期に解消できるため、離職防止につながります。

コミュニケーションとは? 大切な理由、円滑にするポイントを解説
コミュニケーションとは、伝達や意思疎通、あるいはこれらを示す行動のことです。ここではコミュニケーションの重要性やコミュニケーション能力を高めるメリット、コミュニケーション能力不足がもたらす悪影響などに...
部署異動を促す
部署異動は、従業員の離職理由の中でも「人間関係の悪化」や「仕事内容への不満」への有効な対策となります。
長期間同じ部署にいることで生じやすい人間関係の摩擦や、業務内容に対するマンネリ感を解消できるからです。異動により新たな環境や業務に触れることは、キャリア形成にもつながります。
企業側も、社員の適性や希望を把握したうえで計画的に異動を行うことで、離職リスクの高い社員の早期発見や配置転換による定着率向上が期待できます。
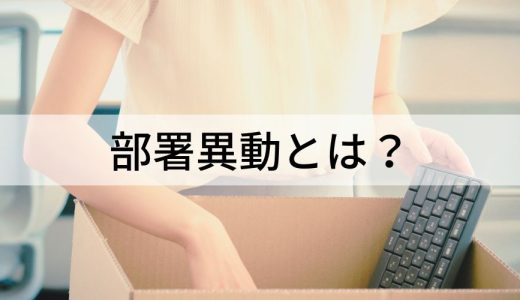
部署異動とは? 実施理由やメリット・デメリット、進め方を解説
部署異動は、会社が従業員に対して行う配置転換のひとつです。従業員が新しい環境でチャレンジすることや、スキルアップを図るため、または人材育成、組織の活性化、新規事業の立ち上げなど様々な目的で実施されます...
柔軟な働き方を推進する
近年、ワークライフバランスを重視する働き方が一般化し、柔軟な勤務制度の導入は離職防止策として欠かせません。フレックスタイム制やテレワーク、時短勤務制度を導入し、社員がライフステージや家庭の事情に合わせて働ける環境を整えることが大切です。
また、有給休暇の取得推進や、育児・介護休業の利用促進も、社員の満足度向上と定着率アップに直結します。こうした取り組みは、単に離職率を下げるだけでなく、採用力の強化や企業イメージの向上にもつながるでしょう。
マネジメントスキルを高める
上司と部下の関係がうまくいかないことが、社員の離職を引き起こす原因になることがあります。
例えば、上司の指導の仕方がきつかったり、言い方が強すぎると、部下はストレスを感じてしまうかもしれません。こうしたトラブルを防ぐためには、上司のマネジメント力を高めることが大切です。
そのための方法として、上司向けのマネジメント研修を行い、適切な指導方法やコミュニケーションの取り方を学んでもらうことが効果的です。スキルが身につけば、部下の成長をしっかりサポートできるようになり、職場全体の人材育成にもつながります。
また、上司と部下の信頼関係を築くには、1on1ミーティングもおすすめです。お互いの気持ちや考えを共有する機会が増えることで、双方の理解が深まり、職場での安心感や定着率にも好影響をもたらします。
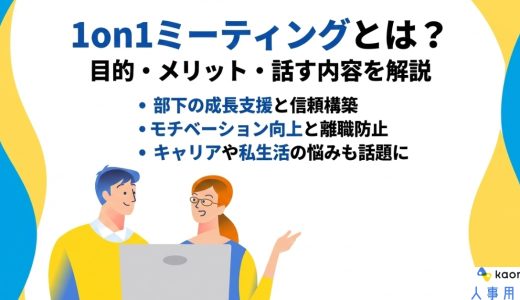
1on1とは? 目的とやり方、メリットや話すことがなくても失敗しない方法を解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
現在では多くの企業が導入する1on1とは、上司と部下が定期的...
タレントマネジメントシステムを導入する
タレントマネジメントシステムは、社員一人ひとりのスキルや経験、キャリア志向をデータで管理し、それぞれに合った配置や育成をサポートするシステムです。
社員の成長意欲やキャリアビジョンに沿った業務や研修を提供でき、モチベーションの向上や離職防止につながります。
さらに、離職防止機能が備わっているシステムを活用すれば、仕事への満足度や成果の状況を定期的にチェックできます。これにより、離職につながる可能性のある兆候を早い段階で察知し、未然に対処することが可能です。

タレントマネジメントシステムとは?おすすめのツールや選び方・比較のポイントを紹介
タレントマネジメントシステムとは、従業員の個性やスキルといった人材情報を一元化・見える化することで、人材評価業務や人材育成などの人事業務に役立つシステムです。タレントマネジメントシステムを導入すること...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.まとめ
社員の離職率を下げ、定着率を高めるためには、まず「離職理由」の分析から始めることが不可欠です。表面的な退職理由だけでなく、実際にどのような背景や要因があるのかを多角的に把握することが、効果的な対策を考えるうえでの出発点となります。
また、離職理由の分析では「労働条件」「人間関係」「仕事内容のミスマッチ」など、よくある課題ごとに対策を講じることが重要です。
労働時間や休日の管理、評価制度の見直し、コミュニケーション活性化、柔軟な働き方の導入など、課題に応じた施策を段階的に実行することで、離職リスクを事前に低減できるでしょう。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」は、社員のスキルや志向をデータで管理し、最適な配置や育成を支援します。
アンケート機能やパルスサーベイを活用することで、離職の兆しがある社員を早期に発見し、早期の対策が可能。タレントマネジメントシステムを離職防止に役立てたい企業におすすめです。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)

