2015年の労働安全衛生法の改正により、従業員が常時50人以上いる事業場では、ストレスチェックの実施が法律で義務付けられました。しかし、現場では「やっても意味がない」「形だけで無駄」といった声も聞かれます。
せっかく実施しても結果が活かされなかったり、従業員が本音を話しにくいと、効果が十分に発揮されません。本来ストレスチェックは、メンタルヘルス不調を未然に防ぎ、働きやすい職場づくりにつなげる重要な仕組みです。
この記事では、ストレスチェックが「意味ない」と言われる背景や、そうならないための企業ができる改善策について、わかりやすくご紹介します。
1.ストレスチェックとは?
ストレスチェックとは、職場における従業員のメンタルヘルスを把握し、ストレスの程度を可視化するために実施する検査です。
従業員は、仕事の量、人間関係、職場の雰囲気などについての質問に答えることで、自分のストレス状態を客観的に知ることができます。
2015年に改正された労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員が在籍する事業場では、年に1回以上の実施が義務付けられています。回答の結果、ストレスが高いと判断された場合は、希望すれば医師との面談が可能です。
また、企業側は、集めたデータを部署ごとなどにまとめて分析し、職場環境の改善を求められています。
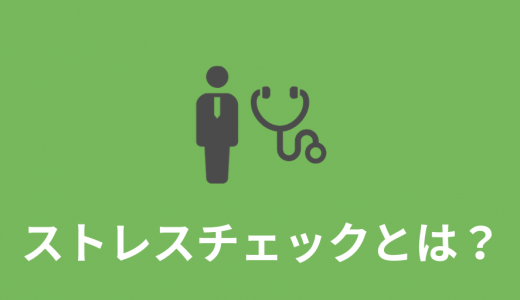
ストレスチェックとは?【実施方法を簡単に】義務化、目的
ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正によって50人以上の労働者がいる事業場で義務付けられた検査です。
定期的に労働者のストレスをチェックすることで、労働者が心身の状態に気付き、メンタルヘルスの不調...
タレントマネジメントシステム「カオナビ」ならコストを抑えて人事労務管理を効率化!
●紙やExcelの帳票をテンプレートでペーパーレス化
●給与明細の発行や配布がシステム上で完結できる
●年末調整の記入や書類回収もクラウドで簡単に
●人材情報の一元化・見える化で人材データを活用できる
●ワークフローで人事評価の運用を半自動化できる
⇒詳しくはこちらから
2.ストレスチェックが「意味ない」「無駄」と思われる5つの理由
従業員数が50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施が義務付けられていますが、なかには「実施しても効果がない」と感じている人も少なくありません。
そのように思われてしまう背景には、主に次の5つの理由が考えられます。
結果が活用されていない
多くの企業では、ストレスチェックを行い、結果を集計・分析するものの、その後に具体的な対応が取られないことがよくあります。
従業員が真面目に答えても、それが職場の改善に結びつかなければ、「結局何のためにやったのか」と疑問に思うのも無理はありません。
さらに企業側も、結果の活用方法が分からず、形だけの取り組みで終わってしまうこともあります。結果をきちんと活かすには、部署ごとの傾向をもとに環境を見直したり、従業員の声を聞きながら改善策を検討することが大切です。
目的が不明確
ストレスチェックが「意味ない」と感じられる理由のひとつに、「そもそも何のためにやっているのか分からない」という目的の不明確さがあります。
本来ストレスチェックは、メンタル不調の予防や職場改善を目的とした大切な制度ですが、企業がその意義をきちんと説明しなければ、ただの質問に答えるだけの作業として受け止められてしまい、「意味がない」「時間の無駄」と思われても仕方ありません。
制度を活かすには、まず目的を具体的に伝えることが重要です。
正直に回答できない場合がある
ストレスを抱えていても「会社に知られて評価が下がるのでは?」といった不安から、無難な答えを選んでしまうケースもあります。
本音で回答しないと正確なデータが得られないため、実際のストレス状態を反映できず、制度の意味が薄れてしまうでしょう。
職場にオープンな空気がない場合、こうした不安は一層強まる傾向にあります。そのため、従業員が安心して本音を伝えられるよう、匿名での回答を取り入れたり、集計結果の使用目的や管理方法を事前に丁寧に説明することが効果的です。
また、管理職や経営層が率先して制度の意義を発信することで、信頼感を高めることにもつながります。
産業医面談を受けづらい
高ストレスと判定された場合、産業医との面談を受けることができますが、実際には「時間がない」「申し出にくい」といった理由から、面談を受けない従業員も多く見られます。
また、「面談を受ける=メンタルに問題がある」と思われるのではないかと心配する人もおり、精神的ハードルが高いのが現実です。
企業側は、従業員が面談に参加しやすいような仕組みづくりを工夫することが大切です。
例えば、「仕事が立て込んでいて時間が取れない」といった声がある場合には、面談の日時を柔軟に設定できるようにし、希望者には就業時間外の対応も視野に入れるとよいでしょう。
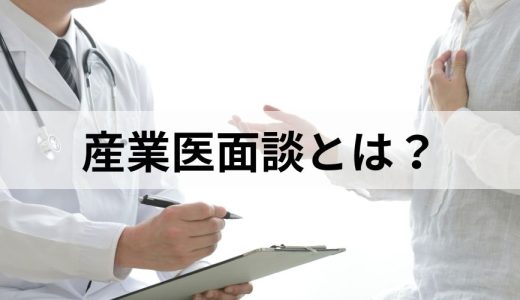
産業医面談とは?【種類と効果】何を話す? クビになる?
産業医面談とは、従業員の健康管理や労働環境の健康安全に関する取り組みの一環として行われる面談のことです。目的、効果、話す内容などを解説します。
1.産業医面談とは?
産業医面談とは、産業医が従業員の...
高ストレス者への対応が不足している
高ストレスと判定された人に対して、企業が十分な対応を取れていないケースも少なくありません。産業医との面談の実施だけで、その後のフォローがないままだと、本人の不調が改善されることなく放置されてしまう恐れがあります。
本来は、職場の配置転換や労働時間の調整など、具体的な支援策が求められますが、それが実施されないと、従業員の信頼は損なわれます。
面談の効果を高めるためには、産業医から企業への意見共有を積極的に促したり、企業と医療機関の連携体制をしっかり整えることが重要です。
こうした取り組みによって、面談が単なる形式ではなく、実際に役立つものだと感じられるようになります。
2025年4月から大幅改正!育児介護休業法の把握はできていますか?
「法改正ガイド」で、改正のポイントや対応すべき内容をチェックリストで確認!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
3.ストレスチェックの目的
ストレスチェックは、従業員のストレスレベルを可視化し、心の不調を早期発見して防ぐことを目的としています。さらに、職場の課題を把握し改善につなげるためにも、このチェックは企業にとって重要な手段となっています。
メンタルヘルス不調の未然防止
ストレスチェックの主な目的は、働く人のメンタルヘルスによる不調を未然に防ぐことです。うつ病や適応障害といった心の不調は、気づかないうちに進行してしまうことがあります。
ストレスチェックを通じて、早い段階で「危険なサイン」をキャッチできれば、専門家の支援や勤務調整といった対応につなげることができます。
「ストレスチェックは意味がない」と感じる人もいますが、こうした予防的役割を理解することで、その重要性が見えてくるはずです。
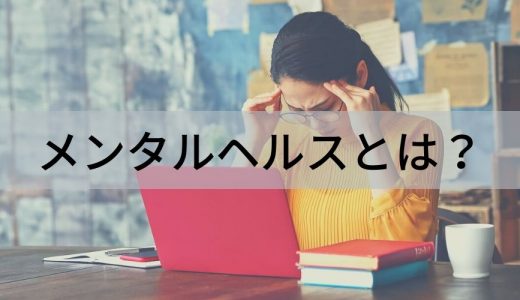
メンタルヘルスとは? 不調のサイン、職場でできるケアや対策を解説
メンタルヘルスとは、精神面・心の健康状態のこと。メンタルヘルスが不調な状態では仕事へのモチベーションや集中力などが低下し、生産性や業績の低下を招く恐れがあります。従業員の心身の健康のため、安定した経営...
労働者自身のストレス状態の気づき
ストレスチェックは、企業のためだけでなく、働く本人が自分の心の状態に気づくためにも行われています。特に職場では、忙しさや責任感から自分の限界に気づきにくく、悪化してから初めて対処するケースも少なくありません。
質問に答えることで、自分の仕事の状況、周囲の環境、そして心身の健康状態を振り返る機会を得ます。結果を通じて、自覚していなかったストレスの程度や原因を知ることができ、セルフケアの必要性に気づくきっかけとなります。
職場環境の把握
ストレスチェックは、個人だけでなく職場全体の環境を見直すためのツールでもあります。
チェック結果をもとに、部署ごとのストレス傾向や課題を分析すれば、「どの部門で過重な業務が発生しているか」「人間関係に問題があるのはどこか」といった具体的な課題が見えてきます。
これを受けて、企業が業務量の調整や職場内のコミュニケーション改善などに取り組めば、全体の働きやすさが向上するでしょう。
「ストレスチェックをやっても意味がない」と言われがちですが、結果を職場改革に活かせば、大きな変化を生む可能性があります。制度を活かすかどうかは、企業の姿勢次第とも言えます。

職場環境とは?【改善のアイディアは?】事例、配慮義務
社員は職場で多くの時間を過ごします。職場の環境は、そこで働く人に大きな影響を与えるといっても過言ではありません。職場環境については法律による定めがあります。
定めの詳細とともに、職場環境を改善した事例...
難しい年末調整の流れをわかりやすく!実務のポイントと効率化を解説。
「年末調整お悩みガイドブック」で、年末調整の基本を確認!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
4.意味のないストレスチェックのデメリット
意味のないストレスチェックを続けてしまうと、企業や従業員にとって、以下のようなデメリットが生じます。
コストと時間が無駄になる
ストレスチェックは、質問票の配布から回収、集計、結果の分析、産業医面談の対応まで、意外と多くの工数とコストがかかる取り組みです。
さらに、従業員も回答に貴重な時間を費やします。これらにかけた費用や時間が、職場改善や従業員のメンタルヘルス対策に結びつかないのであれば、企業にとって「成果の見えない投資」となってしまいます。
特に、ただ法律に従って形式的に実施しているだけでは、意味のある成果が得られず、担当者の負担ばかりが増える結果になりかねません。
そのうえ、従業員側にも「また無駄なことをやっている」という冷めた印象を与えてしまう可能性があります。
従業員の信頼を失う
ストレスチェックを実施するだけで終わり、その後の改善策やフィードバックがない場合、従業員は「やっても意味がない」と感じてしまいます。
特に、本音で答えたにもかかわらず、何の変化もなければ、次回以降は協力しようとしなくなるでしょう。
それだけでなく、会社が本気でメンタルヘルス対策に取り組んでいないと見なされ、企業への信頼そのものが揺らぐ可能性もあります。
従業員との信頼関係が弱まると、相談しづらい雰囲気が広がり、不調があっても声を上げづらくなります。「ストレスチェックは意味ない」と思われないためにも、結果を生かした具体的な行動が欠かせません。
メンタルヘルス不調の早期発見ができない
ストレスチェックの本来の役割は、メンタルヘルス不調の兆しを早めに発見し、適切なサポートにつなげることです。
しかし、チェック結果が放置されていたり、本人が正直に回答できない環境の場合、その機能はほとんど果たされません。
例えば、高ストレス者への産業医面談が実施されなかったり、職場環境の見直しが後回しにされると、不調が進行しやすくなります。
早期対応の機会を逃せば、休職や離職につながるリスクが高まり、本人だけでなく企業側にとっても大きな損失となります。
労務管理システムで、面倒な入退社手続きはどれくらい楽になる?
「入退社手続きガイド」で、労務管理システム導入のメリットをわかりやすく!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
5.意味あるストレスチェックを行うメリット
ここでは、意味あるストレスチェックがもたらす4つのメリットについて詳しく解説します。
従業員のセルフケアへの意識が高まる
ストレスチェックを定期的に実施し、結果を正しくフィードバックすることで、従業員が自分のストレス状態に気づきやすくなります。
日常業務に追われていると、自分の心身の限界に気づかないまま無理をしてしまうことも少なくありません。
ストレスチェックは、あらためて自分の状態を振り返るきっかけとなり、セルフケア意識を高める有効な手段となります。
メンタルヘルスに理解のある職場文化が育つ
厚生労働省が公表した「ストレスチェックの効果に関する調査研究結果等」によると、「職場全体でメンタルヘルスへの理解が深まった(27.8%)」など、企業がストレスチェックの成果を感じていることがわかっています。
ストレスチェックをきっかけに、会社全体でメンタルヘルスへの意識が高まると、従業員同士の理解やサポートし合う職場文化が育まれます。
例えば、管理職がチェック結果をもとに部下との会話の仕方を見直したり、チーム内で仕事の負担が偏らないように調整する動きが生まれることで、周囲の人の体調や気持ちに自然と気を配れるようになるでしょう。
こうした風土が醸成されると、ストレスを感じたときも一人で抱え込まずに周囲に相談しやすくなり、孤立を防ぐことにもつながります。
厚生労働省「ストレスチェックの効果に関する調査研究結果等」
職場環境の改善につながる
意味のあるストレスチェックは、職場環境の具体的な改善につながります。ストレスチェックの結果を分析することで、企業は職場全体のストレス傾向や特定の部署での問題点を客観的に把握できます。
例えば、ある企業では「休息時間の不足」が問題視され、快適な休憩スペースの設置や休憩時間の確保を徹底したことで、従業員の満足度が向上しました。
こうした課題に対して具体的な対策を講じることで、働きやすい環境づくりが進みます。職場の空気が改善されることで、従業員のモチベーションや生産性の向上も期待できます。
休職・退職防止につながる
高ストレス状態を早期発見し、必要な支援につなげることができれば、メンタル不調による休職や退職のリスクを大幅に減らすことができます。
特に、定期的なチェックを通じて従業員の変化に気づく仕組みがあれば、深刻な事態を防ぐことが可能です。ストレスチェックの効果を感じにくいとされる理由は、制度が対応や改善につながっていないことに起因しています。
しかし、チェック結果をもとに面談や業務調整が行われれば、従業員の安心感も高まり、結果的に定着率の向上にもつながるでしょう。

休職とは? 休職理由、手当金の申請・計算方法について
休職とは、労働者が自分の都合で会社を長期的に休むこと。ここでは、休職とは何か、そして業務外での病気やケガの療養で休職しているときに受け取れる傷病手当金などについて説明します。
1.休職の定義とは?
...

定着率とは? 計算方法や上げる方法、平均、離職率との違いを解説
定着率とは、入社した社員が何人残っているかを表す割合のこと。離職率との違い、定着率の計算方法、定着率を上げる方法などについて解説します。
1.定着率とは?
定着率とは、企業へ入社した社員が一定の期間...
労務業務を楽に!労務管理システムの選び方や比較ポイントを解説。
「労務管理システムガイド」で、自社に適したシステムがわかる!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
6.ストレスチェックを意味あるものにする5つの方法
ここでは、ストレスチェックをより有効に活用するための具体的な方法を5つご紹介します。チェックを形だけで終わらせず、従業員の心のケアや職場環境の向上にしっかり結びつけていきましょう。
- ストレスチェックの重要性を従業員に周知する
- 分析結果を職場環境の改善に活用する
- 高ストレス者に適切な対応をとる
- ストレス解消のための制度やサポートを整備する
- 専門機関との協力体制を整える
ストレスチェックの重要性を従業員に周知する
ストレスチェックを効果的に実施するには、まず従業員全員がその重要性を理解することが不可欠です。多くの企業では、ストレスチェックが義務化されているにもかかわらず、実際に受検する従業員は8割に満たないというデータがあります。
この状況を改善するためには、経営層や管理職が率先してストレスチェックの意義を理解し、全従業員に浸透させる必要があります。
具体的には、ストレスチェックの目的、意義、結果の活用方法について、定期的に情報共有することがポイントです。
また、ストレスチェックの結果が個人の評価に影響しないことや、プライバシーが厳重に保護されることを強調し、従業員の不安を取り除くことも大切です。
分析結果を職場環境の改善に活用する
結果を職場環境の改善に積極的に活用することが、ストレスチェックを意味あるものにする鍵となります。
例えば、特定の部署で長時間労働が常態化していることが判明した場合、業務プロセスの見直しや人員配置の適正化を検討できます。
また、コミュニケーション不足が原因でストレスが高まっている場合は、定期的な1on1の導入や、社内イベントの開催など、小さな取り組みからでも改善につなげることができます。
このように、分析結果を具体的なアクションにつなげることで、従業員のストレス軽減と職場環境の改善を同時に実現できるでしょう。
高ストレス者に適切な対応をとる
高ストレスと判定された従業員には産業医との面談を案内するだけでなく、業務内容や人間関係の悩みなどをヒアリングし、必要に応じて部署異動や勤務時間の調整といった具体的なサポートの検討が大切です。
個々の状況に応じた支援策を提供し、定期的なフォローアップを行いながら、改善状況を確認することも重要です。

フォローアップとは?【意味をわかりやすく解説】
従業員のコンディションを把握できていますか?
人材情報を一元化することで必要なフォローアップも見つけられます。
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウン...
ストレス解消のための制度やサポートを整備する
従業員が日頃からストレスに対処できる環境を整えることも欠かせません。
例えば、社内にリラックススペースや相談窓口を設けたり、定期的なカウンセリングの機会を提供したりするなど、ストレスをため込まないための仕組みづくりが効果的です。
また、有給休暇の取得促進や、リフレッシュ休暇の導入、フレックスタイム制度の拡充などが考えられます。さらに、ストレス解消のためのセミナーや運動プログラムを提供するのもおすすめです。
専門機関との協力体制を整える
ストレスやメンタルヘルスの課題は、専門的な知識や経験が必要になることも多いため、企業内だけで対応するのは難しい場合があります。そんなときは、産業医や外部のメンタルヘルス支援機関との連携が有効です。
【人事業務で足りない時間とヒトは、システムでカバーしませんか?】
カオナビならコストを抑えて労務管理・タレントマネジメントを効率化!
●紙やExcelの帳票をテンプレートでペーパーレス化
●給与明細の発行や配布がシステム上で完結できる
●年末調整の記入や書類回収もクラウドで簡単に
●人材情報の一元化・見える化で人材データを活用できる
●ワークフローで人事評価の運用を半自動化できる

