現状(As Is)と理想(To Be)の差を明確にすることで、課題が可視化され、解決への道筋を描ける手法が「As Is / To Beフレームワーク」です。
この記事では、ビジネスの現場で役立つ活用法をわかりやすく解説します。
1.As Is / To Beとは?
「As Is / To Be」とは、現状と理想のギャップを可視化するフレームワークです。
業務改善やプロジェクトの計画を立てるとき、まずは現状を正しく把握することからはじまります。どこに問題があるかわからなければ、適切な対策を講じることはできません。
「As Is / To Be」を使えば、目標と現実の差を客観的に捉えやすくなります。そのため、業務改善・採用活動・マーケティングなど、あらゆる分野で活用されています。
As Is
As Isとは、現在の状況や実態を明確にすることです。業務プロセス、人員配置、設備環境など、今ある状態を客観的に整理します。
たとえば、業務が滞っている原因が特定できない場合、As Isを通じて実際の業務フローや負荷のかかり方を可視化します。
それによって、見えなかった課題が浮き彫りになり、改善すべきポイントや無駄な業務が明確になります。
As Isは、すべての問題解決における出発点といえるでしょう。
To Be
To Beとは、理想的な状態や将来あるべき姿を明確にすることです。手順としては、組織やプロジェクトが目指す目標・ビジョンを具体的な形で描き出します。
理想像の設定により、進むべき方向性が定まり、関係者同士で目標を共有できます。同じゴールに向かって協力することも可能です。
また、To Beが明確になれば、現状とのギャップも把握できます。その差を埋めるために、どのような取り組みが必要なのかも、具体的に見えてくるでしょう。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.As Is / To BeモデルとCan beモデルの違い
As Is / To Beモデルは、現状と理想を比較し、そのギャップを埋める手段を検討するフレームワークです。現状(As Is)を起点に、目指すべき将来像(To Be)を設定し、課題の特定や改善策の立案に役立てます。
一方で、Can beモデルは、理想と現実のあいだにある「実現可能な目標」を定めるモデルです。
To Beの実現には、時間やコスト、人的資源といった多くのリソースが必要です。そのため、Can beモデルは、現実的なリソースや制約を踏まえたうえで、到達可能な目標を段階的に設定します。
これらのモデルは、対立する概念ではありません。むしろ、互いに補完し合いながら、段階的な課題解決を支援する関係です。
まずAs Isで現状を把握し、To Beで理想像を描きます。そのうえで、Can beを活用して中間目標と行動計画を立てることで、現実的な手段で目標達成に近づけるでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.As Is / To Beのフレームワークを使うメリット
As Is / To Beのフレームワークの活用によって、組織やプロジェクトの課題を構造的に整理できます。
具体的には、以下のメリットが得られます。
- 現状と課題の可視化
- 効果的な改善策の立案
- 目標設定と進捗管理の明確化
- 目標の共有と方向性の統一
現状と課題の可視化
As Isを丁寧に分析すると、これまで見えなかった課題やボトルネックが表面化します。現場での違和感の正体を、データや事実に基づいて明確にできます。
また、業務の流れを客観的に捉えることで、改善すべき領域が具体的になります。どこに問題が集中しているのか、何を優先すべきかが判断しやすくなるでしょう。
さらに、優先順位を決めることで、限られたリソースを適切に配分できます。最も重要なポイントにコストをかけられるため、改善に向けてより効果的に取り組めるでしょう。
効果的な改善策の立案
As IsとTo Beの間にあるギャップを分析することで、改善すべきポイントが明確になります。理想に近づくために必要なステップが具体化され、実行可能な施策が検討できるでしょう。
たとえば、現状の業務が非効率だとわかれば、To Beの姿を起点に、改善手段が見えてきます。システムの導入や業務フローの見直し、人材育成といったアプローチも浮かび上がるでしょう。
こうした分析を通じて、実効性のあるアクションプランを立案できる点が大きな強みです。

アクションプランとは? 書き方や具体例をわかりやすく解説
1.アクションプランとは?
アクションプランとは、目標を達成するための具体的なプロセスを示す行動計画のこと。業務の把握と適切な管理を目的に「誰が・いつまでに・何をするのか」をふまえた計画を具体的に...
目標設定と進捗管理の明確化
To Beを明確に描くことで、組織やチームが目指す目標が具体化される点もメリットです。目標が定まると、関係者が同じ方向に向かって行動できます。
さらに、現状とのギャップを数値で把握できれば、進捗状況を客観的に評価できます。必要に応じた軌道修正も可能となり、計画的なマネジメントが望めるでしょう。
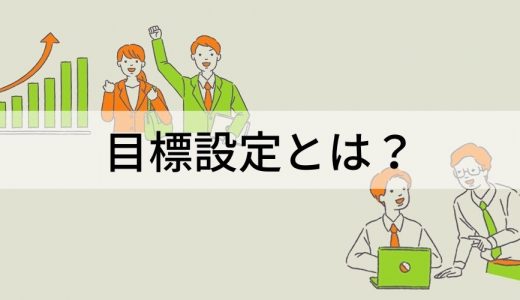
目標設定とは?【設定のコツを一覧で】重要な理由、具体例
目標設定は、経営目標達成や個人のレベルアップのために重要なもの。適切な目標設定ができないと、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやるべきことも洗い出せなくなってしまうでしょう。
今回は...
目標の共有と方向性の統一
To Beを明確に定義することで、組織全体が共通の目標を持てる点もメリットのひとつです。目指す方向が明らかになり、チーム全体の行動に一貫性が生まれます。
個々の判断もブレにくくなり、組織としての意思決定や対応がスムーズになります。結果として、チーム全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード4.As Is / To Beの使い方
As Is / To Beフレームワークは、問題解決や目標達成に向けて非常に有効な手法です。ここでは、その活用手順を7つのステップに分けて紹介します。
- テーマを決める
- 理想像を描く(To Beの定義)
- 現状を整理する(As Isの分析)
- 理想と現状のギャップを明確にする
- 課題に対する解決策を考える
- 解決策に優先度をつける
- 実行と振り返りを行う
①テーマを決める
フレームワークを活用するには、まず分析の対象となるテーマを明確にします。テーマは、企業戦略から日々の業務改善、個人の目標まで幅広く設定可能です。
設定時には、「期間」「関係者の範囲」「内容」の3要素を意識しましょう。簡潔な一文にまとめると、関係者間での共有が容易です。
たとえば、「半年以内に個人の月間営業売上を増加させる」など、具体性のある表現を用いることがポイントです。
②理想像を描く(To Beの定義)
次に行うのは、テーマに対して理想的な将来像(To Be)を描きます。この段階では、制約にとらわれず自由に「どうありたいか」を考えることが重要です。
たとえば、「半年以内に月間営業売上100万円を達成する」や「2026年までにリードタイムを30%短縮する」といった数値目標が有効です。
To Beが明確になれば、全員が共通のゴールに向かえるため、組織の意思決定にも一貫性が生まれます。
③現状を整理する(As Isの分析)
理想像を定めたあとは、現状(As Is)を正しく整理することが不可欠です。業務プロセスや問題点、使えるリソースの状態などを具体的に分析します。
たとえば、「案件ごとに進捗管理がバラバラで全体像が把握しづらい」「受注までに手間がかかり時間が浪費されている」など、現場の課題を明確にしましょう。
インタビューや業務の観察など、客観的な手法で情報が収集できれば、分析の精度が高まります。
④理想と現状のギャップを明確にする
To BeとAs Isを比較し、両者の間にあるギャップを具体的に洗い出します。このギャップこそが、解決すべき課題や改善すべきポイントです。
たとえば、「営業プロセスが標準化されていない」「顧客データの活用が不十分」など、理想と現状のズレを明確にします。
ギャップ分析を通じて、何をどのように変えるべきかが可視化されるため、次の改善策の立案がスムーズに進められます。
⑤課題に対する解決策を考える
ギャップによって明らかになった課題に対し、具体的な解決策を検討します。このステップでは、柔軟な発想で幅広くアイデアを出すことが重要です。
ブレインストーミングや関係者の意見交換を通じて、施策の選択肢を広げます。たとえば、「CRMシステムの導入」や「営業研修の実施」といった案が挙げられるでしょう。
実現可能性やコスト、効果なども比較検討しながら、最適な解決策を絞り込みます。
⑥解決策に優先度をつける
検討した解決策には、実行順序や重要度に応じた優先順位を設定します。限られたリソースを最大限に活かすためには、このプロセスが欠かせません。
緊急性や重要性、実現可能性、ROI(投資対効果)などの観点で評価します。「短期で実施可能な即効性のある施策」や「中長期で効果が見込める施策」に分類するのも有効です。
優先順位を決めることで、効率的に施策を展開し、成果の最大化が図れるでしょう。

ROI(投資利益率)とは?【意味をわかりやすく】計算方法と活用方法を解説
ROIとは「投資収益率」や「投資利益率」のことです。ここではROIの計算方法やメリットとデメリット、最大化する方法などについて解説します。
1.ROI(投資利益率)とは?
ROI(Return O...
⑦実行と振り返りを行う
優先順位に基づいて解決策を実行し、進捗を継続的に確認します。アクションプランには、具体的な施策内容、実施担当者、期限などを明記します。
実行後は、定期的な振り返りが重要です。成果を評価し、必要に応じて計画を柔軟に見直します。この改善サイクルを回すことで、理想の状態に段階的に近づけられます。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.As Is / To Beの4つの注意点
As Is / To Beフレームワークは効果的な手法ですが、運用を誤ると逆効果になるおそれもあります。ここでは、特に注意すべき以下4つのポイントを紹介します。
- To Beから書き出す
- 関係者の理解と合意を得る
- 短期的な結果が出にくい
- To Beが現実離れする恐れがある
To Beから書き出す
フレームワークを使う際は、現状ではなく理想(To Be)からはじめることが効果的です。
最初に理想像を描くことで、現実の制約に左右されず、本当に目指すべき姿を設定できます。
As Isからスタートすると、制約や限界を意識しすぎて、目標が小さくまとまってしまう可能性があります。
まずは制限を取り払ってTo Beを描き、そのあとでギャップを分析する流れが望ましいでしょう。
関係者の理解と合意を得る
As Is / To Beを有効に活用するには、関係者全員の理解と合意が欠かせません。認識にズレがあると、改善策の実行段階で、混乱や抵抗などが生じます。
特に複数の部門やチームが関わる場合は、共通の目的意識を持つことが重要です。そのためには、日常的な対話や説明の機会を設け、目標やプロセスを丁寧に共有する必要があります。
短期的な結果が出にくい
As Is / To Beフレームワークは、中長期的な改善を前提とした手法です。現状分析から理想像の設定、計画の立案まで段階を踏むため、即効性は高くありません。
特に組織全体に関わる改革では、目に見える成果が出るまでに時間がかかります。短期間での結果を求めすぎず、長期的な視野で、地道に進める必要があることを覚えておきましょう。
To Beが現実離れする恐れがある
理想像(To Be)を描く際に、あまりに高すぎる目標を掲げると現実離れしてしまう場合があります。実現が困難なビジョンは、かえってチームの士気を下げる原因になりかねません。
特に、現状のリソースや技術力を無視した理想像は、計画倒れに終わるリスクがあります。To Beを設定する際は、「少し努力すれば手が届く」範囲の目標を意識しましょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード6.As Is / To Beの活用例
As Is / To Beフレームワークは、あらゆる業務領域に応用できる汎用性の高い手法です。ここでは、実際のビジネスシーンにおける代表的な活用例を紹介します。
目標設定
As Is / To Beフレームワークは、個人や組織の目標設定にも効果的です。現状と理想の比較によって、具体的かつ実行可能なゴールを導き出せます。
たとえば、事務職における業務効率化を目的とした場合、次のような活用が考えられます。
| 項目 | To Be(理想) | As Is(現状) | 解決策 |
| 手書き伝票 | ・全体の20%以下 | ・全体の60%以上 | ・電子伝票システムの導入 ・社員研修の実施 |
| 入力ミス | ・月平均2件以下 | ・月平均10件発生 | ・チェックツールの導入 |
| 書類検索時間 | ・月10時間以下 | ・紙ベースで非効率 | ・クラウドストレージへの移行 ・運用ルールの整備 |
このように整理することで、目標達成に向けた具体的な道筋を明確に描けます。現実に即したプランが立てられ、組織全体での共有や実行にもつながるでしょう。
業務改善の分析
As Is / To Beフレームワークは、業務改善の場面でも高い効果を発揮します。現状の課題を可視化し、理想の業務プロセスに向けて改善策を具体化できます。
たとえば、営業部門における業務改善の場合、以下のようになります。
| 項目 | To Be(理想) | As Is(現状) | 解決策 |
| 営業記録 | ・デジタルで一元管理 | ・紙ベースで記録 | ・CRMシステムの導入 |
| 顧客情報 | ・チームで共有可能 | ・個人管理に依存 | ・営業プロセスの標準化 |
| 商談進捗 | ・ダッシュボードで可視化 | ・進捗が把握しづらい | ・ロールプレイング研修 ・戦略立案の仕組み化 |
このように、現状の業務に対して具体的なギャップを洗い出すことで、実行可能な改善計画を立てられます。結果として、組織全体の生産性や連携力の向上につながるでしょう。

業務改善とは?【改善6つの方法】部署別改善方法
多くの企業で取り組みを行っている業務改善。政府が打ち出した「働き方改革」とも密接に関係している、企業の生産性を向上させるためのものです。
企業運営において必須ともいえる業務改善ですが、どのように進めて...
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)

