ロックアウトとは、使用者が労働者の労務提供を拒否することです。ここでは、ロックアウトについて解説します。
目次
1.ロックアウトとは?
使用者が労働者の行う労務の提供を拒否すること。一般的なロックアウトは、仕事場から労働者を退かせる方法で実施されます。
ロックアウトは、「労働者側の争議行為で、労使勢力の均衡が破られた」「使用者側が極端に不利な状況に陥った」などに限り、争議行為として認められているのです。
争議行為とは、労働組合が行う集団行動のこと。労働者の要求の実現や抗議を目的とした団体行動権で、憲法28条で保障されています。
IT用語としてのロックアウト
ロックアウトをIT用語として使用する場合、「ユーザーアカウントを一時的または永続的に凍結する」「ユーザーのログインを拒否し、サービスを利用できない状態にする」といった意味になります。
目的はアカウントを不正利用する第三者をブロックすることです。
2.労働争議とは?
労働組合が、組合員の要求実現や使用者への抗議を目的として行う集団行動のこと。代表的な労働争議はストライキです。ここでは下記4つについて解説します。
- 労働争議の動向
- ストライキ
- ボイコット
- サボタージュ
①労働争議の動向
労働争議は、1960年代以降1970年代末までは先進各国で行われていました。しかし経済のグローバル化や国際的な価格競争などにより、世界各国で発生するようになったのです。
現在、労働争議の件数は減少傾向にあります。日本でも1980年代半ばから、経済の停滞や労働組合の組織率低下といった理由で争議件数は減少しているのです。
②ストライキ
憲法上の団体行動権にもとづいて、労働の拒否を手段として労働条件の改善を求める争議行為のこと。憲法・労働組合法で正当性が認められている行為です。
正当性の要件には、下記のようなものがあります。
- 労働組合の総意にもとづく
- 労働条件交渉に関するものである
- 手続違反や権利侵害がない

ストライキとは?【意味・やり方を簡単に】ボイコットとの違い
ストライキを起こさないためには、人にフォーカスするタレントマネジメントが大切
タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、従業員の個性や生の声を経営に活かしませんか?
⇒ 【公式】https://ww...
③ボイコット
争議行為戦術のひとつで、下記のようなものがあります。
- 使用者に直接的に経済的圧力を加えるために不買運動を組織する一次的ボイコット
- 使用者と取引関係のある第三者に働きかけ不買運動を組織する二次的ボイコット
一次的ボイコットは言論の自由の行使として、正当な争議行為のひとつに位置づけられているのです。
④サボタージュ
サボタージュはフランス語で破壊行為を意味します。「安価な木ぐつを意味するサボ」「産業革命によって生まれた失業者が履いていたサボ」を掛けて、仕事を失う・物を壊すといった使われ方をするのです。
現在、サボタージュは労働争議のひとつとして、権力者に対する抗議行動や破壊行為全般を意味する言葉になっています。
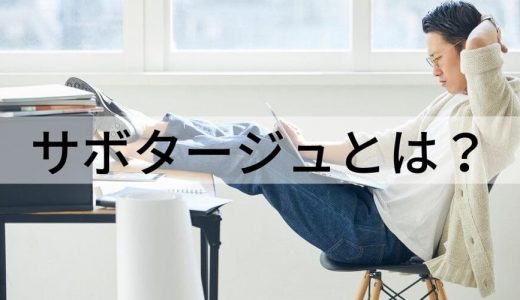
サボタージュとは? 【簡単に解説】「サボる」と意味は同じ?
サボタージュとは、労働の質や量を低下させる行為のこと。しかし、正当なサボタージュであれば、労働条件や労働環境を改善したい労働者の争議行為として刑事免責や民事免責も認められます。
とはいえ、サボタージュ...
3.ロックアウトの3つの条件
ロックアウトには、乱用を防ぐため3つの要件があるのです。それぞれについて解説しましょう。
- 労働組合側による争議行為によってかなりの圧力がかっている
- 経営者側が著しい打撃を受けている
- 労使間の勢力の均衡を回復するための対抗的防衛手段である
①労働組合側による争議行為によってかなりの圧力がかっている
もし労働組合側から何らかの要求の提示を受けていない場合、使用者はロックアウトを行えません。
②経営者側が著しい打撃を受けている
たとえば賃金を軽減させるためにロックアウトをするといった、経営側に著しい打撃がない場合、ロックアウトを行えません。
③労使間の勢力の均衡を回復するための対抗的防衛手段である
経営側がなんら損害を受けていないにもかかわらず、労働者を事業場外に締め出し、就労を妨げるのは認められていません。
不正なロックアウトはできない
ロックアウトは、3つの条件を満たした場合のみ認められます。「労働者側からの圧力がない」のように条件を満たしていない場合、不正なロックアウトだと見なされるのです。
4.ロックアウトによる賃金の支払い
ロックアウト中の賃金の支払いに関して、一定のルールがあります。内容について見ていきましょう。
- 正当な争議行為であれば支払い義務はない
- 労働者が「ロックアウト宣言」を無視した場合
- 部分ストライキの場合
①正当な争議行為であれば支払い義務はない
ロックアウトが正当な労働争議である場合、使用者に賃金の支払い義務はありません。ただしロックアウトが不当な場合、使用者に賃金支払い義務が生じるのです。
一部の労働者によって行われたストライキに対して、全従業員を対象としたロックアウトを行う場合、ストライキに参加していない労働者へ賃金の支払い義務が発生します。
②労働者が「ロックアウト宣言」を無視した場合
もし労働者が使用者側の行ったロックアウト宣言を無視した場合経営者は労働者に対して賃金の支払義務を免じられます。
またロックアウト中にもかかわらず、労働者が勝手に職場内に座りこんだり工場を占拠したりした場合、経営者は労働者に対して立入禁止の仮処分を求められるのです。
③部分ストライキの場合
労働者の行う部分ストライキに対抗するため使用者が全労働者に対してロックアウトを行った場合、ストライキに無関係な労働者には不当なロックアウトになります。
このようなケースでは当該労働者には賃金請求権が発生し、使用者は休業手当の支払い義務が生じるのです。ロックアウトでの賃金支払い義務には、注意しましょう。
5.ロックアウトをする場合は予告通知が必要
ロックアウトをする場合、予告通知が必要です。どういった内容なのか、見ていきましょう。
届出の方法
予告通知を届け出る方法は文書で、争議行為の日時や場所、概要を記載します。
また公益事業における争議行為は、公衆の日常に多大な影響を与えるもの。そのため「争議行為の目的」「争議行為を行う期間」「場所および争議行為の概要」についての詳細を記載することが望ましいとされているのです。
届出期日
「争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに通知しなければならない」と定められています。
「10日前」には、通知があった日と争議を行う日、どちらも含まれません。たとえば争議行為を7月20日に実施する予定の場合、中10日を計算して7月9日までに通知します。
届出先
ロックアウトの予告通知の届出先は、争議行為が行われる都道府県や規模で異なります。具体的には下記のようになっているのです。
- ひとつの都道府県区域内で発生した場合には、都道府県労働委員会または都道府県知事
- ふたつ以上の都道府県で発生した場合、またはロックアウトが全国的に重要な問題となる場合には、中央労働委員会
6.ロックアウトの事例
ロックアウトの事例として、3つの事件を紹介しましょう。
- 安威川生コンクリート工業事件
- 丸島水門事件
- 第一ハイヤーロックアウト事件
①安威川生コンクリート工業事件
安威川生コンクリート工業事件とは、「ストライキを行う」「使用者が出荷を断念した直後にストライキを解除する」を6回繰り返した結果に対する、使用者側のロックアウトのこと。
最高裁判所は、争議行為によって「使用者が資金繰りに窮し、取引先の信用も損なった」といった甚大な被害を受けた点を理由に、対抗防衛措置であるロックアウトの正当性を認めました。
②丸島水門事件
丸島水門事件では、最高裁判所がロックアウトの正当性を認めました。
「個々の具体的な労働争議の場において、労働者側の争議行為によりかえつて労使間の勢力の均衡が破れ、使用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合には、衡平の原則に照らし、使用者側においてこのような圧力を阻止し、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段として相当性を認められるかぎりにおいては、使用者の争議行為も正当なものとして是認されると解すべきである。」という理由です。
③第一ハイヤーロックアウト事件
第一ハイヤーロックアウト事件は、組合が繰り返し行った時限ストや社長室へのビラ貼付に対して、使用者がロックアウトを実施した事件のこと。
組合は、「不当なロックアウト」「未払い賃金の請求」を主張しました。最高裁判所は、「上告会社はこれらの者に対し賃金支払義務を免れないと判断している」と結論づけています。
7.ロックアウトの予防策
ロックアウトを予防するにはどうしたらよいのでしょうか。下記3つについて見ていきます。
- 労働環境を整える
- 労働条件を書面で明示
- スキャップ禁止協定
①労働環境を整える
下記のような、労働環境の整備が欠かせません。
- 長時間労働に配慮した、労働時間の適切な管理
- 誰もが安心して取得できる有給休暇
- 業務に起因して被る災害を防止し、精神衛生上も安心して働けるための安全衛生
②労働条件を書面で明示
労働基準法第15条は、労働条件を労働者に必ず明示しなければならないと定めています。また労働紛争の半数以上は、労働条件を書面で明示すれば予防できた事案となっているのです。
ロックアウトを予防するには、書面による労働条件の明示が有効といえるでしょう。
③スキャップ禁止協定
争議行為中に不要な紛争を起こさないことを目的とし、代替要員を雇入れないとあらかじめ定めた協定のこと。
法的に使用者が代替要員を雇用するのは制限されていません。スキャップ協定を締結すると、労使間の対立の先鋭化を予防できます。
8.ロックアウトとロックダウンの違い
ロックアウトに類似した言葉に、ロックダウンがあります。2つの違いは下記のとおりです。
- ロックダウン:事業所を封鎖し労働者の行動を制限すること、都市封鎖
- ロックアウト:敷地の立ち入りを制限するといった方法にて、労働者を締め出すこと

