ストライキを起こさないためには、人にフォーカスするタレントマネジメントが大切
タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、従業員の個性や生の声を経営に活かしませんか?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
ストライキとは、労働者が企業に対して待遇改善などを要求する争議行為のことです。ここではストライキの歴史と現状、防止策や事例について解説します
従業員の個性や声を見える化し、組織の潜在能力を最大化。
カオナビにはタレントマネジメントに必要な機能が揃っています。
資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから
1.ストライキとは?
ストライキ(strike)とは、労働者が集団で会社に圧力をかけ、対等な立場で交渉を行う手段で、争議行為のひとつです。「団体行動権」として労働者に与えられた基本的な権利のひとつで、「同盟罷業(どうめいひぎょう)」とも呼ばれるのです。
なお日本では、公務員といった官公労働者のストライキを法律で禁じています。
争議行為とは?
労働者が要求の実現や抗議を目的として行う集団行動のこと。ストライキをはじめ、後述する「ボイコット」や「サボタージュ」なども争議行為に含まれます。
- 労働組合員が一斉にストライキを行うもの
- 特定の部門や少数の組合員だけが行う部分ストライキ
- 少数の組合員を指定して行う指名ストライキ
などがあります。
ボイコットとの違い
消費者が企業や国に対して行う抗議行動のこと。労働者が自社の製品やサービスの利用を止める不買運動もボイコットの一種に含まれます。ストライキは業務の放棄、ボイコットは製品やサービスの不買として区別されているのです。
サボタージュとの違い
業務能率を落とすこと。仕事や勉強を怠ける「サボる」の語源にもなった言葉です。
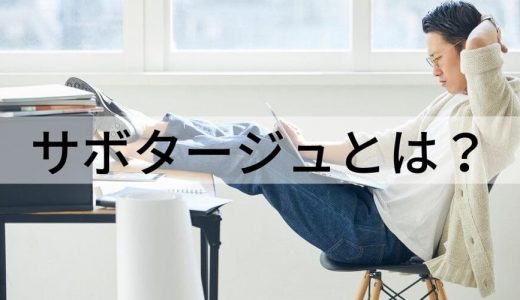
サボタージュとは? 【簡単に解説】「サボる」と意味は同じ?
サボタージュとは、労働の質や量を低下させる行為のこと。しかし、正当なサボタージュであれば、労働条件や労働環境を改善したい労働者の争議行為として刑事免責や民事免責も認められます。
とはいえ、サボタージュ...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
【従業員の個性や能力、生の声を見える化しませんか?】
タレントマネジメントシステム「カオナビ」を使って、組織の潜在能力を最大化
●人材データベースで従業員の個性や能力を見える化
●一人ひとり合った配置や育成を実現
●従業員のコンディションを見える化し離職防止
●匿名・記名式アンケートで従業員の生の声を回収
●アンケートの配布から集計、グラフ化までを半自動化
2.ストライキの歴史と現状
ストライキの歴史は労働組合が誕生した18世紀末のイギリスにさかのぼります。労働者同士が自主的な共済活動をはじめ、首切りや賃下げ、長時間労働などの問題に立ち向かうなかで生まれたのが「ストライキ」です。
日本ではじめてストライキが行われたのは明治政府によって「富国強兵」政策がとられていた1885年。甲府の製糸女子労働者によるストライキが日本最初といわれています。
日本におけるストライキの現状
現代の日本で行われるストライキは減少傾向にあるといわれています。理由のひとつが労使協議制度の定着。労使協議制度により、日本ではストライキを行わなくても会社側と労働者側の意見調整が行いやすくなりました。
また企業業績の悪化から、ストライキを行っても効果が見込めない可能性も出てきたのです。そのため労働者は会社側と無闇に争うより、現実的な改善策を探るようになりました。こうして日本におけるストライキは減少したのです。
海外におけるストライキの現状
日本でのストライキが減少する一方、海外では今でも多くのストライキが行われています。なかでも2018年のアメリカは「ストライキの年」と呼ばれるほど盛り上がりました。
アメリカ労働省の統計によれば、この年のストライキに参加したのは全米で48万5,200人。参加者の90%以上は教育や医療、介護などのケア産業で働く労働者でした。
アメリカでは単なる賃金闘争ではなく、社会的課題に取り組む団体交渉としてストライキが定着しつつあります。
3.ストライキで賃金カットはあるのか?
労働者が業務を一斉に停止して労働条件の改善や維持を要求するストライキですが、ストライキ中の賃金はどのような扱いになるのでしょうか。ここではストライキによる賃金カット、また部分ストや一部ストの際の賃金について説明します。
ノーワーク・ノーペイの原則
ストライキが実施された場合、労働の対価にあたる賃金は原則、支払われません。そもそも賃金とは、労働に対する報酬として使用者が労働者に支払う対価のこと。
ストライキに参加した組合員は、賃金の支払い対象となる労働の提供をしていません。争議行為のために労働を提供しなかった時間に対して賃金を支給することは、労働組合に対する経費援助、つまり不当労働行為であると解されます。
これを「ノーワークノーペイの原則」と呼ぶのです。
賃金をカットする範囲
実際のところ、賃金をカットできる範囲について見解がわかれます。たとえば1日のストライキがあった場合、月額から1日分の賃金を差し引くのは当然認められています。しかし家族手当や住宅手当、交通費補助などはどうでしょうか。
賃金カットの範囲は企業や事案によって異なります。就業規則や労働協約などでストライキが行われた場合の支払い基準について、あらかじめ決めておくとよいでしょう。
部分ストや一部ストの場合
組合員の一部のみが参加する「部分スト」や、労働者の一部を組織する労働組合が行う「一部スト」の場合、どのような扱いになるのでしょう。
部分ストや一部ストによってストライキ参加者以外の労働者が業務につけなかった場合でも、賃金請求権は失われないと解釈されるのが一般的です。
しかし就労不能は使用者にとっていかんともしがたい事態となります。よって過去「ストライキに参加していない労働者に賃金を受ける権利はない」と解釈された事例もあるのです。
4.ストライキ防止策
労働者が企業側に要望を伝えるための争議行為にあたるストライキ。長引けば長引くほど企業側はもちろん労働者側も経済的に苦しむでしょう。ここではストライキの防止策と、それでも起きてしまった場合の対抗措置について説明します。
労務管理の合法性
ストライキの目的は労働条件の改善や維持。つまり労務管理が適切に行われていれば、ストライキが発生する可能性は低くなるのです。企業は賃金や労働時間、休憩や休日、安全衛生や性差別などを適正に管理しなければなりません。
特に賃金額は注意が必要です。使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額は「最低賃金法」によって定められています。たとえ労働者が合意していても、最低限度額を下回る賃金での契約は、認められません。
経営管理の合理性
公平な評価システムや給与システム、昇進システムなどを構築し、経営管理の合理性を図るのもストライキの防止策となります。
2014年、独立行政法人情報処理推進機構が発行した「内部不正の現状について~国内外の内部不正の動向~」によると労働者の5人に1人が人事評価に不満を持っているそうです。
不当な評価や合理性に欠ける人事管理を放置したままでは、ストライキやサボタージュが発生しかねません。
起こってしまった場合の対抗措置
企業は労務管理の合法性や経営管理の合理性見直しとともに、ストライキの発生に備えて本社と現場の役割分担を決め、マニュアルを作成しておく必要があります。
それでもストライキが起きてしまった場合、企業はどのような対抗措置を講じるとよいのでしょう。3つ説明します。
- ロックアウト
- 損害賠償請求
- 争議差止の仮処分
①ロックアウト
使用者が争議行為の相手である労働者に対して労務の受領を拒絶し、事業場から集団的に締め出す行為のこと。ストライキが起きた場合、使用者は平和義務違反として「ロックアウト」で対抗できます。
②損害賠償請求
平和義務に違反してストライキが発生した場合、使用者は労働組合に対して債務不履行にもとづいた損害賠償請求が可能です。ただしこれは、ストライキが正当性の認められない行為と判断された場合に限ります。
ストライキが正当と認められた場合、労働組合やストライキに参加した組合員個人に損害賠償請求はできません。
③争議差止の仮処分
平和義務違反のストライキに差止仮処分が認められるかどうかは判断がわかれます。昭和35年の日本信託銀行事件や昭和48年のノースウェスト航空事件では、平和義務内容を実現する履行請求権が認められず、仮処分は否定されました。
一方、昭和48年のパンアメリカン航空事件では争議行為差止処分を認めています。差止仮処分が認められるかどうかは、裁判ごとの解釈に委ねられているのです。
5.ストライキを行う手順
ストライキは、一般的に以下4つのステップを経て実施されます。
- 正当性が認められる行為だと確認
- 労働関係調整法にもとづいた争議予告通知
- 経営者へのストライキ予告
- 組合内部での準備
①正当性が認められる行為だと確認
はじめに実施を検討しているストライキが、団体交渉における要求を貫徹するための行為として、法的に保護されるかどうかを確認します。そのストライキに正当性が認められてはじめて、刑事免責や民事免責などの法的保護が受けられるようになるのです。
ストライキの正当性は「主体」「目的」「手続」「態様」4つの観点から総合的に判断されます。
労働組合が主体となっている
ストライキをはじめとする争議行為は、団体交渉の当事者となり得る者が主体となる必要があります。
そのため労働組合が主体とならず、組合員の一部が全体の意思にもとづかないまま実施するストライキ(通称山猫スト)は「主体」の面から正当性が認められません。
使用者は団体交渉によって解決できない相手から争議行為を受けて、不当な不利益を強いられるからです。
直接無記名投票において、過半数の賛成を獲得している
ストライキを実施するかどうかは労働組合の投票によって決まります。組合規約に従い、組合員または代議員の直接無記名投票を行うのです。この投票で過半数の賛成を得てはじめてストライキの実施が可能になります(労働組合法第5条)。
なお投票の結果過半数ぎりぎりでストライキ権を確立した場合、ストライキに入る体制は十分だといえません。組合内部の意思統一を再度見直す必要があります。
労働条件交渉に関することが目的である
ストライキの目的は労働に関するものでなければなりません。以下に該当するものに限り、正当性が認められるのです。
労働者の労働条件そのほか経済的地位に関する事項を、目的とする
労使関係の運営に関する事項で、使用者としての立場で支配・決定できるものを目的とする
反対に政治問題に関するストライキやほか組合の支援を目的としたストライキは、正当なものだと認められません。
争議行為の手段や態様が正当である
団体交渉を経ずに行われたストライキに正当性は認められません。
会社の回答を待たずにストライキを実施したり、役員の自宅に直接出向いて面会を強要したりする行為は正当であると認められないのです。そうなると活動に刑事免責や民事免責などの法的保護は適用されなくなります。
またいかなる場合でも暴力の行使は、労働組合の正当な行為として解釈されません。
②労働関係調整法にもとづいた争議予告通知
4つの観点からストライキに正当性が認められたら、ストライキの実施を予告するのです。労働関係調整法(37条)では「少なくとも10日前までに、労働委員会および厚労大臣または都道府県知事にその旨通知しなくてはならない」と定めています。
つまり予告通知をした日の翌日から数えて11日目よりストライキに入れるのです。
③経営者へのストライキ予告
労働委員会および厚労大臣または都道府県知事だけでなく、もちろん経営者にもストライキの予告を行います。ストライキの目的はあくまでも労働者の要求実現。経営者に考える期間を与えるという意味でも、1週間以上に前に予告するのが一般的です。
また混乱を避けたり労働組合の実態や要求を宣伝したりするため、施設利用者や患者にストライキを予告する場合もあります。
④組合内部での準備
ストライキの実行に向けて、組合内部で以下項目の準備を進めます。
- ストライキ実行の日時とタイムテーブル
- 規模や形態
- ストライキの実施内容
- ストライキ集会の実施(組合集会や職場会議)
- 地域への宣伝
- 会場の確保や備品の用意
- 県医労連や地区労協などに集会参加やあいさつを要請する
6.ストライキの事例
ストライキについて理解を深めるため、過去に起こった事例を見てみましょう。ここでは下記3つの事例について説明します。
- ストライキが違法なものと判断された「全日空空輸事件」
- 国家公務員法の規定に言及した「全農林事件」
- 戦後日本における最大の労働争議と呼ばれている「三池争議」
①ストライキが違法なものと判断された「全日空空輸事件」
1966年に東京地裁で判決が下された「全日本空輸事件」では、ストライキが違法だと判断され、組合の役員らが懲戒解雇されました。
賃上げなどを要求した労働組合のストライキはあらかじめ会社側にストライキの予告を行っており、正当な争議行為として認められていたにもかかわらず違法の判決が下されたのです。
本事例ではそのあと、就業規則で定められた懲戒解雇の条項を適用して解雇したのは無効だという判決が出ました。
②国家公務員法の規定に言及した「全農林事件」
2000年に最高裁で判決が下された「全農林事件」は、公務員の労働基本権保障に言及した事例です。
警察官職務執行法の改正案が国会に提出された際、反対の立場だった全農林の労働組合は農林省の職員にデモの参加を勧めました。これが国家公務員法の規定に違反するとして起訴されたのです。
裁判では公務員の争議行為を禁止する国家公務員法は合憲だと判断し、意見の主張は退けられました。
③戦後日本における最大の労働争議と呼ばれている「三池争議」
1959年から1960年にかけて起きたのが、戦後日本における最大の労働争議といわれている「三池争議」。
この年三井鉱山は、石炭産業の全国的な再編成の一環として数千人規模の労働者を失業に追い込む計画を発表しました。これに反対した労働者が1年以上にわたってストライキを実施したのです。
この活動は全国から支持を集め、労働者に全国的リーダーシップや支援が提供されました。しかし結果的に企業側が優先となり、労働者は職を失ってしまったのです。
7.ストライキについての疑問
団体交渉にて要求を貫徹したくとも労働組合がない場合、どうなるのでしょう。またストライキの実行は解雇につながるのでしょうか。ここではストライキに関する3つの疑問について説明します。
- 労働組合がない場合はどうするのか
- ストライキをしたら解雇になるのか
- 1人でもストライキはできるのか
①労働組合がない場合はどうするのか
近年、労働組合がない会社も増えています。厚生労働省の統計資料によれば、雇用者数に占める労働組合員数の割合は17.7%。労働組合員数は年々減少傾向にあります。
そのなか合同労組(ユニオン)に加入して会社と団体交渉を行うケースが増えているのです。合同労組は個人であれば一人でも加入できます。つまり労働者が一人でもいれば、合同労組から団体交渉の申し入れを行えるのです。
②ストライキをしたら解雇になるのか
「ストライキの実施や参加が、解雇につながるのでは」と考える労働者も多いでしょう。結論からいえばストライキを理由とした減給や解雇は法律上で禁じられています。
ただし会社側が「勤務態度に問題あり」といったストライキ以外の理由を作って労働者を不当に扱う可能性もあるのです。この場合、各都道府県の労働委員会に対して救済申立てを行いましょう。
③1人でもストライキはできるのか
一人でもストライキは実施できるのでしょうか。ストライキをはじめとした争議行為は団体で行うことが前提です。つまり一人が仕事を放棄しただけではストライキとして認められません。
もし一人でもストライキを起こしたい場合は、団体交渉をするため社内の労働組合に相談してみましょう。

