従業員満足度調査の運用を効率化!
充実したテンプレートから自社独自のアンケート作成も可能。
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
従業員満足度アンケートのテンプレートとは、従業員満足度(ES調査)を実施する際に使用する雛型のことです。ここでは、テンプレートを使用する目的や調査実施の手順、具体的な質問項目について解説します。
▼従業員満足度調査についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

従業員満足度調査とは?【わかりやすく解説】質問項目例
Excel、紙の調査シートをテンプレートで楽々クラウド化。
カオナビで時間が掛かっていた従業員満足度調査を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダ...
目次
充実した従業員満足度アンケートのテンプレートを備える「カオナビ」の資料を見てみる ⇒こちらから
1.従業員満足度アンケートのテンプレート
従業員満足度アンケートのテンプレートは、顧客アンケートや会場アンケート、社内アンケートなど細かいカテゴリに分かれているため、目的やシーンに応じてすぐに実施できます。はじめに、従業員満足度について確認しましょう。
従業員満足度とは?
従業員満足度とは、従業員の仕事や組織に対する満足度を示した指標のこと。英語ではEmployee Satisfactionと表記するため、略して「ES」とも呼ばれます。
仕事内容や職場環境、待遇や人間関係などのさまざまな要因が、従業員にとって満足できる状態となっているかを定量的に数値化します。近年、従業員満足度の向上が、顧客満足度の向上や組織全体の成長につながるとして、注目を集めているのです。
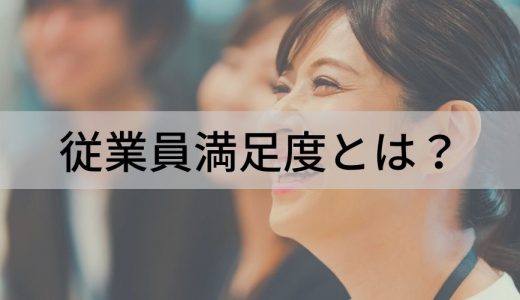
従業員満足度(ES)とは?【調査・事例】エンゲージメント
従業員満足度とは、企業に対して従業員がどれだけ満足しているかの指標です。従業員満足度を向上させると、生産性の向上や人材の定着、顧客満足度の向上などさまざまな面でメリットがあります。
今回は従業員満足度...
基本項目
まずは以下にあげられる基本項目を設定します。調査の表紙や序盤に設定するなどして、回答漏れが起きないようにしましょう。
性別・年齢・所属部署・役職・勤続年数などは、相関や関係性を分析する際に必要な項目です。「従業員満足度の高い従業員は勤続年数が長い/短い傾向にある」「ある部署のみ従業員満足度の低下が目立つ」など、集計後の分析を進める際に必要な要素となります。
仕事満足度
仕事満足度とは、以下3つの要素で構成される満足度のことです。
- 「仕事内容」満足度:自身の業務量や仕事内容が、役職や等級に見合った適切なものであるかをはかる指標
- 「人材育成」満足度:業務を通じて得られる知識や能力、成長感をはかる指標
- 「仕事継続」満足度:勤続意向や組織への愛着をはかる指標
「現在の業務量に満足しているか」「今後も今の職場で働きたいと思うか」などの質問を加えて、日常の業務に対する従業員の満足度をはかります。
仕事内容満足度
「仕事満足度」を構成する3つの要素について、それぞれ詳しく掘り下げてみましょう。自分に課せられた仕事内容や業務量が、役職や等級から見て妥当なものかどうか測る指標を「仕事内容満足度」といい、質問例には次のような項目があげられます。
- 現在の業務にやりがいを感じている
- 仕事内容が自分に合っていると感じている
人材育成満足度
「人材育成満足度」の定義は、仕事を通じて身につけられる知識や能力をはかる指標、また直近3年間での成長感です。
「業務内容に自分の得意分野を活かせたと感じている」「業務を通じてスキルアップに成功したと実感している」といった質問を通じて、業務が自身の能力を高める状況につながっているかどうかを問います。
本人が目指す姿と実務内容に乖離があり、それがモチベーション低下を招いていたという課題に気付ける場合もあるでしょう。
仕事継続満足度
仕事継続満足度は、勤続意向や会社への愛着をはかる指標と言い換えられるものです。具体的には次のような質問を設定します。
- 達成したい具体的な目標がある
- 現在の業務が自身の成長につながっていると感じられる
人材不足が叫ばれるなか、多くの企業で離職率の高さを課題に据えています。勤続の意向や愛着に対する満足度を測り、離職に至る原因の追究および離職率の低下を狙いましょう。
職場満足度
「職場満足度」とは、職場環境に対する満足度をはかる指標のこと。
「チーム内(部門間)でうまくノウハウの共有ができている」「職場の人間関係が円滑であると感じている」といった質問を組み込み、レベルごとに分析を行うと、関係性や傾向が見えてきます。
上司満足度
上司満足度とは、上司との関係性や尊敬の意、上司から向けられる信頼感や指導援助などのこと。従業員満足度アンケートでは上司との関係にもメスを入れ、組織の課題や強みを明確にします。
「上司と相性がよいと感じている」「上司と業務上必要な連携が適切に取れていると感じる」など、デリケートな部分に踏み込むため、質問文の設定では配慮が必要です。
会社風土満足度
会社風土満足度とは、以下3つの項目で構成された指標のことです。
- 「会社風土」満足度:挑戦しやすい風潮がある、市場変化に迅速に対応していると感じられる
- 「会社インフラ」満足度:社内設備やインフラが充実し、安心して仕事に打ち込める環境がある
- 「会社風紀」満足度:各種ハラスメントが存在しない、規律やマナーの遵守が徹底されている
表記によっては漠然とした質問になり、従業員が回答しにくくなる恐れも。質問を設置する際は、具体的な表現になるよう意識しましょう。
処遇満足度
従業員にとって、給与や労働時間などの処遇は非常に重要です。従業員満足度の低下を、単に「業務と給与が見合っていない」「労働時間が長すぎる」といった話で終わらせないよう、次の4つの項目を意識した質問を用意しましょう。
- 「人事評価」満足度:人事評価に公平性を感じられるか
- 「給与等」満足度:業務内容や質に応じた報酬が得られているか
- 「個人目標」満足度:組織目標だけでなく個人目標も尊重されているか
- 「労働時間」満足度:休暇、休日が取りやすい環境にあるか
福利厚生満足度
近年、社内に無料のカフェテリアや託児所を設けて従業員のニーズに応える、独自の福利厚生を提供する企業も増えました。
勤務形態自由度の拡大、退職金や年金制度の充実、慶弔についての十分な配慮などを示す「福利厚生満足度」も、従業員満足度を高める要素のひとつです。
福利厚生満足度を高めると、従業員が定着しやすくなり、結果として離職率低下をもたらす場合もあります。従業員満足度の調査では、福利厚生に対する満足度についても質問してみましょう。
経営満足度
一般的に、会社のビジョンや経営方針に対して従業員が経営層にコメントできる機会はそう多くありません。
従業員が企業の経営に対してどう感じているのか、企業理念や将来性についてどう考えているかが分かることも、従業員満足度アンケートを行うメリットのひとつです。
調査結果の分析を進め、改善策を講じれば、経営層の独りよがりにならない経営方針を生み出すチャンスになるでしょう。
総合満足度
「経営や福利厚生など、細かい部分に不満はあるものの、総合的には満足している」と考える従業員は少なくありません。従業員満足度アンケートでは、細かい要素だけでなく総合的な従業員満足度を理解できます。
「会社に対し、総合的にどの程度満足しているか」といった質問も組み込みましょう。分析結果から、これまで見落としていた意識が見える化するかもしれません。
人事施策満足度
研修制度やOJT制度など、会社で実施した人事施策に関する満足度も忘れずに調査しましょう。
「育成制度に力を入れていると感じる」「気軽にキャリアについて相談できる風土がある」といった質問を加え、経営層や人事部が人材開発のために実施した施策が、従業員からどのような評価を得ているのかを明らかにします。
もちろん、調査結果をさらなる改善につなげる取り組みも忘れずに進めましょう。
従業員の満足度を正確に把握して、モチベーション向上への取り組みに活かす
テンプレートを活用して効率的に従業員満足度アンケートができる!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから
2.従業員満足度アンケートだけじゃない!使えるテンプレートを紹介
従業員満足度を調査するには、このほかにもさまざまなアンケート方法があります。なかには労働安全衛生法に基づいた制度やストレス・顧客満足度にフォーカスした調査制度もあります。目的に応じて以下アンケートの併用も検討してみましょう。

社内アンケートの質問例100選!作り方のポイントもわかりやすく
社内アンケートのクラウド化で、配布・収集・分析にかかる時間を大幅削減。
社員の生の声を効率的に集め、組織改善するなら「カオナビ」です!
⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセ...
ストレスチェックアンケート
労働環境省では、労働安全衛生法に基づいた「ストレスチェック」のアンケートテンプレートを公開しています。ストレスチェックとは、心理的な負担の程度を把握するための検査のこと。
「最近は生き生きとしている」「気が張り詰めている」「食欲がない」などの質問で状態をうかがったり、周囲に対する信頼度をはかったりして、メンタルヘルス不調の一次予防を目指しているのです。
セミナー満足度のアンケート
よかれと思って実施したセミナーや講演会も、従業員満足度が低ければ期待した成果を得られません。セミナーや講演会を行った際は、全体の満足度や次回以降の参加不参加を聞くなどして、セミナーに対する満足度を計測してみましょう。
アンケートで「どういった内容を求めて参加したのか」「どの部分に対して満足度が低くなったのか」などを調査すると、次回以降に活かせます。
顧客満足度調査アンケート
自社商品やサービス向上のために「顧客満足度調査」を実施している企業もあるでしょう。顧客満足度調査とは、人が商品やサービスを購入した際に得られる満足度を定量的に測定する調査のこと。
顧客満足度調査では、どの程度満足しているか、どの部分に満足や不満を感じたか、などの質問を通じて、顧客満足度の向上やリピーターの増加、課題優先度の明確化などが実現できます。
「商品・サービスを周囲の人にどのくらいおすすめしたいか」といった質問を用いるNPSも有効です。
【従業員満足度アンケートに適したテンプレート&自動化で運用効率UP!】
\カオナビなら/
・多様なテンプレートがあるからすぐ開始できる
・自社に合わせた独自アンケートもカンタンに作成可能
・調査を自動で開始・集計・グラフ化するから運用がラク
・アンケート結果から退職リスクも分析
・従業員のコンディションを定点観測できる
・満足度調査の回答がPC/スマホで可能

