他者との比較を避け、過去の成功体験を振り返ることで自信が生まれます。また、ポジティブな自己対話を意識的に行い、自分の価値を見出すことが効果的です。さらに、小さな目標を設定し達成することで、自己肯定感を少しずつ積み上げることができます。
ネガティブな感情が湧いたときには、その感情を受け入れつつも、自分を責めず前向きな行動を心がけることが大切です。
1.自己肯定感を高める・上げるには?
自己肯定感を高めるには「意識」と「行動」を変える必要があります。ポイントはありのままの自分と他者の双方を認めて、前向きな行動をとること。
自己肯定感が高い人のことを「自信家」とイメージする人もいるようですが、両者は大きく異なります。自信家とは、能力や評価、外見や社会的地位など、なにかしらの客観的視点にもとづいた「自身を誇るポイント」を重視する人物のこと。そのため自信家は、他者と自分を比較して優劣をつける傾向にあります。
一方、自己肯定感が高い人は、自分と他者の価値をそれぞれ認めて受け入れます。そのため自分と他者の間に優劣をつける必要がありません。
自己肯定感とは?
自己肯定感とは、ありのままの自分を認めて好意的に考えられる感覚のこと。自分のよい点も悪い点も受け入れたうえで自分の価値とします。
たとえば自分ができないことがあった場合、「今はできないが、できるようになるにはどうしたらいいだろうか」と考えられる人は、自己肯定感が高い傾向にあります。一方自己肯定感の低い人は、「自分ができるはずがない」と考えてしまう傾向にあるのです。

自己肯定感とは? 高い人や低い人の特徴、低い原因、高める方法
自己肯定感とは、類似する言葉、高い人・低い人の特徴、高め方、理解を進めるための書籍などについて紹介します。
1.自己肯定感とは?
自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定する感覚のことです。他人と比べ...
セルフエスティーム(self-esteem)
セルフエスティーム(self-esteem)とは、「self(自己)」と「esteem(尊敬)」を合わせた言葉。自己肯定感のほかにも自尊心や自尊感情、自己評価などと訳されることがあります。
このセルフエスティームは自信や意欲、自我を育てるために重要な要素のひとつ。そのため学校教育や心理学などの領域で注目されており、子どもの教育はもちろん、新入社員や若手社員向けの社内研修などにも組み込まれているのです。
自己肯定感と自己効力感
自己肯定感と似た言葉に「自己効力感」がありますが、それぞれの意味は同じではありません。ここでは自己効力感、自己肯定感との違いについて説明していきます。
自己効力感とは
自己効力感とは、「自分ならできる」や「うまくやれる」と思える感情のこと。根拠のない自信ではなく、「自分はできるだけの能力がある」と確信しているのがポイントです。スタンフォード大学教授で心理学者のアルバート・バンデューラ博士によって作られた言葉で、英語では「Self-efficacy」と表現されます。
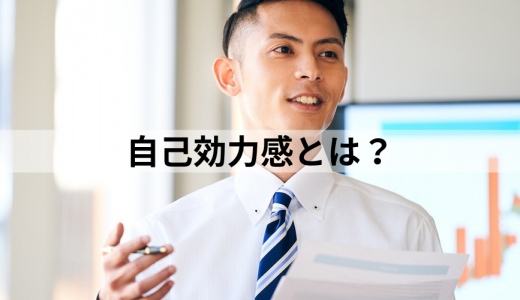
自己効力感とは? 自己肯定感との違いや高める方法を簡単に
1.自己効力感とは?
自己効力感とは、目標達成に必要な能力を自分が持っていると認識することです。簡単に表現すると「自信」です。具体的には、自身の能力や過去の経験から、取り組もうとしている行動に対...
自己肯定感と自己効力感との違い
自己肯定感は「自分自身の存在」を肯定する「感情」であるのに対し、自己効力感は「自分自身の能力」を肯定する「認知」である点が異なります。簡単に言うと、自己肯定感は「ありのままの自分を認める」こと、自己効力感は「自分はうまくできると考えられる」ことです。
たとえば未経験のことに挑戦するときに、自己肯定感が高いと、「未経験なのだから最初からうまくいかなくてもいい。失敗したらそのときに対処法を考えよう」と考えます。一方自己効力感が高いと、「自分は未経験だけど、ほかの人も未経験でやれたのだから自分も大丈夫」と考えるのです。このように自己肯定感では能力や実績などの条件なしに現状の自分を受け入れ、自己効力感では自分が持っている能力を裏付けとして自分を信じます。
自己肯定感が注目されたきっかけ
2014年に国立青少年教育振興機構が、自己認識などについての意識調査を実施。日本を含めた7か国で高校生にアンケートを行った結果、日本人は諸外国の人と比べて自己肯定感が低い傾向にあることがわかりました。この調査によって「自己肯定感」というワードが注目されるようになったのです。
内閣府による調査の結果
2014年に内閣府が実施した日本を含めた7か国の満13歳から29歳を対象とした意識調査で、「自分に満足しているか?」といった自己肯定感に関する質問を行いました。日本以外の6か国は、「そう思う」や「どちらかといえばそう思う」と回答した人が約80%という高い水準だったのに対して、日本でこれらの回答した人の割合は約45%という結果に。このことから日本人はほかの諸外国と比べて、とくに自己肯定感が低いことが判明しました。
それを払拭するために自己肯定感を高める方法についてさまざまな方法が提唱されるようになり、認知が広まっていったと考えられます。
2.自己肯定感が高い人の特徴
自己肯定感は先天的な要因ではなく、自分を取り巻く人間関係によって高くも低くもなります。そのうち自己肯定感の高い人は、何事にもポジティブだったり、努力を継続させるのがうまかったりといった傾向が見られるのです。自己肯定感の高い人の特徴について紹介していきます。
ポジティブにチャレンジする
どのような結果に転んでもポジティブに捉えられるため、チャレンジすることに躊躇しません。思考と行動の軸、つまり判断基準や価値観が自分自身であるため、成功も失敗も自分の責任であると考えられるからです。そのため自分が「やりたい」と思ったら、未経験であっても果敢に挑戦していきます。仮に失敗したとしても、失敗を受け止めて学習し、次回につなげられるでしょう。
努力を楽しく、かつ継続できる
自己肯定感が低い人と比べて、努力を継続させることが得意な傾向があります。そのときに成功しなくても、自分を責めずに前向きに努力していけるからです。また自己肯定感が高い人は、「できないことができるようになれば、もっと人生が楽しくなる」と前向きに考えます。そのためモチベーションを維持しやすく、楽しみながら努力を継続できるのです。
失敗を他人のせいにしない
判断基準や価値観が自分自身であるため、自分が行ってきたすべての行動に責任を持ちます。そのため失敗したときも、人や環境のせいにすることはしません。たとえ現状の環境が理由であったとしても、その環境を選んだのは自分自身であると自分を納得させることができるのです。また失敗を冷静に分析できるため、隠れたチャンスを見つけることもあるでしょう。
感情のコントロールができる
嫌なことや理不尽なことがあっても、自分の感情をうまくコントロールします。感情にまかせてやみくもに行動すると、物事が悪い方へ向かうと知っているからです。自分の判断基準や価値観が確立されているため、たとえ一時的に感情がたかぶってもすぐに冷静な状態に戻れます。そのあとはトラブルや逆境へ立ち向かうモチベーションがわき上がってくることも多いようです。
他人と比較しない
判断基準や価値観が自分自身であるため、他人と自分を比べるようなことはしません。他人と自分は目標も違い、考え方も違うことがわかっているからです。自己肯定感が高い人がだれかと自分を比べる場合、比較対象は過去の自分となります。過去の自分と現在の自分を比較することで、自身の成長につながることを知っているのです。
見返りを期待しない
自分が行ったことに関して、相手に見返りを求めたりしません。自分がやりたいことを実行しただけであり、実行できたことで満たされているため、相手のリアクションを求める必要がないのです。また自己肯定感が高い人は、今までの生活の中ですでに多くの人に助けられていることを理解しています。そのため相手のために行うことも「恩返し」と考え、見返りを求めずに行動できるのです。
3.自己肯定感を高める・上げるための10の方法
これから自己肯定感を高めることは可能です。とはいえ自己肯定感は自分自身への感情であるため、意識して高めるのは難しいかもしれません。まずは自己肯定感が高まりやすい行動をしてみるのもひとつの方法です。ここでは自己肯定感を高める10の方法を紹介します。
新しいことにチャレンジする
プライベートでも仕事でもなんでも構わないので、新しいことへ挑戦しつづけましょう。「慣れたことを再度やる」だけでは、自分の成長にもつながらないからです。新たにチャレンジするなら、自分の得意なことや長所を活かせるものを選びましょう。自分の強みを活かしたものであればモチベーションが上がりますし、チャレンジの成功率も上がります。
「すみません」を「ありがとう」に変える
ささいなことでも「すみません」ではなく、「ありがとうございます」と言うようにしましょう。「すみません」は謝罪の意味を持つ言葉で、「ありがとう」は感謝の意味を持つ言葉。たとえば道を譲ってもらったときや、エレベーターで自分が乗るのを待ってもらったときでも、「ありがとう」と感謝を伝えればよいのです。謝罪の言葉ではなく感謝の言葉を使うようにすれば、ポジティブな感情を維持しやすくなります。
小さな成功体験を積み重ねる
小さな成功体験を積み重ねて自分に自信をつけると、自己肯定感が高まりやすくなります。たとえば「ゴミ出しを忘れない」や「毎日10分余裕を持って出社する」、「毎日腕立てを10回する」など、本当に小さなことでかまいません。とにかく何か小さな目標を立てて、コツコツ達成してくことが大切です。成功するごとに「自分でもやればできる」という自信につながります。またひとつの成功を経験すると、「こんなこともできるかもしれない」と新たなチャレンジへの意欲もわきやすいでしょう。
情報の取捨選択をする
なるべく自分に必要な情報だけを取捨選択して収集しましょう。世の中にはさまざまな情報があふれかえっていますが、なかには批判や中傷、ゴシップなどもネガティブな情報も存在します。このようなネガティブな情報を見ると、自分もネガティブな思考を持ちやすくなるため、自己肯定感を高める効果は期待できません。一方、ほかの人の成功体験や自分と同じ意見を持つ人のコメントなどは、自分の肯定につながりやすい情報といえるでしょう。
自分に必要な情報と不必要な情報を見極めて、自分をポジティブに保つことが大切です。
短所を長所として捉えなおす
自分の短所をポジティブにとらえてみましょう。見方をかえると、短所は長所になりえるからです。たとえば「一度に複数の仕事を進めるのが苦手」という人であれば、「ひとつの仕事を集中して進めるのが得意」と言い換えられます。このように逆転の発想で自分の短所長所に置き換えると、自分に自信を持ちやすくなるのです。
短所を長所へ言い換えるという方法は、面接対策や研修などの自己分析でもよく用いられています。同様に長所も見方を変えると短所となりえるため、長所として活かすように気をつけましょう。
現状をありのままに認める
今の自分自身について、長所と短所を把握したうえでそのまま受け入れることが大切です。とくに短所には「気づき」と「受け入れ」、「許可」の3つのステップが必要です。
まずは自分のどのような点をダメだと思っているのかを書き出しましょう。
次にその自分がダメだと思ったことについて、「今は思い込んでいる」という言葉を加えます。このように書くと、自分がダメだと思っている部分であても改善の余地があると思えるのです。
最後にダメだと思ったことについて「それでもよい」ととらえて許可します。
この3つのステップを行うと、自分が思っている自身のダメな部分を認められるようになるでしょう。
困ったら人を頼る
困ったことがあった場合、一人で悩まずだれかに助けを求めましょう。「相手に迷惑をかけるから」や「できないと思われたくない」などと考えないのがポイントです。「今の自分ではできない」と受け入れて、素直に人の助けを借りましょう。困難を乗り越えて自分自身が成長するうえに、助けた人に対する信頼感が伝わり、よい人間関係を築きやすくなります。
自分をほめる
小さなことであっても自分自信をほめましょう。自分自信の言動を認める、つまり肯定する行為だからです。よく「ほめて伸ばす」といわれますが、これは科学的に実証されています。人はほめられると脳が幸せを感じ、意欲や自信を持ちやすくなるのです。
そのため何か失敗をしてしまったときでも、そこまでの過程で頑張った自分をほめて、その失敗から学んだことがあったことをほめましょう。たとえば「1日1回、ひとつでいいので自分をほめる」という方法も有効です。
宣言する
頭で考えるだけでなく口に出す、すなわち「宣言する」のもよい方法です。たとえば「自分はできる人間である」や「自分はかけがえのない存在である」など、自己肯定感を高める内容を宣言するのです。このとき重要なのは、「実際にそうなった自分を想像しながら宣言する」こと。自分の潜在意識を上書きし、自信や意欲をアップさせる効果があります。
この方法は「アファメーション」や「引き寄せの法則」ともいわれており、マインドセットのひとつとされています。
他者からしてもらったことをリスト化する
「嬉しさ」や「感謝」など前向きな気持ちを持つために、人からしてもらったことをリスト化してみましょう。自己肯定感の高い人は、人に何かをしてもらったときに「やってもらって当然」とは考えず、してもらったことをポジティブに受け止めて素直に感謝します。このリスト化はその第一歩といえるでしょう。
前述したように感謝はポジティブな感情をもたらすので、さきほどの「1日1回、ひとつでいいので自分をほめる」のと同じように、人にやってもらったことを毎日メモしていくのも有効な方法です。
4.自己肯定感を高めることに役立つ本
自己肯定感の注目度が上がるにつれて、自己肯定感を高めるコツなどを解説している書籍も出版されるようになりました。紙の本ではなく電子書籍を利用すると、スマホなどで空いた時間に読み進められるでしょう。ここでは自己肯定感を高めるために役立つ本を3つ紹介します。
敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法
心理カウンセラーである著者が、他人のことを気にしすぎてすぐに傷ついてしまう人に向けて、自分を見つめ直して自己肯定感を高める方法を解説しています。
この本の特徴はたった7日間で実践が完了する点です。読むだけでなくワークも用意されており、自己分析や自己理解をしやすくなっています。1週間しっかりと実践すれば、自己肯定感を高めて今までの自分を変えられる可能性があるでしょう。
参考 敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法Amazon何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書
著者は自己肯定感の第一人者である心理カウンセラーで、「そもそも自己肯定感とはなんなのか」いう基本的な部分から解説している本です。
設題やチェックシートなどで自己肯定感の高さを判定できるので、こちらも自己分析を進めやすくなっています。無理して自己肯定感を高めるのではなく、自然に「高まる」方法を紹介しているので、ストレスなく実行していけるでしょう。
参考 何があっても「大丈夫。」と思えるようになる 自己肯定感の教科書Amazonうまくいっている人の考え方 完全版
「うまくいっている人の考え方」と「うまくいっている人の考え方発展編」の2冊をまとめた携書。「人生がうまくいっている人は自尊心が高い」と気づいたアメリカの経営者である著者が、自尊心を高める方法を解説している本です。
自尊心を高める方法を100項目にわたって紹介しているので、自分が受け入れやすい項目から実践しやすくなっています。この本が発行されたのは今から15年以上も前ですが、今でもベストセラーとなっている本です。
参考 うまくいっている人の考え方 完全版Amazon評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

