部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
リモートワークは、場所や時間に縛られない柔軟な働き方を可能にしました。しかし、その一方で、これまで当たり前だったオフィスでの偶発的なコミュニケーションが失われ、新たな課題も生まれています。
とくに、非対面でのやり取りが増えることで、コミュニケーション不足に陥り、業務効率や生産性の低下、ひいては組織力の低下につながるケースも少なくありません。リモートワーク環境下だからこそ、コミュニケーションへの意識的な工夫が重要です。
そこで今回は、リモートワークでコミュニケーションが不足しがちな理由から、その課題を解決し、チームのエンゲージメントと生産性を高める具体的な方法までを詳しく解説します。
目次
1.リモートワークでコミュニケーションが不足がちになってしまう理由

リモートワーク環境では、コミュニケーションが不足しがちになります。その主な理由を掘り下げていきましょう。オフィスでの働き方とは異なる特性が、コミュニケーションに大きく影響を与えています。
- 話しかけるタイミングが難しいため
- 雑談しにくいため
- 基本はテキストでのやり取りとなるため
- 相手の表情や感情がわかりにくいため
- コミュニケーションツールを使いこなせていないため
話しかけるタイミングが難しいため
オフィスでは、隣の席の同僚に気軽に声をかけたり、休憩中に雑談をしたりと、自然な形でコミュニケーションが生まれていました。しかし、リモートワークでは、相手が今仕事をしているのか、休憩中なのか、集中している最中なのかが見えません。
「話しかけても良いものか」「邪魔にならないか」といった遠慮が生まれ、結果として話しかけるのを躊躇するケースが多くなります。
とくにチャットツールでの連絡は、相手の状況が見えないため、返信が遅れることへの不安や、緊急ではない用件でメッセージを送ることへのためらいにつながります。
雑談しにくいため
オフィスでは、休憩スペースや廊下、ランチタイムなど、仕事とは直接関係ない「雑談」が自然に行われていました。この雑談は、社員同士の人間関係を構築し、心理的安全性を高める上で非常に重要な役割を果たします。
しかし、リモートワークでは、意図的に場を設けない限り、雑談の機会はほとんどありません。
業務連絡に特化したコミュニケーションが増えることで、社員同士のパーソナルな部分が見えにくくなり、結果として「孤立」や「疎外」を感じやすくなります。
雑談が減ることは、チームの一体感を損ねたり、人間関係を構築する機会を失ったりすることにつながるでしょう。
基本はテキストでのやり取りとなるため
リモートワークのコミュニケーションは、チャットツールやメールといったテキストでのやり取りが中心です。
テキストでのやり取りは、記録が残り、後から確認しやすいというメリットがある一方で、言葉のニュアンスが伝わりにくいというデメリットも抱えています。
表情や声のトーン、身振り手振りといった非言語情報が欠如しているため、誤解が生じやすく、意図しない形で相手に伝わる可能性も少なくありません。
また、長文のテキストを読むのが負担になったり、細かい質問のやり取りに時間がかかったりと、コミュニケーションの効率が低下する場合もあります。
相手の表情や感情がわかりにくいため
対面でのコミュニケーションでは、相手の表情や仕草、声のトーンから感情を読み取れます。これにより、相手の理解度や納得度を把握し、話の進め方を調整できます。
しかし、ビデオ会議以外のリモートワークでは、相手の表情や感情を直接的に知る機会がほぼありません。テキストコミュニケーションでは、相手がどのような気持ちでいるのかを推測するしかなく、不安を感じやすくなります。
これにより、本音を言いづらくなったり、意見交換が活発に行われなくなったりすることもあるでしょう。
コミュニケーションツールを使いこなせていないため
リモートワークでは、チャットツール、ビデオ会議システム、プロジェクト管理ツールなど、さまざまなコミュニケーションツールが活用されます。しかし、これらのツールを十分に使いこなせていないと、コミュニケーション不足につながります。
機能が多すぎて使い方がわからない、どのツールをいつ使うべきかのルールが曖昧、といった状況では、ツールが円滑なコミュニケーションの障壁になります。
せっかく便利なツールを導入しても、使いこなせなければ、その効果は半減し、結果として情報共有の遅延や、認識のズレが生じる可能性が高まるでしょう。
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.リモートワークをする上での課題と注意点
リモートワークは働き方の柔軟性を高める一方で、組織運営においてさまざまな課題をもたらします。こうした課題はコミュニケーションの問題と密接に絡み合っている場合が多いです。
コミュニケーション不足以外に、リモートワークでどういった課題や注意点があるかを押さえておきましょう。
社員が不安や孤独を感じやすい
オフィス勤務では、同僚が周囲にいることで自然と安心感が得られ、困ったときにはすぐに相談できる環境がありました。
しかし、リモートワークでは、社員が一人で業務に取り組む時間が長くなるため、「この仕事はこれで合っているのだろうか」「困ったときに誰に聞けばいいのだろうか」といった不安を感じやすくなります。
とくに、新入社員や異動したばかりの社員は、人間関係の構築が難しく、孤立感を深めてしまうリスクがあります。
孤立感は、モチベーションの低下や精神的な不調にもつながりかねず、企業としては社員のメンタルヘルスケアに十分な配慮が求められます。
社員のモチベーション管理が難しい
リモートワークでは、上司が部下の働きぶりを直接見れないため、社員のモチベーションを把握し、適切に管理することが困難です。オフィスであれば、ちょっとした変化から異変に気づき、声をかけられるでしょう。
しかし、リモートワークではそうしたサインを見逃しやすく、社員がモチベーションを低下させていても、気づくのが遅れる可能性があります。
結果として、業務効率の低下や離職につながるリスクも0ではありません。社員が自律的に業務に取り組めるよう、目標設定や評価基準の明確化、適切なフィードバックの機会を設けることが重要です。
勤怠管理しにくい
リモートワークでは、社員がそれぞれ異なる場所で業務を行うため、正確な勤怠管理が難しいという課題もあります。労働時間の把握が曖昧になったり、休憩時間の取得状況が不透明になったりする可能性があります。
また、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすく、過重労働につながるリスクも考えられるでしょう。適切な勤怠管理体制の構築は、労働基準法の遵守だけでなく、社員の健康維持の観点からも重要です。
業務・プロジェクトの進捗状況が把握しにくい
オフィスでは、チームメンバーが近くにいるため、業務の進捗状況をリアルタイムで把握し、必要に応じてサポートや調整ができました。しかし、リモートワークでは、各メンバーの進捗状況が把握しづらくなり、業務やプロジェクトの進捗が滞るリスクが高まります。
とくに、情報共有が不足したり、問題発生時の報連相が遅れたりすると、プロジェクト全体に大きな影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
そのため、定期的な進捗報告の場を設けたり、プロジェクト管理ツールを活用したりするなど、可視化と共有の仕組みを強化することが求められます。
チームや部下の様子がわかりにくい
マネージャーにとって、リモートワークにおけるチームや部下の状況把握は大きな課題です。オフィスでは、部下の表情や声のトーン、作業の様子から、それぞれのコンディションや抱えている課題を察知できます。
しかし、リモートワークでは、そうした非言語情報が手に入りにくくなります。部下のパフォーマンスが低下していても気づきにくいため、適切なサポートや育成が遅れる可能性があります。
チームの一体感を維持し、部下の成長を支援には、意識的な働きかけが不可欠です。
業務効率・生産性が低下する
コミュニケーション不足や情報共有の遅れは、業務効率や生産性の低下に直結します。疑問点の解消に時間がかかり、必要な情報がスムーズに共有されないと、手戻りが発生するなど無駄な作業が増える可能性もあります。
リモートワーク下でも高い生産性を維持するためには、明確な役割分担、効率的な情報共有、そしてスムーズな連携を促す仕組みが必要です。
公正な評価が難しい
リモートワークでは、社員の働きぶりを直接観察できないため、公正な人事評価を行うのが難しいという課題があります。
成果のみに焦点を当てた評価になりがちで、プロセスや努力、チームへの貢献といった側面が見えにくくなる可能性も考えられます。
また、一部の社員の頑張りが見過ごされたり、逆に過大評価されたりといった不公平感が生じるかもしれません。
リモートワーク環境下でも公正な評価を行うためには、評価基準の明確化、目標設定の適切な運用、そして定期的な面談による多角的な情報収集が重要になるでしょう。

評価基準とは?【作り方をわかりやすく】目的、項目の具体例
評価基準とは評価するための水準であり、公平かつ客観的な評価を行ううえで重要な指標です。人事評価への不満は優秀人材の離職の原因ともなり、最悪のケースでは業績不調を招く恐れもあります。
今回は、評価基準と...
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
3.手軽に始められるコミュニケーションを活性化させる方法7選

リモートワークにおけるコミュニケーションの課題を解決し、チームのエンゲージメントと生産性を向上させるためには、具体的な施策を講じることが重要です。
ここでは、手軽に始められるコミュニケーション活性化の方法として、次の7つを紹介します。
- コミュニケーションツールの導入
- 雑談チャンネルの作成
- 社内SNSの導入
- オンラインランチの実施
- 定期的な1on1
- プロジェクト管理ツールの導入
- 社内報の発行
コミュニケーションツールの導入
リモートワークにおいて、コミュニケーションツールは必須のインフラです。コミュニケーションツールには、主に「チャットツール」と「グループウェア」の2種類があります。
| チャットツール | グループウェア | |
| 代表的なツール | Slack、Microsoft Teams、Chatwork | Google Workspace、Microsoft 365 |
| 特徴 | リアルタイムでのテキストコミュニケーションに特化しており、カジュアルな情報共有やスピーディーなやり取りができる | チャット機能に加えて、ファイル共有、スケジュール管理、タスク管理、Web会議など、多様な機能を統合 |
チャットツールは、絵文字やスタンプ、リアクション機能などの活用によって、テキストだけでは伝わりにくい感情やニュアンスを補完できます。
部署ごとやプロジェクトごとにチャンネルを作成すれば、必要な情報が埋もれることなく、効率的な情報共有が実現できるでしょう。
グループウェアは、コミュニケーションだけでなく、業務に必要な情報を一元的に管理できるツールです。情報が分散することを防ぎ、業務効率の向上に貢献してくれます。
雑談チャンネルの作成
「雑談しにくい」という課題を解決するためには、意図的に雑談の場を設けることが効果的です。チャットツールに「雑談部屋」「休憩室」「今日の出来事」などといった名称のチャンネルを作成し、業務とは関係ない気軽な会話を推奨しましょう。
「週末何をしていた?」や「おすすめのランチ情報」など、テーマを設けて発信を促すのもおすすめです。こうしたチャンネルでは、絵文字やスタンプの使用を奨励し、かしこまらずに気軽に投稿できる雰囲気作りが重要です。
これにより、社員同士のパーソナルな側面を知る機会が増え、心理的な距離が縮まり、孤立感の解消にもつながります。
社内SNSの導入
社内SNSは、社員同士が情報発信や交流を行う場を提供するツールです。Facebookのようなタイムライン形式で、個人の近況報告や業務に関する気付き、趣味の話題などを共有できます。
部署や役職の垣根を越えたコミュニケーションを促進し、社内の一体感を醸成する効果が期待できるでしょう。ブログ機能やアンケート機能を持つものもあり、情報発信のプラットフォームとしても活用可能です。
オンラインランチの実施
定期的に、オンラインでのランチ会や親睦会を設定することも有効です。強制参加ではなく、自由参加の形で、業務時間外に行うことで、リラックスした雰囲気での交流を促すのがポイントです。数名ずつのグループに分ければ、より深い会話が生まれやすくなります。
共通の趣味を持つメンバーを集めたり、普段あまり接点のない部署のメンバーを組み合わせたりするなど、工夫次第で多様な交流が生まれるでしょう。これにより、社員同士のつながりを深め、孤立感を解消するだけでなく、チームビルディングにも貢献します。
定期的な1on1
マネージャーと部下による定期的な1on1ミーティングは、リモートワークにおける部下のモチベーション管理や成長支援において非常に重要です。
業務の進捗確認だけでなく、部下の悩みやキャリアに対する考え、プライベートな状況など、普段の業務では見えにくい部分に耳を傾ける時間として活用しましょう。
1on1は、部下が安心して本音を話せる場であるべきです。マネージャーは傾聴の姿勢を心がけ、部下の成長を支援するコーチングの役割が求められます。
定期的に実施することで、信頼関係が構築され、部下の不安や課題を早期に発見し、適切なサポートにつなげられるでしょう。
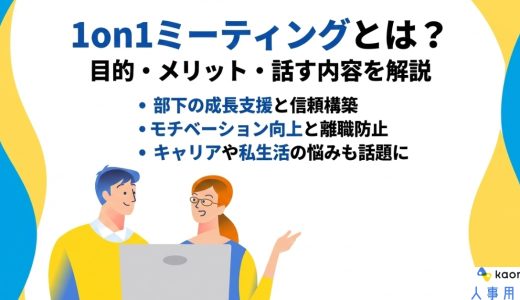
1on1とは? 目的や導入効果、面談との違いとやり方を簡単に解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入す...
プロジェクト管理ツールの導入
業務・プロジェクトの進捗管理が滞りがちなリモートワーク環境では、プロジェクト管理ツールの導入がおすすめです。こうしたツールの活用によって、タスクの進捗状況、担当者、期限などを可視化し、チーム全体で共有できます。
プロジェクトの全体像を常に把握できるため、個々のメンバーが自分の役割を明確に認識し、自律的に業務を進められます。
また、ボトルネックの早期発見や、タスクの再配分などもスムーズに行え、プロジェクトの円滑な進行と生産性向上に大きく貢献するでしょう。
社内報の発行
リモートワークで情報共有が不足しがちな状況において、社内報やニュースレターの定期的な発行は、社員の一体感を醸成し、企業文化を浸透させる上で有効です。
経営層からのメッセージや、各部署の取り組み、社員紹介、福利厚生の最新情報など、多岐にわたる情報の発信によって、社員は会社全体の動きを把握しやすくなります。
社員の顔が見えにくいリモートワークでは、社員個人の活動や成果を紹介するコンテンツは、互いの理解を深めたり、称賛の機会を増やしたりすることにつながります。
オンライン形式の社内報であれば、動画や画像を豊富に盛り込むことで、より魅力的で分かりやすい情報発信が可能です。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.コミュニケーションツールの選び方と運用ルール設計
リモートワークにおけるコミュニケーションを円滑にする上で、適切なコミュニケーションツールの選定と、それを効果的に運用するためのルール設計は不可欠です。
ここでは、リモートワーク下のコミュニケーションを活性化させたり、業務を効率化したりするのに役立つ、コミュニケーションツールの選び方や適切な運用のためのルール設計についてみていきましょう。
コミュニケーションツールを選ぶポイント
コミュニケーションツールを選ぶ際には、単に機能が豊富であるかだけでなく、自社の実情に合致しているかを見極めることが重要です。
以下の3つのポイントから、最適なコミュニケーションツールを選んでみましょう。
- 必要な機能があるか
- 使いやすく見やすいデザインか
- スマホからも使用できるか
必要な機能があるか
コミュニケーションツールで実現したいことや解決したい課題をふまえ、どのような機能があると良いかを明確にしましょう。
単にチャット機能があれば良いのか、ファイル共有、ビデオ会議、タスク管理、スケジュール管理、情報共有ポータルなど、多機能なグループウェアが必要なのかを検討します。
コミュニケーションツールに搭載されている機能には、以下があります。
| テキストコミュニケーション | 素早い情報共有や簡単な質問に適したチャット機能 |
| ファイル共有 | ドキュメントや画像などのファイルを手軽に共有 |
| ビデオ会議 | オンライン会議ができるだけでなく、画面共有や録画機能ができるものもある |
| タスク管理 | タスクや期限を設定できる |
必要な機能が網羅されているかを確認するのはもちろん、将来的にも拡張性があるかどうかも検討するポイントの一つです。機能が多すぎると使いこなせない可能性もあるため、本当に必要な機能に絞って選定することも重要でしょう。
使いやすく見やすいデザインか
どれだけ高機能なツールであっても、使いにくければ浸透しません。とくに、ITリテラシーに差がある社員もいることを考慮し、直感的でわかりやすいインターフェースであるかを確認しましょう。
使いやすさや見やすさに関するチェックポイントは、次のとおりです。
| 操作性 | メッセージの送信、ファイルの添付、会議の開始など、基本的な操作を迷わず行えるか |
| 視覚的なわかりやすさ | 必要な情報が一目でわかるデザインか |
| カスタマイズ性 | フォントサイズやテーマカラーなど、個人の好みに合わせて調整できるか |
| 通知設定 | 不要な通知を減らし、必要な情報だけを受け取れる設定が可能か |
無料のトライアル期間を利用して、実際に社員に触ってもらい、その上で導入できると安心です。
スマホからも使用できるか
リモートワークでは、PCだけでなくスマートフォンやタブレットからアクセスする機会も増えます。
移動中や外出先からでもスムーズにコミュニケーションが取れるよう、モバイルアプリの提供やレスポンシブデザインに対応しているかは重要な選定ポイントです。
緊急性の高い連絡や、出先からの簡単な確認など、場所を選ばずにコミュニケーションが取れる環境を整えることは、業務効率の向上に大きく貢献します。
【用途別】おすすめコミュニケーションツール
ひとくちにコミュニケーションツールといっても、その種類はさまざまです。コミュニケーションの用途別に、代表的なツールと特徴を紹介します。
テキストコミュニケーション・情報共有
| Slack | |
| 特徴 | ・チームコミュニケーションの定番ツール ・豊富な連携機能とカスタマイズ性が魅力で、チャンネルごとにテーマを分けて効率的な情報共有が可能 ・絵文字やスレッド機能も充実しており、カジュアルなコミュニケーションから業務連絡まで幅広く対応できる |
| 料金 | ・フリープランあり ・月額¥1,050〜/1ユーザー |
| 機能 | ・チャンネル作成 ・チームメンバーとの会話 ・外部パートナーとの協働 ・音声・ビデオミーティング ・情報を録音・録画して共有 ・リストでプロジェクトを整理・追跡・管理 ・ファイル共有 など |
| Chatwork | |
| 特徴 | ・日本語に特化したシンプルなUIが特徴 ・ビジネスチャットとして広く利用されている ・タスク管理機能も備わっており、プロジェクトの進捗管理も可能 ・操作が直感的で、ITツールに不慣れな社員でも導入しやすい |
| 料金 | ・フリープランあり ・月額¥840〜(年額の場合¥700〜)/1ユーザー |
| 機能 | ・グループチャット ・タスク管理 ・ファイル管理 ・ビデオ/音声通話 など |
| Microsoft Teams | |
| 特徴 | ・Microsoft 365のサービスの一部として提供されており、Word、Excel、PowerPointなど他のMicrosoft製品との連携がスムーズ ・ビデオ会議、ファイル共有、チャット機能が統合されており、特にMicrosoft製品を多く利用している企業には最適な選択肢 |
| 料金 | ・フリープランなし ・月額¥599〜/1ユーザー |
| 機能 | ・チャット ・音声/ビデオ通話 ・画面共有 ・画像送信 ・ファイル共有 など |
ビデオ会議
| Zoom Meetings | |
| 特徴 | ・高い安定性と画質・音質で、大人数での会議にも対応可能 ・ブレイクアウトルーム機能やウェビナー機能も充実しており、セミナーや研修など幅広い用途で活用されている |
| 料金 | ・フリープランあり ・月額¥1,999〜/1ユーザー |
| 機能 | ・ミーティング ・レコーディング ・メッセージ ・ホワイトボード ・カレンダー など |
| Google Meet | |
| 特徴 | ・Google Workspaceの一部として提供されており、Webブラウザから手軽に参加できる ・シンプルな操作性で、Googleカレンダーと連携して会議を設定しやすい点が特徴 ・Googleアカウントがあれば、参加者100人、最長60分まで無料で会議できる ・モバイルの1対1の通話は時間制限なし |
| 料金 | ・基本無料 |
| 機能 | ・ビデオ会議 ・ブレイクアウトルームの作成 ・リアクション など |
プロジェクト・タスク管理
| Asana | |
| 特徴 | ・タスク管理に特化したツールで、プロジェクトの進捗状況を視覚的に把握しやすいインターフェースが特徴 ・多様なビュー(リスト、ボード、タイムライン、カレンダー)があり、チームのスタイルに合わせて柔軟に利用できる |
| 料金 | ・フリープランあり ・月額¥1,200〜/1ユーザーあたり |
| 機能 | ・タスク、プロジェクト管理ダッシュボード ・アクティビティログ ・ファイルストレージ(最大100MB) ・カスタムテンプレート ・承認 など |
| Backlog | |
| 特徴 | ・ガントチャートやバーンダウンチャートなど、プロジェクト管理に必要な機能が充実 ・直感的な操作性と親しみやすいデザインが特徴 ・国産ツールであるため、日本語でのサポートが充実している点も魅力 ・人数によって料金が変わらないのも嬉しいポイント |
| 料金 | ・月額¥2,970〜/組織チーム向け月額¥17,600〜 |
| 機能 | ・ガントチャート ・カンバンボード ・ファイル共有 ・お知らせ機能 など |
| Trello | |
| 特徴 | ・カード形式でタスクを管理するカンバン方式のツール ・直感的な操作でタスクの進捗状況を視覚的に把握でき、簡単なプロジェクト管理に適してる ・プロジェクトを管理する「ボード」、タスクのステータスや分類を表す「リスト」、タスク単位の担当者や期限などを管理する「カード」で構成される ・複数のメンバーで同じボードを共有し、タスクの進捗状況をリアルタイムで確認できる |
| 料金 | ・フリープランあり ・月額5ドル〜/1ユーザー |
| 機能 | ・クイックキャプチャ ・プランナー ・タイムラインビュー など |
設計すべき5つの運用ルール
 コミュニケーションツールを導入するだけでは、その効果を最大限に引き出すことは難しいでしょう。メリットを上手に活用し、トラブルなくコミュニケーションツールを運用するためにも、以下のルール設計が大切です。
コミュニケーションツールを導入するだけでは、その効果を最大限に引き出すことは難しいでしょう。メリットを上手に活用し、トラブルなくコミュニケーションツールを運用するためにも、以下のルール設計が大切です。
- チャンネルの目的
- 返信の期限・タイミング
- ツール・電話・メールの使い分け
- スタンプや絵文字の使い方
- 投稿NG内容
①チャンネルの目的
各チャンネルの目的を明確にすると、「どの情報をどこに投稿すべきか」がわかりやすくなります。これにより、情報の探しやすさが向上し、必要な情報に素早くアクセスできるでしょう。
Slackでチャンネルを作成する際の一例は、以下のとおりです。
| #general(全体連絡) | 全社員への重要なお知らせ、全社的な共有事項 |
| #(プロジェクト名) | 特定のプロジェクトに関する業務連絡、進捗共有、議論 |
| #(部署名)-daily | 部署内の日報、業務連絡、進捗共有 |
| #random / #雑談 | 業務と関係ないフリートーク、雑談、趣味の話題 |
| #help-desk | 困ったときの質問や相談 |
不要な情報が混ざることなく、必要な情報がスムーズに共有される状態を目指します。
②返信の期限・タイミング
チャットツールはメールより迅速なやり取りが好まれる媒体です。返信を待つ側の不安を軽減し、業務の停滞を防ぐためにも、返信の期限・タイミングのルールを設けることをおすすめします。
たとえば、緊急性の低い連絡であれば「24時間以内」または「翌営業日中」に返信、緊急性の高い連絡であれば「1時間以内」または「可能であればすぐに」返信する、といった具体例が考えられます。
お知らせのような確認のみを促すチャットでも、メッセージを確認した旨を伝える目安として「既読」や「いいね」などのリアクションをすることも決めておくと良いでしょう。
ただし、厳密なルールにしすぎると社員の負担になる可能性もあるため、状況に応じた柔軟性を持たせることが重要です。
③ツール・電話・メールの使い分け
複数のコミュニケーションツールを導入している場合、どの媒体をどのような目的で使うべきかを明確にすることで、混乱を防ぎ、コミュニケーションの効率を高められます。
使い分けの例は、以下のとおりです。
| 目的 | 使用シーン | |
| チャットツール | スピーディーな情報共有、簡単な質問、リアルタイムでの議論、カジュアルな雑談 | 短いメッセージ、進捗報告、アポイント調整、確認事項など |
| メール | 公式な連絡、記録に残すべき重要な情報共有、社外とのやり取り | 契約書などの添付、法的文書の送付、長期保存が必要な情報、外部パートナーとの連携 |
| 電話 | 緊急性の高い連絡、複雑な内容のすり合わせ、テキストでは伝わりにくいニュアンスの伝達 | 緊急の確認、トラブル発生時、込み入った相談、相手の状況確認 |
明確な使い分けによって、社員は迷うことなく最適なコミュニケーション手段を選択できるでしょう。
④スタンプや絵文字の使い方
テキストコミュニケーションでは、相手の表情や感情が伝わりにくいです。スタンプや絵文字の適切な活用によって、メッセージに感情やニュアンスを添え、より円滑なコミュニケーションを促せます。
堅苦しくなりがちなビジネスコミュニケーションに温かみを加え、心理的な距離を縮める効果も期待できるでしょう。
ただし、その使い方については、社員間で共通認識を持つことが重要です。状況や相手によっては、フォーマルな場面での多用は避けるように注意を促す必要もあります。
⑤投稿NG内容
オープンなコミュニケーションを奨励する一方で、投稿してはいけない内容や、避けるべき表現についても明確なルールを設ける必要があります。
ルールを設けることで、ハラスメントや情報漏洩のリスクを防ぎ、健全なコミュニケーション環境を維持できるでしょう。
たとえば、雑談チャンネルなどを除く、業務チャンネルでの私的な長文投稿は控える、特定の個人への攻撃、差別的な発言、セクハラ・パワハラに該当するような言動は厳禁など、具体的にルールを定めます。
これらのルールを明文化し、定期的に社員に周知することで、トラブルを未然に防ぎ、社員が安心してコミュニケーションツールを利用できる環境を整備できるでしょう。
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.リモートワーク導入でカオナビができること
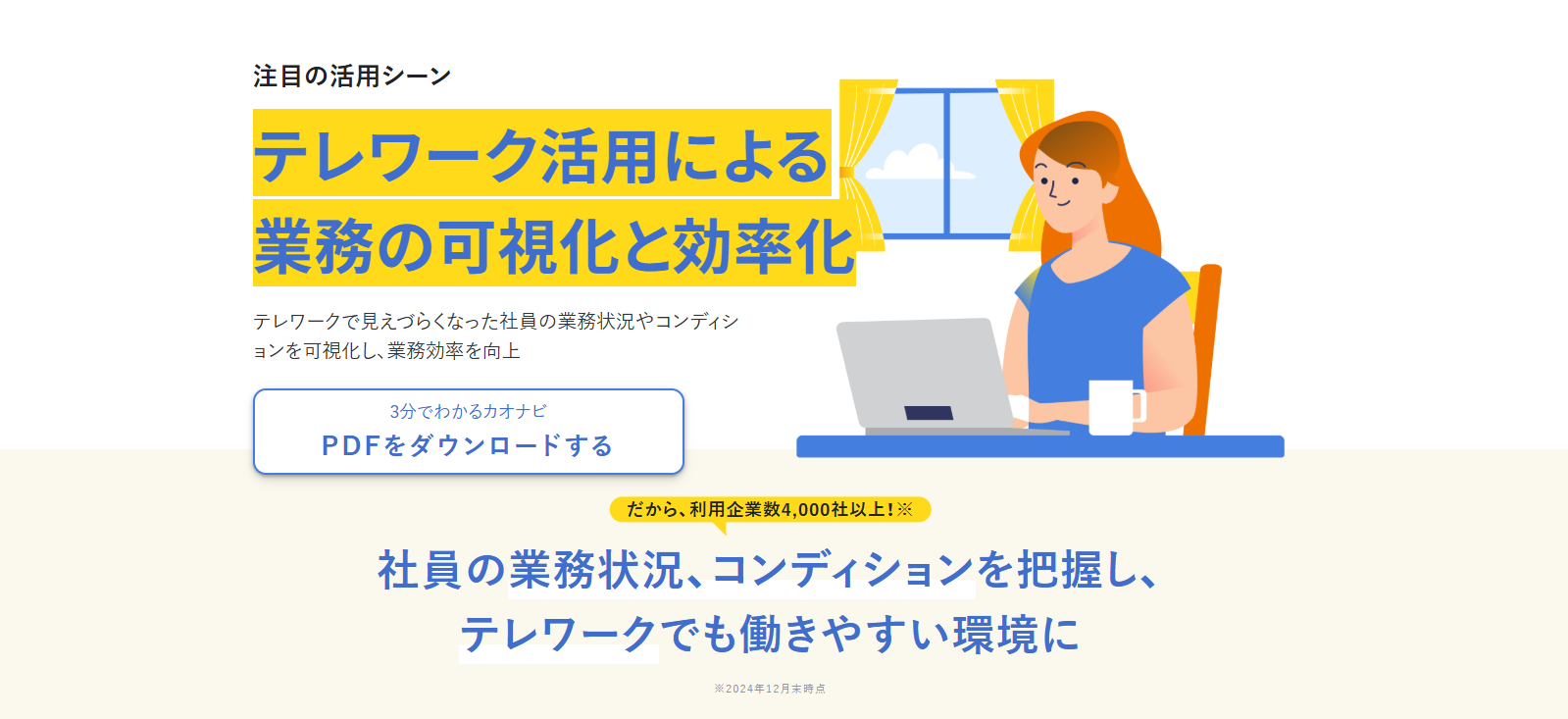
人事・総務担当者やマネージャー層にとって、リモートワークにおける社員の状況把握や評価は大きな課題です。タレントマネジメントシステム「カオナビ」は、以下の機能を搭載しており、リモートワーク環境下での課題解決に貢献できます。
- パルスサーベイ
- 社内アンケート
- 面談記録
リモートワーク環境下で、カオナビをどう活用できるかをみていきましょう。
パルスサーベイ
パルスサーベイは、週1回や隔週などの短い頻度で簡易的なアンケートを実施し、社員のコンディションや組織の状況をリアルタイムで把握する手法です。
リモートワークでは、社員の表情や感情が直接見えにくいため、社員のエンゲージメントやモチベーションの変化に気づきにくいという課題があります。
カオナビでは、パルスサーベイの実施が可能です。初期は3つの最適な設問がデフォルトで設定されており、導入後すぐにアンケートが実施できます。
シンプルな操作画面で使いやすく、スマホからも回答できるので、初めてパルスサーベイを導入する場合でも抵抗なく使えるでしょう。データは一元管理・長期保存できるため、社員のコンディションの変化を把握しやすいメリットもあります。
社内アンケート
パルスサーベイよりも詳細な情報を収集したい場合や、特定のテーマについて深く掘り下げたい場合には、社内アンケートが有効です。カオナビは「社内アンケート」機能を搭載しています。
エンゲージメント調査やリモートワーク環境に関する意見収集など、社員の現状理解を深めるだけでなく、今後のリモートワーク施策の立案や改善に具体的なデータとして活用できます。
また、社内イベントや懇親会などの出欠確認や、社内表彰者の投票など、業務外のコミュニケーションにも利用できるでしょう。
面談記録
リモートワーク下では、上司と部下の対面でのコミュニケーション機会が減少するため、面談記録の重要性が増します。カオナビは、面談記録の機能も搭載しています。
面談記録はカオナビのデータベースに一元化できるため、次回の面談担当者への引き継ぎや本人の健康面ケアに取り組みやすくなるでしょう。
たとえば、面談で共有された部下の悩み、目標設定、進捗状況などを記録することで、マネージャーは部下のコンディションを継続的に把握できます。
また、面談記録は、客観的な情報として人事評価の根拠となるため、リモートワークにおける評価の難しさを解消し、公正な評価の実現にもつながります。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら
6.まとめ
リモートワークは、企業に新たな働き方と可能性をもたらしますが、同時にコミュニケーションのあり方にも大きな変化と課題を与えます。非対面であるからこそ、コミュニケーションは非常に重要です。
コミュニケーションが不足すると、業務効率や生産性の低下を招くだけでなく、組織力を失う可能性もあります。非言語情報がわからない環境だからこそ、コミュニケーションの工夫やルールが必要です。
リモートワークでコミュニケーション不足になる理由や、そのほかに起こりうる課題を押さえ、事前に対策を講じることが有効でしょう。
リモートワークで起こりうる課題を解決する方法として、タレントマネジメントシステム「カオナビ」が活用できます。
自社の状況に合わせた適切なコミュニケーション施策を検討し、リモートワーク環境下でも生産性の高い組織を目指しましょう。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)

