年末調整のシーズンが近づくと、「いつから作業を始めればよいか」「どこまでに終わらせる必要があるのか」で悩む労務担当者も多いのではないでしょうか。年末調整は、源泉徴収票の交付や法定調書の提出など、期限が法律で定められている手続きも多く、後ろ倒しにしづらい業務です。
年末調整の法的な提出期限と実務での理想的なスケジュール、業務を効率化する進め方について詳しく解説します。計画的に対応できるよう、基本情報から丁寧にチェックしていきましょう。
目次
年末調整とは?基本の役割と対象者を整理
年末調整とは、1年間に支払った給与と源泉徴収した所得税を精算し、正確な税額に調整する手続きです。企業は従業員に毎月給与を支払うたびに所得税を源泉徴収しますが、これはあくまで概算です。そのため年末に、当年の収入や各種控除を反映させた正確な税額を再計算し、過不足を調整します。
年末に行われる年末調整の対象者は原則、年末時点で在籍していて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員すべてです。年の途中(12月中も含む)で退職した従業員や、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない従業員などは基本的に対象外となります。
年末調整業務は、対象者の確認や申告書類の回収・確認、給与計算への反映といった実務を短期間でこなす必要があります。労務担当者は、ミスなく進めるために早めの準備をしておかなければなりません。
関連記事:年末調整とは? 確定申告との違い、対象者、流れ、計算、適用される控除 – カオナビ人事用語集
【勤怠アラートで、月末の勤怠管理業務がラクになる!】
カオナビならコストを抑えて、勤怠管理・労務管理・タレントマネジメントを効率化!
●勤怠の集計や給与計算、就業管理がラクになる
●従業員が自身の勤怠や有休の残日数を把握できる
●有休・労働時間の適正把握で法制度にも対応
●PCに不慣れな従業員でも使える画面設計で説明書いらず
●スマホにも対応しているので、PCのない環境でも安心
2025年4月から大幅改正される「育児介護休業法」とは?
・改正のポイントを社労士が解説
・育成・介護の改正イメージを図解でわかりやすく
・法改正で対応すべき内容をチェックリストで確認
無料の解説資料をダウンロード⇒こちらから
年末調整はいつやる?スケジュールの目安を解説
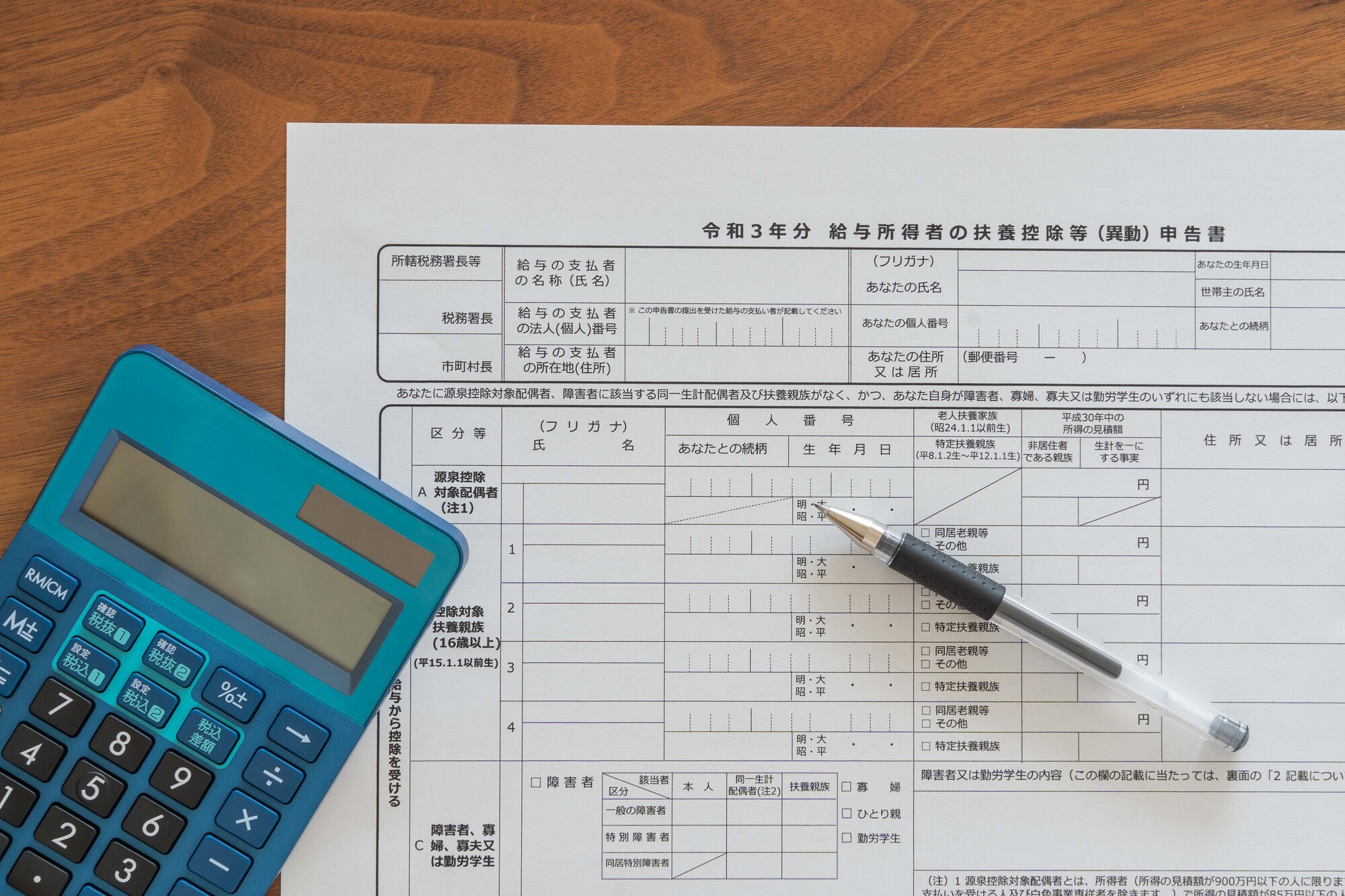
年末調整の業務に慣れていない労務担当者だと、「いつから書類の配布・回収を進めればよいのか」「計算はいつまでにしなければならないのか」など、疑問が多いでしょう。国税庁が発表している資料をベースに、年末調整をふたつのフェーズに分けて時期の目安を解説します。
提出書類の回収・確認の時期
年末調整の書類は、10月中に従業員へ配布し、11月中には回収・確認まで完了させるのが理想です。源泉徴収の過不足は、12月の給与支給時に年末調整で確定した税額を基に精算します。そのため、11月中に申告書の提出・確認まで終わっていないと、対応に十分な時間を確保できません。
特に提出書類に不備がある、配偶者控除・保険料控除の証明書など添付書類が不足しているといった場合は修正依頼・従業員側の対応に時間がかかるため、ミスに備えて早めの提出を促す必要があります。
電子化を進めており、必要情報をWebフォームから入力できるようにしている企業でも、控除証明書などの原本提出が必要な場合はその提出期限をあらかじめ設定しておきましょう。
年末調整のスケジュールは、企業の給与支給日や就業カレンダーに左右されます。毎年の予定に応じて早めに社内スケジュールを作成・共有し、従業員への通知と提出督促を行うことが、円滑な年末調整の実施につながります。
なお、年末調整に必要な書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」「基礎控除申告書」の3点が基本です。これらの書類はすべての従業員が対象となります。
参考:国税庁『令和6年分 年末調整についてのお知らせ』
参考:国税庁『令和6年分年末調整のしかた(手順などの説明)』
年末調整の計算・反映作業の時期
従業員から提出された申告書類を基に、年末調整の計算を行う時期は12月上旬が一般的です。12月の給与に反映させる必要があるため、勤怠の締日や給与計算のスケジュールに合わせて、11月中に確認を終え、12月初旬には控除額の確定と過不足額の計算を完了しておきましょう。
年末調整の結果は、12月支給の給与に「源泉徴収税額の調整」として反映されます。徴収した所得税額に過不足が生じていれば、ここで精算することになります。
給与を支給してしまった後に訂正が発生すると、再計算や再提出などの事務負担が増えるでしょう。従業員への確認も含め、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
入社手続き、年末調整、人事評価、スキル管理など時間が掛かる人事業務を効率化。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」でリーズナブルに問題解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
年末調整の対象となる給与と還付・徴収のタイミング

特に初めて年末調整を任される労務担当者だと、年末調整の対象となる給与や、いつ還付・追加徴収を行うのかを疑問に思うかもしれません。ここでは、二つの疑問について、イレギュラーなケースを除いたルールを紹介します。
いつからいつまでの給与が年末調整の対象?
年末調整の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与です。ただし、実際の支払いが翌年になった場合でも、その年のうちに支払うことが確定していれば年末調整の対象となります。
例えば2025年12月分の給与を2026年1月に支給する場合でも、2025年12月31日までに金額が確定していれば、その分も2025年の年末調整に含まれます。
年末調整業務に初めて携わる労務担当者は、「いつ支払われたか(または支払が確定したか)」で年末調整の対象となる給与が決まることを覚えておきましょう。
還付・追加徴収のタイミングはいつ?
年末調整による所得税の還付や追加徴収は、通常12月支給分の給与に反映されます。年内最後の給与計算で1年間の所得税額を再計算し、源泉徴収済みの金額と差額を調整するためです。
年末調整で源泉徴収額の過不足があった場合には、差額を12月の給与計算に反映します。還付金はほかの控除と相殺して手取りに上乗せし、追加徴収がある場合は控除額を増やす形で処理するのが一般的です。
12月の給与計算が間に合わない場合や退職者など個別対応が必要なケースでは、翌年1月支給分で調整することもありますが、基本は「12月支給分で精算」が原則です。
入社手続き、年末調整、人事評価、スキル管理など時間が掛かる人事業務を効率化。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」でリーズナブルに問題解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
年末調整業務で特に負担が大きい業務とは
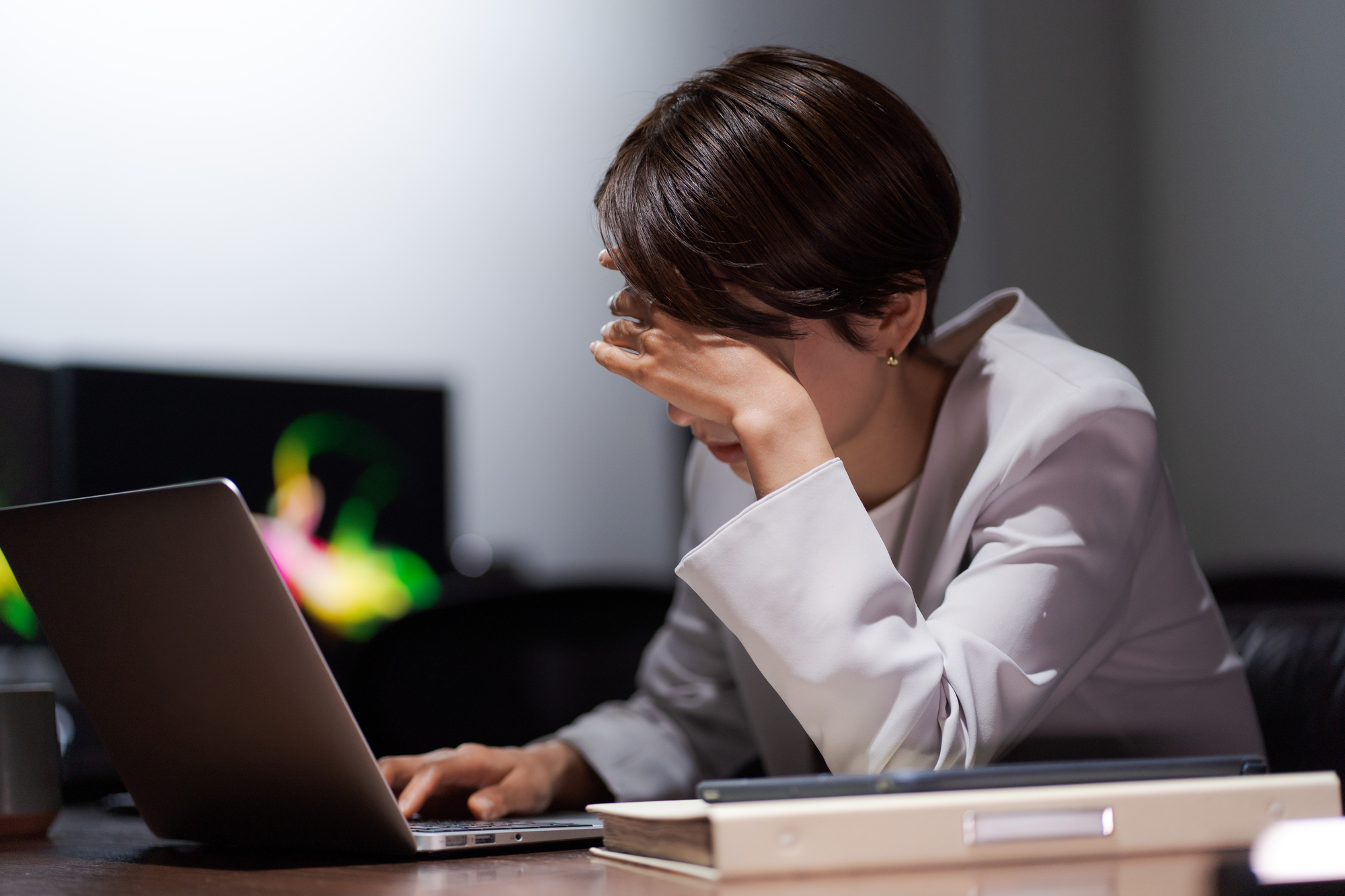
年末調整業務に携わるに当たって押さえておきたいのが、負担の大きい業務です。どのような対応に時間を取られるのかをあらかじめ知っておけば、計画的な準備の必要性が分かるでしょう。
提出漏れ・記入ミスへの対応
年末調整では、従業員からの申告書類や証明書類の提出漏れ・記入ミスが多く発生しがちです。特に11月後半から12月にかけて、労務担当者はほかの業務も立て込んでくる時期のため、確認作業が後手に回りミスに気づくのが遅れる場合もあるでしょう。
提出漏れや記入ミスが発覚した場合、源泉徴収票の発行前であれば企業側での修正が可能ですが、発行後や翌年1月31日の法定調書提出期限を過ぎた場合、従業員本人による確定申告が必要になってしまいます。
加えて紙の書類で回収している企業では、記入不備の見落としや未提出者の把握が難しくなる傾向があります。年末調整に不慣れな従業員が多い職場では、「どの書類を出せばよいか分からない」「氏名や扶養情報の記載に自信がない」といった不安もミスにつながる要因です。
質問が多い項目への対応
年末調整の時期になると、労務担当者は年末調整に関する従業員からの質問対応に追われ、業務負担が増大します。特に初めて年末調整を経験する従業員や、家族構成・保険加入状況が変化した従業員からの問い合わせが多くなると、対応が複雑化するでしょう。
従業員からの質問内容は、控除対象の範囲や申告書の記入方法・必要な添付書類など多岐にわたります。これらの質問に対して労務担当者は正確かつ迅速な対応が求められ、業務負担は相当に大きくなるはずです。
また、年末調整に関する制度変更や法改正が頻繁に行われるため、最新の情報を把握し、従業員に適切な説明をする必要があります。
このような状況は、労務担当者の業務効率を低下させる要因です。従業員からの質問対応や説明に多くの時間を割かれることで、ほかの重要な業務が滞る可能性も否めません。
労務担当者が年末調整業務を円滑に進めるには、従業員への事前の情報提供や教育・FAQの整備など、質問対応の負担を軽減する仕組みづくりが必要です。
労務管理システムで、面倒な入退社手続きはどれくらい楽になる?
「入退社手続きガイド」で、労務管理システム導入のメリットをわかりやすく!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
「カオナビ労務」を使った年末調整業務の効率化

年末調整業務は、労務担当者の負担が大きい業務です。負担を減らしてミスを軽減し、効率化を進めようと思うなら、ツールの導入も選択肢に入ります。労務の効率化を助けるクラウドシステム「カオナビ」は、労務管理機能も備わっており年末調整の効率化に役立つ機能がそろっています。
CSVテンプレートでデータを事前登録する
カオナビ労務の年末調整機能では、従業員情報をCSVテンプレートで一括登録できるため、年末調整の準備段階から入力作業の効率化が図れます。氏名や扶養親族・保険料控除に関するデータを手入力する必要がなくなり、入力ミスのリスクも大幅に低下するでしょう。
特に従業員数が多い企業では、手作業で従業員情報を入力する手間が膨大になり、担当者の大きな負担となります。CSVテンプレートを使えば、必要な情報を事前に一括登録できるため、繰り返し入力の手間を省き、全体の作業時間を大幅に短縮できます。
質問コメントのカスタムで混乱を防止する
従業員からの質問が集中しやすい項目には、年末調整機能に備わっている、質問が来そうな部分をカスタムしておける機能を活用できます。会社独自の説明や補足を質問画面に表示できるため、従業員は内容をより正確に理解し、正しく入力できるようになります。
労務担当者が同じ内容を繰り返し個別対応する手間が減り、集中的な問い合わせ対応の負担軽減が可能です。業務の属人化防止にもつながります。
提出ステータスを可視化して管理する
年末調整業務では、誰が提出済みか・どの申請が差戻しになっているかという進捗を把握するのが煩雑になりがちです。カオナビ労務では、ステータス管理画面で全従業員の進捗をひと目で確認できます。
提出忘れや未対応者へのリマインドもスムーズに行えるため、担当者がエクセル等で別途管理する手間がなくなります。進捗状況を可視化できれば、締め切り間際の混乱や確認漏れのリスクを最小限に抑えられるでしょう。
PDF出力や不備チェックで確認作業を効率化する
カオナビ労務の年末調整機能は、申告データのPDF出力や従業員の記入漏れを防止できるようになっています。
紙の書類を印刷・配布・手作業で確認するといった非効率な工程を省略できる上、従業員の入力に不足があると次に進めないようになっているため、記入漏れによる差戻し件数も大きく減るはずです。
労務担当者が見落としを心配することなく確認作業を進められ、作業精度とスピードの両立が可能になります。
月末の勤怠業務の負担を軽減!勤怠管理システムの選び方や比較ポイントを解説。 「勤怠管理システムガイド」で、自社に適したシステムがわかる! ⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロードまとめ
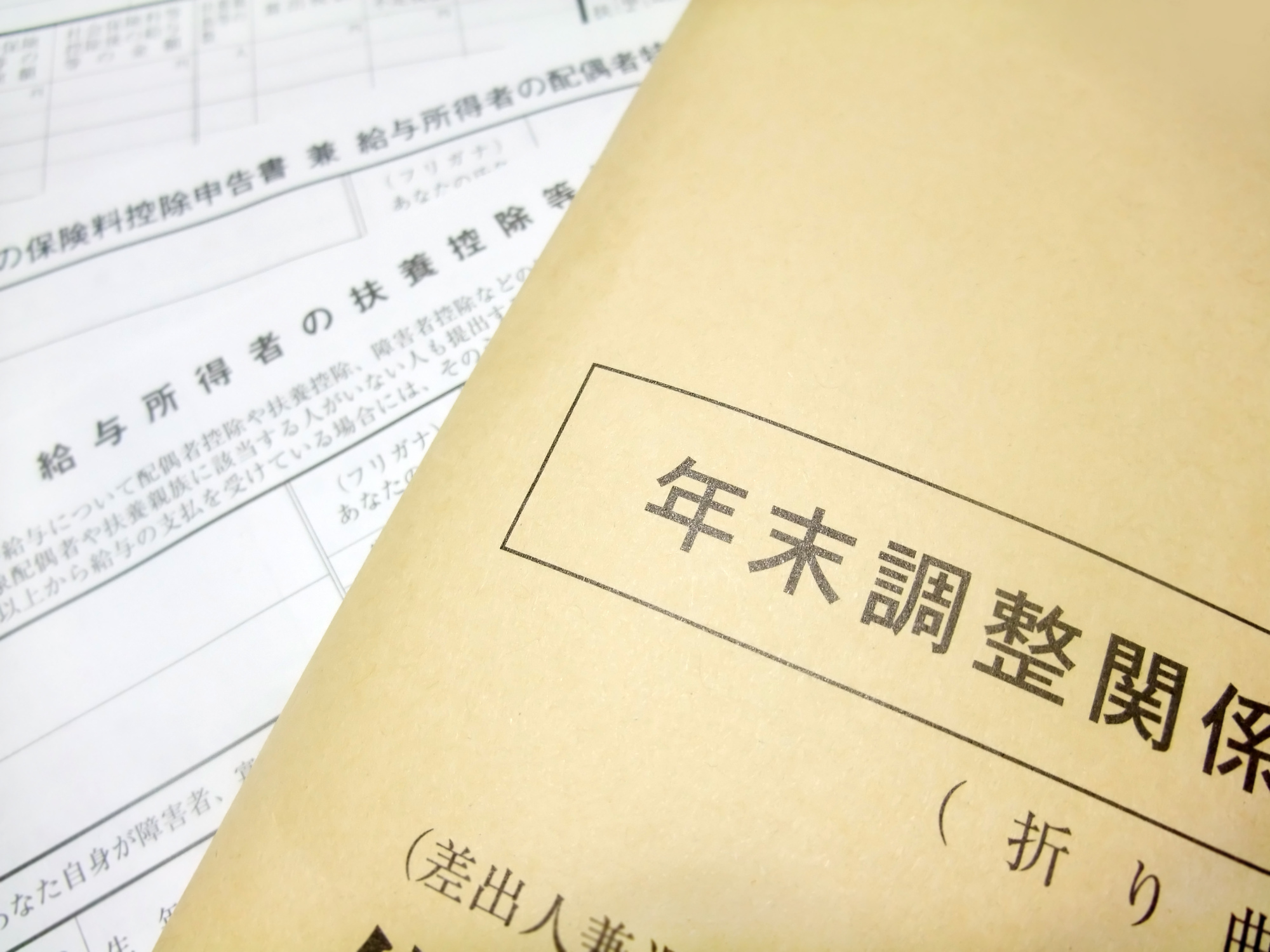
年末調整の手続きをいつから始めればよいか迷ったら、源泉徴収票の交付期限である翌年1月31日を起点に逆算して準備しましょう。実務では、10月〜11月にかけて従業員から申告書を回収し、12月分の給与計算に反映させる流れが理想です。
スムーズに進めるには、提出の催促や申告内容のチェックを早めに進め、提出状況を可視化できる仕組みを整えておくと安心です。年末調整は毎年発生する業務だからこそ、進行のパターンをつかみ、スケジュールを明確にすることで負担を大きく軽減できるでしょう。
【労務管理もタレントマネジメントもコスパよく】
カオナビならコストを抑えて労務管理・タレントマネジメントを効率化!
●紙やExcelの帳票をテンプレートでペーパーレス化
●給与明細の発行や配布がシステム上で完結できる
●年末調整の記入や書類回収もクラウドで簡単に
●人材情報の一元化・見える化で人材データを活用できる
●ワークフローで人事評価の運用を半自動化できる

