希望退職制度とは、退職を希望する従業員を募り、人員整理や人件費削減を図る退職措置の1つです。退職金を一時的に割り増すなどして優遇措置を取り、対象の従業員に対して退職を促します。
今回は希望退職制度とは何かをふまえて、従業員側と企業側それぞれのメリットやデメリット、注意点を詳しく解説します。
目次
1.希望退職制度とは?
希望退職制度とは、主に定年前の従業員を対象に、時期を設定して従業員が自らの意思で退職を選択する制度のことです。期限や目標人数を設定し、臨時的に行われる退職措置といえます。希望退職制度は業績悪化に伴う人件費削減や経営リスクの回避、新陳代謝を目的とした、人員整理の手段の1つです。
希望退職制度は、退職金を一時的に割増するといった優遇措置を提示します。法的な拘束力はないため、従業員に退職を強制できません。というのも、従業員の解雇は労働者保護の観点からも厳しい制限があるからです。
制度を利用した退職では、原則自己都合ではなく、会社都合での退職が成立します。
2.希望退職制度と早期退職制度の違い
希望退職に類似する制度に、定年を待たずに退職できる早期退職制度があります。ここでは、希望退職制度と早期退職制度の違いをみていきましょう。
制度の利用期間
早期退職制度は臨時的に導入される制度ではなく、企業によっては制度として定着しているケースもみられます。希望退職は期間限定で実施される制度であり、早期退職はつねに誰でも利用できる制度である点が違いです。
制度の目的
早期退職制度は組織の人員構成を整えたり、従業員の人生の選択肢を広げたりすることを目的に実施されるため、希望退職制度よりもポジティブな意味合いをもちます。
福利厚生の一環として導入されているケースもあり、定年後のキャリアアップや新しいことにチャレンジするための時間確保などを目的に早期退職する人も少なくありません。
ただし、自らの意思で退職を選択するため自己都合退職となる点は希望退職制度との違いです。

早期退職制度とは? メリット・デメリット、対象金への影響
昨今、注目を集める早期退職制度をご存じでしょうか。ここでは、早期退職制度の目的や特徴、メリット、デメリットなどについて解説します。
1.早期退職制度とは?
早期退職制度とは、従業員が通常よりも早く自...
3.希望退職制度で退職金はどうなる?
優遇措置として特別退職金が上乗せされるため、退職金が割増で支給されます。特別退職金の額に決まりはなく、企業の財政状況や従業員の勤続年数や年齢なども考慮して企業側が自由に設定可能です。一般的には年収の2倍が相場といわれています。
下記は、希望退職制度における退職金の設定例です。
| 年齢別に加算する場合 | ・55歳以上:基本給×4ヶ月 ・30歳未満:基本給×1ヶ月 |
| 勤続年数別に加算する場合 | ・勤続年数15年以上:基本給4ヶ月 ・3年未満:基本給×1ヶ月 |
最初に行った金額設定がその後も基準となるため、不満が起こらないよう金額設定は慎重に行う必要があります。なぜなら、先に行った希望退職よりも退職金が少なくなってしまうと、応募が集まらないリスクがあるからです。

退職金とは? 高卒・大卒の相場、計算方法、税金
退職金は、従業員が企業を退職した際に支給される金銭で、退職後の生活基盤を支える原資として、労働者にとっては重要な意味を持ちます。近年、この退職金制度に改革の波が押し寄せているのです。
退職金とは何か...
4.希望退職制度のメリット
希望退職制度は、従業員と企業の双方にメリットがある制度です。それぞれのメリットを詳しく解説します。
従業員側
従業員側のメリットは、以下3つです。
- 退職金が増える
- 会社都合で失業保険が受給できる
- 転職活動がしやすい
①退職金が増える
優遇措置によって、通常より多くの退職金がもらえます。ただし、割増分がどれくらいか、どのように決定するかは企業によってさまざまです。
また、退職制度がない場合でも、希望退職制度なら退職金が支給されます。さらに、勤続年数的に本来は退職金がもらえない人でも支給される点もメリットの1つ。
しかし、「退職金がもらえるから」「退職金が増えるから」といった観点だけで希望退職を決めないよう注意しましょう。
②会社都合で失業保険が受給できる
希望退職では会社都合扱いとなるため、失業保険の受給にメリットを得られます。
自己都合退職では、失業保険が支給されるのは退職から2ヶ月と一週間後であり、支給日数は90〜150日、最大支給額は約118万円です。
一方、会社都合退職では、待期期間の一週間が経過すればすぐに支給され、支給日数は90〜330日、最大支給額は約260万円となります。
支給開始のタイミングだけでなく、支給日数や最大支給額の面でも有利になる点が特徴です。ただし、支給日数や支給額は、被保険者だった期間によって異なります。
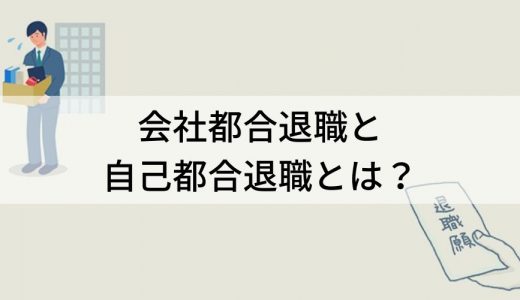
会社都合退職と自己都合退職とは? 手続き、退職推奨との関係
会社都合退職と自己都合退職とは、会社を退職する際の理由による区分けです。ここでは、両者について解説します。
1.会社都合退職と自己都合退職とは?
会社都合退職とは、解雇や退職勧奨、倒産や事業整理とい...
③転職活動がしやすい
自己都合退職は、在籍期間や理由によっては転職活動でマイナス評価になる恐れがあります。しかし、希望退職は会社都合退職となり、かつ希望退職を次のキャリアのために前向きに選択したとアピールできれば、キャリアに影響しにくい点がメリットです。
また、退職してからの転職活動になるため、じっくりと取り組める点もメリットといえます。自己分析や企業研究に時間をかけられるだけでなく、選考の日程調整に悩むことも少なくなるでしょう。
さらに、退職金や失業保険金が支給されるため、当面のお金の心配が少ないメリットもあります。企業によっては希望退職制度の措置として再就職サポートを提供している場合もあり、単なる退職よりも転職活動がしやすくなります。
企業側
企業側のメリットは、以下3つです。
- 人件費が削減できる
- 組織の新陳代謝を図れる
- 従業員とトラブルになりにくい
①人件費が削減できる
一般的に希望退職制度は、経営悪化やそのリスクを見越して実施されます。人件費は簡単に節約できるものではなく、コストに占める割合も大きいため、希望退職制度によって人員を削減することでその分の人件費削減につながります。
とくに中高年層の人件費は大きな負担となっているケースも多いでしょう。かといってかんたんにリストラできないため、希望退職制度によって円満なコスト削減を図っています。
②組織の新陳代謝を図れる
現代は変化の激しい時代であり、組織にも変革が必要であるため、組織の新陳代謝を促すことも重要です。企業の古い慣習を断ち切るため、新入社員の離職が激しく従業員の年齢層が高いといった状況を打開する施策として希望退職制度を導入するケースもあります。
また、新しい経営方針となり、新たな人材を採用すると同時に希望退職を募って新陳代謝を図ることも。
さらに「黒字リストラ」として、中高年層を対象に希望退職を募って若手に所得を分配する取り組みとしても実施されます。
③従業員とトラブルになりにくい
リストラは企業側が退職を強制するもので、従業員の意思とは関係のない退職となるためトラブルに発展するケースもあります。最悪のケースでは、裁判や労働審判に発展することともあり、公になれば企業のイメージダウンにもつながりかねません。
一方、希望退職は従業員の意思を尊重し、双方の納得と合意のもと行われるため、トラブルに発展するリスクが低いといえます。ただし、退職金やその他優遇措置が話とは違ったといったようなトラブルが起こる可能性はあるため、正しい情報提示が必要です。
5.希望退職制度のデメリット
一方で、希望退職制度にはデメリットもあります。メリットと同じく、従業員側・企業側の視点からデメリットを解説していきます。
従業員側
従業員側のデメリットは、以下3つです。
- 安定した収入が途絶える
- 転職先が決まらない恐れもある
- 引っ越しなどのコストがかかる場合もある
①安定した収入が途絶える
退職金や失業保険金が支給されるとはいえ、それらは一時的なお金に過ぎません。退職によって安定した収入が途絶えてしまうため、新たな就職先がなかなか見つからないと精神的な焦りも出てくるでしょう。
会社員時代と同じお金の使い方をしてしまうと、予想以上にお金の減りが早くなってしまう恐れもあるため要注意です。
また、退職後は新たな就職先に入社するまで国民年金への加入となるため、年金支給額が減ってしまう点も将来的な収入面におけるデメリットでしょう。
②転職先が決まらない恐れもある
希望退職を行っている企業は景気がよくない可能性が高く、社会的にそうした傾向にある恐れも考えられます。
そうした状況では、再就職先がなかなか見つからない可能性も。退職してからゆっくり再就職先を探そうとしていた場合、うまくいかないリスクが高まります。また、転職活動期間が長引くと、空白期間がマイナス評価につながる可能性もあるため要注意です。
③引っ越しなどのコストがかかる場合もある
社宅に住んでいるといったように、福利厚生で生活の大部分を賄っていた場合、退職によって補助を受けていた分のコストがかかります。とくに、社宅に住んでいる場合は引っ越しも発生するためコストがかかるだけでなく、部屋探しの手間も発生するでしょう。
そのため、単純な退職金だけでなく、企業からの補助などもふまえて希望退職が自分にとってメリットのあるものかを考えて行動することが大切です。
企業側
企業側のデメリットは、以下2つです。
- 一時的にコストがかかる
- 優秀な人材が退職してしまう可能性がある
①一時的にコストがかかる
希望退職制度は経営悪化のリスクを回避することが目的である一方、退職金の割増によって一時的にコストがかかる施策でもあります。そのため、現状ですでに経営が逼迫している状態では、さらに経営悪化を促してしまう恐れがある点はデメリットです。
中長期的にみると人件費を削減できるためコスト削減に有効ですが、一時的なコスト発生に対処する必要があります。経営を圧迫させないためにも、希望退職制度を実施する場合は目標人数や退職金を計画的に検討することがポイントです。
②優秀な人材が退職してしまう可能性がある
優秀な人材は再就職もしやすく、なかには希望退職を募ったタイミングで退職を検討している人がいるかもしれません。
都合のよいタイミングで希望退職制度が実施されることで、退職金などによるメリットを得て退職するために希望退職をしたいと考える人も出てくるでしょう。
とはいえ、希望退職は双方の合意がないと成立しないため、優秀な従業員の希望退職は引き止められます。しかし、退職を阻止できたとしても忠誠心が低下したり、信頼関係が崩れたりしてしまう恐れがあるため、優秀な従業員が希望退職しないよう工夫も必要です。
6.希望退職制度の注意点
最後に、希望退職制度を利用する際の従業員側・企業側の注意点をお伝えします。
従業員側
従業員側の注意点は、以下3つです。
- 必ずしも希望退職できるとは限らない
- 希望退職を拒否したことで解雇されるリスクがある
- 目先の退職金にとらわれない
①必ずしも希望退職できるとは限らない
希望退職に応募しても、企業側が納得しない場合は退職できません。また、対象者が限定されており、対象外である場合はそもそも希望退職制度の利用が不可能です。
さらに、企業側が手放したくないと思う人材の希望退職は、申し入れがあっても成立しないことが一般的です。
しかし、一度希望退職に応募して退職できないと、その後社内での居心地が悪くなってしまうリスクがあるかもしれないため、希望退職制度の利用は慎重に検討しましょう。
②希望退職を拒否したことで解雇されるリスクがある
円満な人員整理を行うため、まずはリストラの前に希望退職を募るケースもあります。それでも応募者がいない、希望退職に応募してほしいと思っていた人からの応募がない場合、将来的にリストラに値する整理解雇を行う可能性も考えられます。
こうした解雇では、希望退職制度にある退職金の割増などの優遇措置はありません。リストラの対象になる可能性がある場合、希望退職を逃すことでのちのちリストラされるリスクがある点は注意が必要です。
③目先の退職金にとらわれない
希望退職制度は、とくに退職金面で一般的な退職よりも好条件です。しかし、退職後に再就職できないなどのリスクもあるため、目先のお金にとらわれて希望退職を選択するのは賢明ではありません。
目先の条件だけでなく、中長期的な視点に立って希望退職が正しい判断かを見極めることがポイントです。
企業側
企業側の注意点は、以下2つです。
- 不法行為にならないよう気を付ける
- 対象者を性別で限定しない
①不法行為にならないよう気を付ける
対象者を限定することはできても、ダイレクトに退職してほしいと考える人の応募があるとは限りません。希望退職を勧めることもできますが、従業員との今後の信頼関係にヒビが入る可能性が高いです。
かといって、希望退職を強制したり、応じなかったことで不当に扱ったりすることは不法行為にあたります。最悪のケースで損害賠償が請求される恐れもあるため、希望退職制度には企業側も慎重に取り組むことが大切です。
②対象者を性別で限定しない
年齢や役職、部署などで対象者を限定することに問題ないものの、性別で限定するのは違法性があるとみなされてしまいます。とくに、近年は多様性が重視されているため男女差別に値するような行為は企業イメージや信頼性を損ねる原因となるため要注意です。
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

