社内の人的資本を可視化して、組織図を作りませんか?
タレントマネジメントシステムで、時間がかかる人員管理を解決!
⇒タレントマネジメントの解説資料【3点セット】を無料ダウンロード
組織図は組織の内部構造を社内外に見える化するほか、さまざまなメリットをもたらしてくれます。ただし組織図にもいくつか種類があるため、目的に合わせて最適な形式を選ぶとよいでしょう。
ここでは組織図とは何かをふまえながら、組織図をつくる目的やメリット、作り方や用いるツールを詳しくご紹介します。
目次
1.組織図とは?
組織図とは、組織の内部構造を図式化したもの。基本は取締役会から各部署、部門の配置や役割、指揮系統を示し、なかには職務や責任の範囲、権限や従業員の連絡先、顔写真まで掲載されている組織図もあります。
組織図に掲載する情報の粒度は、用途に応じてさまざまです。
【スキル管理の「わからない」「時間がかかる」を解決】
「カオナビ」なら、全社員のうち誰がどんなスキルを持っているかを見える化!
●社員の能力やスキルが一覧で可視化される
●スキルと合わせて人件費の変動も分かる
●顔写真で現場の雰囲気を確認しながら確認できる
●スキルだけではなく人間性やエンゲージメントもわかる
2.組織図をつくる目的
組織図をつくる目的は、社内向けか社外向けかによって異なります。下記で、各目的を詳しくみていきましょう。
社内向けの目的
社内向けの組織図は、従業員に向けて作成します。主な目的は、組織構成や自分の部署の役割・立ち位置、指揮命令系統の認識・確認など。
社内向けの組織図は部門や課、チームや担当者、職務など詳細な情報を記載するケースが多くみられます。従業員が組織における自分のポジション・役割を認識したうえで業務を遂行できるようにするためです。
社外向けの目的
社外向けの組織図は取引先や株主、消費者などのステークホルダーに向けて作成します。主な目的は、組織の構造や骨組み、経営の健全性を示すためです。
たとえば「監査役」の記載は、第三者による監査が実施されているとわかるため、組織の健全性を示すために有効になります。また組織図が開示されているため、自社の透明性が示せ、ステークホルダーからの信頼獲得にも役立つのです。
なお社外向けの組織図は部署や部門単位の記載が一般的であり、社内向けの組織図ほどの粒度ではありません。
適切な組織図を作るための「タレントマネジメント」を戦略的に行えていますか?
具体的なやり方や、自社に合ったシステムの選び方を解説!
⇒資料を無料ダウンロードする
3.組織図をつくるメリット
組織図には、次のようにさまざまなメリットがあります。それぞれについてみていきましょう。
- 指揮・命令系統が明確になる
- 従業員の役割や事業理解に役立つ
- 権限が適切に分配できる
- 社外に組織の健全性をアピールできる
- 人材戦略に活用できる
①指揮・命令系統が明確になる
組織図によって「誰が誰に指示を出すのか」「誰が責任や権限を持つか」一目でわかります。指揮命令系統が明確であれば、新規プロジェクトの進行やトラブルにおける現場の混乱防止にも役立つでしょう。
とくに「組織規模が大きい」あるいは「構造が複雑な組織」であるほど、指揮命令系統が不明瞭になりやすいため、組織図によるメリットも大きくなります。くわえて、業務効率化・円滑化にも有効です。
②従業員の役割や事業理解に役立つ
組織構造を俯瞰できるため、全体像を把握しやすくなる点もメリットのひとつ。自分のポジションや役割が認識でき、自覚を持って業務に取り組めるようになります。また部署同士の関係性や事業での役割も把握でき、連携しやすくなるため業務効率化にも有効です。
さらにお互いの理解が深まるため、コミュニケーションの活性化や部署間の連携強化にも効果的といえるでしょう。
③権限が適切に分配できる
指揮命令系統が明確になるため、権限がどこに集中しているか、把握できます。権限が集中していれば適切に分散でき、さらには業務の偏りを発見するのも可能です。業務や権限の偏り・集中を解消し、組織の最適化・効率化が図れます。
④社外に組織の健全性をアピールできる
「健全に組織がマネジメントされている」「不正に対する監視体制が整っている」などステークホルダーへ経営の透明性や健全性がアピールできるため、信頼性の獲得やイメージアップに効果的です。
またコンプライアンスやリスク管理の適切性のアピールにも有効であるため、上場企業の多くはコーポレートサイトに組織図を掲載しています。
⑤人材戦略に活用できる
組織の内部構造を見える化すると、人材配置や採用、部署の新設や統合の検討など人材戦略に活用できます。
たとえば人材配置の場合、組織図によって部署やプロジェクト単位での人員不足や人員過多を把握可能です。そして人員不足の場合は採用強化の判断を、人員過多の場合はスキルや相性などをみて適材適所への配置が検討しやすくなります。
また定期的に組織図をチェックすれば、状況に応じた最適な人材配置の検討も可能になるでしょう。なかには組織図と従業員情報を連携できるシステムもあり、人材戦略の効果アップに役立ちます。

人材戦略とは?【フレームワーク・事例】戦略の立て方
人材戦略は抽象的な言葉であるため、何を目的に行われるのか、具体的にどのようなことを実施するのか明確に理解できていないという方も多いでしょう。
今回は人材戦略とは何かを踏まえて、人材戦略策定に役立つフレ...
社内の人的資本を可視化して、組織図を作りませんか?
タレントマネジメントシステム「カオナビ」の導入効果を解説!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
4.組織図の種類と特徴
組織図には、下記の4種類があります。
- ピラミッド型(階層型)
- フラット型
- マトリックス型
- 事業部門別
どの形式を用いて組織図をつくるかは、組織形態や組織図作成の目的によってさまざまです。各組織図の特徴をふまえて、種類を解説していきましょう。
①ピラミッド型(階層型)組織図
ひとつの組織またはグループをピラミッドの頂点に置き、その配下に各組織やグループを配置する形式のこと。伝統的であり代表的な組織図で一般的に、取締役会や株主総会をピラミッドの頂点に配置します。
ピラミッド型(階層型)組織図における指揮命令系統はひとつのため「誰が誰の管理下にあるのか」「誰に責任があるのかが明確になる」のです。
一方、縦割りの配置となるため、階層が増えると情報伝達や意識決定に時間がかかったり、横の連携が取りにくいといったデメリットがあります。

ピラミッド組織とは?【フラット・マトリックス組織との違い】
ピラミッド組織とは、トップを最上位に置き、命令や指示が上層から下層に伝わる組織のこと。ここではピラミッド組織の種類や、メリットとデメリット、フラット組織やマトリックス組織との違いなどを解説します。
...
②フラット型組織図
ピラミッド型と似ているものの、上下に多くの階層を持たず階層が平らになるため、フラット型と呼ばれます。
そのため、意思決定や情報伝達の遅さに関するデメリットは解消されるものの、中間管理職が少ないため1人あたりの責任や負担が重くなりやすい傾向にあるのです。
よって「指揮命令系統を細かく定めていない」「役職や部署の人数が少ない」組織に向いています。
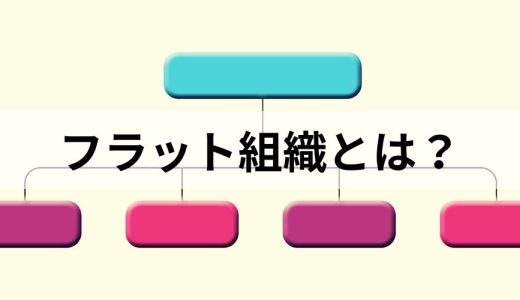
フラット組織とは?【ピラミッド組織との違い】メリデメ
フラット組織とは、管理層を減らして役職構造をフラット(平面的)にした組織形態のこと。ここではフラット組織のメリットとデメリット、ピラミッド組織との違いなどについて解説します。
1.フラット組織とは?...
③マトリックス型組織図
複数の要素を組み合わせて構成された形式です。部門・職能・エリア・プロダクトといった要素を縦軸と横軸で掛け合わせて配置します。
たとえば事業部ごとに部門が分かれている組織では、マトリックス型組織図を適用すると、複数の要素が把握しやすくなるのです。
「部門を超えた連携がしやすい」「コミュニケーション活性化につながる」といったメリットがある一方、指揮命令系統が複数になるため責任の所在が不明瞭になりやすいといえます。

マトリクス組織とは?【図解で簡単に】メリット・デメリット
マトリクス組織特有の「管理できない」「計画が進まない」に悩んでいませんか?
人材管理システム「カオナビ」なら、社員ごとの業務進捗・リソース状況が可視化できます。
⇒ 【公式】https://www.k...
④事業部門別組織図
代表取締役や取締役会といった経営層をトップに置き、その配下に各部門や事業部を配置する形式です。組織によっては、エリア別に配置するケースもあります。
形式はピラミッド型と同じであるものの、部門に焦点を置いているのです。責任や権利は各部門や事業部の部長に分配されるため、事業部・部門ごとの意思決定スピードが早くなります。
データドリブンなタレントマネジメントを行うポイントを解説!
基礎的な知識や、具体的なやり方を紹介。
⇒資料を無料ダウンロードする
5.組織図のつくり方
組織図はかんたんに作成できるものの、ただ組織の内部構図を反映しただけでは活用しにくくなってしまいます。下記ステップをふまえて、戦略的な組織図をつくりましょう。
- 目的を明確化する
- 組織図の種類を選定する
- 対象範囲を決める
- 情報収集する
- 組織図に反映する
①目的を明確化する
まずはそれぞれの役割を理解したうえで、社内向けか社外向けか、明確にしましょう。目的によって、内容と組織図の種類も決まります。
社内向けの場合は「人材配置に活用したいのか」「社内のコミュニケーションを活性化させたいのか」など、組織図作成の目的をさらに深堀りしてみてください。
②組織図の種類を選定する
目的や組織形態、用途に合わせて、活用しやすい組織図の種類を選定します。
- ピラミッド型(階層型):一般的な組織図をつくりたい、指揮命令系統や責任の所在を明確にしたい
- フラット型:トップから現場までの階層を少なくしたい、指揮命令系統を細かく定めていない、役職数が少ない、部署の人数が少ない
- マトリックス型:プロジェクトごとに担当者やエリアが異なるといった複数の要素を見やすくしたい、エリアや支店単位で責任者を配置している
- 事業部門別:各事業部の業務内容が明確に異なる、事業部ごとに複数チームが独立して遂行している
種類が決まったら、どういったツールで組織図を作成するかも決定していきましょう。
③対象範囲を決める
部門・部署・役職・従業員の個人情報(連絡先など)など、組織図の構成要素はさまざま。社内向けか社外向けなのか、どのように活用するのかによって取り入れる情報は異なります。
取り入れる情報を決めるためにも、まずは組織図を「組織全体」「部門ごと」「事業部ごと」のどの範囲で作成するか、検討しましょう。
社外向けの場合は部署・役職までの記載が一般的で、社内向けの場合、目的によって粒度が変わります。マネジメントやコミュニケーションに活用したいときは、氏名や顔写真まで載せる場合もあります。
④情報収集する
組織図の目的や対象範囲が決まったら、具体的に情報収集を開始します。
時間はかかってしまうものの、従業員の個人情報はメールやチャットツールなどを用いて個別に収集したほうがよいでしょう。部署ごとに担当者を設けて、最大限効率化できる方法で情報収集を進めます。
なお社外向けの組織図に個人情報を載せるときは、トラブル防止のため個人情報の取り扱いに関する同意を得るようにしてください。
また社内向け組織図で従業員情報を細かく収集したいときは、従業員情報を活用するためにも人事部門との連携が重要です。活用できる組織図をつくるには人事が扱う情報の精度が重要になるため、日頃からの情報収集が鍵となります。
また正確な情報収集が組織図の精度を高めるのも事実。経営層と連携して情報を整理しながら作成を進めるとよいでしょう。
⑤組織図に反映する
必要な情報が収集できたら、組織図に反映します。主な作成ツールはパワポやエクセル、人材管理システムなど。組織図を作成できる無料ツールも多くあるため、使いやすさや作成できる組織図のクオリティから使うツールを選びましょう。
情報をただ反映するだけでなく、レイアウトを整えて見やすく・活用しやすい組織図をつくることが大切です。
社内の人的資本を可視化することで、組織図を効率的に作れます!
タレントマネジメントシステム「カオナビ」の導入効果や機能を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
6.組織図をつくる際のポイント
組織図をつくる際は、下記ポイントまで意識しましょう。
- 組織図を活用する目的の明確化
- レイアウトの統一性確保
- 組織変化への対応力向上
- 更新体制とルールの策定
組織図を活用する目的を明らかにする
組織図作成において、活用目的を明確に定義することが大切です。
目的が曖昧なまま組織図を作成すると、必要な情報が不足したり、情報過多で見づらい図になったりします。社内向けと社外向けでは、記載すべき情報の詳細度が大きく異なるため、目的に応じた適切な設計が必要です。
たとえば、新入社員のオンボーディング用なら顔写真と連絡先を含める必要があります。一方、株主総会資料用なら役員クラスのみを簡潔に表示した組織図が望ましいです。
人事異動のシミュレーション用なら、スキルや適性情報も含めた詳細な情報があるとよいでしょう。
組織図作成前に、誰が・いつ・何のために使うか、という3つの観点で整理することで、承認者にとって価値のある組織図を短時間で作成できます。
レイアウトを統一する
統一されたレイアウトは、組織図の可読性を向上させる重要な要素です。
レイアウトの統一により、情報の階層性が明確になり、見る人が直感的に組織構造を理解できるようになります。
具体的には、以下のようなポイントを守ることで、可読性の高い組織図が作成できます。
- 同じ階層の役職は同じ色とサイズで統一する
- 部門ごとに色分けをおこなう
- フォントは最大3種類に制限する
- 図形の間隔も一定に保つ
作成前にレイアウトルールを文書化し、標準化しておくことで、複数人の作業でも統一感のある組織図を維持できます。
組織の変化に対応できるようにする
柔軟性のある組織図設計により、人事異動や組織改編にスムーズに対応できる仕組みを構築しましょう。
人事システムの中には、従業員の役職やスキルを更新すると、自動的に組織図を更新してくれるものもあります。
また、マトリックス型組織やアジャイル組織では、プロジェクトベースでの流動的な構造に対応できる表現方法を採用します。
将来の組織変更を事前に想定し、拡張性を考慮したツール選択と情報設計を行うことが重要です。
更新担当者と更新ルールを決める
組織図の正確性と信頼性を維持するためには、明確な更新体制とルールの確立が不可欠です。
更新責任者が不明確だと、情報の陳腐化や更新漏れが発生し、組織図の価値が損なわれます。
また、更新頻度やタイミングが定まっていないと、重要な人事異動が反映されずに混乱を招く可能性もあるでしょう。
効果的な更新体制として、人事部門を主担当とし、各部門から情報収集担当者を指名する方法があります。更新ルールには、四半期ごとの定期見直し、人事発令から3営業日以内の反映、変更履歴の記録保持などを含めます。
更新責任者の明確化や定期レビュー日程の設定、変更通知フローの文書化を実行することで、常に最新で信頼できる組織図を維持できます。
タレントマネジメントを行うポイントをわかりやすく解説!
具体的なやり方や、システムの選び方についても紹介。
⇒資料を無料ダウンロードする
7.組織図における分業と権限とは?
組織図における「分業」と「権限」とは、それぞれ次のような意味をもっています。
- 分業…一目で把握できるようにした図の役割
- 権限…役割の間の指揮命令
以下では、分業と権限について詳しく解説していきますので、参考にしてください。
組織の分業を可視化する
分業とは、ひとつの業務を複数人で分担することです。会社が掲げる目標を達成するためにさまざまな仕事を細分化して、誰がどの仕事を担当するのか役割を決めていく方法を指します。
分業では、高度な職務と比較的単純化された職務に切り分け、それぞれの専門性と効率性を高められます。
ただし、組織内の人の流動性を失うというデメリットには注意が必要です。
上司と部下の権限を可視化する
権限とは、企業や部署の目標を達成するために、命令する人の指示どおりに作業するよう従業員に求める命令などのことを指します。
組織図を作る際は、下記について決定する必要があります。
- 会社の目標やビジョンに向けた分業
- 上司と部下の権限をどのように分割するのか
組織の意思決定事項について、経営者はすべてを決められません。そこで権限委譲が必要になってくるのです。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」なら、組織図を簡単に作れます!
導入効果や使える機能をわかりやすく解説。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
8.組織図作成に役立つツール
最後に、組織図作成に役立つ3つのツールをご紹介します。
- PowerPoint
- Excel
- タレントマネジメントシステム
①PowerPoint
PowerPointで組織図を作成するときは複数の図形が組み合わせられるSmartArtを活用します。PowerPointで作成する手順は、下記のとおりです。
まず[挿入] タブの [図] で [SmartArt] をクリックし、次に[SmartArt グラフィックの選択] ギャラリーの [階層構造] をクリックし、組織図レイアウト ([組織図] など) をクリックして、[OK] をクリック。その後、いずれかの操作にて、テキストを入力していきます。
- SmartArt グラフィックのボックスをクリックし、テキストを入力
- テキスト ウィンドウの [テキスト] をクリックし、テキストを入力
- 別の場所またはプログラムからテキストをコピーし、テキストウィンドウの[テキスト]をクリックしてテキストを貼りつけ
る
PowerPointは企業なら必ず持っているツールであるため、手軽に作成可能です。
②Excel
Excelも同じく、SmartArtで作成します。Excelで作成するメリットは、グリッドがあるため図形を配置しやすいこと。PowerPointかExcelかいずれかで迷ったときは、操作への慣れや更新のしやすさなどから選んでみましょう。
③タレントマネジメントシステム
タレントマネジメントシステムは人材管理システムの一種で、人事データを一元化・可視化し、あらゆる人材戦略に活用できるツールです。主に従業員の基本情報やスキル、能力を軸に、評価や配置などさまざまなデータを管理できます。
組織図の作成に必要な情報が一元管理されており、システムによっては情報収集から組織図の作成を一括で行えるものもあるのです。情報収集の手間を効率化し、最新の情報を用いて組織図が作成できます。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」なら、顔写真つきの組織図が手軽に作成可能です。
ドラッグ&ドロップの直感的な操作で見やすい組織図が作成できるだけでなく、PCで作成した組織図をアプリから閲覧できるといった便利な機能も備えています。カオナビなら、人材情報と連携した人材戦略に活用しやすい組織図が作成可能です。

タレントマネジメントシステムとは?おすすめのツールや選び方・比較のポイントを紹介
タレントマネジメントに関する資料を3点プレゼント!
基礎的な知識や、具体的な進め方、システム選定のポイントなどを解説。
⇒ タレントマネジメント【資料3点セット】 を無料ダウンロード
タレントマネジメ...
【組織図を作る際に、必要な情報にすぐにアクセスできる】
人的資本の情報開示やリスキリングにも対応のカオナビ!
データベースで情報を一元管理でき、人員管理にかかる業務効率を効率化!
●使い勝手の良い人材データベース
●人材データ収集・更新をラクにするアンケート
●人事KPIの推移を把握するダッシュボード
●評価業務を半自動化するワークフロー
●組織状況や優秀人材を把握するための分析機能
