P/L・B/S・C/Fを詳しく解説!
経営数字の読み方が、この一冊でまるわかり。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
「この費用は税金計算で差し引けるのだろうか」という疑問に直面したことはありませんか。法人税の計算において、「損金」の理解は税負担を適正に管理するために欠かせません。また会計上の「費用」と税務上の「損金」は異なる概念であり、この違いを正確に把握していないと、思わぬ追徴課税を受けるリスクがあります。
本記事では、損金の基本概念から損金算入・不算入の判断基準、実務における注意点まで、法人税計算の要となる「損金」について体系的に解説します。
損金とは?費用との違いを理解しよう

企業の税務処理において「損金」の概念を理解することは重要といえます。損金の概念を正しく理解することで、適切な税務処理が可能になり、税負担の最適化にもつながるからです。以下では、損金の基本的な考え方から、費用や経費との違い、そして実務での取り扱いにおけるポイントまで、税務上の重要概念について詳しく解説していきます。
法人税における損金の基本概念
法人税法上の「損金」とは、法人税の計算において企業の収益から差し引くことができる費用や損失を指します。企業活動に関連する支出が税法上認められるためには、「事業との関連性」と「通常性」という要件を満たす必要があります。
法人税額の計算は「益金の額-損金の額=所得金額」という基本構造で行われるため、適切な損金処理によって税負担の適正化が図られます。
損金と費用との違い
損金と費用は、どちらも企業の支出を表す概念ですが、重要な違いがあります。損金は法人税法上の概念で、費用は会計上の概念です。例えば、取引先への接待費であれば会計上は全額が費用となりますが、税法上では一部しか損金にならないケースがあります。
これは、法人税が「公平な課税」を目的とするのに対し、企業会計は「適切な期間損益計算」を目的とするためです。
損金と経費との違い
損金と経費は両方とも企業活動における支出を指しますが、経費は費用と同じく企業会計上の概念で、事業活動に必要な費用全般を指します。費用には企業の全ての支出が含まれますが、一方の経費は売り上げに直結する費用のことです。つまり、費用の一部に経費が含まれています。
あなたの経営判断、「数字」に基づいていますか?
ROICや自己資本比率など、経営数字の分析方法を学ぶ実践ガイド!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
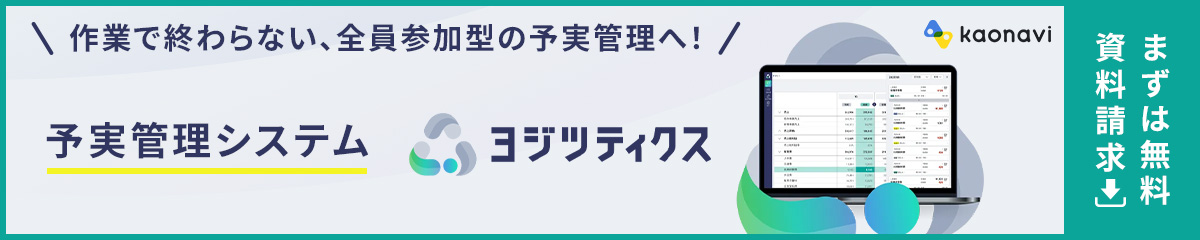 見積もり・デモのお問い合わせ
見積もり・デモのお問い合わせ損金算入・損金不算入とは?

税務上、支出が損金として認められるか否かは企業の税負担を大きく左右します。ここからは、費用が損金算入されるための条件や、損金不算入となる主な費用について詳しく見ていきましょう。適切な損金処理は税務リスクの低減と、適正な課税所得計算の基盤となります。
損金算入とは?税法上認められる費用の条件
損金算入とは、法人税法上で会社の収益から差し引くことが認められる費用や損失のことです。税務上で損金として認められるためには、支出が「事業との関連性」と「通常性」という2つの要件を満たす必要があります。
事業との関連性とは、その支出が会社の事業活動に直接関係していることを意味します。一方、通常性は事業を行う上で一般的に必要とされる支出であることを指します。これらの条件を満たさない場合、会計上は費用であっても税務上では損金として認められません。
損金算入できる主な項目は以下の通りです。
| 勘定項目 | 内容 |
| 租税公課 | 固定資産税・法人事業税・自動車税・印紙税 など |
| 減価償却費 | 損金経理した減価償却費のうち、法人税法で定められた償却限度額範囲内の金額 |
| 保険料 | 生命保険料・損害保険料・厚生年金保険料 など |
| 水道光熱費 | 電気代・ガス代・水道代 など |
| 給与・賃金 | 従業員への給与・賞与・各種手当 など |
| 地代家賃 | 事業所の建物・事務所の家賃 など |
| 消耗品費 | 文具・事務用品 など |
| 修繕費 | 固定資産の修理や改良のための支出のうち、固定資産の維持管理や原状回復として認められた金額 |
損金不算入となる主な費用の種類と理由
会計上は費用として計上できても、税務上は損金として認められない費用もあります。損金不算入とは、損金として認められない費用や損失のことを指します。損金不算入となる主な勘定項目は、以下の通りです。
| 勘定項目 | 内容 |
| 租税公課 | 地方法人税・都道府県民税 など |
| 役員報酬 | 役員報酬のうち、要件を満たしていない部分の金額 |
| 交際費 | 特例が適用されない接待飲食費や贈答品費 など |
| 減価償却超過額 | 減価償却費のうち、償却限度額を超過する部分の金額 |
| 罰金・過料 | 罰則・過料 など |
| 寄付金 | 寄付金のうち、損金として認められない部分の金額 |
一部のみ損金算入が認められていたり、損金算入の条件が設けられていたりする項目もあるため、注意が必要です。
会社の「体力」は、B/Sを見ればわかる。
自己資本比率・流動比率から、経営の安定性とリスクを見抜く!
⇒ PDFを無料DL|【公式】https://www.kaonavi.jp
中小企業経営者が押さえておきたい損金算入・不算入の判断基準

中小企業経営者にとって、損金の扱いは税務上の重要なポイントといえます。特に損金算入・不算入の判断基準は、資本金規模によって大きく異なるため、正確な理解が必要です。ここでは、事業との関連性を基本とした判断基準と、交際費や寄付金など限度額が設けられている費用の取り扱いについて解説します。
損金算入・不算入の判断基準
損金算入と不算入の判断基準で最も重要なのは、支出が事業と直接関連しているかどうかです。特に注意が必要なのが交際費です。資本金の規模によって交際費の取り扱いは大きく異なります。資本金100億円超の法人では交際費の全額が損金不算入となりますが、中小法人(資本金1億円以下)では年800万円または接待飲食費の50%までが損金算入可能です。
取引先との飲食費の扱いも金額によって変わります。1人当たり1万円以下の場合は少額接待飲食費として交際費から除外されますが、それを超える場合は接待飲食費として交際費に含まれます。損金算入の証明には、飲食店の名称・所在地、参加者数、日付、参加者の氏名・関係性などを記録した書類の保存が必要です。
会議費と交際費の区別も重要で、会議が主目的で通常の昼食程度の負担なら会議費として損金算入できます。日常の経理処理では、これらの判断基準を理解し、適切に区分することが税務上のリスク回避につながるでしょう。
損金算入限度額が設けられている費用
法人の税務申告において、全ての費用を無制限に損金算入できるわけではありません。交際費や寄付金などは一定の限度額までしか損金算入が認められていないため、事前に確認しておきましょう。
寄付金の損金算入限度額は、法人の種類や所得金額によって計算方法が異なります。また、公益法人などへの寄付金には特例があり、特別損金算入限度額が設けられています。公益社団法人や公益財団法人への寄付金は、その法人の主たる目的である業務に関連することを条件に、通常より優遇された計算方法が適用される点も覚えておくとよいでしょう。
現場と経営の目線が合った予実管理へ!
標準化と仕組み化で叶う、経営を強くする仕組みとは?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
損金経理とは?確定決算で正しく処理するポイント
損金経理とは、法人が税務上の損金として認められるために、確定した決算書において費用や損失として計上する経理処理のことです。法人税法では「法人がその確定した決算において費用または損失として経理すること」と定義されています。
ここでいう「確定した決算」とは、株主総会などで正式に承認を得た決算書類のことです。減価償却費や貸倒引当金などの一部の費用項目は、この損金経理が損金算入の条件となっています。つまり、決算書に費用として計上していなければ、税務申告時に損金として認められないという重要なルールです。
損金経理は日本の法人税制の特徴である「確定決算主義」に基づいています。これは、会社の確定した決算を尊重し、それを基礎として課税所得を計算するという考え方です。この原則により、会計と税務の処理の一貫性が保たれ、透明性の高い税務申告が可能になるでしょう。
会社の「体力」は、B/Sを見ればわかる。
自己資本比率・流動比率から、経営の安定性とリスクを見抜く!
⇒ PDFを無料DL|【公式】https://www.kaonavi.jp
損金算入に関する注意事項

法人の税務処理において特に注意が必要なのが、特殊なルールが適用される項目です。これらは原則的な損金処理と異なり、特別な要件や制限が設けられています。また、損金算入を税務署に認めてもらうためには、適切な証拠書類の保存も不可欠です。ここからは、損金算入に関する重要な注意事項を紹介します。
役員給与の損金算入には一定の要件がある
役員給与を損金算入するには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当する必要があります。
定期同額給与は毎月同額で支給される給与で、原則として期首から3か月以内か、職務内容の重大な変更時、または業績悪化時にのみ金額変更が可能です。事前確定届出給与は、確定した金額を特定時期に支給するもので、株主総会決議から1か月以内に税務署への届出が必要です。業績連動給与は、利益指標などに基づいて算定される報酬で、算定方法の客観性など一定の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たさない役員給与は損金不算入となり、会社の税負担が増加してしまうため、適切な報酬設計と所定の手続きが重要です。
損金算入のための証拠書類は保管しておく必要がある
損金算入を税務署に認めてもらうためには、支出の証拠となる書類を適切に保管することが不可欠です。領収書、請求書、契約書など、支出内容が明確に分かる証拠書類がない場合、損金算入が否認される可能性があります。
特に重要なのは、領収書に日付、金額、支払先、支払内容などが明記されていることを確認し、取引の正当性を証明できるようにすることです。これらの証拠書類は法令で5年間の保存が義務付けられています。
近年は電子帳簿保存法により、一定の要件を満たせば電子データとしての保存も認められていますが、データの改ざん防止措置や検索機能の確保など、真実性と可視性を担保する必要があります。
税務調査への対策も忘れない
税務調査では損金処理が重点的に確認されるため、事前対策も必要です。特に貸倒損失については、損金経理の要件に関する誤解が多く否認されるケースもありますが、税務上の損金経理要件を満たしていれば問題ありません。
領収書や契約書といった支出を裏付ける書類はすぐに取り出せるよう管理し、交際費明細書などの資料も作成しておきましょう。税務調査への立会い担当者は事前に経理処理の内容を理解しておき、不安がある場合は税理士に依頼することで税務リスクを最小限に抑えられます。
経営数字が読めると、議論の質が変わる。
財務3表のつながりと数字の「意味」を捉える力が身につく実践ガイド。
⇒ 【無料DL】https://www.kaonavi.jp
損金算入できる租税公課と損金不算入の租税公課との違い

法人が納めるさまざまな税金のうち、損金算入できるものと損金不算入となるものがあります。この違いを正しく理解することは、適正な税務処理の基本です。以下では、どのような租税公課が損金算入できるのか、またどのようなものが損金不算入となるのか、その理由と計上時期の違いについて詳しく解説します。
損金算入できる租税公課の種類と計上時期
租税公課の中で損金算入できるものには、固定資産税、事業税、印紙税、自動車税、不動産取得税などがあります。これらは事業活動に必要な経費として認められています。損金算入される租税公課の計上時期は課税方式によって異なる点に注意しましょう。
申告納税方式の税金(事業税など)は、原則として納税申告書を提出した事業年度、または更正・決定があった事業年度に計上します。特例として、申告期限未到来の税金を未払金計上した場合は、その損金経理をした事業年度に算入可能です。
賦課課税方式の税金(固定資産税など)は、賦課決定のあった事業年度が原則ですが、納期開始日の属する事業年度や実際に納付した事業年度に損金経理することも認められています。特別徴収方式の税金や利子税・延滞金にも、それぞれ適切な計上時期があるため、税法に則った正確な時期に計上するようにしましょう。
損金不算入となる税金とその理由
法人が納める税金の中には、損金算入できないものが存在します。その代表例が法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税です。これらの税金は法人の所得に対して課されるため、もし損金として認められると、課税所得が減り、結果的に税額も減少してしまいます。
また、税法上の義務を怠ったことで発生する各種加算税・加算金・延滞税・過怠税なども損金不算入です。これらはペナルティとしての性質を持つため、損金算入を認めると制裁効果が薄れてしまうためです。同様に、罰金や科料も法令違反に対する制裁であるため、損金算入は認められません。
さらに、法人税額から控除する所得税・復興特別所得税・外国法人税も損金不算入です。これらは既に法人税額計算で考慮されており、損金算入すると二重控除になってしまうからです。
経営数字が読めると、議論の質が変わる。
財務3表のつながりと数字の「意味」を捉える力が身につく実践ガイド。
⇒ 【無料DL】https://www.kaonavi.jp
損金の適切な把握には予実管理も重要
予実管理の導入は、損金の適切な把握や管理にも役立ちます。予実管理は予算の無駄遣いを防止し財務状況を適切に管理できるだけでなく、損金計上のための根拠資料としても活用できるため、税務調査への対応力が高まります。
予実管理を効率化するなら、「ヨジツティクス」がおすすめです。多機能でありながら使いやすいインターフェースで、部門別の予算編成と執行管理が簡単に行えます。Web上で随時閲覧・更新が可能なため、場所を選ばず業務が進められる点も魅力です。
また、クラウドベースで導入しやすくセキュリティレベルも細かく設定可能なため、安心してお使いいただけます。
煩雑なファイル管理から脱却し、予実管理を一元化。
最新の数値をリアルタイムで把握できる、予実管理設計ガイド。
⇒ PDFを無料DL|【公式】https://www.kaonavi.jp
まとめ

法人税法上の「損金」とは、法人税の計算において企業の収益から差し引くことができる費用や損失を指します。損失と同じく企業の支出を表す費用や経費は、企業会計上の概念であることも覚えておくとよいでしょう。
損金算入できる項目と損金不算入の項目があり、「一部だけ損金として認められる」「限度額を超えた部分は認められない」といったルールも存在するため、損金経理を行う前に、しっかりと確認しておくことをおすすめします。
複雑な税務処理の管理には、予実管理システムの導入も有効です。ヨジツティクスなら、部門別の予算編成と執行管理が可能で、リアルタイムで予算残高を確認できます。Web上で随時閲覧・更新できるため、経理担当者だけでなく、全社で正確な損金処理を実現可能なため、ぜひお役立てください。
【予実管理の精度を向上させるには?】
多くの企業が抱える運用負担を解消し、 経営の意思決定をサポートする実践ガイド。
●予算・実績・見込みを自動集計でデータを一元管理
●誰でも使える設計だから運用の標準化が進む
●全員がいつでも最新の数字を共有できる状態へ

