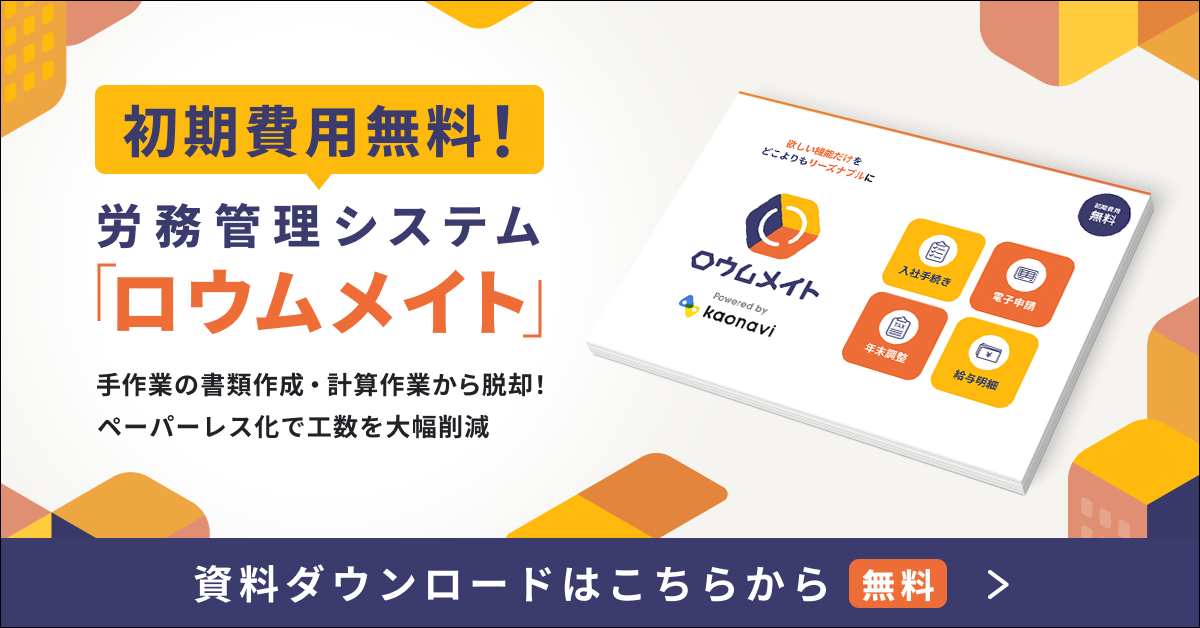「60歳で定年退職」は過去の常識になりつつあります。近年の法改正により、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となりました。この変化は人事労務担当者にとって新たな課題であると同時に、貴重な人材を生かすチャンスでもあります。
定年退職制度の見直しが避けて通れない道となる中、効果的な対応策と実務上の注意点を知って実務に生かしましょう。
目次
定年退職制度とは?企業が知っておきたい基本

定年退職制度は、多くの企業で長年にわたり人事制度の一環として運用されてきました。ただ近年では、法改正や働き方の多様化が進む中で、定年制度のあり方を見直す動きが広がっています。
まずは定年退職制度の基本的な位置づけや法律上の制約、企業が制度を導入するメリットと留意点について解説します。
定年退職制度は法律で定められているのか
定年退職制度を設けることは、法律による義務ではありません。企業はそれぞれの経営方針に基づき、定年制度を設けるかどうかを自由に決めることができます。実際に、一部の企業では定年を設けず、従業員が働ける限り働き続けられる制度を採用しています。
ただし、多くの日本企業では伝統的に定年退職制度を導入しており、人材の新陳代謝や組織活性化のために活用されています。定年制度を設ける場合は、高年齢者雇用安定法第8条により、定年年齢を60歳以上に設定しなければなりません。
この規定に反して60歳未満の定年年齢を設定することは、法律違反となります。同法律は高年齢者の雇用機会を保障し、年金受給までの所得確保を目的としています。企業の人事担当者としては、定年制度の設計や改定時にこの点を十分に理解し、法令に則った制度設計を行うことが重要です。
参考:『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)第8条|e-Gov 法令検索』
一般的な定年退職年齢と設定の自由度
日本企業における一般的な定年退職年齢は、60歳に設定されているケースが最も多くなっています。厚生労働省の「高年齢者雇用状況等報告(2024年)※」によると、定年制を導入している企業は全体の96.1%に達し、そのうち64.4%が60歳を定年年齢と回答しました。とはいえ、65歳を定年とする企業も25.2%あります。
※高年齢者雇用状況等報告(2024年)の調査対象:従業員21人以上の企業23万7,052社
参考:『令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します|厚生労働省』PDF「発表資料」P.5「3 企業における定年制の状況」
企業の定年年齢設定には一定の自由度があります。高年齢者雇用安定法では60歳未満の定年設定を禁止していますが、上限は定められていません。つまり企業は60歳以上であれば、定年退職の年齢を自由に定められ、定年そのものを廃止することが法的に可能です。
定年退職制度を設けるメリットと留意点
定年退職制度を企業が設ける最大のメリットは、組織の新陳代謝を促進できる点です。定年を設けることで、若手社員の登用やキャリアパスの可視化が可能になり、組織全体の活性化につながります。また、人事計画の策定が容易になるのも定年退職制度の利点です。退職時期が予測できるため、人材確保や技術伝承の計画が立てやすくなるでしょう。
一方で、定年退職制度には留意点もあります。一度設定した定年年齢を引き下げることは「不利益変更」と見なされ、原則として認められません。また、年功序列型の賃金制度を採用している企業では、定年延長により人件費が増加する可能性があります。
定年退職に関する法改正にどう対応する?

高年齢者の就業機会確保を目的とした法改正が進む中、定年退職制度に関する企業の対応も求められています。2021年の改正により、高年齢者雇用安定法に制度を大きく動かすルールが追加されました。法改正のポイントと企業が取り得る対応策について整理します。
法改正のポイント|雇用確保義務と就業機会確保努力義務
2021年4月の高年齢者雇用安定法改正後は、65歳までの雇用確保が義務となっています。また、70歳までの就業機会確保の努力義務が追加されました。70歳までの就業機会確保の方法としては、業務委託や社会貢献活動といった多様な働き方も選択肢として認められられています。
これにより、高年齢者の能力や希望に応じた柔軟な就業機会の提供が可能となりました。企業としては、この法改正を単なる規制強化と捉えるのではなく、高年齢者の多様な経験や知識を生かす機会と考えましょう。自社に合った制度設計を検討するタイミングです。
法改正への対応で企業が取れる選択肢
改正高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保が義務付けられています。定年退職の年齢を65歳未満としている企業は、必ずいずれかの措置を講じなければなりません。
- 65歳以上への定年年齢の引き上げ
- 継続雇用制度(再雇用・勤務延長制度)の導入
- 定年退職制度の廃止
70歳までの就業機会確保は、改正高年齢者雇用安定法における努力義務です。企業には、以下のいずれかの措置を講じるよう努めることが求められています。
- 70歳までの定年年齢の引き上げ
- 定年退職制度の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用・勤務延長制度)の導入
- 70歳までの業務委託契約の締結
- 70歳までの社会貢献事業への従事機会の提供
定年年齢の引き上げは安定した雇用機会を確保できますが、人件費がかさむデメリットもあります。継続雇用制度などほかの選択肢についても理解して、自社の状況に合わせた方法で対応しましょう。
参考:『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条1項,第10条の2|e-Gov 法令検索』
人事労務担当者に求められる実務対応とは
法改正に対応するためには、まず現在の定年制度や継続雇用制度を確認し、65歳までの雇用確保義務を確実に満たしているかを点検しましょう。70歳までの就業機会確保措置についても、制度整備を含めた導入計画の検討が必要です。
具体的なステップは以下のとおりです。
- 現行の就業規則を点検する
- 法改正に対応した規定の追加・修正案を作成する
- 労働者代表からの意見を聴取する
- 労働基準監督署に届け出る
この際、対象者の基準や働き方の選択肢を明確にすることが重要です。再雇用契約を採用する場合は、労働条件通知書や雇用契約書の内容を適切に更新する必要があります。制度設計の複雑さによっては、社労士などの専門家への相談も検討しましょう。
継続雇用制度(再雇用・勤務延長制度)の導入ポイント

定年退職後も働き続けたいというニーズに応えるため、企業には継続雇用制度の整備が求められています。再雇用制度や勤務延長制度といった選択肢の中から、自社に適した制度を選ぶことが重要です。それぞれの制度の特徴や違い、導入時のポイントについて解説します。
再雇用制度と勤務延長制度の違い
定年退職後の雇用継続には、「再雇用制度」と「勤務延長制度」のふたつの選択肢があります。両者の大きな違いは、退職手続きが必要かどうかです。
再雇用制度では、従業員は一度定年で退職となり、退職金を受け取った後に新たな雇用契約を結びます。この際、雇用形態や労働条件が変更されるのが一般的です。ただ、企業側にとっては人件費の調整が可能となるメリットがありますが、従業員にとっては収入が不安定になるという懸念点もあります。
一方、勤務延長制度では退職手続きをせず、そのまま雇用を継続します。基本的に定年前と同様の労働条件で働けるため、従業員のモチベーション維持につながります。しかし、企業側は給与水準を維持する必要があるため、コスト面での課題が生じる可能性があるでしょう。
自社に最適な制度を選ぶには、企業の経営状況と従業員のニーズの両方を考慮する必要があります。
定年退職後の契約形態・就業条件の決め方
定年退職後の雇用継続で重要なのは、契約形態と就業条件の選択です。一般的な契約形態としては、正社員や契約社員・嘱託社員・パート・アルバイトなどがあります。各形態により賃金体系や福利厚生が変わってくるため、企業と労働者双方のメリットのバランスを取らなければなりません。
処遇や賃金の設計で注意したいこと
定年後の処遇・賃金設計で最も注意すべき点は、同一労働同一賃金の原則です。定年前後で仕事内容が変わらないのに賃金だけを大幅に下げると、不合理な待遇差と見なされ、紛争に発展する可能性があります。
再雇用時の賃金設計では、職務内容や責任に応じた合理的な制度設計が必要です。専門性の高い業務を担当する従業員には、技能や経験を評価する手当を設けるなど工夫することで、モチベーションの低下を防げます。
また、在職老齢年金の仕組みを理解しておくことも重要です。年金受給と給与の合計額が一定水準を超えると年金が減額されるため、従業員にとって最適な収入バランスを考慮した賃金設計を検討しましょう。
参考:『同一労働同一賃金ガイドライン|厚生労働省』
参考:『さ行 在職老齢年金|日本年金機構』
定年退職制度を変更したときの就業規則や社内体制の見直し方

定年退職制度の見直しにあたっては、就業規則や社内制度の更新も必要です。制度変更にともなう就業規則の修正手順や記載すべきポイント、社内での周知・同意の取り方など、実務上押さえておくべき点を紹介します。
厚生労働省のモデル就業規則を活用した就業規則の変更手順
定年制度変更にともなう就業規則の修正は、厚生労働省が提供するモデル就業規則を活用すると効率的に進められます。
厚労省のWebサイトからモデル就業規則をダウンロードし、自社で現在使われている就業規則と比較して変更が必要な部分を特定します。特に定年退職や継続雇用・労働時間・賃金に関する規定を重点的に確認しましょう。
次に、モデル就業規則を参考に具体的な変更案を作成し、従業員への説明と意見聴取を行います。労働組合がある場合は、労働組合と協議を進めてください。ない場合は、労働者の過半数代表との協議が必要です。
就業規則を変更した後は、過半数労働組合または過半数代表からの意見書を添付して管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。また、退職に関する事項は労働条件通知書の絶対的記載事項となっているため、労働条件通知書の記載変更と再交付も忘れないようにしましょう。
参考:『モデル就業規則について |厚生労働省』
参考:『労働基準法 第90条|e-Gov 法令検索』
参考:『労働基準法施行規則 第5条』
再雇用制度導入時に記載しておくべき内容
再雇用制度を導入する際は、就業規則に必ず記載すべき事項があります。まず適用対象者を明確にし、「希望者全員」とするか一定の基準を設ける場合はその条件を具体的に記載します。また雇用形態と契約期間では、有期契約の場合は契約期間(通常1年)と更新の上限年齢を明記しましょう。
勤務条件では、勤務日数・時間や職務内容、配置転換の有無なども詳細に記載します。特に重要なのが賃金・処遇で、基本給の算定方法や諸手当の扱い、賞与・退職金の有無を明確にしなければなりません。
トラブル防止のために、「業務内容や勤務場所は会社が決定する」といった条項や、「会社の業績や従業員の能力・成果に応じて労働条件を変更することがある」といった規定も検討したほうがよいでしょう。
定年退職制度の変更にあたる従業員説明や同意の取り方
定年退職制度の変更は従業員の生活設計に大きな影響を与えるため、丁寧な説明と同意の取得が欠かせません。定年年齢引き上げなどの重要な変更では、十分な準備期間を設けて、従業員が新制度に適応できるよう配慮しましょう。
まずは定年年齢の引き上げや継続雇用制度の導入などの変更内容と、その理由を明確にした説明資料を準備します。不利益変更となる場合は、その必要性と合理性を客観的に示す根拠が重要です。
次に説明会を開催して、従業員の理解を促進します。質疑応答の時間を十分に設け、不安や疑問に真摯に対応するのがポイントです。この段階で変更によって従業員が受ける影響や、それを緩和するための代替措置についても詳しく説明すると安心感につながります。
退社手続き・契約更新・再雇用の実務にはツール活用も有効
定年退職や再雇用に関わる手続きは、従来の紙ベースの管理では膨大な事務作業が発生しがちです。退職手続きの一元管理や再雇用契約書のデジタル作成・保管は、人事労務業務の効率化に効果的です。再雇用時の雇用契約更新では、条件の変更点を明確に記録でき、後々のトラブル防止にも役立ちます。
「ロウムメイト」のような労務管理システムを活用すれば、こうした手続きの効率化が可能です。ロウムメイトでは「70歳以上被用者該当届」などの電子申請がシステム内で完結できるため、社会保険事務所への提出漏れを防止できます。定年後再雇用者の勤務条件や給与計算データも一元管理することにより、人事労務担当者の負担が大きく軽減するでしょう。
定年退職制度の変更にともなう実務上の注意点

定年制度の見直しを進めた後は、再雇用の対応や社内運用上のトラブルを防ぐため、実務的な注意点にも目を向ける必要があります。以下に、気を付けたいポイントを3つ解説します。
変更後の労働条件通知・雇用契約書の記載事項に注意
定年退職制度を変更したら、労働条件通知書や雇用契約書も適切に更新する必要があります。重要なのは、変更点を明確に記載することです。労働条件通知書には、労働契約期間や就業場所・業務内容・労働時間・賃金など法定の記載事項を漏れなく記載しましょう。
再雇用に際しては、初回の雇用契約と異なる条件が生じることが多いため、変更点を雇用契約書に明記する必要があります。また、有期雇用で再雇用する場合は、無期転換ルールの特例制度の活用も検討しましょう。この特例を適用するには、高年齢者の雇用管理に関する計画書を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。
認定後は、特例の内容を雇用契約書に「有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される期間については、無期転換権が発生しない」と明記しましょう。
ロウムメイトでは、雇用契約書の更新・管理も効率化できます。適切な文書管理で、将来的なトラブルを未然に防ぎましょう。
参考:『高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について|厚生労働省』P.9
再雇用の拒否がトラブルに発展するケースもある
定年後の再雇用拒否は、近年企業にとって大きなリスクとなっています。これは65歳までの再雇用(または継続雇用・定年延長)が法的義務であるにもかかわらず、適切な対応ができていないことが原因です。
津田電気計器事件の判例でも、定年退職後の再雇用拒否は原則として違法とされています。例外的に、正社員の解雇事由に相当する理由がある場合や、企業側が提示した合理的な労働条件を従業員がのまなかった場合には再雇用を拒否できます。
再雇用拒否のトラブルを防ぐためには、再雇用規程に明確な基準を設けましょう。業務命令違反などがあった場合は、段階的な指導や処分を行った上での対応が必要です。
制度運用でよくある社内の課題と対策
定年退職制度や再雇用制度の運用では、実務上いくつかの課題が発生します。よくある問題が、再雇用者のモチベーション低下です。これは賃金水準の低下が主な原因ですが、評価制度を導入し賃金にランクを設けることで改善できます。
また、多様な勤務形態の導入も効果的です。短時間勤務や週の短日勤務・在宅勤務など、柔軟な働き方を提供することで高齢者の満足度が高まるでしょう。
早期の面談で従業員の将来希望を把握することも重要です。定年退職前から希望職種を聞き取り、適切な人員計画を立てましょう。定年退職制度のメリット・デメリットの理解や給与水準について十分な説明が誤解予防につながります。
まとめ

定年退職制度は、組織の新陳代謝や人事計画の明確化といったメリットがある一方で、法的な規制や制度変更にともなう実務的な負担も少なくありません。高年齢者雇用安定法の改正により、企業には65歳までの雇用確保義務と70歳までの就業機会確保努力義務が求められています。
人事労務担当者としては制度の正しい理解とともに、就業規則の整備や契約内容の見直し・継続雇用制度の運用まで、幅広い対応が必要です。業務の効率化には、ロウムメイトのような労務管理ツールの活用も視野に入れ、制度の持続的な運用体制を整えていきましょう。