モラハラとは、倫理や道徳に反した嫌がらせのことで、主に家庭や職場で起こります。企業には職場環境配慮義務が課されているため、モラハラが起こった場合、企業側が責任を問われる可能性もあるのです。
今回はモラハラについて、その定義や行動の具体例、原因や予防策・対処法などを詳しく解説します。
目次
1.モラハラ(モラルハラスメント)とは?
モラハラ(モラルハラスメント)とは、倫理や道徳に反した嫌がらせのことで、精神的DVとも呼ばれます。モラルは「倫理、道徳」であり、ハラスメントは「嫌がらせ」を意味する単語です。陰湿な嫌がらせにより相手を精神的に追い詰める行為であり、無視や暴言、睨む、バカにするなどの行為がモラハラに該当します。
厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、モラハラを以下のように定義しています。
言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること

ハラスメントとは? 意味や定義、種類一覧、実態、対策を簡単に
ハラスメントは相手に嫌がらせを行うこと。1980年代後半からセクシャルハラスメントという言葉が飛び交うようになり、近年はパワハラ、マタハラ、モラハラなどさまざまなハラスメントが社会問題になっているので...
職場におけるモラハラの定義
フランスの精神科医・マリー=フランス・イルゴイエンヌは職場におけるモラハラを以下のように定義しています。
職場内で繰り返す言葉や態度などによって、人の人格・人権や尊厳を傷つけたり、心身の健康を害したりして、その人が仕事を辞めざるを得ないような状況に追い込むこと、または職場の雰囲気を悪化させること
さらに、職場におけるモラハラを「陰湿な行為の繰り返し」と「権力を利用したモラハラ」2つに分類しています。ときには注意や叱責も必要でしょう。しかし過剰かつ不適切で度を超えたものが継続的に行われた場合はモラハラと見なされる場合もあります。
モラハラとパワハラの違い
パワハラ(パワーハラスメント)とは、権力を利用したハラスメントのこと。上司が部下に嫌がらせするなど、上下関係により被害者が逆らえない点が特徴です。
精神的な嫌がらせという点では共通するものの、パワハラには肉体的な暴力も含まれます。それゆえパワハラは周囲から気づかれやすい一方、モラハラは精神的な暴力であるため表面化しにくい点に違いがあります。
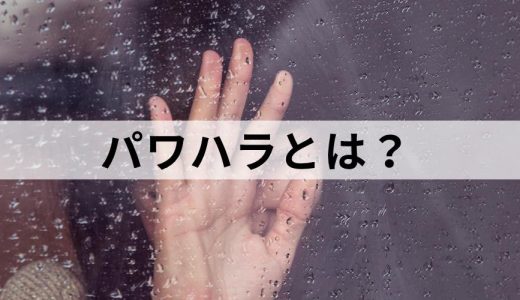
パワハラ(パワーハラスメント)とは? 定義、具体例、対策
パワーハラスメントとは、職場での優位性を利用して相手に心身の苦痛を与える行為のこと。社会でもパワーハラスメントの存在が大きな問題となり、企業が対処を怠ったとして損害賠償を求められるケースも発生していま...
2.モラハラに当たる行動の具体例一覧
モラハラは表面化しにくいため、自分がモラハラを受けていると自覚できないケースも珍しくありません。モラハラを予防し、モラハラから逃げるには、モラハラに当たる行動の具体例を知っておくことが必要です。
家庭と職場にわけて、モラハラに当たる行動の具体例を一覧でみていきましょう。
家庭
- 暴言を吐く
- 相手を無視する
- 相手を貶めることを言う
- 生活費を渡さない
- 極端に束縛する
- 収入にケチをつける
- 何をしても否定する
- 子供に妻(夫)の悪口を吹き込んで洗脳する
- 自分の間違いを認めない
相手に対して自分を優位にみせようと「役立たず」などと言い放ったり、夫から妻に「誰の金で生活していると思っているんだ」などと責めたりする行為は代表的なモラハラです。
家庭という狭い空間で行われるモラハラは周囲に表面化しにくいだけでなく、相手と距離を置かない限り際限なく続く可能性もあります。
職場
- 発言や連絡を無視する
- 否定的なことを言う
- 業務内で嫌がらせをする(妨害行為)
- プライベートに過度に介入する
- 陰口を言う
- 誹謗中傷する
- バカにしたような視線を送る
- チームから仲間外れにする
業務上の必要範囲を超えた過度な注意や叱責のほか、故意に孤立させたり、簡単な仕事しか与えず評価を下げたりするなど、権力を利用して相手に精神的苦痛を与える行為はすべてモラハラです。
職場でのモラハラは一対一の関係性で行われるだけでなく、他の従業員がいる前で行われることもあります。
3.モラハラの被害者と加害者の特徴
モラハラの加害者と被害者には共有した特徴がみられます。ここでは、モラハラの被害者・加害者の特徴を解説します。
加害者
- 自己愛が強い
- 自信過剰または自信がない
- 他人を支配したい
- 過去にモラハラの被害者だった
自分は他人より優れており間違っていないと強く感じる人は加害者になりやすく、自分が優位に立ちたいあまり、他人を貶めたり、人のせいにしたりする傾向にあります。
また、過去にモラハラの被害に遭ったことがある場合、仕返ししたい気持ちから加害者となってしまうケースもあるのです。
性格のような先天的な理由だけでなく、過去に被害にあった経験といった後天的な理由からもモラハラになってしまうこともあります。
被害者
- 自分に自信がない
- 我慢強い
- 自己主張が苦手
- 断るのが苦手
- 謙虚
- 空気を読むのが得意
他人に対して思いやりが強く、優しい真面目な性格の人は被害者になりやすい傾向にあります。また、我慢強いがゆえにモラハラにも耐えられてしまう節があり、自己主張や断ることも苦手なため、加害者もモラハラが加速してしまうのです。
さらに、自分に自信がなく、何かあったときに自分を責めてしまうことが多いため、モラハラされているのも自分のせいだと思い込んでしまい、その状況を受け入れてしまうこともあります。
4.モラハラがもたらすリスク
家庭と職場の両面から、モラハラがもたらすリスクをみていきます。
家庭
- 離婚
- 家庭崩壊
- 被害者や子どもの精神疾患
家庭という狭い空間で行われるモラハラは表面化しにくく、周囲の助けがおよびにくいです。夫婦という一対一の関係性で起こるため長期化しやすく、相手に改善の意思がない場合、離婚しない限りは続いてしまうでしょう。
モラハラによるストレスから睡眠障害や食欲低下、うつ病など精神疾患を発症してしまうことで、健康的な生活が送れなくなってしまうリスクもあります。
また、子供がそうした場面を目にすると精神的なショックも大きく、それが当たり前と感じてしまえば子供もモラハラ気質な性格になってしまうかもしれません。それにより、モラハラの連鎖が生まれてしまいます。
職場
- 企業イメージの低下
- 離職率の増加
- 従業員のモチベーション低下
職場でのモラハラは、被害者がうつ病や適応障害を発症してしまう恐れもあります。
企業はモラハラやいじめなどを防止し、従業員が安心して働ける環境を作る「職場環境配慮義務」があるため、モラハラが原因で従業員に何らかの被害がおよんだ場合、責任を問われる可能性も高いです。
モラハラが解決しなければ被害者は離職に追い込まれ、モラハラが横行していることで従業員の心理的安全性も低下してしまいます。職場環境が悪いことでモチベーションが低下するだけでなく、居心地の悪さから離職が後を絶たない恐れもあるでしょう。
このように、企業にとってモラハラを放置することはリスクしかありません。
5.モラハラをする原因
モラハラをする原因は人によってさまざまです。代表的な原因として、もともとの性格やストレス、幼少期の家庭環境が挙げられます。
「人を支配したい」「人より上に立ちたい」「自信過剰または自分に自信がない」など、性格上モラハラ気質な場合もあり、相手が優しく自己主張しない人だとその気質が強くなってしまうこともあるのです。
また、幼少期に親が過干渉だったり、同じくモラハラを受けていたりする場合もモラハラをする原因になります。さらに、仕事や職場、家庭でのストレスが蓄積され、心の余裕を失ってモラハラに該当する行為をしている可能性も考えられます。
6.モラハラの治し方
モラハラは、精神病の一種です。確実な治し方はないものの、本人の自覚と意志によって治すことは不可能ではありません。
しかしモラハラに該当する行為は長年培われてきたものであり、その人の行動様式として定着してしまっているため、加害者は自分の行為がモラハラだと自覚していないケースも珍しくありません。
モラハラを治すにはまず、「本人がモラハラをしている」と自覚し、やめようと意識することが重要です。
カウンセリングを受けるのも一つの方法でしょう。しかし人によってはモラハラが治らない可能性もあるため、そこに労力をかけて自分が精神的に追い込まれないように気をつける必要があります。
7.モラハラが治らない人への対処法
モラハラに遭っている場合、相手にモラハラをやめてもらうには一筋縄ではいきません。モラハラが治らない人への対処法を押さえ、まずは自分で自分を守りましょう。
相手にしない
加害者は自尊心を満たすため、または相手よりも優位でいることを自覚したいためにモラハラしている場合があります。
このケースでは加害者に対してまともに取り合わない、相手にしないことが大切です。ただし、反論しない、言いなりになるのではありません。怖がったり弱い部分を見せたりすると相手がつけあがる可能性もあるため、毅然とした態度でスルーするとよいでしょう。
モラハラの証拠を集める
モラハラが原因で離婚や退職をする場合は証拠が必要なため最悪の決断に備えて、証拠を集めておくとよいでしょう。証拠は、以下のような方法で集めることをオススメします。
- ICレコーダーで発言を録音する
- ビデオに録画する
- テキストで言われたことはログを残しておく
いつ、どういった内容のモラハラを受けたかを記録に残しておきましょう。
相手にモラハラを認識させる
自分の行為がモラハラである自覚がない加害者もいるでしょう。悪気なくモラハラに該当する行為をしてしまっている場合、認識させることで改善される可能性もあります。
相手の気を悪くしない言い方を意識し、いきなり「モラハラ」というワードを出さず嫌な思いをしていることを伝えてみましょう。
8.モラハラの予防策
企業には、職場環境配慮義務やパワーハラスメント防止措置が義務化されているため、モラハラの予防策は必須です。ここでは、3つの予防策をご紹介します。
相談窓口を設置する
相談窓口は、被害者の味方となる存在です。社内の人だと話しにくいという場合に備え、外部相談窓口も使えるようにするとよいでしょう。相談窓口ではモラハラだけでなく、仕事の悩みなど幅広い内容に対応できるスタイルがオススメです。
そして、相談窓口は設置するだけでなく、存在を周知して利用しやすい環境を整えることが大切です。
ハラスメント研修を行う
加害者が自分の行為がモラハラに該当する自覚がなく、同様に被害者も自分がモラハラを受けているか判断できていないケースもあるでしょう。
ハラスメント研修を行うと、どういった行為や言動がモラハラに該当するかが認識できるため、モラハラにならないよう言動や行動に注意する意識づけがなされます。研修は、モラハラを専門とする外部講師に依頼するとよいでしょう。
リテラシーを強化する
職場でのモラハラは許さないという考えを浸透させることも大事な予防策です。ただ口頭で伝えるだけでなく、就業規則にハラスメントの規則や処分について明記するなど、モラハラは罰則の対象であるという意識づけをしましょう。
正社員だけでなく、パートやバイトを含めた全従業員に対してハラスメント研修を行うなど、会社を挙げてリテラシー強化に取り組むことをオススメします。
9.モラハラが起こってしまった際の対処法
どんなに予防していても、モラハラが起こってしまう場合もあります。ここでは、モラハラが起こってしまった際の対処法を家庭と職場の両面から解説します。
家庭
モラハラが起こってしまった場合、将来的に離婚を選択する可能性があるかもしれません。
そうした場合に備えモラハラを受けた際は言動を録音する、メールやLINEなどテキストでの言動をログに残す、いつどんな内容のモラハラを受けたかなど、記録に残しておくことが大切です。
「日時」「被害の内容」「モラハラに至った経緯」「その時の体調や心情」などを記載しておくとよいでしょう。
また、モラハラを受けて心身に異常を感じた場合は、早めに病院へ行くことをオススメします。一人で抱え込まないよう、家族や友人、公的機関に相談することも大切です。
相談機関
家庭でのモラハラを相談できる機関は、以下のようにさまざまです。
| DV相談+(プラス) | ・電話:0120-279-889(24時間受付) ・メール(24時間受付) ・チャット(12:00〜22:00) |
| 女性の人権ホットライン | ・0570-070-810(8:30〜17:15) |
| 婦人相談所 | ・各都道府県に1施設が設置されてい |
| 配偶者暴力相談支援センター | ・各地域に施設が設置されている |
周囲に相談できず、現状を我慢しているままでは心に大きな傷が残ってしまいます。家族や友人など身近な人に相談できない・しにくい場合でも一人で抱え込まず、このような機関に相談することがモラハラの被害者から抜け出す第一歩です。
職場
職場でモラハラが起こってしまった際、相談を受けた企業側は以下手順で対処しましょう。
- 事実確認
- 第三者機関を交えた話し合い
- 就業規則にもとづく適切な措置
まずは被害者と加害者から話を聞いて、事実を確認しましょう。話が食い違う場合もあるため、第三者となる従業員や第三者機関を交えた話し合いが必要になる場合もあります。
話し合いの結果モラハラした事実が明らかになれば、加害者には就業規則などにもとづき適切な措置をとり、被害者にはメンタルケアを行って職場環境の回復に努めましょう。
企業側がモラハラに対して適切に対処する姿勢をみせて心理的安全性を高めること、再発防止のためハラスメント研修を実施することも大切です。
