自社の雇用契約書に問題がないか見直すとき、法律面の問題が気になっている人事労務担当者も多いのではないでしょうか。実務では混同しがちな「労働条件通知書」との違いを分かりやすく解説した上で、雇用契約書の必要性や記載しておくとよい事項を紹介します。法改正や社会の動向に対応するためのアップデート方法や、雇用契約書に関する業務の属人化が引き起こす問題と解決策もあわせて押さえておきましょう。
目次
雇用契約書とは?作成の意義と法律上の位置付け
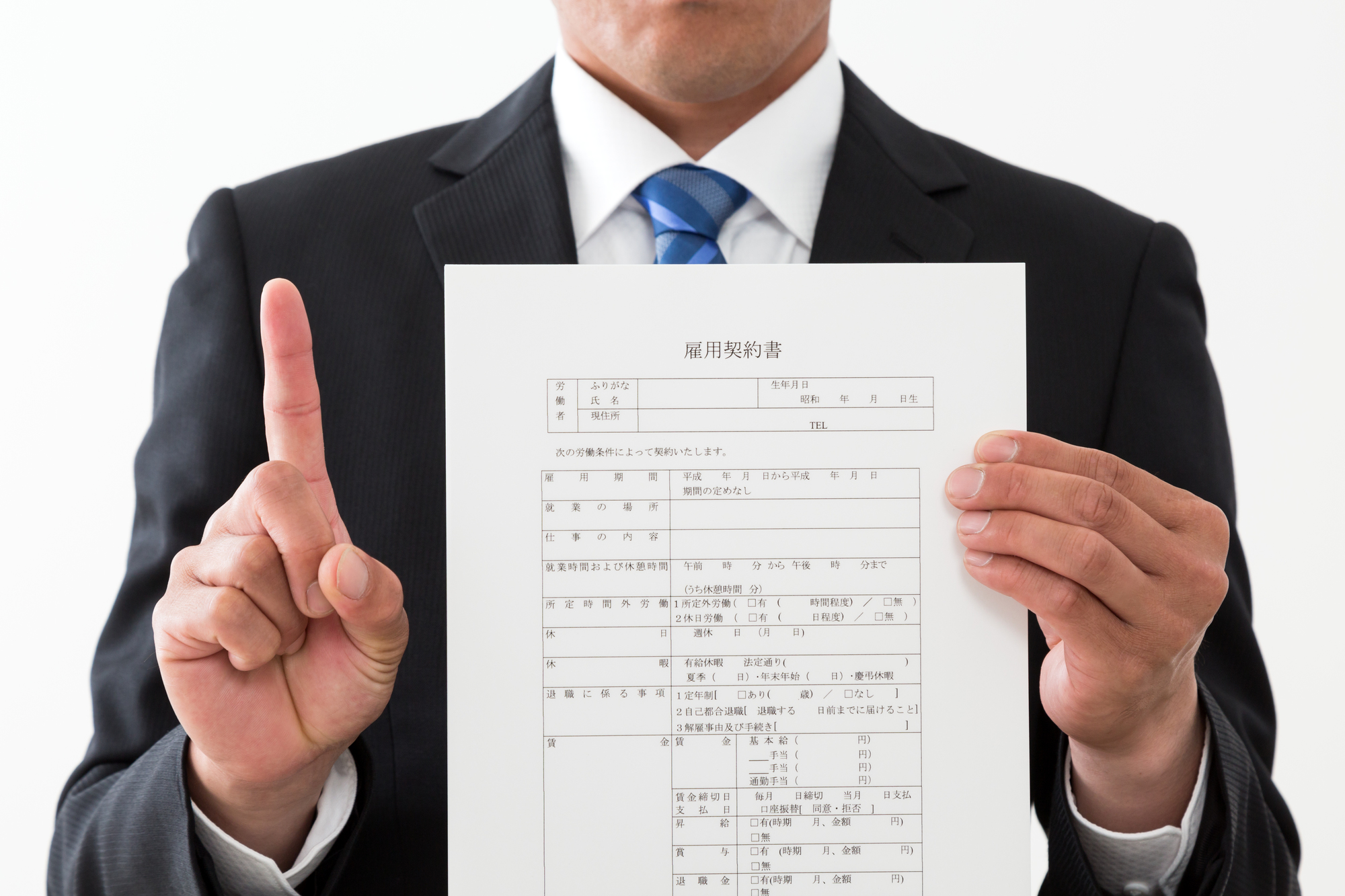
雇用契約書について、作成義務があるのか・具体的な必要性は何か、疑問に感じる人事労務担当者も多いでしょう。雇用契約書の法的な位置付けや、多くの企業が作成していることからも分かる雇用契約書の重要性を解説します。
雇用契約書に法的な作成義務はある?
雇用契約書は、労働契約の内容を書面化したものです。しかし実は労働基準法では作成が義務付けられていません。
雇用は民法第623条の契約に当たり、民法で定められた契約は口頭の合意だけでも有効に成立します(第522条)。ただし、実務では労使間のトラブル防止や証拠保全の観点から、雇用契約書を作成するのが一般的です。
一方、労働条件通知書については、労働基準法第15条により明示が義務付けられています。雇用契約書の作成に法的義務はありませんが、労働条件通知書は必ず作成して明示しなければなりません。
多くのケースでは、「万が一の紛争発生時に備えて」「合意内容を明確にするために」雇用契約書を作成・発行しています。特に労働時間や給与などの重要な労働条件は、労働者が合意したという書面にも残しておくことで後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
参考:『民法 第522条, 第623条|e-Gov 法令検索』
参考:『労働基準法 第15条第1項|e-Gov 法令検索』
法的義務がなくても雇用契約書を作成する理由
雇用契約書の作成自体に法令上の義務はありません。しかし実務においては、雇用契約書の作成が非常に重要です。契約内容を書面に残すことで、労働条件などの雇用に関する合意内容が明確になり、後のトラブルを防止できます。
「言った・言わない」の水掛け論を避けられるだけでなく、万が一民事訴訟になった場合の証拠資料としても強い効力を持ちます。裁判所では書面の証拠が重視されるため、雇用契約書があるかどうかで対応に大きな差が出るのが実情です。
また、企業の多くが雇用契約書を基に労務管理を行っています。労働時間や給与といった重要事項が整理されていれば、従業員と認識が食い違う事態も生じにくく、日常の人事労務業務がスムーズになります。
法的義務はないものの、企業リスクの予防と人事労務実務の円滑化を両立させる上で、雇用契約書は必須といってもよいでしょう。
【勤怠アラートで、月末の勤怠管理業務がラクになる!】
カオナビならコストを抑えて、勤怠管理・労務管理・タレントマネジメントを効率化!
●勤怠の集計や給与計算、就業管理がラクになる
●従業員が自身の勤怠や有休の残日数を把握できる
●有休・労働時間の適正把握で法制度にも対応
●PCに不慣れな従業員でも使える画面設計で説明書いらず
●スマホにも対応しているので、PCのない環境でも安心
2025年4月から大幅改正される「育児介護休業法」とは?
・改正のポイントを社労士が解説
・育成・介護の改正イメージを図解でわかりやすく
・法改正で対応すべき内容をチェックリストで確認
無料の解説資料をダウンロード⇒こちらから
労働条件通知書とは?法的に求められる内容
雇用契約書と混同されがちな文書に、「労働条件通知書」があります。労働条件通知書とは何なのか、法律を基に作成の義務や記載すべき事項を見ていきましょう。電子交付が可能かどうかについても解説します。
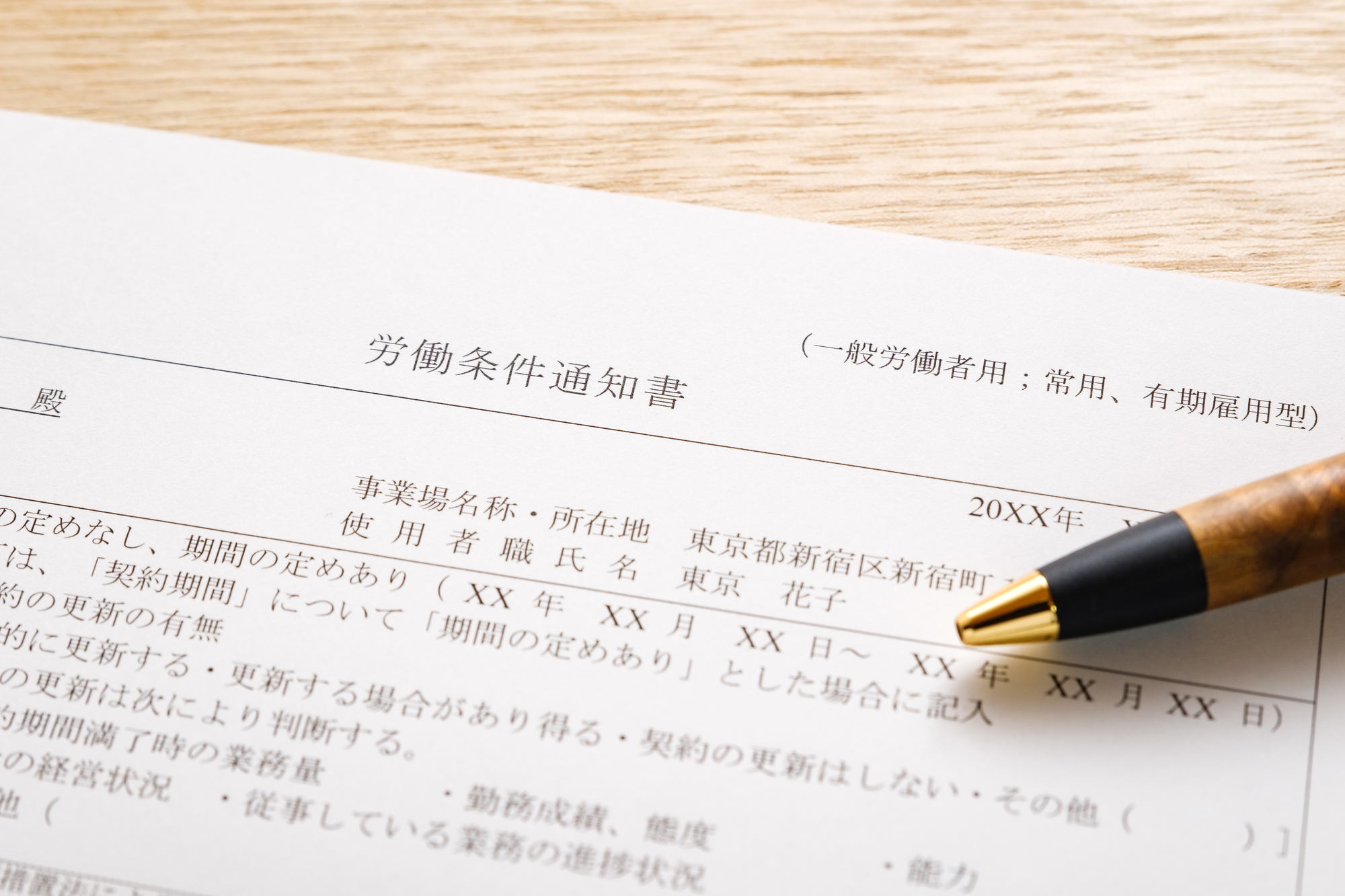
労働基準法の「労働条件の明示義務」を果たす通知書類
労働基準法第15条と同法施行規則第5条4項によれば、使用者はすべての労働者に対して、労働条件のうち規定の項目を、原則として書面で明示する義務があると定めています。これを満たす書面が「労働条件通知書」です。
労働条件通知書は単なる「通知」であり、雇用契約書のような双方が合意する「契約」とは概念が異なります。労働条件の明示義務は正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。
明示義務の対象となる項目は、労働期間や就業場所・賃金などの基本的な労働条件です。企業側は雇用時にこれらの情報を書面にして従業員に渡すことで、法的義務を果たしたことになります。
参考:『労働基準法 第15条第1項|e-Gov 法令検索』
参考:『労働基準法施行規則 第5条第4項|e-Gov 法令検索』
参考:『「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ|厚生労働省』
絶対的記載事項・相対的記載事項とは
労働条件通知書に記載する項目には、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」の2種類があります。これらは、労働基準法施行規則第5条第1項に基づくものです。
絶対的記載事項は雇用形態や自社の制度を問わず、すべての労働条件通知書に必ず記載しなければならない基本的な労働条件です。一方の相対的記載事項は、自社に該当する制度がある場合にのみ記載が求められます。
以下の表で、絶対的記載事項と相対的記載事項を整理してみましょう。
| 絶対的記載事項 | 相対的記載事項 |
|
|
絶対的記載事項の記載漏れが許容されないのはもちろん、自社に退職金制度があるなら退職手当について、賞与を支払っているなら賞与について記載しなければなりません。
参考:『労働基準法施行規則 第5条第4項|e-Gov 法令検索』
紙と電子どちらでも交付できる?
労働条件通知書は、2019年4月の労働基準法施行規則改正以降、電子交付も一定の条件下で可能になりました。従来は紙での交付が義務でしたが、改正後は労働者が希望した場合、電子メールなどでの通知も認められるようになっています。
ただし電子交付には条件があります。まず労働者の明示的な希望・同意が必要です。また、メールの添付ファイルなど労働者が容易に出力して書面を作成できる形式であることや、改ざん防止策を講じることも求められます。さらに、情報が確実に労働者に届いたことの確認も重要です。
紙での運用は運用を変えなくて済みますが、保管や管理の手間がかかります。一方、電子運用はペーパーレス化や検索性の向上というメリットがあるものの、セキュリティ対策や労働者のITリテラシーへの配慮が必要です。いずれの方法でも、労働条件を適切に明示する法的義務は変わりません。
参考:『「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ|厚生労働省』
月末の勤怠業務の負担を軽減!勤怠管理システムの選び方や比較ポイントを解説。 「勤怠管理システムガイド」で、自社に適したシステムがわかる! ⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード雇用契約書と労働条件通知書の違いを理解しよう
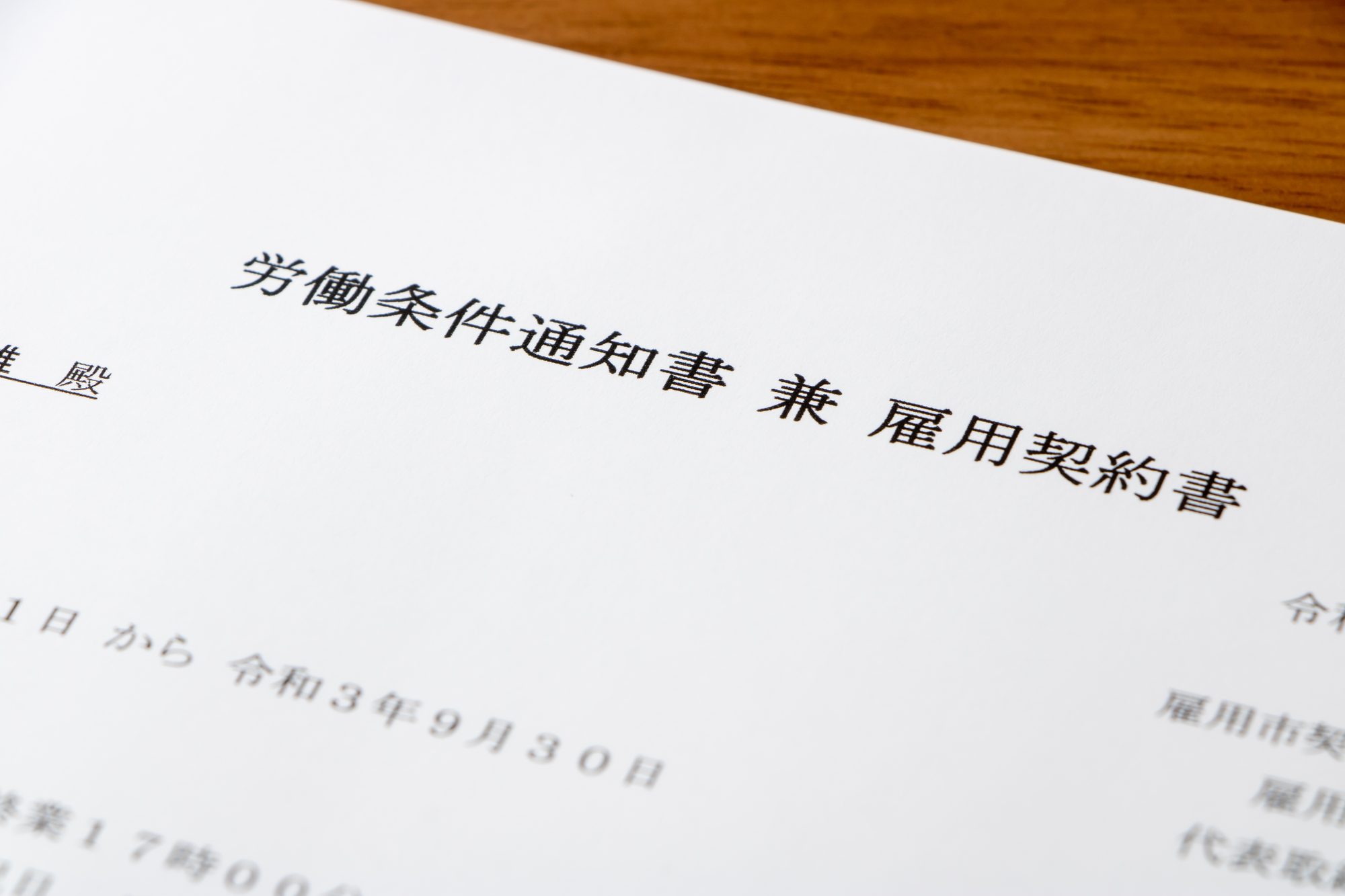
雇用契約書と労働契約書の違いを正しく理解することで、書類の作成・管理における落とし穴を避け、法令順守と円滑な労務管理を両立できます。では、雇用契約書と労働条件通知書は具体的にどのような点で異なるのでしょうか。それぞれの役割や法的性質の違い、両者を兼用するときの注意点を見ていきましょう。
役割の違い「契約の証明か労働条件の通知か」
雇用契約書と労働条件通知書は、一見似ていますが根本的な役割が異なります。雇用契約書は労使間の「合意内容を証明する文書」です。万が一トラブルが起こったときには、この契約書が双方の合意内容を示す重要な証拠となります。
一方、労働条件通知書は使用者が労働者に対して「労働条件を知らせる義務」を果たすための文書です。労働基準法第15条に基づく法定義務であり、使用者から労働者への一方的な通知という性格を持ちます。
両者の違いを表で整理すると分かりやすいでしょう。
| 書類の種類 | 役割 | 法的性質 | 当事者間のやりとり |
| 雇用契約書 | 契約の証明 | 民法上の契約書 | 労使双方の合意 |
| 労働条件通知書 | 労働条件の通知 | 労働基準法法条の義務的通知 | 使用者からの一方的な通知 |
この違いを理解せずに運用すると、トラブル発生時に適切な対応ができなくなるリスクがあります。両者の役割を認識した上で、適切な文書管理を心がけましょう。
雇用契約書と労働条件兼通知書を兼用する場合の注意点
多くの企業では「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として、一体化した文書を作成しています。この方法は効率的ですが、労働基準法上の通知義務を確実に果たしているか確認することが重要です。特に絶対的記載事項に記載漏れがあると法令違反となります。
また、労働条件は曖昧な表現や抽象的な記載を避け、具体的に明示する必要があります。「賃金は別途通知」「勤務時間は上司の指示による」といった不明確な表現では、通知義務を満たしたとは認められません。
一体型文書を作成する場合も、「通知書としての要件」と「契約書としての要件」の両方を満たす構成にしましょう。一般的には最初に労働条件の明示部分を置き、後半に双方の合意に関する契約条項を配置する形式が多く採用されています。
労務業務を楽に!労務管理システムの選び方や比較ポイントを解説。
「労務管理システムガイド」で、自社に適したシステムがわかる!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
実務で雇用契約書の記載内容をどう考える?

雇用契約書の内容を実務的に考える際、何を盛り込むべきか・関連書類との整合性をどう保つかが重要なポイントです。雇用契約書の具体的な記載内容や、ほかの労務文書との整合性を保つためのポイントを詳しく解説します。
雇用契約書に盛り込むと望ましい内容例
雇用契約書には労働条件の基本となる要素を漏れなく盛り込むことが重要です。基本的な労働条件は以下のとおりです。
- 労働期間
- 勤務地
- 業務の内容
- 勤務時間や休憩
- 休日の日数や曜日
- 賃金(基本給や諸手当など)
少なくとも上記の労働条件は、明確に記載しましょう。内容は労働条件通知書の絶対的記載事項と整合させる必要があります。
また、トラブル防止の観点から、懲戒処分の種類や解雇条件・退職手続きについても詳細に定めておくと安心です。特に退職時の手続きや書類提出期限などは、具体的に記しておくと後々の混乱を避けられます。
労働条件通知書の内容と整合性を取るコツ
雇用契約書と労働条件通知書は、一体として扱われることも多いため、両者の整合性を保つことが重要です。通知書と契約書の内容に食い違いがあると、解釈の違いからトラブルに発展するリスクがあります。両文書は常にセットで見直しましょう。
たとえば項目の記載順序や使用する文言を統一することで、担当者の確認漏れやミスを防止できます。「賃金」という項目名をもう一方では「給与」と記載するといった不一致があると、解釈の違いによる混乱を招く可能性も出てくるでしょう。
また、人事制度の変更や法改正があった際には、必ず両方の文書を同時に更新する必要があります。一方だけ修正して他方を放置すると、最新の内容と古い情報が混在して法的リスクを高めかねません。システム化により、両文書の連動した管理が可能になれば、さらに効率的な運用が実現します。
就業規則との関係性もチェック
雇用契約書と就業規則の整合性を確保することは、労務管理上の重要な課題です。両者の内容に矛盾があると、解釈の違いから労使間トラブルに発展するリスクがあります。
たとえば雇用契約書では「時間外手当は固定残業代に含む」とされていて、就業規則では「実労働時間に応じて支給」と定めている場合、混乱を招きます。
労働契約においては、原則として「労働者にとって有利な方の定め」が優先されます。つまり、就業規則より労働者に有利な条件を雇用契約書で定めている場合は雇用契約書が、逆に就業規則のほうが有利な場合は就業規則が優先されるということです。
法的に問題のない雇用契約書を運用するためには、両者の整合性を定期的にチェックし、矛盾がないよう管理することが重要です。
労務管理システムで、面倒な入退社手続きはどれくらい楽になる?
「入退社手続きガイド」で、労務管理システム導入のメリットをわかりやすく!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
法改正・社会動向に応じた見直しポイント

働き方改革の促進や法改正にともない、雇用契約書も定期的な見直しが必要になっています。電子契約の普及や押印不要の流れも、雇用契約書の運用方法に変化をもたらす動向です。最新の法改正や社会の動向が雇用契約書に与える影響と、それに対応するためのアップデート方法を解説します。
近年の法改正の影響
近年は働き方改革に関連する法令の改正により、雇用契約書の見直しが求められています。特に注目したいのは、産後パパ育休(出生時育児休業)や育休の分割取得制度など、新たな権利に関する記載の要否です。
また、コロナ禍以降に普及したフルリモートワークや、フレックスタイム制・短時間正社員などの多様な働き方に対応した条項の整備も重要になっています。
こうした新しい勤務形態は、従来の雇用契約書では想定されていなかったケースも多く、労働条件の明確化が必要です。たとえば、リモートワークにおける通信費負担や業務用機器の貸与条件なども、雇用契約書に明記することでトラブルを防止できます。
企業としては、法改正があったり働き方に変化が見られたりしたときは都度、雇用契約書のテンプレートを見直し更新することが必要です。専門知識を持つ担当者がいない場合は、外部の専門家や労務管理システムを活用するとよいでしょう。
電子署名・押印不要論と契約実務への影響
雇用契約書への押印については、2020年6月に内閣府・法務省・経済産業省の3府省が発表した「押印に関するQ&A」で、押印がなくても契約の効力に影響しないことが明記されています。
法的には雇用契約書に印鑑は必要ありません。しかし実務では、「念のため」という意識から従来どおりの押印を続ける企業もあります。
電子署名法に準拠した電子契約も有効です。電子署名とタイムスタンプを電子ファイルに施すことで、当事者の合意の証拠を残すことができ、業務効率化やコスト削減・契約書の一元管理が簡単になります。近年は採用プロセスの迅速化を目的に、雇用契約書を電子化する企業も増えてきました。
重要なのは自社のリスク許容度に合わせた運用を選択することです。
参考:『法務省:押印についてのQ&A』
参考:『電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)|e-Gov 法令検索』
法改正にともなう雇用契約書のアップデート方法
雇用契約書の定期的な見直しは、法的リスク回避の要です。自社内に法改正情報を定期的にチェックする体制を構築し、テンプレートを更新する責任者を明確にしましょう。労務管理の専門誌やWebサイト・社労士からの情報も積極的に活用することで、見落としを防げます。
テンプレート更新の際は、変更履歴を残し、旧版が使われないよう社内周知を徹底することがポイントです。特に育児介護休業法など頻繁に改正される法律については、年1回以上の見直しが望ましいでしょう。
雇用契約書の運用マニュアルも同時に更新することで、担当者交代時のトラブルを防止できます。労働条件通知書との整合性確認も忘れずに実施しましょう。
システム化によりテンプレート一元管理と自動更新の仕組みを導入し、更新漏れリスクを削減するのもひとつの選択肢です。
月末の勤怠業務の負担を軽減!勤怠管理システムの選び方や比較ポイントを解説。 「勤怠管理システムガイド」で、自社に適したシステムがわかる! ⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード契約業務の属人化・非効率は大きな課題

雇用契約書の運用における課題は多くの企業が直面している問題です。属人化によるテンプレートの不統一や更新漏れ、Excelベースの管理が抱える課題を解決するには、どのような方法があるのでしょうか。雇用契約書管理における具体的な課題と解決策について詳しく見ていきましょう。
テンプレ管理の属人化や更新漏れによるミス
一部の企業では、雇用契約書の管理が属人化している実態があります。担当者ごとに異なるテンプレートを使用していたり、法令改正時の更新漏れが発生していたりする企業も少なくありません。ある部署では最新版を使用している一方で、別の部署では古い契約書を使い回しているといったケースもあります。
このような状況では、誰がどのテンプレートを使用しているのか社内で把握できず、統一した運用が難しいでしょう。最悪の場合、古い条文のまま契約を締結してしまい、法的リスクを抱える可能性も否定できません。
また、契約書の更新履歴が適切に管理されていないと、何度も同じミスを繰り返すことになってしまいます。組織として契約書テンプレートを一元管理する仕組みが必要です。
紙とExcelによる運用が抱える課題
紙やExcelによる雇用契約書の運用には、さまざまな課題が潜んでいます。まず書類の紛失リスクが高く、必要なときにすぐ探せない検索性の低さが業務効率を下げています。複数の拠点がある企業では、郵送コストや手続きの煩雑さが増大し、非効率的な状況になりやすいでしょう。
さらに紙媒体は情報漏えいのセキュリティリスクが高く、Excel管理では最新版と旧版の混在や更新管理の複雑さが問題です。法改正への対応も遅れがちなため、最新の法令に準拠した契約書更新が後手に回ることもあります。
こうした課題は単なる業務の非効率だけでなく、コンプライアンスリスクにも直結します。特に労働基準監督署の調査時に適切な文書を提示できないと、法令違反と見なされる可能性に注意が必要です。
「カオナビ」で実現する業務の一元管理
雇用契約書の管理をクラウド上で一元化できる「カオナビ労務」なら、業務効率化とコンプライアンス強化が同時に実現できます。テンプレートの統一管理により、担当者によるバラつきや記載ミスを防止し、契約ステータスの可視化も可能です。
紙での運用を電子化することで、印刷用紙や郵送・保管場所にかかるコストをカットできます。さらに書類の紛失リスクが減り、担当者が変わったとき「何がどこにあるのか分からない」という混乱が起きる心配もほぼありません。管理者権限さえあれば、いつでも必要な情報の参照・出力できます。
カオナビは雇用契約書の電子締結にも対応しており、正社員用やパート・アルバイト用など多様なテンプレートを自社専用にカスタマイズ可能なため、作成の手間も大幅に削減できます。1人ずつの契約締結だけでなく、CSVアップロードによる複数人との一括契約が可能な点も便利です。
専用フォーマットに沿って入力するだけでCSVファイルを簡単に生成できるため、データ管理の効率も格段に向上します。紙やExcelでの管理に悩む人事労務担当者にとって、理想的なソリューションといえるでしょう。
月末の勤怠業務の負担を軽減!勤怠管理システムの選び方や比較ポイントを解説。 「勤怠管理システムガイド」で、自社に適したシステムがわかる! ⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード雇用契約書を安全かつ効率的に管理するには

多くの企業では、雇用契約書の管理に課題を抱えているのが現状です。紙での保管による紛失リスクや、法改正への対応遅れ、担当者ごとのテンプレート管理などが問題となっています。では、どのような管理方法が理想なのでしょうか。
雇用契約書の作成から保管までの基本的なプロセスや、電子化に必要なシステム機能、初めての電子化に適したサービスについて解説します。
雇用契約書の作成から更新・保管までの基本フロー
雇用契約書の管理には、「作成→承認→契約締結→保管」という基本フローがあります。まず人事労務担当者が法的要件を満たす契約内容を作成し、次に部門責任者がその正確性を確認・承認します。その後、従業員と企業双方が合意して契約を締結する流れです。
署名された雇用契約書は、法令に基づいて適切に保管しましょう。雇用契約書の法定保存期間は5年です。労働基準法第109条では「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。」とされています。
雇用契約書は労働基準法で作成が義務付けられている書類ではありませんが、「労働関係に関する重要な書類」に当たると考えてよいでしょう。
安全と効率を両立する電子契約システム
雇用契約書の電子化は、安全で効率的な管理・運用をかなえる選択肢です。ただ、確かな効果を感じるには、適切なシステムの選定が欠かせません。
まず、法的効力を確保するための電子署名機能と、誰がいつ契約書を確認・変更したかを記録する履歴管理機能が必要です。また、権限のない人が閲覧できないアクセス権限設定機能や、必要な契約書をすぐに探せる検索性が求められます。
データの改ざんを防ぐ保管体制も重要です。雇用契約書は労働基準監督署への提出を求められることがあるため、法的要件を満たした形式で出力できる設計になっているかを確認しましょう。
これらの機能がそろった電子契約システムを導入することで、契約業務の効率化とコンプライアンス強化を同時に実現できます。
初めての契約書電子化には「カオナビ」を
雇用契約書から電子化を始めようと思っている企業には、手厚いサポートが用意されているクラウドサービスがおすすめです。カオナビの労務機能では、1社につき1人の専任担当が付き、システム上申のための書類作成から導入後の運用までサポートする体制を備えています。
契約書の締結・給与明細・年末調整といった労務管理機能の中から、自社に必要なものだけを選べるのも、カオナビが初めての契約書電子化に向いている理由です。初期費用は0円なので、予算が少ない場合でも手軽に始めやすいでしょう。
労務業務を楽に!労務管理システムの選び方や比較ポイントを解説。
「労務管理システムガイド」で、自社に適したシステムがわかる!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
まとめ
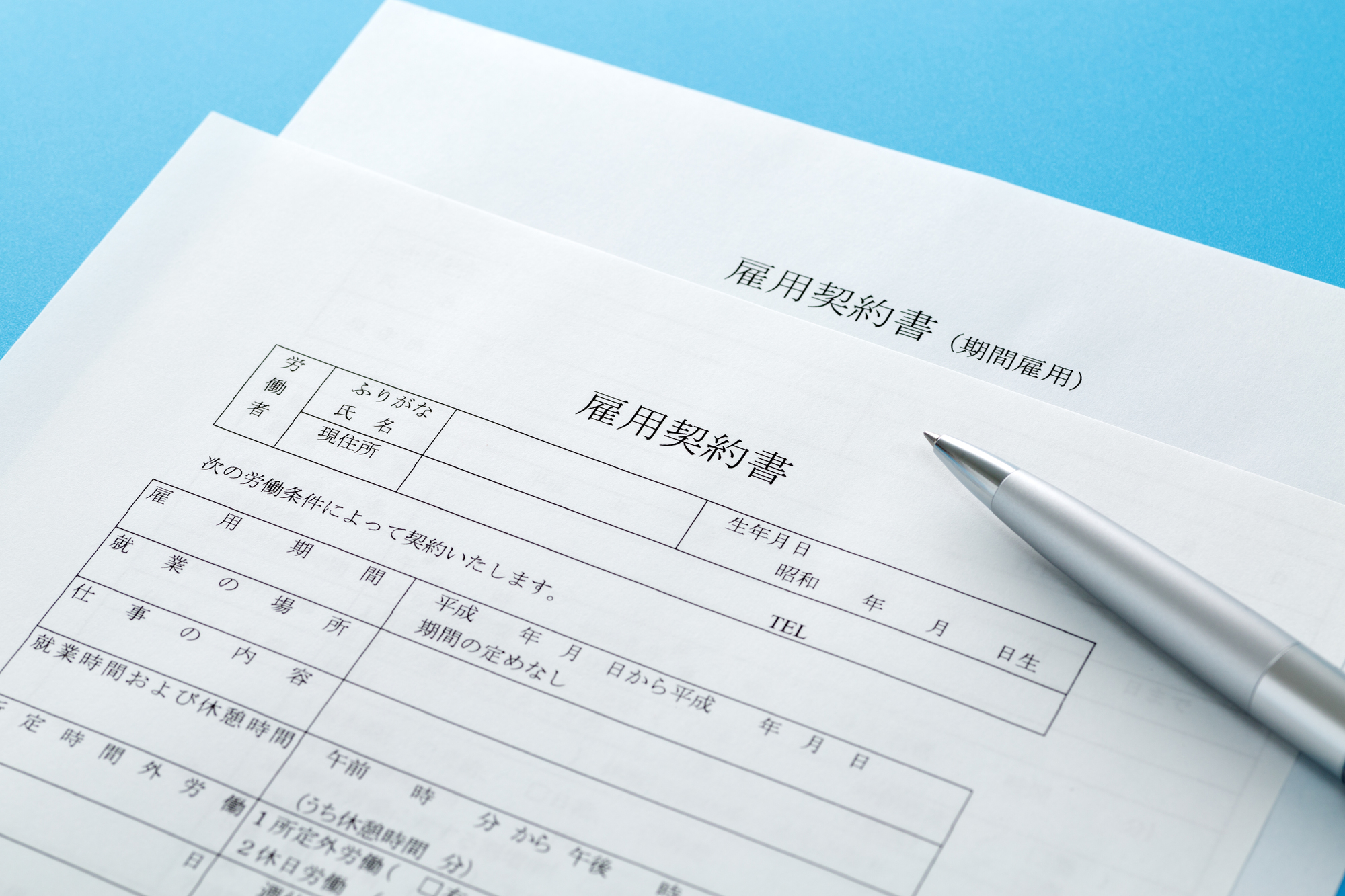
雇用契約書は法的な作成義務こそありませんが、労使トラブル防止や証拠保全の観点から作成が推奨されます。一方で労働条件通知書は労働基準法で定められた法的義務であり、絶対的記載事項と相対的記載事項の適切な記載が欠かせません。
両者を一体型で運用する場合は、それぞれの役割の違いを理解し、特に労働条件通知書としての法的要件を満たしているかどうかの確認が重要です。就業規則との整合性が取れているかのチェックや、法改正への対応も求められます。
雇用契約書の作成・管理における属人化や非効率な運用は、更新漏れやミスを招くリスクがあります。電子契約システムをうまく活用して、テンプレート管理の統一や作業効率の向上・セキュリティ強化など、雇用契約書の管理・運用の課題を解決しましょう。
【人事業務で足りない時間とヒトは、システムでカバーしませんか?】
カオナビならコストを抑えて労務管理・タレントマネジメントを効率化!
●紙やExcelの帳票をテンプレートでペーパーレス化
●給与明細の発行や配布がシステム上で完結できる
●年末調整の記入や書類回収もクラウドで簡単に
●人材情報の一元化・見える化で人材データを活用できる
●ワークフローで人事評価の運用を半自動化できる

